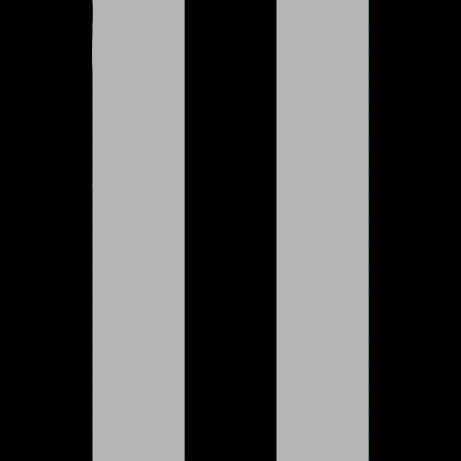【お知らせ】メンテナンスは終了しました。ご協力ありがとうございました。
イラストを魅せる。護る。
究極のイラストSNS。
GALLERIA[ギャレリア]は創作活動を支援する
豊富な機能を揃えた創作SNSです。
- 作品を最優先にした最小限の広告
- ライセンス表示
- 著作日時内容証明
- 右クリック保存禁止機能
- 共有コントロール
- 検索避け
- 新着避け
- ミュートタグ
- ミュートユーザ
- フォロワー限定公開
- 相互フォロー限定公開
- ワンクション公開
- パスワード付き公開
- 複数枚まとめ投稿
- 投稿予約
- カテゴリ分け
- 表示順序コントロール
- 公開後修正/追加機能
- 24時間自動削除
- Twitter同時/予約/定期投稿
- 病床探偵の命名推理一日目:「端的に言うと、君は死にかけた」
目が覚めたら病室だった。──などというのは空間消化作戦に従事していれば珍しい体験でもないのだろうけれど、それでも民間協力者となって日が浅い私にとって、ここには何とも言い表せない感慨があった。
だからといって、その少年の言葉に実感が沸くかと問われれば、また別の話になるのだが。まるで夢のような出来事だった。夢のように、覚めたら忘れ去っていた。
死にかけた記憶が、まったくない。
「厳密には殺されかけたんだけどね。もっとも覚えがないのも無理はない。それなりの時間、魔人と離れていたようだから」
少年は言う。──おそらく少年のはずだ。一見では女性かと思ったような美人なので吸血鬼の可能性も考慮したが(非科学的な話なので本気で想定したわけではないのだが)、残念ながら鏡も十字架もないので検証には至らなかった。
冗談はさておき。
殺されかけた──それは死にかけたのとは違うのだろうか。消化作戦で死にかけるのと、空間に殺されかけるのとでは、ほとんど同義になるのでは?
「容疑者が魔物や手下だけなら僕もそう言っただろう。けれど」
この殺人事件ならぬ殺人未遂事件には、人間の容疑者も存在する。
それが彼の言い分だった。
「僕は探偵でね。空間管理機構から真実の究明と報告書の作成を依頼されているんだ。ゆえに君から話を聞こうと思っていたのだが──」
当事者の記憶はごっそりと抜け落ちていたわけだ。お役に立てなくて申し訳ない。
「もっとも、おおよその筋道は既に把握している。あとは君の技能さえ分かればパズルは完成したも同然だ。しかし……」
探偵はそこで神妙な顔をしてみせた。
「手違いか、あるいは何か他の理由でか。その技能について、機構のデータベースに一切登録されていなかったんだ」
ふうん、そうなんだ。たぶん手違いだと思うよ。
大した技能じゃないからね。
そう言いかけて気づく。作戦参加の弊害、単独行動の代償。
「私の技能って、どんなのだったっけ」
そんなとぼけた反応に「やはりね」と前置きしてから少年はこう述べる。
「だから君には、自分の技能について思い出してもらう必要がある。毎日少しずつ、事件に関する情報を提供するから、その穴を埋める形で自分の技能を推測してみてほしいんだ。なに、そこまでの正確性を求めているわけではないからね。せいぜい技能の名前さえ分かれば報告書なんてそれらしく書けるわけだし、とりあえずはそこを目標にしてみてくれ」
いいのかそんな適当で。
とはいえ名前当てくらいならば、そこまで高いハードルでもない。そもそも自分の技能なのだ。最悪の場合は新しく名付ければいい。
そんなこんなで。
探偵の依頼を受け、病床探偵の命名推理が始まったのだった。
二日目:「一人目の容疑者について教えよう」
次の日、私の病室へとやってきた彼はこう切り出した。
「名前は影匿院八(えいとくいん えいと)。君が発見された当時、胸に刺さっていたナイフ──それを顕現した技能を持つ高校生だ。君とほぼ同地点に倒れており、現在も意識不明の重体。昏倒の原因は薬剤の過剰服用と思われる」
なるほど完全に容疑者だ。彼が私を刺した上で隠蔽工作のため自らも意識を断ったとかで良いんじゃないだろうか。
「短絡的だな君は」
話の続きを聞きたまえ、と本職の探偵は言う。
「ナイフが刺さっていた胸元に、ほとんど傷が残っていないだろう。これは犯人に罪悪感がなかったことを意味する」
と言うと?
「影匿院少年の技能『罪悪館の殺人』は、抱く罪悪感が強ければ強いほど威力を増す能力だ。扱えるのはミステリに登場しそうな凶器に限るという制約こそあるけどね。そして、もしその彼が君を殺そうと考えた場合、罪悪感がないのを分かっていながら、わざわざ技能を使うだろうか」
分からないよ。実際に刺してみるまで「罪悪感がある」と思い込んでいたのかもしれないし。
──刺してみたら案外、威力が出なかっただけかもしれないし。
とはいえ、彼の言うことにも一理ある。これ見よがしに影匿院くん(以降、略してエイトくん)のナイフを残したのが、容疑を彼へ向けるためのカムフラージュである可能性も、結構な割合で否定できなかった。
でも、ところでなぜエイトくんは薬の過剰摂取なんてしたのだろう。意識を失うほどの量なんて、自らの判断でない限り服用できるとは思えない。たとえば水を魚の形にして泳がせる技能保持者なんかであれば無理矢理飲ませることも可能かもしれないが、見知らぬ誰かさんを疑うのは(今のところ)やめておこう。脅されたか、自殺を図ったか──後者であれば、やはりエイトくんが犯人だった可能性も出てくるけれど……。
思考がこんがらがってきた。
そもそも手持ちの情報はこれだけではないはずだ。もう少しヒントがほしい。
「もちろん幾らかの取っ掛かりは用意しているけれど」
少年は悩ましげに言う。
「一定量を超える手掛かりを、同時に提示するのは得策とは思えない。できれば君には、今日の情報を咀嚼しておいてほしいんだが」
もちろん明日にはまた新しい話を持ってくるとも。
そう笑って探偵は病室を後にした。──私がどんな技能を持っていればこんなことが起きるのかは、結局さっぱり分からないまま。
三日目:「二人目の容疑者について教えよう」
昨日とまったく同じ調子で、探偵は説明を始めた。
「先述の『罪悪館の殺人』という技能に関して、これと同じものを使える者が今回に限りもう一人存在する。──前回の空間について、おおまかな記憶はあるかい?」
まったく。
「では軽く紹介しよう。ざっくりした言い方をしてしまえば、擬人化した技能が襲ってくる空間だ」
つまり、人の姿を取った「罪悪館の殺人」が二人目の容疑者ということ?
「そう。この空間における手下は、探索者を殺し尽くすか、あるいは自らが滅ぼされるまで止まらない。しかし、それゆえに殺人を遂げるほどの罪悪感を持たず、結果として君が『死にかけるだけ』で済んだ可能性は、ある程度の真実味を持って提言できる。の、だけど……」
言葉を濁さないでほしい。
もう良いじゃんそれで、などと早くも思考を停止しかけた私に少年は告げる。前提をひっくり返しかねない事実を淡々とぶつける。
「彼ないし彼女──『罪悪館の殺人』と見られる技能の姿においては、目撃報告が一切上がっていない」
▽
そう聞いた時には少し驚いてしまったけれど(今はそれから少し経っている。探偵が帰った後だ)、よく考えてみれば「目撃報告がない」という情報には二通りの可能性が考えられた。
すなわち「技能の擬人化が誰とも遭遇しなかった場合」と「目撃者が証言をしなかった場合」だ。前者であれば、そもそも殺人が成立しない。探知系の技能保持者もいる中で、凶器を顕現する謂わば「実行犯型」の技能が姿を隠しながら敵を攻撃できるとはとても思えなかった。どうしても技能『罪悪館の殺人』を、容疑者から外さざるを得なくなる。
しかし後者ならばどうだろう。たとえば、その姿を見たのが私とエイトくんだけだった場合、記憶混濁と意識不明が目撃証言などできるはずがない。同様に、その事実を隠している人物がいた場合──それをして得をするのは、十中八九この事件の犯人ではないだろうか。
とはいえエイトくんも容疑者から外れたわけではないので、このあたりはフェアに詰めていきたい。明日からは、私の方から探偵に質問をしていくことになっている。まずは第一の容疑者においてのホワイダニットから。
四日目:「彼に犯行の動機はあるの?」
そもそも、そんなテーブルゲームみたいな名前の男の子に刺される謂れはないのだ──忘れているのでなければ。空間の影響で記憶が曖昧な今、それについては確認しておく必要があった。
探偵の答えはこうだ。
「それは難しいところだね、人の内心というのは分からないから。それでも周囲の評価を鑑みるに『あまりなさそうだ』というのが調査結果だ」
──とはいえ、と彼は付け足す。
「あれこれ思い悩むタイプの少年ではあったようだ。存在することさえ否定される魔物への憐憫。精神的順応にしたがって使い物にならなくなりつつある技能。解決のために薬の研究や技能訓練の真似事もしていたみたいだけど、いずれも上手くはいっていなかったようだ」
どれもこれも、どちらかといえば自殺の理由みたいな悩みだけれど。何かの弾みに糸が切れてしまった、という可能性は案外悪くない取っ掛かりのように思える。
すなわち動機の排除。推理小説を技能のモチーフにするような少年が、たとえば誰でもいいから人を殺そうと思った時、被害者として選ぶのは一体どういう人間だろう。あるいはの話──手持ちのトリックを使用するためだけに「アリバイ工作に使える技能の持ち主」を探すこともあるのではないだろうか。
これを受けて探偵は、
「なるほど、そこで君の技能推測に繋がるわけか。その条件に当てはまる能力については僕の方で候補を立てておこう」
君には別の方向性についても検討してみてほしい──などと、肯定とも否定とも言えないような言葉を残すと踵を返して出ていった。真意が読めないのは気に食わないけれど、ともあれ。
ひとつの可能性のみを、一度に突き詰めすぎない方が良いのは確かだ。次は二人目の容疑者に関するフーダニットを。
五日目:「コピー技能の持ち主はいた?」
探偵の提示した「能力の候補」を「趣味に合わない」という理由で全却下した私はこう質問した。
本人以外にその技能を使う人物がいる──。これまで言及されなかったとはいえ、その可能性を挙げられてしまった以上、避けて通れないのがこの問題である。なにせ容疑者が増えかねない。こういう面倒な枝分かれは、早めに潰しておきたかった。
「そんな君に朗報だ。作戦に参加した職員、協力者および巻き込まれた民間人のうち、他者の技能を模倣しうる6名──その全てにアリバイがある」
同行者がいた、技能での観測があった、記録写真に残っていた、エトセトラ。中には「身内の証言」程度の信憑性のものもあるとはいえ、ひとまず全員、一応の不在証明が成立しているらしい。
誰一人として私達と接触していない。しかも今回の作戦全体を通して。
たしかに余計な可能性を潰しておきたいとは言ったけれど──その一方で、新たな容疑者の出現に期待していなかったわけでもないのだ。
引っかかるのはナイフ。
見るからに分かりやすくエイトくんの持ち物であるナイフは、なぜ私の胸に刺さったままだったのだろう。もちろん威力がないとはいえ抜けば失血死していたかもしれないので、それについて文句を言うつもりはないのだが、どうしても。
「つまり『影匿院少年の犯行に見せかけたかった誰か』の存在を念頭に置いているわけだね」
探偵が補足をする。
「であれば、それが出来るのは何もコピー技能の持ち主に限られない。奪ったり、借り受けたり、そういった手段でも同じことが可能だ」
それはそうなのだけど。私が思うのはもっと根本的な問題だ。
このナイフは、ただのメッセージなのでは?
それが真実を現していようと、ミスリードを誘っていようと──誰かが何かを伝えるためだけに残した可能性。しかし、であれば。
件の刺し傷よりほかに怪我のない私は、はたしてどうやって死にかけた?
明日は、まだ見ぬ容疑者についてのハウダニットを。
──投げかける予定だった。の、だが。
六日目:「もうヒントはいらない」
結論から言えば、おおよその答えには既に辿りついてしまっている。事件の真相も、そこから導かれる自分の技能も。
けれど、まだ一つだけ考えなくてはならないことがある。きみが何より欲するその解答を、きっと明日には得てみせよう──。
彼は私の言葉を聞くと、そっと微笑んで部屋から出ていった。
七日目:「這い寄る犯罪の賽子」
あえてルビを振るなら「ザ・ダイス」。それが私の技能の名前。そして──
「きみの名前でもある」
そうだろう探偵。
「その探偵も、いまをもって廃業ですけれどね」
彼は、その瞬間に「変装」を解いた。口調を改め、表情を崩し、声音を、姿勢を、思考を切り替え──指の一本も動かすことなく、彼女に戻った。
「今日からは『推理小説の象徴』ではなく『不可能犯罪の協力者』。サイコロでもダイスでも、邪神でも混沌でも好きなようにお呼びなさい」
それとも、あなたの命名センスであれば──名探偵ならぬ名センスであれば『賽子(さいこ)』と呼ぶかしら。
彼女はくすくすと笑う。
「それでは答え合わせの時間にしましょう。真相に辿り着いても、探偵が居なくなってしまっても、推理を披露しないことには、物語は終われないのです。──そうでしょう? 第一の容疑者、影匿院八くん」
賽子の促すような目線を受けて。
私──否、俺は死ぬほど焦がれた、あるいは殺すほど憧れた『推理演説』というものを、生まれて初めてすることになる。
▽
パラダイムシフト。
肉体が瀕死に、あるいは精神がそれに近い状態へと追い込まれることによって、それまでの技能が全く異なるものへと変化する現象──影匿院八は、それを人為的に起こそうとしたのだろう。記憶はないけれど、そう思う。
菖蒲月某日。民間協力者として空間へ入った彼は、頃合いを見計らってわざと魔人からはぐれた──数分後に発見されるよう、あらかじめ用意した手掛かりを残して。
一人になったところで致死量ぎりぎりの薬剤を服用。続けていたという「薬の研究」は、このためだったのだろう。しかし、それでも下手をすれば行き着く先は死だ。彼は、そのために誰かが疑われることを厭った。だから有事の際への保険として──自殺に見せかけるべく、自らの胸にナイフを刺した。当然ながら罪悪感などなく「ただのシグナル」たるナイフが出来上がる。
そして少年は意識を失い、いまも夢の中にいる。
推理に手間取ったのは、そこに二人の人間がいると考えていたからだ。事件を殺人未遂──「加害と被害」として認識していたからだ。では、なぜ「探偵」は真相を知りながらミスリードを誘ったか。
彼は──技能の擬人化である彼女は、自分の新たな名を知りたがったのだろう。そのために推理という形を利用して、一度は忘れ去られた出来事を、命名権者の中に再構築しようとした。実際、事実だけを淡々と告げられたところで、いまいち実感が沸かないことは、初日の私が証明している。
ここで次の段階に移ろう──すなわち新たな技能の命名。パラダイムシフトに失敗しているという線もなくはないが、探偵が名前を欲していること、「登録されていない」自分の技能に対して罪悪館の殺人がデータとして持ち出されたことから、その可能性は低いと考えられる。
では「罪悪館の殺人」は、いったいどのような技能に変化したのか。手掛かりとなる情報は二つ。
第一に──このパラダイムシフトが意図されたものであるなら、件の「技能訓練の真似事」が、その方向性を操作するための試みであることは明白だ。すなわち彼は、ただ罪悪館の殺人を手放せれば良かったのではなく、それを任意の形に作り替える必要があった。
第二に──悩みの種は、いずれも空間にあった。魔物にせよ技能にせよ、消化作戦に参加し続ける限り目を逸らすことはできない──少なくとも私の感覚では。なればこそ「協力者をやめる」という選択も、同様に出来なかったのだろう。たとえ役に立たないようなそれだったとしても、技能を持つは限り永劫に出来ないのだろう。
しかし「無いに等しい」どころか「害になる」技能ならばどうだろう。彼が目指したのは、作戦参加を断念できるような技能──無差別攻撃型の能力だったのではないか。
これは推測でしかないのだが、おそらく私は名探偵になりたかったのだろう。──そして、きっと今はそうじゃないのだと思う。それでも、あらゆることを忘れてなお推理用語が思考に混ざるほどに、今なお謎に惹かれ、事件に惹かれているのもまた確かであり、だから──それが全てではないにせよ──「この手で描いてみたい」と思ったからこそ、今回の技能殺しに踏み切ったようなところも少なからずあるような気がする。もし私が彼なら、そう思う。
であれば新たな能力は「実行犯型」ならぬ「黒幕型」──自ら動かずとも技能が勝手に人を殺す、完全と不可能犯罪の形を目指したはずだ。そこまで分かってしまえば、あとは自分の趣味で名付けたところで問題はなかろう。名高き創作神話より言葉を借りて──
▽
「素晴らしい! 歴戦の黒幕も舌を巻く完璧な自白でした」
推理だってば。
これでも、まだ曖昧にすら思い出せていないのだ。いましがた話した内容も、結局のところ空論でしかない。──自分のことなのに。
「その点については私が保証しましょう。先の推理は正解、紛うことなき真実ですよ」
それはよかった。で、あれば。
「パラダイムシフトは──きみは、どの程度まで狙い通りになっている?」
「それはもう完璧に。もっとも、だからこそ、それを試す機会はないのでしょうけど」
そうでもないよ。
厳密には、あと一度だけ切り抜けなければならない場面が存在する。──だから
「上手くやってくれ、ナイアルラ」
「お任せなさい、共犯者」
死の淵から這い上がったあなたに、外なる神の祝福を。ついでに記憶も、返しておくわ──彼女の手が頬に触れると同時に、意識が遠のきはじめる。
次に目覚める病室はきっと、ここではない。
(終)
----
おまけの辞典風設定補足
えいとくいんえいと【影匿院 八】
①悩める少年(過去形)。将来的には大学を中退して推理作家になったりするのではないかとくようは思っている。ときどき御堂の政敵排除に立案協力したりもするのではないかと思っている。
ざいあくかんのさつじん【罪悪館の殺人】
①エイトの技能(前)。攻撃型。ミステリに出てきそうな凶器を顕現する能力。攻撃に付随する罪悪感が強いほど威力が上がる。
②エイトが推している作家のデビュー作。うみはるさんの記事「高校生よ大志を抱け」で手に取っていたのは、新しく出た文庫版(だとくようは思っている)。
③未来の話、大学生になり推理小説を書き始めたエイトが②をオマージュして書いた同名の小説。新人賞に応募した結果それなりの評価は受けたが、いかんせん先人の存在に依存しきった作品であるため(+権利関係の諸々により)受賞には至らなかった。
ざ・だいす【這い寄る犯罪の賽子】
①エイトの技能(後)。効果型。能力としては
・一時間ごとにランダムで、空間内に存在する使用者以外の一人が「その場の誰にも起こすことが不可能な要因で」命を落とす。
・犠牲者が決定される際、使用者の脳内にダイスを振る音が鳴ることで、この殺人が技能によるものであることが認識される。
・使用者以外に対して、この殺人が技能によるものであることが隠蔽される。具体的には「技能を感知する」「技能をコピーする」「技能を封じる」等、技能を対象とした能力の効果を受けない。
②未来の話、作家としてのエイトが初めて出す本の題。異能推理もの。
さいこのろみやさいこ【殺々宮 賽子】
①技能「罪悪館の殺人」および「這い寄る犯罪の賽子」の擬人化。
②小説「罪悪館の殺人」(③の方)における探偵役。神話的事件を専門とする『冒涜探偵』──だったのだが、「這い寄る犯罪の賽子」ではニャルラトポテフとして暗躍に勤しむ。なお、その原因として(クルーシュチャ方程式を含む)神話の謎を全て解明してしまったことが描写されている。特技は変装。一日目:「端的に言うと、君は死にかけた」
目が覚めたら病室だった。──などというのは空間消化作戦に従事していれば珍しい体験でもないのだろうけれど、それでも民間協力者となって日が浅い私にとって、ここには何とも言い表せない感慨があった。
だからといって、その少年の言葉に実感が沸くかと問われれば、また別の話になるのだが。まるで夢のような出来事だった。夢のように、覚めたら忘れ去っていた。
死にかけた記憶が、まったくない。
「厳密には殺されかけたんだけどね。もっとも覚えがないのも無理はない。それなりの時間、魔人と離れていたようだから」
少年は言う。──おそらく少年のはずだ。一見では女性かと思ったような美人なので吸血鬼の可能性も考慮したが(非科学的な話なので本気で想定したわけではないのだが)、残念ながら鏡も十字架もないので検証には至らなかった。
冗談はさておき。
殺されかけた──それは死にかけたのとは違うのだろうか。消化作戦で死にかけるのと、空間に殺されかけるのとでは、ほとんど同義になるのでは?
「容疑者が魔物や手下だけなら僕もそう言っただろう。けれど」
この殺人事件ならぬ殺人未遂事件には、人間の容疑者も存在する。
それが彼の言い分だった。
「僕は探偵でね。空間管理機構から真実の究明と報告書の作成を依頼されているんだ。ゆえに君から話を聞こうと思っていたのだが──」
当事者の記憶はごっそりと抜け落ちていたわけだ。お役に立てなくて申し訳ない。
「もっとも、おおよその筋道は既に把握している。あとは君の技能さえ分かればパズルは完成したも同然だ。しかし……」
探偵はそこで神妙な顔をしてみせた。
「手違いか、あるいは何か他の理由でか。その技能について、機構のデータベースに一切登録されていなかったんだ」
ふうん、そうなんだ。たぶん手違いだと思うよ。
大した技能じゃないからね。
そう言いかけて気づく。作戦参加の弊害、単独行動の代償。
「私の技能って、どんなのだったっけ」
そんなとぼけた反応に「やはりね」と前置きしてから少年はこう述べる。
「だから君には、自分の技能について思い出してもらう必要がある。毎日少しずつ、事件に関する情報を提供するから、その穴を埋める形で自分の技能を推測してみてほしいんだ。なに、そこまでの正確性を求めているわけではないからね。せいぜい技能の名前さえ分かれば報告書なんてそれらしく書けるわけだし、とりあえずはそこを目標にしてみてくれ」
いいのかそんな適当で。
とはいえ名前当てくらいならば、そこまで高いハードルでもない。そもそも自分の技能なのだ。最悪の場合は新しく名付ければいい。
そんなこんなで。
探偵の依頼を受け、病床探偵の命名推理が始まったのだった。
二日目:「一人目の容疑者について教えよう」
次の日、私の病室へとやってきた彼はこう切り出した。
「名前は影匿院八(えいとくいん えいと)。君が発見された当時、胸に刺さっていたナイフ──それを顕現した技能を持つ高校生だ。君とほぼ同地点に倒れており、現在も意識不明の重体。昏倒の原因は薬剤の過剰服用と思われる」
なるほど完全に容疑者だ。彼が私を刺した上で隠蔽工作のため自らも意識を断ったとかで良いんじゃないだろうか。
「短絡的だな君は」
話の続きを聞きたまえ、と本職の探偵は言う。
「ナイフが刺さっていた胸元に、ほとんど傷が残っていないだろう。これは犯人に罪悪感がなかったことを意味する」
と言うと?
「影匿院少年の技能『罪悪館の殺人』は、抱く罪悪感が強ければ強いほど威力を増す能力だ。扱えるのはミステリに登場しそうな凶器に限るという制約こそあるけどね。そして、もしその彼が君を殺そうと考えた場合、罪悪感がないのを分かっていながら、わざわざ技能を使うだろうか」
分からないよ。実際に刺してみるまで「罪悪感がある」と思い込んでいたのかもしれないし。
──刺してみたら案外、威力が出なかっただけかもしれないし。
とはいえ、彼の言うことにも一理ある。これ見よがしに影匿院くん(以降、略してエイトくん)のナイフを残したのが、容疑を彼へ向けるためのカムフラージュである可能性も、結構な割合で否定できなかった。
でも、ところでなぜエイトくんは薬の過剰摂取なんてしたのだろう。意識を失うほどの量なんて、自らの判断でない限り服用できるとは思えない。たとえば水を魚の形にして泳がせる技能保持者なんかであれば無理矢理飲ませることも可能かもしれないが、見知らぬ誰かさんを疑うのは(今のところ)やめておこう。脅されたか、自殺を図ったか──後者であれば、やはりエイトくんが犯人だった可能性も出てくるけれど……。
思考がこんがらがってきた。
そもそも手持ちの情報はこれだけではないはずだ。もう少しヒントがほしい。
「もちろん幾らかの取っ掛かりは用意しているけれど」
少年は悩ましげに言う。
「一定量を超える手掛かりを、同時に提示するのは得策とは思えない。できれば君には、今日の情報を咀嚼しておいてほしいんだが」
もちろん明日にはまた新しい話を持ってくるとも。
そう笑って探偵は病室を後にした。──私がどんな技能を持っていればこんなことが起きるのかは、結局さっぱり分からないまま。
三日目:「二人目の容疑者について教えよう」
昨日とまったく同じ調子で、探偵は説明を始めた。
「先述の『罪悪館の殺人』という技能に関して、これと同じものを使える者が今回に限りもう一人存在する。──前回の空間について、おおまかな記憶はあるかい?」
まったく。
「では軽く紹介しよう。ざっくりした言い方をしてしまえば、擬人化した技能が襲ってくる空間だ」
つまり、人の姿を取った「罪悪館の殺人」が二人目の容疑者ということ?
「そう。この空間における手下は、探索者を殺し尽くすか、あるいは自らが滅ぼされるまで止まらない。しかし、それゆえに殺人を遂げるほどの罪悪感を持たず、結果として君が『死にかけるだけ』で済んだ可能性は、ある程度の真実味を持って提言できる。の、だけど……」
言葉を濁さないでほしい。
もう良いじゃんそれで、などと早くも思考を停止しかけた私に少年は告げる。前提をひっくり返しかねない事実を淡々とぶつける。
「彼ないし彼女──『罪悪館の殺人』と見られる技能の姿においては、目撃報告が一切上がっていない」
▽
そう聞いた時には少し驚いてしまったけれど(今はそれから少し経っている。探偵が帰った後だ)、よく考えてみれば「目撃報告がない」という情報には二通りの可能性が考えられた。
すなわち「技能の擬人化が誰とも遭遇しなかった場合」と「目撃者が証言をしなかった場合」だ。前者であれば、そもそも殺人が成立しない。探知系の技能保持者もいる中で、凶器を顕現する謂わば「実行犯型」の技能が姿を隠しながら敵を攻撃できるとはとても思えなかった。どうしても技能『罪悪館の殺人』を、容疑者から外さざるを得なくなる。
しかし後者ならばどうだろう。たとえば、その姿を見たのが私とエイトくんだけだった場合、記憶混濁と意識不明が目撃証言などできるはずがない。同様に、その事実を隠している人物がいた場合──それをして得をするのは、十中八九この事件の犯人ではないだろうか。
とはいえエイトくんも容疑者から外れたわけではないので、このあたりはフェアに詰めていきたい。明日からは、私の方から探偵に質問をしていくことになっている。まずは第一の容疑者においてのホワイダニットから。
四日目:「彼に犯行の動機はあるの?」
そもそも、そんなテーブルゲームみたいな名前の男の子に刺される謂れはないのだ──忘れているのでなければ。空間の影響で記憶が曖昧な今、それについては確認しておく必要があった。
探偵の答えはこうだ。
「それは難しいところだね、人の内心というのは分からないから。それでも周囲の評価を鑑みるに『あまりなさそうだ』というのが調査結果だ」
──とはいえ、と彼は付け足す。
「あれこれ思い悩むタイプの少年ではあったようだ。存在することさえ否定される魔物への憐憫。精神的順応にしたがって使い物にならなくなりつつある技能。解決のために薬の研究や技能訓練の真似事もしていたみたいだけど、いずれも上手くはいっていなかったようだ」
どれもこれも、どちらかといえば自殺の理由みたいな悩みだけれど。何かの弾みに糸が切れてしまった、という可能性は案外悪くない取っ掛かりのように思える。
すなわち動機の排除。推理小説を技能のモチーフにするような少年が、たとえば誰でもいいから人を殺そうと思った時、被害者として選ぶのは一体どういう人間だろう。あるいはの話──手持ちのトリックを使用するためだけに「アリバイ工作に使える技能の持ち主」を探すこともあるのではないだろうか。
これを受けて探偵は、
「なるほど、そこで君の技能推測に繋がるわけか。その条件に当てはまる能力については僕の方で候補を立てておこう」
君には別の方向性についても検討してみてほしい──などと、肯定とも否定とも言えないような言葉を残すと踵を返して出ていった。真意が読めないのは気に食わないけれど、ともあれ。
ひとつの可能性のみを、一度に突き詰めすぎない方が良いのは確かだ。次は二人目の容疑者に関するフーダニットを。
五日目:「コピー技能の持ち主はいた?」
探偵の提示した「能力の候補」を「趣味に合わない」という理由で全却下した私はこう質問した。
本人以外にその技能を使う人物がいる──。これまで言及されなかったとはいえ、その可能性を挙げられてしまった以上、避けて通れないのがこの問題である。なにせ容疑者が増えかねない。こういう面倒な枝分かれは、早めに潰しておきたかった。
「そんな君に朗報だ。作戦に参加した職員、協力者および巻き込まれた民間人のうち、他者の技能を模倣しうる6名──その全てにアリバイがある」
同行者がいた、技能での観測があった、記録写真に残っていた、エトセトラ。中には「身内の証言」程度の信憑性のものもあるとはいえ、ひとまず全員、一応の不在証明が成立しているらしい。
誰一人として私達と接触していない。しかも今回の作戦全体を通して。
たしかに余計な可能性を潰しておきたいとは言ったけれど──その一方で、新たな容疑者の出現に期待していなかったわけでもないのだ。
引っかかるのはナイフ。
見るからに分かりやすくエイトくんの持ち物であるナイフは、なぜ私の胸に刺さったままだったのだろう。もちろん威力がないとはいえ抜けば失血死していたかもしれないので、それについて文句を言うつもりはないのだが、どうしても。
「つまり『影匿院少年の犯行に見せかけたかった誰か』の存在を念頭に置いているわけだね」
探偵が補足をする。
「であれば、それが出来るのは何もコピー技能の持ち主に限られない。奪ったり、借り受けたり、そういった手段でも同じことが可能だ」
それはそうなのだけど。私が思うのはもっと根本的な問題だ。
このナイフは、ただのメッセージなのでは?
それが真実を現していようと、ミスリードを誘っていようと──誰かが何かを伝えるためだけに残した可能性。しかし、であれば。
件の刺し傷よりほかに怪我のない私は、はたしてどうやって死にかけた?
明日は、まだ見ぬ容疑者についてのハウダニットを。
──投げかける予定だった。の、だが。
六日目:「もうヒントはいらない」
結論から言えば、おおよその答えには既に辿りついてしまっている。事件の真相も、そこから導かれる自分の技能も。
けれど、まだ一つだけ考えなくてはならないことがある。きみが何より欲するその解答を、きっと明日には得てみせよう──。
彼は私の言葉を聞くと、そっと微笑んで部屋から出ていった。
七日目:「這い寄る犯罪の賽子」
あえてルビを振るなら「ザ・ダイス」。それが私の技能の名前。そして──
「きみの名前でもある」
そうだろう探偵。
「その探偵も、いまをもって廃業ですけれどね」
彼は、その瞬間に「変装」を解いた。口調を改め、表情を崩し、声音を、姿勢を、思考を切り替え──指の一本も動かすことなく、彼女に戻った。
「今日からは『推理小説の象徴』ではなく『不可能犯罪の協力者』。サイコロでもダイスでも、邪神でも混沌でも好きなようにお呼びなさい」
それとも、あなたの命名センスであれば──名探偵ならぬ名センスであれば『賽子(さいこ)』と呼ぶかしら。
彼女はくすくすと笑う。
「それでは答え合わせの時間にしましょう。真相に辿り着いても、探偵が居なくなってしまっても、推理を披露しないことには、物語は終われないのです。──そうでしょう? 第一の容疑者、影匿院八くん」
賽子の促すような目線を受けて。
私──否、俺は死ぬほど焦がれた、あるいは殺すほど憧れた『推理演説』というものを、生まれて初めてすることになる。
▽
パラダイムシフト。
肉体が瀕死に、あるいは精神がそれに近い状態へと追い込まれることによって、それまでの技能が全く異なるものへと変化する現象──影匿院八は、それを人為的に起こそうとしたのだろう。記憶はないけれど、そう思う。
菖蒲月某日。民間協力者として空間へ入った彼は、頃合いを見計らってわざと魔人からはぐれた──数分後に発見されるよう、あらかじめ用意した手掛かりを残して。
一人になったところで致死量ぎりぎりの薬剤を服用。続けていたという「薬の研究」は、このためだったのだろう。しかし、それでも下手をすれば行き着く先は死だ。彼は、そのために誰かが疑われることを厭った。だから有事の際への保険として──自殺に見せかけるべく、自らの胸にナイフを刺した。当然ながら罪悪感などなく「ただのシグナル」たるナイフが出来上がる。
そして少年は意識を失い、いまも夢の中にいる。
推理に手間取ったのは、そこに二人の人間がいると考えていたからだ。事件を殺人未遂──「加害と被害」として認識していたからだ。では、なぜ「探偵」は真相を知りながらミスリードを誘ったか。
彼は──技能の擬人化である彼女は、自分の新たな名を知りたがったのだろう。そのために推理という形を利用して、一度は忘れ去られた出来事を、命名権者の中に再構築しようとした。実際、事実だけを淡々と告げられたところで、いまいち実感が沸かないことは、初日の私が証明している。
ここで次の段階に移ろう──すなわち新たな技能の命名。パラダイムシフトに失敗しているという線もなくはないが、探偵が名前を欲していること、「登録されていない」自分の技能に対して罪悪館の殺人がデータとして持ち出されたことから、その可能性は低いと考えられる。
では「罪悪館の殺人」は、いったいどのような技能に変化したのか。手掛かりとなる情報は二つ。
第一に──このパラダイムシフトが意図されたものであるなら、件の「技能訓練の真似事」が、その方向性を操作するための試みであることは明白だ。すなわち彼は、ただ罪悪館の殺人を手放せれば良かったのではなく、それを任意の形に作り替える必要があった。
第二に──悩みの種は、いずれも空間にあった。魔物にせよ技能にせよ、消化作戦に参加し続ける限り目を逸らすことはできない──少なくとも私の感覚では。なればこそ「協力者をやめる」という選択も、同様に出来なかったのだろう。たとえ役に立たないようなそれだったとしても、技能を持つは限り永劫に出来ないのだろう。
しかし「無いに等しい」どころか「害になる」技能ならばどうだろう。彼が目指したのは、作戦参加を断念できるような技能──無差別攻撃型の能力だったのではないか。
これは推測でしかないのだが、おそらく私は名探偵になりたかったのだろう。──そして、きっと今はそうじゃないのだと思う。それでも、あらゆることを忘れてなお推理用語が思考に混ざるほどに、今なお謎に惹かれ、事件に惹かれているのもまた確かであり、だから──それが全てではないにせよ──「この手で描いてみたい」と思ったからこそ、今回の技能殺しに踏み切ったようなところも少なからずあるような気がする。もし私が彼なら、そう思う。
であれば新たな能力は「実行犯型」ならぬ「黒幕型」──自ら動かずとも技能が勝手に人を殺す、完全と不可能犯罪の形を目指したはずだ。そこまで分かってしまえば、あとは自分の趣味で名付けたところで問題はなかろう。名高き創作神話より言葉を借りて──
▽
「素晴らしい! 歴戦の黒幕も舌を巻く完璧な自白でした」
推理だってば。
これでも、まだ曖昧にすら思い出せていないのだ。いましがた話した内容も、結局のところ空論でしかない。──自分のことなのに。
「その点については私が保証しましょう。先の推理は正解、紛うことなき真実ですよ」
それはよかった。で、あれば。
「パラダイムシフトは──きみは、どの程度まで狙い通りになっている?」
「それはもう完璧に。もっとも、だからこそ、それを試す機会はないのでしょうけど」
そうでもないよ。
厳密には、あと一度だけ切り抜けなければならない場面が存在する。──だから
「上手くやってくれ、ナイアルラ」
「お任せなさい、共犯者」
死の淵から這い上がったあなたに、外なる神の祝福を。ついでに記憶も、返しておくわ──彼女の手が頬に触れると同時に、意識が遠のきはじめる。
次に目覚める病室はきっと、ここではない。
(終)
----
おまけの辞典風設定補足
えいとくいんえいと【影匿院 八】
①悩める少年(過去形)。将来的には大学を中退して推理作家になったりするのではないかとくようは思っている。ときどき御堂の政敵排除に立案協力したりもするのではないかと思っている。
ざいあくかんのさつじん【罪悪館の殺人】
①エイトの技能(前)。攻撃型。ミステリに出てきそうな凶器を顕現する能力。攻撃に付随する罪悪感が強いほど威力が上がる。
②エイトが推している作家のデビュー作。うみはるさんの記事「高校生よ大志を抱け」で手に取っていたのは、新しく出た文庫版(だとくようは思っている)。
③未来の話、大学生になり推理小説を書き始めたエイトが②をオマージュして書いた同名の小説。新人賞に応募した結果それなりの評価は受けたが、いかんせん先人の存在に依存しきった作品であるため(+権利関係の諸々により)受賞には至らなかった。
ざ・だいす【這い寄る犯罪の賽子】
①エイトの技能(後)。効果型。能力としては
・一時間ごとにランダムで、空間内に存在する使用者以外の一人が「その場の誰にも起こすことが不可能な要因で」命を落とす。
・犠牲者が決定される際、使用者の脳内にダイスを振る音が鳴ることで、この殺人が技能によるものであることが認識される。
・使用者以外に対して、この殺人が技能によるものであることが隠蔽される。具体的には「技能を感知する」「技能をコピーする」「技能を封じる」等、技能を対象とした能力の効果を受けない。
②未来の話、作家としてのエイトが初めて出す本の題。異能推理もの。
さいこのろみやさいこ【殺々宮 賽子】
①技能「罪悪館の殺人」および「這い寄る犯罪の賽子」の擬人化。
②小説「罪悪館の殺人」(③の方)における探偵役。神話的事件を専門とする『冒涜探偵』──だったのだが、「這い寄る犯罪の賽子」ではニャルラトポテフとして暗躍に勤しむ。なお、その原因として(クルーシュチャ方程式を含む)神話の謎を全て解明してしまったことが描写されている。特技は変装。 くよう.
くよう.
![創作SNS GALLERIA[ギャレリア] 創作SNS GALLERIA[ギャレリア]](/s/img/Title_20.gif)