[7/23新刊サンプル]愛してるのつづきをどうぞ【合冊版】「弟を愛せないんだ。殺してしまいたいとすら思う。同時にあいつを見ていると酷く興奮して、滅茶苦茶に犯したいとも思うんだ。――なあ、杉元、俺はどうすればいい?」
深淵を凝縮して閉じ込めたような純黒の双眸が真っ直ぐに杉元を見据える。縋るように見えるのは杉元自身がそう願っているからだろうか。問われた言葉ではあるけれどきっと尾形は何も求めてはいないだろうし、どう答えたところでこの男には少しも響きはしないのだろう。その「弟」の言葉以外は。
だから杉元は尾形の眼差しからすいと視線を逸らし、沈みゆく夕陽に目を眇めながらこう答えた。
「お前がゲイで弟を犯そうが、泥沼愛憎劇の果てに殺人者になろうが、別にどうでもいい」
尾形はそれ以上言葉を紡ぐことはなかった。縋るようにも見えた双眸がどう動いたのかも杉元は知らない。ただ、最後に爪痕を残すかのような強烈な陽射しが、世界を突き刺し姿を消していく光景が目に染みるなと思った。
ああ、まったく、どうしてお前は俺にそんなことを言うのか。
――およそ百年前、お前を殺した、この俺に。
尾形百之助と初めて出会ったのは中学の入学式のことだ。
父親の転勤により杉元佐一がこの春から住み始めたのは、茨城県のとある町。山は見えるが近いというわけでもなく、海もあるけれどやはり特段近いわけでもない。何か名物料理や特産品があるわけでもなく、観光名所になるような場所もない。かといって閑散とした「ド田舎」というわけでもなく、国道沿いには有名チェーンのファミリーレストランやファーストフード店が並び、映画館を併設した巨大なショッピングモールもある。つまりどこにでもある普通の町で、杉元がこれまで暮らしていた町より若干栄えているかもしれない。
そんな町にあるやはり何の変哲もない公立中学校に初めて足を踏み入れた杉元は、些か緊張気味に顔見知りが誰一人としていない校門を潜るとクラス表が提示してある掲示板の前へと立った。
一学年五組のクラス分けを一組から、五十音順に並ぶ名前の中より己の名を探すと三組のところでふと視線が止まり、ひゅっと鋭く息を吸う。
――尾形百之助。
見間違いかと一度目を擦り、再び視線を向ける。「尾形百之助」見間違いではない、確かにそこにはそう記載がされている。
時代錯誤とも思えるその名前にぶわりと鳥肌が全身の皮膚を覆う。まさかここでその名前を目にすることになるとは。一瞬で殺気だった空気にすぐ傍にいた保護者が気付き、訝し気な視線を向けられながらすいと距離を空けられる。
マズイ、やっと制御出来てきたというのにコントロールを失ってしまった。一度緩く目を閉じて、深く息を吸う。
大丈夫だ、ここは明治の「あの時」じゃない。今までに見つけた誰も彼もが「あの時」の記憶を持ってはいなかった。だからこの男だって、「あの時」の人間とは違うだろう。
吸った分だけの息をふっと吐き出し、改めて掲示板と向き合う。件の名前の数行下に自分の名前を見付けた。
「マジかー……」
思わず漏れた一言に今度は反対側に立つ同級生と思われる女子生徒が怯えるように立ち去った。
あの時は奴の方が幾つか年上だった筈だが、今生ではどうやら同い年らしい。一年三組、あの男とこれから中学生活始まりの一年を共に過ごすことになるとは何んとも言えない薄ら笑いが込み上げてくる。
杉元佐一には前世の記憶を持つという突拍子もない秘密がある。およそ百年前、明治後期を生きたもう一人の自分の記憶だ。
物心ついた時には当たり前のように脳の片隅にあったその記憶を、幼い頃の杉元は特別なことだとは思っていなかったが、年を取るにつれそれが随分と特殊なことだと気付いてからは誰にも明かせない秘密として抱えている。
この年になるまでの間、前世で関りのあった人物とは何人か会っている。正確に言えば会っているというより、杉元が一方的に知っているだけだ。何せ誰も前世の記憶を有しているわけではなく、杉元の姿を見ても何の反応もなく今では正真正銘ただの他人だ。
初めて出会ったのはアシリパだった。父親に連れられて赴いたとある博物館で研究員として働いていた彼女は杉元よりも随分と年上で、アイヌに興味があると話せば熱心に説明をしてくれたが、終ぞ彼女の口から「杉元」と呼ばれることはなかった。
その時は酷くショックを受けた。やっと出会えた前世の相棒は杉元のことなどすっかり忘れていたのだから。しかし彼女にしてみれば前世の記憶は良い思いをしたばかりではない。記憶を持っていない方がいいのかもしれないし、記憶がなくてもこうしてアイヌ文化を研究しているのだからそれで良いのだと思えた。
だからその後、何人かの前世絡みの人間に会っても期待をするわけもなく、ショックを受けることもなく、自分が特殊なのだと淡々と受け止めた。
――まぁ、例外がたった一人いるのだが。
クラス表に提示されていた一年三組の教室へ一歩足を踏み入れた途端、室内の空気が一変した。決して居心地が良いとは言えない変わった空気を肌で感じながらも杉元はちらと前方の黒板へと視線を遣り、出席番号順に座るよう指示されている内容を見て窓際へと顔を巡らせた。
「あ……」
また自然と声が漏れていた。窓際の一列目、最後部席。そこによく知る顔の男が静かに文庫本を広げて視線を落としている。正確に言えば見たことはない顔だ。見たことはないが、その顔があと十年ほど歳を重ねた姿ならよく知っている。
本当にいたんだな……と思いながらも、杉元は黒板に書かれた座席順をもう一度目にして自席に腰を降ろした。窓際から三列目の最後尾、周りの喧騒など気にもせず相変わらず文庫本に視線を落としている尾形から、一つ席を置いた並びだ。
公立中学だけあって、近隣に住む生徒達が集まる室内はすでに何組かのグループに分かれていてそれぞれで明るい声が響いている。父親の転勤がなければ杉元も生まれ育った町の中学校で、彼等のように同じ小学校から来た同級生と明るい声を上げていただろう。しかしここに顔見知りは誰もいない。敢えているとしたら並んだ席にいる尾形百之助くらいだが、彼は誰とも混じることなく、杉元がすぐ近くに腰を降ろしても文庫本に落としたままの視線を上げたりはしない。
友達がいないのだろうか。明治期の尾形を思い返せば、親しい友達が出来るような男ではなかったが、要領は良いように思えたから外面だけでそれなりの友達と呼べる人間を作れそうな気もする。しかし彼に声を掛ける人間はいない。引っ越してきたばかりの杉元と同じように遠巻きにされ、二人の周りはぽかりと誰もいない空間が広がっている。
全く新しい環境に馴染めるだろうかと緊張していたそれが、意味を変えた。友達が出来るかとかの期待や不安じゃない。何はともあれすぐそこにいる尾形が「あの時」の記憶を持っているのかいないのかが気になる。
ちらちらと何度も視線を送ってしまう。あの時のようなツーブロックで、髪を後ろに撫でつけた姿ではなく、今時珍しい丸坊主。しかし特徴的な眉毛や重たげな瞼、アイラインを引いたかのようにはっきりとした双眸と真っ黒な瞳は変わらない。そして何より、両の頬に薄っすらと浮かんでいる縫合痕。
あれはおよそ百年前――前世で初めて尾形と出会った時にやり合って負った傷だった筈だが、今生では出会う前にすでについているのが不思議だ。一体どうして傷を負ったのだろうか。
とはいえ杉元も前世と同じく派手な傷を顔面に負うことになった。殺し合いの果て……ではなく、幼少期に少々やんちゃをしてできたものだ。あの頃に比べれば目立たないが、事情を知らない者と対面した時は大抵ぎょっとした顔をされる。だから尚更、今も遠巻きどころか誰も目を合わせようとしてこないのだろう。
「……っ!」
ふと、紙面に顔を落としていた尾形がすいと杉元へと視線を向け、ばちりと合ったそれに思わず大きく肩が震えた。あからさまに見ていたわけではないが、視線は感じていたのだろう。その口から何かが飛び出してくるだろうかと、心臓が大きく鼓動を打ち冷やりとした汗が背中を伝った。
あの時の記憶はあるのだろうか。杉元もまだまだ幼い顔立ちをしているが、さすがにこの傷を見れば分かるだろう。そう、記憶があれば。
しかし尾形は驚いたわけでもなければ、眉を顰めるわけでもなく、ただ無表情に杉元の顔をしばし見遣ってからすぐにまた文庫本へと視線を落とした。
とんでもない言葉が飛び出してこなかったことにホッとしつつも、記憶を持っているわけでもなさそうな雰囲気に拍子抜けもする。しかし相手はあの尾形百之助だ。記憶があっても綺麗に隠して誰にも悟らせず、素知らぬ振りをして飄々と生きていくことも出来そうな気がする。
とにかく油断はしないようにしよう。何だっらさり気なくあの時の記憶があるか探りを入れてもいい。話す機会があれば、だが。
「もしもし?」
『――……杉元』
「うん、どうした? お前が電話してくるなんて珍しいな。あ、そういやあけおめだな」
『ああ……。なぁ、少し出てこれないか?』
唐突な電話に、唐突な誘い。それにどこか歯切れの悪い口調に内心首を傾げながら杉元は時計に視線をやった。十八時四五分、もうすぐ夕食の声が掛かりそうだが尾形に会うと言えば喜んで送りだしてくれるだろう。
「いいよ。どこに行けばいい?」
『初詣、行きたいんだろ』
「へ……?」
『もう行ったのか?』
思い掛けない言葉に一瞬思考が停止した。数日前に一度はスルーされた話題だったのだが、まさか尾形の方から誘いを掛けられるとは思いもしない。
「行ってない! 行く!」
勢い込んで返事をし、すぐさま部屋着から着替えるためクローゼットを開けると慌しい様子が伝わったのか、電話の向こうで尾形が少し笑った。
『俺の家の近くの神社でいいよな? 鳥居のところで待ってる』
「分かった! すぐ行く!」
電話を切ると手早く着替えコートを羽織り、キッチンにいる母親に声を掛けて杉元は夜へと飛び出した。
――何だろう、この気分の高揚は。ああ、そうか、思いがけず尾形に会えて嬉しいんだ。今までずっと二人でいたのに突然一人で放り出されて、寂しかったのかもしれない。特に話したいこともないし、会えばまた嫌味や皮肉を言われ個人宿題を課せられるかもしれないがそれでもいい。単純に尾形に会えるという事実が嬉しい。
冷たい夜風を全身に受けながら自転車を走らせ約束の神社へと辿り着けば、マフラーに顔を埋めた尾形が開口一番「遅い」と文句を垂れた。その憮然とした口調すらなんだか嬉しくてつい笑みを浮かべると、尾形の視線が途端に冷たいものへと変わった。
三が日を過ぎた境内は二人以外に人影はなくとても静かだ。授与所も閉まっていて灯りは最小限にぽつぽつと。年が明けた際には人出も多く賑やかっただっただろうに、今は静穏とした暗闇に包まれている。
「あ、財布忘れた!」
手水舎で手を清めいざお参りというところでダウンコートのポケットに財布がないことに気付く。慌てて支度をしたせいですっかり忘れていた。気付けばスマホすらもっていない。ジーンズのポケットなども漁ったが、一円玉ひとつすら出てこなかった。
「え~、マジかよ……なぁ尾形、お賽銭なくても神様ってお願い事聞いてくれっかな?」
「お前、そんなのがいるとか信じてるのか?」
情けない声を上げながら尾形を伺い見れば、彼は幼げにきょとんと目を瞬かせながら杉元を見返した。――いや、お前ここまできてそれはないんじゃねぇの? と思ったが、尾形のこれまでの境遇を考えれば神様なんて存在自体が怪しくていないものだと思うのもしょうがないかと察してしまった。何も信頼できるものがない今の尾形にとって、目には見えない存在を信じることが一番難しいことなのだろう。
杉元だって本当に神様がいると信じているわけではない。目には見えない何かに縋って、少しでも心の安穏を保ちたいだけだ。だから何事もなかったかのように「まぁ、いっか」と声を出そうとした時、すっと目の前に手が差し伸べられた。
「ほら、これで足りるか?」
尾形の白い手の平には鈍い色を放つ五円玉が一つ。「へ?」と間抜けな声を出しながら、差し出された手と尾形の顔を交互に見遣ると無理矢理手に握らされた。
冷たい指先と温かな五円玉が触れた瞬間、ひくりと心臓が小さく音を立てる。
「ありがと……。今度会った時返すよ」
「いや、いい。お前の願い事とやらがもしも叶ったら、その時に倍返ししてくれ」
拝殿へと向かうためくるりと背中を向けた尾形の後ろ姿に、また心臓が一つ大きく鼓動を打つ。
人からもらったお金で願い事が叶うだろうかとか、倍返しって狡くないかとか、ふと脳裏を過った下らない思考が体内から打ち鳴らす鼓動によって搔き消される。
渡された五円玉をぎゅっと拳に握り締めながら尾形の後を追い拝殿の前に立つ。神社での参拝の作法など覚えていないけれど、ひとまず一礼して鈴を鳴らす。隣に立つ尾形はぼんやりと拝殿を仰ぎ見るだけで身じろぎしない。当たり前だ、きっと尾形は今よりずっと幼い時に神様はいないと絶望したのだから。
だから、尾形から渡されたこの五円玉は尾形のために使う。神様を信じていない尾形に代わって、――俺が尾形の神様になる。
握り締めた拳から放たれた五円玉は緩い放物線を描き、賽銭箱へ落ちていった。からころと響く小気味良い音を耳にしながら手を合わせ目を閉じる。
尾形と一緒に志望校に合格しますように。そんな願い事をしようと思っていたが、倍返しにしないといけなくなってしまったので予定変更だ。
――神様、お願いです。貴方がいるかも分かりませんが、貴方がいなければ俺が叶えるしかないけど、どうかお願いです。どうか、尾形が……――。
合わせた両手にぐっと力を篭めて最後に一礼をして顔を上げる。すると隣から「拝んでるっていうより殴り掛かろうとしてるようにしか見えなかった」と指摘をされて、へらりと笑いながら誤魔化した。正に神様に喧嘩を売ったようなものだと思う。
「俺の願い事が叶ったら三倍返しにしてやるからな! 覚悟しとけよ!」
「なんか増えてねぇか?」
「増えてる方がいいだろ。俺の願い事が叶ったらお前の徳になるんだぜ?」
「ははぁ、そうだな」
馴染みのある独特の笑い方と伸びた前髪をゆるりと背後に流す仕草。よく知っている。それは前世の尾形百之助もよくやっていた癖だ。そして向けられる冴えた眼差し。それでいい。そうやって何も期待をしないでいてくれれば、俺の願いが叶わなくてもお前は気付くことがないから。
参拝を終えて神社の出入り口となる鳥居を目指し、再びゆっくりと二人で歩く。相変わらず尾形は自ら何も語ろうとしない。杉元もやはり何か話したいこともないので黙っている。けれどそれが特に居心地が悪いわけでもないと感じるのは、前世でも必要以上に言葉を交わしたりはしなかったからだろうか。
二人が待ち合わせた鳥居の前まで戻り、自転車の鍵を外している時、杉元は尾形と離れたくないと唐突に思った。何故だろう。このままずっと見ていたい、出来ることならずっと傍にいたい。そんなことを当たり前のように考えて尾形に答えを委ねるようにして縋った視線を向けていた。
尾形はその視線の意味に気付いたのだろうか。白く冷えた指先がそっと伸びてきて、杉元の顔に走る傷をなぞるように触れた。ふっと白い吐息を零しながら尾形が口を開く。
「俺の父親だっていう男に会ってきた……」
その言葉に、はっと息を呑む。尾形の父――今までに誰からも、尾形からも聞いたことがない人物だ。存在していたのかとすら思う。
「尾形の、お父さん……?」
「ああ、戸籍には当然載ってないが、DNAってやつはそうなっているらしい」
とつとつと語りながら尾形の指先は杉元の左頬に走る傷跡を辿り、唇へとゆるりゆるりと下りていく。
「ガキの頃から何度も思っていたことがある。ここに父親がいたらどうなってたかってな。……でも、実際に顔を合わせるとこれは俺が欲しかったものじゃねえって駄々を捏ねたくなる」
ふと、思う。尾形は幼かった時に神様に縋るよりも、まず会ったことのない父親に縋ったのではないかと。神様よりもとても身近で頼りになる、しかし尾形にしてみれば目には見えない神様と同じくらい遠いところに存在していたもの。
あれだけ高揚していた心臓が不規則に鼓動を刻み、ざわざわと落ち着きをなくす。このまま尾形の傍を離れてはいけないのではないかとう焦燥が更に募る。
「お前が、この休みには会えなっていってのはそのせいなのか……?」
頬を辿る尾形の手を摑まえてきゅっと握り締めると、杉元を見据えていた双眸がぱちりと一つ大きく瞬き、視線を伏せるようにして微かに頷いた。
「そうだ。クソみてぇにつまんねえ話しだから聞かせるつもりはないけどな」
「いいよ、別に聞きたいとも思ってねぇし」
尾形が語ろうとしないのなら、杉元の耳には何も届かない。所詮尾形の父親というだけで、その人間自体に興味はない。
「なぁ、杉元」
「ん」
握っていた尾形の手が、徐に握り返してくる。さっきまであれだけ冷えていた指先が体温を分け合うかのようにして、仄かな温もりを帯びている。
「もしも俺が……、」
言葉を紡ごうとした尾形は、しかし不意にそこで口を噤むと「いや、なんでもない」と言いながら視線を逸らし、握っていた指を離した。途端に指先が寂しさを訴え、心の中を騒がせる焦燥が膨らむ。
「なんだよ」
「何でもない」
尾形の手を追い掛けて伸ばした指先は寸前で躱され掠りもせず、逃げるように尾形はさっさと歩き出した。自転車を押しながら慌ててその背中を追い掛ける。
「尾形」
「お前ん家は逆だろ、着いてくるな」
「何言おうとしたんだよ、教えろって」
「コンビニでも行くか。貧乏な杉元くんに肉まんでも奢ってやるよ」
「財布を忘れただけで金はあるんだよ。つか、誤魔化すなって」
コンビニの明かりが見えてきたところで観念したのか、尾形は足を止めると後頭部を掻き毟り杉元へと顔を向けた。
「もしも俺に何かがあっても、お前は俺を忘れないか?」
「お前みたいな奴、忘れるわけねぇだろ」
何を言い出すのかと思ったらそんなこと。これだけ強烈な人間は前世の繋がりがなくてもそう簡単に忘れられるわけがない。
躊躇いもなく答えを出した杉元に満足したのか、尾形はどこか嬉しそうに少し笑うとコンビニへ向けて真っ直ぐに歩き出した。
その背中をしばし眺めて思う。――忘れたくても忘れられないんだ。百年前からずっと、殺した相手の顔は忘れたりしなかったから。
それから尾形に会えなくなった。
三学期に入っても尾形は登校せず、いつの間にかどこかへ転校していた。
法学部の尾形と文学部の杉元が広大な大学キャンパス内でそうそう顔を合わせることはないだろうと思っていたのだが、運命の悪戯か第二外国語が尾形と被っている。杉元に至っては楽だと聞いていたスペイン語から弾かれてのロシア語だ。よりによってロシア語……極寒の樺太の地を思い出し、悪戯にもほどがあるだろうと運命を恨む。
そんな事もあり尾形とは頻繁に連絡を取り合ったりはしないが週に一度は必ず顔を合わせることになり、その日は流れで昼食を共にし、時々授業が終わると落ち合って尾形は杉元の家までやって来たりする。
二人で会って何をしているのかと言えば、特に何もしていない。尾形が一方的に弟、勇作のことを喋り散らかしているだけだ。――そう、数年振りに再会して変わったのは容姿だけでなく、尾形はよく喋るようになった。その話題の殆どは勇作のことに関してで、杉元にとってはこれっぽっちも面白い話しではないが、聞いていようといまいと関係なく尾形は気が済むまで「己を慕う可愛い弟」の話しをしていく。
その眉目秀麗、成績優秀、品行方正な弟は尾形の二歳下、つまり杉元と同い年でこの春に威風堂々とした赤門を有する大学に現役で合格をしたという。その話しを聞いた時、無性に往復ビンタを喰らわせたくなった。
口を開けば弟の話ししかしない様は他者から見れば度が過ぎたブラコンでしかないが、偶々聞いた学部生の話しによると尾形は授業外でも必要最低限の会話しかしない寡黙な男だと思われているらしい。要は尾形の本質は中学時代から変わってはおらず、自ずからコミュニケーションを取ろうとしている相手は極限られているということだ。
そこにまた杉元は愚かにも優越感を抱いてしまう。誰にも明かせない話しを自分だけにするのだと思えば稚い恋心はそれだけで疼いてしまい、聞きたくもない可愛い弟の話しを聞いてしまうのだ。
そして杉元は再び「悪夢」に魘される。
尾形を殺す夢だ。高校時代に飽きるほど見てきた尾形を殺す夢が再び繰り返されるようになった。だが、あの頃とは違って結末は実に胸糞が悪い。
以前の夢は様々な方法で尾形をただ殺すだけに終始していたが、今回は続きがあった。
尾形を殺した夢の中の杉元佐一は、死んだ尾形を前にしてひどく安らかな気持ちになるのだ。
――これでお前はもうどこにも行けなくなった。弟のところに帰る必要もない、否絶対に帰さない。最期に目にするのは俺の姿で、お前は俺のことを恨みながら死ねばいい。そうすればお前はきっと俺に憑りつく筈だ。憑りつかれたらこの先もずっと共にいられる。
息絶えた尾形の死体に覆いかぶさり、恋した男の血と臓物に塗れながら甘美な安穏に浸り……――そこで、目が覚める。
目が覚めた時、杉元はやはり本当に尾形を殺していないか確かめる。前後の記憶を探り、己の手が血に塗れていないか確認し、どこかに尾形の死体がないか家中を探し回る。そして自分がまだ尾形を殺していないことを改めて認識し……失望する。尾形を己のものにできていないことに。
失望してしまう自分が衝撃だった。百年前に不死身と呼ばれた杉元だって好んで人を殺していたわけではなく、今だって当然人殺しなんて以ての外だと思っている。だが、あの夏の夜に尾形が請うままに殺していれば、弟に奪われてはいなかったかもしれないと、何故殺してやれなかったのだろうかと……どうしてもそう考えてしまう。
ふっと視界の先でひらりと白いものが掠めていった。ぱちりと目を瞬かせると、黒い目玉が二つぎょろりと杉元を凝視している。
「な、に……?」
次いでぱちりぱちりと瞬きを繰り返し明瞭になった視界に捉えたのは、杉元の顔を覗き込む猫の目にも似た真っ黒な双眸と鼻先に近付いた尾形の白い指先。何でこんなに近くにあるのだろうとまた一つ深く瞬いた杉元に、テーブルの向かいに座っている尾形が訝し気に双眸を眇めた。
「寝てたのか?」
「寝てないよ。なんで?」
週に一度のロシア語の授業後、いつもの流れで昼食を取るため訪れたキャンパス内のカフェテリア。季節は六月に入り段々と蒸し暑くなってきていたが、屋内エリアは人で埋まりしょうがなく屋外エリアに席を確保し食事をした後、これまたいつもの流れで尾形の一方的なお喋りを聞いていた。……聞いてはいたが、内容は全く脳に響いていない。
何か尋ねられたりでもしただろうかと誤魔化すように笑みを浮かべると、尾形は双眸を眇めながら更に指先を杉元へと近付けた。
「顔色が悪い」
「そうか?」
目の下をついとなぞる白く冷たい指先からやんわりと逃れアイスコーヒーに手を伸ばそうとした時、視界が僅かにぶれた。掴み損ねたカップが倒れ、溶けかけていた氷がころころと音を立てながらテーブルを濡らす。幸い中身は殆ど残っていなかったが、テーブルから零れ落ちた雫がアスファルトに染みを作る。
「何やってんだ」
「わりぃ……」
杉元へと伸びていた尾形の指がカップを戻し、散らばった氷をその中に入れていく。
「何があったんだ?」
ナプキンでテーブルを拭きながら問われた声に、「別に」と答えようとしたが鋭い視線に見据えられお手上げするように溜め息を一つ。
「最近あまり眠れないだけだ」
あまりにも醜い自分の内面を映し出す夢を見たくなくて、眠るのが恐ろしくなった。だからここ暫くは自室のベッドに座ってすらいない。有り余った夜の時間は勉学に費やしたり、読書をしたり映画を見たりして潰している。それでもうとうとと微睡むことはあり、またあの夢を見て飛び起きる。
度重なる寝不足と気温の上昇に体力が奪われ、このままでは不味いとは思っているがうまく眠れない。
「帰った方がいいんじゃないか? 送ってやる」
「大丈夫だって。今はほら、飯も食ったばっかだしちょっとぼんやりしてただけだ」
「以前のお前に比べれば随分少なかったけどな」
尾形の指摘に杉元はやはり小さく笑うことで誤魔化した。寝不足が続き食欲も落ちてきている。見た目はまだそれほど変わっていないが、真夏ですら平気で乗り越えてきた体が、初夏の陽気にすでに参っている。
「今日は帰ったらすぐ寝るよ。じゃあ、俺先に行くな」
これ以上無駄に詮索されることを避けるため杉元はトレイを手にして立ち上がると、さっさとその場を後にした。しかし背中に強い視線を感じる。身も心もボロボロなのに尾形の注意を引けていることに仄暗い喜びを感じてしまう。このまま体調不良を偽っていればずっと尾形の関心を得られるだろうかとまた愚かなことを考えて、ひっそりと自嘲する。
そんなことを考えるからあんな禄でもない夢を見るのだ。恋をすると人は愚かになるとはよく言ったものだ。全く持ってその通りであまりの愚かさに自分で自分が嫌になる。
暫く尾形から距離をとった方がいいのかもしれない。あと一月ほどで夏休みにも入ることだし、ロシア語の授業の後も何かしら理由をつけて尾形とは極力顔を合わせないようにしよう。
そうでもしないと本当に尾形を殺してしまいそうだ。
「――んっ、あっ! あ、あ……っ…!」
「……っは……、は……」
ぐっと最奥を抉られて触れられてもいないペニスから勢いをなくした白濁がぽたぽたとシーツの上に零れ落ちた。それとほぼ同時に胎の中に注がれた熱い感触に胸が甘く締め付けられる。しかし、射精の余韻に浸る間もなく耳元に寄せられた唇から零れる言葉は深々と杉元の胸を突き刺した。
「はっ……あいして、る……ゆう、さくさん……」
どれだけ快楽に塗れ溺れてもその一言が杉元を深淵へと突き落とす。そして深淵から救い出す手はない。当然だ。この深淵には自ら飛び込んでいるのだから。
浅く短い呼吸を繰り返しながら尾形が身を起こせば、掲げられていた足と尾形の背へと縋っていた手が無造作にシーツへと落ちる。そして散々暴かれた杉元の後孔からはとろりと白濁が零れたが、その子種の主である男は後始末をすることもなく杉元の隣に倒れ込むようにして横たわった。
広く大きなベッドの上、ガタイのいい男が二人、精液を全身に散らしながら小さく息を乱し天井を仰ぐ姿は傍から見れば酷く滑稽に映るだろう。だが、尾形との事後なんてだいたいこんなものだ。恋人ではないのだから睦言を交わすこともなければ、甘い余韻に浸って体を寄せ合うこともない。もう少し落ち着いたらいつものように尾形が先にシャワーを浴びに行くだろうと思いながら、杉元はぼんやりと見慣れぬ天井を見上げる。
十月下旬になって鶴見が帰国をした。暫くは日本に滞在するつもりでいるらしく、尾形にそれを告げるとホテルに行かないかと提案された。予想外の提案に杉元が断れる筈もない。誘われるがままにラブホテルへと足を踏み入れ、一旦は途切れるかと思っていた体だけの付き合いがまだ続いている。
当初はホテルに行くまでのことでもないだろうと断った。何せホテルに行けば休憩だろうと金を取られるのだ。貧乏というわけでもないが裕福とも言えない杉元にその出費は少々痛い。そのことを告げると尾形は「俺が出す」と言ってきかなかった。
そもそも性欲処理だけが目的のセックスをする提案をしたのは杉元の方だ。ならば尾形だけに余計な出費をさせるのは何かが違うだろうと思うのだが、ホテル代がなければその金は酒を買うための金となり、尾形ご自慢の勇作さん話しに繋がるのならただの性欲処理とはいえ自分とのセックスに使われた方がいいだろうという結論に落ち着いた。どちらにしても良い使い道だとはいえないが。
胸を突き破るかのように激しく脈打っていた心臓も落ち着き始め杉元が深く息を吐き出すと、隣からも同じタイミングで深く息を吐く音が聞こえた。「はぁー……」と、まるで温泉に浸かったオヤジのような吐息が重なったのがおかしくて小さく笑うと、尾形もまた小さく笑った気配。
ふと中学時代を思い出す。昔から尾形はあまり笑ったりはしなかったし、時折笑ってもそれは心底呆れ馬鹿にした笑い方だった。けれど、何でもないふとした言動に目を細め口元を小さく綻ばせて笑うことがある。今から思うとその笑い方に好意を持ち始めたのかもしれない。――何せ百年前は見たことがない、今生になって初めて目にした表情だったから。
虚しさも一転、擽ったい嬉しさにころりと体を転がして尾形の方へと向くと、また同じタイミングで尾形も杉元へと体を向けた。
僅かに身じろげばすぐにでも肌が触れ合いそうな距離。けれど、どちらかが意思を持って近付こうとしなければ触れ合えない距離。杉元にしてみればそれは近付くことを恐れている距離でもあり、尾形に近付いて欲しいと願う距離でもある。
だが、それ以上は近付かない。これだけ近いところにいるのに触れ合えない距離、それが今の杉元と尾形の距離だ。
尾形の真っ黒な双眸がすぐそこにある。もう時間がないからさっさとシャワーを浴びろと、いつもは声にしている言葉がなかなか口から出ていかない。
ただ互いの顔を見合っているだけの無為な時が、不意に止まる。
「この傷、どうしてできたんだ? 山でって言ってたよな」
近付くことはないと思っていた距離の間に尾形の指先が眼前に迫った。目潰しかと反射的にきゅっと瞼を閉じてみても、身構えていた衝撃は襲ってくることもなく、右頬から鼻を辿り左頬へとなぞっていく。
中学に入学したばかりの頃、交わした会話を思い出す。たいして話しが盛り上がったわけでもなく、呆気なく終わった会話だったが尾形が覚えていたとは驚きだ。
「ガキの頃に山菜をとりに山に入ってさ、はしゃいで滑って転んで崖から落ちて、気付いたら顔面血塗れだ」
「なんだそりゃ、死んでないのが奇跡だな。痛かったか?」
「当たり前だろ。痛いわ寒いわ怖いわで死ぬかと思った」
「へぇ……、お前が?」
「俺を何だと思ってるんだよ……」
不死身のくせに? ――そう続きそうな尾形の言葉に思わず視線を逸らす。そういえば、いつからか尾形に前世の記憶が蘇ることを恐れなくなった。もしかしたら尾形とは既に一つの関係を確立できたせいかもしれないと思う。なるようになると割り切っていたのもあるが、ここまできてしまったら尾形が記憶を得たところで大きな変化が起こるとも考え難い。今尾形に記憶が蘇ったら更に泥沼へと発展しそうな気配はあるが。
「泣いたか?」
「助けにきてくれた親父とお袋の顔を見た瞬間にわんわん泣いたよ。泣いたら傷が広がって、涙も沁みて痛くてさ、また泣いた」
「俺はお前が泣いたところを見たことがない」
「この年でそうそう泣くかっての。てか、見たいのかよ」
「見たい」
傷に触れる指先の冷たい感触に、ふと目の奥に熱を感じた。泣くことはないと言った傍から涙が溢れてしまいそうになる。――尾形が「杉元佐一」を知ろうとしているから。
「どんなに激しくしたってお前は泣かねぇだろ」
「な、んだよ、それ……」
さりさりと他の肌とは感触の違う傷跡を辿る優しい指先。上擦り掛けた声を誤魔化すようにシーツの上に投げ出された尾形の脛を蹴る。「いえてぇな」と文句を口にしつつ尾形の指は杉元の傷跡から離れていかない。劣情が滲んでいない触れ合いは久し振りでただひたすらに面映ゆく、杉元もそろりと尾形の頬に薄く残る縫合痕へと指を這わせた。
「お前のこれは?」
「お前みたいな愉快な話しじゃねえぞ」
「俺の話しだって愉快じゃねぇだろ」
尾形は躊躇いがちにしばし宙へと視線を彷徨わせる。恐らくこの傷は尾形が決して語ろうとしない幼少期にできたものだ。出来ることなら蓋をしておきたい過去かもしれない。けれど知りたいと思ってしまった。そこにあるのは単純に尾形百之助を知りたいという欲深さだけしかない。尾形に語るつもりがないならこれ以上の詮索はしないつもりでいる。けれど、やがて杉元と再び顔を合わせた尾形は小さく息を吸うと、口を開いた。
「母親の男に殴られたんだよ。今でも何で殴られたのか分からんし、理由はなかったのかもしれん。そもそもあの男には俺が人間だって認識がなかったのかもしれん、顎が割れてたにも関わらずそのまま暫く放置されてたんだからな」
ある程度の予想はしていたが、実際に話しを聞くと胸糞の悪さは予想以上だった。放置をされていた間、お前の母親は何をしていたのかなんてとても聞けるような話しじゃない。
「殴られてからどれだけ時間が経ったのか分からんが、後から別の男が来てそいつが俺を闇医者に運んだんだ。ヤクザ崩れのどうしようもない男だったが医者に連れて行ったくらいだ、俺の母親よりまともだったな」
尾形の頬に触れる杉元の指先がひくりと微かに震えたことに気付いたのだろう、尾形はふっと口元だけを緩め曖昧な笑みを浮かべると杉元の手に己のそれを重ねた。尾形の低い体温と杉元の熱がじわりと溶けあう。
「勇作さんは、この傷を見て可哀相だと嘆くんだ。お前は何を思った?」
二人きりの空間を引っ掻き回すかのような問い掛けに杉元はゆっくりと一つ瞬きをした。「勇作さん」の話題を出せば杉元の心が乱れることに尾形はとっくに気付いていて、だからこうしてわざとらしくその名をあげる。その言動にどんな意味があるのか分からないが、親の興味を引こうとする子供みたいだと時々思う。
「正直に言えばムカつく……かな。この傷は俺が付けてやりたかった」
「なんだそれ……、お前やっぱり頭がおかしいんじゃないのか?」
眉を顰める尾形に軽く笑い返して、百年前に比べて目立たなくなった縫合痕をするりと撫でる。「あの時」だって意図して傷を付けたわけじゃない。だが百年前の尾形についていたあの傷は、杉元佐一が殺しきれなかった証でもあったなと思う。それを今生では見知らぬ男に意味もなく付けられたのかと思うと腹が立つのは、一種の独占欲でもあるのだろう。
尾形がその時、どれだけ辛い目に遭ったか想像はできるのに、結局そんな矮小な独占欲を覚える己がどうしようもないと思う。どうしようもないが、止められもしない。
しかし、一度は眉を顰めてみせたが、尾形はにやりと笑いながら再び杉元に覆い被さってきた。するりと意図を示すように太腿に擦り付けられた尾形の下肢の感触に、杉元はぱちぱちと目を瞬かせる。
「なに? もう一回すんの?」
「ああ、すげぇ興奮した。延長戦だ、杉元。嫌なら俺の顎を割るくらい抵抗してみせろよ」
「……そうするよ」
お前も相当な特殊性癖持ちだぞ……とは口にせず、呆れた溜め息だけを吐き出せばそれすら尾形を煽ってしまったらしい。嬉々として勃起したペニスをぬかるんだ後孔に擦り付けてくる様に杉元は目を閉じて静かに挿入に備えた。
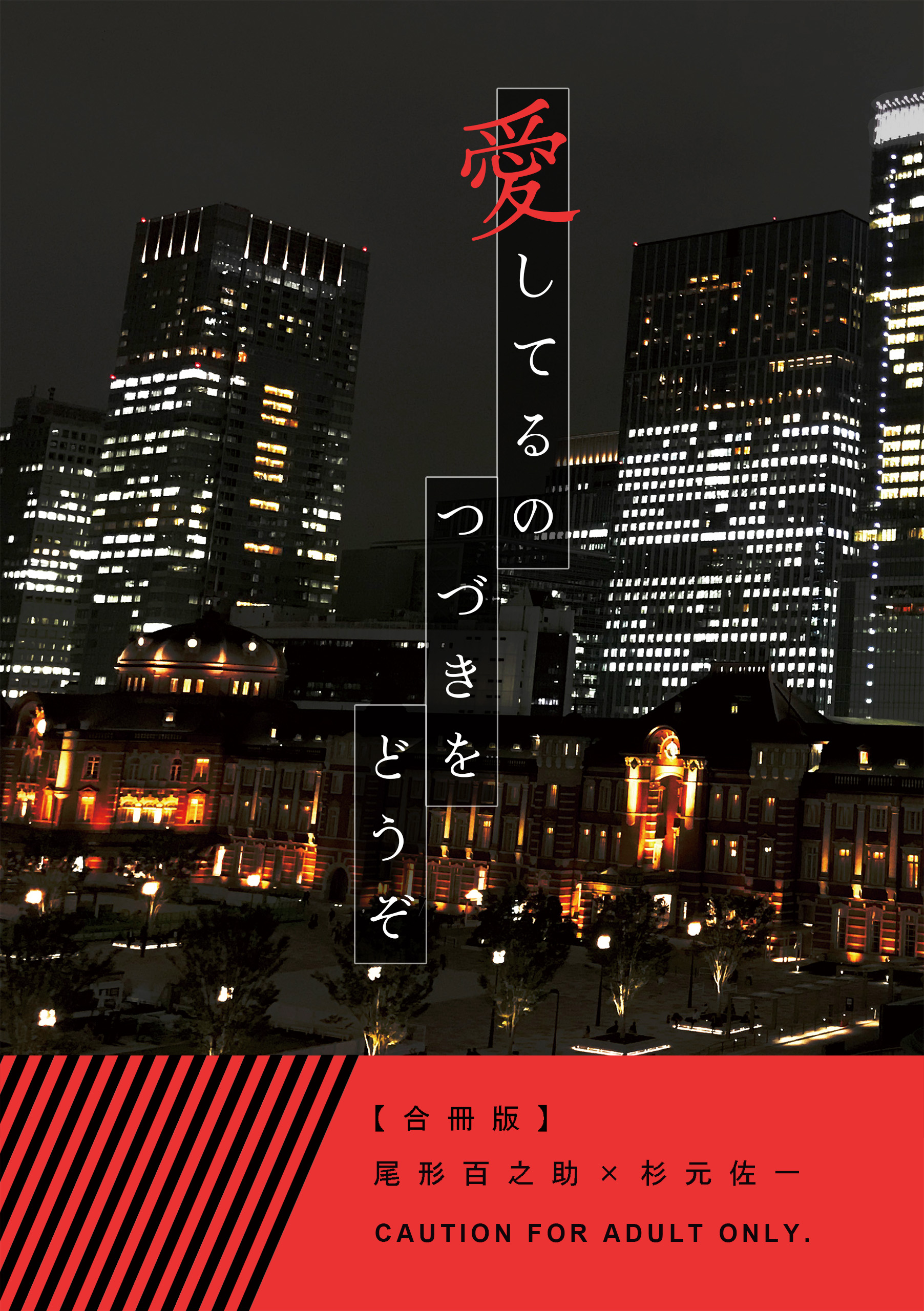
 yukioji_3
Link
Message
Mute
yukioji_3
Link
Message
Mute
 ステキと思ったらハートを送ろう!ログイン不要です。ログインするとハートをカスタマイズできます。
ステキと思ったらハートを送ろう!ログイン不要です。ログインするとハートをカスタマイズできます。
