漆月拾玖日壱
今でもはっきり覚えている、幼少時の記憶がある。
当時からうちは母子家庭だった。
母さんは自営業で比較的時間の融通が利くから、僕はその頃から家にいることが多かったけれど、それでもやはり忙しい時はあったようで、一時的に託児所へ預けられることも度々あった。
僕は別段、寂しさや怒りを感じることもなかった。幼心にもその行動の意味は理解していたつもりだったから。
託児所の先生からは、物分かりの良い子だと評価されていたらしい。
とはいえ、1日以上離れなければならないともなれば、話は違ってくる。
普段利用していた託児所では日を跨いでの対応はしていなかったし、だからと言って未就学児をひとり家に置いていくわけにもいかない。
母さんは気丈な女性で、できる限りのことは自分で解決するような人だけど、どうしてもという時に人に頼ることもまた上手な人だ。
そんなわけで、やむを得ない事情により、僕は数日間、伯父さんの家にお世話になることになった。
伯父さんの家は代々、とある町の寺の住職を勤めていて、そこには数珠丸という名の、僕より年上のひとり息子がいる。
初対面だったけど、僕たちはその日にすぐに打ち解けた。
何か通じるものがあったんだろう、と今なら思う。
僕もひとりっ子だし、彼もまた落ち着きのある人だ。
これは今でもそうなんだけど、僕は自然と彼のことを「数珠丸にいさん」と呼ぶようになっていた。
そして、あの時の僕にはもうひとつ、大きな出会いがあった。
日にちもはっきり覚えている。
7月19日。伯父さんの家に滞在して3日目のことだった。
近所の神社でお祭りがあるというので、数珠丸にいさんに連れられてやって来たはいいけれど、その会場で彼とはぐれてしまった。
町や神社の規模から考えると意外なほど大きなお祭りらしく、参道や境内の屋台の並ぶ付近にはそれなりに人混みができていた。というのもある。
だが、決定打は間違いなく別のものだった。
歩く途中でいくつか見かけた、灰色の砂のような、靄のようなもの。
何となくでもあの時の僕には分かっていた。
あれは多分、普通には“見えない”ものだと。
僕はいわゆる、生まれつき“見えた”り“聞こえた”りする人間だ。
幸い、母さんはその方向にある程度は理解がある人だった。
まあ、近しい親戚に住職がいるくらいだし、その手の話は多少なりとも聞いていたのかもしれない(物心付く前から、何もないはずの空に向かって、何かを目で追うように見つめていたことがある…というのは、更に後になって母さんから聞いた話だ)
ただ、それと同時に現実的な人でもあったから、理解のない人に知られたら不利益を被るかもしれないことを教えてくれたし、僕もその教えをすんなりと受け入れて、他の人に安易に打ち明けることはしなかった。
でも、伯父さんの家に来た僕は新たな発見をしたんだ。
同じような人は案外身近にいる、ということを。
実は数珠丸にいさんも、そういったものを認識できる感覚の持ち主らしい。
僕ほどはっきり、というわけではなく、気配が感じ取れるくらいだそうだけど。
だいぶ年が離れているにもかかわらず、僕たちが互いに親近感を覚えたのは、ひとりっ子同士というだけじゃ決してなかったのだろう。
閑話休題。
だから、僕は多くの人には見えない色々をしばしば目撃していたけど、“それ”は今まで見たことがなくて、純粋な興味からしばらく立ち止まって眺めていたんだ。
カーブミラーの下にある、蹲ったような灰色の陰を。
そしたら、いつの間にか数珠丸にいさんの姿が見えなくなっていた。
幼い子供にとって、馴染みの薄い土地での迷子というのはさぞかし心細いものだろう。
でも、肝心の当時の僕はさほど慌てても、怖さを感じてもいなかった。
もし迷子になったらあまり無闇に動かない方がいい、と母さんも言っていたことがあるし、いざとなれば歩いて帰れると思っていたからだ。
母さんの忠告通りその場に留まって、自分なりに考えた結果、誰か神社に関わる人に助けてもらおうという結論に至った。
お寺に伯父さんや数珠丸にいさん以外にも人がいたことを思い出して、きっと神社にも人がいるに違いない、と幼いながらに判断してのことだった。
お寺でも、大体の場合、人がいるのは建物の方だとはぼんやりと理解していた。
境内を進んでいく間も、不思議と不安は無く、むしろ心地良さすら感じていたのが今でも不思議だ。
清浄な空気とは、きっとああいうのを言うんだろう。
僕が拝殿らしき建物に辿り着いた時には、まるで狙ったかのように人がいなかった。
――ただひとりを除いては。
「おや。幼子がこんなところにひとりとは、珍しいね」
近付いてきたのは、聞くものを無条件に安堵させるような、柔和な声だった。
この人なら大丈夫だ、と僕に直感的に思わせてしまうほどに。
「…はぐれてしまったんだ。にいさんといっしょにきていたんだけど」
事情を話すと、その人は僕の目線に合わせるようにしゃがみ、小さく首を傾げた。
切り揃えられているかと思えばちょっと違う前髪が、はらりと動いた。
「その割には落ち着いているね。君くらいの子で、迷子になってここまで落ち着きのある子は珍しいよ」
「それ、ほかのひとにもいわれたことあるけど。そんなにめずらしい?」
事実だったし、偽りのない本音だった。
「ふむ、私の感じた印象も間違ってはいないわけだ。将来有望だねえ」
何を考えていたかは分からなかったけど、彼はうんうんとひとり頷いて、じっと僕の目を見据えてきた。
お日様が昇る少し前の、きれいな空の色をしているな。と思った。
「お兄さんが探している可能性を考えると、しばらくは社務所か、本殿の近くで待っていた方がいいかもしれないね。お兄さんはどんな人なのかな?」
いくら知っている人でも、どんな人か、と聞かれてとっさに的確に説明するのは難しいものだ。
けれど、僕が数珠丸にいさんの姿を思い浮かべ、特徴を言葉に変換するまでの間も、彼の瞳が僕から逸らされることはなかった。
「かみがとてもながくて――めがぱっちりあいてないひと。じゅずまるっていうなまえなんだ」
「じゅずまる?…ああ、ひょっとしてあのお寺の数珠丸さんかい?」
「しってるの?」
「あそこには昔から、色々とお世話になっているからね。君はもしかしてあのお寺の子なのかな?」
同じ町の神社と寺であれば、つながりがあっても何らおかしくはないだろう。
ただ、あの頃の僕はそのことを知らなかったから、素直にびっくりした。
「ぼくはおてらのこじゃないよ。でもちょっとだけいるんだ」
そのせいもあって、その時の自分の状況を、あまり上手くは説明できなかった。
だから、どう受け取られたのかは分からない。
彼はただ静かに「なるほど」と返しただけだった。
「数珠丸さんのことは私も知っているから、見つけられればすぐに分かるよ。もし見つからなかったとしても、お寺まで送り届けて差し上げよう。だから、安心してここにいなさい」
この時、僕は初めて知った。
こういう事態の時に出会った初対面の人が、自分に近しい人と知り合いであると知ると、安心感が段違いなのだと。
「うん」
僕の返事を聞いてから立ち上がった彼だったが、あっ、と何かを思い出したような顔をして、慌ててもう一度中腰になった。
「すまない、申し遅れたね。私は石切丸という。よければ君の名前も教えてくれないかな」
「あおえだよ」
「あおえくん、か。良い名前だね」
いしきりまる。ちょっと変な名前だなと思った。――まあ、僕の名前も大概だとは思うけれど。
ただ、変わった名前だったからこそ、すぐに覚えられて印象に残った、というのもある。
「いしきりまるさん、ありがとう」
一礼と共に感謝の念を述べると、彼はいっそう笑みを深めた。
「どういたしまして。いくら大人びているとはいえ、迷子を放っておくわけにはいかないからね」
彼はその見た目や声からの印象に違わず、ゆったりと話をしてくれた。
例えば、神社とは神様を祀る場所であるということ。日本にはたくさんの神様がいるということ。
中には当時の僕には難しくて理解できない内容もあったけれど、彼の話をただ聞いているだけで心が落ち着いた。
「いしきりまるさんはいろんなことをしってるね」
「私はこの神社の関係者だからね。これでも、この辺りのことには詳しいつもりだよ」
突然、彼の双眸が細められる。
にこにこしていたはずの彼が、少しだけ怖いと感じた。
そして、次の瞬間、僕は確信した。その直感は正しかったのだ、ということを。
「――“ああ”いうものにも、ね」
数珠丸にいさんがするような、丁寧な指し示し方だった。
「君には、“彼ら”が見えているんだね」
トーンこそ変わらなかったものの、ほとんど断定していると言っていい口調だった。
確かにこの時の僕は、彼の話を聞いている間も、不自然に思われない程度にちらちらと“あれ”を見ていた。
優雅に揃えられた彼の指の先、白く大ぶりな花の根元にあるもの。
数珠丸にいさんとはぐれる直前に見かけたものは、もう少し小ぶりだった気がする。
しかし、彼がそれに気付いているということは。
「…いしきりまるさんにも、みえるの?」
彼は躊躇なく「見えるよ」と肯定した。
「見えるだけではなく、音も聞こえるね」
「じゃあ、あれのおとも?」
根拠はなかったけれど、僕には“あれ”が発しているものだとなぜか分かっていた。
やや離れた場所から聞こえる楽音に合わせるかのような“あれ”の音が、耳に届いてきていた。
「ああ、かすかに音がしているね。何と言うか――言葉にならない、囁き声のような音だ。歌っているようでもある」
言われてみれば、確かにそんな音だった。
やはり彼には“見えて”いるし、“聞こえて”もいるらしい。
「“あれ”は、いつもいるの?」
そのことを理解した瞬間、僕の口はますます軽くなってしまった。
そんな人に――自分と同じくらい感じ取れる人に、会ったのは初めてだったからだ。
「いつもはそうでもないのだけれどね。今日はお祭りの日だから、いつもより多いんだよ」
「おまつりのひにはおおい?」
「祭りというのはね、こちらの世と、あちらの世の境が曖昧になる時なんだ。だから、君や私には見えるああいうものたちが、私たちの近くにやって来やすくなるし、私たちもあちらへ行きやすくなるんだよ。時々、それに巻き込まれてしまう人がいたりもするのだけれど――」
彼は僕の方へ視線を戻し、目を閉じたが、1秒と経たないうちに瞼を上げた。
「君はどうやら、霊力も普通の子より強いようだね」
「れいりょく?」
初めて聞く言葉だった。
今なら何となく言葉としての意味は知っているけれど、それでもよく分からない。
ましてその時は、本当に謎の言葉だった。
僕が頭に疑問符を浮かべているのを察したのか、彼は殊更温和な口調で話してくれた。
「人と同じように、君が見たり聞いたりしているものの中にも、人に悪いことをするようなものがいる。それは知っているかな」
「うん。じゅずまるにいさんからきいたことがあるよ」
「君はそうしたものから、悪さをされにくい体質なんだよ」
「わるさをされにくい?」
「だから、明らかに悪いものは、そう易々と君には近寄れないだろうけれど――そうでないものほど、気を付けた方がいいかもしれないね。自分のことを分かってくれるというだけで、君と仲良くなろうとするものは多いだろうから」
「それって、だめなこと?」
純粋な疑問だった。
あの頃から、僕にとってはとても身近な存在だったから。
「…え?」
僕の質問に驚いた様子を見せた彼に、この人も驚くことがあるんだなあ、と妙な納得をしたのを覚えている。
「なかよくするのは、だめなことなの?」
もう一度尋ねると、彼の目がぱちぱちと瞬き、少しだけ考える素振りを見せた。
でもすぐさま、緩やかに、しかし明確に首を振った。
「いや、駄目なことではないよ。むしろ良い心がけだ。けれど、“彼ら”が良かれと思ってやったことが、君にとっても良いこととは限らないからね」
日が落ちきってしまう直前の、暗い赤と青の混じる空が彼の顔に陰を作っていて、その声も、心なしか深みが増したように聞こえた。
「先ほども言ったように、この時期は私たちもあちらへ近付きやすくなる。特に気を付けなければいけないよ」
本当に気を付けなければ、と頭に過ったのは、もはや本能的な理解と言ってもよかったのかもしれない。
わかったよ、と僕が返答する前に、彼は自らの懐を探り、何かを取り出した。
「これを持っておくといい」
その指から下がっていたのは、当時の僕が知ったばかりのものだった。
「おまもり?」
「私がそばにいればお祓いや祈祷などで何とかして差し上げられるのだけれど…そういうわけにもいかないからね」
確かに、そばにいてくれたらきっと心強いだろうな、とは思った。
でも、幸か不幸か、それが今は叶わないであろうことを察するくらいには、僕はすでに分別がついていた。
「もし何か怖いことがあっても、これがあれば大丈夫だよ」
手を出してごらん、と言われるままに開いた手の平に、お守りがそっと乗せられた。
僕がお寺で見たものよりは小さかったけれど、白地に金糸が細かく編み合わされているのが美しかった。
「ありがとう。だいじにするよ」
お守りの触れたところがあたたかい、とすら感じた。
あの後、数珠丸にいさんとは無事に合流できた。
それから石切丸さん(漢字でどう書くのかは随分後で知った)は、「いっしょにいこうよ」という僕のお誘いと数珠丸にいさんの説得により、僕たちと一緒になったんだ。
お祭りの中での行動でね。あまり長い時間ではなかったけれど。
数珠丸にいさんよりも背の高い彼と並んで、時々彼とまた話をして。
少しの間だけ、手を引かれたりもした。
その時に、確かに感じたんだ。
ぼく、このひとがすきだなあ。――って。
ちなみに、お守りのことは、実は数珠丸にいさんにも話していない。
何となく、本当に何となくだけど、誰にも話してはいけない気がしたから。
まあ、彼のことだから、何となく察している気もするんだけどね。
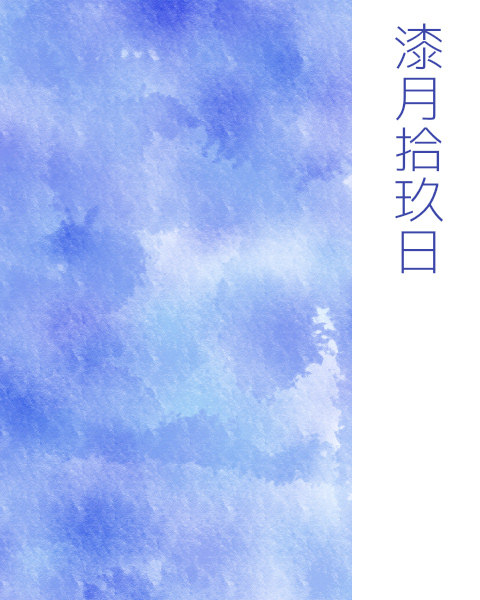
 音華
Link
Message
Mute
音華
Link
Message
Mute
