窓際二名特別コースNG食材はセロリ「……はい、人間と吸血鬼一名ずつです。えっと、人間の食べ物はほぼ食べなくて、乳製品とか血液食品なら多少、けっこう少食なんでくどいのはあんまり……はい、好みはB型です。あっ、酒ですか?けっこう強いです、吸血鬼用のもそれなりに飲む方です。NGはセロリで。はい、はい……では、よっよろしくお願いします!」
「なぁ、来週の日曜飯いらねぇから」
やたらと思い詰めた表情でそう告げるロナルドにドラルクは首を傾げた。友達をバーベキューに誘うのに「明日」と平気で言い放つ男が三日以上先の予定を言うとは珍しい。
「やっとアポの概念を覚えたかシンヨコ原人。まぁその日ならジョンもお出かけだし、どれ、たまには一人で美味い血でも飲みに」
「いいや、テメーには俺と一緒に来て美味い飯を食ってもらうぜ……」
「グルメな立てこもり犯か?話がさっぱり見えんのだが」
目の前にスマホを無言でぐっと突き出され、近い近いと押し退けながら画面を確認する。映っているのはレストランと思しき差出人名のメールに窓際席二名様ご予約の文字。顔をこわばらせたロナルドが地底を這うような声で曰く、
「俺と、や、夜景ディナーデート、しやがれください……!」
「ファーーーー!本当にやりよった!!君が?一夜の夜景とかを?っふふ、ロマンチック案内してくれるのかね?」
ドラルクの脳裏にまず浮かんだのはいつぞやの退治で敵性吸血鬼にワヤワヤの夜景デートを申し込むロナルドの姿だった。本人は芝居だからぎこちなかったのだと言い張っていたが、実際のデートでも結局同じことらしい。
「なんだよ!今日のは何もおかしなこと言ってないだろうが!言ってないよな!?」
「いや、あまりにもベタだったもんだからつい……しかし言っとくが私は夜景とディナーでメロメロ!ロナルド君素敵!ってなタイプじゃないぞ」
二人はやぶさかでない仲になってそれなりに経つが、いわゆる交際イベント的ことをこれまでしてこなかった。企画下手のロナルドは言うまでもなく、ドラルクから提案したこともない。ドラルクとしてはこれまで通りの生活に多少甘いやりとりが混ざる程度で丁度よかったのだ。
そうした状況からロナルドなりの「恋人らしさ」に踏み出そうとした結果なのだろうが、あまりにも唐突かつテンプレ的だし、ときめきよりはくすぐったさが勝って恋人モードに入れる気がしなかった。
「うるせぇんなこと百も承知だわ!いいだろベタでも、俺はただ、お前と楽しい、ロマンチック……うぅ、嫌なら来なくていいよチクショウ……」
「ほらすぐそうやってイジける!嫌とは言っとらんだろうが。いいよ、君の期待に沿うリアクションができるかは分からんが、たまにはこんなのも楽しかろう」
「余裕ぶってられんのも今のうちだぜクソ砂、当日俺のエスコートに驚いて腰抜かすなよ!」
「さっきからなんで決闘みたいなテンションなの?」
日曜を待たずして既にテンパり気味のロナルドに呆れつつ、まぁいいお手並拝見といこうか、と吸血鬼はほくそ笑んだ。
果たして日曜日、二人はヴリンスホテルのエレベーターに乗っていた。ジャケットスタイルにネクタイを締めたロナルドは窓ガラスで前髪をチェックしながら口を尖らせる。
「俺だけおしゃれしてお前はいつも通りかよ……」
「ファーー!?貴様がネクタイをタコ結びにしたからアニマルレスキューしてやってたんだろうが!あの時間がなければ私も服選べたわ!これでドレスコードに引っかかるわけないんだから良いんだよ!」
足を踏み入れたレストラン内はやや暗く、シンプルなモノトーンでまとめられたインテリアは装飾も少なくモダンな印象だ。この雰囲気ならロナルドもなんとか入れるだろう。
「いつの間にこんな店ができてたんだねぇ」
「最近オープンしたんだってよ。人間用のメニューと吸血鬼用のメニューを時間帯関係なく提供してるらしいぜ」
予約を告げて席に着くと、間もなくテーブルを担当するギャルソンが現れた。
「本日はお越しくださりありがとうございます。テーブル担当させていただきます藻部山と申します」
「ロ、ロナルドと申します……?退治人やってます」
お見合いめいたロナルドのリアクションにドラルクは吹き出しかけた。必死に口の内側を噛んで澄ました顔を取り繕う。今日はなかなか楽しくなりそうだ。ロナルドがお前自己紹介しないのかよみたいな顔で見ているが、本人のためにもここは一旦スルーである。
ギャルソンはご丁寧にありがとうございますとにこやかに頭を下げ、二人にワインリストを広げて見せた。
「食前酒はいかがなさいますか?」
「えっ、あっ……」
答えに窮してロナルドが固まる。よく考えたらドラルクのためのメニューのことで頭がいっぱいで自分がどうするか全く想定してきていなかった。ワインの区別はつかないし、適当に頼んでうっかり潰れるのも怖い。下戸だと伝えても馬鹿にされないだろうか。静かに混乱する若者をよそに、ドラルクは注文を早々と決める。
「私はこれで。あと彼にはそうだな……ミモザをお願いします」
「みもざ」
「当店のミモザはシャンパンだけでなくオレンジジュースもこだわって選んでおります。おすすめですよ」
状況を察したらしい藻部山がおすすめの体でさりげなく解説に回る。とりあえずミモザがカクテルであることは理解し、ロナルドはぎこちなく頷いた。
「じゃあ、俺はそれでお願いします……」
ほどなくして二人の前に食前酒のグラスが運ばれた。ギャルソンが席から離れるのを見送ってロナルドがどっと大きなため息をつく。
「つっかれた……」
「まだ席に着いただけだろうに、前菜も出ないうちからそれでどうする。さ、とりあえず乾杯でもしようか」
「何に乾杯すんだよ」
「なんだっていいよ。じゃゴリラに乾杯」
「ふざけんな」
「はいはい互いの健康を祈って」
「お前の口から健康って変な感じするわ、乾杯」
二人でグラスを掲げ、それぞれに口をつける。ロナルドは飲み慣れないシャンパンに怯んだものの、慣れたオレンジの甘さが口に広がり少しほっとした。
「飲めそうかね?キツかったら無理に飲み干すなよ」
「ん、甘いしたぶん平気」
「ならよかった、勝手に頼んじゃったから」
炭酸水頼んでも良かったんだけど最初の一杯は付き合ってもらってもいいかなって、そう続けながらドラルクは慣れた様子ですいすいグラスの中身を減らしていく。
「飯食わない割にこういうの慣れてんのな」
「まぁ外食しなくても時代柄マナーはうるさく教えられたから……あ、そうだロナルド君。さっきギャルソンさんが名前教えてくれた時だけど、あれ客は名乗らなくていいんだぞ」
「そうなの!?うわはっず……先に言えよそういうのは」
「だってそんな注意が必要だなんて想像もしなかったもん。ロナルド君は元気にご挨拶できて偉いでしゅね〜」
「ングゥゥ………!」
年上の恋人を見返すつもりが早速子供扱いされ、ロナルドはぐぅの音も出ない。いつもなら殺しているところだが、食事の席で砂を撒き散らすのは気が引ける。
色とりどりの前菜にパンの籠が並び、テーブルの上が一気に華やぐ。食欲をそそる香りを放ち、いますぐにでも手をつけたくなるような料理を前にしてしてロナルドはフリーズしていた。
「これどれから使えばいいんだ……?」
呆然とした目線の先にずらりと並ぶのは眩く輝くカトラリー。シルバーとも呼ぶがここは吸血鬼対応の店なので間違いなくピューター製だろう。ロナルドの脳裏に以前ドラルクから聞かされた講釈がよぎるが今必要な情報はそれではない。
「えっ君下調べとかしないで来ちゃったの?」
「だって、古風な吸血鬼にもオススメだけどカジュアルで良い店ですってネットに書いてあったんだよ! 内装も今っぽかったし大丈夫かなって思ってぇ……」
あぁ、と呟いてドラルクはちらりと店内を見渡す。たしかにノータイの客も多く、若いカップルも見受けられるので嘘が書いてあったわけでもなさそうである。ただ、ロナルドが想定するカジュアルとはずいぶん違うかもしれない。いい店に慣れた美食家の何気ない書き込みが不幸な若者を傷つけたというところか。
「まぁここをカジュアルと呼ぶ世界もあるってことだ。いい勉強になっ……」
「なにこれとりあえずちっちゃいナイフで切ればいいの?」
「おい待てそれはバターナイフだ!っていうかうちにもあるだろうがよく見んか」
「ウェーン場所が変わると別人に見える!」
「街で私服のクラスメイトとばったり会ったみたいに言うんじゃない」
ロナルドはカトラリーの上でわやわやと両手を彷徨わせ、使うナイフを決めあぐねる。ふと、右端に置かれた大きなスプーンに気づいて顔を輝かせた。
「なぁこれ、デザートにすげーデカいアイスかプリンが出るんじゃね?うわー楽しみ……」
瞬間、それまでニヤニヤと静観していたドラルクがとうとう堪えきれずに肩を震わせだした。
「ヒィッ、あ、あんまり笑わせないでくれ、外なんだから、ウッフフフフ」
いつもなら舌を出し指差して盛大にからかうところだろうが、今は辺りを憚ってか口元を抑えてくっくっと笑っている。普段あまり見ない表情と仕草にロナルドはうっかりときめきかけたが、何を間違えたのかもわからないまま笑われて眉間に皺を寄せる。
「てっめぇなぁ……!人が困ってんの見てそんなに楽しいか?」
「今さらそれを聞くかね?心底愉快に決まってるだろう。いやぁ酒が美味い」
「俺の醜態を肴に飲むんじゃねぇ!」
いつもの調子でパンチを繰り出そうとしたところでここがどこかを思い出し、慌てて拳を引っ込めた。反撃の手段を封じられた今日のロナルドはやられっぱなしである。そもそも状況が不利すぎるのだ。やたらと多いナイフとフォークの使い方はわからないし、恋人は今日も元気に性格が悪い。アウェーでひとりぼっちのロナルドは完全に拗ねた。とりあえずカトラリーのいらないパンに手を伸ばす。
「ちくしょう、もう俺の味方はこいつだけだ……!えっ何これうま!なんも入ってないパンなのめっちゃ味がする」
いじけた次の瞬間に焼きたてパンの虜となったロナルドはあっという間にカゴを空にした。すぐさま差し入れられたふた籠目もうまうまと平らげかけたところで、細い指先が嗜めるようにロナルドの手の甲をちょいとつつく。
「こら、そんなにパンばっかり食べるんじゃない。まだ後があるんだぞ」
「しょーがねーだろ他のやつ食い方わかんねぇんだから」
ドラルクは不貞腐れるロナルドを見ておかしそうに笑ったあと、静かに一言呟いた。
「……外側から」
「え?」
「私はかの女王陛下ほど優しくないからね、一緒に間違えてはやらん。でも正しいマナーくらいは教えてやろう。別に難しいことはない、ナイフとフォークは外側からセットで使うだけだ」
大丈夫、君の銃の手入れよりずっと簡単だよ。そう言うドラルクの声は、ジョンの料理を手伝ってやる時のような優しさを含んでいた。
「ドラ公……!」
「あとそのスプーンはスープ用だからデザートまで持ち越さんでよろしい。食後に大きなプリンが、ッフフ、出るといいね」
「やっぱりテメーはそういう奴だわ店出たら覚えてろよ!……なぁ、これで合ってるか?」
ぎこちない手つきで料理を切り分けながら上目遣いにドラルクの顔を伺う。
「大丈夫大丈夫。よっぽどうるさかったり汚かったりしなければ多少は大目に見てもらえるよ」
「うぅ、周りの目がこわい……」
「自意識過剰だ、気になるなら私と皿だけ見ていたまえ」
叱られたと思ったのか、ロナルドはなおもうつむき加減のまま黙り込んでしまう。ドラルクはしばしもの言いたげに視線を彷徨わせると、そうじゃなくてと口を開いた。
「……デートなんだろう? 目移りするんじゃない」
そう言うなりグラスを煽り顔を隠してしまった恋人を見て、ロナルドは目をぱちぱちと瞬かせた。青い瞳が一段明るくなったあと、柔らかく細められる。
「そう、だったな。うん、デートだもんな……えへへへへ」
「せっかくだから楽しまないと。お味はいかがか?」
「なんか難しい味がする。うまいことだけはわかる」
「ンッフフ、よかったね」
一口二口と料理を食べ進めるにつれ、ロナルドは会話を楽しむ余裕を取り戻し始めた。この肉うまい、ここにマナー違反連れてきたら違反するマナーが多すぎて逆に大変そう、窓から事務所が見えるかと思ったけど、今日は電気を消してきたから夜景の中にはないだろうな。そんな他愛もない話をするうちにコースは進み、同時にドラルクの前にも次々と血液やワインのグラスが並ぶ。メインに差し掛かる頃には、若者の手はすっかり滑らかに動くようになっていた。
「そうだ、そっちのメニューカード見せて」
それがテーブルにずっと置いてあった呪文の書かれた紙のことだとロナルドが思い至る前に、細い指先は紙片を攫ってしまった。目を往復させては何やら思案げに呟いている。
「ベースはフレンチだけどけっこう創作っぽいんだな……メインのソースなんだろう、ねぇそれどんな味がする?」
「なんか酸っぱい」
「役立たずめ。フルーツの香りはしますか?甘味はありますか?コクを感じますか?もろみっぽさはある?」
「いきなりアキネーターになんな、モロ美って誰だよ」
「君それ本気で言ってるのか?あとで半田君に教えてあげよう」
「やめろテメェ、デート中にヤツの名前を出すな。つーかもしかしてこれ作るつもりなの?」
「さすがにいきなり一流のプロの真似はできないけどね。ただ、君の好みなら参考にしようかなって。ジョンも喜ぶだろうしさ」
それは嬉しいけど、と口籠りながら、ロナルドは控え目にドラルクの前を指差した。
「今日はお前も食う側なんだしさ、作ることはうち帰ってから考えてもいいんじゃねえかな。ほらそれとか、もしいけそうなら食ってみたら?」
そこには小さなチーズの盛り合わせと、血液のジュレやパテなどを載せた皿がサーブされている。どれも少しずつだが美しく盛り付けられており、ロナルドのメインに合わせて出された点からもその意図は明らかだ。なるべく近い形で、一緒に食卓についてみたい。ドラルクが普段食事を摂らないことをよく知る青い目は、受け止めてほしいが押し付けたくないといった様子で揺れている。そんなに不安がらなくてもいいのに。とは口に出さなかった。
「おっとついうっかりしていたな。せっかくの料理をほったらかされるのは私にとっても最も耐え難い所だからね、もちろんいただくとも」
ドラルクは別段かしこまるでもなく、しかし音一つ立てずに料理を切り分け口に運ぶ。ロナルドは自分の手を止めて、その様子をじっと見つめた。
「……なんだね」
「それうまい?」
「うん、美味しいよ。自分じゃわざわざ血液を料理にはしないから、こういうのは新鮮だね」
「そっか。……へへ、よかったぁ。お前もいっつもこういう気持ちだったんだな」
「あんまりジロジロ見るな、見せ物じゃないんだぞ」
視線を振り払うようにドラルクはロナルドを睨むが、若者はおかまいなしにドラルクの手元に見惚れたまま、夢見るような口調でぽつりと言った。
「お前がナイフとフォーク使うとこ初めて見たかも。鉛筆でメモでも取るみたいに食うんだな。自然なんだけどなんか綺麗で、見てて飽きねーわ」
そう言われた途端、ドラルクはそれまでほとんど無意識に動かしていた両手の動かし方が急に分からなくなった。色気のない喩えをするな、と口では返すが、心臓がおかしな音を立てた気がする。食べるところを見つめられるのは慣れないし、ついさっきまでバタバタやっていた癖にいきなり口説き文句のようなことを言われてはたまらない。
アホでも五歳児のゴリラとばかり思いがちだが、ロナルドはこれで一応作家なのだった。下手な美辞麗句よりもずっと深く刺さって忘れられなくなるような、自分の言葉を持っている。これからカトラリーを使うときには、ドラルクはかならず今日のことを思い出すようになるだろう。
ドラルクは深呼吸して両手をテーブルに置き、話を変えることにした。
「ここ、確かに吸血鬼にもいい店だね。メニューが充実してるし、君と私とじゃコース内容もペースも違うのにサーブのタイミングはぴったりだし……素敵な所に連れてきてくれてありがとう」
「本当か!?実は……」
珍しく素直なドラルクの言葉ににロナルドは思わず身を乗り出し、今日のプランについて説明しかけたところでふと躊躇った。この手のもてなしは黙っているのが粋というか、そもそもデートで恩着せがましくするのは良くない気がしたのだ。
「実は?」
「えっと、実は、先週予約したんだぜ……」
「いやそれは知っとるわ。思いっきり予約画面見せてきただろうが」
「うん……」
食卓に落ちる妙な沈黙に、ロナルドはやらかしたな、と胸中ひとりごちた。今日はずっと空回りっぱなしだ。料理が喜ばれたのはよかったが、どうにもロマンチックさやスマートさに欠けている気がする。
そういえばさ、と沈黙を破ったのはドラルクの方だった。
「秘すれば花なんて言葉もあるが、私はショーを見たら裏話まで聞きたいタイプだ」
「なんだよそれ」
「要するにだな、私に畏怖を示すために何をしたのか、まだ隠してるんならさっさと吐けケチルド君」
お見通しだとばかりに悪戯っぽく眉を吊り上げた恋人を、悔しさ半分助かった気持ち半分で眺めながらロナルドは答えた。
「ハァ? さっき食ったパンよりもヤワな相手に畏怖とかねーわ。ねぇけど、実は、前もってお前の好みとか伝えて個別にコース組んでもらってて、使う血液の種類選べる料理はB型にして、食事の量とかも調整して、あと……」
慣れないなりの心尽くしを数え上げる青年の様子は拾た木の枝を得意げに見せる子犬のようで、ドラルクは思わず頬を緩めた。ドラルクに向けた純粋な思いやりと褒められたいという下心がほんの少しだけ混ざった優しさは、ロナルドが普段仕事で振り撒いているそれとはまるで違ういじらしい甘美さがある。嬉しい、楽しい、可愛くって仕方がない。ここがレストランでなかったら、頭をくしゃくしゃに撫でて頬にキスしてやりたい。
先週デートの提案をされた時のやりとりを思い出す。ドラルクは夜景とディナーでロナルドにメロメロになったりはしない。元からけっこうメロメロだ。ただ、いかにもなデートの型がこの若者の素敵な一面を浮かび上がらせるのは楽しかった。
「あと、セロリを抜いてもらった」
「アハハ、それは君のためじゃないか」
「笑うなよ!食事中に俺がパニクったらそっちも困るだろうが、結果的にはお前のためだわ」
顔がニヤつく本当の理由を悟られるのは少し悔しくて、吸血鬼は揶揄いの中に笑顔を誤魔化した。
食事が終わりテーブルがまっさらになった頃、宝石のようなデザートの見本が銀のトレーに載せられて運ばれてきた。ロナルドはわかりやすく目を輝かせ、店舗でスイーツの販売もしておりますよ、などとギャルソンに案内されている。トレーには吸血鬼用のデザートもあったが、ドラルクはブラッドオレンジのソルベを選ぶことにした。夜食の後にパンケーキを五枚も平らげたりするロナルドはこってり甘いケーキでも頼むかと思っていたが、意外なことに同じものをと言い出す。
「いいのかね? ケーキとか、プリンじゃないけどクレームブリュレとかもあるぞ。ソルベの味が気になるなら試させてやってもいいし」
味のソルベはもちろんドラルクの好みだが、もとよりアイスとプリンの予感にはしゃいでいた恋人に半分、あるいは皿ごと差し出してやっても構わないつもりで頼んだのだ。デザートのシェアはマナーとしては微妙なところだが、親しい者どうしのひっそりしたやりとりを咎めるほど杓子定規な店でもなさそうだから良いだろう。
しかしロナルドはそうじゃなくて、と首を振った。
「ほら、ウチだと同じ皿で同じものが並ぶことってあんまないだろ?せっかくデートだしさ、シメは一緒がいいなって」
はにかみながらそう言った若者の目元は甘い。ロナルドの食い気についてしか考えていなかったドラルクは完全に不意打ちにあった形だった。言われたことはもちろん嬉しい、嬉しいが横に人がいるのだ。耳にじわじわと熱が上る。
「あ、お前もしかして他のと半分こしたかったのか?だったら」
「あーーーーうるさい黙れそれ以上喋るな!すみませんオレンジのソルベを二つで」
「ふふ、かしこまりました。では
同じものをお二つ」
ギャルソンの目は暖かく、最後の最後にロナルドの度重なる失敗に負けずとも劣らない大恥をかいたドラルクは、この日初めて砂と化した。
「ウェェン俺もうこの店来れねえ……!」
テーブルチェックを知らずに会計をしっかりトチッて有終の美を飾ったロナルドは、店から出るなり片手で真っ赤な顔を覆って呻いた。もう片手を塞いでいる箱の中身は言うまでもなくジョンへのお土産だ。丸は寛大で慈悲深くまた妬むことをしないが、二人きりで美味しいものを食べた上に手ぶらで帰ったとあってはその限りでない。レストラン付属パティスリーのケーキで手を打ってもらおうという算段である。
一方のドラルクは上機嫌で、繊細なケーキを揺らさないようゆっくり歩くロナルドを置いて、鼻歌混じりに前を行く。
「出禁になったわけじゃないんだ、次はもっといいお客になって来ればいいさ」
決していい加減な慰めなどではない。退店の間際、見送りに来たギャルソンにロナルドは「藻部山さん、今日は本当にありがとうございました」と名前をきちんと覚えて礼を言っていた。「またお越しください」はきっと社交辞令ではないだろう。この若者は、場慣れさえすればきっと本当の意味でどこに出しても恥ずかしくない男になる。
「それはそうと、もう少し手頃な店を探すのはいいかもしれんな。しょっちゅうこんなことしていては破産してしまうし」
デートというのも案外楽しかった。特別なことはしなくていいなどというのは自分にあるまじき欲の無さだったかもしれないとドラルクは思う。この辺りでもう少し寛いだ雰囲気でデートの向けの店はあっただろうか。心当たりに思いを巡らせながら足を進めた。
「え?」
「え?じゃない。確かに君はけっこう頑張ってるが、無駄遣いは感心せんぞ」
これだから加減を知らないゴリラは困る、プレゼントも無意味に予算オーバーさせるタイプだろ君、などと嘯くドラルクは自分の発言にできた死角に気づかない。そしていかに鈍いロナルドといえど、デート欲を持て余しているタイミングでそれを見逃しはしなかった。
「なにお前、しょっちゅう今日みたいなことしてぇの?」
揶揄いの色を含んで投げかけられた言葉に、踊るように揺れていた後ろ姿がぴたりと止まる。
「いや、今のは言葉の綾というか、君の感覚で勘違いされては困るなぁ!私の感覚でしょっちゅうと言ったら、そうだな、十年に一度くらい」
「じゃ破産しねぇじゃん」
ロナルドは大股に三歩前に出て、黙り込んだ吸血鬼の前へあっという間に回りこんだ。得意げにキラキラ光る瞳がドラルクを見据える。確信と期待に弾んだ声が問いかけた。
「本当は?」
「…………しゅ、月一くらいが、妥当なんじゃ、ないのかね……」
語尾が窄まっていくのに合わせてドラルクの顔がそっぽを向いていく。もっとも、顔が見えなくなったところで赤い耳がよく見えるだけなので大して意味はない。
「そうだなぁ、仕事のこと考えるとデートは月一くらいになると思うけど、二人になれるタイミングは週一くらいで欲しいよなぁ」
「やかましい!私はそんなこと言っとらん!」
「でもそう言いたかったんだろ?」
食事中と打って変わって強気になったロナルドはドラルクの手を捕まえて大きく前に振る。
「ちょっ、ケーキ崩れるだろやめんか!離せ!」
「やだ。なぁ、今度はお前が行きたい店選べよな。ジョン連れてくのもいいしさ」
ロナルドはドラルクの抗議に耳を貸さずにぶんぶんと大手を振って進んでいく。初デートの成功と酒に酔った若者は万能感に満ち満ちて、その強靭な体幹で以って右手で恋人を振り回しつつ左手のケーキを水平に保つくらいのことは簡単にこなして見せるのだった。
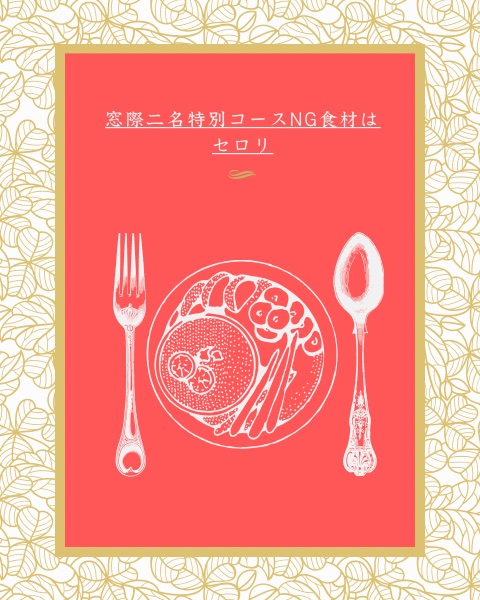
 うとい
Link
Message
Mute
うとい
Link
Message
Mute




























 ステキと思ったらハートを送ろう!ログイン不要です。ログインするとハートをカスタマイズできます。
ステキと思ったらハートを送ろう!ログイン不要です。ログインするとハートをカスタマイズできます。

 うとい
うとい うとい
うとい うとい
うとい うとい
うとい