明ノブ&鬼ノブlog 生前軸&カルデア叡山にて(明ノブ)
天も地も赤かった。血と臓物と、それらの焼ける臭気が澱んでいた。寺へと続く踏み固められた大路を、幾筋もの血泥の足跡が汚していた。
幼児の亡骸もあった。老女の亡骸もあった。撫で斬りにせよとの下知であった。光秀は密かに、自身の手勢にだけはその四字を伝え忘れていたのだが、他の部隊の大将方は物覚えの良い方々ばかりであったらしい。参道に残っていた痕跡は、戦ではなく虐殺のそれだった。
ひたすらに足が重い。体が重い。わけもわからぬままに命を絶たれた刀も持たぬ民たちが、焼け爛れ千切れかけた腕でこの身に取り縋っているかのように重い。道の先で待っているあのお方に、申し上げなくてはならないのに。血を含んだ草履が一歩毎にぐずぐずと鳴り、その重さを増していった。
織田上総介信長公には天下を手に入れるだけの才覚がある。
これは全く確かなことである。定石から逸脱した奇策を案じ多勢を打ち破り、常に大局を捉えながらも微細な機を決して逃さず、それでいて詰みを察すればそれまでの犠牲を惜しむこともなくさらりと引く。戦上手を集めれば紛れもなく日の本で随一であろう。
その一方で、天下を治めるだけの器量があるとは世辞にも言えぬと、このところ光秀は気づき始めていた。
天下を取ることとそれを統治することには、全く別の才が必要なのだ。公をこの目で見、その戦を知り、その在り方を理解するまで全く思いもしなかったことであった。しかし今となっては至極当然のことのように感じられる。優れた猟師と優れた料理人は、同一人物でない場合の方が多かろう。
信長公に欠けているのは耳だった。公は民の声をお聞きにならない。華々しく戦をする、その場所に生きている民の暮らしをほんの一欠片でも想うということがない。ともすれば、それは卓越した戦上手と切り離すことのできぬ、副作用の如き欠落なのやもしれぬ。成る程、足元を這い回る虫けらの命など気に掛けていては相撲は取れぬ。此度の撫で斬りとて、恨みを抱えた叡山の者が後々に叛逆できぬよう徹底的に戦力を潰しておくという考え方は、周囲に敵の多い織田家の状況を鑑みれば理には適っている。公が天下を俯瞰しようと上った樹はあまりに高く、その根を住処とする民の声は届かぬのだろう。それを責めても詮無きことだ。欠落あっての信長公であるのだから。
魅了されていた。戦の手腕に。胆力に。冷酷さに。射抜くような瞳に。高い知性と野蛮なまでの柔軟さを同時に感じさせる言の葉に。それらは全て己には無いものだった。眩く、貴いものであった。何の制限も受けることなく自由闊達に、傍若無人にその天賦の才が振るわれるところを、ただお側で拝見し、圧倒されていたい、嘆息していたいという気持ちは確かにある。しかし、それを是とできるほどには光秀は愚鈍ではなかった。このまま、民の声を聞かぬまま、人を人とも思わぬままの覇道を歩み続けることは公のためにならぬ。そのやり方で天下を取るということは、天下全ての者から憎まれ、忌まれ、恐れられるということに他ならない。斯様な天下、ながくはもたぬ。何時か何処かで背中を撃たれる。或いは、天下へ辿り着くより先に。
それを防ぐため、輝く
道行を最後までお側で見届けるために必要なのは、我こそが公の耳となり民の声をお届けすることであろう。公に聞こえぬ声も己には聞ける。代々織田家に仕えてきた家臣のお歴々が口を噤むのであれば、余所者の明智が申し上げるまで。それこそが真の忠義というものであろう。
「戻ったか」
足を引き摺るようにして本陣へ帰り着くと、信長公は既に具足を外し、城に居るのと何ら変わらぬ軽装で
床几に腰掛けていた。撫で斬りにせよと自分が命じたのだから、戦の終わった今、もはや矢が飛んでくることも残党が斬り掛かってくることもないという判断によってそうしたのだろう。合理的ではあるがあまりに肝が据わりすぎて、どこか人間味に欠けてさえいる。光秀が独断で民を見逃していたなどとは思ってもみないのだ。そういうところから、何時か足を掬われるに違いないのに。
「──畏れながら、申し上げたき儀がございます」
床几の前に膝をつく。ん? と僅かばかり首を傾けて光秀の言葉を待つその瞳は、今以て燃え続ける延暦寺の炎と同じ色をしていた。
天正十年 夢十夜(明ノブ)
【第一夜】
こんな夢を見た。
皆で打ち合いをした。庭だった。誰の剣が筋が良いかと、木刀を持ち出して順に仕合うた。酒か何かを賭けていたような気もする。皆若かった。
体が軽く、面白いように動いた。柴田殿を破り、羽柴殿を破り、私は勝ち進んだ。武の神にすら打ち勝てそうな思いがした。私の前にはもう仕合う相手が居なくなった。そうすると、縁の上から声が掛かった。
「楽しそうじゃな。わしも混ぜよ」
白い素足が、何も履かぬままにひらりと庭に下り立つ。
「公といえど、負ける気はいたしませぬ」
木刀を構え見合うた。剣先がこつりと触れた瞬間、獣のように体が動き、渾身の力で喉笛を突いていた。がぼ、と声にならぬ声を上げ膝を折る公の長い髪が浮き上がる。その中心を間髪入れず打ち下ろした。華奢な頭蓋の砕ける艶かしい感触が木刀を震わせ、手を濡らした。皆が公のお側へ駆け寄る中、羽柴殿だけはそうしなかった。厭な夢だった。
【第二夜】
こんな夢を見た。
茶を点てていた。茶会の席ではなく、何か茶器をやるから茶を飲ませろと城へ呼び寄せられていた。公は御自慢の名物を並べて甚く御満悦だった。
「そなたの茶は久方ぶりよな」
そう言って目を細める公に茶椀を差し出す。サルは駄目じゃあいつ、全部やりすぎるんじゃよな、何度言っても直らん。白い喉がこくりと上下する。味に違和感を覚えたのか、不思議そうな顔で頑是なく茶碗を覗き込み、そして取り落とした。
胸を押さえ前のめりに倒れ込む。細い背中が呻きながらのたうち、爪はばりばりと音を立てて畳を掻き毟る。謀反人の顔を焼き付けようと燃え上がる瞳がこちらを見た。食い縛った歯が真珠のようだった。
手を握って差し上げた。握り返していただくには遅かったようだった。酷く冷たく、瘧のように震え、やがて動かなくなった。形の良い爪に千切れた畳表が挟まっていた。厭な夢だった。
【第三夜】
こんな夢を見た。
安土城の天主が完成した。琵琶湖を一望できる天主を公は大層お気に召し、人を呼んでは見せているようだった。
「この眺めは本当に絶景じゃな。実の所、坂本城からの眺望が忘れられんで、琵琶湖を見下ろすよう造らせたのよ。佳い城を建てたな」
強い風が吹いて長い髪をはためかせた。高欄に腰掛ける公は、西陽の逆光を背負い表情が見えない。廻縁の内側に置かれた足も照柿色に染まっていた。足首はあまりにか細く、掴み上げると指が余るほどだった。
一息に高く掲げたので、袴が捲れ上がり雪のように白い腿が露わになった。しかしその向こうで見開かれた夕陽と同じ色の瞳の方に視線を吸い込まれた。
重心を失った体は高欄の外側へ倒れてゆく。ほっそりとした足が手の中を擦り抜けた。随分と下の方で、どさりと音がした。西陽の差し込む天主は確かに美しかった。厭な夢だった。
【第四夜】
こんな夢を見た。
蔵のような場所だった。窓はなく、じめじめとして空気が悪かった。公はそこで暮らしていた。私が公をそこへ押し籠めたのだと知らぬ筈もなかろうに、私が行くといつも喜んだ。
「そなたの顔を見るのだけが楽しみじゃ」
公は弱っていった。ろくに食事を与えていなかった。しかしひもじさや苦痛を訴えてくることはなかった。ただ活けた花が萎れるように一晩ごとにくしゅくしゅと乾いて、やがて石張りの床に倒れたまま、頭も上げられなくなった。
公の傍に腰を下ろした。首を持ち上げ、膝枕にお乗せした。手入れをされず縺れた髪を指で梳くとぞろぞろと抜けた。乾燥しきった唇に触れると、弱々しく歯を立てられた。最早顎の力が残っていなかったのか、甘噛みだったのかは判然としなかった。転がる鞠がやがて止まるように、ゆっくりと呼吸が止まり、胸の鼓動が止まった。厭な夢だった。
【第五夜】
こんな夢を見た。
首実検に向けて用意を整えていた。先の戦で挙げた首級をごろごろと並べ、自ら洗って化粧を施していた。何故か夢の中では女子の仕事だとは思わず、早う仕上げて天主に持参せねばとそればかり考えていた。
最後の首が公の首だった。凶相である左眼や歯噛の首ばかり片付けた中で、黒々とした睫毛を伏せた穏やかな地眼の相だった。髪を結い、白粉を叩き、紅を差した。まるで生きているかのようになった。温もりさえも蘇ったような気がして、暫く膝に抱えていた。心地好い重量だった。生れたばかりの子を抱いた時を思い出した。しかし当然ながら首が生き返ることはなく、腥い血の臭いがしていた。
もう天主へ行かねばと思った。遅れれば機嫌を損ねると思った。誰の機嫌を、と思ったところで目が覚めた。厭な夢だった。
【第六夜】
こんな夢を見た。
舟遊びをしていた。夜の湖だった。巨大な満月が湖面に揺れており、それを掬いに行くと仰るので小舟を漕ぎ出したのだ。
公はほろ酔いで歌を口遊んでいた。月明かりに青白く照らされた姿はこの世のものとは思えず、いっそ幽鬼の類のようだった。舟はするすると進んだ。月の真下、真白く切り取られたかのような場所へ舳先が辿り着き、漕ぐのを止めた。ぱしゃぱしゃと水を触っていた公が不意にこちらを見て言った。
「そなたは取らんで良いのか」
水音はそれほど大きくなかった。舟は大きく傾いだが、辛うじて転覆は免れた。船縁を掴む細い指を何度も引き剥がした。顔が水面に出れば櫓で突いて沈めた。暫くすると湖面は元通り静謐な白と黒に満たされた。海藻のように揺れていた髪も直ぐ見えなくなった。小舟の上に小さな草履が残っていた。厭な夢だった。
【第七夜】
こんな夢を見た。
戦をしていた。鉄砲隊として敵陣の程近くで撃ち掛けていた。敵方からも時折、鉛玉が飛んで来た。戦況は膠着しているようだった。
ぬるい風が吹いた。敵陣の奥から小柄な将が躍り出た。公だった。兜もつけずに兵を鼓舞して回っている。疲弊し士気の下がった兵らに業を煮やして飛び出してきたのだ。坊主の弾など当たるかと宣うて。覚えている。本願寺だ。
火縄に火をつけた。長身の将が後を追って飛び出してくる。公を連れ戻しに来た自分だ。あの日は既の所で公を地に引き倒してお守りできたが、今日は銃火が一歩先んじた。
どう、と胸を叩く反動。小さな的が翻筋斗打って倒れた。討ち取った、と思った次の瞬間、何故か足元に転がる公を見下ろしていた。眉間に穴が開いていた。童のように驚いた顔でこちらを見上げていた。弾は貫通したのか、血溜まりが広がっていった。火薬の匂いがしていた。厭な夢だった。
【第八夜】
こんな夢を見た。
天も地も赤かった。血と臓物と、それらの焼ける臭気が澱んでいた。撫で斬りにせよとの下知だった。焼け残った建物の陰を覗き、骸を槍で突いて命のないことを確認しながら歩いた。草履が血を含んで一歩毎にぐずぐずと鳴った。
これ以上は無駄だろう。報告に戻ろうと踵を返した。すると、血泥の足跡が続く道の先に、何処から現れたのやら、小さな影が動くのが見えた。追って斬り伏せてみれば、娘はよくよく見知った顔をしていた。
「わしも斬るか」
仰向けに倒れたまま公が問うた。口の端から血泡がごぼごぼと溢れた。よく似た色をした瞳がすうと細められた。
「女子供も生かすなとの主命ですので」
忠義者め、と公は嗤った。透き通る喉に刃を当てた。峰に体重を乗せればごとりと首が落ちた。どくどくと噴き出した血潮は直ぐに泥に混じり、他の何百何千の骸の流した血と区別がつかなくなった。
立ち上がると日が暮れかけていた。泥の上に広がる豊かな黒髪を、血染めの草履で踏み付けにしていたことに気づいた。厭な夢だった。
【第九夜】
こんな夢を見た。
切腹の支度をしていた。客人として坂本城に預かっている三淵殿の腹を公が望まれた。知らぬ仲ではないだけに残念ではあったが、公ならばそう仰るだろうとも思った。庭に茣蓙を敷き、白無地の陣幕で目隠しをした。人払いをし、夜を待った。
陽が落ち、暑さが弛み、虫が鳴き出した。白装束で現れたのは、髪を低い位置で纏めた公だった。御腹を召されるのは公だったのだ。自分は何か勘違いをしていたようだった。
三方には柄を外され紙を巻かれた短刀が載っていた。公の愛刀が、主の自害を拒み腹に刺さらなかったという謂れを持つことを思い出した。三方に載っているのはその刀なのだろうか。伝説が再現されるようなら、自分が介錯せねばならない。
「何を考えとるか分かるぞ。楽しみじゃな」
果たして、薬研藤四郎は油でも塗ったかのように公の腹を滑り、傷一つ負わす事が無かった。ふふと笑う頸に刀を振り下ろし、抱き首に落とした。形だけでも腹を切った亡骸にせねばと思った。抱き起こし、自分の短刀で十文字に掻き切った。はらわたが温かかった。厭な夢だった。
【第十夜】
こんな夢を見た。
寺の周囲を取り囲んでいた。点々と燃える松明が、怨みを抱いて集まってきた人魂の群れのようだった。公を怨みつつ焼き捨てられていった命の数は、全くこの比ではなかろうが。
日が昇り始めた。暗すぎず明るすぎない、仕損じる可能性の最も低い時間だ。恐ろしい程に全てが計算通りだった。
鬨の声が上がる。兵は一斉に門を破り、塀を越え、砦としての機能を備え頑強に造られた寺を押し潰さんばかりに群がっていった。それを馬上から、指一本動かさず呼吸すらも止めてただ見ていた。
汚している、と思った。華々しくも覇道を突き進んできた公の生涯に、織り上げてきた荘厳絢爛な錦に、どす黒い汚泥をぶち撒けている。天下は今にも織り上がる所だったのに。斯様な所で臣下のつまらぬ別心を受けるような方ではないのに。今日より後に世人が公を語る時、この敗北が常に付いて回るのだと思うと、何とも歯痒かった。公の価値を毀損したいとは毛頭思わなかった。しかし如何する事もできない。自分だけが理解していればそれでいいと思うことにした。
奥から火の手が上がった。何人も討ち漏らすなとは厳命したものの、火責めは命じていなかった。事態が決し、公の判断で火をかけたのだろう。同時、敵将深手を負い奥へ退避との報告が入った。ならば、今。まさに今、この瞬間。
きちんと腹に刃は刺さったろうか。腹を捌く力は残っていただろうか。上手く首を落とせる者はお側に居ただろうか。桔梗の旗印はご覧になったろうか。最期に何を見、何を考え、何を仰ったのだろうか。それを知れないことはこんなにも侘しいものだったのか。掌には何も無い。頭蓋を砕いた手応えも、ぞろりと指に絡んだ黒髪も、はらわたも首も無い。ただ汗がじっとりと冷えているのみだった。風向きが変わり、飛んできた火の粉が頬を焦がした。
途方もない間違いを犯しているような気がした。妙に生々しい、厭な夢だ。早く醒めてはくれないものか。毛利攻めに発たなくては。魘されている場合ではないのだ。最近は如何してか悪夢ばかり見る。戦が片付いたら医者にかかろう。その前に、まずは毛利だ。羽柴殿が首を長くして待っている。
目をきつく瞑り、そっと開いた。
本能寺はいよいよ轟々と燃えていた。
終
─────────────────────────────────────
『天正十年 夢十夜』は豆本で頒布しています。
お手元に必要でしたらどうぞ▶https://haijiro.booth.pm/items/2744213
藪の中(明ノブ+道満)
体が冷えてゆく。陰霪と降りつのる雨に体温を奪われ続けていた。厚く垂れ込めた鉄色の雲は途切れる気配もない。竹藪の中は一層暗く、時間の概念すら曖昧にさせていた。靄のかかった、どこか現実から剥離してしまったように感じられる世界の中で、脇腹の穴だけが火箸でも突っ込んだかのように生々しく熱い。一歩ごとに裂け目がほつれ、腹の中身が零れ出ているような気がしてならない。体温の低下も視界の暗さも、天候のせいばかりではないと分かっていた。よろしくない。何処かで止血をする必要が──あるだろうか? これ以上、私を見放したこの世に縋る意味はあるのだろうか。
力の限りに動かしている足は夢の中の如くに重く縺れて、一向に前へ進まない。限界を迎えたのは肉体だったか、それとも精神だったのか。上がらなくなった足を霖淖に絡め取られ、膝を突いてしまうと最早、立ち上がることはかなわなかった。臓腑の揺れによって喉元に押し上げられ、なす術なく口から溢れたものがぼたぼたと泥の上に血溜まりを作った。差し込む激痛に阻まれ上手く咳き込むことができず、喉の粘膜に不快感を張り付かせたまま、目についた木の下へずるずると這って潜り込んだ。竹どもの繁殖力に負けてしまったのだろう、寄らば大樹とは世辞にも言えぬ痩せた木だが、どうにか雨糸は凌げる。幹に背を預けるとほんの僅かに体が楽になった。
役に立たぬ目に代わり、耳に意識を集中する。追手の声も、味方の声もない。聞こえるのは潸潸と青葉を叩く雨滴の音と、死に際の獣の如き呼吸ばかりだ。独力では城に戻るどころか一歩たりとも動けそうにない。此処で終わるのだ。二度と輝く日輪を拝むことなく、降り止まぬ濯枝雨に溺れて死ぬのだ。この身が陽の光を最後に浴びたのは何時だったろう。それにつけても忌々しきはこの淮雨。そも、私は彼奴の戦に敗れたのではない。天に敗れたのだ。無尽蔵に降り注ぐ銀箭が奴に味方した。それさえ無ければ勝ちの目は十分にあったのだ。兵の数を頼みにしようなどとは端から考えてはおらぬ。彼奴がどれほど頭数を揃えて来ようとも、此方には調練に調練を重ねた鉄砲隊があった。数の差を殺す隘路で迎え撃つ布陣も最善のものであった。それなのに。ただ一度の晴れ間も無いのでは、鉄砲など嵩張るばかりの荷物に過ぎぬ。どうして。どうしてこうなる。早々に信澄殿を討った丹羽軍もそうだ。四国征伐の命を受け、本来であればあの日は海上に居た筈だったものを、時化のために出立を見送り、京から目と鼻の先の摂津に留まっていたという。私はどうすれば良かったというのだ。信長公────貴方のみならず天までも、私でなく彼奴に笑いかけるというのですか。
じわりと視界が滲む。鼻がつんと沁みた。顔を擦ることすら大儀で、指一本動かすことなく成り行きに任せた。雨で濡れた頬には涙の感触は判別できず、流れているのかどうかも分からなかった。
早々に腹を切って、終いにするべきなのだろう。これ以上消耗しては刀を握ることも難しくなる。僅かばかり存えた命を彼奴の手の者に討ち取られ武功の証とされるよりは、密やかにこの地の民に全てを引き渡したい。無用な戦に巻き込んでしまったことへの、せめてもの償いとさせてほしい。刀、鎧、兜に首。まとまった金になる筈だ。
鞢を引き抜き、胴を外す。直垂は既に腹を切った後かと思われるほど深緋に染まっている。討ち漏らした大将首には褒賞金を懸けるのが戦の習いであるが、果たして彼奴、この首にいくらの値をつけたものだろうか。低いのも業腹だが、変に高くされるのも力を誇示されているかのようで鼻につく────
ちりん。
薄暗い藪に不釣り合いな、異様に澄んだ音が耳を掠めた。
脇差の柄にかかっていた手が止まる。顔を上げると、ざあ、とぬるい風に散らされた細かな雨粒が吹きつけた。思わず目を閉じ、何度か瞬きをしてから再び音の方角を見る。すると、──その時にはもう、それは、そこに立っていた。
身の丈七尺に届こうかという大男。士官先を転々とした人生の中で、どの城でも我こそは国で一番と標榜する屈強な体格の兵を見てきたが、これほど大きな者にはついぞ見えなかった。僧衣らしきものを纏っているわりに、ぞろぞろと長い髪がうねりながら腰の下まで伸びている。野点にでも使うような大振りの、鮮やかな朱の端折傘を雨除けにしているが、斯様に幅のある傘を差してこの竹藪を歩けるものだろうか。
ちり、とまた鈴の音が鳴った。
「随分と降られましたな──拙僧の見立てでは、昼には上がるようですが」
しかし、それまでお待ちにはなれぬご様子──。
柔らかな、それでいて温かくはない低音が、雨音を弾くようにしてするりと耳に流れ込む。鬼か、化生か、妖狐の類か。肩に、何処ぞで拐ってきたのだろうか、子供の体を俵のように担いでいる。力なく垂れ下がった白い寝間着の腰から下だけがこちら側に見えている。気を失っているのか、死んでいるのかは定かでない。持ち帰って喰らうのだろうか。私のこともそうするのだろうか。あまり美味くもないだろうが、首から下ならば好きにするといい。首だけこの藪に置いていってくれればそれでいい。
「そう構えることはございませぬ。無理をなさらず、お体を楽に。拙僧、今は満腹ですので──いえいえ失敬。純粋なる善意から、貴殿に贈り物を差し上げたく罷り越しました次第にて」
男はべらべらと一人で機嫌良く喋っていたかと思うと、不意に言葉を切り、その場にどっかりと座り込んだ。あまりの豪胆な所作に泥水が飛沫を上げる。着物や髪の汚れを全く意に介さぬ振舞いはいっそ不気味で、やはりヒトのように見えてヒトでない何かなのだという確信を強固にさせた。
背後に無造作に置かれた形になった巨大な端折傘が赤黒い影を作る。腰を下ろしても尚、その体躯には威圧感があった。男は身を乗り出して此方を覗き込むと、赤黒い顔のままでにっこりと微笑んだ。
「時間もなさそうですので、まずはご覧に入れましょうぞ」
そう言い置いて、怪僧は肩に担いでいた荷物を抱き下ろし、ごろりと目の前に転がした。子供のように見えていたのは担ぎ手の常識外れな体格のためだったようで、実際には華奢な女の体だった。細い足が無造作に濡れ落ち葉を蹴る。豊かな黒髪が泥の上に散る────その髪から顔へと視線が辿り着き、呼吸が止まった。
「のッ……!?」
声が絡まり喉が裏返る。先刻は出せなかった咳が厭というほど出た。眠っているかの如き安らかなかんばせに飛沫を飛ばさぬよう必死で口を押さえ横を向いた。捩じ切れそうな脇腹の痛覚を無視して口の中に溢れた血反吐を無理矢理に飲み込み、視線を戻す。先と変わることなくそこにはあのお方のお顔があった。見紛うはずもない。あの日どれほど焼け跡を掘り返しても見つけられなかった、私の全てが────。
そこまで考え、漸く気付く。火傷の痕がない。着衣にも焼け焦げの様子はない。そも、あの日から十日以上が経つにもかかわらず、腐臭も蛆の湧いている気配もない。とすれば、これは。
「ンンンン〜! どうか、どうかお怒りにならず! それをそのように見せているのは拙僧ではございませぬ。とは申しましても、貴殿の目にどのように映っているものやら、とんと見当もつきませぬが──それ、聖杯というのは、そのように出来ているモノなのでございます」
再び饒舌に化生の口が回り出す。言うことには、これは本物の公の遺体ではなく、少々汚染が進んではいるものの万能の願望機、聖杯であると。見る者によって欲望を投影し形を変えているのだという。俄かに信じがたく、にやつく口許に目をやると、拙僧の目には幼くして死に別れた母の似姿に映っておりまするなどと嘯いた。益々不信感が募る。似姿とはいえ母親の体を泥に投げ出す奴があるか。
「お疑いも当然のこと。であれば、触れてみては如何です? 魔力の存在を感じられるかと」
言葉が耳に届くより先に手首を掴まれていた。熊か何かのように厚い掌に有無を言わさず引き寄せられ、白い衿の合わせに押し付けられる。冷たい膚に触れたその瞬間、言わんとすることが理解できた。触れた指先から確かに何かが流れ込んできた。全身の血液が逆流するような、反則的な、肉体の時間が遡る感覚。傷の痛みが薄れていく。呼吸がしやすくなる。ヒトの理の及ぶところでない力が働いているのは明らかだった。聖杯の魔力。万能の願望機と言ったか。この力が真に万能というのなら、このような瑣末なことに浪費している場合ではない。正しく利用しなくてはならない。これさえあれば、私は。信長公は。やり直すことができる────。
獣の指を振り払い、手を浮かす。途端、脇腹に激痛が蘇り体が折れた。食いしばった歯の隙間から呻きが漏れる。傷の治癒は幻だったのか。いや、それならそれで良い。この素晴らしい力を無駄遣いしたくはない。傷口を圧迫し、荒ぶる呼吸を整えていると、最早うきうきとした様子を隠そうともしない声が降った。
「なんとご殊勝なお心! 今際の際にありながら、肉体の快復には興味がないと! しかしながら一点、残念なお知らせがございまする。こちらの聖杯、魔力量こそ一級ではありますが完品とはいかぬものなれば。汚濁を大いに含むものゆえ、そのような美しくも難しき大願、おそらく望まれるような形では叶えられませぬ。故に拙僧も持て余し……いえいえ。しかし拙僧、考えがございます」
聖杯の汚染。それがどういう状態を意味する言葉なのか、それ以前に聖杯とは一体何で、誰が何のために生み出したものなのか。法師の好き勝手に口走ることを自分は半分も理解できていないように思えた。白い胸にべったりと赤い手形を残されたそれは、確かに汚染されたという形容が似つかわしくはあった。
「一先ずは、この聖杯を使うのではなく呑んでしまうのです。触れるのみでも随分と楽になったのでは? 躰に納めてしまえば全快も同然。吐き戻さぬ限り、ヒトとしての寿命すら無くなりましょう。半永久の命を手にした上で、その身に取り入れた力を以って時間をかけて織田信長復活の儀を執り行うのが宜しい。百年、千年かかるやもしれませぬが、確かな方法がございますれば。拙僧がご説明するまでもなく、聖杯を御身の血肉とすれば自然、流れ込んでくることでしょう」
朗々と流れる演説が途切れると、ざあ、と思い出したように再び雨の音が藪を覆った。押し殺した獣の息遣い。聞こえていた筈の演説は、しかしほとんど頭に入っていなかった。
無性に喉が渇いていた。はだけた胸に残る汚らしい手跡から目が離せない。聖杯の力、生の希望を知ってしまった体が、とても足りぬもっと寄越せと喚いている。違う、この力は信長公だけのために使うのだと、理性ではそう考えるのに。自分は此処で終わるのだと一度は受け入れた筈だったのに。今となっては全身の残り少ない血の全てが、目の前の福音を求めて沸き立っている。欲しい。欲しい。ほしい。黒髪の中にしどけなく浮き上がる細い喉笛。いかにも柔らかそうに張った薄い膚。その膚の下の、何もかも。視界が暗くなっていく。脳が渇く。体が傾ぐ。懐かしい、甘い香り。
ぶつりと噛み切った首筋から溢れ出す甘露。
藪の雨は未だ、止みそうにない。
本能閣、オープン前夜(明ノブ)
ざばざばと砂を洗う波の音に、遠い湖を思い出す。何処までも続くかに見えるこの海も、実のところ水平線の先は閉じられており浜から一定以上は離れられぬらしい。琵琶湖と同じ、広大なようでいて閉じた海なのだ。だからだろうか──波の声がよく似て感じられるのは。日が落ちて海面が墨を流したように染まり、景色の違いが闇に塗りつぶされると、尚のこと脳が錯覚を起こしたがって耳の神経ばかりを研ぎ澄ます。
開いたままのビーチパラソルを一本見つけて、くるくると畳んで砂の上に転がした。ついでにそこにあったビーチチェアに腰掛けて、雪駄の中に入り込んだ砂を落とす──帰る途でどうせまた砂だらけになることは分かりきっているのだが。日没からかなり時間が経っているにもかかわらず、砂は未だ人肌のような淡い熱を含んでいた。
「ミッチーーーー~~!! 待ってこれすごすぎんか!? いやわしが言うたんじゃが、そうなんじゃがこれマジで全焼しとらんの!? マ!?」
建物の方からぱたぱたと同じ雪駄の足音が駆けてくる。夜闇の中に煌々と輝く瞳。どういうわけかこの特異点において唐突に浜辺の温泉旅館のオーナーとなった織田上総介信長公その人である。常人の目から公の行動が唐突に見えるのは生前の通りではあるが、それにしても常軌を逸してはいないかと畏れながら尋ねてみたところ、特異点ってそういうもんじゃから是非もないのよネ、南蛮の英霊がどっかで聞いたような大名になっとるとかあるあるじゃし、との御回答が下った。腑には落ちないが実際にそのようになってしまっているものは否定のしようがない。一も二もなく、光秀も雇われ支配人としてノッブリゾートの名に恥じぬ働きをすることをこの特異点での己の役目と定めたのであった。
「あくまで幻術ですので、戸口に焚いた篝火が大きく見えているだけです」
「ウッソじゃろお前……だってお前……普通に熱いんじゃが!? 中で信勝死んどらんかこれ!?」
「熱も異臭も木の爆ぜる音も幻覚です。建物と篝火を同時に観測した際に観測者の認知に対して術の効果が発生するので、建物内への干渉はありません。建物外であっても、篝火の視認できない場所では術の影響を受けません。館の裏手に回っていただければご確認になれるかと」
はぇ〜、上手いことやるもんじゃの〜と嘆息し、公はつい先程まで光秀が腰掛けていたビーチチェアに身軽な体を投げ出した。がたんと大きく傾いだチェアの外枠を咄嗟に掴み、間一髪転倒を防ぐ。一瞬の静寂の後、けらけらと底抜けに明るい笑い声が響き、そこだけが真昼間のように照らされた。
「なるほどなー、全くの無からこれほどの幻を捻り出すのはキャスタークラスといえどキツいから、実在の炎を足場にしてコストカットしとるわけか」
「お恥ずかしい限りです……この演出で御眼鏡に適いましたでしょうか」
「いや十分十分! ここまでリアルに4DXで燃やせると思っとらんかったし、ってかこの距離でも熱い、熱くない? 火の粉飛んどるし」
ひらひらと顔付近の空気を払う仕草をしながら上機嫌の声が言う。パラソルを開いたままにしておけば良かっただろうか。ちらと建物に目を遣る。光秀の目に映る館は、戸口の篝火の他は小火ひとつ起こすことなく、しんと静まり返っている。当然、火の粉も煙も飛んで来ようはずはない。
「火勢が強すぎますか? 術者自身には術のかからぬようにしてありまして、体感がないのですが……」
月明かりに照らされた深紅がぱちぱちと瞬く。えっじゃあこの大炎上も見えとらんわけ? こんなんなっとるのに? と指差す先で、篝火だけが海風にふらりと揺れた。
「寂然と寝静まった館が見えます」
「はー、そういうことか。完全に理解した」
幻覚の炎と術者の顔とを交互に眺めていたかと思うと、信長公は徐ろに立ち上がった。
「座れ」
「いえ、私は」
「いいから」
袖を強く引かれ、主君の前で己だけ腰掛ける形になってしまう。目を伏せよの下命と同時、喉仏から顎先までを熱を帯びた指がついとなぞり上げた。腰の隣に膝が突かれる気配。ビーチチェアが二人分の体重に軋む。
すぐに唇が触れるかと思いきや、そうはならずに鼻頭のぶつかりそうな距離で接近が停止したのを産毛の感覚で認識する。頤を両側から掬い上げられ、逃げ場のないまま額が当たる。温かな呼気が当たる。自分はというと、意識するまでもなく呼吸を止めていた。猫の子のするように前額を擦り付けられ、夜の帳の如く流れる髪が頬をさらさらと擽った。
そのうちに息が続かなくなり、出来る限り細く吐き出そうと恐る恐る口を開けかけた時だった。暗闇の中で公の気配が嗤った。柔らかな熱にしっとりと塞がれる唇。確かな意思を持った舌先の促すまま薄く開けば、甘く尖った肉が満足げに割り入ってくる。その濡れた肉を伝ってとろとろと魔力を含んだ体液が口内に流れ込む。目的は窺い知れないが、光秀に唾液を与えたいのだということだけは察せられた。仄甘い露が喉へと転がり、先刻の間は口腔にこの下され物を溜め込んでいたからかと理解の追いついた矢先、じわりと背に不自然な熱を感じた。次いで頸、頬にちりちりと炙られるような感覚。思わず命に背き瞼を上げてしまう。視界の端が明るい。赤い。煙が鼻腔を満たす。轟々と吹き上げる気流の音が、耳についた。
硬直した舌を戯れに食みながら、膝の上の影が髪を掻き上げ体をずらす。左目の視野が広がる。燃えている。巨大な炎が夜空を焼いている。炎の中に辛うじて建物の形が浮かんでいるが、そこにあったはずの温泉旅館の輪郭ではない。何処かで柱が折れた音がした。屋根が傾く。知っている。この光景を確かに知っている。あの日と同じ場所に火の粉が当たった。口を吸われているのに何故だか喉が急激に渇いてゆく。瞬きの仕方が分からなくなって、眼球がじりじりと焼けてゆく。
「えらく生々しく焼けとると思えば、お前の内にある業火をそのまま貼り付けとったんじゃな」
体液を通じて擬似的にパスを繋いでの知覚共有──魔術師の真似事で幻覚の断片を逆流させられたのだと悟った頃、唇が離れ、ややあって燃え盛る寺も消え失せた。炎の音は遠ざかり、どくどくと煩い心悸と潮鳴りだけが耳に残った。掌に濡れた感触を覚え、軋む首を下に向ければ、両手の中にきつく鷲掴んでいたのはTシャツ越しの細い腰だった。ばちんと強い電流が走って手を離す。手が離れても裾の皺は戻らず、その下の膚がどのような状態になっているかを易々と想像させた。
「道理で物々しい戦支度じゃと思うたわ」
詫言も申し開きも口に出す間がなかった。光秀の爪先から脳天までを舐め上げた瞳の中に、変わらず揺らめくあの焔があった。見下ろした足元はスラックスに旅館の雪駄を突っ掛けた素足で、臑当はおろか足袋すらも履いていない。上半身に至っては袖を捲ったシャツ一枚だ。物々しさとは程遠いこの略装が戦備えに見えているのだとしたら、それは────あの日の光秀が幻視されているのに他ならない。大鎧に身を固め、陣胴服を羽織り、呼吸も忘れてただ噴き上がる焔を目に焼き付けていた光秀が。
「…………先にお休みになってください。今少し、術にチューニングの必要がありそうですので」
「そうか? もっぺん見とくか? せっかくじゃし」
「お気持ちだけ頂戴します」
するりと伸びて目元を撫でた細い指の温度が、熱くも冷たくもなかったことに少しだけ救われた。
足を踏み出すと案の定、すぐに生温かな砂が指の間に入り込んできた。早々に雪駄を脱いで裸足で歩き出した公の判断が正しいのだろうと思いつつ、それに倣う気力が湧かぬまま、小さな足跡を踏まぬようざりざりと館への数十歩を引き返した。濤声は何も変わらず、懐かしい音で鼓膜を濡らし続けていた。
森可成の次男の初陣(鬼ノブ)
「よう帰ったな」
主君は閉じた扇子を小さく動かし、もそっと寄れと膝元を示した。
長可がのそのそと近づき真正面に座り直すと、薄らと沈香が薫った。先の戦で兜に焚いたのが残っているのだろうか。大将首ともなれば討ち取られた後のことまで考え、持ち帰る際に悪臭がせぬよう兜に香を焚きしめるものだという。数日前、森家の当主として初陣の長可も焚いてもらったが、香気なんぞとっくに消え失せていた。このひとにだけまだ甘い薫香が纏わりついているのは、腰まで流れる豊かな髪のせいだろうか、それとも香木自体の品質の違いか。或いは、常に戦をしているせいで総身に香が染み付いたのか。
「初陣は何もせず帰ってくるのが一番の大手柄じゃ。指の一本も落とさなんだなら親父超えじゃな。お前はえらい!」
わしわしと乱暴に髪を掻き回される。父や兄にそうされた遠い記憶が呼び起こされ、それに比べてあまりに小さな掌の感触に思わず顔を上げる。
「さすがに禄はやれんがの、褒美はやろう。好きじゃったろ」
小さな掌の主は、小さな歯の並びを見せてにかりと笑った。
求められるまま差し出した手に、懐紙に包まれた干柿が転がる。この烏帽子親がくれる干柿は、昔から矢鱈と甘かった。
◆
遡ること数年。
当時父上殿は戦に忙しく滅多に帰らなかったので、家で一番強いのは留守を預かる兄上殿だった。
打ち合っても、弓を引いても、四つに組んでも勝蔵は兄に敵わなかった。六つも歳が違うのだから当たり前だと兄は笑っていたが、納得はいかなかった。同じ年頃の子らは勿論、兄よりもっと年長の大人達とて勝蔵の馬鹿力には手を焼いていたからだ。勝蔵は毎日兄に挑んだ。兄は毎日勝蔵を庭に転がした。いつの日か兄を倒すのが幼い勝蔵の悲願であったが、それが叶う日はとうとう訪れなかった。
ついに父上の側でお役に立てるのだ、この腕で武功を挙げられるのだと瞳を爛々とさせていた十九の兄は、初陣から帰ってこなかった。
朝倉の城に一番乗りを果たし、血が逸ってか深入りしてしまい討たれたのだという。
家で敵無しの兄であっても、戦では呆気なく死ぬのだ。鬼や怪物のような敵を想像した。実際、幾度もの戦を生き延びている父は怪物と評されていた。全身の肉は岩のように堅く、勝蔵と三人の弟を一度に抱き上げ、雷鳴の如き声で笑う。牛馬ほども呑み食いするし、指は一本欠けていた。しかしその父でさえも同年に討死した。怪物の闊歩する戦場を見たこともないまま、勝蔵は森家の家督を継ぐこととなった。
兄に遅れること三年、初めて見た戦場には鬼も怪物も居なかった。居たのは芋のようにごろごろと数だけは多い坊主や農民で、具足も満足に揃わぬ者もあった。
見渡す限り全ての敵が、簡単に殺せそうに思われた。それでも長可は敢えて前に出ることはしなかった。若すぎる当主に家中の者らが不安を覚え、戦慣れした腕の立つ将を側に置いたのもある。長可に何かあれば、まだ声変りもせぬ蘭丸を立てるしかないのだから当然だろう。しかしそれ以上に、長可自身が自制していた。
ここで好きに暴れて、万が一にも命を落としては兄と同じだからだ。
長可は何としても兄を負かしたかった。父の武勇を見慣れた主君に落胆されたとしても、内弁慶の臆病者と家臣に謗られたとしても、戦に敗れたとしても初陣からは絶対に生きて帰らなければならなかった。兄の勝ち逃げを食い止める最後の機会がこの初陣なのだから。この縛りさえなければ、こんな獲物だらけの狩場で、誰が息を潜めてなどいてやるものか。指を咥えて遠巻きに祭を眺めるなど、本来長可の気性からは最も遠い振舞いだった。
◆
「本気で言ってんのか?」
主君がぴたりと動きを止める。室内の温度が急速に下がる。間合の外から家の者が上擦った声で呼ぶのを無視する。
「此度の戦、首のひとつも持たずに手ぶらで帰んのを良しとしたのはオレだ。オレが決めてオレがそうした。だがよぉ、殿は、織田信長は、あんなにも鳴らした攻めの三左の跡取りを、その程度だと思ってんのか? 帰ってくるだけで大手柄の木偶の坊だと? 舐めてんのかよ?」
大きな目玉が長可を見据えたまま、梟のように細められる。勝手なことを口走っている自覚はあった。しかし間違っているとは思わなかった。これはオレの問題だ。初陣を手ぶらで帰って大勝利だと笑うのは、自分だけに許されることだ。他の奴がそう言ったならそれは侮辱でしかない。長可だけでなく、長可に色濃く流れる可成の血に対しての。長可を鍛えた可隆の腕に対しての。たとえそれが主君であろうともだ。
「殿の初陣は十四と聞いたぜ。オレは今年で十六だ。あんたの目にゃ干柿しゃぶって喜ぶようなガキのまんまに見えるのかもしれねぇけどな、情けねえって、それでも森可成の息子かよって、嫌味のひとつでも寄越すところだろうがよ」
ばらり。
長可の放言を切るように派手な音を立てて扇子が開いた。ひらひらと緊張感なくはためくそれに虚を衝かれ、口が止まる。
笑っていた。
扇子の向こうに見えた顔は、人に見せるために作られた先刻の懐っこい笑顔とは全く違う、心底愉しそうな、滴るような笑みだった。
「勝蔵よ」
半間と離れていないのに、その声は遠くから、炎のように妖しく揺らめいて届いた。他の音は何も聞こえなくなる。長持に仕舞えそうなほど小作りな主君が急に自分より二回りも大きくなったような気がして、長可は眉を寄せた。
指先まで神経が張る。足が勝手に、いつでも立ち上がれるよう床板を確認する。頸の毛がぞわぞわ逆立つ。唾を飲み込みたいのを習い性で堪えた。長島には鬼も怪物も居なかったが、もしも戦場でこれに相見えていたら自分は───じっと息を潜めていられただろうか?
「さっきのは取消しじゃ。言い直そう───よう我慢したな」
ぱちり。
小気味良い音がして、夢から覚めたように視界がくっきりする。閉じた扇子が鼻先に当たるか当たらぬかの距離で差し向けられる。目の前の生き物は元通り小さくて、干柿を寄越した時の人好きのする顔に戻っていた。長可は目を瞬かせた。
「長島はまた直ぐに攻める。次は全勢力を投入して潰す。その時こそお前の初陣と思え。誰の息子でも弟でもなく、ただのお前のな───どれほど暴れてくれるやら、楽しみにしておるぞ」
広間を辞し、傅役の小言を喰らいながら歩き出してようやく、手の中で潰れていた干柿に気づいた。どれほど握り締めたやら、全く記憶にないが、哀れな干柿は破れた懐紙からはみ出して掌をべたべたと汚していた。指を口に運ぶ。甘ぇ、と思わず笑ってしまい、小言が長引いた。
一年後、長可は長島で二十七の首級を挙げ、長きに渡る初陣を凄まじい戦果で決着させることとなるが、そのことをまだ誰も知らない。
そしたらまた褒めてくれ(鬼ノブ)
転がした大筒の先端に点火すれば、すぐに火花が溢れ出した。火花は見る間に刃渡りを伸ばし、長可の身の丈を軽く超え、うわばみほどの長さにまで生長した。破裂防止のためにきつく縄を巻き締めた竹の筒をゆっくりと持ち上げ、縦に構える。轟轟と噴き出す火柱が夜空を舐める。重力に負けてちぎれた火のかけらがぱらぱらと風に舞う。
「大殿ぉ────────‼︎ 見えてるか─────⁉︎」
ひらひらと手を振る小さな影。何か叫び返しているようにも見えるが、耳元で暴れる炎の音しか聞こえなくて笑う。見えてるんならそれでいい。振り返した手にも火の粉が落ちる。一瞬だけ熱くて、そのくせ雪のようにすぐ融けて消えてしまう。この花火もそうだ、始まった以上はじきに消える。そういうところが好ましいのだ。
右の頬を焦がす熱、懐かしい火薬の匂い。長可の全身に細かな火花が雨あられと降り注ぐ。全天の星がどしゃどしゃ落ちてきているかのようだ。視界が豪華に焼けていくので、向こうの暗がりに居るはずの小さな影はもうよく見えなかった。この大盤振る舞いの星降る景色は持ち手の自分にしか味わえないものなのかと思うと、少し勿体ないような気もしてくる。あっちからはどんな具合に見えてるんだろうな。大蛇の如き火柱が天に突き刺さって見えてるんだろうか。そんなら降り注ぐ星は返り血だ。それはそれでさぞ壮観だろう。
ドッ、と何処かで聞いたような爆音が鼓膜をぶっ叩くと同時に、砲身が大きく弾んだ。火薬が尽きたのだ。かすかに痺れた手のままで、残り火を吐き出す大筒を抱えて歩き出す。まだ目がおかしいが方角は分かる。火薬の匂いしかしなくても、何処に居るかちゃんと分かる。
「──手筒ってよ、要はでっけえ火縄銃だったんだな」
「なんじゃそれ、余韻もクソもないのう」
星の降らない世界にだんだんと目が慣れて、おぼろげに輪郭が見て取れた。しゃがめと手振りで示され、そうする。なんか臭うぞ、どっか焦げとらんか、うわ髪熱ッ! などと騒がしく調べる手つきが髪をまさぐる。夜気に冷えた手は熱を吸い込んだ頭に心地よかった。
「変なこと考えたもんだよなぁ。天に向かっていくらぶっ放しても、誰を殺せるわけでもねえのによ」
あれほど焼いてやったはずの夜空は、何事もなかったかのように取り澄まして暗く、星も月も落ちてなどいなくて、しっかりと天に張り付いている。あれだけの火薬、銃に詰めたら何人殺せただろう。大筒に合わせたでっけえ弾を籠めりゃ城でも船でも壊せるだろうに。花火がきれいで、楽しくて、潔くて、良いもんだということは分かる。それでも何だか、食糧で遊んでいるのを見たような据わりの悪さを感じていた。きっとあの音が似すぎていたせいだ。
「ああ、鉄砲隊の役も御免となった太平の世の賜物よな。つまらんか?」
ぼんやり白く光る指が眉間の、ずっと昔に開いた穴のところを揉む。今の体じゃ穴は塞がっていて、指は入ってこられない。ここから脳味噌掻き回してくれた鉛玉は、どんなにきれいで楽しい銃火を噴き上げて飛んできたのだろう。音だけは鼓膜に焼き付いているが、気づいた時にはもう眉間だったから、火の花の記憶は残っていなかった。
「いや。侘びてんなって思う」
「で、あるよなー。正直わしの世で作らせたかったなー。竹千代に嫉妬」
「大殿は花火よりか物凄ェ派手な鉄砲作った方が似合いだぜ」
「侘びるなってか」
ぱちんと中指で、塞がった穴を弾かれる。蚊に食われたほども痛くねえし目から星も出ねえ。もっとくれ、とふざけて額を押し付けてみると、指の方が折れるわとけらけら笑った。目はもうすっかり宵闇に慣れ、こちらを見下ろす顔の甘さが月明かりだけでしっかり分かる。
「……大殿、最後までちゃんと見てたか?」
「瞬きもせんかったぞ」
「そっか」
指弾の代わりに柔らかな親指が眉間を撫でる。夜風に当たるうちに火照りが抜けたのか、もう冷たいとは感じなかった。戻るか、の言葉で立ち上がる。すたすたと歩き出す狭い歩幅を後ろから捕まえて肩に抱えた。竹筒などより余程身が詰まっているはずなのに、運ばれる気があるというだけで随分軽く感じる。
太く短く、お望みとあらば星だって降らせて咲き散ってみせるから────噴き出す火柱を今度こそ、ハネの瞬間まで特等席で、とっくり堪能してほしい。
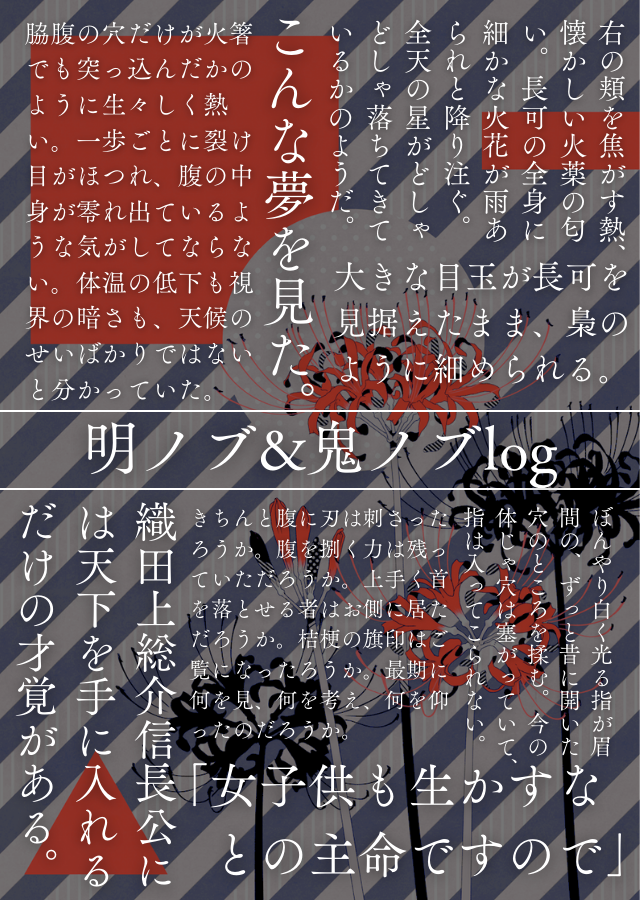
 ハイジロー
Link
Message
Mute
ハイジロー
Link
Message
Mute

 ハイジロー
ハイジロー ハイジロー
ハイジロー ハイジロー
ハイジロー ハイジロー
ハイジロー