一等星とワルツを チャイムが教室に響いて、起立、気を付け、礼。
授業用のノートを広げたはいいが、正直なところ、かなり眠たい。いや、授業中に寝てしまうとペンやら指し棒やら何やらが僕に向かって飛んでくる。……それは避けたい。避けたいけれど、眠気には、抗えな──。
「──ッで!」
「そこ! 授業を受ける気がないのなら、いっそのこと外に出ていろ!」
そう、こんなふうに。デジタルペンが頭にクリーンヒットして、当たった所がじん、と鈍く痛む。眠ってしまった僕も悪いけど、こうやって物を投げるのは教える側としてどうなんだろうか……そんな事をぼんやりと考えながら、言われた通り外に出ようと教室の扉を開けた。
この世界は、変わった。良くも悪くも変わりすぎてしまった。勉強や仕事は全てデジタル化。授業では生徒が個人のタブレットを持って小さな画面とにらめっこするし、仕事ではロボットが人間と代替わりした。そのロボットのメンテナンスに人間が起用される、という感じに社会は回っている。
政治や治安についてはよくわからないが、最近この都市──現代キョウトネシアの上空には空色のバリアが張られ、幼き頃に読んだ近未来SF小説のようになった。ここは極東の紛争地のように別の国や都市から襲撃されるわけでもないから、きっと機械化の発達を他国に
虚飾するためだろう。
さて、先ほど個人のタブレットを持っているとは言ったが、僕は未だにアナログタイプのノートとシャーペンを使っている。デジタルは楽でいいな、と羨むことなんて毎日のようにあるが、いかんせん液晶とにらめっこをしてデジタルペンを動かすことに慣れないのだから仕方がない。
ふわ、と何度目かのあくびをして、ふと横を見る。
「今、休み時間だっけ?」
「まさか! あら、あなた、顔から転んだの?」
「あー……いや、先生にペン投げられちゃってさ。赤い?」
「そうね、少し赤いかしら。治してあげ──ああ、隣は
種類違いね」
「じゃあ君は
僕らの形を真似た精巧な機械ってわけだ。ところで、君はなんで外に?」
「スリープモードだったのよ」
やっぱりお仲間じゃないか! と喜んだのも束の間。彼女は都市を支えるロボットなのだ。フル充電で二ヶ月、光による発電で半永久的には充電がなくならないはずである。……つまり、スリープモードになる必要はないのではないか?
「不思議?」
そりゃあ不思議さ、と口を開けた。いや待て、僕は今、頭の中でスリープモードになる必要はないと考えただけだ。どうして通じている? 最近クラスで流行りの読心術か、それとも僕は顔に出やすいタイプなのか。
「私、育てられたの。ちゃんとお父様とお母様がいるわ」
「……それは、開発者とか、君を組み立てた人じゃないの?」
「いいえ。確かに私を組み立てたのはお母様だけれど、れっきとした私と種類違いのお父様とお母様よ。だからほんの少しだけ、相手の表情から考えを読み取る事が出来るの」
彼女が得意気に目を細めるのを見て、嘘はないだろう、と思った。
基本ロボットというのは、工場生産が主である。工場生産のロボットは、ロボットに組み立てられ、僕らと同じように学校──もう学校なんて名称が古いけれど──で基礎知識を教えられる。よって、一ミリの誤差もないクローンのようなロボットを作り上げていく。
本来、人間はロボットのメンテナンスをするだけの存在であって、ロボットを
育てるなんてのは間違いなのだ。
けれど、彼女はどうも違うらしい。表情から感情を読み取ることは他のロボットにはない性能だし、何よりさっきの笑顔が証拠だった。
悶々と考えていると、彼女が口を開いた。
「私を育てて、二人はキョウトネシアからは急に居なくなってしまったけれど……あのね、ずっと種類違いさんに聞きたかったことがあるの」
「難しいことじゃないなら答えるよ」
「お父様とお母様が居なくなってしまったのは、どんな名の感情が正解なの? やっぱり、
シアワセかしら?」
僕は、とっさに首を横に振った。親と離れてシアワセ? そんなの、違う。僕らはいつまでも乳飲み子ではいられないのはわかるけれど、先ほどから彼女の話を聞く限り、優しいお父様とお母様だ。そんな二人が急に居なくなるなんて、何かあったのかもしれないのに、どこをどう見てシアワセだと思ったんだろう。
彼女はあら、と言うように首をかしげている。僕は話を仕切り直すために咳をして、彼女の方を向いた。
「えっと、それはシアワセじゃないよ。ある日突然、何も言わずに居なくなったんだろ? 僕たちの親は突然居なくなったりしないし、それに……シアワセは、僕らが追い求めて必死になるものだと、僕は思うから。君はお父様とお母様が居なくなった時、寂しくて悲しかったんじゃあ、ないの」
「……確かに、何も言わずに、それこそデータを削除するように消えてしまったわ。でも私は、その、欠陥品らしいから、感情がわからなくて。本で読んでも勉強しても、少しも理解できないの」
「心が錆びついてるってこと? 錆は磨けば取れるけど」
「違うの。この間、メンテナンスをしてもらったけれど……入っていない、と言われたわ。その時も、カナシミ? があるかどうかを聞かれたけれど、それすらわからなかったの」
欠陥品。最初から心がないなんて。僕たち人間の欠陥は、数十年前になくなったというのに。長くゆっくり進化してきた僕らと、短く早く進化したロボットたちでは、進化の過程も方法も、何もかもが違うし、工場生まれではない彼女に欠陥があってもおかしくはない。だって彼女は完璧なクローンではないのだから。
──わからない、と彼女は言うけれど、気付いていないだけなのかもしれない。もちろん、少ししか話していないし、根拠を言えと言われたら困ってしまうけれど。 もし本当に【心】はないとしても、そのパーツが体に使われているならば。彼女はきっと自分を欠陥品だと思い込んでいるだけで──。
「でもきっと、心は僕ら人間より強いんだろうね」
「あら、あなたたちの心の方が柔らかくて強いんじゃなくって?」
「そうかもね──ところで君、名前はなんて言うの? ……識別番号じゃなくて。お父様とお母様がいたなら、特定の言葉で呼ばれなかった?」
「エトワール……愛しい、エトワール。耳に残っているのは、その言葉よ」
何となく、想像はついていた。大切に育てられた、言葉遣いの美しい彼女の名。それは星。美しく煌々と輝く、一等星。
私の一番古い記憶。それは、目覚めてから少し経った私が、おじ様たちと踊る記憶。お母様からは社交ダンスの指導を受け、お父様からはマナーなどを教わった、三人で共有している大切なもの。
私はお父様とお母様の一人娘として、おじ様の手を取って、ドレスの裾を広げるの。くるりと回って、優雅なステップを踏んで。
ああ、ああ、素敵だったあの頃はもう帰ってこないとわかっているのに。理解しているのに。それでもまだ、求めてしまう。賑やかなあのダンスホールを、熱を帯びたあの空気を。
一人でタンゴを踊る。私を支える人はいないから、そのまま地面に倒れてドレスを汚してしまうの。誰にも好まれない、汚く憂鬱なタンゴのステップを踏みましょう、裸足で、冷ややかな床を慰めながら。
汚れたドレスのまま、一回転して。空に置かれた手を取る手がいつまでも現れないのは、きっと私のステップが下手だからね、なんて。ああ、また、ドレスが汚れていく。一人でタンゴを、ヴェニーズワルツを、フォックストロットを。どれを踊っても、満たされない。満たされないのは──何故?
月明かりが差し込むダンスホールで、今夜もドレスを汚していくの。
「……綺麗だね」
「ドレスを汚すこと? それとも私の見目かしら?」
「いいや、君の心が」
「心は……私の中に、入っていないのに?」
「気付いてるんだろ、本当は」
「……」
「部品はきちんとあるって、知ってるんだろ?」
「どこに、あるって言うのよ」
「……」
「質問に答えて」
「……君が、壊れないなら。それを約束してくれるなら、答える」
「約束するわ、だからお願い、教えて……!」
「エトワール、君の心は──」
指先から、ぼろぼろと崩れていく。
私がないと思い込んでいた心は、体の一部になっていたようで。処理が、追い付かない。どうすれば助かるのだろう。どうしよう。どうして。目が、水に溺れていくのなんて知らない。お父様、お母様。エトワールは、あなたたちのお星さま──いえ、星屑の方が正しいかしら──は、本当のお星さまに、なるかもしれないわ。
例え捨てられたとしても、エトワールは、あなたたちを信じるしかなかったのです。ダンスホールの冷たい床を慰めながら、二人の帰りを信じて疑わない他なかったのです。私の体が、体に埋め込まれた部品が、ダンスを褒めてくれたのを覚えていたから──死ぬまで、壊れるまで、充電がなくなり朽ちるまで、踊り続けるしかなかったのです。
──制服を汚して、追悼のワルツを。
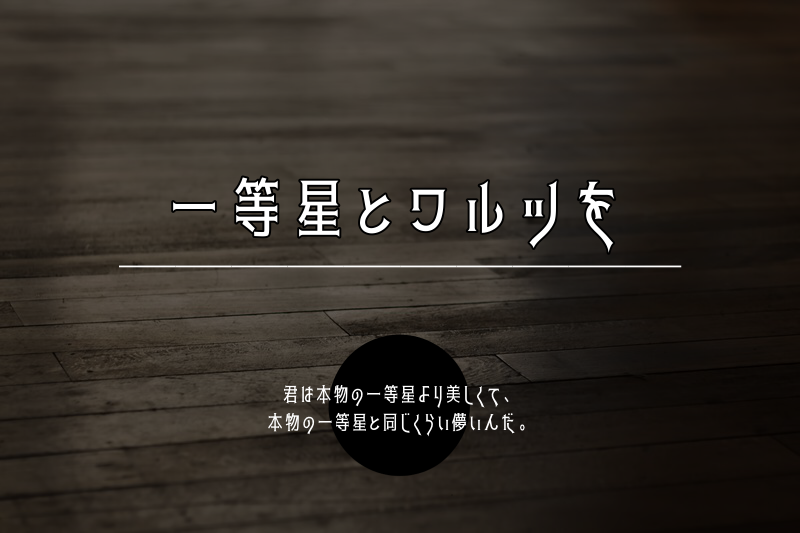
 潮屋
Link
Message
Mute
潮屋
Link
Message
Mute




 ステキと思ったらハートを送ろう!ログイン不要です。ログインするとハートをカスタマイズできます。
ステキと思ったらハートを送ろう!ログイン不要です。ログインするとハートをカスタマイズできます。

 潮屋
潮屋 潮屋
潮屋 潮屋
潮屋 潮屋
潮屋