【橙】Happy day! Happy day! Happy birthday!【ラーヒュンラー】「ずっと一緒にいたい。結婚してくれないか」
「は?」
ヒュンケルがラーハルトとエイミと共にダイの捜索に旅立って、初めて気づいたことがある。地上の魔族についてだ。魔王や大魔王の支配下に容易には落ちぬ、いわゆるロン・ベルクのような魔族達は一体どこにいるのか。今までそれを気にしたこともなかったが、ヒュンケル達がダイの捜索に向かうような場所、つまり人里離れた僻地にぽつりと小屋を見つけることがあった。戸を叩くと出てくるのは大概が蒼い肌をした魔族で、人間に追われてここに隠れ住んでいるのだという。情報交換をするヒュンケルやエイミの隣で、無言のラーハルトの怒気が強まるのが分かった。大魔王の侵攻が終わったことを伝えると、皆一様にほっと胸を撫で下ろしたようだった。
しかし、フレイザードによって根こそぎ人間が虐殺され、完全に人の国として滅亡したオーザムは違った。そこここに魔族の集落ができ、その噂を聞いた魔族が更に集まり、開拓をし交易を行い、今まさに魔族の国として成り立とうとしていた。新たな時代が始まる。ヒュンケルはそう実感した。
ダイの捜索は難航した。三ヶ月を費やしても手がかりが見えず、仲間たちは一旦フローラとアバンの待つカール城の会議室に集まった。天界や魔界の捜索も視野に入れるべきではないか、と話し合っているときに、「その前に海の中も探すべきだ」と提案したのは意外にもチウだった。かつて超魔生物と化したハドラーとの激突により北海に落ちたダイを捜索した経験からだった。至極もっともだとその意見は採用された。あれからメンバーの増えた新獣王遊撃隊から海洋モンスターが七匹ほどと、金属生命体で酸素を必要としないヒムを中心に、一行は根気強く海底の捜索に当たった。
その結果、ダイはアルゴ岬の南、かつてアルキード王国のあった場所の海底で見つかった。ダイの母親についての詳細を知っている仲間たちは、なにか運命的なものを感じざるを得なかった。カール城の一室に運び込まれたダイは、黄金色に光る半透明の繭のようなものに包まれた状態だった。それをじっくりと眺めたアバンは、「竜闘気の一種ですかねえ」と呟き、下手に繭をこじ開けるよりもこのまま自然に任せたほうが良いと提案した。皆はそれに賛同した。そしてダイはそのままカール城の一室で、飲食も排泄もせずに黄金の繭の中でこんこんと眠り続けた。一ヶ月経っても二ヶ月経ってもダイが目覚める様子はなく、代わる代わる様子を見に来る仲間たちをやきもきさせたが、引き上げられてから九ヶ月と半を数えて、ダイを包む繭に変化が起きた。徐々に輝きが衰えてきたのだ。これは大きな変化だ。そう思いアバンは各地へ散った仲間たちに急いで文を飛ばした。文を受け取り我先にと集まった仲間たちが固唾を飲んで見守る中、ダイは発見から十ヶ月後にその瞼を開けた。まるで産まれ直したかのようだった。ダイが目を覚ますと繭は霞のように消えた。
目覚めたダイは「ここどこ? 黒の核晶は?」ときょろきょろと周りを見回した。ダイに抱きついて大声で泣き出したのはまずポップだった。それから仲間たちは泣いたり笑ったり抱き合ったり様々で、ダイはいつぞやのようにもみくちゃにされた。今度こそ勇者は帰還したのだ。
ダイは特に不調もなく、出された病人食に「これじゃ足りない」と不満を言い、その後は「寝てるのなんて退屈だ」とカールの城内を散策していた。念のために医師の診察も受け、「まったく健康そのもので、問題ない」と太鼓判も押された。
その翌週にはダイはさっそくパプニカに移り、未来の王配としてふさわしい者になるべく、城内に居候しての帝王教育が始まった。と言っても、文字もろくに読めないダイにはまず初歩の初歩の勉学からだったが、ダイはあまり飲み込みの良い生徒とは言えなかった。
パプニカに迎えられたダイに追従し、ラーハルトは引き続き主人の護衛の任に就いていた。ラーハルトは少々ダイに対して過保護なきらいがあった。食事でダイの苦手なものが出ると代わりに食べてしまうし、ダイが勉強を放り出して遊びに行きたいと言うと、諌めるどころか飛竜に乗って共にどこぞに出掛けてしまう。そして遂にある日、机の上で行う勉学が苦手なダイが「授業の時間がつらい」とラーハルトに弱音を零して、パプニカ王室の手配した家庭教師をダイの勉強室から叩き出した。そして主人の未来の妻君たるレオナから直々に護衛の任を解かれた。「今すぐ荷物をまとめてどこへなりとも消えなさい」レオナは氷点下の声でそう言った。
ダイの無事が確認された後、ヒュンケルはバルジ島に唯一ある“バルジの塔”の守り人に着いた。バルジの塔は平時には特筆すべき役割はないものの、有事の際は兵の駐屯地となる。いざという時のために内外を整え、修繕をしておくのがヒュンケルの役目だった。兵站の備蓄にヒュンケルの食糧と日用品、塔の保守のための物資は、月に一度、主にマトリフ方式の海上を滑る無人船で届けられた。時折エイミを筆頭とした三賢者が、様子見ついでに気球で持ってくることもある。
毎日の朝食を終えると、ヒュンケルはまず塔の内外に劣化や異常がないか確認を行う。小さなひびや欠け、備品の修理程度ならそのままヒュンケルが補修を行った。滅多にそのようなことはなかったが、塔の劣化がひどく人手や物資が足りない、あるいは専門家の指示を仰ぎたい場合などは、パプニカ本土へ向けて伝書鳩で文を出し支援を依頼した。特に目立った異常がないときは、塔内部の掃除や汚れてきたリネン類の洗濯などの雑務をこなし、船着き場から塔へ続く道を整えるために木の伐採などを行った。手入れを行いながらも、ヒュンケルは存命の間にここが二度と使われることがないよう願うばかりだった。
そのヒュンケルの元に二、三ヶ月に一度、飛竜に乗って定期的にやってくる男がいる。ラーハルトだ。ラーハルトはレオナに解雇されてからは、マルノーラ大陸──旧オーザムにある魔族の集落のひとつに居を移していた。まだ開拓途中のオーザムでは仕事には事欠かないようだった。
ラーハルトはああ見えて恋多き男だったらしい。武人として主人のために生きていたときは本人も気付かなかったようだ。主人という拠り所を無くしたラーハルトは、今は恋人にそれを見出そうとしていたが、必ずと言っていいほど、いや、必ず振られていた。そうしてその度にラーハルトは酒をたんまり持ってヒュンケルの元に愚痴をこぼしにくるのだ。ヒュンケルには魔族の価値観というのはよく分からないが、ラーハルトはそれなりに美丈夫であるらしかった。振られてもすぐに次の相手は見つかるが、それもまたすぐに振られる。ラーハルトが来たときは滅多に飲めない酒にありつけるチャンスでも、ヒュンケルはそろそろ親友のことが心配でならない。
バルジの塔内にある大食堂で差し向かいに座りながら、ふたりはラーハルトの持参した酒を酌み交わしていた。
「また振られたのか」
「振られたんじゃない。振ってやったんだ」
「原因は?」
「『いい加減なところがムカつく』だとさ」
「たしか前の原因は?」
「『頭が固すぎて疲れる』」
ラーハルトは深くため息をついた。
「もうオレはどうしたらいいんだ……」
ヒュンケルはあえて返事をしなかった。
「ラーハルト。あれを見ろ」
壁一面に飾られた酒瓶を指差す。ゆうに五十本はある。
「あれはお前が振られるたびにここへ持ってきた酒だ」
ラーハルトは喉の奥から潰された蛙のような声を出してテーブルに倒れ伏した。
「こう……方向性を変えたらどうだ? 今までと違うタイプにも目を向けてみるとか、魔族じゃなくて人間の女性とか……」
「気の強い魔族の女がいい……」
親友のアドバイスにラーハルトはテーブルの上に倒れたままか細い声でそう言うと、今度は急に起き上がり勢いよくグラスをあおった。これは何を言っても無駄だとヒュンケルは溜息をついて天井を仰いだ。
さんざん女の愚痴を言うだけ言って酒を流し込んだラーハルトは、テーブルに突っ伏して寝息を立て始めた。ヒュンケルは酔い潰れたラーハルトを横抱きにかかえる。ぼろぼろになった体でもその程度の力は残っている。
ここには個別の寝室というような上等なものはない。いや、あるにはあるのだが、そこは有事の際に将校が使うものだ。ヒュンケルはいつも一兵卒の寝室となる大部屋を使っている。いくつかある大部屋の中でいつも使っている部屋の扉を開けると、十ある寝床のうちの手近なひとつにラーハルトを放り込む。出会った時はこんなに手のかかる男だとは思わなかった。ひとつ溜息をつくと、ヒュンケルは定位置になっている窓際のベッドに潜り込んだ。
夜半にラーハルトは目を覚ました。靴も脱がさず上掛けもかけられず、しかも枕に足を載せてベッドの上に寝かされていた。繊細そうな顔をしているくせにやることが雑なのだ。ヒュンケルは。
文句のひとつでも言ってやろうかと起き上がり、窓際のベッドで眠るヒュンケルの横に立ってその姿を覗き込む。ヒュンケルは横向きに丸まってすうすうと寝息をたてて熟睡していた。その寝姿はまるで無邪気な子供のようで、ラーハルトはすっかり毒気を抜かれてしまった。
ラーハルトはヒュンケルの隣のベッドに腰掛けると、ひとり滔々と考えた。先程ヒュンケルが言ったことも一理ある。方向性を変えるのも悪くない。魔族も人間と同じく、歳をとれば権力者でもない限り色恋の相手は見つかりにくくなる。ラーハルトも人間の歳で数えるともうそろそろ三十になる。このあたりで妥協というものを覚えても良いのかもしれない。
ベッドで眠るヒュンケルの顔を見やる。これだけ本音をさらけ出せる相手は初めてだった。ラーハルトは半魔ゆえに幼い頃から人間から迫害され続け、人を信じるということができなくなっていた。父を亡くして独り身だった母に良くしてくれた隣の家の老婆も、ラーハルトとつるんでいた悪ガキ仲間も、ハドラーの侵攻が始まった途端、揃って掌を返したように母とラーハルトに石を投げ始めた。せめて自分の外見がもっと人間らしかったらと苦悩したこともある。おぼろげにしか覚えていない魔族の父を恨んだときもある。幼い子どもには強烈な体験だ。心を閉ざすのも無理はなかった。唯一信じることができたのはかつての主人バランだけだったが、それはあくまで上司と部下という関係の上だった。対等な立場でお互いを信じ合い、物を言えたのは、ヒュンケルが初めてだった。それができたのはまずヒュンケルがラーハルトを心から信頼し、尊重してくれたからこそだ。戦友が全幅の信頼を置いてくれているというのに、それに応えないのは、戦士として恥ずべきことであった。
ラーハルトは立ち上がり、もう一度ヒュンケルの寝顔を覗き込む。いつも険のある顔をしているが、寝顔にはどことなく愛嬌がある。十分すぎるほど気も強い。気が強すぎて口を開けば説教ばかりしてくるが、不思議と共にいるのは苦痛ではなかった。どこか放っておけないところもある。そう、放っておけないのだ。人のことにはいつも口うるさいくせに、自分のこととなるとすぐに自暴自棄になる。そういった部分で人の手を必要とするのに、肝心の師や弟妹には頑として頼るまいとする。だったら他の誰かが面倒を見てやらなければいけない。
そっとヒュンケルの頬を指の背で撫でる。ここまでされても起きない。自分は随分とヒュンケルに信頼されている、そう驕っても構わないだろう。ヒュンケルの肌は陽光の下で旅を続けていたわりに、しみのひとつもなく滑らかだ。
かつての主人を除いて、これだけ長く同じ相手といたことはない。今誰よりも自分の近くにいるのは、ヒュンケルだ。他にない。そして誰よりもヒュンケルの近くにいるのは、自分だ。
ラーハルトは月光に照らされるヒュンケルの白銀の髪を静かに撫でた。
「ずっと一緒にいたい。結婚してくれないか」
「は?」
起きたばかりで布団から体を起こしただけのヒュンケルは、寝起きで焦点の合わない目をすがめてラーハルトを見返した。ラーハルトは先に起きていたようで、隣のベッドに腰掛けてこちらを向いている。ヒュンケルは幻聴だと思って寝癖のついたぼさぼさ頭を振る。
「寝起きでよく分からなかった。今何と言った?」
「お前とずっと一緒にいたい。俺と結婚してくれないか」
「すまん。体調が優れないようだ」
ヒュンケルはもう一度寝床に潜り込もうとする。
「待て。お前、幻覚か何かだと思っているな?」
「それ以外になにがある……」
再びすっかり布団に包まれたヒュンケルは絞り出すように声を漏らした。
「俺は本気で言っている。もう一度言うぞ。お前とこの先もずっと一緒にいたいから俺と結婚してくれないか」
ヒュンケルは力なくもぞもぞと布団の中に頭まで潜った。
「すまない……いよいよ具合が悪いようだ……。悪いが街まで飛んで行って医者を呼んできてくれ……」
「待て待て待て。どうしてそんなに信じられないんだ」
「つい昨日女に振られて管を巻いていた男に結婚しようなどと言われて信じる奴があるか!」
ヒュンケルは顔だけ布団から出して叫んだ。
「しかもなんでオレなんだ!? 手近で済まそうとしてないか!?」
「何事も妥協は必要だと悟った」
「オレは妥協案か!!」
語気を荒くしたヒュンケルは半身を起こしてラーハルトに枕を投げつけた。それはラーハルトにぽすんと当たって床に落ちた。
「それにこう……プロポーズをするならこう……あるだろう……花とか指輪とか……くそっなんでオレはこんな寝起きに寝癖頭で求婚されているんだ……」
心底から呆れたような顔でラーハルトが言う。
「人の趣味をとやかく言うのもなんだが……お前のそういうところ、どうにかならんのか? 夢見がちすぎてまるで穢れを知らない乙女のようだぞ。いい歳して」
ラーハルトの言葉で遂にヒュンケルの堪忍袋の緒は音を立てて千切れた。滅多に声を荒げることのないヒュンケルが、今すぐここから出て行けと叫んでラーハルトを部屋から蹴り出すと、今まで使ったこともない部屋の閂を閉めて布団の中で籠城を決め込んだ。
昼過ぎに空腹に耐えかねて部屋から出ると、ラーハルトの気配はなく、本当に帰ったようだった。軽い求婚もあったものだ、とヒュンケルは忌々しく食堂のテーブルに出しっぱなしになっていたパンをかじった。
ラーハルトが来ない。
ヒュンケルはバルジの塔の屋上の壁に寄りかかり、遠く海の上に広がる空を眺めながら嘆息した。
前は二、三ヶ月に一度は必ずヒュンケルの元を訪れていたラーハルトが半年も来ないのだ。今の恋人と上手くいっているのなら良いのだが、それは絶対にないという確固たる自信がある。長年の付き合いからくるヒュンケルの勘だ。
ヒュンケルもラーハルトも、お世辞にも弁舌の才があるとは言えず、この前のようにちょっとした行き違いで喧嘩をすることもある。しかし、いつもなんだかんだとうやむやに元通りの関係に戻っている。
高慢な男のように見えるが、実のところラーハルトは人一倍寂しがりやだ。自分も人のことを言えた義理ではないが、幼い頃に両親を亡くしたせいで甘え方というのを知らないようだった。人と付き合うための適切な匙加減が分からない。過度にダイに対して甘いのもそのせいだ。だから重いと言われて女に振られて、そこを改めると今度は軽いと言われて女に振られる。次から次へと恋をして振られてはヒュンケルのところで管を巻くのは、つまるところは人恋しいからだ。
ヒュンケルにとってもラーハルトは本音を言い合える唯一無二の存在だ。弟妹達にはこれ以上弱さを見せられないし、師にはこれ以上心配をかけられない。
そもそもこんな人里から隔離された辺境の守り人に着いたのも、人付き合いを厭うてのことだ。
ヒュンケルは幼い頃から親しい相手を作らずにいた。己の父バルトスの死に様から、“情は人を弱くする”と考えたからだ。父ほどの剣豪が人間の勇者ごときに負けるはずはない、負けたのは愛情深い父が相手に一片の情けを見せたからだ。そう思った。ミストバーンの元にいた頃には親しくなろうと擦り寄って来る者もいた。大魔王の腹心ミストバーン、その愛弟子。ヒュンケルはコネを作るにはこれ以上ない良物件だっただろう。ヒュンケルはその誘惑を跳ね除けてきた。
情は人を弱くする。かつてはそう思っていた。だがマァムの愛情に救われ、師と弟たちの誠情に支えられ、ラーハルトとヒムの友情に助けられ、ヒュンケルは今ここにいる。今のヒュンケルは断言する。情は人を強くすると。
様々な情に恵まれた今のヒュンケルでも、未だ知らないものがある。家族──伴侶への情だ。
この先も独りで生きていくといきがるのは簡単だ。かつての自分がそうだった。けれども結局は誰かの手を借り続けてヒュンケルはここまで生き延びてきた。人は独りで生きていくことは不可能なのだ。共に時を過ごす相手を見つけても良いのではないか。ラーハルトに求婚されてからそう考えることが多くなった。
マァムに対して愛情のようなものを感じるときはある。しかしそれは恋慕というよりも、雛鳥が初めて見たものを親だと思う、そういった感覚に近い。その自覚はあった。初めて触れた、自分にはない清く正しいものへの憧れ。一種の信仰のようなものだ。エイミは──ずっと見守っていてくれる彼女には感謝している。自分は彼女に対して特別な感情はないが、彼女は自分を好いてくれている。だが、それだけが理由では不誠実であるし、それではきっとお互い不幸になるように思えた。
結局、伴侶──共に時を過ごしたいと思える相手など、どれだけ考えてもひとりしか浮かばなかった。
ラーハルトは失恋二十八回目を数えて、オーザムの魔族の村にある酒場の二人席でひとり飲んだくれていた。向かいに座っていた女は随分前に「あなたってキザよね。キザってどう書くか知ってる? 気に障るって書くの」という言葉を吐いて去って行った。最初はラーハルトのクールなところが素敵、と言っていたくせに。負けなしの陸戦騎がこと恋愛となるとこのザマだ。いや、一度だけ負けた。ヒュンケルとの勝負だ。あのときに全てが変わった。
五本目の蒸留酒の瓶が空いたので店主を呼ぼうとしたとき、フードを目深に被った者が向かいの席に座った。マントで体が隠れているが、体格からして男なのは分かった。今は男にも女にも用はない。用があるのは酒だ。
「他の席も空いているだろう。そっちへ行け。今オレは気が立っている」
フードの男はラーハルトの言葉を気にかけず、店主に声をかけた。
「店主、ビールをひとつ。あとこいつには水をくれ」
聞き覚えのある声にラーハルトは目を見張る。
男はフードを取った。ヒュンケルだ。
「やれやれ。ここで人間は目立つな」
ラーハルトは面食らった。今までヒュンケルからラーハルトの元を訪れたことは一度もなかったからだ。
「どうしてここが分かった?」
「この辺りに住んでるのは聞いていたからな。女に振られては飲んだくれてる鬣みたいな金髪をしてる男を知らないかと聞いたらすぐ見つかった」
ラーハルトが顔が良いわりによく振られる恋多き男なのはこの一帯では有名だ。だがこれはなかなか屈辱的な探され方だ。
「なぜここへ?」
「お前の申し出、受けてやろうと思ってな」
「申し出、とは……?」
「自分で言っておいて忘れたのか」
ヒュンケルは懐から小箱を取り出すと、蓋を開けた。そこには紅いベルベットの生地の上に、華奢な白金の指輪がふたつ収まっていた。
「あのパプニカの名工の作だ。少し時間がかかってしまったが、品質は間違いない」
ヒュンケルはラーハルトの戦士らしいごつごつとした左手を取ると、指輪の片方をその薬指にそっと滑り込ませた。
「少しゆるいな……お前の指のサイズが分からなかったからな。とりあえず両方ともオレのサイズで作ってもらったんだが……。今度直しに行こう」
「これは……どういう……?」
ラーハルトは酔いもすっかり冷めて口をぽかんと開けた。
「お前、まさか本当にオレに求婚したのを忘れてるのか?」
「いや、覚えている……覚えているが……」
「あれから考えたんだ。お前のこういうダメなところ、放っておけない」
ヒュンケルは折り重なっている空の酒瓶を目で示すと、ラーハルトの左手を両手でぎゅっと握りしめた。
「お前とずっと共にいたい。結婚してくれないか」
「いや……その……いや……」
「それはノーということか?」
ヒュンケルは哀しげに眉を下げた。
「いや……その……」
「ではイエスということで良いのだな?」
一転、ヒュンケルはぱあっと顔を明るくした。
ちがう、とラーハルトが声を上げようとしたところで、間の悪いことに店主がビールと水を持ってやってきた。
「おうおうおう、いつも振られて飲んだくれてるにいさん、ついにゴールインか?」
ビールのジョッキと水の入ったグラスを豪快にテーブルに置くと、恰幅の良い魔族の店主はからかうようにラーハルトにそう尋ねた。
ちがう、とラーハルトが声を上げようとしたところで、ヒュンケルが返事をした。
「そうだ。いつも迷惑をかけたな」
「マジか! こちらさん、ご結婚だってよ──!」
店主の良く通る声が店中に響き渡った。
「マジかー! 今夜は祝杯だー!」
「ご結婚おめでとーございまーす! 乾杯!」
「乾杯!」
夜も深くなり、酒場にいるのはとにかく飲む口実が欲しい呑んだくればかりだ。あちらこちらで乾杯の音頭が上がり、酔っ払いたちが代わる代わるヒュンケルとラーハルトのテーブルにやってきては祝いの言葉をかけていく。それにヒュンケルはありがとう、とはにかんだ顔で答えた。
突然のことになにがなんだか訳も分からずそれを眺めながら、騒がしい空気に飲まれ酒が回ったラーハルトは机に突っ伏して酔い潰れた。
ラーハルトが目を覚ますと見知らぬ天井があった。ベッドに寝かされている。混乱して慌てて身を起こすと、窓辺に寄りかかりヒュンケルが外を眺めていた。
「目が覚めたか」
「ここは?」
「お前の家が分からなかったのでな。とりあえずオレの宿に運んだ」
ヒュンケルがこちらに向き直る。
「お前の寝顔、久々に見た。子どものようだな。愛嬌がある」
「それはお前も同じだろう」
「そうか?」
「そうだ」
ラーハルトは左手に違和感を感じた。目の前にかざすと、節くれだった薬指の第二関節に白金の指輪が引っかかっていた。それをじっと見つめる。
「やっぱり、嫌なのか?」
窓辺で月明かりに照らされたヒュンケルがそう尋ねた。
「そうじゃない……嫌ではない、嫌ではないんだ。ただ……」
言葉を探すようにラーハルトを天井を見つめた。
「ただ……随分と遠回りをしたものだと思ってな」
その言葉にヒュンケルは柔らかく笑う。
「探し物とはそういうものだ。忘れた頃にひょっこり出てくる」
「青い鳥のようにか?」
「そんな童話もあったな。そうだ。探してみれば、案外近くにあるものだ」
「お前もそうだったのか?」
「そうだな。お前よりは早かったが、遠回りはしたな」
ラーハルトは立ち上がり、窓辺に立つヒュンケルの隣に寄り添うように並んだ。
「今日は月が綺麗だ」
そう言いながら窓の外を眺めるヒュンケルの白銀の髪は月明かりに照らされて、いつもより一層きらきらと輝いている。
ラーハルトはヒュンケルに問うた。
「口付けをしてもいいか?」
「もちろん」
満月の光に照らされながらラーハルトはそっとヒュンケルの薄い唇に自分のそれを重ねた。それだけでまるで初恋の人に初めて触れた少年の頃のように胸が高鳴った。ヒュンケルの唇は冷たく硬くかさついていて、今まで触れたどんな女のものとも違った。
触れるだけの口付けを終えて唇を離すと、ヒュンケルが口を開いた。
「……もし、よければ、このまま一緒にお前の家に行きたいのだが、よいだろうか?」
ヒュンケルは少し他人行儀にそう言うと、月のように静かに笑った。
答えの代わりにラーハルトはもう一度口付けた。
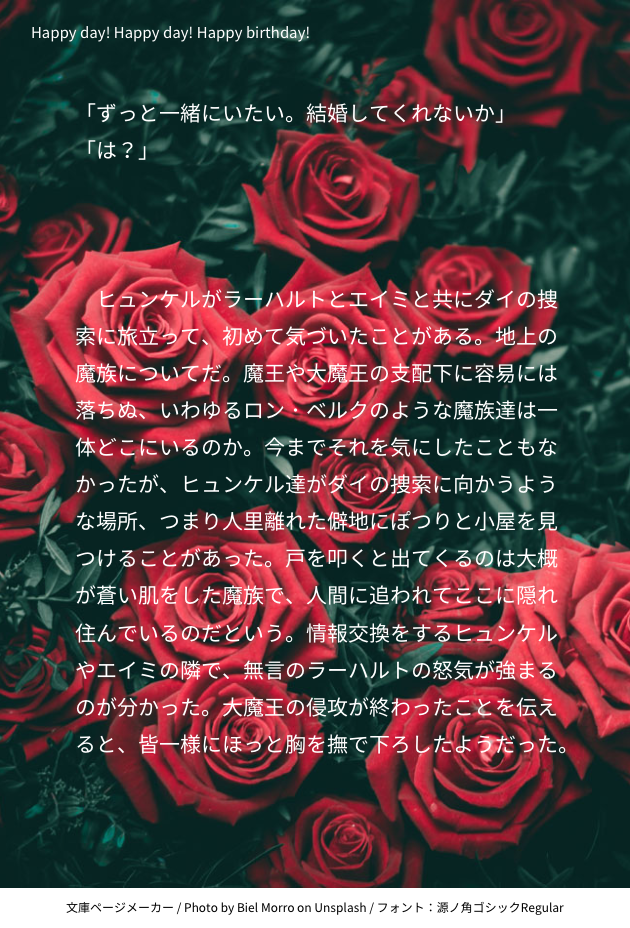
 コージ
Link
Message
Mute
コージ
Link
Message
Mute




 ステキと思ったらハートを送ろう!ログイン不要です。ログインするとハートをカスタマイズできます。
ステキと思ったらハートを送ろう!ログイン不要です。ログインするとハートをカスタマイズできます。

 コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ