【橙】なんでもない日、おめでとう【ラーヒュンラー/ヒュンラーヒュン】 何もせずとも毎朝決まった時間に目が覚める。これは戦士だった頃の名残りだ。
ぎしぎしと音がなる古びたベッドから起き上がる。ひとつ伸びをして寝床から出る。ベッド脇の棚の上にある水差しから盥に水を移す。冷たい水で顔を洗う。
手拭いで顔を拭きながら窓から空を見やる。今日は洗濯日和になりそうだ。
随分と所帯染みてきたものだ。そう思ってラーハルトは苦笑した。
ラーハルトはダイに死ぬまで付き従うつもりだった。それが、義理の父──そう呼ぶのは今でも大変おこがましく感じるが──であるバランの願いでもあったからだ。
ダイは無事に救出され体も整い、育ての親であるブラス老のところへ帰ると決めた。そしてラーハルトにこう言った。もう戦う必要はないのだから、自分に付き従う必要もない。どうかラーハルト自身の人生を生きて欲しい、と。
ラーハルトは戸惑った。戸惑ったが、なによりも主人の願い──命令だ。否という選択肢はなかった。
ヒュンケルも、ダイが見つかったことでもう流離う必要はなくなった。戦の時代でもない。むしろそう願って平和を勝ち取ったのだ。
だから、ラーハルトとヒュンケルのどちらともなく、共にどこかへ腰を落ち着けよう、という話になった。
知己がいるのはパプニカとカールだ。
パプニカの王女──今は女王だ──のレオナは、ラーハルトとヒュンケルと共に戦った仲だ。しかしパプニカはかつてヒュンケルが一度滅ぼした国だ。心中穏やかではない国民もいるだろうし、なによりヒュンケル自身が顔向けができなかった。
同じくカールはフローラとアバンが共同で王座を守っているが、カールはバランが蹂躙した国だ。ラーハルトも多少の後ろめたさを感じた。
考えた末、ふたりは国王が事情に厚いテランに腰を落ち着けることにした。
不本意ながらも一緒に旅をした仲だ。筋を通すためにエイミにもそう伝えると、「どこかあてはあるの?」と聞いてきた。ヒュンケルがかぶりを振ると、エイミはレオナを通してテランの国王に相談したようだった。そしてテラン王はベンガーナとの国境にある小さな村を紹介してくれた。以来ふたりはエイミには頭が上がらない。
その村の南外れにある山の中腹に、古びたあばら家があった。元は国有林である山の管理人が住んでいた家であったが、テランは過疎化が進み、人材も懐の余裕もなくそのまま捨て置かれていた。山の管理をすることを条件に、テラン王が無料でそれを払い下げてくれた。「あばら家を建て直してやることもできない貧しい国庫だが、せめてこれくらいは」と、年に僅かばかりの管理料も貰っている。
ラーハルトもヒュンケルも手先は器用な方だった。幸いにも家を修理するための材料は山にいくらでもある。そうして最初はすきま風に晒されながらも少しずつあばら家を直して、なんとか家と言える形にまで整えた。居間と厨房と寝室がふたつと客間がひとつ。それがラーハルトとヒュンケルの新しい城だった。
青みを帯びた肌に、長く尖った耳。一目で魔族の血が流れていると分かるラーハルトが里山に住み着いたことで、村の住人はざわついた。無理もない。魔王、そして大魔王の脅威に晒されてからまだ数年も経っていなかった。
ラーハルトとヒュンケルが山に住み始めてからふた月目、とある日の夕暮れ時だった。村の代表を名乗る人が数人、ふたりの家の玄関先へとやってきた。曰く、魔族を村の近くに住まわせることはできない、と。血気盛んな連中を止めるのもいよいよ難しくなってきた、とも。
またこれか、とラーハルトは諦観した。旅の途中でもよく遭遇した。宿から追い出されたことすらあった。差別、というやつだ。
「……少し、村の皆と話をさせはてもらえないか?」
ヒュンケルがそう言うと、村の代表たちは玄関先で顔を突き合わせて何か相談を始めた。相談を終えると、顎髭をたくわえた初老の男がこう言った。
「では、臨時で民会を開きます。一時間半後に村の議場まで来てください。場所は分かりますか?」
ヒュンケルはゆっくりと頷いた。
代表者たちが慌ただしく帰っていくと、ラーハルトはヒュンケルの肩をつかんだ。
「おい、ヒュンケル。一体どうするんだ」
「オレに考えがある」
「お前の考えは大抵ろくでもない。テラン王に任せた方が良いのではないか?」
「命令はできる。でもそれでは人の心は動かせない」
「だが」
ラーハルトがなおも食い下がると、ヒュンケルは少しだけ顔を伏せると、懐かしげに目を細めてこう言った。
「弟妹達によく言われたよ。『お前は言葉が足りない』とね」
ヒュンケルは顔を上げると、ラーハルトの肩を軽く叩いた。
「まぁここはオレに任せておけ」
一時間半後、ラーハルトとヒュンケルは議場の議長席にいた。任せろと言われたもののラーハルトは不安で胃が痛んで吐きそうだった。どんな強敵と対峙してもこのようになったことはない。
大魔王が斃れてのち、国王が質素倹約の手綱をいくらか緩めるようになってから、テランにもぽつりぽつりと人が戻り始めていた。また、魔王軍の侵攻がなかった唯一の国ということもあり、壊滅的な被害を受けた他国からの移住者も増えた。今のテランの人口はかつての倍以上に膨れ上がっていた。議長席からラーハルトが人々を一瞥すると、さして広くもない議場には、老若男女、ざっと20人ほどの村人が詰めかけていた。今まさに魔族の青年を目の前にし、村の者の様子は落ち着かないようだった。あからさまに殺気立った視線を投げかけてくる者もいた。
「もういいだろうか?」
そんな中、隣のヒュンケルが、後ろに控えた顎髭の初老の男──どうやら村の有力者らしかった──に確認を取ると、ゆっくりと口を開いた。
「ご足労いただき申し訳ない。村の皆が魔族が住んだことに不安に感じていると聞いた。そのことで少し話をさせてもらいたい」
さすが元不死騎団長だ。張りのある良い声をしている。
「皆が不安に思う気持ちも理解できる。我々はつい数年前まで大魔王の脅威に晒されていた。多くの魔族たちが大魔王の邪悪な意志に操られ、人々を脅かした。ラーハルト……彼もそうだ。彼が人を害したことがないとは言わない。だが勇者によって大魔王は倒され、全てが変わった。もう変わったんだ。それに人を害するのは魔族だけとは限らない。人同士で傷つけ合うこともあるだろう。彼ばかりを色眼鏡で見るのはやめてもらえないか。彼が人を傷つけるようなことは絶対にない。オレが保証する。だから1年……いや……半年でいい。様子を見てはもらえないか。どうか、頼む」
そう言ってヒュンケルは深々と頭を下げた。あの人並み外れた矜持を持つヒュンケルが、だ。
ラーハルトはかつて自らの意志で人を憎み、バランの元で人々を踏みにじった。ヒュンケルは人の身でありながら魔王軍に属し、人々をその手にかけた。
事実とほんの少しの嘘が混ざったそれは、実直で不器用なヒュンケルが紡げる、精一杯の誠意に満ちた言葉だった。それはなによりもラーハルトの心をついた。
頭を上げたヒュンケルは、目を伏せると静かな声でぽつりとこう言った。
「誰にでも“家”は必要なんだ」
議場は水を打ったように静まり返った。
さらにヒュンケルはこう付け加えた。
万が一にも彼が人を害するようなことがあれば、オレが彼を殺す。そして責任を取ってオレも死のう、と。
それからもうすぐ二年が経つ。
日々の山の間伐や木々の世話。ヒュンケルはそれに加えて、ときどき村で小間使いのようなことをしている。隣村へ物を届けたり、野良仕事の手伝いをしたり。子守を頼まれた日には、真夏の野良仕事のあとよりもふらついた足取りで帰ってきた。
ラーハルトは人里に降りるのを好まない。その代わりに里近くに野獣や魔獣が出たときがラーハルトの出番だ。槍の冴えには一点の曇りもない。駆除はお手の物だ。必要ならば剣も弓も使った。
そうして得た小金と肉と毛皮と、庭にある小さな菜園。ふたりで生きていくにはそれだけで充分だった。
パンとチーズとミルクだけの質素な朝食を終えると、ヒュンケルとラーハルトは井戸のそばに家で一番大きな盥を出し、溜まっていた洗濯物を片付け始めた。ラーハルトが洗い、ヒュンケルがそれを絞って干す。いつもその役割だ。
そのかたわらで雑談を交わすのが、共に暮らす間に日課のようになっていた。
「たしか今日は“おつかい”の日だったか」
からかうようにラーハルトが言うと、ヒュンケルは不満げに眉根を寄せた。
「“仕事”だ」
その憮然とした言い様にラーハルトは鼻を鳴らした。
「で? 今日の仕事はどこだ」
「三つ角の大工の爺さんのところだ」
「あそこか。で、何を?」
「爺さんに初孫が生まれたらしくてな。はりきって赤子用のベッドをこしらえたから、隣村の孫の家まで運んで欲しいと……」
「代わる」
「なんだって?」
「その仕事、代わる」
「お前、村は苦手だと言っていただろう」
木に結んだ物干しの紐に洗った上衣をかけながら、ヒュンケルはそう言った。ラーハルトはその鼻先に濡れた指を突きつけた。
「何度言ったら分かる。お前は全身ボロボロなんだ。力仕事は自重しろ」
「赤子用のベッドくらいどうでも……」
「あの女にもきつく言われている」
ラーハルトの言うあの女、とはエイミのことだ。エイミは無事にダイが見つかったあと、なんとかヒュンケルの体を治せないか、その方法を探しにパプニカへと戻り東奔西走している。
ラーハルトとヒュンケルとエイミ、三人でダイを探す旅をしている間、こんなことがあった。
ロモスの山間部を旅していた時のことだ。もう五日も山での野宿が続き、さすがに旅慣れたラーハルトも辟易していた。あと一つ峠を越えれば村でまともな食事と寝床にありつける。その勢いに水を差すかのように、エイミが先頭を歩くラーハルトに声をかけた。
「ラーハルト。今日はもう峠を越えるのを諦めて、休む場所を探しましょう」
「馬鹿を言え。まだ日暮れまでには時間がある。雨の気配もない。この峠を越えればようやく村だ」
「日暮れまでに村には間に合わないわ」
「急げば間に合う」
「長旅よ。無理はやめて、諦めて野営しましょう」
「うるさい女だ。休みたければ一人で……」
そう言いながら睨みつけたラーハルトの顔を、まるでなにかを訴えるかのようにエイミはじっと見つめ返した。その瞳に何かを感じ取ったラーハルトは、ふっと顔をそらした。
「そうだな……長旅に無理は禁物だ。休む場所を探そう」
山道から山中へ少し分け入ると、樹齢何百年かというほどの大樹があった。その根元を野営地に決め、枯れ枝を集め火を起こして周囲に座り込んだ。すると、堅いパンと干し肉だけの簡素な夕食もそこそこに、ずっと黙っていたヒュンケルが大樹に寄りかかり寝息を立て始めた。その顔を見つめてエイミが言う。
「……ずっと無理をしていたのよ。朝から具合が悪かったのに」
「……よく分かったな」
ヒュンケルは口が裂けても自分から体調が悪いなどとは言わない。
「好きな人のことだもの。顔を見ればなんだって分かるわ」
ヒュンケルの肩にエイミはそっと毛布をかけてやる。
「私のことは別にいい。勝手に付いて来たんだもの。付いて行けなくなったら置いて行って構わない。でも、ヒュンケルはそうじゃない。もっと気にかけてあげて」
エイミは悲しげに長い睫毛を伏せた。
「……もう、前の彼とは違うの」
「……善処しよう」
ラーハルトはそう答えるしかなかった。
「ひとつ聞かせてくれる?」
エイミはラーハルトの顔を見上げた。
「ヒュンケルはあなたのなに?」
「……友だ」
そう答えるラーハルトの黄玉の双眸を、エイミの黒曜の瞳がひたと見据えた。
「本当に?」
「…………」
ラーハルトは押し黙った。
ようやく洗濯物を洗い終え、盥を抱え上げるとラーハルトは言った。
「今日のお前の仕事はオレが代わる。おまえは菜園の手入れをしていろ」
「しかし、使わなければ体が鈍る」
「庭で素振りでもするんだな」
ヒュンケルは最後の洗濯物を手に不満な顔を露わにしていたが、ラーハルトは見なかったことにした。
約束は十一時だとヒュンケルは言っていた。ラーハルトの体内時計は正確だ。きっかり十一時に、村の三つ角にある大工の爺さんの家の扉を叩いた。内側から扉が開くと、爺さんは目を丸くした。
「ありゃ? 魔族のあんちゃんじゃねえか。銀髪のにいちゃんはどうした?」
「事情があってな。オレが代わりに来た」
村では今もラーハルトと距離を置く者が半分、気さくに接する者が半分、といったところだ。三つ角の大工の爺さんは、ラーハルトにも気安い人間の一人だ。
手先が器用なラーハルトとヒュンケルでも、さすがに家具を作るのは困難だった。家具のほとんどは中古で揃えたが、一部はこの爺さんの作だ。爺さん、と言っても、髪こそ白く顔や手に皺があるものの、背筋はまっすぐで動きも矍鑠としている。
「それで? 赤子用のベッドだと聞いているが」
「おう、こっちだよ」
手招きされ家の中へと入る。すると居間の一角に小さいながらも見事なベッドが鎮座ましましていた。花をモチーフにした優美な細工が全体にあしらわれている。大した腕だ。
「見事な細工だな」
「へへっ、ありがとよ!」
素人目に見ても繊細に彫刻が施された、美しい、とさえ言えるベッドを眺めながら、ラーハルトはあることに思い至った。
「爺さん、さては孫は女だな?」
「あたり! わかったか? あんちゃん、にいちゃんより鋭いな!」
あの鈍いも鈍い、鈍い男の中の鈍い男、鈍さの化身であるヒュンケルと比べられたくはない、とラーハルトは心の中でだけ思った。
「作業場に置いといたんだけどな、仲間に『自慢かー』って言われてうちに持ってきたんだ。運ぶの大変でな」
赤子用のベッドといえど、普通の人間が運ぶのであれば荷車や荷馬車が必要だ。方針としては穏やかにはなったものの、未だ質素倹約を国是とするテランではそれも贅沢品だ。この村にも一台二台あるかないかだろう。それも誰かが先に使っていればそれでおしまいだ。
そういうときに未だ人並み外れた筋力を持つヒュンケルは重宝されていた。
ラーハルトはひょい、とベッドを片手で抱え上げた。
「おお、あんちゃんもすげぇなぁ」
「西の村でよかったか?」
「そうそう、村の入り口からそのまま西へまーっすぐ。半日ってとこかな。セニア村ってとこだ。誰かに『赤ん坊が生まれたシーナん家』って聞けば分かるさ」
常人の足で片道半日なら、ラーハルトならそれで行って帰ってこられる。
「ついでだ。爺さんも孫の顔を見に行くか? 行くなら背負ってってやるぞ」
ラーハルトにとっては老人一人など羽毛と変わりない。だが、爺さんは虚をつかれたような顔をすると、豪快に笑い出した。
「こりゃ傑作だ! いつもぶすっくれてるあんちゃんも冗談を言うんだなぁ! いくらあんちゃんが力持ちでも、俺を背負ってなんか行ったらへばっちまうわ!」
爺さんは目の端に涙を浮かべながら笑っている。
「生憎と俺はこのあとも仕事でさ。孫と娘にはあとでゆ────っくり会いに行くからよ。あんちゃん、ありがとな」
そう言うと爺さんはラーハルトの背を力強く叩いた。
道行は順調だった。壊れ物の荷に万が一のことが無いように、速さは少し抑えて歩いた。それでも人が見れば走っているように映っただろう。村を出てから四時間弱、というところで、遠目に村を囲う塀が見えてきた。あれがセニア村だろうか。
村の入り口にはささやかな看板が掲げられていた。セニア村。ここで間違いない。
ラーハルトは村に入ると、まず通りすがりの青年をつかまえて、「赤子が生まれたばかりのシーナの家」までの道順を尋ねた。青年はラーハルトの外見におっかなびっくりしつつも丁寧に道を教えてくれた。単に怯えていただけかもしれないが。
青年に教えられたとおりの道を行く。目印は青い屋根だと言っていた。青い屋根の家──あそこだ。
青い屋根の家の扉をノックすると、中から黒髪で中肉中背の、いかにも人のよさそうな下がり眉の青年が出てきた。年の頃はラーハルトとそう変りないだろう。青年はラーハルトの姿を見て身構えたようだったが、爺さんの使いだ、と告げると緊張を解いた。
「さっそくだが、贈り物はどちらへ?」
「妻も娘もさっき寝たところで……。あとで僕と近所の父で寝室に運びますから、とりあえず居間に」
下がり眉の青年が先導し、ラーハルトは居間の入り口近くにベッドを据える。
「お義父さん……こんなに立派なものを……」
贈り物を眺めながら、青年は感極まったように涙ぐんでいた。
「それでは、これで」
「あの」
用を終えて去ろうとしたラーハルトを青年の声が止めた。
「こんなに重いものを運んでさぞご苦労だったことでしょう。今からあちらに戻っては途中で日も落ちてしまいます。せっかくですから、うちに一晩泊まって行ってください。大したおもてなしはできませんが……」
青年の精一杯の申し出を、「お子さんが生まれたばかりで色々と大変でしょうから」とラーハルトは固辞した。それは半分は本音で半分は建前だった。ラーハルトは未だにいわゆる“普通の人”と接するのが苦手だった。
下がり眉の青年は「本当にありがとうございました」と、ラーハルトが路地の角を曲がるまでずっと頭を下げ続けていた。
セニア村を後にすると、ラーハルトは道の端に座り込んだ。持ってきたパンと干し肉で遅い昼食をとる。食事を終えて立ち上がるとラーハルトは伸びをした。行きは壊れ物を運んでいたので全力を出せなかったが、帰りは身ひとつだ。
ラーハルトは風を置き去りにして疾り出した。
予想通りに、日暮れ前には自分の村へ戻ることができた。
まずは大工の爺さんのところへ無事に荷を運び終えたことを報告に向かった。
「ありがとよ! これが約束の仕事代だ。これは孫が生まれた振る舞い酒だ。もらってくれな」
そう言って爺さんは瓶に入った上等なぶどう酒をラーハルトに渡した。樽入りの、水で割って飲むぶどう酒は酒場にいくらでもある大衆的なものだ。しかし、水で割らない、瓶とコルクで密封されているものとなると、ここテランではまだ高級品だ。
「爺さん、いいのか? こんな高価なものを……」
「無粋なことは言いっこなしだ! 黙って持っていきな」
「……では、ありがたく頂戴する」
ラーハルトは、万が一のことがないよう、丁寧に瓶を抱えなおした。
ラーハルトとヒュンケルの住む山は村の南、ベンガーナ側にある。ぶどう酒の瓶を抱えながら、村の南から里山へ続く細い道を行く。家に続く道は手入れをしておらず半ばから獣道になる。なぜか充足感に胸がいっぱいで、その道を殊更ゆっくりと登っているうちに日が暮れてきた。家は山の中腹の開けた場所にある。自分の家に明かりがついたのが見えた。
「今帰った」
明かりの漏れる家の戸を開けると、そう声をかける。
「おかえり。ちょうど夕食ができたところだ」
ヒュンケルは居間から続く厨房で何やら鍋をかきまわしていた。
「南瓜がよくできていた。シチューにしてみたんだが……」
今よそってやるから待っていろ、と、ヒュンケルは棚から皿を二枚取り出した。その間にラーハルトは居間のテーブルにぶどう酒の瓶を置き、厨房にある水瓶から水を汲んで手を洗った。
食卓の上には朝にも食べたパンとチーズと、干し肉とくず野菜と南瓜のシチューが並んだ。傍らにはぶどう酒の瓶がある。ラーハルトの差し向かいに座ったヒュンケルは、まず首にかけているアバンのしるしを手に取った。ダイが無事に見つかって以来、ヒュンケルはアバンのしるしを手に食前の祈りをささげるようになった。何に祈っているのかは知らないが、神に祈るような男ではないことは知っている。それが終わるのを待ってラーハルトは食事に手をつけた。
まずラーハルトはヒュンケルの作ったシチューをスプーンで一口含んだ。南瓜がほっくりとしていて甘い。
「……なるほど。本当によくできているな」
「だろう? 今年は当たり年だ。他の作物も楽しみだな」
ヒュンケルはぶどう酒の瓶を見やる。
「この瓶はなんだ?」
「大工の爺さんから酒をもらった。振る舞いだと」
「酒なんて久しぶりだな。食後に一杯やろう」
そう言いながらヒュンケルはパンをちぎった。
肉体労働を終えたばかりのラーハルトはシチューを二回もおかわりした。ラーハルトの皿にシチューを盛ってやりながら、ヒュンケルは「良い食べっぷりだ。作り甲斐がある」と笑った。
夕食を終えたふたりはさっそくぶどう酒をいただくことにした。保存が悪いと酒も傷んでしまう。専用の酒器などという洒落たものはなかったが、かろうじてガラス製のグラスが一対あった。コルク抜きは、以前メルルから「ヒュンケルさんの体にいいと思うので」と薬草酒をもらった時に買った。
やけに慣れた手つきでヒュンケルがコルクを抜いてグラスにぶどう酒を注いだ。ぶどう酒は紅玉のような鮮やかな赤で、絹に似た艶があった。
ヒュンケルはぶどう酒の杯をランプに掲げて光に透かしてから、顔を近づけて香りを嗅ぐと、独りごちるように呟く。
「軽やかだな……祝いに相応しい。果実の香り……ベリーにカシス、スパイス……土の匂いもするな」
「分かるのか?」
「少しだけな」
ヒュンケルは大魔王のお気に入りでもある不死騎団長だった。上等な酒を飲み慣れていても不思議ではない。
「乾杯」
ヒュンケルはそう言ってグラスを掲げた。
「何にだ?」
ラーハルトが尋ねるとヒュンケルは目を泳がせた。
「まぁ……特にないが……。そうだな……なんでもない一日に、乾杯」
なんだそれは、とラーハルトは吹き出した。
「そこは『爺さんの初孫に』ではないのか?」
「それもそうだな。では、爺さんの初孫に乾杯」
「乾杯」
そう言ってふたりはグラスを高く掲げてから口をつけた。
今ならあのときのエイミの問いに答えられるかもしれない。なぜだかラーハルトはそう思った。
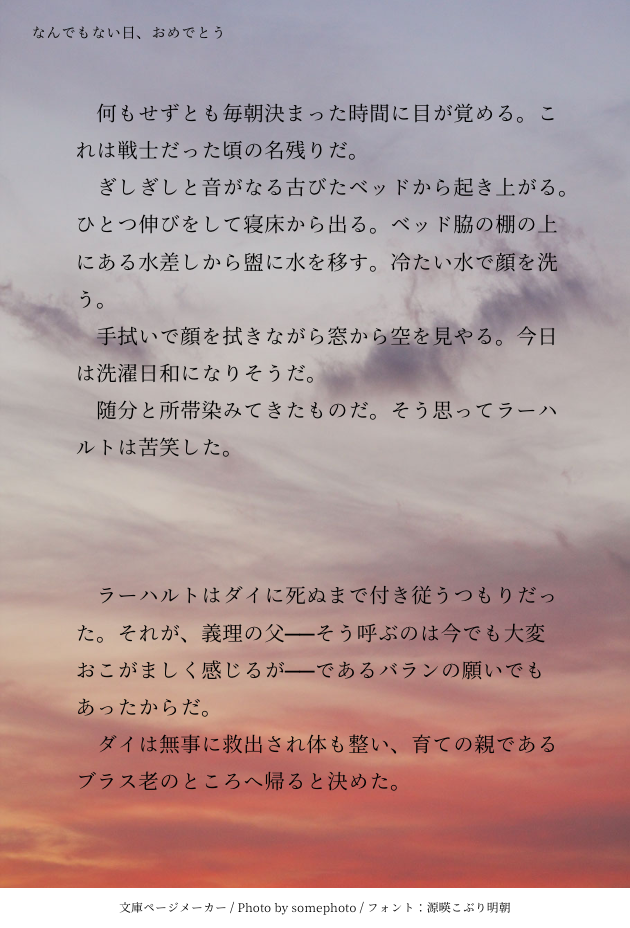
 コージ
Link
Message
Mute
コージ
Link
Message
Mute



 ステキと思ったらハートを送ろう!ログイン不要です。ログインするとハートをカスタマイズできます。
ステキと思ったらハートを送ろう!ログイン不要です。ログインするとハートをカスタマイズできます。

 コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ