【橙】青い季節【ラーヒュンラー/ヒュンラーヒュン】「湯治って知ってる?」
「トージ?」
ヒュンケルが執務室を訪れると、レオナはいきなりその言葉を発した。それを鸚鵡返ししてヒュンケルは黙考した。
「いや、知らない」
ヒュンケルの頭の中の辞書にその言葉はなかった。
「じゃあ、温泉って知ってる?」
「ああ、それなら知っている。地底魔城の付近には死活火山があって、湯がふんだんに湧き出していた。オレもよくそれで湯浴みをしていた」
「それなら話は早いわ。湯治っていうのはね、その温泉に日に何回も、続けて何日も……ときには何ヶ月も入る健康法なの。不思議なことに、それで魔法でも医師でも治せない怪我や病気が良くなることがあるのよ」
大魔王との戦いから帰還してそれまでの疲労で昏倒したヒュンケルは、目覚めてすぐ何人かの医師や僧侶に代わる代わるに診察された。しかし皆口を揃えて「こんな症例は初めてだ。治療法も皆目見当がつかない」と首を横に振るばかりだった。
「あなたの体もひょっとしたらそれで良くなるかもしれないわ。王家の別荘がいくつか無事だったから、王都に一番近いところを使えるように用意させたわ。湯治に行ってきなさい」
有無を言わさぬレオナの言いぶりに、ヒュンケルは口を開く。
「だが、今はダイの行方を……」
「体が満足に動かないあなたがいて何か意味がある?」
ポップはルーラを利用して各国の連絡役に文字通り飛び回っている。力自慢のマァムは城下の復興の手伝いを買って出た。一方でヒュンケルはというと、今は一日の大半をベッドの上で過ごすだけだった。レオナらしい直截で辛辣な物言いにヒュンケルは素直に降参した。
「確かにその通りだ。今のオレは何の役にも立たない」
「一刻も早くダイ君の行方を探したいのはよく分かるわ。あたしもそうだもの。でも今はその準備段階よ。その間に少しでも体を治してきなさい、ってことよ」
それまで溌剌と話していたレオナは、少し声を低くした。
「それで、まだ魔王軍の残党が辺境を襲っているわ。規模は大きくはないけれどね。特にあなたは魔王軍から“寝返った”身。あなたを狙って魔王軍がやってくるとも限らない」
“寝返った”という言葉にヒュンケルは複雑な思いで奥歯を噛み締める。
「あなたの過去もごく一部の者しか知らないけれど、どこからか漏れてあなたに害をなす人が現れるかもしれないわ。だから、一人くらい護衛が必要かと思って。ラーハルト、よろしく」
「なに? なぜオレが」
ヒュンケルがレオナの執務室を訪れると、なぜか先にラーハルトがいて面食らったが、こういうことか。
レオナは異議を唱えたラーハルトではなくヒュンケルに言った。
「ポップくんでも良いんだけど、彼、ヒュンケル相手だと変なライバル心出して意地張っちゃうときあるでしょ。ヒュンケルも“アバンの使徒の長兄”の役割から抜けられなくて肩の力が抜けないと思うし。あなた達は歳が近くて仲がいい割にベタベタしてないし、ちょうど良いかと思って」
「ふざけるな。オレは一日でも早くディ……ダイ様を探し出して」
「良いこと!」
食い下がるラーハルトの鼻先にレオナは指を突き付けた。
「全国の首脳会議で、自国にダイ君の行方に関しての御触れを出すと決定したのが五日前、首脳が自国に戻って実際に御触れを出し始めたのが二日前。スピーディな方よ。これでもね。複数の国で同時に事を進めるにしては」
立て板に水を流したようなレオナの弁に気圧されて、ラーハルトはじり……と少しだけ後退った。
「国民の末端まで御触れが浸透するには一ヶ月はかかるでしょうね。まだ戦後の混乱期だから。ダイ君の情報が上がってくるのはそのあと。あなたがどこをほっつき歩いてたって良いけど、肝心のダイ君の情報が出てきたときに逃しちゃうかもね」
レオナの至極冷静な指摘に、ラーハルトは一言呻くと唇を真一文字に結んで黙り込んだ。
「大破邪呪文のときに参戦してくれた“勇者たち”の中には、故郷に戻って御触れを村々に伝えるのを手伝ってくれている人もいるけど、あなたそういう伝手もないでしょ。つまりあなたも今は特にやることがないってこと」
ラーハルトの眉間に皺が寄った。
「今はまだ情報戦の段階よ。遊撃はそのあとでいい」
レオナは自分に言い聞かせるように小さな声でそう言った。一転、楽しげに両手の指を組むと至極明るく続けた。
「それともヒムに頼もうかしら。温泉なんて文字通り生まれて初めてだろうしね」
ヒム、という名前にラーハルトの長い耳がピクリと動いた。
ラーハルトとヒムは馬が合わない。竹を割ったような性格のヒムと、いつも斜に構えたラーハルトでは当然と言えば当然である。ヒムはラーハルトを「スカした槍野郎」と呼び、ラーハルトはヒムを「直進しか能のない歩兵」と呼んでいる。
そのヒムを引き合いに出されたとなると。
「……オレが行く」
ラーハルトは絞り出すようにそう言うと、レオナは「それでよろしい」と満面の笑みを浮かべた。
高貴な身分のわりに気さくな振る舞いをするレオナだったが、流石は“王者たれ”と教育を受けたものの事はある。政をするのが王ではない。政のために人を据えるのが王だ。人の性質を見極め、適所に据えていく手腕があまりにも見事で、軍団の長の端くれであったヒュンケルは舌を巻いた。
「なにか情報が出てきたらすぐに使いを出すわ。だから、ちょっとはゆっくりしてきなさい」
そう言うとレオナは優しく微笑んだ。
件の別荘はパプニカの王都から北上し、馬車に揺られて三日のところにあった。早馬を飛ばせば一日ほどで知らせは届くだろう。なるほど、絶妙な場所を選んだな、とヒュンケルはレオナの手腕に再度感嘆した。
馬車で鬱蒼とした森を抜けると、屋根付きの馬車でも分かるほど急に視界が開けた。
小高い丘を馬車で登っていくと、植物園ほどの広大な庭の中に、白亜の建物があった。開放的な作りのその建物は、温暖なパプニカの中でどちらかというと避暑地、といった位置付けの別荘であるようだ。
馬車はそのまま門番が開けた入口から敷地の中に入り、広大な前庭を館に向かって進んで行く。窓から外を覗いてみると、庭の手入れはかろうじてされているようだったが、手が行き届いているとは言えなかった。しかし、ヒュンケルは戦後の間もなく人手が足りない中で、精一杯のもてなしをしようという心を受け取った。
館の玄関前で馬車を降りると、口髭をたくわえた初老の男性がいた。その焦茶色の髪には白いものが混ざってはいるが、正装に包んだその身は清々しいほどに背筋が伸びている。
「いらっしゃいませ、ヒュンケル様、ラーハルト様。わたくしはここの管理をしております、執事のアルバートと申します。お荷物はこちらの従僕にお預けください。お部屋にお運び致します」
従僕の青年が「お預かり致します」とヒュンケルとラーハルトの少ない荷物を預かった。
「よろしければそちらのお荷物も」
「不要だ」
ラーハルトは布の巻かれたやけに細長い荷物を持っていた。魔槍だ。馬車の中ではさすがに立てられないので床に置いていた。これは人には預けられない。
青年はそれ以上は口を出さず、「それでは、失礼いたします」と、ふたりの鞄を持って去っていった。
「お疲れでしょう。まずはテラスでお茶をお召し上がりください。さ、どうぞこちらへ」
ヒュンケルは多少は失礼のないように、上は襟付きの七分袖の紺色シャツに、ベージュのカーディガン。下は白のぴったりしたスラックスに、ダークグレーの編み上げミドルブーツを履いてきた。選んでくれたのはエイミとマァムだ。「正装でなくて大丈夫だろうか」と心配するヒュンケルに、護衛の賢者として何度も王族に随従したことがあるエイミは、「そんなに気を張らなくていいのよ。別荘なんだから」とにこやかな顔で言っていた。
装いについては我が道を行くラーハルトは、うっすらと柄の見えるゆったりしたベージュの半袖チュニックの上に、落ち着いたオレンジ色の柄付きのストールを巻き、これまたゆったりしたカーキのズボンを履いていた。ズボンの裾はショートブーツの中に消えている。
エイミの言う通り、服装の心配は杞憂だったようだ。アルバートは道すがら「こちらには何種類かの部屋着をご用意してございます。是非そちらをお召しになってごゆっくりとお寛ぎください。敷地内でしたらそちらで外出いただいても問題ございません」と話してくれた。
庭が一望できるテラスに案内されると、まるでこの時間に着くのが分かっていたかのように、綺麗に用意された茶器があった。
執事が手ずから淹れてくれた紅茶は、今まで飲んだどのお茶よりも香り高かった。王族用の茶葉だからなのか、執事の腕なのか。おそらくその両方だろう。
「なぜオレたちがこの時間に着くことが分かったのですか?」
紅茶を飲みながらヒュンケルは率直に疑問を口にした。
「……申し訳ございません、ご質問の意図をはかりかねております」
「いえ、あまりにも準備が良いので……純粋な疑問です」
「ああ、それでしたら、入口から馬車が来るのを見て準備しただけのことです」
いくら広大な前庭の向こうに馬車が見えた、と言っても、それだけの時間で人員を配置しお茶の準備まで整えるのは、さすがその道のプロとしか言いようがない。
「本来ならば女中や厨房の者、従僕や部屋係ももっとお付けすべきなのですが、なにぶん……このような状況ですので、正直に申し上げて人が足りておりません。ご不便をおかけすることもあるかと存じますが、ご容赦くださいませ」
アルバートはそう言うと深々と頭を下げたが、人が足りない原因を作ったヒュンケルは複雑な思いで唇を噛んだ。
その様子を見たのか見ないのか、アルバートはこう続けた。
「その、ヒュンケル様とラーハルト様の……過去、については、この館の中でわたくしにしか知らされておりませんので」
その気遣いにヒュンケルは更にほぞを噛む思いだった。
「後ほどお二人のお世話をする近侍をご紹介いたしますので、まずは冷めないうちにお茶をお召し上がりください」
ヒュンケルとラーハルトがカップを置いた頃に、アルバートより幾分簡素な服装をした中年の栗毛の男性がやってきた。
「お二方の近侍を務めさせていただきます、フレッドと申します。ご用がございましたら、なんなりとお申し付けください」
そう言うとフレッドは深々と頭を下げた。
「本来ならばお二人に別々の近侍をお付けするべきなのですが……ご容赦ください」
「いえ、こちらはふたりとも誰かについてもらうのは慣れませんので、かえって気が楽です」
「ありがとうございます」
アルバートとフレッドは深々と頭を下げた。
「ご夕食までまだお時間がございます。長旅でお疲れかと思いますので、それまでお風呂でお寛ぎになってはいかがでしょう?」
湯治とは日に何度も温泉に浸かることだと聞いている。ちょうど汗を流したい頃合いでもあったヒュンケルとラーハルトは、アルバートのその提案を受けることにした。
「まずはご入浴の前に、お二人のお部屋にご案内いたします」
フレッドはそう言って館を指し示した。
フレッドが館の構造──図書室の場所や、万が一の非常時の出口など──を説明しつつ先導して、館の中の広く開放的な廊下を進んでいく。と、珍しくラーハルトが口を開いた。
「王家の別荘なのだろう? こんな造りではいざというときすぐに落とされるのではないか?」
「ラーハルト、無礼だぞ」
ラーハルトらしい、しかしあまりに失礼な質問に、ヒュンケルは小声で諫めた。
「いえいえ、もっともな疑問でございます。そうですね……王族の皆様も護衛を連れていらっしゃいますし、使用人には退役軍人などの腕に覚えがある者も採用しています。こう見えて私も弓についてはちょっとしたものです。何かありましたらお逃げいただく時間くらいは稼げるでしょう。ただ、こちらは要塞ではなく別荘です。基本的にお寛ぎいただくことを目的としておりますので、無用心といえば無用心ですが……あまり閉塞的な作りになってしまうと、本来の意味を失ってしまいます」
そう話しながら、館の南東あたりだろうか。フレッドは足を止め、二つのドアを指し示した。
「こちらがヒュンケル様のお部屋、こちらのお隣がラーハルト様のお部屋です」
ヒュンケルの部屋のドアの向かってすぐ左隣がラーハルトの部屋のドアだ。なにかあればすぐに駆けつけられるだろう。いざとなれば壁をぶち破ればいい。
「必要なものがありましたらなんなりと使用人にお申し付けください。お風呂の準備が整いましたらお迎えに参りますので、それまでお部屋でお寛ぎください」
そう言い置いてフレッドは下がっていき、ヒュンケルとラーハルトは視線を交わすととりあえず案内された部屋に入ってみることにした。
あてがわれた部屋は一般庶民の家が一軒収まるほどの広さがあった。部屋の端にある文机の側には、使用人部屋のベルに繋がる紐もある。王家の別荘というのであれば当然ではあったが。
部屋の東側にある大きな窓近くに据えられたベッドは天蓋付きで、当然のようにキングサイズだ。ベッド脇にはサイドテーブルと小さなチェスト。部屋の中央には寛ぐための大きなローテーブルと、それを囲むようにたっぷりとクッションが置かれた大きなソファが三つ。窓際には外を眺めるためのソファチェアが対面で二つ。その間には茶を飲むための小さなテーブル。一人では使いきれない広いクローゼット。身支度を整えるための大きな鏡台と姿見。冬に火を入れるための暖炉。その全てに繊細な装飾が施されていた。
従僕に運ばれた荷物はクローゼットの前に置かれていた。ヒュンケルは旅慣れてはいても“旅行”など生まれて初めての経験だ。考えに考えてありったけの着替えとほんの少しの日用品を詰め込んだ鞄は、部屋の豪華さに対して、いっそ滑稽なほどに小さく貧相だった。
ベッドの側には室内履きが用意されていたが、ヒュンケルは靴を履いたままどさりと天蓋付きのベッドに寝転がった。ベッドが体重を受け止めて体がゆっくりと沈み込む。
執事と使用人がいる場所で、このような豪奢な部屋で、こういった天蓋付きのベッドで眠って暮らしていたことも、ヒュンケルにはあった。しかしたった数ヶ月前のことなのに遥か昔のことのようで、もはやその全てに慣れなかった。
と、コンコン、と部屋のドアがノックされた。
「はい」
ベッドから起き上がって返事をすると、フレッドの声が聞こえた。
「お風呂のご準備が整いましてございます」
「すぐ支度します」
「いえ、手ぶらでお越しくださって結構です」
「?」
ヒュンケルの頭には疑問符が浮かんだが、その言葉に従うことにした。
部屋のドアを開けるとフレッドがいた。ラーハルトはまだらしい。しばらく待っているとラーハルトの部屋のドアが開いた。
「なんだこの部屋」
ややげんなりした様子のラーハルトが続ける。
「落ち着かない……」
気持ちは分かる。ヒュンケルも軍団長時代の経験があっても落ち着かない。
「お揃いでございますね」
フレッドはふたりの顔を見てにっこりと笑った。
「こちらの別荘には趣の異なる三つのお風呂がございますが……先刻執事が申し上げた通り、なにぶん人手不足ですので……。今回は一つだけお開けしております。ご容赦ください」
「それでも充分すぎるほどです」
申し訳なさそうにそう述べるフレッドに、ヒュンケルはそう答えた。心の底からの本心だ。
「勿体無いお言葉でございます。では、お風呂にご案内いたします。お二人のお部屋に一番近いお風呂を開けてございます」
ふたりとも温泉に入るのは初めてだと話すと、フレッドは道すがら温泉の入り方について詳細に説明をしてくれた。
「ここは冷ましたり温めたりしなくても、入浴に丁度良い温度のお湯が自然に湧くのです。王族の皆様にも人気の温泉でしたので、きっとお気に召すはずです」
ほう、とヒュンケルは思わず声に出した。軍団長時代のヒュンケルが拠点としていた地底魔城にも温泉が沸いていたが、死活火山が近かったせいか湯の温度が高く、一度汲んで置いておくか水を加えるかして、適温に冷ます必要があった。
「こちらでございます」
館の中央より少し南寄りだろうか。フレッドはひときわ豪奢な扉を指し示した。フレッドは扉を開けると、「どうぞお入りください」とふたりを促した。
ヒュンケルはぽかんとした。ラーハルトも隣でぽかんとしている。脱衣所だけで宿屋の三人部屋ほどの広さがあり、立派な鏡台が二つに、水差しと寝椅子が置いてある。脱衣所だけでこの広さだ。その先はどうなっているのだろう。
「ヒュンケル様、ラーハルト様。どうぞ中へお上がりください」
ヒュンケルははっと我に帰ると、先ほど説明された通りにミドルブーツの紐を解いて、一段高くなっている脱衣所の中に上がった。ラーハルトもショートブーツのベルトを解いて中へ上がる。今更ながら、人前で裸足になるのは恥ずかしい気分になってきた。
フレッドも「見苦しい姿で失礼いたします」と、靴を脱いで上がってきた。
「ご説明いたします」
フレッドは何枚も折り畳まれ積み重ねたタオルを指し示した。
「こちらがご入浴の際にお使いいただくタオルです。大きいものと小さいものと用意してございます。何枚でもご自由にお使いください。使い終わったものは隣の棚に置いていただければ後で係の者が回収に参ります」
フレッドはまた別の棚にある折り畳まれた白い衣服を示した。
「こちらに湯上りのお召し替えを用意してございますので、よろしければお使いください。上下別れております。お好きなサイズをお使いください。このお召し物で夕食にお越しいただいても問題ございません。お洗濯が必要なお召し物がございましたら、こちらの袋に入れておいてくださいませ。お天気にもよりますが翌日には綺麗にしてお部屋にお届けしておきます」
フレッドは流れるように説明する。
「では後ほど係の者がお背中を流しに伺います。先にお風呂にお入りになってお待ち下さい」
「あっ、あの!」
「はい」
「あの……それはいいです。自分たちでできますので」
ヒュンケルもかつて軍団長として地底魔城にいた頃は、ゆったりと猫足のバスタブに横になって下僕に体を洗わせていた。しかしそれは相手がスケルトンやマミーの下僕だったからできたことだ。生きている人間に体を洗われるとなると恥ずかしくて仕方ない。今はもう相手がスケルトンでも頼めるかどうか怪しい。
「承知いたしました」
ゆっくりと一礼して、それではごゆっくりお寛ぎください、と、フレッドは扉の向こうに消えていった。
「……おい」
些か呆然とした様子のラーハルトから声をかけられた。
「なんだ」
「なんなんだこれは……温泉とはみんなこうなのか……?」
「いや……たぶん……違う」
他の温泉施設を知らないからなんとも言いようがなかったが、たぶん、たぶん違う。これは王族専用だ。
至れり尽くせりの豪奢さは置いておいて、気を取り直してさっそく温泉に入ることにした。
入浴には不要だろうと、ふたりともカーディガンの類は部屋に置いてきた。ラーハルトはフレッドに言われた通り、長い髪が水面に付かないよう、鏡台にあった紐で髪を高い位置で括った。
脱いだ服を入れる籠の前で服の裾に手をかけ、ラーハルトは何かに気付いたように手を止めた。
「どうした?」
「思わず手ぶらで来てしまったが、オレはお前の護衛であるからして、一緒に湯浴みをしてはまずいのではないか?」
「個別に離れる方が狙われる可能性が高いのでは?」
「それもそうだが……」
レオナは名目としては“ヒュンケルの護衛”としてラーハルトを同行させたが、この湯治はレオナからラーハルトへの労いでもある。ヒュンケルはそう踏んでいる。
ラーハルトは竜の血の力によって甦ると、すぐさま大魔王との決戦に駆け付けた。彼がいなければバーンとの戦いはあれ以上に壮絶なものとなったであろう。勇者一行の一員として、また一国の指導者として、レオナがラーハルトへ何らかの褒賞を与えたいと思うのは自然なことだった。
しかし、ラーハルトは頭の固い武人だ。レオナが率直に褒賞を与えたいと告げたところで、自分は主人であるダイのために戦っただけだ、主人からならともかく何の関係もないお前から褒美を貰う謂れはない、と頑として断っただろう。
だからこその“ヒュンケルの護衛”だ。ここでもレオナの手腕は見事だった。そのレオナの思惑を汲んだヒュンケルとしても、ラーハルトにはあまり気を張らせぬよう努めたかった。
「武器だけ持ち込めばいいだろう。お互い裸では立ち回りができないというわけではあるまい?」
戦士としての長い経験の中で、ラーハルトも裸で戦わざるを得なかったことはある。しかし股間のものがぶらぶらして妙に落ち着かなかった記憶がある。
「では槍を……」
「浴室に槍ではかえって動き難くないか?」
「……そうだな。護身用のナイフならベルトに挟んである」
「オレもだ」
ヒュンケルは服のボタンを外しながら続けた。
「それに、幼い頃アバンから、極東の“裸の付き合い”というものについて聞いたことがある」
「“裸の付き合い”?」
「ああ、なんでもその極東の島国には多くの火山があり、あちらこちらで湯が湧き出てくるそうだ。だからここのような入浴施設がたくさんある。そこで身分も関係なく皆裸になって、胸襟を開いて親交を深めるのを“裸の付き合い”と言うそうだ」
アバンはよく小さなヒュンケルと一緒に湯浴みをしたがったが、その話を聞いてからヒュンケルはより一層アバンと湯浴みをしたくなくなった。仇と親交など深めたくなかったからだ。
「しかしオレとお前が“裸の付き合い”とやらをして何になる?」
「オレはお前のことを友だと思っている。しかしお前の生い立ち以外のことはほとんど何も知らない。お前もオレが軍団長だったこと以外は知らない。そうだろう?」
「確かに、そうだな」
「オレは友のことをもっと知りたいと思う。だが、お互いに口が達者な方ではない。まぁだから、借りられるものの力は借りてみてもいいのではないか、と思うのだ」
ラーハルトは黙ったままだ。怒らせてしまっただろうか、とヒュンケルは心配になった。ラーハルトの怒りの沸点はいまいちよく分からない。
「……オレもお前のことは友だと思っている」
幾分照れ臭そうにラーハルトはそう言った。
「そうだな、“裸の付き合い”も悪くないだろう」
ふたりとも服を脱ぐと、腰にタオルを巻き、いつも服のベルトに挟んでいる護身用のナイフを持った。脱衣所と浴室を隔てる木の扉を開けると、そこは一面の緑だった。木々が外から中を伺えぬように壁の役割を果たし、しかし丁寧に手入れをされたそれらは目にも美しく、閉塞感は感じさせない。上を見上げると真っ青な空が見えた。
上級の宿屋の四人人部屋ほどもある広い浴室の床は、石を敷き詰めて固められていた。浴室の三分の二ほどを占める洗い場には、壁際に小さな椅子と桶が二つずつ用意されていた。そして、浴室の端、ちょうど見上げると空が見える位置に、木でできた大きな円形の浴槽が埋め込まれていた。六~七人が入ってもまだ余裕がありそうな広い浴槽だ。同じく木材を組み合わせて作られた樋からは、ふんだんに乳白色の湯が浴槽へと流れ込み、眺めている間にも浴槽の端を越えて次々と湯が溢れていく。
浴槽の傍らには背の低いテーブルに銅製のグラスがふたつと水差しが、また別の傍らには休憩用の寝椅子の上にふかふかとしたバスローブもそれぞれふたつずつ用意されていた。寝椅子と寝椅子の間にもテーブルがあり、そこにも水差しとグラスがあった。至れり尽くせりとはこのことだ。
フレッドに習った入浴の手順を思い出す。まずはかけ湯。桶で湯を汲む前に試しに浴槽に手を入れてみる。なるほど、入浴には最適な温度だ。改めて桶で湯を汲むと、椅子に座って心臓から遠く、足から徐々に湯をかけていく。しっかり汗を流すように、とも言っていた。もう一杯湯を汲むと、今度は全身に湯を浴びた。ふと、近くで何かが香った。花の香りだろうかと周りを見回してみても、そのようなものは見当たらない。匂いの元を探ってみると、先程は気が付かなかった石鹸がある。ここから花の香りが薫っていたのだ。ヒュンケルはあまりの豪奢さに目眩を起こしそうだった。石鹸自体も高価なものだが、香り付きのものとなると更に高価だ。それがヒュンケルの分とラーハルトの分、ふたつ惜しげもなく置いてある。予備も含めればもっとあるだろう。
ヒュンケルが石鹸に思いを馳せている間に、背後でざぶんと水音がした。ラーハルトが早々に湯に入ったようだ。ヒュンケルもかけ湯は終わった。護身用のナイフだけ浴槽の傍らに置く。入浴の手順でフレッドが言っていたこと。「浴槽にタオルを入れてはいけない」。ヒュンケルは腰に巻いたタオルを取り払うと素早く浴槽に体を滑り込ませた。
浴槽に入ってしまえば、乳白色の湯に隠れて体はすっかり見えない。タオルはとりあえず浴槽の外で絞って、入浴用の手すりにかけておいた。
「遅かったな。何かあったか?」
「いや……王侯貴族にくらくらしていただけだ……」
「?」
ラーハルトは怪訝な顔をしたが、それ以上は何も聞いてこなかった。
「ふむ……オレは温泉というのは初めてだが、こうやって露天で温かい湯に浸かるというのも、湯屋や水浴びと違って良いものだな」
「オレも軍団長だった頃はよくバスタブで湯浴みをしていたが、こうして全身を浸かるのは初めてだな」
「ほう、意外と綺麗好きだったんだな」
「意外とはなんだ、意外とは」
お互いに、友、という認識のある相手ではあるが、お互い饒舌な方ではない。すぐに沈黙が訪れた。けれども不快なものではない。湯が流れる音だけが周囲に響き渡り、時折小鳥の鳴き声が聞こえて来る。美しく整えられた景色を眺めながら湯に浸かり、気のおけない友と穏やかな時を過ごす。それはヒュンケルの苛烈な人生にはなかった、なんとも心地よい体験だった。
しばらくすると額にふつふつと汗が湧いてきた。用意された水差しからグラスに水を汲み、一息にあおる。
「お前もどうだ?」
「もらおう」
そうラーハルトに聞くと、彼も汗をかき始めたようだった。グラスを受け取るとやはり一気に飲み干した。
「そろそろ出るか。のぼせそうだ」
「ああ」
ヒュンケルの提案にラーハルトは首肯した。
浴槽から上がるとまた腰にタオルを巻き、ナイフを持って脱衣所に戻る。大きなタオルを使って体の水滴を拭いていく。今までに使ったことが無いほどふかふかのタオルだ。
「なんだこのタオルは……」
流石のラーハルトも困惑している。
用意してもらった部屋着は、頭から被って着る柔らかくゆったりした七分袖のシャツと、同じ素材のゆったりしたズボンだった。ウエストでサイズを選んだらズボンの丈が足りなかったので、少しウエスト周りが緩いがワンサイズ上に変えた。紐である程度調節できるので問題ないだろう。ラーハルトもそうだった。
部屋着に着替えたヒュンケルが、洗濯物袋を使おうか悩んでいると、部屋着に着替えたラーハルトが隣で容赦なく服を袋のうちの一つに放り込んでいた。
「使うのか?」
「使えるものは使う」
なるほど、合理的なラーハルトらしい。
「……下着もか?」
「そうだ。今はさっきのを履いてるが、夜の湯浴みの後に替えたら洗ってもらうぞ」
この豪胆さが羨ましい。
結局ヒュンケルもありがたく洗濯物袋を使わせてもらうことにした。下着をどうするかは夜までに考える。
風呂からお互いの部屋に戻り、ヒュンケルは室内履きに履き替えると、特にやることもなくなった。遠慮なく紐を使わせてもらって女中を呼ぶと、紅茶を頼んだ。それを飲みながら最初は窓際のソファチェアで外を眺めていたが、日も落ちて風景も見えなくなっていった。カーテンを閉めようとしたときにノックがあり、女中がカーテンを閉めて出て行った。本格的にやることがない。暇を持て余したヒュンケルが、文机の引き出しに入っていたパプニカの歴史書をソファで読んでいると、再びノックの音があった。
「はい」
「御夕食の準備が整いましてございます」
フレッドの声だ。
「すぐ行きます」
ドアの外に出ると、今回は先にラーハルトがいた。ヒュンケルと同じ部屋着のままだ。
「暇だ……」
げんなりした様子でラーハルトは言った。
食堂の広いテーブルにはずらりとカトラリーが並べられ、従僕がヒュンケルとラーハルトそれぞれの椅子を引いた。ヒュンケルの対面に座ったラーハルトは、カトラリーの数に困惑していた。ラーハルトは気付いていないようだったが、カトラリーは全て銀製だ。
ラーハルトはバランに随従した際に失礼の無いよう、ひと通りのテーブルマナーは習ったが、それは一度も使われず記憶の遥か彼方だ。普段は毅然とした態度のラーハルトが目を丸くしているのが新鮮で、ヒュンケルは思わず微笑んだ。
「おい、今笑ったな」
「笑ってない」
「いや笑っただろ」
そう言いながらしばらくカトラリーと睨めっこをしていたラーハルトは両手を上げた。
「降参だ。確かフォークとナイフは外側から使うのでよかったか?」
「そうだ」
「お前はどうもこういった生活に慣れているな……」
「幼い頃アバンに叩き込まれただけだ」
「オレもバラン様にひと通り習ったが、一度も使わなかったから忘れたぞ」
「まぁ、あとは……今となっては不本意ながら……まぁ、色々だ」
部屋に待機している使用人の手前、ヒュンケルは言葉を濁し、ラーハルトは事情を察してそれ以上はその話題について言葉をかけては来なかった。
カトラリーの数から分かっていたが夕食はコースだった。
まずパン皿にバゲットと丸パンが配られ、そのすぐ後に前菜がやってきた。採れたての季節野菜のサラダに、近くの小川で獲れるという小魚のフリット。甘くなるまで炒めた玉ねぎとベーコンがたっぷり入ったキッシュ。野菜は普段食べているものより随分と味が濃く、甘かった。小魚は頭から尻尾まで丸ごと食べられるということで、香ばしくて歯応えも良い。
間にあっさりとしたトマトベースのスープを挟んで、次は魚料理だ。これも近くの川で獲れるというマスのオーブン焼き。キノコの入ったソースがかかっていた。そしていよいよメインの肉料理だ。山で獲れたばかりだという猪のステーキがやってきた。赤ワインを煮詰めたソースがかけられた肉は筋肉質で野性味が強く、野山を駆け回る力強い味がした。
最後にはテーブルの上が片付けられ、デザートのプレートが並べられた。生菓子にフルーツが添えられ、ソースが美しい絵画のようにかけられていた。プレートの端にはごく小さなガラスボウルが載せられ、そこに球状をした淡いクリーム色のものが乗せられていた。
「おいヒュンケル、この白いのはなんだ?」
「これはシャーベット……氷菓子というやつだな」
「ほう! これが!」
「オレも数えるほどしか食べたことはないが……」
氷菓子はヒャド系の魔法を使って作られる。魔法使いの協力を必要とするために、貴族でなければお目にかかれないほど高級、というわけでもないが、庶民が手軽に買えるほど安いものではない。庶民にとっては冷やしたスイカのほうが手軽で安価だ。
ヒャド系魔法の他にメラ系魔法の火力も料理人にとっては魅力的なものらしい。どちらにせよ魔法の適性がある人の方が少ないため、魔法を利用した料理は高級なものになりがちだ。
「うまい! うまいぞこれ! ヒュンケル、食べてみろ!」
珍しくはしゃいだラーハルトに促され、スプーンでシャーベットをすくって口に運ぶ。スプーンを口に含んだ瞬間にやってくるのはまず冷たさ。それがみるみるうちに口の熱で溶けていき、果汁の旨味が口いっぱいに広がる。桃のシャーベットだ。
食後にはお茶が出された。コーヒー、紅茶、ハーブティーの中から選べるということで、ヒュンケルは紅茶を、ラーハルトは「実は飲んだことがない」という理由でコーヒーを選択した。
「悪くないな」と言いながらコーヒーを飲むラーハルトと差し向かいで紅茶を楽しんでいると、フレッドがやってきて、明日の起床と朝食の時間を尋ねてきた。
おそらくフレッドが起こしに来て身支度を手伝ってくれるのであろうが、ヒュンケルもラーハルトも戦士の性分で毎日決まった時間に目が覚める。身支度を人に手伝ってもらうのも落ち着かない。その点は丁重に断って、朝食の時間の希望だけを伝えた。
「それでは、そのお時間に。朝食はこことは別のお部屋になりますので、お時間になりましたらご案内に参ります」
「ああ、ところで」
ヒュンケルはフレッドに聞きたいことがあった。
「湯治のためには温泉に日に何度も入ったほうが良いと聞きました。だいたい何度ほど入るものなんですか?」
「そうですねぇ……そのお方や状態よりますが、日に一、二度程度の方から、日に五度、というような方もいらっしゃいます」
「五度!」
「ですが入浴はその分お疲れにもなりますので……。私は一日二、三度から様子を見るのをお勧めいたします」
「なるほど」
ああそうです、とフレッドは何かを思いついた顔をした。
「ご朝食前にもお入りになられては? 胃腸の動きも活発になってよろしいと思います」
「是非そうさせていただきます」
「では、朝もご入浴できるように準備しておきますので、お好きなお時間にお入りください」
フレッドは「お食事後、すぐに入浴するのはお勧めできません。消化が悪くなりますので」と言っていたが、言われるまでもなく入れない。腹がパンパンだからだ。
とりあえずは一度各々の部屋に戻って、適当な時間に声をかけることにした。
一時間ほど経って腹の落ち着いたヒュンケルは、ラーハルトの部屋の扉を叩いた。
「ラーハルト、大丈夫か?」
「ああ。大丈夫だ」
ふたりは下着だけ持って風呂に向かった。
風呂に着くと、脱衣所は綺麗に元の通りに整えられていた。浴室もそうだろう。部屋着も新しく薄いグレーものに取り替えられている。生地も今着ているものより柔らかい。「ご就寝の際にお使いください」とカードが添えてあった。フレッドの名だ。
「王族や貴族は皆こんな生活をしているのか……?」
服を脱ぎながらラーハルトはヒュンケルに尋ねた。
夕食の味がほとんど分からなかった……とラーハルトはぼやいた。
「オレは貴族でも王族でもないから知らん」
「似たようなものだったろう」
「軍団長なんぞただの管理職だ」
さくりと言い捨てたヒュンケルはさっさと服を脱いで腰にタオルを巻くと、ラーハルトより一足先に浴室へ向かった。
まず桶に湯を汲んで、今度は椅子に座って香る石鹸で全身をよく洗った。「なんだこの石鹸は……匂いがするぞ……」と、ラーハルトは隣で困惑していた。
またふたり揃って湯に入る。ラーハルトは頭を洗った後にまた髪を括り直している。いつもは鬣のような前髪もぺしゃんこになって、まるで別人だ。
「何をニヤニヤしている」
「いや、そうして濡れた髪を括ったお前も新鮮だと思ってな」
「そういうお前もいつものふわ毛がぺしゃんこだぞ」
ラーハルトはヒュンケルの頭を指差した。
「食事に酒が付かんのが残念だな」
「療養目的で来ているからな。しかし酒が出るにしても、値段が付けられないような高価なワインが出てくるだろう。これでいいのさ」
「確かにな……飲んだ気がしないな……」
浴槽に入ってしばらく落ち着いてから、ヒュンケルはそれに気付いた。
昼の時と同じ水差しとグラスの間に、足のあるガラス製の器の中に氷が敷き詰められ、その中に片手で持てるほどの金属製のボウルがあった。中には色とりどりの一口大の丸い物体が入っている。なんなのか正体が分からず湯に浸かりながら摘んでみると、指先が冷たい。氷菓子だ。夕食の時のシャーベットよりも、湯のそばでも溶けにくいようにもっと中心まで固く凍らせたものだ。
本職の魔法使いの協力を得る他に、料理人自身が初歩の魔法を修めるケースもあるという。ここの厨房の場合はそうかもしれない。
ひとつ口に含んでみる。薄紫のこれは葡萄の味だ。温かい湯に浸かりながら冷たいものを食べるというのは、これ以上ない至福の贅沢だった。
「ラーハルト、氷菓子だ」
「何!?」
ラーハルトはざぶざぶと湯をかき分けヒュンケルの隣にやってくると、ひょいと氷菓子を摘んで口の中に放り込んだ。余程気に入ったらしい。
「なるほど……こういうタイプもあるのか……」
「全部食べていいぞ」
「子ども扱いするな。半分でいい。半分で」
それでもきっちり半分は持っていくのか、とヒュンケルは笑いを堪えた。
無邪気に氷菓子を摘むラーハルトを見ながら、ヒュンケルはは何かあたたかなものが胸に広がるのを感じた。
結局、ヒュンケルは朝食前と昼食後、そして夕食後の一日三回、温泉に浸かることにした。
朝の入浴時には新しい紺色の部屋着が用意されていた。何もかもが行き届いている。
数日はラーハルトも律儀にそれに付き合っていたが、目下の危険は無いと見て、朝食前には別行動をして庭で槍の鍛錬をするようになった。あの魔槍を鍛錬に堂々と使っていては、使用人の間に何かの噂が出かねないので、有事の際に使う別荘の槍を借りているようだった。ヒュンケルも是非ともそれに参加したいところではあったが、体がそれを許してはくれなかった。
治るのだろうか、この体は。戦士としての死を宣告されたときは、そうか、とただ何の感慨もなくそう思っただけだった。しかし戦えない自分が何の役に立つのだろう。改めてそう考えると足元からじわじわと何かに侵食されていく気がした。
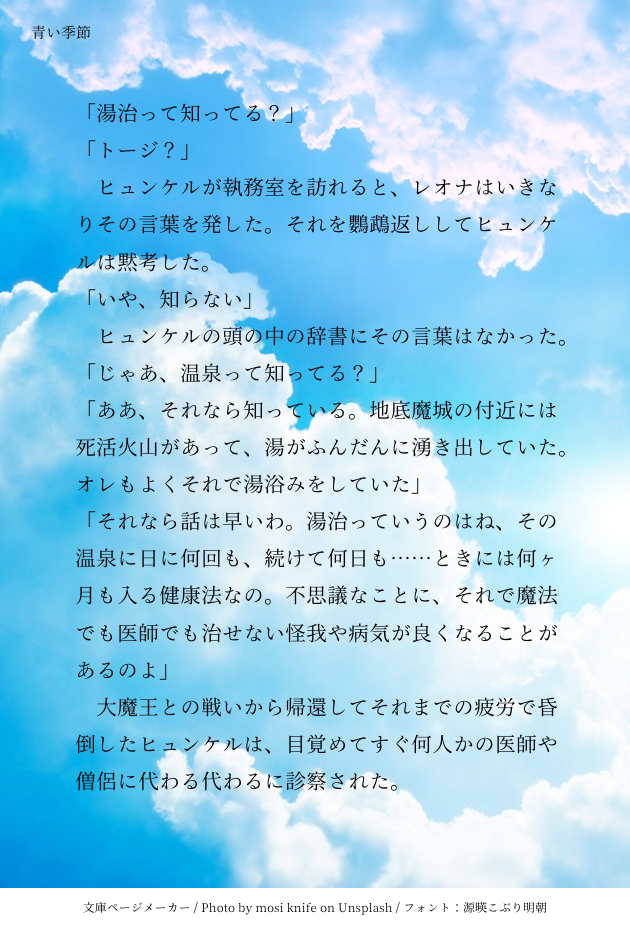
 コージ
Link
Message
Mute
コージ
Link
Message
Mute








 ステキと思ったらハートを送ろう!ログイン不要です。ログインするとハートをカスタマイズできます。
ステキと思ったらハートを送ろう!ログイン不要です。ログインするとハートをカスタマイズできます。

 コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ