【橙】ラーヒュンお題企画再録【ラーヒュン】<ただ君を見ていた>
霧のような雨が降っている。
足早に道を行けば濡れることもないような、ささやかな天の恵みだ。
しかし、街道の遙か遠くに目をやる彼は、頭から爪先まで水でも浴びたかのように濡れていた。
彼の師がここへやってきて、帰るとき、彼はいつもそうだった。雨が降ろうが風が吹こうが雷が鳴ろうが、いつまでもその背を追いかけて街道に佇んでいる。
師が従者の傘を断り、屋根付きの馬車に乗り込むまでの間、彼は何を話すでもなくずっとその側で師に寄り添っていた。
「濡れてしまいます。見送りはもういいですから」
彼の師は馬車の中からそう優しく声をかける。師は手袋を外し、窓から手を伸ばすと、しっとり濡れた彼の銀髪を慈しむように撫でた。
「元気で」
馬車を出します、と御者が言う。彼は馬車から身を離した。
街道を進み出す馬車の窓から、師は何度も何度も彼を振り返り、彼は馬車が見えなくなるまで街道で見送った。
それから今になるまで、ずっと彼は馬車の消えた先を眺めている。
その背中は飼い主を見送る仔犬のようだった。忠義心で必死に覆い隠された寂寥。ここにいることを選んだのは彼自身だというのに。
「もうそのくらいにしておけ。濡れ鼠のようだぞ」
そう言うと彼は振り返って、少しだけ目を丸くした。
「……お前もびしょ濡れじゃないか」
いつだって見ていたから。彼を。ずっと。
<鋼鉄>
夜の帳を切り裂くように赤い色が広がる。
火事だ。
お人好しの相棒に宿から連れ出されたが、できることは何もなかった。
集まった村の人々は、燃え盛る家から立ち昇った炎が、嘲笑うかのように夜の闇を舐めるのを呆然と眺めていた。村人の足元には、消火のための水が入った桶があちらこちらに置いてあったが、どう傍目に見てももう手遅れだった。あるいは、ヒャダインやマヒャドを扱える者がいれば状況は違ったかもしれないが、そのような手練れの魔法使いがこの辺境の村にいるわけがない。結局、村の人々ができたのは延焼を防ぐために隣家を壊すことだけだった。
突然、相棒がマントのフードを深く被り、足元にあった桶の水を頭からかぶった。さらにもう一杯。
相棒の奇行に狼狽していると、気配に聡い相棒は小さく呟いた。
「まだ中に人がいる」
止める間も無く、相棒は炎が揺らめくかつて入り口だった場所に飛び込んでいった。
一瞬だけ逡巡すると、クソ、と悪態をつきながら相棒に倣いフードの上から水をたっぷりと被り、炎の中へ飛び込んだ。
中はまだ原形を留めていたようだった。それでも崩れるのは時間の問題だ。人の気配を探る。上だ。
二階に向かう階段で相棒と合流した。
「後先を考えろ馬鹿野郎」
「オレが後先を考えるわけがない」
それもそうだと納得しかけて、納得してどうするとかぶりを振る。
「ここが崩れたら面倒だ。さっさと上に行くぞ」
「ああ」
まだ火の手の回っていない部屋の隅にいたのは、十にも満たないだろう二人の姉弟だった。恐怖のあまりにただ呆然と手を取り合っていたのを、こちらの姿を認めると、「お兄ちゃん! お兄ちゃん!」とわんわん大泣きしながらそれぞれの首にしがみついてきた。
相棒は脱いだマントで姉を包んでやりながら、その背中を優しく叩き、「よく頑張ったな。偉いぞ」と声をかけていた。
「お前はこっちの弟を運べ。姉の方はオレが面倒を見る」
「分かった」
「先に行け」
弟の方を頼んだのは、若干でも重量の負担を考えてのことだ。姉の方も着ていたマントで包んで抱え上げた。自分にとっては羽のような軽さだ。
行きの時はまだ原形を留めていた階段も、所々歯抜けてきていた。足場を見極めて跳ぶようにして階下へ向かう。
その途中で、ちょうど相棒の頭の上に燃え盛る梁の一部が落ちてきた。弱々しいヒャドを放ち、火が弱まったところで梁を蹴り飛ばす。一瞬の出来事だった。
「ありがとう。助かった」
「呪文は得意でない。過信するな。早く行け」
「ああ」
こんなことで死ぬものか。死なせるものか。
自分を殺すのは鋼だ。鋼鉄だ。相棒の振るう鋼鉄の剣だ。
相棒を殺すのも鋼だ。鋼鉄だ。自分が振るう鋼鉄の槍だ。
なんとか一階まで降り立ち、不慣れなヒャドを連発して道を作りながら出口まで駆け抜ける。
外までたどり着いたふたりを迎えたのは、村人たちの歓声と、遂に家が崩れ落ちる音だった。
「この子たちの親族はいるか!?」
元軍団長の相棒が、よく通るその声で歓声を割ると、人々の合間を縫って、中年と言うにはやや若い男性が崩れ落ちるようにふたりの前にやってきて膝をついた。子どもたちは身を乗り出す。
「パパ! パパ!!」
「ヒルド! エイリーク!」
ふたりは抱えていた子どもたちを下ろす。駆け寄って泣き始める子どもたちを、父親はきつく抱きしめた。
「ありがとうございます……ありがとうございます……。なんと……なんとお礼を言ったらいいか……」
父親は涙ぐみながら自分と相棒を見上げた。
話を聞くと、三人目の出産を控えた妻が里帰りをしており、その様子を見に行っていた間の惨事だった。陽のあるうちに戻る予定だったが、通り道にモンスターが出たと帰る間際に騒ぎになり、迂回をしている間に夜になってしまったという。
「あのね、夜になってね、寒くて、暖炉をつけようとしたの。そしたら、薪が……」
しゃくり上げながら姉が拙い言葉で説明をすると、「そうか。ごめんな、2人だけにしてごめんな」と、父親は子どもたちを更に強く抱きしめた。
「しっかりした子たちだから、昼間に留守にするだけなら2人でも大丈夫だと思ったんです。でも人を頼むべきでした」父親は血が出るほど強く唇を噛んだ。「もし最悪の事態になっていたら……」と、父親は青ざめた顔でまた何度も何度も礼を言った。
「ほらほら!」
ぱんぱん! という手拍子の音と共に、よく通る女の声があたりに響いた。
「お礼は後でゆっくりしな! 兄さん方を休ませてやらにゃ! 火傷だらけじゃないかね!」
そう叫んだのはふたりが泊まっている宿屋の女将だった。
「兄さん方もそっちの家族もうちに来な! おちびちゃんらも火傷の手当てをせにゃね! 隣の家の連中は親戚の家にでも泊めてもらいな!」
女将の言葉を皮切りに、「薬屋はどこいった!?」「誰かホイミを使える奴はいるか!?」とあちらこちらで声が上がった。
改めて相棒と顔を見合わせる。服は見る影もなく穴だらけ。顔は煤だらけで火傷があちこちにある。髪も一部焦げて縮れている。少し切らなければならないだろう。
お互いの酷い姿にふたりは苦笑いをした。
<兎にも角にも負けず嫌い>
焼いた肉を一口かじって、ヒュンケルは渋い顔をした。
「どうした? 生焼けだったか?」
夕食の調理を担当したのはラーハルトだった。串がわりの木の枝に肉を刺して、焚き火で焼いたシンプルな料理だ。今日の獲物は兎。鹿や猪などの大物も狩れないことはないが、旅の最中では肉を持って歩くのが面倒で、その都度に小物を狙うことが多い。近くに川があれば魚も獲る。
「いや……よく焼けているのだが……」
ヒュンケルは相変わらず渋い顔をして、言いにくそうに続けた。
「その……お前、塩と胡椒以外の味付けはないのか……?」
「不味いとでも?」
ラーハルトの片眉がピクリと上がった。
「不味くはないのだが……こう……なんと言うか……とても美味いわけでもないと言うか……」
「絶妙な塩梅だろうが」
「そう、塩と胡椒だけにしては大したものだ。しかし……毎日これでは味気ないと言うか……」
そう、肉も焼き加減は絶妙で、生焼けでもなく焼きすぎて固くもなっていない。だからこそ、塩と胡椒だけでは物足りないと感じてしまうのだ。
「料理はバラン様に習った。バラン様を侮辱するのか」
「お前はまたそういうことを言う。毎回言うがそういう意図はないぞ。ただ……うーむ……」
「そう不満を言うお前は大層な料理が作れるのだな? 普段はオレと大差ない料理を作っているが?」
「……まあ、その気になれば」
本来は夕食の料理当番は週替わりだ。しかしヒュンケルの物言いが腹に据えかねたラーハルトは「本気を見せてもらおうじゃないか」と言い、翌日の料理当番はヒュンケルが担当することになった。
翌日、道々で休憩を取る度に、ヒュンケルは何やら周囲の草やキノコを選んでむしっていた。
さて、夕食の時だ。獲物は奇しくも昨日と同じ兎だ。腕のほどを見せてもらおう。
ヒュンケルは兎の下処理をすると、ひと口大に切り分けて塩と胡椒、採っていた草とでよく揉んだ。それを焚き火で温めた鍋に入れると、表面に焼き目を付けるように炒める。肉の焦げる香ばしい匂いが辺りに広がり、もうこれで充分ではないか、とラーハルトは思った。ヒュンケルは鍋に沢で汲んできた水を入れる。ふつふつと水が煮立ってくると、途中で摘んでいた最初とは別の葉をいくつかと、キノコを鍋に加えた。しばらく鍋を煮立たせると、最後に味見をしながら塩を加えて、胡椒をふる。ヒュンケルはそれを椀によそると、ラーハルトに差し出した。
「食べてみろ」
受け取ってスプーンでひと口すすると、口の中に広がったのは兎肉のふくよかな旨みと、それを引き立てるキノコの出汁。それらをまとめて引き締める何かの風味を感じる。使った調味料はラーハルトと同じく塩と胡椒のだけのはずなのに。
「……お前……これは……どんな魔法を使った?」
「オレが魔法は使えないのは知っているだろう。出汁のよく出るキノコと、香草を何種類か入れただけだ」
なるほど、途中で集めていた謎の葉は香草か。
「お前、誰に料理を習った? まさかミストバーンではあるまい?」
「料理は子どもの頃にアバンに教わった。食にもうるさい男でな。戦うなら健康的な食事を摂らなければならないと」
なるほど、あの繊細そうな男が料理の師でもあるならこの腕も頷ける。おかわりをしながらラーハルトはそう思った。
さすがは我が強敵(とも)。料理の腕でも人並み以上とは。しかしいつか追いついてみせる。ラーハルトはそう固く誓った。
翌日から、ラーハルトの自己流創作料理を食べることになったヒュンケルは、夕食当番は自分がやる、どうしても料理がやりたいなら自分が教える、と、申し出たが、聞き入られることはなかった。
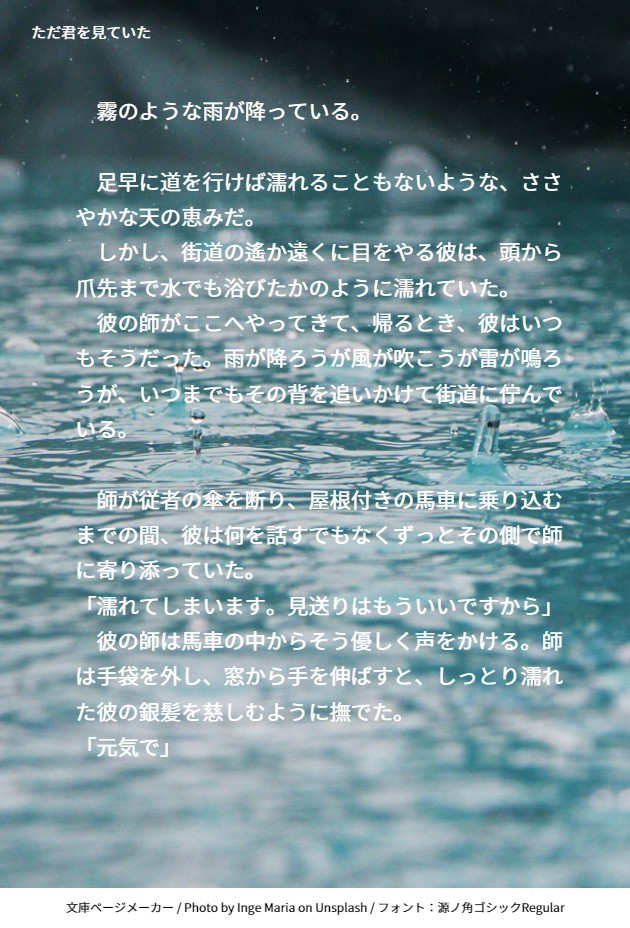
 コージ
Link
Message
Mute
コージ
Link
Message
Mute
























 ステキと思ったらハートを送ろう!ログイン不要です。ログインするとハートをカスタマイズできます。
ステキと思ったらハートを送ろう!ログイン不要です。ログインするとハートをカスタマイズできます。

 コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ コージ
コージ