viva la vida(中)隊員の一堂が、やっつけ隊の前から姿を消した。
ビル一つ分ある大きさの怪獣チャッカドンは、チャッカドンの動きを阻止せんと立ちはだかったワラトルマンとともに揉み合い、壊滅したビル群を作り上げた。
失われた経済的損失を考えるとアタマが痛いが、人死にが出なかったことだけが、辛うじての今回の功績だった。
「まさか、二回続けてワラトルマンが負けるとはな」
吐き捨てるように呟いた冷越隊員の声をかき消すように、零さんがいない!との叫び声が聞こえた。
河川の声だ。宇留の制止を振り切り、瓦礫の山を掻き分けて、「零さん」と一堂の名前を連呼していた時の、河川の鬼気迫る表情と震えた声は、今も脳裏に焼き付いている。
viva la vida
「まだ行方不明扱いですか?」
「死体も回収されてないからな。あいつが居なくなる直前、あいつはどこにいたのか、こちらも把握出来てない。ここに来てあいつのサボり癖が仇になったな」
隊員室では、一堂以外の隊員が揃った。
「一堂隊員は、サボってなんかいません」
先日、勤務が暇なのをいいことに、一堂の言いつけでカーテンを買いに走った河川が、堪りかねたように声を上げる。
「その話は後にしろ、河川」
隊長って唯ちゃんには素っ気ないよなと、出瀬が大間に耳打ちをする声が聞こえた。
「あのう、事代隊長さんよぉ」
歯切れの悪い口調で、冷越が俺に声をかけた。
「オレが、倍、働くから」
冷越の顔は、俺の方を向いていたが、目線は宇留のほうを追っている。
「千絵ちゃん……、いや、女の子たちは、今後こういう現場にはタッチしないというの、どうだよ?」
「どういうことよ、豪くんっ!」
宇留が咎めるように声を上げ、冷越の肩を掴む。
「女は役に立たないって言いたいの?」
「言ってねぇよ。そうだ、おめえ今すぐ辞表を出せっ」
「何言ってるのよっ。零さんが居なくなったいま、欠員をこれ以上出せないでしょうが?」
「んなもんしるかっ!あの零が居なくなったんだぞ。……おめえだってどうなるか分からねえんだぞ?」
「馬鹿ね……、豪くん」
忘れてた。コイツら、内緒で付き合っているんだった。
「バラとかユリとかタンポポみてぇな、おめえの綺麗な顔が傷つかねぇか、オレぁ心配でよ」
「もうっ……」
二人とも急にネッチョリとした雰囲気になりだしたので、俺はわざとらしく咳払いをした。
「お前ら、そういうのは勤務時間外にやってくれ」
既にこの二人については、公然の秘密と言ったところで、内緒もへったくれもないのだが。
「で?辞めるのか、宇留」
「辞めませんよ?結婚してご祝儀と休暇もらって、産休育休バッチリ取っておかないと、損ですもん」
「……お前ら、そこまで具体的に話がいってたのか」
出瀬の羨ましいやら、物星の尊いやらの溜め息が聞こえる中、通常運転の隊員たちに、俺は少し安堵した。
「だから、唯!帰ってくるわよ、零さんは」
「……なんで、そう言い切れるんだ、宇留」
「女のカンです。隊長、アタシたち女性隊員も置いといて損はないですよ。ね、大くん」
「え?ボク、千絵ちゃんたちの仲間なの?」
通信担当の女子二人と、情報処理担当の微妙な立ち位置の物星で、お互いに目を合わせると、三人とも次第に笑みが零れてきた。
「隊長、やっぱり居た方がいいですよ、女の子!」
「お前は、自分の士気のために言ってるんだろ、出瀬」
「まあまあ。陸奥博士が戦闘機もグレードアップさせるって言ってるし。豪!パイロットのおれがいるから、女の子たちは危険に合わせないぜ」
出瀬が細い目をさらに細めた後に、女子たちにウインクをすると、冷越が気持ちわりいなと呟き、それをきっかけに場が湧いた。……こういうのは、一堂の役割だったんだがな。いなければいないで、誰かがそれを引き受けるものなのか。やっつけ隊は脆い柱のようなものだと思っていたのは俺だけだったのかもしれない。
「事代隊長、やっつけ隊に男も女もありませんから」
河川は力強くそう言うと、お茶入れてきますねと、いつもの笑顔を見せた。
「男も女も無いわけないでしょう。馬鹿ですか、隊長は」
やっつけ隊の前から姿を消したはずの一堂は、俺のアパートに身を隠していた。
「それを言ったのは、河川だからな?」
「……さっすが、唯ちゃん。天晴れな心意気なのだっ」
「お前、河川が絡むと、人格が変わるなぁ」
俺が呆れたように呟くと、一堂は夕飯のカップラーメンを啜りながら返した。
「けど、女性は非力だし、他にもっと大事な役割があるから、最前線にいるのは反対ですよ」
「……大事な役割って?なんだそりゃ」
「誰だって、木の股から生まれないって話です」
キザな言い回しに流石に照れてきたのか、このラーメン、バター入れたら美味しくなりませんかね?と、一堂は問うと、俺は冷蔵庫を開け、乱雑にマーガリンを渡してやった。
「……賞味期限、切れてるじゃないですかっ」
「うるさい、このゲテモノ食いがっ!」
なんで、俺はこんな男を拾ってきてしまったのか。
ワラトルマンがチャッカドンなる火を噴く上に空を飛べる怪獣と二度目の対峙をし善戦したが、返り討ちにあった。ワラトルマンが出てきてからしたことは、壊滅したビル群を作りあげたことくらいにしか、世間は見なさなかっただろう。
実は私、ワラトルマンなんですよぉー
一堂は、人を食ったような笑顔で、出動前にそう言った。チャッカドンが二度目のおでましで、やっつけ隊の緊急招集の館内放送が流れた、あの日あの時だ。もともとくだらん冗談を抜かしては気を引きたがる男だからと、俺は聞き流していた。
その言葉が持つ言外のSOSに気づいたのは、ワラトルマンとチャッカドンの対決の後だった。一堂と懇意であった河川が「零さんがいない」と蒼白した顔で叫び、「零さん零さん」と連呼しながら瓦礫をかき分ける姿を目の当たりにして、俺は一堂の「実は私、ワラトルマンなんですよぉー」を思い起こしたのだ。
いざと言う時は自分を探してくれ。そう言いたかったのか、一堂。
「意外とイケますね、醤油ラーメンのマーガリン添え。隊長もやってみます?」
「食い物で遊ぶなっ」
「どうせ、賞味期限切れてるでしょ?」
「マーガリンなんぞ、なかなか使い切らんからな。男やもめだ、どうせ」
ワラトルマンが消えたと思しき場所に、一堂は倒れていた。救護班や病院にも、一堂を引き渡さず、男やもめの自分のアパートに、身柄を隠すように連れ帰ったのは、我ながら思考回路がイかれている。
「殺風景だな、隊長の部屋。給料お高いんでしょ?」
「寝に帰るだけだからな。根を下ろす気もない仮住まいだ」
結婚を予定していた相手に、愛想をつかされてしまったのだ。誰でもいい、殺風景なこの部屋を埋めて欲しいと思う気持ちで、俺は一堂を連れ帰ったのか、それとも、一夜限りとは言え、体の関係を持ってしまった一堂を、河川には取られまいという張り合う気持ちで、俺は一堂を連れさらったのか。いずれにしても、馬鹿だ、俺は。
「やっぱり私、こうしてはおれません。やっつけ隊棟もダメージ食らったんでしょ?明日から出勤しますね」
「そこまで、殊勝な心がけしておきながら、なぜ時々サボるんだ、お前は。いいから休んどけ」
「だって、唯ちゃん、私のこと心配してるだろうし……」
「まだ、足が動かんのだろう?やっつけ隊には、お前のことはちゃんと伝えておいた。河川も安心しているぞ」
大嘘つきだ、俺は。そんなこと一言も誰にも言っていない。死にものぐるいで一堂を探し回り、今でも、穏やかでない心中を笑顔で必死で押さえつけ、一堂の生還を待ちながら、普段と変わりなくお茶を入れる河川に、一堂は生きているからと、なぜ言ってやれない。
「お言葉に甘えて明日までここにいます。昨日は丸一日、私が眠ってたから、隊長のお布団取っちゃいましたね?ごめ……」
「謝らなくていい。客用の布団を買っておいた」
何言ってんだ、俺は。
ごめんなさいという一堂の言葉を遮るように、繋いだ言葉が、客用の布団を買ったなどと。いつまで、俺はここに一堂を囲う気だ?
「その布団は隊長が寝てくださいな。新品なんだし」
「お前、それじゃ客用の布団の意味がないだろう?」
「別に一緒に寝てもいいんですが?」
「寝るもんかっ!」
河川に一堂を渡すべきなのに。
「……そのカーテンはどうしたんですか?」
河川が一堂のお使いで買ってきたカーテンだ。隊員室のカビたカーテンの代わりに使うつもりだったが、一堂の行方不明騒ぎで、それどころではなく、河川も行方不明直前に会話していた一堂のことを思い出してしまうだろうから、このカーテンを持って帰ってきたのだ。俺はそれを広げると、部屋の真ん中にあたる天井部分から、天幕のように吊るした。
「この部屋の間仕切りだ。お前にもプライバシーがあるだろ」
「隊長職なのに、六畳一間に住んでるとは、正直思いませんでしたがね」
「お前はどーなんだ、お前はっ」
俺はこの男のことを何も知らない。
一堂の消息を心配しているかもしれない、一堂の実家に電話を入れようと思った。連絡先を聞こうとして、上司にもあたる陸奥博士に一堂の実家の連絡先を訪ねたが、「何かあれば、こちらから連絡をしておくから、その必要はない」と返されたし、一堂を囲っていることを、上層には伝えていなかったので、あっさりと俺は引き下がった。
「私の生活も殺風景なもんですよ。怪獣のフィギュアがある以外は隊長と似たようなもんです」
一堂を自分の生活に引き入れた。以前に、一堂に抱かれた夜のめくるめくとした心の動きと、対照にひとりの部屋の寂しさに、心が散り散りになり寝つきも浅かったが、この男がいることで、不思議と頰が緩み、心も波打たない。
一堂、お前がワラトルマンだってなんだって、俺は構いはしない。ワラトルマンであることが、お前を縛り付けるなら、お前は戦いに戻らなくていい。そんなことを言ってしまったら、根はシビアな性格の一堂だから、一笑に付されるだろうが。
一堂の表面に見えるふわっとした性格や表情をそのまま信じて、俺は共にいる。やっつけ隊の連中は、俺も含めて一堂はそういう男だとしか、知らない。
「これまたオッサンに不釣り合いなメルヘンチックなカーテンだなぁ」
カーテンの間仕切りをしている俺を見上げて、一堂は呆れたように呟いた。
一堂の性格を読んだかのような、パステルカラーが色とりどりにやかましい、花や小動物の図形が溢れたカーテンだ。
「悪趣味だろ?河川が選んだやつだぞ」
「なるほど、芸術性に長けたカーテンなのだっ。殺風景な部屋に、なんというかこう、真心とか、メッセージを届けているというか……」
「抜かしてろ」
こいつは、河川を崇めないと死ぬのか。
「隊長?」
「なんだ」
「一緒に寝ませんか?」
「足も治ってないやつが何言ってるんだ。何も出来やしないだろ」
「……一緒に寝ませんかって言っただけなのにね、何を想像したんだか」
「くっ」
間仕切りが出来たら、一堂の空間と俺の空間が出来た。
「湯を沸かしてやるからな、体を拭けよ」
「シャワー浴びたかったなー」
「湯船しかない、ぼろアパートで悪かったな」
アパートに連れ帰って一日は眠りこけ、目覚めた時は右足の足首に違和感を生じ、思うように動けなかった。俺が捻挫みたいなもんかと言うと、一堂はそろそろかな、と諦めたように笑った。その言葉の意味を深くは追求しないでいる。一日だ。あと一日だけ、ここに居させて、病院にでも行かせよう。明日は上層にこのことを報告して……処罰は免れないか。ほんと、何をやってんだ俺。
「隊長」
一堂の声は、河川が買ったカーテンの間仕切りの向こうだ。その向こうで、一堂は体を拭いている。夜を共にした時の裸がそこにある。正確に言うと、この男は全裸にはならなくて、ガウンを着たまま、俺を抱いていた。
「……こっちに着て、身体を拭いてくれません?背中に手が回らなくて」
「嘘つけ。お前、伏臥状態反らしが直角になるくらい、身体が柔らかいだろ?」
「ちえっ」
カーテン向こうで、一堂は脱いでいる。一夜限りの性交渉をしたあの夜に、ガウンに隠れて見えなかった背中が丸出しだ。
「……隊長」
「はいはい、次はなんだっ」
「なんで、私のこと何も聞かないんです?」
性交渉の時、一堂がガウンを脱ぎたがらなかったのは、その背中に隠したいものがあったからだ。
「お前が何も言わないからだよ」
俺の部屋で、丸一日眠りこけていた一堂を服を脱がせて介抱する時、俺は一堂の背中に、ケロイドがあるのを見てしまったのだ。以前の身体検査ではこんなものはなかった。……いつものくだらない冗談だと思っていた、一堂の「ワラトルマンなんですよぉー」が真実だとしたら、チャッカドンの炎を背に受けて出来た傷だということが成り立つし、何よりワラトルマンが消えた場所に一堂が倒れていたことが何よりの証拠だ。
「一堂」
「はい」
「居たいだけ、ここにいて構わんぞ」
カーテン向こうで、一堂がふふっと笑う声がした。
その晩、「隊長の布団がいいです」と一堂に俺の布団を取られ、俺は客用の布団で寝た。河川が買ってきたカーテンの間仕切りでお互いを隔てたままだ。
不思議なくらいに、昨晩はよく眠れた。カーテン越しとはいえ、となりに誰かの寝息を聞きながら、ゆっくりと目覚めた朝は悪くない。
一堂は、だいぶ良くなりましたからと、足を引きずりながら、簡単に朝食の準備をしてくれた。久しぶりに焼いたトーストに、賞味期限が切れたマーガリンをつけて食べる。一堂とともにした朝食はこれで二度目だ。
一度目は、一夜限りの逢瀬を過ごした後に慌ただしく迎えた朝だった。二人でコンビニエンスストアに駆け込んで、パンやらおにぎりやらを買い、朝帰りですねなどと一堂が言うのを苦笑いしながら、駅のホームにて、牛乳で流し込むようにして取った朝食だ。
「これはなんだ?」
「林檎のうさぎさんですよ?」
うさぎさんですよはいいが、耳を立てようとするあまり、皮を削り過ぎて、身が半分以下になっていた。やはりこういうことは、女の子がしてくれた方がいいなと一堂はつぶやき、俺は、天井から吊るされた間仕切りのカーテンを見ながら、河川を思った。
「隊長ってさ、零の行方不明にダメージ受けてないよね」
やっつけ隊にて、いつもの職務に追われていると、大間に声をかけられた。
「なんだか今日は機嫌が良さそうに見えるもん」
「そ、そうか……」
のんびり屋でグータラしていると思っていた男に、思いも寄らない鋭い指摘を受け、俺は狼狽えた。
「俺は元軍人だからなっ。気持ちの切り替えなどお手の物だ」
「秘密っぽいけど、零とは深い仲に見えたよ」
……思い出した。一堂が河川にカーテンを買いに行かせた後に、一夜限りの逢瀬のことを、一堂と言い合っていた現場に、大間は居たのだ。てっきり、あの時の大間は昼寝しているものだと思っていたが。
「ば、馬鹿を言え。お前も物星や宇留みたいなこと言うんじゃないっ。持ち場に戻れ」
「美味しいもの、せしめられると思ったのになー」
「河川に頼めっ。林檎くらいは剥いてくれるぞ」
「その唯ちゃんだけどさ、隊長からほどほどにしろって言っといてよー」
「………河川がどうした?」
陸奥博士とともに、整備班にまじって、戦闘機のメンテナンスをしているというのだ。
確かに通信係は業務が少ないし、他の隊員でも兼ねられる仕事だ。やっつけ隊の中でも、雑用係の側面もあるし、言ってはなんだが、女子のために置いているようなポジションだ。
「河川!」
「はあい」
戦闘機格納庫に入ると、陸奥博士とともに戦闘機のメンテナンスに精を出す、河川がいた。面食らう俺に、陸奥博士は、今日はもういいね、と河川に声をかけ作業を終了した。俺と河川はつれだって隊員室の方向へ歩き出す。
「じっとしてると、悲しい事ばかり考えちゃうから」
整備班に借りたツナギ姿のまま、河川は俺を見て笑いながら答えた。
一堂もかつては、陸奥博士と一緒に火器の改造や戦闘機の整備をしていたのだ。ヘッタクソな林檎のうさぎを作る男だが、機械いじりは得意だった。
そして、今は河川が身に余るツナギを着て、機械いじりに奮闘している。やはり女子は好いた男の軌跡を辿りたがるものだろうか。
「……目が赤いな、河川」
「すみません……」
「謝らなくていいが、ちゃんと寝ろよ」
一堂を失ってから、河川は眠れない夜を過ごしているのだろうか、それとも、毎夜泣いているのだろうか。
「お前の気持ちもわかるが、体調管理も仕事のうちだぞ」
お為ごかしか。河川から一堂を奪ったのはこの俺なのに。
「隊長」
「どーした?」
「わたし、役に立っているでしょうか」
「あのなあ……」
河川が役に立っていないというなら、昼寝ばかりしている大間や、乱闘騒ぎを起こす冷越や、コンパに余念のない出瀬などどうなるのだ。
「ちゃんと見てなくて悪かったな。ちゃんと役に立ってるぞ、お前さんは」
「良かった。うふふ」
「そうだぞ、わはは」
こういうところか。一堂が河川に惑わされるのは。
「隊長もみんなも普段よりうんと明るいから、わたしも沈んでいてはダメですね」
「生真面目だなぁ、河川は」
宇留も物星も、普段より身振り手振り激しくガールズトークとやらに入れ込んでいるし、出瀬は一堂の代わりにくだらない冗談を連発しては、冷越も声を張り上げてツッコミ代わりにプロレスの技をかけている。それを見て俺はいい加減にしろと声を張り上げる。
「うふふ。隊長ってまるで、学校の先生みたい」
「やめてくれ。命かけた職場だ、ここは」
ワラトルマンが、チャッカドンに二度やられた。
今まで、ワラトルマンが盾になり、怪獣、地底人などを殲滅してくれていたのが、ワラトルマンのチャッカドンの敗北で、盾は完全ではないものと知った。
「ワラトルマンが、必ず助けに来てくれるとも限らんのだぞ」
盾を失った、我々は脆い。そして、その盾を俺は人類に返したくはないのだ。
今日こそは一堂を囲っていると上層に伝えるつもりだった。一堂も、職場に戻りたがっていた。戻ったら、空元気で回っていた、職場も、本当の活気で満ちてくるだろう。
「安心して甘えきってました。ワラトルマンや零さんに」
「……ああ」
「いないとすごく心細くって。早く帰ってきてほしいのが本音です」
頼られたら、あの男のことだ。お待たせと、極上の笑顔でホイホイと駆けつけ、そして、自分の身をすり減らす。それを知っていて帰還を期待しているのだとしたら世間は鬼だ。
「いいな、お前らって」
「なんのことですか?」
二十歳過ぎの小娘の言葉に、カチンと来た俺は、すでに一堂のことに関して、冷静さを失ってきていた。
「聞き流せ。独り言だ」
一堂と河川は、傍から見たら、恋人か新婚夫婦のようだった二人だ。河川の心細いという言葉も、一堂と仲の良い証だとしか取られまい。
「でもね。わたし、待ってるだけじゃ嫌なんです。ワラトルマンや、零さんが、なんとかしてくれることばかり期待するのは違う気がして、そう思うとジッとしてられなくて」
一堂が河川に惚れたのは、こういうところなのだろう。
「無理はやめとけ。自己満足や焦燥感でやるくらいなら、自分の仕事や体調管理を万全にしろ」
母親が病気がちで、父親の収入が乏しく、幼い弟を抱え、どんな状況でも自分の中の最善を探している。一堂は自分の中の鋼の部分を隠しているが、河川はいつも剥き出しだ。一堂は会話の端々で、そんな彼女を時に心配し、時に崇めていた。
「女子には女子の役割があるだろ?宇留を見てみろ?笑ったり着飾ったり、毎日楽しそうじゃないか?肩の力を抜いてけ?な?」
「……零さんが居なくなって、そんなこと心からできません。千絵だって、わざと楽しそうにしているの、わたしにはわかります。零さんも、そんな人でした。だから、わたしには眩しかったんです。出会った時からずっと生き生きと怪獣退治に乗り出す零さんがいて、居なくなったのが頭でわかっていても、気持ちがついていかなくて。でもね。零さんがしていた整備の仕事をやってたら、零さんがそばにいてくれる気がしたんです。零さんがやっつけ隊みんなを盛り上げてくれたあのころが、忘れられないの。わたし、すごく楽しかったんです。たくさん愚痴も聞いてもらったし、笑わせてもらったし、優しくしてもらっちゃったから……」
「そうかそうかー」
河川には優しいんだな、河川には。
「零さんに及ばないけど、零さんがしていた整備のお仕事を通じて、役に立ちたいって思ったの。わたし、やっつけ隊にも何も返していないから」
「返していないって……?」
「うち、あまり裕福じゃないから、ここを勤める時に支度金たくさんもらっちゃったんですよ」
「支度金?聞いたことないぞ、それは」
急に話がキナ臭くなりだした。もちろん二十歳そこそこの河川は、就職する際のお金を出してもらったとしか思っていないだろう。
「事代くんっ」
「……陸奥博士?いつからそこに」
禿頭とメガネの朴訥とした人の良さそうな博士がそこにいた。一堂も河川も、そして俺も、この人ならばと信頼している人物だ。
「河川くんに教えそびれたことがあってね。ちょっと河川くんを借りるよ」
「はあ……」
河川は、うさぎのように赤く充血した目を三日月のように細くして笑うと、俺に会釈したのち、陸奥博士と一緒に、再び戦闘機の格納庫へと戻っていった。
二人の後ろ姿を見送ったのち、俺は大事なことに気づく。
「河川にはせめて、一堂が生きていることくらい教えておくべきだったかな」
「学校の先生の方が向いてますよ、隊長は」
「お前ら、俺をなんだと思ってるんだ」
夜だ。俺のアパートに男二人だ。
河川が買ってきたカーテンが、六畳一間を区切り、それぞれ俺と一堂がいて、それぞれの布団で横になっている。
「なんでしょうね?肩書き以外で自分が何者かだなんて、考えたことありますか?」
「質問に質問で返すな、この厄病神がっ」
「正義の味方と言ってみたり、悪魔だと言ってみたり、最終的には神さまですか。忙しいなー、私」
俺の部屋で過ごす、最後の夜だ。今晩も一堂は、俺の布団で寝る方がいいと訳のわからん主張をした。俺は一堂からカーテンを隔てて、客用の布団で寝ている。
「明日からキリキリ働いてもらうからな。ゆっくりできるのも今日だけだと思え」
一堂を囲っていることを伝えていない上層になんて言おうか。その前に病院だ。一堂が引きずっている右足は中々良くならない。捻挫ではなく神経麻痺をおこしているのだろうか?休みを取らせてやるべきだ。例え、この男が、人類の盾になる、ワラトルマンだとしても、この男にはこの男の生命がある。人々の期待なんかで身を擦り減らしてはならないのだ。
「私を消耗品扱いしてませんかね」
「ははっ。それなら俺も消耗品だ」
部屋の明かりを消した後の、男二人の寝室を、一堂はどうみているのだろう。俺は夜目に慣れて、いつもの自室の天井と、河川が買ってきたパステルカラーと花や小動物のファンシーな絵柄がやかましいカーテンを、明日から、これを一人で見るのかとぼんやり思っている。
「今日の晩ご飯、楽しかったですね」
「ああ。お前、飯作るのヘッタクソだけどな」
宴のあとの静寂が、しんと心に響く。晩飯どうしよう、なんて、考えたのはいつぶりだろう。一人で暮らしていた時は、スーパーで半額の弁当を適当に買って帰るか、カップラーメンで済ましていた。ただのエネルギー源にしか思えなかった食事が、家で待っている人間がいると思うと、ようやく献立に気が回るのもおかしなものだ。
「お腹に入れば一緒なのに、まさか隊長がカレー作り出すなんて思わなかったなー」
「お前が、レトルトのカレーでいいなんて味気ないこと言うからだ」
「美味しかったですよ」
「いまなんて言った?」
「二度も言いません」
河川に向ける優しさの三分の一くらいは、こちらに向けてくれないものか。
「足、大丈夫か?」
「おやおや。事代隊長は優しいな」
「お前が悪魔でも正義の味方でも、痛いものは痛いだろ」
「大したことありません。痺れが取れないくらいですよ。昔は一晩寝たら治ったんですがね」
「ずっと治らなきゃいいのにな」
自分が言った言葉に俺自身驚いてしまった。……そうだ。治らなければ、一堂は第一線で働くこともない。
「鬼ですか、あなた」
カーテン向こうから、引きつったような一堂の声が聞こえる。
「世の中にはな、俺が作ったカレーより、美味いものがたくさんあるぞ。この前のキャバクラのネーちゃんも、うまくやれば、お手合わせ願えるかもしれん」
「いやです、そういうのめんどくさい」
「お返しだよ。何日か前に、お前が俺に言ってた、生きてさえいればいい人に巡り会えるってやつな。お前だって、思うことはいっぱいあるんだろう?」
「やめてください、キリがない」
「なあ。救いきれないものは救いきれないで、いいんじゃないか。ワラトルマンよ」
もう一つの名前で呼んだ。ビルを壊す破壊神でもあり、火を噴く怪獣から人々の盾となる、救い主の名前だ。
「………急にどうしたんです?」
「お前を囲うのは最後の夜になりそうだから、言ってみただけだ。お前は俺に知ってもらいたかったんだろ、正義の味方さんよ」
背中にやけどを負って、足を引きずらせてまで、人類を守っているのだ。それが彼にとって、なんの得であるかすら、わからない。
「すまないとは思ってますよ。怪獣をやっつける為とはいえ、私の不手際で損害も出してしまっているし、隊長も、忙しさのあまり、彼女に逃げられてしまった」
「蒸し返さんでいい」
一堂は思うところを、俺には吐き出す気持ちになったのだろうか。ワラトルマンは故郷の職業の一つであること、故郷から出奔した怪獣たちを懲らしめ回収することが自分の任務であることを語り出した。
「人間の一堂零として働いて、ワラトルマンとして体を張って。この一粒で二度美味しいみたいな扱いはどうなんですか?」
「アーモンドグリコみたいな生き様だな、お前」
話しているうちに、一堂はやっつけ隊にいる時のいつもの口調に戻っており、俺は安堵の溜息を吐いて続けた。
「お前も河川も、妙なところで生真面目だからな。河川は家のため、お前は人類の平和のため。やめとけやめとけ。体を張ったところで給料なんて対して上がらないぞ」
「せめて給料二倍にしてもらえませんかね?」
「言う相手が間違っとるわ。それに俺に言ったところで何も変わらん」
誰かの期待のために、自分の人生を捧げる真似をするなと言ったのは、俺だ。この殺風景なアパートの自室が、俺のように誰かの期待のために自分の人生を捧げた成れの果てだった。肩書き抜きでは自分が何者かも語れない。
「お前が、俺に正体を明かしたということは、お前は自分のことをどうでもいいなんて、本当は思ってないからだろう」
「情が濃すぎるんですよ、あなた。やっぱり、学校の先生にでもなれば良かったんだ」
「だから、自衛隊から、こんなところに左遷されたわけだよ。そっちへ行くぞ」
「ちょっと……!」
河川が買ってきたカーテンを開けて、一堂の布団に潜り込んだ。いや、もともとは俺の布団だ、ややこしい。客用の布団を用意したのに、なんで俺の布団で寝たがるんだか、こいつは。
「……へへっ、来ちまった」
「何やってるんです、明日早いんでしょうが?」
夜目に慣れたせいか、暗闇の中でもぼんやりと一堂の輪郭が映し出された。表情までは分からない。そういうやつだ。いつだって朗らかで笑っているけれど、この男が、何者かなんて、誰も知らない。ワラトルマンだと自分の正体を口にしたけれど、人間の一堂零は、何者なのかもわからない。
「なあ………………するか?」
「………」
「………」
「……………」
「……………」
「………………………」
「聞かなかったことにしてくれ」
「聞く方が野暮ですよ、あんた」
一堂のいる布団に潜り込んだときのこもった熱が、俺の体に伝わり、熱くなりだす。
「昨日、さんざん、私が誘ったじゃないですか」
一堂は俺の首に手を回すと、顎、首筋、鎖骨と、軽く口づけをしだした。皮膚を軽く口でつまんで吸う音が、殺風景な部屋中に響いていた。
「……病人だったろ?昨日のお前は」
一堂が俺の首に手を回しているのなら、俺は一堂の腰を体に引き寄せていた。
「それに忘れてるだろうがな、右の足首がろくに使えていないんだぞ、お前」
「……わかってますよ」
「この間した時、お前に俺は女役に見立てられたからな。お前が足を使えない分、今晩はお前が俺にどうされるかわかってるだろ」
「うっわ、変態だなあ」
一堂の腰に回した手を、一堂の服の下に滑り込ませ、一堂の背中を直接触る。俺の手のひらは一堂のすべすべした感触を味わうと、ある部分に触れた。
「なんでそこ、触るんです」
一堂は吐息交じりに話すと、身をよじらせた。
「もし、お前に親というものがいたとしたら、申し訳なくてな」
「仕事ですよ、気にしないでください」
怪獣チャッカドンの吐いた炎を浴びて出来た、背中のケロイドだ。
「痛かっただろ……」
そう言う俺の唇を塞ぐかのように、一堂は俺に口づけをした。
俺の目は闇に少しずつ慣れてきたが、怪獣から人類を救う守り神は、その素顔も声も、人々が眠りにつく夜中でも、 なかなか、つまびらかにしない。
「参ったなぁ。人恋しくなっては、生きていけなくなるのに」
そう呟くのとは裏腹に、一堂は盛んに顔を交互にさせては、俺の唇や舌を溶かし出した。
「お前の心も体もお前のものだろう。お前が心のままに生きてなにが悪い」
こいつの心に河川が住もうが、一堂零という男が、仮の姿だろうが、もうどうでもいい。俺は一堂の服を脱がして、一堂も俺の服を脱がし、胸と胸を合わせた。
「隊長の胸毛、ジョリジョリしてますね」
お前の胸は早鐘のように鳴っている癖に、それが、胸郭を震わせて、俺の体まで伝わっているのに。
「ムードもへったくれもないな、お前……」
「だって私……」
声が震えている。
「さては、照れてるのか、お前?」
「ちゃっちゃっと済ませてくださいよ!このオッサンはもうっ」
一堂の故郷のワラトルマンという仕事がどういうもこなのかは、俺の頭の中では、理解の範疇を超えている。
背中のケロイド、必死で街を守ったのにも関わらず、浴びせられる罵声、俺が見つけなければ、人知れず瓦礫の中に埋もれるかもしれなかった体、悪魔でもなく、正義の味方でもなく、消耗品と自分で揶揄もしてしまいたくなるだろう。
誰かに認めて貰わないと、この部屋のように、殺風景な心になりそうになるのは、俺も同じだ。誰がそれを満たしてくれる?
怪獣が現れて、体を張って助けに来た時にだけ貰える賞賛か?
救い主だ、守護神だと、世間や、やっつけ隊が当たり前のようにそれを受け取るというのなら、誰が、神になりたがる?
「隊長……痛いっ」
「悪いっ、力入れすぎた」
「鬼だ、あんた」
「隊長だったり、鬼だったり、挙げ句の果てには、学校の先生が向いているとか言われるわ。なんなんだ、俺は」
「あなたは隊長ですよ。あなたから見て私はなんですか?」
「タチの悪い部下だ」
ようやく、ぎこちないながらも行為は終えた。夜も白み始めている。
二人とも服を着ず、体幹と体幹を合わせ、時にはお互いの手足や体毛を絡ませたままだ。
「なあ、一堂」
「はい」
俺は、前の夜に一堂に約束した。
居たかったら好きなだけ居ていいと。
「逃げるか、俺と」
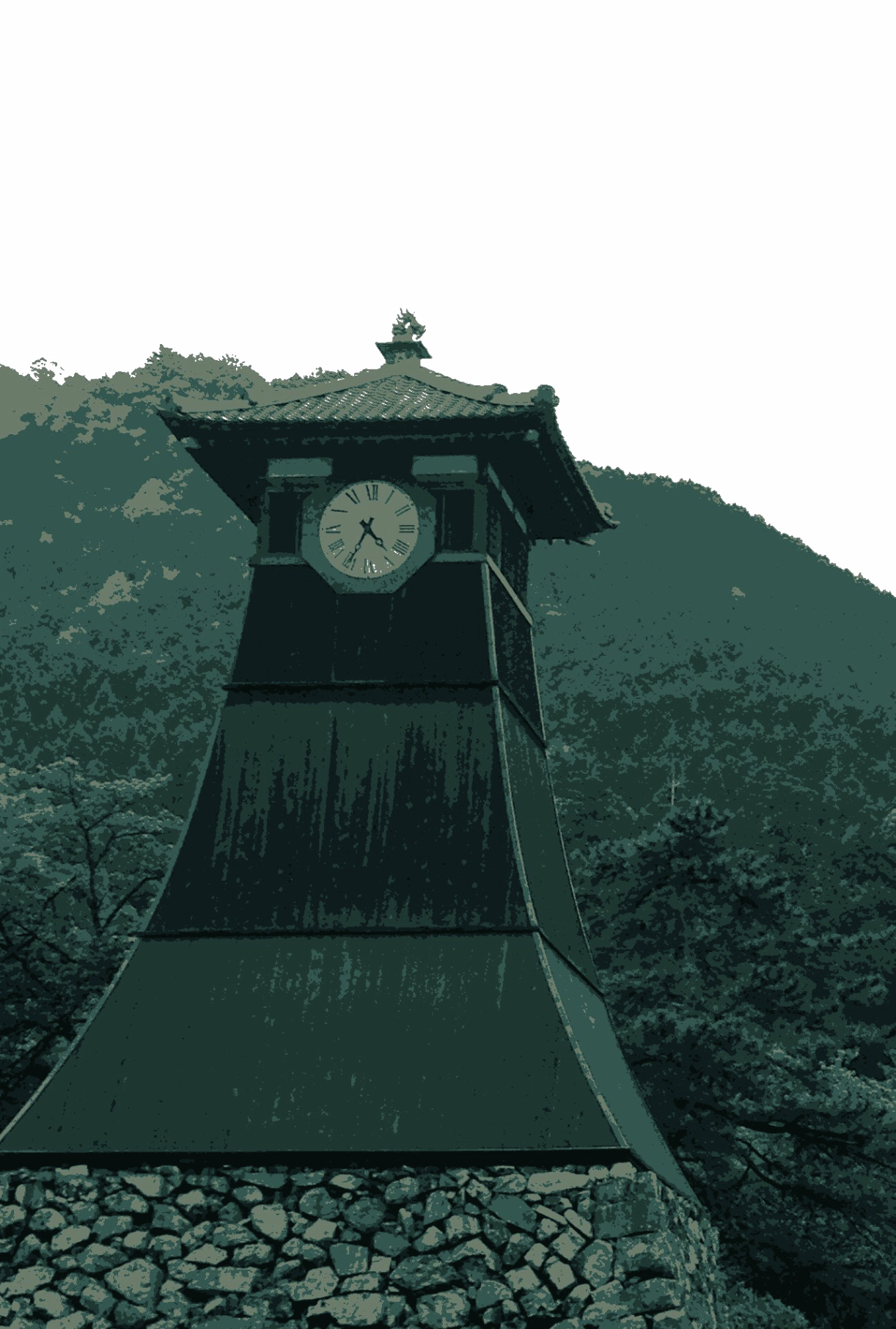
 こまつ
Link
Message
Mute
こまつ
Link
Message
Mute

 こまつ
こまつ こまつ
こまつ こまつ
こまつ こまつ
こまつ こまつ
こまつ こまつ
こまつ こまつ
こまつ こまつ
こまつ こまつ
こまつ こまつ
こまつ こまつ
こまつ こまつ
こまつ こまつ
こまつ こまつ
こまつ こまつ
こまつ こまつ
こまつ こまつ
こまつ こまつ
こまつ こまつ
こまつ こまつ
こまつ こまつ
こまつ こまつ
こまつ こまつ
こまつ こまつ
こまつ こまつ
こまつ こまつ
こまつ こまつ
こまつ こまつ
こまつ こまつ
こまつ こまつ
こまつ