こどくな星の名清らかなるなりそこない
「お疲れ様でしたあ!それじゃあまた明日!」
イベントに向けた話し合いが終わって、斑は学園内のとあるレッスンルームを後にした。学生アイドルにとっての師走とは、かくも忙しい時期である。クリスマスに正月にという季節行事は勿論のこと、ユニットに関わる様々な年度内の手続きや、学生としての試験なども待ち受けているからだ。
もちろん夢ノ咲学園もその多分に漏れず、未だ学生の身分である斑も方々を駆け回っている。今日終えたのはとある商店街のクリスマスライブのに向けた話し合いだ。年末商戦の賑やかしとして、アイドルを呼ぼうといった分かりやすい企画である。なのだが呼ばれたユニットに予期せぬトラブルが起こってしまい、斑は足りぬ人手を埋めるための手助けをしているのだ。あまり出しゃばりすぎて仕事を奪ってしまうのも良くないだろうと考え、今回の斑は裏方のフォローに専念していた。
おおまかな方針に細かい肉付けをしていくための会議ではあったが、予想よりも遙かにスムーズに進んだのは嬉しい誤算だ。とは言え、日は既にとっぷりと落ちきっている。暗い廊下を進むたびに、窓の外で瞬く夜空が目に入った。
さてどうしようかとあてども無く歩いていると、ふと視界の端にゆらめく光が見えた。一番端にある教室から、微かな明かりが漏れていたのだ。授業では使われていない空き教室であるが、斑はその部屋が別の用途で使われているのを知っていた。
少し引き返した所にある自販機に立ち寄って、湯気の出そうなほどに熱い缶を二つポケットに押し込める。そしてそのまま、件の教室へと近づいていった。木製の引き戸にノックをすれば予想通りの声が返ってきたのを、斑は知らずの内に笑みを浮かべた。
「こんばんは、あんずさん!ママだぞお……☆」
「三毛縞さん?どうかしたんですか」
「つい通りかかっただけで、特にこれといった用事はないんだけどな」
勢いよく開いた扉の先には、驚いたようにこちらを見る少女がいる。半分だけ明かりのついた教室の隅で、あんずは裁縫道具と書類に囲まれていた。
使われなくなって久しいこの教室を、あんずが生徒会に許可を貰って簡易な作業部屋にしていることは知っていた。正確にはあんずの他にもこの教室を使っているらしいが、なんとなく居残っているのは彼女だという予感があった。
あんずに近しい椅子を引いて、斑は机ひとつぶんの距離を開けて座った。そのまま手を少し伸ばして、蓋の開いた裁縫箱の横に先ほど買った缶コーヒーを置く。
「大したものじゃなくて悪いが」
「あ、お気遣いありがとうございます」
しきりに申し訳なさそうにしているが、何も謙遜することなど無いのに。アイドル達への彼女の献身は、缶コーヒーひとつじゃとてもつり合いが取れない。この学園のアイドル達は皆、うら若き少女の青春を星々への慈愛一色に塗りつぶしてしまった罪科がある。斑とてアイドルである限り、この輝かしくも憐れな少女の献身を享受する身分であるのだから。その事実はいつだって残酷でもあった。
チラリと見下ろした資料にはデザイン画らしきラフがいくつか書き連ねてあった。色や形からしても、あんずが今ちょうど手にしている衣装で間違いないのだろう。スパンコールの鮮やかな、冬らしい壮麗さと暖かみのある良い衣装だった。
「もうほとんど完成してるんだなあ!さすがあんずさん、出来のいい娘でママも鼻高々です!」
「あと飾りをつけたら完成なんですけれど、キリの良いところまで進めたくて……」
「じゃあそれまで俺も待とう、送っていくから終わったら教えてくれ」
机の上に頬杖をつく斑を、あんずが驚いたような顔で見る。いつもだったら彼女の同級生たちが、騎士のように家まで送っていくのだそうが、生憎今日彼らは仕事である。それもあって斑は様子を見に来たのだけれど。案の定あんずは、夜道をひとりで歩いていくつもりだったらしい。
「流石にそこまでしてもらうわけには」
「どうしても断るんなら、他の人を呼んであんずさんを送ってもらうまでだなあ」
「……そうしたら、三毛縞さんにお願いします」
「うんうん、母娘むつまじく帰ろうなあ!」
がっくりと諦めた様にあんずが肩を落とす。今ここに居ない誰かを呼びつけられるよりは、斑ひとりの世話になった方が良いと考えたのだろう。本当に思考の分かりやすい子だと、思わず笑顔になってしまう。
手早く作業を進めるためか、あんずはそれきり黙り込んだ。針が布の上を進む音と、衣擦れに潜むふたりの呼吸だけが場に響く。斑は特に何をするでもなく、じっとそれら全てを見つめていた。
華奢な手の中で衣装飾りが煌めくのを見て、ふと学園近くの並木道がイルミネーションに彩られていることを思い出した。自治体が町おこしの一環として行っているそうで、規模こそ小さいがそれなりに見栄えがするのだ。今日はバイクで来ているし、どうせなら帰りはそこを通っていこうと思った。少し早いクリスマスプレゼントだなんて、気障なセリフを言えはしないのだけれど。
迷わずに糸と針を生地の上に踊らせていく手指は、斑のものよりもずっと小さくてか細い。何も知らない少女と高を括って、斑が利用しようとした手だ。良いように騙して甘やかして、それで上手くいくと考えていた。斑が勢いよく握りしめたなら、柔らかいこの手なんて容易く傷つけてしまうだろうに。
いつだって消えない罪の意識を抱いている。ありもしない過去を作り出して、近づいて利用しようとして。そのくせ身勝手な感傷と罪悪感に満たされているのだから救えない。こんなにも愚かな男をそれでも慕っていてくれているのは、彼女が何も知らないからだ。
少し伏せがちな目線で己の手元を見つめているのは、かつてただの転校生だった少女だ。寄ってたかって仕立てあげて、革命に光もたらす女神となることを自ら選ばせた。それを都合がいいなんて思っていた、あの日の斑だってその行いに加担したのだ。
窓の外の空気はどこまでも冷え切って、夜闇の暗さを寒々しく染め上げている。明日は雪になるだろうと天気予報が伝えていた。そのままどこまでも降り積もって、醜いものや汚いものなんて全てを覆い隠してしまえばいい。あんずの目に映るものが、美しく輝く白銀の世界だけであればいいのにと。斑はひとり考えた。
こどくな星の名
もうすぐクリスマス、らしい。気まぐれにつけたテレビ番組の特集で、あんずは季節行事の訪れを知った。ゲートキーパーと名乗る男の家に住まわされて、もっと言うならば軟禁状態に置かれて早や数日。外に出ることも叶わないものだから、日々の移り変わりはカレンダーやら時計やらで知るばかりだ。
「おい、茶を飲んでいるなら俺の分も淹れたらどうだ」
大きなソファに一人で座るあんずに、後ろから掛かる声がある。一応はこの家の主であり、あんずが契約を交わした男その人だ。言葉すら一切返さないのはいつものことであるので、男は特に気を咎める様子も無い。
通りがかったついでに声を掛けただけだったらしく、男は身支度を始めた。何処かへ行くのだろうが、いまのあんずはそれを知ってもどうすることもできない。いつもと変わらない背広姿の男を少し見やって、またテレビへと視線を移した。
「俺は少し出かける、いつも通り良い子でお留守番でもしていろよ」
振り返りもしない少女の背中にそんな言葉を投げて、男はさっさと何処かへ消えてしまった。たぶんまた何かしらの悪巧みでも進めているのだろう。一切の情報を絶たれ、アイドル達と物理的な距離を離されているのこの身では、すべてにおいて推測しか出来ないことが歯がゆい。ティーカップの中身を飲み干そうとして、とっくにカップもポットも空であったことに気がついた。
「ふぅ……」
細く長いため息をついて、部屋の中空を見つめた。色々なことに目を瞑るならば、いまの状況は突如として降って湧いた休暇と呼べなくも無い。衣食住の心配は要らず、頭を悩ませる案件からも引き剥がされ、ただゆっくりと過ぎていく日を受け入れる。けれど常に働き続けていたこの身体にとっては、何も出来ないことこそが苦痛の日々だ。あの男はそれすらも見越して、あんずをこの状況においたのだろうか。だとしたら何と趣味が悪いことか。
夢ノ咲学園に足を踏み入れたあの日から、あんずはずっと走り続けてきた。巻き起こる革命に打ち込まれた楔のように、目まぐるしくも愛しい綺羅星を追いかけ続けてきたのだ。
女神の呼び名は未だこの薄い肩には重苦しいと感じる時もあるのだけれど。それでも革命の旗を掴んだのであれば、ただの少女ではいられなかった。無知な女子高生では、星々のようなアイドルを手助けできない。
彼らをさらに輝かせる術を知りたくて、彼らの笑顔がもっと見たくて。何もかもを薪のように燃やし尽くしてここまでやってきたのだ。今更立ち止まろうにも、どうすればいいのかなんて分からなくなってしまった。
「だってみんな、本当に綺麗だから」
プロデューサーとはアイドルを支える影であれと、胸に秘めた時に。まるで惑星に付き従う衛星のように生きていこうと思った。アイドルたちはみな、それぞれ生まれ持った物語の掛け替えない主役だ。それを一番間近で見ていられるのならば、何と嬉しいことだろうか。
なのにある日、あんずがとうに押し込めたはずの過去を揺り動かす男が現れた。
「ああ、やっぱり!この笑顔を覚えてるぞお、懐かしいなあ!」
ただの少女であるあんずは求められない。求められているのは女神でプロデューサーで転校生で。心からそうなりたいと望んだ姿が揺らいでいく。私すら忘れてしまったような私をこの人は、三毛縞斑は覚えているのだと。
(どうしてそんなことをするの!)
身体も心までも全部捧げて、すり減らして、走り続けて走り続けて走り続けて。やっと私はプロデューサーになれたの。どうか暴かないで、そのまま見逃してよ。私の中に潜んだままのただのあんずを、ひっそりと眠らせておいて欲しい。
混乱して申し訳なくって、いっそ逃げ出してしまいたくなる。きっと昔なじみにただ声を掛けてくれただけなんだろう。初めこそ驚きはしたが、斑が優しさを周囲に向けようとする人であることは分かっていた。それでもあんずの心に生まれた動揺を、無かったことにするなんて出来なかった。
だからあんずは、斑をよくよく見つめるようになった。母と呼ぶことを要求されるのは困りものだったから、あまり自分から近づくことはしなかったけれど。それでも可能な限り彼を見つめた。知らないからこそ、斑の事をもっと知ろうとしたのだ。だから、彼が抱える言いようのない寂しさにもすぐに気が付いてしまった。
騒がしい場が好きで賑やかな言動をするのは、そうすることで周囲に溶け込もうとするから。力加減が苦手で皆を振り回して時には傷つけてしまうことを、斑自身が誰よりも恐れている。皆の母を名乗るのに、仲間も拠り所も持たずに孤独なままで生きている。あんずから見た三毛縞斑はそんな人だった。
ふと耳慣れた音程が聞こえてきて、あんずは我に返った。付けたままにして置いたテレビから、アイドルの特集番組が流れてきていたのだ。幾人かのアイドルたちの名前が出た後に、斑とこはくの写真が画面いっぱいに映される。
あんずが曲を作り、あんずが衣装を用意して、けれど彼らが為していることを教えては貰えなかったユニット。映像は他の音楽番組のものを流用しているようで、どこか見覚えのあるものだったけれど。
「やっぱり、格好良いなあ」
こうして改めて彼らを見つめると、そのバランスの良さに惚れ惚れとする。何をやらせてもソツが無く大人びた雰囲気の斑と、確かな芸事の素養を感じさせながらも未だ少年らしさの残るこはく。もちろん彼らにはそれぞれのユニットがあるとはいえ、期間限定で終わらせてしまうには勿体ないと思える魅力がある。それに、彼らがふたりで活動した思い出が、血なまぐさい記憶だけで占められてしまうなんてあんまりだ。彼ら自身がなんて思おうと、どこまでだってアイドルなのに。
そのままテレビの電源を消して、そっと窓の方へと近づいていく。急激な寒波が訪れたこともあり今日は特に冷え込む日だったが、いつの間にか粉雪までもが降り出していた。積もってしまうこともなく、窓の外の手すりやガラスに触れて溶けてしまう雪をただ見つめる。
あんずは自分を、少し離れた場所にいる衛星だと捉えていた。アイドルという星に付随して存在する、どこか遠いサテライト。ひとりきりだと思っていたその近くに、力強いのに寂しい孤独な星が居たのだと知った。血玉髄を思わせる色合いは鮮やかで、触れたならその温度を知れるのに。もしも孤独な星と孤独な星が集まったなら、私達は何に成れるのだろう。
目を瞑って、何かに祈る。雪の下であの人が凍えることがありませんように。あたたかい絆の輪に加わっていますように。そうしてまたもう一度だけでも、あのいつかの冬の日のように。私に笑いかけてくれたならどれほど嬉しいのにと。少女を部屋に置き去りにして、冬の夜は深まっていった。
ひかりの未来
公園広場の大きなクリスマスツリーの下で、あんずはひとり立っていた。辺りを見渡せばデートに訪れた二人連れがそこら中にいるので、ひとりぼっちではないのだが。日にちはクリスマスの夕暮れ、場所はまごうこと無きデートスポットで。あんずはいずれ来る人と待ち合わせているのだ。
吐く息が白く視界に被さったあとに、まるで煙のように消えていく。手袋にマフラーは着けてきたれど、アウターはもう少し厚手でも良かったかも知れない。それでもせっかくのデートだ、あまり着ぶくれてしまって動きにくくても本末転倒だ。そんなことを考えていると後ろから急ぐような足音が聞こえる。振り返った先には待ち合わせをしたその人こと、斑が立っていた。
「お待たせあんずさん、冷えてないか」
「三毛縞さんこそお疲れさまです」
変装も兼ねて帽子と伊達眼鏡を着けているので少し印象は変わっているが。その下に覗く柔和な瞳の色は、いつもと同じ新緑の色をしていた。仕事帰りだけあって大きな鞄を肩に下げているのも、日ごろの身軽そうな印象とはどこか変わって新鮮だった。
そういう意味ではあんずのほうが、いつもと違った身なりをしている。なんせデートの予定があると知った周囲に、午前中には仕事を取り上げられていた。仕事ができないのは不服だが、お陰で自宅に一度帰りゆっくりと支度をする暇があったのだ。
いつもひとつに纏めるだけの髪も手間をかけて整え、頭を悩ませながらいつも通りのパンツスーツから華奢なワンピースに着替えた。リップだっていつもより良いものを付けてきたし、好きな匂いの香水をこの日のために購入していた。そんな手間暇に気が付いて欲しい気もするし、恥ずかしいから言及しないでほしい気持ちもある。けれど今目の前にいるのはそういったことにこそ目ざとい斑だ。
「今日はすごくおめかしさんだなあ」
「その……あの、デート……なので……」
「うん、とっても可愛いあんずさんを見せてくれて有難う」
蕩けてしまいそうな微笑みを向けられた後、流れるような手つきで手を繋がれた。お互い手袋越しだから体温は分からない。けれどもし素手で触れたなら、指先まで熱くなったあんずの温度が伝わってしまうだろう。だから今は布越しぐらいで丁度いい。目に見えて斑の機嫌が良くなったのがわかって、気恥ずかしさから顔すらまともに見つめられなかった。
今までふたりには様々な困難があって。本当にまあ、思い返すだけでため息をついてしまいそうなトラブルやら障壁を乗り越えて。今のあんずと斑は、臆面なく思いを交わす恋人同士であった。
何がどうしてこうなったのかと首を傾げる日が無いわけでは無い。プロデューサーの地位につきながらもアイドルと交際していることに、後ろめたい気持ちを抱いてしまう日はどうやってもある。現に今日だってクリスマスなどという格好のイベント日和に、アイドルである斑の時間を独り占めしてしまっているのだから。
「本当に良かったんですか」
「何がだあ?」
「クリスマスを私と過ごしたりして」
レストランの予約時間まで少しあるからと、ふたりは広い公園の中を散歩している。その最中にふと疑問が声に出た。手は繋いだままであるので、斑はあんずの歩幅に合わせてゆっくりと歩いている。だから斑の表情や息遣いまでもが非常によく見えた。あんずに問われた答えを、随分と時間をかけて考えているようだ。首を何度か傾げた後に、斑は優しく喋りはじめる。
「働いてなかったわけじゃないぞ、ついさっきまで現場だったし」
「ええ本当にお疲れさまでした、でも他にも予定とかあったんじゃって」
「うーん……まあ簡単な話なんだが」
俺がいちど、可愛い恋人のあんずさんとクリスマスを過ごしてみたかっただけなんだよなあ。一拍置いて呟かれた言葉に心臓が飛び出そうになった。あんずに聞かせるための言葉ではなく、本当に心の声が漏れ出たかのような言葉だったから余計に胸が高鳴る。くしゃりと目じりを歪ませて、わがままを言って甘える子供のような顔さえしていた。あんずは斑のこういう仕草に弱いのだ。きっといくらかは分かっててやっているんだろうから、とても性質が悪い。
「そういう顔は、ずるいと思います」
「だって本当のことだ、あんずさんはどう思ってる?」
「……三毛縞さんと今日会えたことは、嬉しいです」
「はは、俺もだ」
急に斑が立ち止まるので、手を繋がれたままのあんずはつんのめってしまいそうになる。それをすかさず斑の腕の中に抱きこまれた。顔のすぐ近くで斑の香りがするので、頭がくらくらする。思考すべてがもやに包まれて、正常な判断何てできなくなってしまいそうだ。
「あんずさん、この公園に昔来たことを覚えてるかあ」
「三毛縞さんがバイクに乗せてくれました」
「そうそう、あの時もツリーを見せてやりたくて」
抱きこまれたまま視線だけを横に逸らすと、今しがたあるいてきた広場が見えた。中央には立派なツリーが壮麗なイルミネーションを施されて飾られている。流石に細部は違っているのだろうが、昔にもふたりであの輝きをみつめたことがあった。ひかりの美しさだけは今も昔も変わらずに、何者をも平等に照らしている。
あんずもあの頃よりは斑のことが分かるようになってきたから、勝手に答え合わせができるけれど。多分あの日の斑は、本当はクリスマス当日にイルミネーションを見ようと誘いたかったのではないだろうか。けれどそれは出来なかったんだろう。誰かの特別になってみたいと願いながら、誰かの特別になることを恐れて離れていく人だから。
そんな人がスケジュールを綿密に調整して、デートがしたいだなんて誘えるようになったのだ。目を見張るほどの変化と成長だと思うし、あんずは心から愛されているんだと思う。不器用な人がそれでも伸ばした手を払いのけるほど、残酷には生きられない。
「あの、三毛縞さん」
「うん?」
「私、あなたが好きですよ」
だからせめて、この人が今度こそ何処にも行ってしまわないように言葉を贈ろうと思った。あなたをとても尊敬しています。アイドルとしてのあなたを応援したいと思います。自分一人で何もかも背負ってしまう所は好きじゃありません。けれど信じてほしいことには、あなたを偽りなく愛しています。
抱きしめたままの身体が、少し震えたのが分かった。泣いているどうかは確かめない。彼の心をすべて暴きたいわけじゃない、ただ隣にいる特別が欲しいだけだ。少し経ってから旋毛に口づけられた。そしてそのまま、抱いた腕の力を少し強められる。
あなたが孤独な星であっても、私は暗い夜空を彷徨ってあなたに会いに行く。私は衛星、輝く星にひきつけられて共に浮かぶもの。どんな星をも愛する、誰かにとっての女神。触れた場所からじくじくと溶けだすものが、愛と呼べるものであればいい。
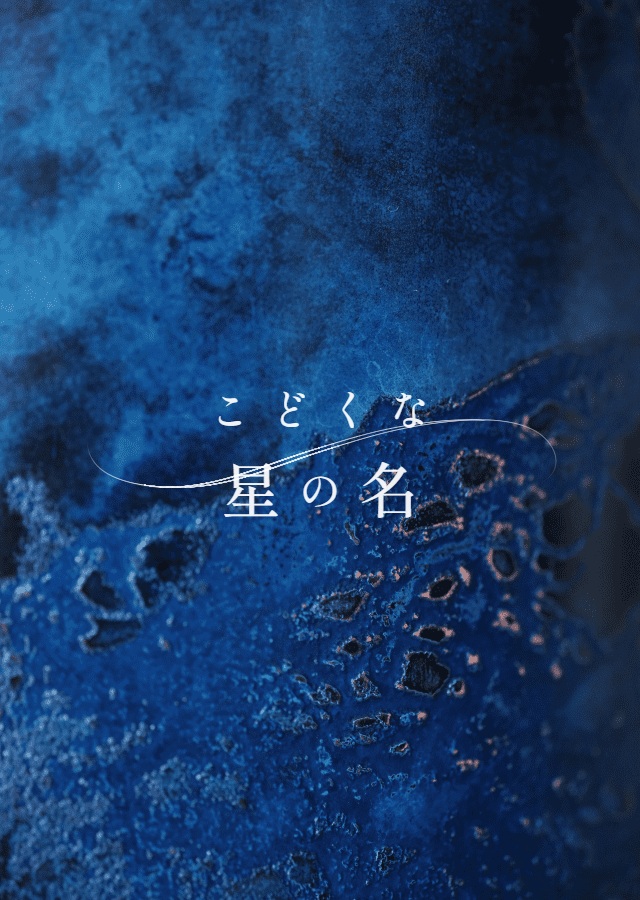
 みなも
Link
Message
Mute
みなも
Link
Message
Mute

 みなも
みなも みなも
みなも みなも
みなも みなも
みなも みなも
みなも みなも
みなも みなも
みなも みなも
みなも みなも
みなも みなも
みなも みなも
みなも みなも
みなも みなも
みなも みなも
みなも みなも
みなも みなも
みなも みなも
みなも みなも
みなも みなも
みなも