【VVV夢】かっこうの思い出 ~アードライを追う先~ カルルスタイン機関は傍目には一集落という様相をしていたけれどもきちんとした
居住コミュニティと呼ぶには大人の姿はほとんどなく、見かけられるのは子供の姿ばかりで果たしてどれだけ騙し仰せる事が出来たのだろう。
「アードライ様っ、待ってくださいっ!」
ツェーツェンがカルルスタインに移り住んでからというもの、来る日も来る日もアードライの背を追いかけてばかりだった。
通っていた初等部を辞めさせられてまで、彼の身辺に仕えるよう父に大役を命じられたのだ。ドルシアを守る偉い軍人である父に応えたくて夢中であった。
「君に待てと言われ、私が待つ筋合いなどどこにもないだろ!」
しつこく食い下がればアードライも足を止める。その少し先ではエルエルフが不思議そうに、けれども決して割って入る事もなく二人の様子を観察していた。
「ありますよ! こういうのは追われるうちが華なんですからっ、私が追いかけたら捕まってくれるくらいのサービスして下さいよっ」
「……何を言っているんだ
ツェーツェン」
そのアードライはと言うといつもいつも気がつけばエルエルフの姿を見つけては彼に駆け寄っているのだから、実に説得力に乏しい。見ようによっては
ツェーツェンはアードライと一緒になってエルエルフの後ろ姿を追いかけていたようにも見えているかもしれない。
「大体君は違うチームなのに、私と一緒に居ても仕方が無いだろう?」
しかし何も元王子様は意地悪で
ツェーツェンをかわしたいというわけではない。――端的に言えば、鬱陶しいだけであった。
「むしろ私が一緒に居て、アードライ様にどんな不都合があるとでもいうんですか?」
「不都合は有る!」
別に
ツェーツェンは元王子殿下と仲良し遊びをしたいというわけではない。ただ後ろから静かに、見守る事を許して欲しいだけ。たったそれだけの願いを否定されるのも納得いかないというのが彼女の弁であった。
「じゃあその理由次第では善処します」
納得いかぬから具体的な理由の提示をと
ツェーツェンが言い張ると、アードライは途端に狼狽える。右に左にと視線を彷徨わせた後、アードライは実に言いづらそうに胸中を吐露した。
「その……君に付いて来られたら……、エルエルフに恥ずかしいだろう……」
「……はぁ?」
「ぷっ!」
予想だにしていなかった答えに
ツェーツェンは普段の敬意交じりの言葉遣いも忘れる。そして遠くでは唐突に名を出されたエルエルフが噴き出していたのもまた、想定していなかった事態であった。
「ク……ハハハハハ! お前達は本当に仲が良いな」
「いきなり何がおかしいのエルエルフ!?」
「なっ、仲がいいわけではない! 誤解しないでくれエルエルフ!」
あの年に似合わぬ鉄面皮を持つ冷血漢のエルエルフが、まさか声を上げて身をよじりながら笑っているとか。アードライがますます顔を真っ赤に茹で上げるのも忘れ、
ツェーツェンはひどく可笑しそうなエルエルフの姿に目が釘付けになった。
「何なに~?
ツェーツェンってばあのエルエルフが大笑いするくらい、王子様でなぁにしたのさ?」
エルエルフの声につられ、クーフィアが後ろから
ツェーツェンに飛びついて来る。年はだいぶ違ったけれども、同期という事もあって彼は
ツェーツェンにだいぶ気易く接してきていた。
「何もされてなどいないっ!!」
「聞いてよクーフィアー。アードライ様ってばね、私が付いて歩くとエルエルフに恥ずかしいって――」
「だから喋るな
ツェーツェン!!」
アードライのヒステリックな声が何度も上がると、クーフィアは面白おかしそうに
ツェーツェンのチュニックの裾を引っ張って笑う。……もしかしたら彼は、こうなるのを予想してわざとあんな訊き方をしてきたのかもしれない。
「おっ。チーム違うのに今日も来てくれたんだ
ツェーツェン?」
「すごいな。まるで本物の王族の近衛兵みたいだ」
「ハーノイン! イクスアイン!」
年上の男の子達が来たところで、
ツェーツェンの頬がうっすらと桃色に染まる。
カルルスタインは年齢を減るにつれて過酷な訓練内容に訓練生の数を減らしていく。数少ない年上達である彼らの存在を、
ツェーツェンは憧れの異性としてはっきりと意識していた。いっそ、アードライもエルエルフではなく、彼らに懐いて歩き回ってくれればいいのに――なんて思うほどに。
「程々にしろよ~? 向こうの班に
ツェーツェンを取られた~って責められんの、俺達なんだから」
「大丈夫だよ、皆にはちゃんと言ってきてるから」
ハーノインはそう言うけれども、
ツェーツェンも別に自分の居るチームが嫌いなわけではない。
ツェーツェンは子供ながらに己の使命を全うしているに過ぎないのだ。
「いっその事
ツェーツェンも同じ班だったら、何があっても俺とハーノで守ってあげられるんだけどな」
「えっ本当?」
イクスアインの言葉に
ツェーツェンは不意打ちで胸が高鳴る。確かにエルエルフも居るこのチームと比べ、
ツェーツェンの所属するチームは訓練実績は芳しくないけれど。いわゆる“アードライの付き人”に過ぎない自分が、そこまで好意的に見られていたとは思ってもいなくて。実際はもう少し煙たがられているとでも思ったのだ。
「ヒュー! イクスが女の子に興味持ってんの初めて見たぜ!」
「ハーノ! そういう意味じゃなくてッ、俺とハーノがいれば
カルルスタイン機関でも安心ってだけで!」
「イクスってば耳まで真っ赤じゃーん!」
イクスアインにとってはとんだ失言だったのか、ハーノインやクーフィアが口々に囃し立てる。
幼馴染みの王子様が賑やかな居場所を見つけられた事には少しだけ安堵する。ここが過酷なこの世の果てである事実は嘆くべきであるが、それでも宮殿に居た頃よりずっと友人に囲まれていると思うのだ。
「君のせいだぞ
ツェーツェン! 君がそんな生半可な気持ちで
カルルスタインまで来るから――」
年上のイクスアインが散々なからかいのネタに使わているのを見て、アードライが憤慨したように
ツェーツェンを睨むものの。今更そんな小言くらい、痛くも痒くもない。
「そんな事言わないでください! アードライ様が居なければ、私がここに送られて来た意味がありませんしっ!」
「……やっぱり仲が良いんじゃないか。クククッ……」
「わっ、私は彼女にこんな危ない場所まで来いと言った覚えなどないからなエルエルフっ!?」
未だ笑うエルエルフに対し、アードライは必死で挽回の弁解を捲し立てる。
人が人の輪を呼ぶというのは、こういう事を言うのだろう。極力他人を退けていたエルエルフと親しくなろうとしていたアードライであったが、彼の冷血漢は案外――人の輪の中心に居る幼少期を過ごしたように思えるのだ。
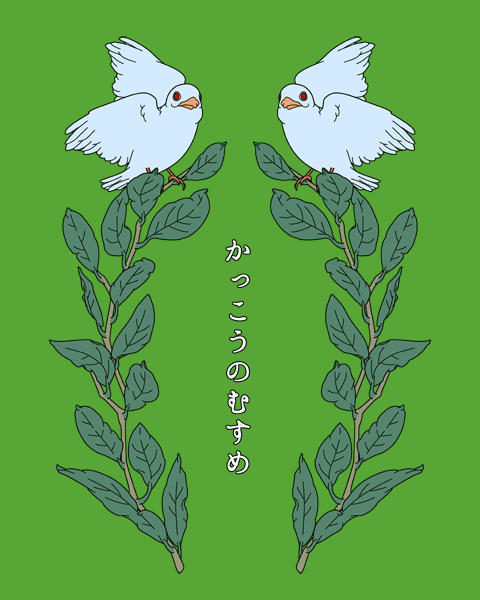
 OH
Link
Message
Mute
OH
Link
Message
Mute
 ステキと思ったらハートを送ろう!ログイン不要です。ログインするとハートをカスタマイズできます。
ステキと思ったらハートを送ろう!ログイン不要です。ログインするとハートをカスタマイズできます。

 OH
OH OH
OH OH
OH OH
OH OH
OH OH
OH OH
OH OH
OH OH
OH OH
OH OH
OH OH
OH OH
OH OH
OH OH
OH OH
OH OH
OH OH
OH OH
OH OH
OH