ARCANASPHERE2 ジリリリリ。目覚ましが鳴り響く。毎朝の洗礼で、騒音とも呼べるその音を浴びるアキは、手探りでベル音を止めようとするがなかなか見つからない。
(確かこの辺りに……)
おかしいと思いながらさらに手をのばすと、ふいにその手を掴まれて硬い目覚ましの上に叩きつけられた。
「痛った!」
アキは悲鳴をあげて文字通り飛び起きる。そこには不機嫌そうなハルヒの姿があった。
「朝っぱらからいつまでもリンリンリンリンうるせえんだよ」
「ご、ごめん……」
アキに背を向けてハルヒはリビングへ戻っていく。アキもその後を追って寝室を出た。
リビングにはすでにカゲトラの姿もあり、彼はアキにやっと起きたかと言ってから、朝のニュースへ視線を戻した。ハルヒはじっと窓の外を見ている。
F地区での事件のあと、アキがハルヒとカゲトラを自宅へ匿って2日が経過していた。日にち薬とはよく言ったもので、ハルヒは苛立っているものの、叔母を殺されたショック状態からはなんとか立ち直ろうとしていた。
「怪我はどう?」
だいぶいいとカゲトラは答えたが、かなり酷くやられていたため、完全回復はまだ程遠そうだった。
「シャワーしてくる」
アキは伸びながらバスルームへと入っていった。すると、ハルヒはソファーに座って、カゲトラと一緒にテレビを見始める。
ナツキのことはあの日以来何も情報がない。B地区にある軍事施設のどこかで捕まっているのはわかっていても、いまは助け出す方法がない。なにより、カゲトラの怪我が治るまでは動きようがなかった。
(ナツキ……)
ナツキはハルヒとカゲトラをあぶり出す餌だ。だからその目的を遂げない限り殺されることはない。それがわかっていても、頭で考えるよりも身体が先に動くハルヒは苛立っていた。
バスルームの扉が開き、半裸のアキが姿を見せた。シャワーのたびに服を着ずに戻ってくるアキに、カゲトラはなんとも言えない顔をしてハルヒをチラリと見るが、彼女のほうは特に気にしている様子もなかった。
アキは玄関に突っ込まれていた新聞を手に取り、それをテーブルの上に置くと次にキッチンへ向かって水道水をコップに注いだ。
「俺ももらっていいか」
「もちろん」
アキはもうひとつコップを取り、そこに水を注ぐ。その間カゲトラはアキの身体をジッと見つめた。
「ねえ、なんで熱視線?もしそうなら申し訳ないんだけど、僕は女性が好き」
アキは苦笑してカゲトラに水を差し出した。それを受け取り、カゲトラは自分も男は対象外だと返した。
「その傷痕は?」
それはカゲトラが昨日から気になっていたことだった。カゲトラが指差すアキの胸にハルヒも目をやる。ちょうど心臓の上あたり、アキの胸には大きな傷痕が残っていた。
「ただの手術痕だよ」
アキはそう言うと寝室に戻り、すぐにシャツを着てネクタイを締めながら出てくる。そして、仕事に行ってくると部屋を出ていった。
「……不用心な男だな」
やれやれとカゲトラは息を吐く。それとも、中流階級の生活に余裕のある人間というのは、知り合ったばかりの他人を、しかもテロリストを家に匿うことすら許容の範囲内なのか。いまここから放り出されたらそれこそどうにもならないが、アキが何を考えているのかカゲトラは理解できなかった。
「ハルヒ。飯を食え」
「要らねえ」
「ナツキも食ってる」
「………」
「きっと無事でいる。ナツキを助けるのには体力が必要だ。しっかり食え」
「……わかったよ」
ハルヒは嫌々ながらもテーブルの上にあるパンを掴むと、それを豪快に噛みちぎった。
□◼︎□◼︎□◼︎
レーベル社とプレートに書かれた扉を開けると、すでに自分以外の社員は全員席についていた。アキは朝の挨拶をしながら自分のデスクへと座った。
「おはよう。クサナギくん」
「おはようございます。ミナシロさん」
アキの隣に座るのはレイシャ・ミナシロという。たった1年の差ではあるが、アキの先輩社員でもあった。彼女は今年の新作リップを塗った唇を微笑ませて、ちょいちょいとアキを呼んだ。この小さなオフィスで内緒話は絶対に無理なのに、彼女はよくアキの耳元に話しかけたがる。
「社長、まだ怒ってるわよ」
そう言われたアキは、胸の前で腕を組んだハインリヒに視線をやる。彼のデスクには大量の吸い殻を乗せた灰皿と、何本もの空になったコーヒー缶が並んでいる。
「取材できなかったんだから仕方ないわよね」
「ははは」
裁判所での取材には行ったが、途中で腹が痛くなって取材できなかったと、アキはハインリヒには報告していた。さすがに【トライデント】の逃亡を手助けして、彼らを匿っているなんて職場では言えなかった。
ハインリヒの機嫌が悪いのは、他の者が裁判所での騒動を軒並み記事にしているのに、自分のところだけが写真の一枚も掲載できなかったからだ。
「社長。ごめんなさいってば」
また新しいタバコを口に咥えたハインリヒは、はぁぁっとため息をついた。
「でもテロリストを取り逃がした軍の失態なんてうちでは記事にできないじゃないですか」
レーベル社では軍の権威を貶めるような記事は書けない。アキの体調が万全だったとしても、裁判所でのことは記事にはできない。それはハインリヒもわかっていた。
「わかってるけどよぉ。リュケイオン大佐もいたんなら写真の1枚くらいさぁ。あいつの記事載せたらばかみてぇに売れるんだからよぉ」
ハインリヒのデスクの上には他社の雑誌や新聞が置かれていて、そのどれにも【テロリスト逃亡】【トライデントの報復】など様々なタイトルがつけられた記事が掲載されていた。
カゲトラはもちろん、ハルヒも写真に撮られているが、あのときの彼女は変装させたようなものだから、同じ服装をさせない限り、あれがハルヒだとはなかなか気づきにくい。
「テロリストの少女ねぇ……」
現に、掲載されているハルヒの写真を見てもハインリヒは気づかないようだ。一度会ったくらいでは他人の顔の認識度なんてこんなものだ。だが、元々の知り合いのカゲトラやレイジは、どんな格好をしていてもハルヒだと見抜いた。
軍の動きはアキの予想よりも慎重だ。ハルヒの実名を出して公表したり、手配書を配って賞金をかけたりするかと思ったが、いまのところそれはない。そんなことをしなくても、弟でハルヒが釣れると思っているのかもしれない。
もっともその予想は遠からず現実になるだろう。そろそろ何かナツキを奪還する方法を提示しなければ、ハルヒは痺れを切らして何かをしでかすだろう。
「ねえ、クサナギくん」
そんなことを考えていると、レイシャに話しかけられる。
「今夜、みんなで飲みに行かないかって話してるんだけど、あなたも来るでしょ?」
「ああ―――、いえ、やめときます」
「ええー、どうしてぇ」
レイシャは甘えた声で聞き返した。レイシャにとって、アキが来ないのなら同僚との飲みに意味はなかった。
「早く帰らなきゃならないんで。えっと、そう。犬を飼い出して」
「犬がいるの?」
苦し紛れの言い訳を間違えたことにアキはすぐ気づいた。レイシャの目は明らかに輝いている。
「私、犬は大好きなの。見に行ってもいい?」
「見に……、来る?」
カゲトラとハルヒ。あのふたりを犬に例えるなら、とんでもない大型犬と躾のなってない狂犬だ。とてもレイシャに見せられるようなものでも、もちろん犬でもない。
「ミナシロさん。仕事をしてください」
こうなったら本物の犬を用意するしかないのか。アキがそう思い始めた頃、レイシャの前に座っている男性社員がレイシャを注意した。
斜めにピシリと前髪を分けたその社員はイスズ・バレシアと言って、アキの後輩だった。レイシャがアキと話しているといつも口を挟んでくることから、レイシャのことが好きなのだろうとアキは予想していた。そう言ったことに対してアキは鈍いほうじゃない。レイシャが自分に好意を抱いていることも知っていたが、アキは彼女とどうこうなる気がなかった。
「アキ」
ハインリヒがアキを呼んだ。
「おまえ今日の夜、取材行けるか?」
「行けます」
即答したアキに、犬はどうしたとレイシャの視線が痛いほど突き刺さるが、仕事は優先だ。
「じゃあ、ビルの完成記念パーティーを取材しに行ってくれ」
「私も行きますっ」
レイシャが立ち上がる。
「ひとりで十分ですよ」
すかさずイスズが口を挟んでくるが、ハインリヒはレイシャにOKを出す。今度はイスズが立ち上がった。
「じ、自分も行きますっ」
「ふたりでいいわよ」
レイシャがバッサリと切ると、ふたりでいいとハインリヒにトドメを刺され、イスズは沈み込むように机に突っ伏した。
「パーティーには軍のお偉方なんかが集まるからな。ほら、前に女性関係でスキャンダルを起こしたあの議員、なんて言ったっけ?」
「ああ、レムナンデス議員ね」
不倫疑惑で一時騒がれたが、その後すぐに別の大事件が起きてあやふやなまま沈静化した。テロリストの事件に比べれば取るに足らないワイドショーネタでしかない。
「あのじいさんも来てるだろうから、拾えそうなネタあったら片っ端から拾って来い」
アキがハインリヒに了解だと敬礼すると、レイシャが後ろから腕を絡めてくる。
「よろしくね。クサナギくん」
「こちらこそ」
アキはにこやかな笑顔でレイシャを振り返り、その手をやんわりと払いのけた。
□◼︎□◼︎□◼︎
その頃、ハルヒはC地区を歩いていた。
先日初めて行ったB地区は街並みも建物も見たことがないような世界だったが、この中流階級の街並みもハルヒにとってはそうだった。
外を出歩くことをカゲトラは止めたが、じっとしていられないハルヒは、気をつけるからと言い切って外へ飛び出した。
あれからハルヒはアキに着せられたワンピースではなく、いつもの自分の服を着ていた。着古されてくたびれたハルヒの服装を見て、すれ違う人々はクスクスと笑ったが、ハルヒは気にもならなかった。
下を向いて歩いていたハルヒが顔を上げると、いつの間にか通りの向こうには軍施設が見えていた。たとえ普通の建物に見えても、軍施設の前には警備の兵士が立っているからすぐにそうだとわかる。建設されたばかりなのか、入り口は風船や花で飾られ、掲げられた大きなプレートにはブロッケンタワーと書かれていたが、ハルヒには読むことができなかった。
(ナツキ……)
あの兵士にナイフを突きつけてナツキの居場所を吐かせたい。だが、ハルヒは自分にそんなことはできないことを思い知った。【トライデント】で威勢のいい男たちに囲まれているときは、自分はなんでもできると思っていた。強くなったと勘違いしていた。
ハルヒはパン!と自分の頬を叩いた。それには自分に喝を入れる意味があったが、実際には心が晴れることはなく、頬がヒリヒリと痛んだだけだった。
そろそろカゲトラが心配して、彼まで外に出てきたらさすがにまずい。ハルヒと違い、カゲトラの顔はそこら中に知れ渡っているし、あんな大男はそういない。
(……戻るか)
F地区と違って、C地区は交通量も多い。舗装された道路を走るのはラクダ車ではなく、エンジンが積まれた車が大半だった。車が途切れるのを待っていたハルヒの前を、最後に黒い車が通り過ぎた。ハルヒはその車内にレイジの横顔を見つける。
「!」
息を飲んだハルヒは自分の前を通り過ぎた車に顔を向ける。車内でレイジが横を向き、隣に座る人物に何か話しかけているのが見えた。ハルヒに見えたのは後部座席から少し見えた栗色の髪だけだったが、それだけで十分だった。
「―――ナツキッ!」
ハルヒは車の後を追って走り出した。
ナツキを乗せた車は軍施設の地下駐車場へと入っていく。車を通した警備の兵士は、あとから走ってきたハルヒに気づいてその前に立ち塞がった。
「止まれ!ここはおまえのような小汚いガキの来る所じゃないんだ!」
「うるせえ!どけッ!」
ナツキがここにいる。そう信じて疑わないハルヒは、警備兵に噛み付きかねない勢いで怒鳴り散らし、警備を突破しようと暴れる。
「なんなんだこいつ……!おい!応援を、……いや待て、こいつ、どこかで……」
ハルヒの顔を訝しげに見つめる警備兵の目が見開いていく。
「おまえ――――」
(まずい……!)
警備兵を思い切り突き飛ばし、ハルヒはその場から逃げ出した。待てと叫ぶ警備兵の声はどんどん遠くなっていく。
(クソ……!クソクソッ!)
ナツキがあの施設の中にいるのに、それがわかっているのに、自分は逃げなくてはならない。行動の矛盾がハルヒの胸を締め付け、じわっと悔し涙が溢れてくる。腕で涙を拭うと、ハルヒは目立つ大通りから路地裏へ駆け込んだが、その先は行き止まりだった。
F地区ならばほとんどの道を知っていても、ここはC地区だ。完全に袋小路に追い詰められた。
「こっちだ!」
警備兵が路地裏に入り、迫ってくる。捕まるわけにはいかないハルヒは辺りを見回し、そこに置かれていたゴミ箱の上によじ登り、フェンスの上を飛び越えた。
「追いかけろ!」
「でもこの屋敷って……!」
そんな会話を交わしながらバタバタと引き返していく警備兵たちの足音を聞きながら、飛び越えたフェンスの先にあった木の幹の後ろで、ハルヒはホッと胸を撫で下ろす。おそらくまだ諦めないだろうが、時間を稼ぐことはできた。
(ここ、どこだよ……)
ハルヒは木の陰から周囲を見回して、見たこともない景色に目を丸くした。見渡す限り一面に敷かれた緑はF地区でも、C地区でも、裁判所があったB地区でだって見たことがない。砂の国にはあり得ない景色だった。
「なんだこれ……」
綺麗に手入れされた瑞々しい芝生の上には大きな噴水やパラソル。その下には白いテーブルセットもある。芝生の向こうには大きな屋敷が建っていた。ふらっと歩き出したハルヒは、ゆっくりと噴水に近づき、透明な水に指で触れた。水温こそ生温かったが、それでも水には変わりなかった。
「……あの、」
「!?」
ハルヒはその声に驚いて振り返る。そこには、ティーセットを持った少女が立っていた。黄金色の髪を赤いリボンで飾った白い肌の少女は、ハルヒよりもわずかに幼く見えたが、それでもその美しさはスタフィルスでも類を見ないほどのものだった。
「どなた、ですか……?」
少女はハルヒにそう質問する。突然のことにどうすればいいかわからず、ハルヒはゴクリと息を呑んだ。
「お嬢様。どちらにいらっしゃいますか?」
建物のほうから、おそらく少女を呼ぶ声が聞こえた。声の質から老人だとわかる。
「ココレット様」
身を強張らせたハルヒに気付き、ココレットと呼ばれた少女はティーセットをテーブルの上に置いた。
「隠れてください」
ココレットに言われ、ハルヒは噴水の後ろに身を隠す。それを確かめてからココレットは自分を呼ぶ声に返事をした。すると、燕尾服を着た白髪頭の老人が姿を見せる。
「お嬢様。こちらでしたか」
「セバスチャンったら。さっきお茶にするって言ったじゃない。そんなに慌ててどうしたの?」
「それが、お屋敷にお戻り願えませんか。なにやら近くで騒ぎが起こったようでございます」
「騒ぎって?」
「よくは存じ上げませんが、例の【トライデント】かもしれません。敷地内は安全だとは思われますが、念のために」
「……わかったわ」
ココレットと呼ばれた少女は一度噴水を振り返ってから、彼女の世話係であるセバスチャンと言う老人と一緒に屋敷へと戻っていった。
(俺のこと、言わなかった……)
ココレットとセバスチャンがいなくなると、ハルヒは額から流れ落ちる汗を拭った。
(なんで……。いや、気まぐれだ)
恵まれた人間と言うのは、たまに気まぐれを起こす。F地区の住人に施しをする上流階級の人間はたまにいる。ココレットもその類だろうとハルヒは自分を納得させ、今度は木をよじ登ると路地裏に戻った。
そこから尾行されていないことをよくよく確認し、念には念を入れてかなりの回り道をしてハルヒはアキの自宅へ戻った。玄関を開けると、今夜の取材準備のために一度帰宅していたアキとバッタリ出くわす。
「まさか外に出るとは思わなかったな」
困った顔でそう言うアキを無視して、ハルヒはソファーに座っていたカゲトラの前までやってくる。
「ハルヒ?」
「見つかった」
「見つかったって……、軍にか?」
「違う!ナツキだ!」
カゲトラはアキと視線を合わせた。
「どこにいる?」
「軍の施設に入っていくのを見た!助けに行こう!」
「それはどこにある施設だ?」
「入り口になんか書いてあったけど、ええと……」
ハルヒはあのときに見たプレートを思い出すが、文字の形は覚えていてもそれがどんな発音をする文字なのかはわからなかった。
「ハルヒ」
頭を抱えるハルヒに、アキはテーブルの上にあった雑誌を見せた。
「ここに書かれている文字の中から探せる?」
「……ああ。ええと……、最初はこれで、次が確かこの字で」
字は読めないが、ハルヒの記憶力は確かで、彼女は一文字も間違えることなく雑誌の中のアルファベットを指差していった。
「もしかして、ブロッケンビル?最近できたばかりの軍施設だ」
「入り口に花が置いてあった」
「間違いなさそうだね」
「トラ!すぐ行こう!」
「だめだよ」
カゲトラを説得しようとしたハルヒをアキが止めた。
「なんでてめえに指図されなきゃなんねえんだよ!」
「落ち着いて考えて。どうやって中に入るって言うの?」
「正面からでも裏口からでもどっからだって入ってやるよ!」
さすがに見かねたカゲトラが落ち着けと口を挟む。
「……だって、ナツキがッ」
「ハルヒ」
カゲトラの静かな声はやけに部屋に響き、そのあとには張りつめたような静寂が訪れた。頭を冷やせとカゲトラに言われ、ハルヒは握り締めた拳を震わせる。
「……偶然だけど、今夜そのビルでパーティーがあるんだ」
ビルの完成披露パーティーだよとアキは言って、ガラステーブルの上に招待状を置いた。ハルヒとカゲトラはそれに目をやる。
「僕は取材も兼ねて招待されてる」
「……俺も、」
「残念だけどハルヒは連れていけない」
アキはハルヒにキッパリと言い切った。
「ふ、服……、裁判所で着たあの服なら行けるだろ!すぐ着替えるから!」
「無理なんだ。会社の同僚と行くことになってるから」
今回は本当に連れていけないと繰り返し、アキはハルヒの肩に手を置いた。
「本当に弟だった?」
「……どう言う意味だ?」
「君を誘い出すための罠って可能性は?」
「あれはナツキだった!」
ハルヒはそう言い切った。
アキは考える。確かにハルヒが目撃したのはナツキだったのかもしれない。だが、知りたいのはそれが罠かどうかだ。いまのハルヒは冷静さを欠いていて、そこまで頭が回らないようだった。
「僕が見てくるよ」
「え……」
「どうにか探ってみるからハルヒはここで待ってて」
「………」
「お願いだよ。わかったって言って」
子供に言い聞かすようなアキに、ハルヒは小声でわかったと呟いた。それを聞いたアキは招待状を手に取る。
「ナツキのこと頼んだぞ」
「……善処するよ」
アキはカゲトラにそう返事をして部屋を出て行った。それからしばらくの沈黙の後、カゲトラが口を開く。
「ハルヒ」
「なんだよ」
「前に、クサナギとは軍施設前で会ったと言っていたな」
アキとどうやって知り合ったのか。裁判所から逃げ出し、少し落ち着くとカゲトラは当然とも言える疑問をハルヒに投げかけた。
「それがなんだよ」
「いや、なぜ奴が俺たちを手伝うのかと思ってな」
「……本気で弾除けになりたいんじゃねえの?」
「ハルヒ」
適当に答えたハルヒはカゲトラに睨まれ、面倒そうに口を尖らせる。
「あいつが俺に潔白を証明したいって言ったんだ」
「潔白とは?」
「軍の狗じゃねえってことだよ。あのときは、俺に協力しておまえを助けることでそれを証明するって」
「それならその証明はされたわけだな」
証明がされたからこそ、裁判所で有罪判決を受け、公開処刑されるところだったカゲトラはいまここにいて、まだその首と胴は繋がっている。
「だが、奴はまだ俺たちを匿っている。その理由はなんだと思う?」
「知らねえよ」
いまはナツキのことだけが気になるハルヒは、カゲトラとアキの話なんかしたくなかった。
「軍をヨイショしすぎてフラストレーションでも溜まってんじゃねえの」
「ヨイショ?」
「ああ……、なんか仕事で軍の記事を書いてるらしいぜ」
俺は読めねえけどなと、読み書きを覚える気のないハルヒはそう言った。カゲトラは手近にあった古い雑誌を手に取る。パラパラと適当にページをめくったカゲトラは、そこにアキ・クサナギの名前がある記事を見つけた。
そこで軍の栄光を讃える、【トライデント】側から見れば胸糞の悪い嘘ばかりの記事を読み終えたカゲトラは、雑誌の裏にある社名を見て息をつく。そして、読むのではなかったと後悔もした。
みんな生きるために必死だ。生きるためには本意でない仕事でもしなくてはならない。カゲトラだってそうして生き延びた経験があった。果たして、どの顔がアキの本当の顔なのか。ますますアキという人間が奇妙に思えてくる。そして、あのときタイミングよく閉じた法廷の扉も。
「トラ?」
黙り込んだカゲトラに気づいたハルヒが彼を呼んだ。
「ハルヒ。ナツキを助けに行くか?」
「……いきなりどうしたんだよ」
アキに任せろと言ったのはカゲトラだ。ハルヒは怪訝な顔をする。
「いまさら軍に売られることはないとは思うが、俺はどうにもあいつを信用しきれない」
レイジに裏切られたばかりで過敏になっているのかもしれない。そう言うカゲトラにハルヒは首を振った。ハルヒも同じ気持ちだったからだ。アキには何度も助けられはしたが、数日前に出会ったばかりの彼は仲間ではない。カゲトラがアキを疑うのなら、ハルヒが信じるのはカゲトラのほうだった。
「ナツキを助けたらどうする?」
のこのこF地区の家に帰れば捕まるのは目に見えている。
「C地区の【トライデント】に連絡を取るつもりだ」
【トライデント】は地区別に分けられていて、F地区が全滅したとしても、ほかの仲間が残っている。カゲトラの考えにハルヒも頷く。
「じゃあまずはナツキだな」
カゲトラと自分が【トライデント】だと知ればナツキは驚くだろう。ハルヒはもうナツキを助け出したあとのことを考えていた。そんなハルヒに、「俺の指示に従えよ」とカゲトラは念を押した。それが言うだけ無駄だとはわかっていても。
□◼︎□◼︎□◼︎
ブロッケンビル前にアキが到着すると、すでにそこで待っていたレイシャが手を振った。
バイクを停めてレイシャを見ると、昼間とは違った装いで、彼女はカクテルドレスに身を包んでいた。化粧も普段より夜会映えする色を使っていて、随分と気合が入っているように見えた。
ハルヒにも思ったことだが、着るものひとつ変えただけで、女性は別人のように化ける。まるで手品だなと思いながら、その言葉を口にしてもレイシャが喜ばないことはわかっていたので、アキは何も言わず笑顔で手を振り返した。
「3分遅刻」
「すいません、なかなかエンジンがかからなくて」
言い訳を口にしながらアキはバイクを駐車場に停め、レイシャが腕を組みやすいように左腕を浮かせる。アキがエスコートの姿勢を見せたことでレイシャの機嫌は簡単に直り、ふたりはブロッケンビルに向かって歩き出した。
自動扉をくぐり、受付を済ませるとエントランスを抜けてエレベーターに乗り、招待状にあった会場に入ると、すでに他の記者たちはお目当ての相手を捕まえていた。
「出遅れたって感じね」
「まあまあ、社長の目的はあの議員でしょ」
録画テープとメモを取り出したレイシャの耳に、あそこにいるとアキはレムナンデスの居場所を教えた。
記者たちから逃げるように、レムナンデスはコソコソとワインを飲んでいる。太った大柄な体にはちきれそうなスーツを着込み、寒いくらい冷房の効いた部屋でなにが暑いのか、ダラダラと髪の毛もない頭から大量の汗をかいていた。不倫騒動が災いしたか、いつも隣で陣取る妻の姿はない。強制ではないものの、そのほとんどが夫婦や恋人と出席するパーティーで、妻も不倫相手も従えていないレムナンデスは完全に浮いていた。そんなに居た堪れないなら、出席しなければいいと思うが、立場上そういう訳にもいかないのだろう。
「行くわよ」
「ミナシロさんひとりだけのほうがいいと思いますよ。あのひと、綺麗な女性にはペラペラじゃべってくれるから僕は邪魔になる」
「私がひとりであのハゲオヤジの取材するの?」
「僕は別の特ダネを探します」
「なんか押し付けられた感じだわ」
「頑張って」
レイシャの背中を押したアキは彼女にバイバイと手を振った。納得できないようだったレイシャだが、仕事と割り切ったのか振り返りはしなかった。
アキはやれやれとため息をつく。レイシャを追い払った理由は、彼女がいたのではナツキを探すことができないからだ。
(まあ、でもちょっとは仕事しておかないとまずいかな)
だれかいいカモはしないものか。獲物を見繕おうとしたアキは、小さな悲鳴に顔を向けた。そこには薄ピンク色のドレスにワインのシミをつけ、涙ぐむ美しい少女の姿があった。周囲にいた同年代らしい少女たちが、くすくすと笑いながら足早に去っていく。
上流階級の中でも差別意識は存在していて、陰湿ないじめは力の弱い者へ降り掛かる。泣き出すのだけは必死に堪えようとする少女の前にアキは進み出た。自分にかかった影に気づいた少女は顔を上げる。
「失礼します」
そう言って、アキは跪くと、少女のドレスについたワインの染みを、胸ポケットから取り出したハンカチで押さえた。
「け、結構ですっ」
「これはご無礼を致しました」
アキは頭を下げた。見た目はハルヒと同じ年頃の少女でも、記者と上流階級の人間しかいないこのパーティーに来ていると言うことは、彼女はアキより身分が上と言うことになる。おそらく、軍幹部の娘だろうと当たりをつける。妻と見るにはまだ幼すぎたからだ。
「そ、そうではなく……、あなたのハンカチが汚れてしまうので……」
少女から自信のなさそうな声が漏れた。いじめの標的にされるのも無理はないと思えるほど、その声は弱々しかった。
「記者の方ですか?」
「レーベル社のアキ・クサナギと申します」
「私は……ココレット・リュケイオンと申します」
アキはその名前にココレットの黄金の髪を二度見した。裁判所で、リュケイオンの名を持つ男には最近会っていたからだ。だが、じっくりと彼女を観察する前に、ココレットの表情は硬く強張った。
「……お兄様」
聞き取れるギリギリの声量でココレットがそう口にする。アキが振り返ると、そこにはココレットの兄であるルシウス・リュケイオンの姿があった。
ドクンッとアキの心臓が大きく鼓動する。あのときは一応サングラスをかけて変装していたが、バレないとは限らない。アキとルシウスとはつい先日、この距離で話をしていた。
「ココレット。おまえも来ていたのか」
「あ、はい……あの、」
ルシウスの登場で、ココレットはますます萎縮して肩を小さくした。ルシウスはココレットのドレスについた汚れを一瞥し、小さく舌打ちしてからアキに目を向けた。
「きみは?」
「初めまして、大佐。レーベル社のクサナギと申します」
アキはそう言って名刺を差し出した。ルシウスはそれを受け取ることはなく、アキの顔をじっと見ていた。
(やば……)
この沈黙は心臓に悪いが、少しでもおかしな行動をとれば怪しまれる。いや、すでに十分に怪しまれている。それも無理はなく、サングラス以外は髪型も、服装だって裁判所で会ったときと似たようなものだ。アキの背中を冷たい汗が流れ落ちた。
「前にどこかで会ったかな?」
「いいえ。ですが、閣下の記事を書かせていただいたことは何度か」
レーベル社がルシウスの特集を組んだことは過去何度もある。ただし、その記事を書いたのはルシウスファンのレイシャで、アキではなかった。
「そうか。取材はほどほどに、今夜はパーティーを楽しむといい」
バレなかった。アキが胸を撫で下ろしかけると、ルシウスはココレットに目をやった。
「みっともない。さっさと着替えろ」
「は、はい……」
ルシウスにそう言われたココレットは逃げるようにその場から立ち去った。
(あれがリュケイオン家の娘か……)
ルシウスは広くメディアに露出しているが、未成年であるココレットはその存在は知られていてもなかなかその姿を見た記者はいない。アキもその中のひとりだった。もしかすると、今夜のパーティーが初の社交界デビューなのかもしれない。だとしたら開始早々にドレスを汚され、可哀想なことだ。
軍の頂点に将軍として君臨するゴッドバウム・リュケイオンを父親に持つあの家の事情は複雑だ。ココレットはまだ15歳で、ルシウスとはかなり歳が離れている。レーベル社の方針から間違っても記事にはできないが、噂ではココレットはゴッドバウムが外で作った子供という噂もあった。
「パーティーを楽しんでくれ」
ルシウスはアキにそう言い残して会場へ戻っていった。心臓に悪い。そう思いながら、アキはその背中を見送った。
大佐殿からのせっかくのお言葉ではあるが、アキにパーティーを楽しんでいる時間はない。取材はレイシャに任せてナツキの居場所を探らなければならなかった。
このビルの構造や配置はだいたい頭に入れてきた。ナツキがいるとすれば、この上の階になるだろう。トイレに行くふりをしてそっと会場を出て、エレベーターか非常階段を探す。
ふと、なぜナツキを探しているのかアキは自分に問いかけた。それは彼がハルヒの弟だからだ。ではなぜハルヒに手を貸すのか。身の潔白ならカゲトラを救い出すことでもう証明したはずだ。
「どうしてかな……」
ぎゅっと胸が締め付けられるように痛んだ気がして、アキはシャツの上からそれをぐっと押さえた。
「だからそうじゃないって言ってるでしょ!」
廊下にヒステリックな声が響いたのはそのときだった。
顔をやると、ちょうど化粧室から出てきたばかりの年配の女性が、携帯電話を片手に通話相手に怒鳴りつけているところが見えた。肩までの髪を綺麗に巻いていて、膝丈のドレスから見える脚が忙しく動くたびにピンヒールがカツカツ音を鳴らす。招待客だろうが、彼女にはパーティーを楽しむ余裕がないようだ。
「あなたじゃ話にならないわッ!ドクター・タオはいないの!?彼に伝えなさい!」
怒り狂う女性ほど恐ろしいものはこの世にない。さっさとエレベーターへ向かおうとしたアキだったが、女性が口にした名前にピタリと足を止める。
「2200から2220までのナンバーズは廃棄よ!いいわね!伝えるのよ!」
女性はそこで一方的に通話を切って、怒り冷めやらぬまま顔を上げた。そして、自分を見ているアキに気づく。
「……なぜ私を見ているの?」
「す、すみません……」
「質問に答えなさい。なぜ見ていたかと聞いているの」
「それは……ただ……」
「ただ、なにかしら?」
女性は言いながらアキに近づき、彼が首から下げているネームプレートを手に取った。そこには社名とアキの氏名が書かれている。それは、パーティーに参加する記者が身に着けることを義務付けられた、身分証明だった。
「知人に似ていると思って……だけど、勘違いでした。本当にすいません。少し酔ったみたいで……」
アキはアルコール類を一滴も飲んでいない。それは咄嗟に口をついて出た、相手の懐に飛び込むための嘘だった。
「それは心配ね」
女性は赤いマニュキアを塗った手をアキの頬に手を伸ばす。指先から強い香水の匂いがした。自分に触れる生温かい体温に、アキは獲物が網にかかったことを確信する。
「上に部屋をとってあるんだけど、そこで休む?」
「―――お言葉に、甘えさせてください」
アキはそう言って、自分の頬にある女性の手にそっと触れた。
エレベーターに乗り込んだアキと女性は、最上階のひとつ下の階である49階までやってきた。扉が開くと見えたその部屋は、アキのアパートの3倍以上の広さがあった。スウィートルームだ。アキの手を引いてソファーに座らせると、女性はテーブルの上にあったワインをグラスへ注ぐ。
「まずは乾杯しましょうか」
アルコールの匂いがしないのだ。酔ったと言う嘘は見抜かれているらしい。だが、別段構わない。もう獲物はかかった。
アキは赤ワインが注がれたグラスを受け取り、今夜の素敵な出会いにと、女性とグラスを重ねて口に含んだ。ワインは上等なものには違いないはずなのに、まるで味はわからなかった。
「ドクター・チグサ・ワダツミ」
アキに名前を呼ばれ、女性───チグサはフッと笑った。
「さすが記者ね。私のことを知っていたのね」
「覚えてらっしゃらないでしょうが、以前お会いしたことが」
「あら。そうなの」
「でも、人間の記憶なんて曖昧ですね……。実物には勝てない」
アキはそう言いながらチグサの髪を指ですく。アキが以前にチグサを見たときは、彼女の頭には一本の白髪もなかった。だがいまの彼女には、隠そうとしても隠しきれていない老いが見えた。
一方、チグサはアキのその言動をポジティブに捉え、満足そうに口元を笑わせると、ワインをその身体に流し込んだ。
「……ねえ」
ワインで顔を紅潮させたチグサは、ソファーの前にあるテーブルを乗り越えると、アキのネクタイを手に取る。
「酔いは覚めたかしら?」
「いいえ。むしろ酔ってきた」
「ふふふ……」
チグサは手慣れた様子でアキのネクタイを外すと、首元からシャツのボタンを外していく。アキはされるがままそれを傍観していた。
「傷つくわね」
少しも動こうとしないアキの首に手をかけ、チグサはふざけて力を入れる。
「こんな年増じゃその気にならない?」
実際、アキとチグサは親子ほど年齢が離れていたが、チグサは自分の美貌に絶対の自信を持っていた。
「そんな。あなたはとても魅力的ですよ」
アキは苦笑すると、チグサの身体をソファーの上に押し倒した。チグサはアキの太ももの内側をさすり、さらなるリードを催促する。
「ドクター・ワダツグ……」
「その呼び方はやめて」
耳元で囁いたアキに、チグサは首を振る。
「チグサでいいわ」
これから情事に耽ろうというのに、ドクターなんて呼ばれたくはなかった。チグサは仕事とプライベートはきっちりと分けておきたいタイプだ。そのため、パーティー会場にまでかかってきた仕事の連絡に、しかも失態を知らせる連絡に激怒した。
「では、チグサ。僕のことはB−101と呼んでください」
「……なんですって?」
チグサはアキが何を言ったのかわからなかった。
意図を探るべくアキの顔を見つめるが、彼の表情は変わらない。B−101。アキが呼んでくれと行ったその番号を、チグサは頭の中で繰り返す。その番号には覚えがあった。連日、研究施設で似たような番号を扱っていたからだ。
「なにを言ってるの……?」
聞き返すが、アキは柔和な笑みを浮かべたままだ。さっきは好ましいと思ったその笑顔が怖くなり、チグサは自分の上にいるアキの胸を押しのけ、ソファーから後退した。
軍の研究機関のことは一部の人間しか知らない。その一部の人間も、表向きに発表している研究内容しか知らされておらず、アキの口にしたナンバーズの番号は、関係者しか知り得ない情報だ。だがアキは記者だ。秘密を嗅ぎつけられたのだとチグサは結論づけた。
「いくら欲しいの?」
記者という生き物をチグサはよく理解していた。彼らはカネのためならば手段を選ばない卑しい生き物だ。ちょっと見目がいいからと思って部屋に連れてきたのが間違いだった。
「おカネには困ってませんよ」
「強欲過ぎると足元をすくわれるわよ」
カネ以上のものを要求する気かとチグサは吐き捨て、チラリと部屋にある電話を見た。通報したほうがいいか。だが、アキが研究のことをどれほど知っているのかわからないまま大ごとにすれば、自分の立場が危うくなるかもしれない。チグサはいまの立場を失うわけにはいかなかった。
チグサがあれこれと考えを巡らせる中、アキは脱がされかけたシャツを開いた。胸元が露わになり、そこにある大きな傷痕を目視したチグサは、ヒュッと息を呑んだ。見る見るうちにその顔は血の気を失っていく。
「その顔は僕がだれか思い出した顔?」
「嘘よ……」
チグサの身体はカタカタと震え出していた。
「報告では……ゴザで死んだと……!」
「じゃあ、さしずめ僕は亡霊かな」
チグサは柔らかな絨毯の上に座り込む。いつの間にかその呼吸は小刻みに弾んでいた。それを見下ろすアキは、自分が意外と冷静であることを不思議に思っていた。
ああ、あの頃、絶対的な力で君臨していたこの女はこんなに小さく、弱く、老いぼれていただろうか。あれから何年経ったのか―――、チグサは年老いて、アキは大人の男へと成長した。
立場は完全に逆転した。電話で助けを求めるどころか、声も上げることができないチグサの命は、いまやアキの手の中にあった。
「ねえ、B−101って呼んでよ。昔みたいに」
「ちが、違う!私はただ命令に従って……!」
突如、チグサの髪を噴き上げた風が、固く閉じていたバルコニーへの扉を開け放ち、カーテンをはためかせる。顎を滑り落ちたものがチグサの胸元へ落ちた。ドレス生地に染み込む血に、チグサは切り裂かれた自分の頬に触れて悲鳴を上げた。
「あなたに聞きたいことがあるんだ」
「た、助けて……!助けて!殺さないで!」
「それは質問に答えてくれるなら考えるよ」
バルコニーから入ってきた風にアキの黒髪がそよぐ。
「彼はどこ?」
「か……彼?」
「ドクター・ステファンブルグはどこにいるの?」
アキの口から出た名前に、チグサは首を振る。ゴクリとその喉が鳴った。
「し、知らない……」
「そんなはずないよ」
「本当よ!彼とはずっと会ってないの!」
「あなたは彼と仲が良かったじゃないか。居所くらいわかるでしょ」
「本当に知らないのよ!」
叫んだチグサの肩が切り裂かれ、そこから血が噴き出した。痛みと恐怖に絶叫するチグサの前にしゃがみ、アキは彼女の顔を覗き込んだ。
「ほ、本当に……知らないの……!殺さないで……っ」
致命傷ではないがチグサは血まみれで、床には点々と彼女の血が飛び散っている。
「お願い、殺さないで……!」
「ねえ、どうしてそんなに怖がるの?あなたたちが僕に与えた力じゃないか」
震えて泣くばかりでチグサは何も言えない。下手なことを言えば次は首が飛ぶかもしれない。恐ろしくて声など出なかった。
そのとき、コンコンとノックの音がして、アキとチグサは同時にそこへ顔を向ける。
「ドクター・ワダツグ。大きな音が聞こえたのですが、何か問題がありましたか?」
暴れすぎたか、どうやら警備兵が部屋の様子を見にきたらしい。
「残念。時間切れだ」
アキはシャツのボタンをかけ直し、開け放たれた49階のバルコニーから躊躇うことなく飛び降りた。
□◼︎□◼︎□◼︎
パーティー会場を後にしたココレットは、トボトボとした足取りで控え室に向かって歩いていた。
パーティーに出席するためにセバスチャンが準備してくれたドレスは酷い有様だ。彼がこれを見たらきっと悲しい顔をするだろう。それを思うとココレットも悲しかった。
家族には父と兄がいるが、彼らはそれぞれ違う家を持っていて、ゴットバウムとルシウスは仕事柄会うこともあるが、ココレットがふたりと顔を合わせることはほぼなかった。
こんなパーティーのときにだけ会う歳の離れた兄は、ココレットが物心ついたときには冷たい態度を取り、父とは何年も会ってすらいない。ココレットにとってはセバスチャンと、彼の娘だけが本当の家族のようなものだった。
一応換えのドレスは用意してあるが、もうパーティー会場には戻りたくない。終わるまで控え室で待っていよう。そう思って、ココレットは控え室の扉を開けた。
「わっ」
それに驚いたのは扉を開けたココレットではなく、なぜか控え室にいた少年だった。
「……だれ?」
部屋を間違えたのかとココレットは控え室の中を確かめるが、確かに自分の荷物が置いてある。
「あ、あのっ、勝手に入ってごめんなさいっ」
少年はココレットに対して謝罪する。
「一度部屋を出たら、自分の部屋がわからなくなっちゃってっ、すごくいっぱい部屋があるからっ」
まくし立てるように弁解をしだした少年に、ココレットはただただ目を丸くするばかりだ。
「ごめんなさい……」
肩を落とす栗色の巻き毛の少年はパーティーでは見かけなかった顔だった。パーティーで気疲れしていたココレットは、少年の素朴な雰囲気に癒されてホッと息を吐いた。
「いいのよ。迷ったんでしょう?あなたを咎めたりなんかしないわ」
「……あ、ありがとう」
少年もほっとしたのか笑顔を見せる。
「ぼ、僕、ナツキ・シノノメ」
「ココレット・リュケイオンよ」
「えーと……」
ナツキの視線にココレットは自分のドレスが汚れていることを思い出す。見苦しかっただろうかと情けない気持ちになったココレットに、「綺麗だね」とナツキは言った。
「え?」
「お姫様みたいだ。すごくきみに似合ってるし、きみみたいに可愛い子、初めて見たよ」
ココレットはナツキの言う通り可愛らしい容姿をしている。だが、セバスチャンと彼の娘以外からそんなことを言われたのは、ココレットだって初めてのことだった。
それに、ナツキはリュケイオンの名を聞いても態度を豹変させたりはしなかった。それはただナツキがリュケイオンの名前を知らなかっただけに過ぎないが、ココレットにとってはどちらでも同じだった。
「えっ」
ココレットの目に浮かんだ涙に気づき、ナツキは驚いた声を上げる。ナツキには、ココレットがなぜいきなり泣き出したのか見当もつかなかった。
「どうしたの?どこか痛いの?」
「ううん。違うの……」
どこも痛くはないが、涙が止まらない。小さな肩を震わせるココレットを見ていると、彼女の感情に同調してしまったナツキの目にも涙が滲んだ。
「どうしてあなたも泣くの……?」
「だって、きみが泣くから……悲しくて」
「そんなのおかしいわ」
「そうかな?姉ちゃんは、僕が苦しいとき、自分も苦しそうだよ」
「あなたも、あなたのお姉様も、とても優しいのね」
ココレットはそう言って涙を拭った。
「あなたのこと、ナツキって呼んでもいい?」
「うん。僕もココレットって呼びたい」
短時間で心を許し会ったふたりは呼び名を確認し合う。少し話をしないかと、ココレットはナツキにソファーを勧めた。
「あなたもパーティーに招待されたの?」
ナツキの隣に腰掛けたココレットはそう聞いた。
「ううん。レイジさんはパーティーへ行ったけど、僕はお留守番だよ」
「レイジさん?」
「レイジさんはね、僕のお父さんの友達なんだ」
話を聞きながら、ココレットはコロコロと変わるナツキの表情に釘付けになる。ナツキはこれまでココレットのそばにはいなかったタイプの人間だった。
「お姉様も一緒に来てるの?」
「姉ちゃんはね、いまレイジさんが探してくれてるんだ」
ちょっと色々あってと、ナツキはそこで初めて言葉を濁した。ウララの一件は忘れるにはまだ日が浅く、だれかに話せるまでにナツキは気持ちを整理できていなかった。
「ココレットにはきょうだいはいる?」
「……私にはお兄様がいるの」
いまはパーティーに出席してると、ココレットは言った。
「ナツキはお姉様のことが好き?」
「もちろん好きだよ」
ナツキは即答する。迷いなど微塵も見せなかった。
「ココレットは?」
「私は……よくわからない。……私とお兄様は、お母様が違うの。だから私とお兄様は、半分しか血が繋がってないの」
ナツキはココレットの話を黙って聞いている。
「私はお兄様に嫌われているの……」
ルシウスの母親は、ココレットが生まれた日に自殺した。ココレットがその話を聞いたのは、10回目のバースデーの日だった。【売春婦の娘へ】と書かれたバースデーカードに書かれていたメッセージは、セバスチャンがココレットに見せることを拒んだほどの酷い内容だった。そのバースデーカードを送ってきたのは、当時ルシウスとの関係が噂されていた女性だったが、実際はルシウスから送られてきたようなものだった。
「……ココレット」
「お話してくれてありがとう。そろそろ部屋まで送るわ」
「えっ」
「レイジさんがあなたのこと探してるかも知れないでしょ」
「うん……」
ココレットに押し切られるようにナツキは頷いた。
警備室に連絡を取ってレイジの部屋を確認すると、ココレットはナツキをそこまで送っていった。
「もう迷子にならないでね」
ココレットはそう言ってナツキに手を差し出した。ナツキも握手で別れようとするココレットの手を握った。
「また会いたいな。ココレット」
「私もよ。ナツキ」
また今度会ったらゆっくり話すことを約束し、ふたりは別れた。ナツキはココレットが見えなくなるまで手を振り、部屋の扉を閉めてそこに背中を預けた。その数秒後、ブロッケンビルに忍び込んだハルヒがその前を通り過ぎたのも知らずに。
ナツキを部屋まで送り届けたココレットは、自分の控え室に戻る通路を歩いていた。もうパーティー会場には戻りたくはないが、自分の控え室に行くには会場前を通らなくてはいけない。
パーティー会場の前は広いフロアになっていて、天井まである大きな窓から街の夜景を見ることができた。足を止めたココレットが夜景を見ていると、パーティー会場からルシウスとレイジが出てくるのが見えた。ココレットはレイジを知らなかったが、兄の姿にびくりと肩を震わせる。
その背後から、同じものを見つけたハルヒがココレットの腕を掴んだ。一瞬ではあったが間近で視線を合わせたふたりは、お互いにあのとき屋敷で会った人物だと気づくが、ハルヒはあとには退けなかった。
「レイジッ!」
張り上げたハルヒの声に、話をしていたレイジとルシウスが顔を上げた。ココレットの腕を捻り上げたハルヒは彼女の喉元にナイフを突き付ける。ココレットの悲鳴は声にはならなかった。
「弟はどこだッ!?」
恐怖に怯えた妹の姿を目にしても、ルシウスは冷静にハルヒの様子を見ていた。服装がまるで違って別人のようだが、ハルヒが裁判所で見た少女だと確信したルシウスは、銃を抜こうとしたレイジを止める。
「……きみのような女の子が【トライデント】だなんて、まだ信じられないな」
ルシウスが一歩踏み出す。ハルヒたちの背後で窓ガラスがガタガタと風に揺れた。
「妹は軍人ではない。解放してくれないか」
「妹……?」
ハルヒは蒼白になっているココレットの顔を横目で見て、首を振った。
「おまえの妹なら好都合だ」
「落ちついて話し合おうじゃないか」
「ナツキを返せ!」
ハルヒが口にしたナツキの名にココレットが肩を震わせる。何がどうなっているのかココレットには理解できなかった。
「やれやれ。こっちだよ」
ルシウスはレイジに耳打ちすると、パーティー会場への扉を開いた。赤絨毯が敷き詰められた会場に残っている人間はまばらだが、すぐに異変を感じ取った鼻の効く記者がハルヒにカメラを向ける。
「どうした。来ないのか?」
明らかな罠だ。ハルヒは会場内にナツキの姿を探すが、記者たちが邪魔でよく見えない。
ブロッケンビルに侵入するにあたり、カゲトラとは二手に分かれた。絶対に無茶はするなと釘を刺されたが、レイジを前にしてハルヒに冷静になれと言うのが無理な話だった。
ハルヒが一歩踏み出すと、記者たちはカメラのシャッターを切る。無数の光にハルヒの目が眩む。記者たちの背後から兵士が銃を構えた。当てるなと、ルシウスは抑揚のない声でそう言った。
数発の弾丸が発射され、ハルヒたちの背後の窓ガラスが砕け散る。高層階に吹き付ける強風が、ハルヒとココレットの髪を巻き上げた。一歩間違えば、ココレットに当たっていたかもしれないことは、だれの目にも明らかだった。
「投降しなければ次は当てる。妹を解放しろ」
妹まで撃ち殺しかねない命令を下しておいて、白々しい態度のルシウスは手を持ち上げた。その手のひらが開くときが発砲の合図だ。
完全に人質を間違えた。妹と言いながら、ルシウスがココレットを助けるつもりがないことにハルヒは気づくが、いまさら遅い。こうなればココレットはもう荷物でしかなかった。
「……わかった。解放する」
ココレットには一度見逃してもらった借りがある。ハルヒは震えるココレットから手を離した。ココレットは大きな瞳を見開いてハルヒを振り返る。
「あ、あの、ナツキって……」
「……ッ、おまえナツキのこと、」
ナツキの居場所を知っているのかと、ハルヒが言いかけたとき、ルシウスがその手を開いた。
「ハルヒッ!」
それはアキの声だった。その声に反応し、ハルヒはココレットの頭を抱え込むように身を伏せる。銃声が響き、会場内からも悲鳴が上がる。
そこへ駆け付けたアキはハルヒの腕を掴むとココレットから引き離し、その身体を胸に抱いて割れた窓から身を投げ出した。
「クサナギくんッ!」
一部始終を見ていたレイシャが叫ぶ。会場に集まった大勢が目撃する中、ふたりはあっと言う間に闇の中に吸い込まれていった。
「嘘……、嘘、嘘でしょ……!?」
頭を抱えて取り乱すレイシャに、周囲の記者たちが顔を向ける。
「さっきの男ってレーベル社の……」
「レーベル社は【トライデント】と関わりがあったのか?」
「これはスクープだぞ」
記者たちはレイシャを取り囲み、【トライデント】について質問し始めた。取材する側から取材される側になり、カメラのフラッシュにレイシャはすくみ上る。
「死体を回収しろ」
ルシウスの命令に兵士が階下へと駆け出していく。テロリストには【トライデント】のことについても、カゲトラの居場所についても吐かせたかったが、この高さから落ちれば生存は絶望的だ。だが、話はほかの人間から聞けそうだ。
「すみません。少しお話をおうかがいしても?」
記者に取り囲まれているレイシャにレイジが近づき、彼女に任意同行を求めた。ドサリと言う音にルシウスが目を向けると、そこには意識を失ったココレットが倒れていた。
□◼︎□◼︎□◼︎
落下スピードは落ちるほどに速まり、地上がどんどん近づいてくる。こんなものどう考えても助かりようがない。迫る地上に、ハルヒは固く目を閉じて歯を食いしばった。
瞬間、ぶあっと身体が下から吹き上げられ、落下スピードが弱まった。ふわりと、まるで羽根が生えたかのように地上へ降りたハルヒは、自分の身に何が起こったのかわからずにただビルを見上げた。
助かるわけがないはずなのに、まだ生きている。この間から不思議なことが立て続けに起こっていた。さすがに偶然で済ますには無理がある。こんなことが起こり始めたのは───、
「う……っ」
同じく無事に地上へたどり着いたアキが胸を押さえて呻いた。そこでハルヒはようやくハッと我に返った。
「クサナギ……!撃たれたのか!?」
アキはそうじゃないと首を振るが、冷や汗が滲む顔色は紙のように白かった。彼は息苦しそうにゼエゼエと喘ぐ。
(カゲトラ……)
ブロッケンビルに潜り込み、ナツキを探すためにカゲトラとは二手に分かれた。侵入するにはもってこいのダクトにカゲトラの身体が入らなかったためだ。別の入口を探すからダクトの出口で待っているように言われたが、ハルヒはその指示に従わなかった。おそらく、カゲトラはまだビル内にいる。そして、ココレットもナツキのことについて何か知っている様子だった。いま戻れば有力な手がかりが得られるかもしれない。
(でも……)
いまにも気を失いそうな状態のアキをひとりにすることは、ハルヒにはできなかった。それに、ここから早く移動しなければ、軍は死体を確かめに来るだろう。
「ハルヒ……。そこに、バイクが……」
アキが指をさすそこには、見覚えのあるバイクが停めてあった。ハルヒはアキの腕を肩に回すと、自分よりも重いアキの身体を支えながらバイクまで移動する。
アキの後ろに乗ったときに運転のやり方なら見ている。ハルヒは運転席にまたがると、アキの手を自分の腰に回し、その手首を頭に巻いていたバンダナで縛った。
「……はは。なんか悪いことしてるみたい」
「何が悪いことだよ。俺はテロリストだぞ」
ハルヒはそう言うとバイクを走らせた。
□◼︎□◼︎□◼︎
カゲトラが駆けつけたときには、すでにすべてが終わったあとだった。
パーティー会場の前の窓ガラスは粉々に砕け散り、身を隠した壁側から、気を失った少女が兵士に運ばれていくのが見えた。そこにレイジの姿はなく、途切れ途切れに聞こえてくる記者たちの話で、窓から記者が落ちたことを知った。
記者ならハルヒではない。落ちたのはハルヒではない。自分にそう言い聞かせながら、カゲトラはその場をあとにする。
騒ぎが起こったため、警備の数が増えている。このままではナツキを見つけるどころではない。ハルヒは怒るだろうが、今回は諦めて戻るしかない。ハルヒもそう判断していることを祈りつつ、カゲトラは来た道を戻ろうとして、小さな悲鳴に気づいた。
それは奥の部屋から聞こえたものだった。ハルヒではないとわかっていながらも、女性の悲鳴を放っておくことが出来なかったカゲトラはその部屋の前までやってきて、少し開いている扉の隙間から中の様子をうかがった。
「質問には慎重に答えるのがおまえの身の為だ」
部屋には3人の兵士と、椅子に座っているひとりの女性の姿があった。首からかけてあるネームプレートで、カゲトラは彼女が記者であることを知る。それはレイシャだった。
「もう一度聞くが、おまえは【トライデント】か?」
「ち、違いま……!」
「嘘をつけ!」
兵士が壁を殴りつけ、レイシャは怯えて身を縮ませた。
「おまえの連れは【トライデント】だろうが!」
「クサナギくんは……ッ」
「おまえも仲間なんだろ!」
カゲトラには何がどうなっているのかわからなかった。レイシャは【トライデント】の一員ではない。
「違、……違います……私は違う……っ」
「あらら、泣いちゃったよ」
兵士のひとりが鼻で笑う。
「こんなに優しく聞いてるのに、よッ!」
兵士に椅子の足を蹴られ、レイシャは床に投げ出される。ドレスがはだけて露出したレイシャの脚を見て、3人は顔を見合わせて無言の合意を得る。
兵士たちの視線に気づいたレイシャはドレスを直すが、兵士は彼女の両手を床に押さえつけ、悲鳴を上げようとした口も塞いでしまう。
見ていられない状況に、カゲトラは部屋に踏み込み、早速前のジッパーを下ろそうとした兵士の後ろ首を掴むと、その頭を壁に叩きつけた。カゲトラの侵入に気づいた残るふたりが銃を抜こうとするが、発砲前に銃は叩き落とされ、ひとりは顎を殴られて目を回し、もうひとりは顔面に拳を食らって鼻血を噴き出しながら倒れた。
あっと言う間に3人の兵士をのしたカゲトラは、呆然と自分を見上げるレイシャに、大丈夫かと手を差し出した。
□◼︎□◼︎□◼︎
アキのアパート前にはすでに軍の車が数台停まっているのが見えた。ハルヒは兵士たちの目に触れないようにバイクの方向を変えてその場をやり過ごす。
(どうする……)
アキのアパートにもF地区にも帰れない。だが、アキはどこかで休ませないとまずそうだ。もうほとんど意識のないアキの頬に手にやると、体温が異常に高いことがわかった。
安全であり、身を隠せる場所。それを必死に考えたハルヒは、アキが首から下げているネームプレートを見て、そこに書いてある文字と同じ文字が書かれた場所を思い出し、そこへ向かうことにした。
ほどなくしてたどり着いたレーベル社にはまだ灯りがついていた。だが、そこにも兵士の姿があり、彼らは建物の中から大きな段ボール箱を抱えて運び出していた。全部軍に先回りされている。これ以上どこにも行き場がない。絶望感がハルヒの肩に重く圧し掛かる。
「おまえらなにやった?」
「ッ!?」
背後からの声に振り返ると、頬に押し当てられたのは銃口ではなく指だった。ハルヒの頬の感触を指でぷにぷにと楽しみながら、ハインリヒはぐったりとしているアキを見下ろす。
「会社に忘れもんして取りにきたら、俺の許可なく軍の手が入ってるじゃねえか。ったく、こう言うのが嫌だからいままで軍にへこへこしてきたってのに、この分じゃいまごろ俺の家もアウトだろなぁ……」
やってくれたなと、ハインリヒは意識のないアキの頭をガシガシと撫でると、安全な場所へ移動するぞとハルヒにそう言った。
□◼︎□◼︎□◼︎
ハインリヒが案内したのは、同じC地区にある集合住宅だった。C、D地区はアパートやマンションが多い。その理由はこのふたつの地区の住民が、この街の中で多数を占めるからだった。
アキを背負ったハインリヒは、こいつでかくなりすぎだとアキの重みに文句を言いながら、角部屋のインターホンを鳴らした。しばらくすると中でパタパタと足音がして、玄関の扉が開く。中から顔を見せたのは下着姿の女性だった。
「あら、ハインリヒじゃない」
「よぉ、俺の仔猫ちゃん」
寝ていたのか、化粧がドロドロに崩れた女性の歳はハインリヒと同じくらいか、少し下か。豊満な胸を惜しげも無く晒した女性は、ハインリヒが背負ったアキと、その後ろにいるハルヒに視線をやって眉をしかめた。
「面倒事はごめんよ」
「俺は大歓迎だろ?」
「……目立つから入って」
開かれた玄関から中に入ると、ハインリヒはソファーの上にアキを下ろした。アキは意識を失ったまま、顔色も戻らない。
「で、これは何事よ?」
女性は腕を組んでハインリヒを問い詰める姿勢だ。ハインリヒは肩をすくめて、「実は俺もよくわかってない」と答え、ハルヒを見た。
説明しろと言う空気になって、どうしたものかとハルヒは迷う。もうすでに【トライデント】ではないのにアキもハインリヒも巻き込んでいる。家に上がり込んだ時点でこの女性だって無関係では済まされない。それなら正直に話したほうがいいとハルヒは判断した。情報は身を守る武器になる。
「俺は……【トライデント】だ」
ハインリヒはどこか察していたのか表情を変えなかったが、女性は冗談じゃないと吐き捨てた。
「ハインリヒ!あんたテロリストなんか連れてきたわけ!」
「みてえだな」
「いますぐ出て行ってよ!」
「……わかった。出て行く」
女性の言い分はもっともだ。ハルヒもここで長居するつもりはなかった。一度アキを振り返って、ハルヒはハインリヒに悪かったと頭を下げた。
「こいつにも謝っておいてくれ」
「自分で言えよ」
「……こいつのこと、頼む」
もうここに戻ることはない。ハルヒは覚悟を決めて部屋から出た。
□◼︎□◼︎□◼︎
行きがかり上、カゲトラはレイシャを連れてブロッケンビルを脱出することとなった。あのまま部屋にレイシャを放置すれば、彼女は昏倒した兵士達の説明までしなければならなくなるからだ。
兵士の目をうまくかわしながらようやく地上へ辿り着く。敵力はとりあえず脱出できたわけだが、レイシャの身体の震えは止まらなかった。このままレイシャを連れて歩くのは危険だ。ここまでだと判断したカゲトラは彼女にそれを伝えた。
「え、待って。お願い、家まで送ってください……っ」
レイシャはカゲトラに懇願する。いまのレイシャに夜道をひとりで歩いて帰る勇気はなかった。守ってもらえるはずの軍に裏切られた失望感と恐怖が彼女の中を渦巻いていた。
「……家はどこだ?」
「C地区のマンション……」
ここからそんなに距離がある訳じゃないが、いまは警備の数が多い。一刻も早くレイシャは帰宅したいのだろうが、すぐに動くのが得策とは言えなかった。
「わ、私のこと守って、く、ください。お願いします」
レイシャの声は震えている。あの場ででしゃばらないほうがよかったかと、カゲトラはもう1つの分岐点を考えた。
あのままレイシャを放っておけば、彼女は兵士たちに強姦されただろう。巷では、一度【トライデント】と疑われたら、死ぬまで解放されないと言うのが通説だった。たとえ【トライデント】でなくても、レイシャはもうもとの生活には戻れない。カゲトラに助けられて追われる身となるのとどっちが良かったかと聞かれれば、答えはひとつ。パーティーに来たのがそもそもの間違いだった。
「……家まで送ろう」
家に帰ったところで、名前も身元もバレているのだからすぐに軍が追ってくる。家は安全な場所ではないのに、それがわからないくらいレイシャは混乱していた。だが、それが唯一彼女を落ち着かせる言葉だ。
「……あ、ありがとうございます」
カゲトラの言葉に安心して、レイシャは胸を撫で下ろした。
「俺から離れるな」
レイシャにそう言ったカゲトラが巡回している兵士に視線をやる。すると、その兵士の身体は前触れなく倒れた。
「!?」
カゲトラはレイシャを自分の後ろへ隠した。その間にも、次々と警備は倒れていった。
「なんだ……?」
「探したぞ。バンダ」
暗闇の中から声がした。その声はカゲトラにとって覚えのあるものだった。
「……カガリヤ?」
「裁判所で見失ってから見つけ出すのに苦労したぞ。いったいどこに隠れていたんだ」
カガリヤと呼ばれた男が闇の中から姿を見せる。その男は、カゲトラには及ばないが、長身でがっしりとした体格をしていた。
「心配ない。仲間だ」
怯えているレイシャにそう言って、カゲトラはカガリヤと握手を交わした。ヨウヘイ・カガリヤ。彼は連絡役と呼ばれる【トライデント】の一員だった。年齢はまだ若いが、【トライデント】のメンバーに与えられる武器や情報はすべて彼が調達してくるもので、仲間としてカゲトラは彼を信用していた。
「カガリヤ。F地区の仲間が……」
「話は後にしよう」
カガリヤの言うことはもっともだ。こんな場所では落ち着いて話せない。それにレイシャもいる。
「わかった。先に彼女を家まで送り届ける」
「彼女は何者だ?」
「訳あって保護した一般人だ。家に、」
「同志でないのなら生かしておけない」
カガリヤの言葉にレイシャが息を呑んだ。
「一般人だ。軍とも【トライデント】とも関係ない」
「コウヅキの裏切りで、仲間内でも不信感が募っている。不安分子を放置することはできない」
確かに、レイジの裏切りは【トライデント】に多大なる被害をもたらした。同じ轍は踏めない。だからと言って───。
「わ、私……」
だれにも言わない。そう言ったところでカガリヤは信じない。彼は信用できる男ではあるが、同時に融通のきかない冷徹な男でもあった。レイシャが生き延びることができる方法。その答えはひとつだ。
「か……彼女も、【トライデント】……だ」
そう言うしか他に道はなかった。
□◼︎□◼︎□◼︎
悪いとは思ったが、時間を節約するためにアキのバイクを借りた。まだ朝方の冷気の残る風を受けながら、ハルヒは逃げた道を今度はひとりで戻った。
戻ってきたブロッケンビルを見上げたハルヒは、パンッと両頬を叩くと正面エントランスへと向かった。
ナツキはここにいる。レイジがここにいたことと、ココレットが口にしたナツキの名から、ハルヒの中でそれは確信めいたものになっていた。
ブロッケンビルの周りはまだたくさんの警備の姿がある。それも、落ちたはずの死体が見つからないのでは無理もなかった。
正面突破は不可能。だからと言って、非常口にも抜かりなく警備が付いている。カゲトラとハルヒが侵入したとき、警備はザルのようなものだったが、ようやくパーティー気分は抜けきったようだった。
ハルヒは大きく息を吸った。どの道、中に入れば監視カメラに映る。レイジとも決着をつけなければならない。もうだれも巻き込まないために。
ビルに近づくハルヒに兵士が気づく。発砲命令が出ていないのか、それともあまりに堂々としたハルヒの態度に呆気にとられたのか、誰も制止の声すらかけない。
ハルヒは正面ゲートをくぐり、広いエントランスに入った。そこには赤毛の女性兵士が待ち構えていた。
「ハルヒ・シノノメか」
問いかけにハルヒは頷いた。
「私はエルザ・アスタエル少尉だ。リュケイオン大佐がお会いになるとおっしゃられている。ついて来い」
機械的なしゃべり方で用件を伝え、ハルヒの返事を待つ前にエルザと名乗った女性兵士はエレベーターのボタンを押した。
「俺が会いたいのはレイジ・コウヅキだ」
「大佐がお会いになる。ついて来い」
エルザと名乗った女性兵士は、録音された音声のように同じ音を繰り返した。それ以外に選ぶ道はないと言うことだ。ハルヒは仕方なく歩き出したエルザに付いていく。侵入したときはダクトからだったが、今度はエレベーターに乗って落ちた分だけ上昇していく。
ハルヒは自分に背中を向けたエルザをジッと見つめる。人質にすれば交渉できるかと考えたが、相手は軍人で、ドレスを着たお姫様ではない。そう簡単にはいかないだろう。それにエレベーターには監視カメラが付いている。
そんなことを考えている間に、高速で上昇したエレベーターは目的の最上階へと到着した。
エレベーターを降りたエルザとハルヒは赤い絨毯が敷かれた床を進む。ハルヒには価値がわからない美術品が各所に置かれていて、突き当りの壁一面は水槽になっていた。生まれて初めて魚を見たハルヒは、水の中を泳ぐ生き物に一瞬釘付けになる。
「マーテルから取り寄せたものだ」
その声にハルヒはハッと身構える。そこにはルシウスの姿があった。
「砂漠ではなかなかお目にかかれないものだろう。気に入ったのならプレゼントしようか?」
ハルヒは黙ったままルシウスを睨み付ける。ルシウスは敵地の真ん中でも威勢を失わない少女にクッと笑った。
「エルザ。下がっていい」
「しかし大佐。小娘といえど、テロリストです」
「私は下がっていいと言っている」
ルシウスの命令に、エルザはハルヒをひと睨みしてからその場を立ち去った。コツコツという靴音が遠ざかっていく。
「立ち話もなんだ。まあ、かけたまえ」
ルシウスはハルヒにソファーを勧め、自分はグラスにワインを注いだ。ハルヒは立ったまま、唯一持ってきた武器の存在をジャケットの上から押さえて確かめる。
「しかし驚いたな。死体が見つからないとは聞いていたが、まさか本当に生きているとはな」
どう言ったカラクリなんだと、ルシウスは興味深そうにハルヒに聞いたが、彼女は答えなかった。そもそも、あの高さから落ちてどうやって助かったのかなんて、聞きたいのはむしろハルヒのほうだった。
「まあともかく、コウヅキから事情は聞いた。ここへ戻ってきた理由は弟を取り戻すため、そうなんだろう?」
「……弟はどこだ」
「勘違いしてもらいたくないのは、きみの弟は凄惨な現場から軍が保護したという事実だ」
「弟を返せ!」
この国では太陽が照り付ける昼は長く、月が穏やかに降り注ぐ夜は短い。すでに白々と夜が明けだした街には強い太陽の日差しが降り注いでいるのが、ルシウスの背後にあるガラス戸の向こうに見える。この時間ともなればとっくに30度は越えているはずなのに、この部屋の中は気味が悪いほど居心地のいい室温が保たれている。そんな中にいるにも関わらず、ハルヒの額には緊張から汗が滲んでいた。
「まず、無事であることを確認してもらおうか」
ルシウスはそう言うと、テーブルの上に一枚の写真を置いた。そこには車に乗っているナツキの姿が写っていた。毎日顔を合わせていたたったひとりの弟だ。これが撮影されたのがごく最近のものだとハルヒにはわかる。
「無事は確認してくれたかな」
「……弟はどこにいる」
「この件は先ほどコウヅキから聞いたばかりなんだ。まさか、あんな少年を保護しているとは知らなくてね」
「……士官が部下のやったことを知らないで通すつもりか」
「まさか。私はどこかの政治家のような無責任なことはしない」
それはそうと。そこでルシウスは話題を変える。
「彼は元気かい?」
「………」
「きみと一緒に落ちた、あの記者―――、確かクサナギくんだったか」
「……奴は関係ない」
「それはないだろう。裁判所でもここでも助けてもらったじゃないか」
「ナツキはどこだって聞いてんだよ!」
ハルヒはポケットから取り出したナイフを抜く。それを見たルシウスはワイングラスを置くと、ハルヒに向かって両手を広げて見せた。
「……ッ」
刺してみろと言わんばかりのルシウスの態度に、ハルヒは汗で滑るナイフを握りしめた。
「ひとつ聞くが、そのナイフでひとを刺したことはあるのか?」
そう言ってルシウスは一歩ハルヒへ近づいた。もとから30センチ近くは身長差があるルシウスは、近づくほどハルヒにとって大きな壁となった。
「そのナイフでひとを殺したことは?」
「……ッ、てめぇが最初だよ!」
挑発に乗ったハルヒがナイフを振り上げると、ルシウスはナイフではなく彼女の手首を受け止め、それに気を取られたハルヒの足を払った。
ハルヒは床に倒れ、その手から落ちたナイフをルシウスは部屋の隅まで蹴り飛ばす。そして、起き上がろうとするハルヒの体の上に覆い被さった。
「この……ッ!」
押しのけようとするハルヒの両腕を掴み、頭上にあげてひとまとめにすると、ルシウスの目に映る獲物の顔は見る見る青褪めていった。
(……たまにはこういった毛色の違う女で遊ぶのもいい)
ハルヒはルシウスを睨み付けてはいるものの、その目には涙が浮かんでいる。そういえばと、ルシウスはレイジから受け取ったハルヒ・シノノメのファイル内容を思い出す。家族は両親と弟だったが、父親は行方不明、母親は強姦されて殺されていた。その現場を見ていたハルヒには強いトラウマが残っている。そうファイルには書かれていた。
「どうした。青ざめているじゃないか。もっと喜ぶといい。私の寵愛を受けられる女はそういない。ましてテロリストでは夢のまた夢だ」
ハルヒにキスをしようとしてルシウスは咄嗟に顔を引く。そのすぐあと、ルシウスの鼻に噛み付こうとしたハルヒの歯がガチンッと鳴った。
「……まるで獣だな」
唇を噛みちぎられるところだったことに苦笑し、ルシウスは笑顔のままハルヒの顔を平手で殴った。そして、軽い脳震盪を起こしたハルヒが回復する前に、彼女のシャツの襟首を掴むと躊躇なく引きちぎった。
「どうした?」
ルシウスはハルヒに聞くが、答えはなかった。服を破られ、肌を剥き出しにされたハルヒの身体は震え出していた。滲んでいた涙が目尻から流れ落ちて黒髪を濡らす。
「なるほど。泣くほど嬉しいのか」
勝手な解釈をしたルシウスがどうやって楽しむかと目を細めたそのとき、コンコンと壁をノックする音がした。ハルヒとルシウス以外はだれもいないはずの室内に響いたその音に、ふたりはそこへ顔を向ける。
「クサ、ナギ……?」
ハルヒが呆けたように呟いた。そこには、壁にもたれかかったアキが立っていた。まだその顔色は青白いが、アキはハルヒと目が合うと、偶然出会ったときに見せたように手を振って見せた。
「なんで……!」
「きみは……ほんとに無茶するね……」
ハルヒは覚えていないだろうが、最初に助けたときとまるで同じ状況だ。自分を女性だと認めれば、こんな危険が待っていると予想することもできるのに。だが、いまはハルヒにそんな説教をしても仕方ない。アキはハルヒを押さえつけているルシウスと目線を合わせる。
「……クサナギくん。だったね」
「どうも……っ」
アキは小さくむせ込んだ。
落下死したと思っていたアキが生きていたことに、ルシウスは大して驚かなかった。ハルヒがピンピンしていることから、どんな奇跡かは知らないがアキが生きている可能性は高かった。腑に落ちないことは、どうやってあの高さから落ちて助かったのかと言うことと、どうやってここまでやってきたかと言うことだ。
正面入り口も、裏口も、パーティー開催時とは比べようもならないほどの警備で固めている。その警備から侵入者があったとの報告を、取り込み中だったとはいえルシウスは受けていなかったし、あの真面目なエルザが職務を放り出したとは考えにくい。
「種明かしをしてくれないか?」
ハルヒを押さえつけたまま、ルシウスはアキに言った。
「どうやってここまでたどり着いた?」
「エレベーターで直通でしたよ」
「警備の兵がいただろう」
「さあ……どうだったかな。そんなことより……彼女を離してください」
「これはきみの恋人か?」
そう言いながら、ルシウスは銃を抜いてアキに向けた。目を剥いたハルヒが暴れるが、ルシウスの片手一本を振り解くことができない。
「やめておいたほうが……賢明だと思いますよ……」
アキは壁から背中を離し、ふらつきながらやっとのことで立っている。その様子は言っていることとまるでちぐはぐだった。
「クサナギ!逃げろ!」
ハルヒが叫ぶ。だが、銃口で眉間を狙われても、アキは逃げようとしない。その顔には笑みさえ浮かんでいた。
「逃げろって!ばか野郎ッ!」
「クサナギくん。私は時と場所をわきまえない冗談は嫌いだ」
「クサナっ……!」
パンッと銃口が火を噴いた。
硝煙が上がる銃を目にしたハルヒはまばたきもできない。どんなに射撃が下手でも外す距離じゃなかった。ハルヒはルシウスの銃から視線を外すことができない。眉間に穴を開けられただろうアキの姿を見ることができなかった。
だが、音を立てて床に落ちたのはルシウスの銃だった。
「……な、ぜ」
それはルシウスの声だった。落ちた銃からハルヒが視線を上げると、アキはさっきと同じ姿勢のまま立っていた。確かに発砲音が鳴ったのに、どこも撃たれた様子はない。
「なぜ、だ……!」
疑問を口にしながら、ルシウスはがくりと膝を折る。その胸には赤い血の染みが広がっていった。
「え……」
銃が暴発したのかと一瞬ハルヒはそう思った。だが、ルシウスの銃にはそんな形跡は見当たらない。撃ったのはルシウスのはずだ。だが、撃たれたのも彼だった。ふわっと柔らかな風がハルヒの髪をなびかせる。部屋の窓はどこも開いていないのに風が吹いている。それはまるでアキの吐息のようだった。
「あなたじゃ僕は殺せない」
「なん、だと……!」
「軍が裏でなにをしているのか知りもしない、お飾りの大佐じゃね」
銃を拾おうと手を伸ばしたルシウスの真横を風が通り抜けた。それはルシウスの傷ひとつない顔に赤い血の筋を作り、背後のコンクリートを削り、そこに巨大な獣がつけたような爪痕を残す。
見覚えのあるその傷痕にハルヒは息を飲んだ。それは首輪のつけた少年が射殺されたE地区の壁に刻まれていたものとあまりにも酷似していた。
「こんな、ばかな……っ」
自分の目で見ていることが信じられないまま、ルシウスはその場に倒れた。アキもフラついて壁に手をつく。のしかかってきたルシウスを押しのけ、ハルヒは転がるようにアキのもとへと走った。
「クサナギ!」
「……だい、じょうぶ」
そう言いながら少しもそうは見えないアキは、胸を押さえてゼエゼエと息を吐く。ビルから飛び降りたときより悪化していることは見た目にも明らかだった。
「なんで来たんだよ……!」
「なんでって……」
ハインリヒに止められたがここへ来た。アキはその理由を考えるが、心臓の音がうるさすぎて考えがまとまらない。
「なんとなく……?」
「そんな理由で来るところじゃねえだろ!」
これ以上巻き込みたくなかったのにと、ハルヒは俯いた。アキはその髪をそっと撫でる。
「……痛いのか?」
胸を押さえるアキの手には血管が浮き出ていて、かなり強い力で胸を押さえているのがわかった。
「ちょっと、ね……。使わなければ落ち着くから」
使わなければ―――。その言葉に、ハルヒは壁に刻まれた裂傷をもう一度見た。やはり、壁にこの傷をつけたのはアキの力なのだと確認するために。裁判所でも、ビルから落ちたときも風が吹いた。そのすべてにアキの姿があった。
「ナツキくんを探さなきゃね……」
アキの言葉は、ハルヒにこのビルへ戻ってきた本来の目的を思い出させる。その時、バリバリバリと屋上で鼓膜を破るような音が響いた。ガラス戸に視線をやると、飛び立って行くヘリが見える。その操縦席にレイジの姿を発見し、ハルヒは息を呑んだ。
「止められるかも」
アキが言った。だが、ハルヒはその腕を掴んで首を振った。
「脱出する」
「だけど―――」
「いまにも死にそうな顔色して、なにが止められるかもだ!冗談は時と場所をわきまえろ!」
「……わかった」
頷いたアキに肩を貸すのはこれで二度目だ。身長差からあまり意味がないかもしれないが、ハルヒはアキの歩調に合わせてエレベーターへ向かった。エレベーターを一階まで降りると、エントランスに何十人もの兵士が倒れていた。
「これ……おまえがやったのか?」
「さすがに疲れちゃったけどね」
アキは否定せず、ハルヒもそれを信じた。
ハインリヒたちの安全を考えれば、彼らのもとへ戻るわけにはいかなかった。いまならハインリヒは逃亡幇助の罪もかからない。
アキの案内で、ふたりはブロッケンビルとは天地の差がある古びたモーテルへやってきた。C地区にも酷い建物があるものだとハルヒは思ったが、この際アキを休ませるベッドがあればどこでもいい。元気そうに振舞ってはいるが、モーテルへ到着する頃には、アキはほとんど自分の力で歩くことができなくなっていた。
用心しながら店に入ると、カウンターに座っている老婆は居眠りをしていた。いつも寝てるんだよとアキが笑った。ハルヒは空いている部屋の鍵を取ると、入口から一番近い部屋の扉を開けた。
余計なものがまったくない部屋には、ベッドがひとつ置いてあるだけだ。ようやくアキを休ませることができる。ハルヒはホッとして、彼をベッドの上へ腰掛けさせた。
「寝ろ」
言われるまま、アキはベッドへ横になって深い息を吐いた。すぐに瞼が重くなってくる。ここまで立て続けに力を使ったのは本当に久しぶりだったからか、胸の痛みが治まったあとは意識も身体も鉛のように重くなっていった。
「そうだ……これ」
眠ってしまう前に、アキはポケットに入れていたハルヒのバンダナを差し出す。
「忘れ物」
「ああ……」
アキの手からそれを受け取り、ハルヒは床に腰を下ろした。自分が落ち着かなければ、アキも休まないだろうと思ったからだった。
「さっきはその……助かった」
「……ん」
アキはもうウトウトし始めている。力が抜けていくその顔を見ながら、ハルヒはアキの周りに吹いていた風のことを考えていた。
ルシウスがいた部屋に着いた裂傷は、E地区のあの壁についたものと同じだった。あの首輪がついた少年が射殺された場所に裂傷をつけたのもアキなんだろうか。あのとき、裂傷についてアキはなんて言っていたか。あのときのアキはハルヒにとって怪しい人物でしかなかったため、疑うことで頭がいっぱいでよく思い出せなかった。
「クサナギ。おまえあのとき、」
「それ……やだな……」
「え?」
「クサナギって……言うの。僕の名前……アキって呼ん、で……ほしぃ……」
最後の音は寝息に混じって消えていく。やがて寝息を立て始めたアキに、ハルヒは言いかけた言葉をため息に変えた。
□◼︎□◼︎□◼︎
カゲトラとレイシャが連れて行かれたのは、A地区にある荘厳な建造物の前だった。それまで外が見えない車に乗せられていたレイシャは、外に出るなり腰を抜かすほどに驚いた。カメラがあれば連続でシャッターを切っていただろうその場所は、王政が崩壊してから軍の管理下に落ちたスタフィルスの王城だった。
「こっちだ。来い」
ふたリはカガリヤに急かされて王城へと足を踏み入れた。カゲトラもここへ来るのは初めてだったが、車に乗ったそのときから、いや、連絡役であるカガリヤが現れた瞬間から、連れて行かれる場所が王城であることは予想外だったものの、引き会わされる人物は予想できていた。
カガリヤに続いて建物へと続く階段を上がる。その先には、砂の国の王族が住んでいた宮殿がそびえ立っている。この国でクーデターが起こったのは20年ほど前のことになる。それまでは王政だったこの国は、その歴史的事件をきっかけに軍政へと姿を変えた。
王は王妃たちやその子供らもろとも、信じていた騎士に殺された。その後、その騎士はスタフィルスの軍の将軍となった。
「すごい……」
レイシャは感嘆の声を漏らす。
「王宮なんて初めて入るわ……」
王族が絶え、宮殿が軍の監視下に置かれたと言っても、それは建前でとっくに打ち捨てられているとだれもが思っていた。だが、内部は荒れ果ててなどなく、むしろ磨き上げられて生き生きとしている。まるで王がまだここにいるかのように。
宮殿の中に入るとレイシャは小さな悲鳴をあげる。なぜなら、王座まで続く両脇にズラリと鎧を身につけた騎士がズラリと並んでいたからだ。白銀の鎧を身につけた兵士たちは正面を見据えたまま全員が兜を脇に抱え、白獅子の紋章を胸に抱いていた。
「どうして白獅子の騎士が……」
レイシャの疑問はもっともだった。スタフィルス王族は途絶え、ここに並ぶ白獅子たちが守るべき存在はすでにない。スタフィルス最後の王にはたくさんの子供がいたが、彼らはひとり残らず殺された。だがあの頃、まことしやかな噂が飛び交った。ひとり生き延びた身重の王妃がいたと。
「カゲトラ・バンダだな」
玉座にはひとりの若い女性が座っていた。黄金色の豊かな長い髪と、眩いばかりの美貌がレイシャの視線を釘付けにする。この世のものとは思えない美しさとは、このことを言うのだろうと、レイシャは玉座の女性に魅せられていた。
カゲトラはその場に膝をつく。すでに彼女が何者なのかわかっているからだ。ハルヒには話していなかったが、【トライデント】は玉座の女性の存在があってこそ成り立つ組織だった。
「跪け」
ポカンと立っているレイシャをカガリヤがギロリと睨んだ。
「アメストリア女王陛下の御前だ」
アメストリア女王陛下。そう呼ばれた彼女がだれなのかレイシャにはわからない。だが、ピンッと張り詰めた空気が彼女を跪かせた。
「やめろ。堅苦しい。だからこの椅子に座るのは気が進まないのだ」
アメストリアはカガリヤに不快だと言い捨てた。
「バンダ。そして娘。立て」
アメストリアの命令に、カゲトラとレイシャは立ち上がる。
「F地区でのこと、残念だった」
アメストリアはそう言った。
「許せ。こちらも、コウヅキの裏切りは予想外だったのだ」
「……私が気付くべきでした」
「自分を責めるな。バンダ。まだ終わったわけではない」
アメストリアはそう言うが、F地区の【トライデント】はレイジの裏切りによって壊滅したも同然だ。散り散りになった仲間とは未だに連絡を取れていない。カゲトラにしてみれば、もはや立て直しは不可能に思えた。
「むしろ始まったばかりだ」
アメストリアは脚を組み替えてレイシャに視線をやった。
「娘。そなたはレーベル社とやらで働いていると聞いたが」
「は、はい」
「アキ・クサナギを知っているか」
予想もしていなかったアキの名前が出て、レイシャは彼を最後に見たときのことを思い出す。
「知ってますけど……クサナギくんはもう……」
「死んではいない」
「えっ?」
レイシャはアメストリアに聞き返した。
「適合者はあれくらいでは死なない」
「な……」
アメストリアの言葉に、今度声を上げるのはカゲトラのほうだった。
「あの男が適合者だって……!?」
アメストリアはその顔に満足そうな笑みを浮かべて頷いた。
□◼︎□◼︎□◼︎
ピッ、ピッ、ピッ。定期的な機械音が鳴る。心拍数を教える機械の横には、たくさんのコードに繋がれたルシウスの姿があった。その周りを医師団が取り囲み、体に埋まった銃弾をピンセットで取り出している。
銃弾が取り出されると、その様子を手術室の外からガラス越しに見ていたエルザはホッと息をついた。難しい手術ではないと聞いていたが、手術は手術だ。油断はできない。だが、心拍数も血圧も安定している。残るは縫合だけだ。
ブロッケンビルはたったひとりの民間人に襲撃された。万全の警備を敷いていたにも関わらず、ほとんどの兵士がまともに戦うこともできずに倒された。たったひとりの武器も持たない男の、得体のしれない力を前に敗れ去った。そして、自分が情けなくも失神している間にルシウスは撃たれた。ビル内の異変に気づいた外回りの警備兵に発見されたルシウスはすぐに軍病院へ運び込まれ、緊急手術が行われることになった。
パーティーでテロリストの人質にされたココレットは無理ないとしても、息子が緊急手術を受けるというのに、父親である将軍は姿も見せない。家族というのは名ばかりで、リュケイオン家は冷え切っていた。
「―――大佐!」
突如、手術室で悲鳴が上がった。何事かと目を向けたエルザは、手術台の上で身を起こしたルシウスの姿を見つける。縫合中だった傷口から血が吹き出し、床に撒き散らされた。
「どこだクサナギイィッ!」
ルシウスはアキの名を叫び、その姿を探して腕を振り回し、周りにある手術器具を薙ぎ払う。エルザは真っ青になってガラスに張り付いた。
「殺してやる!必ず殺してやる!」
「鎮静剤を早く!」
十分な量を投与していたはずなのに暴れ出したルシウスを数人で押さえつけ、さらなる麻酔が追加される。それでも烈火の如きルシウスの怒りはしばらく治らず、手術が再開したのはそれから数十分もあとのことだった。
―――アキ・クサナギ。あの男、殺しても飽き足らない。エルザは爪が食い込むほど強く自分の拳を握り締めた。
ハプニングはあったものの、手術は無事に成功し、ルシウスは病室へと移された。一時はどうなることかと思ったが、いまは麻酔がよく効いて入るようだ。エルザは病室の椅子に腰掛け、深い寝息を立てるルシウスの頬にそっと触れた。
手術をすることになったことも、それが無事に終わったことも父親の将軍に報告はしたが、返事はなかった。将軍を父親にもつルシウスは将来を約束され、30歳の若さで大佐にまで上り詰めたが、温かい家族と言うものには恵まれなかった。
ルシウスは家族を愛していないし、リュケイオン家のだれもルシウスを愛しはしない。それでも世間は彼らを栄光の家族と呼んだ。
コンコン。扉がノックされて開かれた。看護師かと振り返ったエルザは、ズカズカと病室へ入ってきた明らかに病院関係者ではない女に腰から抜いた銃を向けた。
「いやだわ。物騒な物はしまってくださいな」
そう言った女―――チグサは、エルザに対して襟元についているバッチを見せた。それは軍の研究機関に属することを証明するバッチだった。
エルザは仕方なく銃をホルスターへ収める。研究機関は同じ軍属ではあるが、エルザは生理的に秘密主義の彼らを好きにはなれなかった。
「あらあら。せっかく来たのに、ボウヤはまだおねんねしてるのね」
チグサはルシウスのベッドに腰を下ろして、遊ぶように点滴の管を指で弾いて揺らした。
「用件は私がおうかがいしましょう」
「結構よ」
「私は大佐直属の部下です」
「お嬢さんじゃ役不足よ」
軍人として侮辱されたエルザは銃を抜こうとしたが、その腕をチグサではない別のだれかの手が掴んだ。
「な……!?」
いつからそこにいたのか、エルザの気づかないうちにそこにはフードを目深にかぶった男が立っていた。フードの中から覗く目に、ゾクリとエルザの背筋は凍り付いた。
「やめなさい」
チグサがそう言うと、フードの男はエルザから手を離す。強く掴まれていた腕は解放されてもジワリと痺れていた。
「あら」
チグサがその顔に笑みを浮かべる。ベッドの上では、ルシウスが薄く目を開けていた。
「お目覚めですか。大佐」
「……だれだ」
ルシウスはまだハッキリとしない意識をチグサに向ける。
「はじめまして。研究機関のチグサ・ワダツグと申します」
「研究機関……」
ルシウスはその言葉を繰り返し、何度か目をまばたきさせた。
容体は落ち着いてはいるが、まだ話ができる状態じゃない。そう判断したエルザは立ち上がった。
「本日はお引き取りください。大佐はまだ……」
「大佐はアキ・クサナギのことを知りたくありませんか?」
チグサはそう言って、ルシウスにファイルを差し出す。ファイルの1ページ目には、まだ幼さの残るアキの顔写真があり、その横にはNo.B−101と番号が書かれていた。
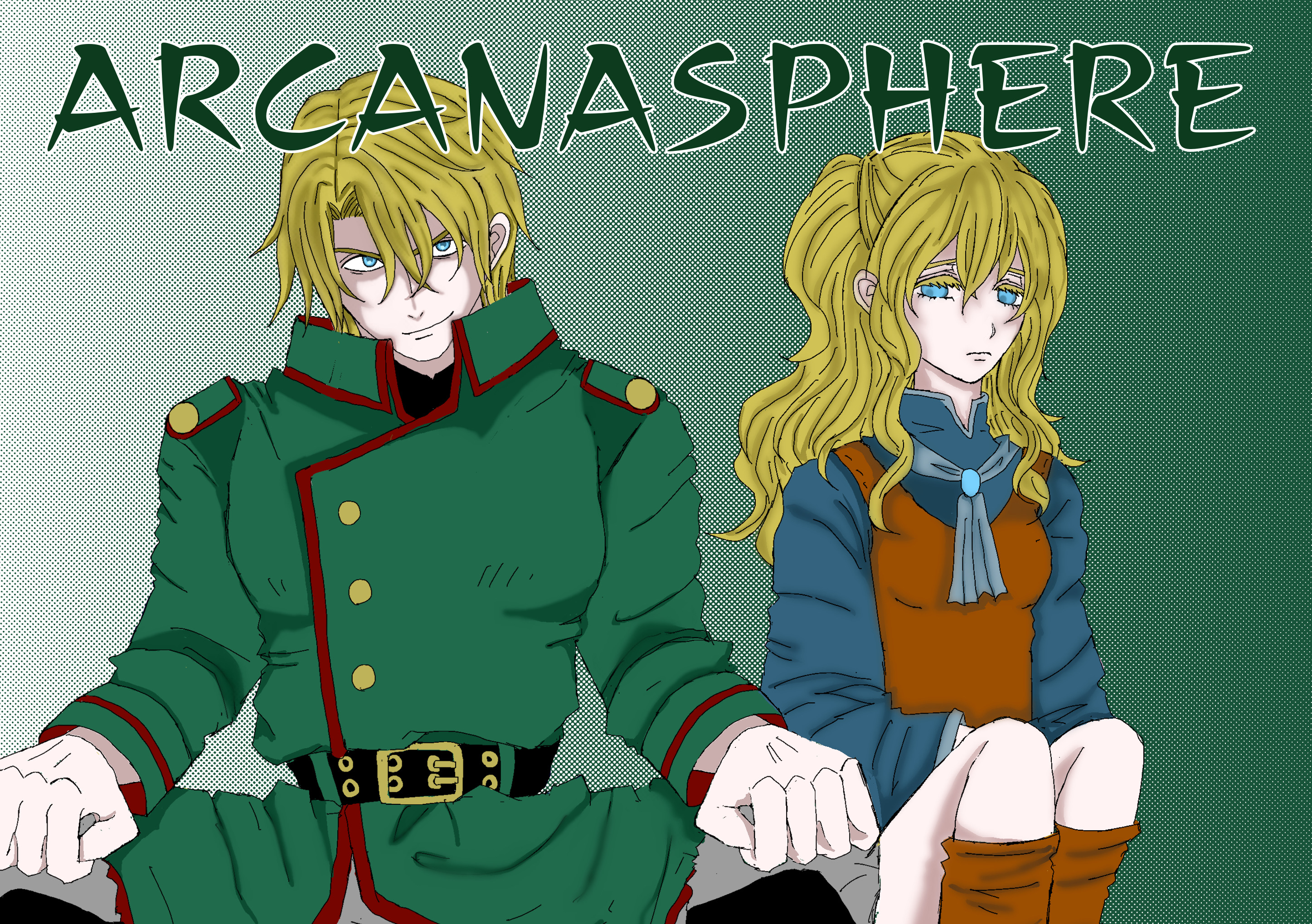
 にぃなん
Link
Message
Mute
にぃなん
Link
Message
Mute

 にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん