ARCANASPHERE12 そろそろ死ぬのかも知れない。
殴られ続けたキュラトスはボンヤリと自分の死について考えた。このままコシュナンで死ぬことになれば、死体はどう扱われるだろう。そのままの形でマーテルへ送り返されるか、一部だけが送り返されるか。それとも海にでも投げ捨てられるか。もしくは獣に食われるか。
キュラトスが危惧することは、自分の死によってマーテルは被害しか被らないという点だった。アイシスはきっと自分を取り戻そうとする。このままでは、マーテルは前後を敵に挟まれることになる。
マーテル国内では、奔放な王子だったキュラトスは国のためになることなどしたことがない。そして、ようやく国のためになることをしようとした結果がこれだ。
「何を考えているの?」
マーテルに残してきたアイシスの未来を思ったキュラトスは、ジブリールに髪を掴まれて顔を持ち上げられる。
「絶対に許さないわ……」
夫を殺したと噂されているジブリールに、コシュナン国内で復縁の相手など見つかるわけがなかった。彼女はこのコシュナンに一生閉じ込められて生きる道しか残っていなかった。そこへ舞い込んできたのが、キュラトスとの政略結婚の話だった。
デイオンから、キュラトスがティアと姦通したと聞いた直後は、謝ればキュラトスを許すつもりでいた。デイオンの思惑よりも、ジブリールは一回り以上年下のキュラトスに夢中になっていたからだ。
彼が跪いて自分に許しを請うのならば、ジブリールはデイオンに逆らってでも鎖から外してやるつもりだった。だが、キュラトスは謝るどころか、いくら打っても悲鳴さえ上げず、その態度はジブリールの神経を逆撫でた。
「なんて強情なガキ……!」
唇を噛んだジブリールは、今度は素手でキュラトスの頬を引っ叩く。久しぶりに食らった軽い一撃に、キュラは痛む口を笑みの形に変えた。それはさらにジブリールの怒りを増長させる。
(アイシス……)
きっといまごろは、キュラトスが他国の王子の妻を寝取ったなんて言う、前代未聞の連絡がマーテルへ飛んでいっているはずだ。同盟を結ぶはずだった使者が、マーテルの足枷になってしまうとは笑える。実際に笑いがこみ上げてきたキュラトスは、ゲホゲホとむせ込んだ。
むせ込むたびに肋骨が痛んだ。ジブリールの扇子は鉄扇で、それに容赦無く何度も打ち据えられれば、骨にヒビも入るというものだ。
ジブリールは血と汗でボロボロになっているキュラトスのシャツを引っ張る。すでに耐久性など皆無になっていたシャツは、簡単に千切れて落ちた。
「あら、素敵ね」
初めてキュラトスの肌を見たジブリールは声色を一変させた。どんな拷問を加えても、泣きついて許しを請わないキュラを、どうやったら屈辱の渦に叩き込むことができるだろう。彼女はずっとその答えを探していた。
自分の胸に触れたジブリールの手に、キュラトスはゾクリと悪寒を覚え、無意識に逃げようとする。鎖がガチャガチャと鳴った。
「殿下は、こう言ったことのご経験はおありですの?」
「……ッ」
「何も知らないまま死なせるのは気の毒ですわね」
急に機嫌が直ったジブリールの手がキュラトスの下半身へと降りていく。
「触んなクソ女……!」
吠えるだけなら犬でもできる。強がって乱暴な言葉を吐いても、いまのキュラトスはジブリールに対して手も足も出ない。明らかに虚勢を張り、動揺しているキュラトスに、ジブリールが愉悦を感じたそのとき、ピタリとその首に冷たい刃が当てられた。
「お久しぶりです。ジブリール姉上」
キュラトスが顔を上げると、そこにはジブリールの首にナイフを押し当てたパルスの姿があった。
「ぱ、パルス……ッ!?」
あの日、キュラトスに見せた快活な様子とはまるで雰囲気の違う、猛禽類のような瞳をギラつかせたパルスは、ジブリールの肉の断層にナイフの刃を埋めていく。
「なっ、なぜおまえがここに……!」
「さて、なぜでしょうねえ」
そう言うと、パルスはナイフの柄でジブリールの後ろ首を殴る。急所を的確に殴られ、白目を剥いたジブリールはキュラトスの足元に倒れた。
「よう、キュラ」
キュラトスはポカンと口を開けてパルスを見ている。
「随分と可愛がられたもんだな」
「……おまえ」
「だから言ったろ。デイオンには気をつけろって」
パルスはそう言うと、壁にかかっていた鍵で、キュラトスの身体を吊り下げている鎖の南京錠を外した。支えをなくすと倒れ込んでくるキュラトスの身体を受け止め、パルスはミッション終了と息をついた。
「そういや、おまえティアとはヤッたのか?」
「……ヤッたわけ、ねえだろ」
だろうなと、パルスはため息をついた。噂は噂だ。デイオンの策略に決まっている。それがわかっていてもだれも彼に口出しすることができない。いまのコシュナンの状態は最悪だ。
「状況は最悪だな……」
「まだ諦めるな。同盟が必要なのはコシュナンだって同じだ」
「……デイオンがそう思ってるとは思えねえよ」
「キュラ。おまえはデイオンと同盟を結びに来たのか?違うだろ」
「………」
「デイオンはコシュナン王じゃない。やつには本来なんの権限すらないんだ。おまえはハナから交渉相手を間違えてる。ここは王政国家だ。国の決定を下すのは王だ」
「あんな形だけの……」
老いぼれた老人になにができる。謁見の間で玉座に座るリオルドはデイオンの言いなりにしか見えなかった。
「王は、生きている限り王なんだ」
コシュナンの王は、前王の指名と、コシュナンに寄り添うように集まるラグーンの半数以上の代表が承認するかどうかで決まる。デイオンはマイスの代表の娘であるティアを娶っているため、その中のひとつの承認は得たことになる。
残ったラグーンを抱き込むためにもデイオンはあらゆる手をつくしていた。父親の亡き後、彼が王位を奪う準備は十分すぎるほど完璧にできているが、まだリオルドは生きている。
「俺が父上に進言してやる」
「………」
「マーテルとの同盟は必要だと俺が口添えする。だから諦めるな」
パルスの言葉に、諦めかけていたキュラトスの心に光が射し込んだ。
マーテルの王子を助けねば、このコシュナンに未来はない。
リオルドは、長い間訪れたこともなかった地下の牢獄への階段を降りていた。なんとしても水の国と同盟を組まなければならない。壁に掛けられている燭台の火が揺らめく灯りだけを頼りに、彼はその足を急がせる。
リオルドがもっとも愛した女性、パルスの母親が死んだ日に彼の心も死んだ。自分の息子が、愛する妻とパルスを殺したのかもしれないという疑いは彼に強いショックを与え、年齢以上に彼は老け衰え、近年は政権のほとんどを息子のデイオンが取り仕切るようになった。
デイオンの権力への渇望は酷いものだった。自分の邪魔になるものは殺してでも排除する。彼はそんな人間になってしまった。だが、これだけは思い通りにさせてはならない。マーテルの王子だけは殺させてはならない。
世界は排除するだけでは生き残れない。手を取り合わなければ未来はない。コシュナン王として、この国が、民が、死に絶えるようなことを許すわけにはいかない。螺旋階段を降りる王の耳に、話し声が聞こえてくる。
牢番の無駄口か、そう思いながらリオルドは階下へ目をやる。そこで彼は驚きにその目を見張った。階下に見えたのは、逞しく成長したパルスの姿だった。
「パルス……!」
震える声が喉から漏れる。石壁に反響したそれに気付いたパルスは、キュラトスとの会話を中断し、階段を見上げた。その顔に笑顔が浮かび、
「父―――」
その笑顔は硬直した。パルスの目に、涙を浮かべて自分を見下ろす父の背後から、剣を振り下ろすデイオンの姿が映った。
「父上ッ!!」
デイオンが振り下ろした剣は、リオルドの右肩から腰骨に至るまでを骨まで断ち割り切っていた。裂かれた肉の断面がパルスの目に生々しく映る。
「なりませんぞ、父上……。罪人を勝手に牢から出すなど、言語道断―――」
倒れゆくコシュナン王の後ろ首を掴み、デイオンはその耳元に囁いた。ゴボッとリオルドはその口から血を溢れさせる。
「法を破りし王に、裁きを……」
デイオンが手を離すと、リオルドの身体は階段を転げ落ちた。自分の足元へ落ちてきた父を助け起こすこともできず、パルスは血塗れになった彼を呆然と見下ろす。母が息を引き取るその時まで口にし続けた言葉が、耳鳴りのように彼の頭に響く。
恨んではいけない。憎んではいけない。―――憎悪は、連鎖するものだから。
「デイオォォオオオンッ!」
パルスは壁にかかっていた斧を手に階段を駆け上がり、それを迷うことなくデイオンに振り上げる。剣と斧がぶつかり合って火花を散らした。
「……コシュナン、王」
右腕の力だけで床を這い、キュラトスはコシュナン王のそばへと移動する。リオルドの傷は恐ろしく深かった。裂かれた場所から臓器がはみ出している。どんな手当てをしても助からないことはわかりきっていた。
「デイ、オン……、パル……ス……」
リオルドは殺しあう息子たちがぶつかり合う音を聞いていた。キュラトスは震える彼の手をしっかりと握った。
―――いつからか捻じ曲がってしまった。
いまはもう亡くなったデイオンの母である王妃は、気位の高い人物で、自分が生んだデイオンが王位につくことをひたすらに願った。だから、リオルドが愛情をそそぐパルスの母親が気に入らなかった。彼女はその恨みつらみを息子に言って聞かせた。母の恨みを晴らしてくれ。母の憎しみを晴らしてくれ。死ぬまでそれを繰り返した。
リオルドは、恨み言ばかりを言い続けるデイオンの母を疎ましく思うようになり、彼女を遠ざけた。反面、自分を包み込んでくれるパルスの母を愛した。そこに憎しみが生まれた。恨みが生まれた。力を合わせてコシュナンを守って欲しい。息子たちにかけた夢を捻じ曲げたのは―――潰したのは―――他でもない自分だ。
リオルドの死は直前に迫っている。なにかを言いたそうに口がパクパクと開いたのを見て、なんとかそれを聞き取ろうと、キュラトスはコシュナン王の口元へ耳を寄せた。掠れた声がどうにかキュラトスの耳に届くと、リオルドの身体から力が抜けた。
コシュナン王の遺言を聞き取ったキュラトスは呆然と、殺し合うデイオンとパルスを見上げた。デイオンの剣を力任せに弾き飛ばしたパルスだが、階段の上にいるデイオンの蹴りを食らいそこから転がり落ちた。ふたりは父親が死んだことにすら気付いていなかった。
「パルス……。パルスッ!」
キュラトスの叫ぶ声に、ようやくパルスがハッと我に返り、その顔を歪めた。デイオンもリオルドの死に気づき、その顔に歪んだ笑みを浮かべる。
「やっとくたばったか。老いぼれが……」
パルスは握力の限り斧の柄を握り締めた。
―――ずっと心を殺してきた。母の遺言を守るために、心を殺して生きてきた。母の死でデイオンを憎み、恨んで争えば、父が悲しむ。デイオンと争うことはただの兄弟ゲンカでは済まない。壮絶な王位争いが起こり、コシュナンという国が混乱する。
心を殺した。デイオンがどんなに自分を憎んでいようが、母を殺したのが彼で間違いなかろうが、そのすべてを心の奥底へ封じ込めた。それがいま爆発する。
パルスは階段の上にいるデイオンに斧を投げつけ、それを避けた彼に飛びかかった。転倒したデイオンに馬乗りになると、パルスは彼を殺すつもりで持っていたナイフを振り下ろす。その刃は顔を逸らしたデイオンにより、石の階段に当たって欠けた。
欠けたナイフに一瞬気を取られたパルスをデイオンは押し返そうとするが、パルスはそれを許さず、兄の首を絞め上げた。
憎んではいけない。恨んではいけない。頭に響く声に、そんなことは無理だとパルスは腕を震わせる。
母の最後はとても安らかとは言えないものだった。あの日、デイオンの別荘で行われたパーティーにパルスと母は招待された。だが、それは王位を得るために邪魔になるパルスを殺すための罠で、振舞われた酒は毒入りだった。
幼い頃から王位を巡る策略の中にいたパルスが毒に殺されないようにと、母は毒に耐性をつけるために、毎日少量の毒を食事に混ぜて彼を育てた。だが、この時に盛られたのは猛毒で、途端にパルスは立っていられなくなった。
母がよかれと思ってやってきたことが裏目に出たと言っていい。そこらの毒は効かないと決め付け、パルスは警戒もせずにデイオンの勧める食事を食べた。パーティーに招待されたのは次の王位にデイオンを推す一派で、パルス母子は野獣の群れの中に飛び込んだようなものだった。
母はすぐにパルスの異変に気付いたが、すでに遅かった。デイオンたちは笑いながらその別送を後にした。ふたりきりで残された山奥の別荘に、食べ物の匂いにつられ、一匹、また一匹と狼が集まって来るのには、そうたいした時間はかからなかった。
冬の寒さの中、飢えた狼たちは、パルスを置いて逃げることもできない母をじわじわといたぶって食い殺した。母は狼たちに体を食い千切られながら、毒で痺れて手も足も出ないパルスを庇い、一晩中彼に言い聞かせた。
憎んではいけない。恨んではいけない。憎悪は連鎖するものだから。おまえがデイオンを憎んで、恨んで、彼を傷つければ、きっと父が悲しむから。デイオンの大切な人がおまえに憎悪の感情を抱くから。
明け方になって、母の身体は崩れ落ちた。母と言う盾がなくなり、狼の爪に引き裂かれたパルスの視界が真っ赤に染まると、朝靄を吹き飛ばす音が鳴り響く。それはやっと駆け付けた父の兵士たちが鳴らした銃声だった。
母は生きたまま獣に食い殺された。どれほどの苦痛と恐怖だったのか、それは計り知れなかった。
デイオンは、毒でパルスを殺すつもりだったのだろう。生半可な毒では効かないとわかっているから、新種の毒を使ってそれでケリがついたと思った。まさか、パルスの母を狼が食い殺すとは思っていなかったはずだと、父はパルスに説明した。そして、許してくれと縋り付いた。
パルスには王子である自分を捨て、逃げることしかできなかった。
「そんなに王位が欲しいか……!」
パルスは吐き捨てた。
「俺の母を殺し、自分の父親まで殺して、そこまでして王位が欲しいか!?」
「欲しいに……決まっている……!」
首を絞めつけられながらも、デイオンはパルスを睨みつけてそう答えた。
「おまえとてそうだろう……!」
「ぐ!」
デイオンの膝がみぞおちに入り、パルスは思わず手を離す。ゲホゲホと噎せこみながら、デイオンはパルスから距離を取った。
「俺が、王位を望んでるだと……!?」
「そうだ……。王位など、眼中にないような澄ました顔をしているが、真実は違う!おまえだって俺を蹴落として、王位を手に入れたかったのだろう!庶子と言えど、おまえは父上のお気に入りだった!!」
「俺は王位なんか欲しいと思ったことはないッ!」
「いいや、違う!おまえは王になろうと画策している!わかるか!パルス!海賊まがいのことをやっていても、おまえの周りにはいつの間にか人が集まり、幾重にもその輪は広がる!おまえの母が生きていた頃のクルザの屋敷を覚えているか!まるで年中春のように花が咲き誇るあの庭で、おまえとおまえの母は父上を引きとめ、俺の母から遠ざけ、長兄である俺から王位を略奪しようと目論んでいたのだろうッ!」
デイオンの顔には狂気に染まっていた。
「どうやって俺を亡き者にしようか策略を巡らせていたのだろう!?だから先に手を打ってやった!腹をすかせた狼は予想外だったがな。だが、父上をたぶらかした下賎な女を始末できたのは幸運だったさ……!」
この世界には、同じ言語を使っているのに、言葉が通じない人間がいる。まるで話ができない相手がいる。パルスはそれをいま目の当たりにしていた。
「おまえは、俺からすべてを奪っていく……」
―――あの下賎な女が私から陛下を奪った。どうか母の恨みを晴らしておくれ。母の憎しみを晴らしておくれ。私の可愛いデイオン。可哀相なデイオン。あの母子が生きている限り、おまえが陛下に愛される事はないのだ。
突如として、デイオンの身体を虚しさが支配する。父がいなくなったいま、望みに望んだ王位はすぐそこにあると言うのに。この脱力感がなんなのか、彼自身理解できてはいなかった。
「そこまでよ!」
その声に、パルスはハッと階下を振り返った。そこには、キュラトスの首にナイフをあてがったジブリールの姿があった。
□◼︎□◼︎□◼︎
あらかじめ決められていたことのように、処刑準備は進んだ。広場に設置された絞首台は、太い縄を吊り下げていまかいまかと罪人の到着を待っている。絞首台の周りには噂を聞きつけてやってきた城下の人々で溢れ、その刑が開始されるのを待っていた。
なにしろ、絞首刑が公開されるのは久しぶりだ。また、どこぞの貴族がデイオンの機嫌を損ねたのだろうと民衆はタカをくくっていた。そこへ、罪人を乗せた車が到着する。
鉄格子のついた後ろの扉が開かれると、兵士に突き出されるように、その男は広場に姿を見せた。集まった人々はあっと息を呑んで真っ青になる。それはパルスだった。
パルスは目の前の絞首台を見上げてため息をついた。続けて、車から引きずり出されたキュラトスの姿に民衆はもっと驚いていた。一週間前には歓声の中コシュナンへやってきたマーテルの王子が、なぜこんなことになっているのか、野次馬の中のだれひとりとしてそれがわかる者はいなかった。
キュラトスは兵士に両脇を抱えられ、絞首台まで引きずっていかれる。ジブリールの執拗なまでの拷問であばら骨が折れていて、ひとりでは歩くことができないからだ。
パルスとキュラトスが絞首台へ移動すると、到着した車からデイオンが姿を見せた。彼は兵士に渡された書状を広げ、すうっと息を吸った。
「これより、リオルド・ジル・コシュナンを殺害した罪人を絞首刑に処す」
どよっと人々はざわめいた。
「法に従い、パルス・ノア・コシュナンおよび、キュラトス・ミオ・マーテル、2名の絞首刑を申し付ける。始めろ」
淡々とした調子で語られたデイオンの死刑宣告を受け、パルスの背中を兵士が押した。
パルス様と人々が口にする。処刑を止めろと口々に騒ぎ出す。だが、兵士に槍を向けられてしまえば黙るしかない。これでコシュナンは終わりだと口にする者もいた。
絞首台の上に上がると、パルスの顔にかぶせる黒い布を兵士が手にする。その顔は真っ青になっていた。できることならパルスを殺したくはない。兵士たちの心はひとつだった。だが、もうどうすることもできない。
「デイオン・マグナ・コシュナン王の名において、死刑を執行する」
黒い袋がパルスの頭に被せられる。それを見ていたキュラトスがハッと笑った。静まり返っていた広場にその声はやけに響いた。
「なにかおかしいか?」
デイオンが聞いた。
「……そりゃ、おかしいだろ」
キュラトスは顔だけをデイオンに向けた。
「おまえが王だと……?それは、だれが決めたんだよ……」
デイオンは表情というものが消え失せた顔でキュラトスを見た。兵士たちは顔を見合わせる。
「げほっ、げほっ」
しゃべると息ができない。身体の痛みを堪えてキュラトスは震える唇を動かした。
「おまえが殺した先王リオルドが、おまえを次の王にすると言ったってのか……?俺はその場にいたが、王は死に際にそんなこと言ってなかったけどな……」
ざわっと広場に集まった人々がざわめいた。
「戯言をッ!」
ジブリールが兵士の手から剣を奪い、キュラのもとへとそれを引きずっていく。
「おまえが王だと、いったい誰が認めた……?」
「黙りなさいッ!」
キュラトスの首を刎ねようとしたジブリールを、兵士が3人がかりで止めに入る。
「痴れ者め!おまえから先に処刑してやるわ!」
「……勝手に、国王面してんじゃ、ねえぞ」
ゼェゼェとキュラトスは荒い息を吐く。
「そんなに順番を変わりたいか?」
デイオンの言葉に、キュラトスは口の端に笑みを浮かべた。デイオンが兵士に指示を出すと、パルスが絞首台から降ろされ、黒い袋から顔を出される。代わりに両脇を抱えられたキュラが引き摺られるように段上へと上げられた。
(ここまでか……)
コシュナンに到着してから一週間ほど。長いようで短い日々だった。自分なりに慣れないことを頑張ったつもりではあったが、結果はこれだ。国を守るためならなんでもすると言うジグロードの姿勢はある意味正しかったのかもしれないと、キュラトスは自嘲気味な笑みを浮かべた。死ぬ直前にあんな男を称賛するなんて、いよいよどうかしていると思ったからだ。
キュラはどこまでも青い空を見上げ、ゆっくりと目を閉じた。そして、まぶたの裏に、空色のバンダナを巻いた少女の姿を思い浮かべる。
(生きて戻れよ……ハルヒ)
パンッと銃声が鳴り響いたのはそのときだった。続けて馬の嘶きが響く。空に向かって銃弾を放ったのは処刑場へ馬で駆けつけた女性だった。
「フォルトナ……!」
パルスが目を見張る。数人の騎馬隊を護衛につけ、凛とした表情でこの場へ駆けつけた王女に望みを託すがごとく、人々は彼女のために道を開ける。馬から降りると、デイオンとパルスの顔を交互に見たフォルトナは、腰に下げてあった書状を真っ直ぐに掲げた。
「リオルド・ジル・コシュナンが記した王印の書状を開封する!この場にいる者たちが立会人となり、真実をしかとその耳と目に焼きつけよッ!」
王印の戒めがフォルトナの手で破られる。青空の下、渇いた日差しの中、書状の内容をフォルトナは読み上げた。
「リオルド・ジル・コシュナンが亡き後は、パルス・ノア・コシュナンにその王位を譲ることをここに示す!」
自分の即位を認めない。父王の残した書状の内容にも、デイオンは反応を見せなかった。まるで穴が開いたかのような心を、渇いた風が吹き抜ける。父王が選んだのはやはりパルスだった。諦めの色を滲ませたデイオンとは違い、書状の内容にジブリールはその顔色を失った。
王印に勝る遺言はない。ワッと観衆が湧いた。だが、パルスの顔は晴れない。その訳は、デイオンのそばにいるジブリールが証明した。
「ラグーンの半数以上の承認がなければ王にはなれないわ!」
彼女の言う通りだった。コシュナンに寄り添うラグーンの承認がなければ、いかに王印の書状があろうと、パルスは即位することができない。
「デイオンは議会の承認を得ているわ!貴族が王にと望んでいるのよ!たかが王印を押した紙切れを恥もなく!フォルトナ、さがりなさいッ!」
姉の激昂にもフォルトナは微動だにしない。
「早く罪人を処刑しなさい!その生意気な王子の息の根を止めるのよ!」
いきり立つジブリールの隣で、デイオンは立ち尽くしていた。父が王印を使ってまで、パルスを王にと望んだ。すべてはデイオンを王とは認めたくないがために。
「デイオン!処刑を命じるのよ!」
「………」
「どうしたの!あなたがコシュナン王なのよ!さあ、殺しなさ―――!」
「させません」
フォルトナを護衛する騎馬隊の馬から、兵士に助けられながらひとりの少女が地上へ降りた。その真っ直ぐな視線は、逸らされることなく、デイオンを見つめている。
「ティア……」
デイオンがその名を口にした。
「承認します」
ティアが口にしたそれは、強い意志を持った言葉だった。ジブリールがヒクッと息を詰まらせた。
「我がマイスは、パルス殿下の国王即位を承認します」
ラグーンのうちのひとつ、マイスの即位承認がティアの口から公言される。よろりとジブリールは後ずさった。
「た、たかが一国の承認を得たくらいで……っ」
「国王指名の権限を持たない議会の承認を得たデイオンと、前国王の王印に、ラグーンの承認をひとつ得たパルスと、姉上はどちらが即位に相応しいと思われる?」
フォルトナの言葉に、ジブリールは持っていた扇子をミシミシと折り曲げていく。
「それでもこのコシュナンの王にはなれないわ!なれるわけがない!処刑を続けなさい!なにをしているの!続けろと……!」
ジブリールは自分の目を疑う。フォルトナの手にある銃が、こちらにその口を向けていた。
「姉上のおっしゃる通りです。ラグーンの半数以上の承認がなければパルスはコシュナン王にはなれない。ですが、ひとつでも承認があれば、パルスはすでに王位を継ぐかも知れない王子です。処刑などさせはしない」
たかだか19歳の小娘が発しているとは思えないほど、それは物凄い気迫だった。それに完全に圧倒されたジブリールはヘナヘナとその場に座り込んだ。
□◼︎□◼︎□◼︎
その後、召集をかけられたラグーンの代表たちは、揃ってパルスの即位を承認した。歴史上、一度もひとつになったことがない代表たちの意見が見事に一致したのは、デイオンよりはマシだろうと言う安易な考えから導き出された答えだったかもしれないが、それによりコシュナン王家を揺るがせた事態は収拾した。
パルスは傷が癒える間もないまま、新たなコシュナン王として即位した。そして、先王を殺害したデイオンと、それに関与したジブリールは投獄された。まだどんな刑罰がくだるかははっきりとはしていないが、王殺しは重罪だ。人々は片付けられない広場の絞首台を目にしては、いつこれにデイオンが吊るされるのかと囁きあった。
キュラトスがようやく目を覚ましたと言う知らせを聞き、パルスはすぐに彼のもとへ向かった。ノックも忘れたパルスが扉を開けると、キュラトスの部屋にはティアがいた。おっとパルスは足を止める。
「では、私はこれで……」
ティアは慌てて立ち上がろうとするが、パルスが要件はすぐに終わるからと引き留めた。そして、自分が殴り書きした書状をキュラトスに差し出す。
それは一枚の紙切れだ。だが、キュラトスが喉から手が出るほど欲しかった、コシュナンとマーテルの同盟協定を約束した書状だった。
「コシュナンはマーテルに全面的に協力し、スタフィルスの脅威に備えることを約束する」
そう言ってパルスは手を差し出した。コシュナンにきてまだ一週間ちょっとだ。だが、もう何年もここにいたような気がする。柄にもなく泣きそうになるのを堪え、キュラトスはパルスの手を握り返した。
キュラトスの同意を得たことを確認し、パルスはティアが用意した椅子に腰掛けた。
「で、だな。まあ、その……」
「なんだよ?」
キュラトスとパルスは年齢差もあるし。出会ってまだ日も浅いが、同等の立場で話すことができた。波長が合うのだろう。十年来の親友のような感覚がすでにあるのは、不思議であり、当たり前のようにも思えた。
その親友が、もごもごと言いにくそうに口を動かすので、はっきりしろとキュラトスは眉をしかめた。あー、とパルスはポリポリと頭を掻く。
「俺は別に要らないと思うんだが、議会連中が言うには、同盟ってのは婚姻関係で結びつけるのが定石だそうだ」
またそれかと、キュラは苦い顔を見せる。まさかもうジブリールと結婚しろと言われるわけではないだろうが、どうしても婚姻自体は避けては通れない道なのかもしれない。
「それでだよ。おまえに妹たちを紹介しようかと思ったんだが……、必要ないか?」
パルスはそう言って、チラリとティアを見た。
パルスが何を言おうとしているのかを理解し、キュラトスは首を振る。
「やめろよ」
デイオンは投獄されたが、ティアはまだ彼の妻だ。マイスの両親は早く離婚することを望んでいるようだが、決めるのは彼女だ。
「ま、ゆっくりでもいいから考えてくれよ」
「ああ……。そうだな」
相手はどうあれ結婚は必要だ。キュラトスとパルスの間では紙切れ一枚でも同盟は結べるが、国と国になればそうはいかない。
「俺がおまえを嫁さんにもらえれば話が早いんだがなあ」
「俺は男だ」
「面は可愛いのに残念だよ」
「おまえな。マジで怒るぞ」
「なーんで、おまえの姉ちゃんがマーテル王かね」
アイシスがマーテルの使者としてコシュナンに来ていればといまなら思う。パルスとアイシスの結婚。そして、キュラトスとコシュナンの王女のだれかが結婚すれば、待ち望んだ固い絆を結ぶことができる。
「婚姻関係で同盟を築くことを考えれば、王は男で、女は他国に嫁いで太いパイプ役になるのが世の常だろ。おまえ、なんか王になれない訳でもあったのか?」
もしかして、アレがすごく小さくて使い物にならないとか。冗談めかして口にしたパルスに、ティアは顔を赤らめた。
「ぶっ殺すぞ」
「理由を聞いてんだよ」
キュラトスはため息をついた。
「……アイシスを王にしたのは、水神があいつに宿ったからだ」
アイシスを王に押し上げて、国と言う重たい枷をつけさせて、彼女を守ろうと思った。だから、なんとしてもキュラトスはコシュナンとの同盟を結ばなければならなかった。
「それって……、もしかして神話の話をしているのか?」
「生憎とこの目で見た。神話でもなければ、あれは神と呼べる代物でもなかった」
水神は数分間でイニスの町を恐怖と混乱に陥れた。守護神と呼ばれる存在でありながら、マーテルの民を傷つけ、殺した。
「……コシュナンの雷神は?」
キュラトスは思い立ったようにパルスに顔を向けた。
「誰に宿っているかなんてわかるか?」
マーテルでも、ジグロードが死ぬまで水神が誰に宿っているかなんてわからなかった。そのため、キュラトスはパルスの答えに期待はしておらず、案の定彼は首を捻るだけだった。
「なんか決まった特徴でもあれば探してみるが」
「特徴?」
「その宿主に共通する印みたいなのないのか?」
「ないと思う」
「じゃあ絶望的だろうなあ」
パルスは天井を見上げて息を吐いた。
「コシュナンはマーテルと違って一夫多妻制で血族も多いし、ティアと俺だって血はえらく薄いが他人じゃない」
コクン、とティアは頷いた。ゴッドバウムが雷神の宿主を見つけるためには、この大きな大陸全てを焼き払う必要があると言うことだ。その命が尽きなければ、神は宿主から姿を現さない。それは、ここで口に出すことではないような気がして、キュラトスはそのまま押し黙った。
□◼︎□◼︎□◼︎
ティアのかいがいしい看護を受けながら、なんとか起き上がれるまでにキュラトスの傷が癒えるまでは、それからさらに数日がかかった。まだ完治には程遠いが、明日はやっとマーテルへ戻る船に乗ることができる。
同盟を知らせる使いは先に送っているが、吉報は自分でマーテルへ持って帰りたい。その気持ちがキュラトスを祖国へ急がせた。
そしてキュラトスがマーテルへ発つ頃、法に裁かれたデイオンもまた、ジブリールと共にコシュナンの地の果ての孤島へ送られることとなった。
「キュラトス殿下」
声をかけられて顔を向けると、淡いピンク色の花束を抱えたティアが顔を覗かせた。それは初めて彼女を見たときに庭園に咲いていた花だった。優しい笑顔を浮かべているティアはもう、デイオンに虐げられ、支配されていた少女ではなかった。
「またそんなに……」
花なんか持って来なくていいと再三に渡って言っているのに、ティアは毎日のように部屋の花を取り替える。だが、花瓶にはまだ昨日入れ替えたばかりの花が咲き誇っていた。
「まだ枯れてないだろ」
「これは贈り物にしてください」
「贈り物?」
「フォルトナ様は淡いお色がお好きだと聞きましたので」
「………」
明日マーテルに戻るキュラトスを、どうにかフォルトナと結び付けたいのだろう魂胆が見え見えだ。パルスが結婚の話を振った時、ティアは嫌だとは言わなかったが、言葉にせずとも拒否されているのはわかる。
はあっとため息をつき、キュラトスはティアの手から花束を奪い取った。パッとティアの顔が輝く。
「フォルトナ様は、さきほど南の庭園でお見掛けしました」
はいはいとティアに手を振って、キュラトスは庭園とは反対の方向へ歩いていった。
地下牢は昼間でも薄暗い。キュラトスは自分の足音だけが響く階段を、花束を抱えて降りていた。まだ交代の時間でもないのに、人が近づいてくる気配に気付いた牢番が、なにごとかとキュラトスに灯りを向けて慌てて頭を下げた。
「キュ、キュラトス殿下。こんな場所に―――ど、どうされました」
「中に入りたい」
「あ、あの、許可証などは……?」
「そんなもんない」
ここを守るのが牢番としての自分の役目である。困り果てた顔をする牢番に、ちょっとだけだからとキュラトスは頼み込む。牢番はしぶしぶとキュラトスを牢獄の中へ入れた。
冷たい石の通路をしばらく歩くと、ふふふふと笑い声が聞こえてくる。キュラトスは声のするほうへ目をやって、変わり果てた元婚約者の姿に絶句した。
この何日かの牢獄生活で、ジブリールは風船がしぼんだような姿になっていた。彼女は壁にもたれかかり、暗闇に向かってなにか話し掛けては、そこから応答を得たようにくすくすと笑っている。完全に気が触れてしまっていた。
「ジ……」
「やめておけ」
哀れな女に声をかけようとしたキュラトスを、向かい側の牢に入れられていた男が止めた。かける言葉が見つけられず、キュラトスは後ろを振り返った。そこにはデイオンの姿があった。
簡素なベッドの上に腰掛け、彼はキュラトスを見るわけではなく俯いている。王宮で権力を振るった面影はそこにはない。
「もはやなにも聞こえはしない」
感情の起伏のない声が石壁に響く。
「いつから……」
こんな状態に―――。
「さてな。ここにいると、日にちの感覚は消え去る。三度の食事が運ばれてくるのが、唯一時間を示しているが……」
くくっとデイオンは笑った。
「俺とくだらんおしゃべりをしに来たのではあるまい。なにをしに来た?」
顔を上げたデイオンは、キュラトスの手にある花束を見て、その美しさに目を細めた。日の光が入らない地下で、花などを見ることはない。淡く優しい色は、立ち上がれないほどに傷つけた少女の面影を映し出した。
「……結婚の承諾が欲しければマイスへ行け」
「は?」
「島送りになる罪人に妻はない」
やっとデイオンがなにを言っているのかを理解し、どいつもこいつもとキュラは眉を寄せた。
「ティアにそんな気はない」
「ではおまえにはあるのか」
「あるわけないだろ」
「正直になれ」
またデイオンは笑う。大人の余裕を見せ付けられたような気がしてキュラトスは内心おもしろくなかった。
「それとも、俺のお下がりは嫌か?」
「違う!違うけど……!ああもう!俺は明日マーテルに戻る!」
「それで別れの挨拶か。あんな目に合わされて、つくづくばかな―――」
「だから、リオルド・ジル・コシュナンの、息を引き取る寸前の言葉を伝えに来た」
デイオンの軽口がやっと止まる。硬直したその視線が、キュラの顔を見上げた。
「遺言だ」
「……来る場所を間違えている」
デイオンの口元に引きつった笑みが浮かんだ。最後の最後で、父親が自分に遺言など残すものか。父は王位をパルスに渡した。長兄で、長年そばに仕えた自分ではなく、弟のパルスに。
ずっと以前からわかっていた。父にとって、自分は邪魔な存在でしかなかったのだ。彼にはパルスさえいればそれでよかったのだ。
母の言葉を信じ、デイオンは自分が愛されるために、パルスを何度も殺そうとした。だが、それは間違っていた。消えなければならないのはパルスではなく、自分だった。
それを思い知れば思い知るほど苦しくて、どうにもならない憤りを、やはりパルスを求めた父王に向け、剣を手に取った。そして、この手で愛されるチャンスを叩き潰した。
「パルスに遺言はなかった。あったのかも知れないが、言葉になったのはこれだけだ」
―――すまな、かった。デイオン。
「おまえに悪かったと」
―――愛して、いる。
「愛している、と」
キュラトスの言葉と、母の言葉がデイオンの頭の中で響き渡った。
可哀相な子、おまえは愛されることはないんだよ。
「……嘘だ」
デイオンはそう呟いた。キュラは牢獄の鉄格子の前に花束を置く。
「俺の親父は救いようのない人間だった」
「………」
「同盟を結んだ国を次々と裏切り、裏でスタフィルスと手を組んで……。死んでも涙ひとつでなかった」
いまだに泣くこともできない。だが、それをもう薄情だとは思わなかった。
「だけど、おまえの親父は、死ぬには惜しい人だったぞ」
キュラは拳を強く握る。
「自分を斬ったおまえを……最期までおまえを愛してた……」
無残な死体だった。憎しみ合う息子たちをどうしてやることもできずに、老王は自分を責めて。斬り殺されても、仕方ないと思うほどに。
「嘘を言うな!」
デイオンは鉄格子の向こうにいるキュラトスの胸倉を掴む。ガシャンッと大きな音が鳴った。
「戯言を語っても騙されはせんぞ!父上が俺を愛していたはずはない!父上は母と俺を疎んじ、俺たちの側から離れていった!俺が憎いからだ!父上にはパルスさえいればそれでよかったのだ!」
「違う」
その声に、キュラトスとデイオンは顔を向ける。そこにはパルスとティアが立っていた。キュラトスがうまく花を渡せたかどうかが気になったティアがフォルトナにそれとなく聞いてみると、彼女はそんなものはもらっていないし、キュラトスは来てもいないと答えた。
忽然と姿を消したキュラトスに不安を覚えたティアは城内を探し回り、泣き出しそうになったところを、政務を放り出したパルスに見つかった。パルスは使用人や兵士にキュラトスの行方を尋ねて回り、ティアを連れてここへやってきた。
自分から隠れるように立っているティアから、デイオンは視線を逸らした。
「……なにが違う」
デイオンの言葉に、パルスは目を伏せる。
「母が死んだとき、父上は俺に何度も詫びた」
ハッとデイオンは鼻で笑った。
「それがなんだと言うのだ。父上がおまえに詫びたからなんだ?」
「許してくれと言われた」
搾り出すような声だったのを覚えている。昨日まで笑顔で生きていた人が、一晩で徐々に死んでいく光景に立ち会ったパルスは、ぼう然自失の状態ではあったが、確かにデイオンに殺意を抱いていた。
「母上の葬儀が終わればその足で、俺はおまえを殺しに行くつもりだった」
「………」
「父上は、たぶんそれを見抜いていたんだろうな。俺の腕を強く掴んで、すまないと繰り返した。許してくれと言う父親が、国内の混乱を恐れているのだと思ったから……俺は忘れようと決意した。憎しみも恨みも、コシュナンの存続のために。だけど、それは違っていたんだと思う。」
「……違うだと?」
「父上は俺に詫びているんだと思っていた。死んだ母に、すまなかったと。確かにそれもあったかも知れない。だが、いまになって思うよ。あれは、おまえのことを許してくれと言っていたんだ」
母を殺されたパルスに、それでも、デイオンを殺さないでくれと。本人もその矛盾には気付いていただろう。それでも、必死になってリオルドはパルスを止めた。
「おまえは証拠を残さなかったが、動機は十分あった。当時、議会はおまえを裁こうと進言したらしい。だが、父上はそれを受理しなかった。なぜか。その答えは、マーテルの王子が言った通りだ」
「戯言だ」
「かもな」
パルスは太い首を傾げる。真実を確かめようにも、すでにリオルドは死んでしまった。彼の謝罪の意味を正しく知る者はいない。
「なにもかも昔話だよ」
そう言って、パルスは背中を向ける。隠れ蓑を失ったティアが、俯いたデイオンの姿に、ぎゅっと胸の前で拳を握った。
「出て行け」
退去を命じる低い声に、キュラトスはティアの肩を押す。牢獄には、狂ったジブリールの笑い声だけが響いていた。
□◼︎□◼︎□◼︎
次の日の朝、デイオンとジブリールは北の孤島へ向かう船に乗るため、港の桟橋に移送された。ふたりのが誤送車から降りると、通りの集まった人々は石を投げて罵声を浴びせた。先のコシュナン王の殺害はもとより、パルスの母の殺害についての嫌疑が再燃したデイオンは、城下の人々の激しい怒りを一身に浴びていた。
傷だらけになりながら船へと乗り込むその姿を見ていたティアが、たまらなくなってフォルトナのそばを離れた。
「デイオン様!」
ティアの声にデイオンが振り返る。フォルトナが止める間もなくデイオンの側に駆け寄ったティアの頭に、誰かが投げた石が当たった。小さな悲鳴をあげたティアがデイオンの妻だとわかると、彼女を同罪と決め付けた男がその長い髪を掴む。フォルトナが銃を抜こうとしたが、その前にデイオンが枷のついた手でその男を殴り飛ばした。
「この野郎!」
激昂した人々がデイオンを袋叩きにしようと囲む。
「静まれッ!」
フォルトナの声と銃声が響き渡る。暴動が起こる一歩手前で、人々はデイオンとティアから離れていった。頭から流血し、涙目になっていたティアは、自分を庇った大きな背中にそっと手を添える。
「デイオン様……」
「……マーテル行きの船は、反対側の港だろう。急がねば出港に間に合わんぞ」
騒ぎがおさまると、駆けつけた兵士たちがデイオンをティアから引き離した。
「おまえとは離縁する。金輪際、俺とおまえはなんの関係もない」
背中を向けたままデイオンはそう言った。
「だから、おまえもどこへでも行けばいい。マイスに戻るも、好きな男のもとへ行くも、これからは自由に、好きに生きればいい」
デイオンの背中が遠ざかっていく。一度も振り返りはしない彼には見えないとわかっている。それでもティアは何度も首を振った。カタカタと震える唇が、小さな声でなにかを言っている。だが、それは出港の汽笛にかき消されて、誰の耳にも届かない。
「マーテルに来るか?」
そう言ったキュラトスの瞳は真っ直ぐにティアを見ていた。コシュナンと同盟を結ぶことに成功したキュラトスは明日、マーテルへと戻ることになる。今夜はコシュナンでの最後の夜だった。
その晩、最後の機会をと焦った議会は、キュラトスの部屋へティアを向かわせた。もう毒は飲むなよと、開口一番キュラトスはティアに念押しした。そして、なんの用だと聞かれても、真っ赤になって俯くことしかできないティアが、なにをしにここへ来たのかをキュラトスは察した。
国と国の同盟には、婚姻関係を用いるのが常だ。このままキュラトスがコシュナンのだれとも婚姻の約束さえせずマーテルへと戻ることは、古い考えを主張する議員たちには避けたい現実だった。キュラトスの年齢から考えても、あてがうのならコシュナン王家の血を濃く受け継ぐフォルトナが一番だ。だが、両者ともにお互いまったく興味を示さない。
仕方なく、議会はまだ脈がありそうなティアを選び、キュラトスのもとへ向かわせるしかなかった。デイオンとティアはまだ正式に離婚していないが、孤島へ送られるデイオンがどんなに強情を張ったところで、同盟国の王子がティアを娶ると言えば諦めるしかない。それだけ、キュラトスとデイオンには立場の差がついたのだ。
黙ったままなにも言い出さないティアの目の前までやってきて、キュラトスはずっと言おうと思っていたことを口にした。
マーテルに来るかという問いに対して、室内には沈黙が流れた。ティアの身体は動かなかった。頷こうとしているのに、ままならない。コシュナンのために、よりよい同盟関係のために、キュラトスが望むのなら彼と婚姻を結ばなくてはならない。それはラグーンといえども王家の血を引く者としての務めだと、議会から言われていた。
(どうして……)
どうして首を縦に振れないのだろう。こんなに優しい人が妻にと望んでくれているのに。どうして自分の目からは涙が零れ落ちるのか、ティアにはわからなかった。
キュラトスは息をつき、ティアの頭をがしがしと乱暴に撫でた。
「いい加減気づけよ。おまえは俺と結婚すんのが嫌なんだって」
「そ、そんなこと……っ」
「そんなことあるんだよ」
キュラトスは必死に言葉を探すティアの肩を軽く抱き締めた。決して踏み込んでこないその態度が、ティアの目にまた涙を溢れさせる。
「婚姻関係なんかなくても、俺はコシュナンとパルスを信じる。パルスもきっと信じてくれる」
「……キュラトス様」
「だからおまえも、おまえの信じた道を行け」
キュラトスはティアの額にそっと口付け、その背中をわずかに押した。
ティアは零れ落ちる涙を堪える。そして、フォルトナの制止を聞かずにデイオンのもとへと走った。
「デイオン様!」
聞いたこともないティアの大声に、デイオンが驚いた顔で振り返る。
「どこにも行きませんっ!」
はっきりと強い意志を持った言葉が響き渡る。
「私はあなたの妻です!あなたがここへ戻るまで、どこにも行きません!」
デイオンは自分の耳を疑った。
なぜそんなことが言えるのだろう。忘れたわけではないだろうに。この名ばかりの夫に、どんな酷い目に合わされたかを。
「あなたがお戻りになるのを、待っています……!」
「……なぜだ?」
デイオンはティアの気持ちがわからなかった。さっさとキュラトスについてマーテルに行けばいいものを、どうしてこんな所でモタモタしているのか。
「私はコシュナン神に誓いました」
「………」
「あなたを生涯に渡って愛すと、私は誓いました」
「……忘れろ」
「いいえっ」
「俺はおまえに愛されるような夫ではなかったはずだ!」
「人は変われます!」
いつもオドオドして、視線を合わすことのなかったティアの視線は、いまデイオンを真っ直ぐに見ていた。
「また、私たちはやり直せます、デイオン様……」
思う間もなく、デイオンの身体は動いていた。ティアに駆け寄る彼を止める者もいなかった。コシュナンの人々が見つめる中、一組の夫婦はしっかりとお互いを抱き締めあった。
「フラれたな」
パルスに背中を小突かれ、キュラはうるさいと言い返した。
「議会の画策も無に帰す、か」
パルスはおもしろがっているようにしか見えない。その軽口をこれ以上聞きたくはなかったので、キュラトスはさっさと船に乗り込む。桟橋の手すりに寄りかかったパルスは、フラれた男の背中をにこやかに見送った。
からかってはみたものの、パルスも本心ではこれでいいと納得できていた。心のない婚姻など、いまの時代には流行らないではないか。わざわざ血の同盟を結ばなくても、コシュナンとマーテルは理解し合い、協力し合っていける。キュラトスの人となりを見定めたパルスはそれを確信していた。
「ああ、そうだ。キュラ」
船が出港する汽笛を聞いてから、パルスは思い出したように手を打った。
「もうだいぶ前だけど、おまえとそっくりの奴を見たよ」
パルスの言葉に、キュラは自分の耳を疑う。だが、すでに船は桟橋を離れ始めている。
「!?」
(ラティがコシュナンにいた!)
「そいつはいまどこに!?」
「さあね!だが、フィヨドルへ行くとか言ってたらしいぞ―――!」
遠ざかる船に、パルスはなんとか自分の知り得る情報を伝えようとするが、船はどんどん遠ざかっていく。キュラトスはまだなにか叫んでいるが、もう声はここまで届かない。
もう一言、あれは危険だと伝えたかったが、無理なようだ。パルスはそこで諦め、キュラトスに大きく手を振った。これで終わった訳じゃない。これからコシュナンとマーテルは、あの侵略国と刃を交えることになる。王としての自分の仕事はまだ始まったばかりだ。
パルスの声が届かなくなると、キュラトスは操舵室に駆け込んだ。
「針路を変更してくれ!」
「いったいどうなされました」
「フィヨドルへ行く!船の向きを変えてくれ!!」
船長の顔色がさっと変わる。船員たちも顔を見合わせた。
「それはできません」
「命令だ!俺を降ろすだけでいい!」
「我々の役目は殿下を無事マーテルへ送り届けること。ご命令には従えません」
ぐっとキュラトスは唇を噛む。パルスがアキを見たのはきっと昨日や今日の話じゃない。すでにフィヨドルにいないことだって想定できる。だが、やっと得たアキの情報を耳にして、大人しくマーテルに帰るわけにはいかなかった。
それに、ハルヒもフィヨドルに行くと言っていた。一刻も早くふたりの首を掴んでマーテルへ引き戻したい。だが、この船ではだめだ。パルスが手配したこの船は一応戦艦ではあるが、戦争に行くわけではないため、戦える装備はほとんど積んでいない。
フィヨドル近海がどんな状況にあるかはわからないが、コシュナンの国旗をつけた大型船が彷徨いこんで無事に済むとは思えない。自分の我侭で乗組員全員を危険に晒すのは、上に立つ者としてやってはならないことだ。
「……わかった。悪かった。忘れてくれ」
キュラトスが納得し切れていない様子は見ればわかった。船長はキュラトスが下手な行動を起こさないように、船員たち全員に注意するよう伝える。脱出用の小船などにも見張りがつけられ、キュラトスの船室の前には何人もの見張りが昼夜問わずについた。それにも関わらず、キュラトスの姿は明け方には煙のように消えてなくなっていた。
□◼︎□◼︎□◼︎
広大な土地を持つ緑の国フィヨドルは、過ごしやすい風土から世界で一二を争う人口を長年保持し続けた強国だったが、いまそれも見る影もない。人の消えた森には腐葉土だけが何層も積み重なっていた。
闇に紛れてフィヨドルに到着したハルヒたちは、小さな入り江に船を隠し、黒獅子軍に見つかることなく国内に入ることに成功した。
入江から森に入ると、船から持って来た物資を分け合い、腐った木々が寄りかかるように並んでいる森の中で、ハルヒ、ナツキ、ココレット、カゲトラの4人は夜を明かすことになった。
野宿は初めてだ。一応は、今までどんな目にあっても屋根の下で眠っていたココレットは、腐葉土の上に直に寝転ぶことに抵抗があるようだった。
「ココレット」
ナツキは自分が来ていた上着を脱いで腐葉土の上に敷き、ココレットを呼んだ。
「この上で寝たら大丈夫だよ」
「だ、大丈夫よ」
ココレットが強がってそう言うと、ナツキはキョトンと目を丸くする。
「僕の上着、洗濯したから臭くないよ?」
「そ、そうじゃなくて……」
「無理すんな」
すでに寝転んでいるハルヒが目を閉じたままそう言った。
「無理なんてしてないわ」
「あっそ。トラ。2時間で起こせ」
「もっと寝ろ」
起こせよと念を押し、ハルヒはすぐに寝息を立て始める。
「まだ怒ってるのかなあ」
ナツキ、ココレット、カゲトラの3人はハルヒに黙って船に乗り込んだ。姉はそのことを怒っているのかも知れないと、ナツキはしょんぼり肩を落とす。
「もう寝ろ」
見張りのカゲトラがナツキの頭をポンと叩く。怒っているにしろ、そうでないにしろ、もう自分たちはここまで来たのだ。カゲトラにしてみても、ここでハルヒと別れるつもりは毛頭ない。
「ココレット。おいでよ」
ナツキに呼ばれ、ココレットはおずおずと彼の上着の上に腰をおろした。ナツキもそのすぐそばに横になる。そして、お互いになんの緊張もないまま寝息を立て出したのに、カゲトラは少々痛む頭を押さえた。
ナツキはここ最近でぐんと背が伸びた。声も低くなり、力も強くなった。そう―――彼は少年から男になりつつある。だが、中身はなんら変わらないのだ。だからココレットも警戒すら抱かずに、ぴったりと寄り添って眠っている。
だが、本人たちが自覚しなくても、周りで見ている者は頭を抱えることがある。このまま放っておいていいのだろうかと。ナツキの性格上、ココレットが泣くようなことにはならないとは思うが、油断はできない。なぜそう思うかは、カゲトラ自身が通ってきた道だからだ。
パチパチと燃える焚き火を視界に入れて、カゲトラは重い息をついた。―――アキラはこの国にいるのだろうか。まだ、生きているのだろうか。ハルヒはアキラが生きていることを、どこまで信じているのだろうか。
アキラの死を真っ向から否定することはできないが、カゲトラの胸には絶望感が渦巻いていた。確かに、あの時点ではアキラはスタフィルス研究機関のトップの研究員だった。だが、いまの研究機関の代表はヴィルヒム・ステファンブルグだ。あのときアキラにしかできなかったことも、いまでは違う。現に適合者はどんどん作り出されている。
ざざっと腐った木々の葉が揺れる。カゲトラが森の中に異様な気配を感じたと同時に、熟睡していたはずのハルヒが飛び起きて、胸に抱いていた銃を構える。
「起きろッ!」
ハルヒの怒鳴り声に、ナツキとココレットがガバッと身を起こす。
ぱあんっ!
「きゃあ!」
焚き火の炎が燃え上がった。悲鳴を上げたココレットを、ナツキが自分の背中へ回す。
しゅっ!
「ぐっ!?」
カゲトラがくぐもった声を上げる。その首に刺さっている吹き矢に気づき、ハルヒはすぐさまそれを抜くが、カゲトラは身体を痙攣させて腐葉土の上に倒れ込んだ。
(毒……!?)
周りの木々に隠れて吹き矢を撃ってきた。ハルヒは自分の周りすべてに銃を向けるが、標的が絞れない。
短い息を吐き、ココレットが倒れる。続けてナツキも腐葉土の中に沈んだ。このままでは全滅だ。ハルヒは暗い森の中を睨み付け、そこにわずかな光が煌いたのに気づく。
その瞬間、飛んできた吹き矢をしゃがんでかわすと、ハルヒはそこへと走り込む。ざざっと腐葉土がこすれて音を鳴らす。
「逃がすかよっ!」
逃亡を図った吹き矢の主にとび蹴りを食らわし、ハルヒはその後頭部に銃口を突きつけた。
「何者だ!」
「く……!」
「答えなきゃ脳みそぶちまけ……!」
後頭部にピリッとした痛みを感じてすぐ、ハルヒの身体から力が抜ける。敵はひとりではない。それはわかっていたのに、油断した。
「ラウル。大丈夫か?」
腐葉土を踏み締めて男が近づいてくる。
「おっせえんだよ、クロノス!」
「悪かった」
クロノスと呼ばれた男は、ラウルと呼んだ男に素直に詫びて、倒れているハルヒを手に持っていたライトで照らした。そして息を呑む。普通ならばすでに意識を失ってもおかしくないのに、射殺すような目でハルヒに睨みつけられたからだ。
「こいつら何者だ?」
「さあな。見たところ、スタフィルス兵ではないようだが……。ちょっと待て。まだ子供じゃないか」
ふたりのやりとりが遠くなっていくのは、距離が離れているのではなく、意識が遠のいているからだ。そうわかってはいても、ハルヒは閉じていく瞼の重みに逆らうことができなかった。
□◼︎□◼︎□◼︎
アキラのことはアキに聞け。ヴィルヒムはハルヒにそう言った。だが、アキはアキラのことを知らないと言った。確かにあのとき、父の名を口にしたのに。
スタフィルスから亡命するときは、アキの心はハルヒのすぐ近くにあった。ハルヒはアキとの間にある信頼関係を感じていた。だが、マーテルに到着してしばらくして、アキがバルテゴの王子だったということがわかってからは、すれ違いが続いた。そして、アイシスが水神を宿してからは、アキは彼女に寄り添うため、ハルヒのそばから離れていった。
「……クサナギ」
何度呼んでも、アキは振り返らない。振り返らずに闇の中へ消えていく。伸ばしたハルヒの手は何も掴めずに落ちた。
「ああ良かった。気がついた」
「!?」
声をかけるまで、すぐ隣に人がいることに気づかなかった。驚いて飛び起きたハルヒは、そこが腐葉土でないことにも気づく。声をかけてきたのは黒髪の男だった。一瞬、アキかと思ったハルヒは自分自身に舌打ちする。どうやらテントの中のようだが、視界が届く範囲にナツキたちの姿はない。
「仲間はどこだ!」
ハルヒは男から視線を逸らさず、何か武器がないかを探すが、逆に男はハルヒを見ないように顔を背けた。その様子に、ハルヒはようやく自分が下着しか身につけていないことに気づいた。
「……っ」
ハルヒはまともに動揺する。相手の男も半裸だった。
「ええと……、色々と説明があるんだが、まずは名乗ろう。俺はクロノスだ。きみは?」
上着も靴も脱がされて、武器になるものはすべて奪われている。ハルヒにしてみれば自己紹介どころではなかった。ハルヒはシーツを掴むと、クロノスと名乗った男に思い切り投げつけ、そのままテントの外へと飛び出した。
ハルヒが姿を見せると、テントの周りにいた男たちの目がいっせいに彼女へ向けられた。突然テントから下着姿の女が姿を見せれば、だれだって驚いて目を向ける。ハルヒは足を竦ませた。周りは敵ばかりだ。
「ちょっと待って―――」
服を着ながら追って来たクロノスが伸ばした手を、ハルヒは振り向き様にはねつける。そして間髪入れず、握りしめた拳で殴りかかった。まともに顔を殴られたクロノスの姿に、ギョッとした男たちは思わず武器を手に立ち上がった。
「大丈夫だ!」
一気に緊張状態になったその場にクロノスの声が響く。
「手を出すな」
クロノスは周囲を牽制すると、自分を睨みつけて威嚇してくるハルヒに歩み寄り、そして深く頭を下げた。
「まずは無礼を詫びたい。すまなかった」
「………」
「痺れ針が効き過ぎたんだ。きみの体温が急激に下がったため、俺の体温で温めた。フィヨドルの神に誓って、それ以上のことは何もなかったと誓える」
「……テメェ、何者だ」
どうも様子がおかしい。周囲には多くのテントが設置されているが、ハルヒの目にはそこにいる男たちが黒獅子軍やアメストリアの軍の人間には見えなかった。
「俺はフィヨドル第三特務部隊隊長。クロノス・エイベルジュだ」
「フィヨドル……特務部隊……?」
「きみは?スタフィルス人には見えるが……」
兵士ではなさそうだと、クロノスは聞いた。
「俺は……ハルヒ・シノノメ。スタフィルス人だが、兵士じゃねえ」
「どっちかと言えばゲリラだろうな」
そう言った赤毛の男が前に出てくる。それは、ハルヒが森の中で飛び蹴りを食らわせた男だ。彼はクロノスより幾分か若く見えた。
「この猛獣女」
「吹き矢野郎……!」
ラウルの姿を見たハルヒは、倒れた仲間のことを思い出す。
「あいつらはどこだ!?」
クロノスとラウルは顔を見合わせる。
「俺の仲間はどこだ!」
「彼らは本拠地へ移ってもらった。きみだけはさっき言ったことが理由で動かせなくてね」
「尋問してんだよ」
ラウルが言った。
「スタフィルス軍の手の者かどうか調べる」
「俺たちは違う!」
「どうだかな。口先だけならなんとでも言える」
「やめろ。ラウル」
クロノスに止められたラウルはハルヒに向かってベッと舌を出す。
「彼らは無事だ。本拠地で質問はされているだろうが、スタフィルス軍ではないのなら、我々は危害を加えたりしない。それは約束するよ」
「……本拠地って?」
「これからきみにも来てもらおうと思っている。ゆっくりするというわけにもいかないが、きみの話も聞きたいしね」
クロノスの落ち着いた口調を聞いていると、不思議とハルヒの気分も落ち着いてくる。やっと少しは緊張を解いた様子のハルヒにクロノスは自分の軍服をかけると、まずはテントへ戻ろうと促した。
クロノスとハルヒがテントの中に戻ると、そこにラウルも付いてくる。クロノスは肌を合わせて身体を温めるために脱がせた服をハルヒに返した。
「フィヨドル特務部隊って……なんだよ」
背中を向けた男ふたりに、着替えながらハルヒは聞いた。
「簡単に言えば、フィヨドル兵の生き残りだ」
「!?」
ハルヒは目を丸くした。フィヨドル人は全員殺されたか、研究機関の実験体にされていると思い込んでいたからだ。
「その顔は信じた顔か?」
「え?」
「俺らがフィヨドルの生き残りだって信じた顔かって聞いてんだよ」
「だって、いまおまえがそう言って……」
「単純だな。ばか女。証拠もないのに信じやがって」
「ラウル」
よほどハルヒに蹴り飛ばされたのが気に入らないらしく、事あるごとに突っかかろうとするラウルにクロノスはため息をついた。
「おまえがスタフィルス軍じゃないってのも、こっちは信用してないってことだよ」
「彼女はスタフィルス軍じゃないよ。マーテルから来た」
ハルヒはクロノスを振り返った。ハルヒはマーテルの名前を口にしてはいない。クロノスは自分の首を指差す。ハルヒはそれにつられたことで、自分の首からチェーンでぶら下げている指輪を思い出した。それは、マーテルを出発する前にキュラトスがくれた、彼の王位継承権を示す指輪だった。
「マーテルの紋章入りの指輪だ。少なくとも、俺はそれをスタフィルス軍の人間が持っているとは思えない」
「おまえ何者だ?」
マーテルの紋章入り指輪なんて、だれでも持っているものじゃない。しかもキュラトスの名前入りだ。スタフィルス軍ではないだろうが、ラウルは単純に、ハルヒが指輪を持っている理由が気になった。
「………」
ここでマーテルから来たと正直に言えば、どうなるかとハルヒは必死に考える。クロノスとラウル、そしてテントの周りにいる男たちはフィヨドルの兵だ。フィヨドルはマーテルと手を組んではいなかったが、彼らがマーテルにどういう感情を抱いているかはわからない。返事ひとつでこの状況が良いようにも悪いようにもひっくり返る可能性がある。下手なことを言えば、自分どころかナツキたちの命まで危ないことをハルヒは理解していた。
「当ててやろうか?盗んだんだろ。それか流れ着いた盗品を手に入れた。そんなところだろ」
「そうなのか?」
「……も、貰ったんだ」
どの答えが正しいのかわからず、ハルヒは本当のことを口にした。それが良いか悪いかなんてわからない。わからないのなら、嘘をつくことはやめた。
「貰った?」
「正確には、貸してもらった。マーテルに戻ったら返すつもりだ」
「だれに?」
「……キュラトス。マーテルの王子に」
クロノスとラウルは顔を見合わせる。
困ったときは自分の名前を出せ。キュラトスはそう言っていた。頼むと、ハルヒは心の中で必死に祈る。
「マーテルの王子の知り合い?」
「指輪を持っている理由にはなる。それに、入江に隠してあった船もマーテル製だった」
クロノスはハルヒの答えに満足そうな顔を見せた。選択はこれで間違っていなかったのか、ハルヒはふたりの出方を伺った。
「きみは、ここがいまどんな場所か知らないわけではないだろう?」
「……ああ」
フィヨドルはゴッドバウムによって滅ぼされた。王城には巨大な花の姿をしたフィヨドル神が現れ、市外に毒粉を撒き散らした。
「わかっていてなぜ、まだ安全なマーテルからフィヨドルへ来たんだ?」
「……父親を探してる。スタフィルス研究機関にいるかもしれないんだ」
ラウルはあからさまに嫌な顔をする。クロノスの表情も暗かった。スタフィルス研究機関に対する思いはハルヒだって同じだ。できることなら自分から関わりたいなんて思わない。だが、そこにアキラがいるとなれば話は別だ。カゲトラは、アキラはもう生きてはいないと思っているが、ハルヒはまだ一縷の望みを捨てきれずにいた。
クロノスは納得いかない顔をしたラウルに頷き、まずはナツキたちがいる本拠地へ行こうとハルヒに提案した。
□◼︎□◼︎□◼︎
黒獅子軍はフィヨドル神を殺した後、フィヨドル国内でその適合者となるべき人々を探した。捕虜にされたら、死よりもむごたらしい目に合う。どこからかそんな噂が流れて、フィヨドル人は自害の道を選び出した。やがて黒獅子の矛先は小さな農村地区にまで迫った。
ある村の男たちは老人や女、子どもたちを村の外へ似がした。森へ逃げた女たちは、クロノスが率いる部隊と出会い、急いで村に戻ったが、男たちはもうどこにもいなかった。
クロノスは悲しみにくれる彼らを連れ、森の中に匿うことを繰り返した。そうすることでその人数はどんどん増えていった。
現在、黒獅子軍は白獅子軍と睨み合っているため、一時的に追手はかかっていなかったが、それも時間の問題だ。膠着状態がいつまで続くかの保証はない。どちらかの軍が動けば、フィヨドルはまだ戦火に包まれる。その前にクロノスたちは行動を起こさなければならなかった。そんなときに現れたのがハルヒたちだった。
「姉ちゃん!」
クロノスに案内されたテントに入ると、そこには食事中のナツキ、ココレット、カゲトラの姿があった。走ってきた弟を受け止めると、ハルヒはホッと胸を撫で下ろす。ナツキたちに乱暴されたような様子は見えなかった。
「弟か?似てねえな。じゃあこいつが親父か?」
ラウルがカゲトラを顎で指す。
「父親を探しに来たっつってんのに、こいつなわけあるか。テメェばかかよ」
「なんだと!」
ハルヒとラウルの相性は最悪だ。何度目だろうかと思いながら衝突するふたりを止めると、クロノスはカゲトラにすまないと謝った。ラウルは腐葉土を蹴り払い、ふてくされてその場を後にする。
「頼りになるやつなんですが、まだ若くて」
クロノスの言う通り、ラウルはどう見ても、10代後半にしか見えない。対して、クロノスは30代前半の落ち着いた雰囲気を見せていた。
「あんたがここの隊長なんだって聞いたが?」
「クロノスです。行ってしまった彼はラウル・ティヴォ。昨夜の非礼をお詫びします」
「まあ、だいたいの事情も聞いている」
この集団がどうやって集められたかということなどを。カゲトラはすでに聞いていた。こちらから聞かずとも、ハルヒが無事かどうか聞くと、世話をしてくれた女たちが自分たちから話してくれたそうだ。
「それなら話が早い。それで、これは提案なのですが……」
クロノスがそう言いかけたとき、テントの中から幼い少女が飛び出してきた。
「クロノス!」
5歳ほどの少女は、クロノスの姿を見つけると彼に飛びついた。
「ロクサネ」
クロノスは少女を抱き上げギュッと抱きしめる。ロクサネと呼ばれたのは、茶色がかった髪に、くりくりとした丸い目をした可愛らしい少女だった。
「クロノス。ロクサネ、かしこくまってたよ」
「そうか。偉いな」
ふたりの様子を見ていたハルヒは怪訝な顔をした。
「おまえの子か?」
まさかとクロノスはそれを否定して、丁寧な手つきでロクサネを下へ下ろした。
「俺はこれから大事な話をしなくてはならないから、あっちで遊んでいてくれるか」
「えー、つまんない。クロノスとあそびたいよ」
「ロクサネ」
静かな口調でクロノスがたしなめるようにそう言うと、ロクサネは口を尖らせてその場を走り去り、数人の女性がそれを追いかけていった。
クロノスはハルヒたちをテントのひとつに案内した。中に入ると、そこにはフィヨドルの地図が広げられていて、海岸線に大きな赤丸がつけられていた。
「現在位置はここです」
クロノスは赤丸との反対側の海岸を指す。
「そして、ここが黒獅子軍のフィヨドル前線基地です。きみの言う研究機関もここにある」
そして、国境線を挟んだスタフィルス側でそれと睨み合っているのがアメストリアの白獅子軍だ。その数は2万を超えるらしいとクロノスは言った。
「戦闘は起こっているのか?」
「小さな小競り合いのようなものなら、数度。最新の戦況では黒獅子軍が勝利しましたが、おそらく、また白獅子は押し返してくるでしょう」
「なぜわかる?」
「これまでもそうでした。幾度となく黒獅子に打ちのめされても、すぐに人員を補充して見事に態勢を立て直す。白獅子の軍は、一度このフィヨドルの大地に足を踏み入れたこともあります。まあ、わずか一週間で後退しましたが」
アメストリアを王位に押し上げたのは、彼女を守ってきた王宮騎士団だ。白獅子軍はそれを根に形成されている。だが、その騎士の数は多いとは言えなかった。クーデターが成功したのも、ヘリオス大佐の裏切りがあってこそだった。カゲトラには疑問だった。黒獅子の正規軍を相手に、アメストリアのどこにそんな力があるのか。
「疲れを知らない軍。俺たちの中には白獅子の軍を不死軍と呼ぶ者もいます」
「不死……」
死なない人間などいない。だが、クロノスたちにそう思わせるものがアメストリアの軍にはあるのだろう。
「俺は蛇女って呼びたいけどな」
アメストリアを何かに例えるのなら、獅子でも不死でもなく、ハルヒにとっては蛇だった。
「なぜだ?」
「蛇みてえな女だからに決まってんだろ」
「本人に会ったことがあるのか?」
「何度かな」
ハルヒは王族に縁があるようだ。だが、ハルヒたちはスタフィルス人だ。そういう機会もあったのかもしれないと、クロノスは自分を納得させた。
「それで、おまえらの目的は?」
「………」
「黙るなよ。それを話すためにここまで連れてきたんだろ」
クロノスは頷く。
「あくまでもこれは……提案なんだ。そこは誤解しないで欲しい」
「前置きはいい」
「俺たちをマーテルへ亡命させて欲しい」
ハルヒは胸にあるキュラトスの指輪をぐっと握った。ここに集まっている人々は兵士じゃない。戦える者はクロノスやラウルという一部の者たちだけだ。いつか黒と白の軍の均衡が崩れたなら、どちらかの正規軍が攻めてくる。それに太刀打ちできる力が彼らにはない。
「その代わり、俺がきみの父親を探す手伝いをする。現在、黒獅子軍が使っている軍施設は、もともとフィヨドルのものだ。内部構造にも詳しい。俺はきみに貢献できるはずだ」
ハルヒとカゲトラは顔を見合わせた。
フィヨドル人のマーテルへの亡命。言葉にするには容易いが、それを承諾する権限などハルヒにはない。クロノスもそれはわかっている。それに、マーテルとフィヨドルは同盟国でもない。だが、マーテルの王子の指輪を持つ彼女という存在に希望を見た。
「きみたちの中のだれでもいい。どうかマーテルへの橋渡しになってくれ」
ハルヒは胸の前で腕を組んだ。すでにその頭の中では、だれをフィヨドル人と船に向かわせるかを考えていた。自分自身はもちろん軍施設へ向かう。カゲトラも戦力に欲しい。残るはナツキとココレットだが、彼らも本人の意思で船に乗り込んできたし、それぞれ目的もある。ナツキを説得するかと、ハルヒは振り返った。
「私がこの人たちを連れて戻るわ」
そう言ったのはココレットだった。それは意外な立候補だった。
「だっておまえ……いいのか?」
ココレットは頷く。
父親を止めようと躍起になってはみたが、実際は足手まといで、迷惑をかけてばかりだ。隠れて船に乗り込んで、強引に連れて来てもらっても、何の役にも立っていないことがココレットは苦しかった。
せめてフィヨドルの人たちを無事に船まで案内することができたなら、ここまで来た意味もあるかもしれない。そう思った。
「だったら任せるぞ」
ハルヒは、メアリーのように過保護にココレットを慰めたりはしない。背中を押されたココレットはもう一度はっきりと頷いた。
クロノスたちは、すでに全員が乗れるだけの船を用意していた。あとはマーテルの入国許可だけだったが、それに光を当てたのが、他でもないハルヒが持っていたキュラトスの指輪だったというわけだ。
ハルヒは首からキュラトスの指輪を外すと、ココレットの胸にそれをかけた。これがマーテルへの通行証になるのなら、自分が持っているよりはココレットが持っているほうがいいと考えたからだ。
□◼︎□◼︎□◼︎
「おまえは皆とマーテルへ行ってくれ」
夕刻過ぎ、クロノスはラウルにそう告げた。
「……おまえまで行く必要あんのか?」
ラウルの機嫌は悪い。彼がピリピリしているのは、ハルヒたちが現れてからではなく、フィヨドルが戦火に巻かれてからずっとだ。ラウルはまだ若いが、彼は誇り高きフィヨドルの騎士そのものだった。
「敵の本拠地だぞ」
「それが約束だ」
フィヨドル人をマーテルへ亡命させてくれること。それと引き換えに、クロノスはハルヒを黒獅子の軍施設へ案内する。
「騎士が一度誓ったことを破ることは恥だしな」
「そうやって騎士道を唱えた奴が全員無駄死にしたのをもう忘れたのか?」
清廉潔白な騎士の中の騎士と言える男たちは、フィヨドル城に咲いた毒花に殺された。クロノスとラウルも、もう少し脱出が遅れていたら同じ目に遭っていた。世間一般的には騎士にあるまじき腰抜けと蔑まれようと、生き残っているのはあのとき騎士の矜持を捨てたからだ。
「城から落ち延びた時点でもう騎士とは言えないだろ」
「あれは王命だった。騎士なら逆らえない」
あの日逃げたことで、ラウルはずっと騎士である自分を恥じている。彼の苛立ちのそもそもの原因はそれだった。
「ロクサネを頼む」
クロノスはラウルの肩を引き寄せて最後の別れにしようとしたが、彼はそれを拒否して首を振った。
いくらだめだと言った所で、クロノスは一度決めたことを覆したりはしない。この口論自体が無駄なのだ。どうせ、クロノスの言う通りにするしかない。その結果、彼がスタフィルス人と死ぬことになったとしても、ラウルにそれを止める力はなかった。
クロノスが行くと言うのなら、ラウルはロクサネのそばにいなければならない。命に代えても彼女を守らなければならない。まだ幼い彼女をひとりにするわけにはいかない。
「後から追いつくよ。マーテルで待っていてくれ」
クロノスはそう言うが、それはきっと無理だ。ラウルは黒獅子の恐ろしさを知っていた。
□◼︎□◼︎□◼︎
その夜のうちに、フィヨドルの人々は荷物をまとめ、明朝に船を隠している入江へ出発することになった。
重要な役目を担うことになったココレットは、ハルヒから預かったキュラトスの指輪をぎゅっと握った。
移動を始めた人々の中にはラウルとロクサネの姿もあった。出発してすぐ、歩けないと抱っこをせがんだロクサネを、ラウルは無言で抱き上げた。
「ねえ、クロノスはこないの?」
「後から来る」
「うそよ。こないんでしょ?」
幼いなりに、なにかこの別れに思うところがあったのかも知れない。ロクサネは口を尖らせる。
「来るって」
傍目から見ても、ロクサネはラウルよりクロノスに懐いている。国が滅ぼされても騎士らしくあることに躍起になるラウルよりも、年齢的にも現状を正しく判断しているクロノスのほうが、自分を大きく包み込んでくれることがわかっているからだ。
「クロノスには、ロクサネよりだいじなことがあるんでしょ?」
「そんな用あるわけねえだろ」
ロクサネよりも大切なものは、もうどこにもない。守るべき者はもうこの小さな女の子ひとりだけだ。
「みんなきらい」
ロクサネが言った。
「おとうさまも、おかあさまも、すぐにくるって行ったのに、ぜんぜんこないんだもん」
「………」
ラウルは何も言えなかった。実際、ロクサネの言う通り、彼らは二度と娘のもとへは帰らないからだ。ラウルだって、あの日偶然ロクサネの護衛任務についていなければ、いま頃ここにはいなかった。
正規軍と共に侵略者と戦いたい。そんなラウルの願いは王に聞き入れられることはなかった。ロクサネは、末娘だけは命にかえても守ってくれ。それがフィヨドル王の最後の命令だった。彼らに託されたロクサネを抱いて、ラウルは腐葉土を踏み締めて歩いた。
入江が見えたぞ。先頭からそんな声が聞こえてきた。人々が安堵の声を漏らす。あとは船に乗るだけだ。全員が森を抜け、最後の難関である岩場を進む。ラウルとロクサネが入江の入り口へ差し掛かろうとしたとき、先頭を歩いていたココレットが逃げてと叫んだ。直後、空に向かって一発の銃弾が放たれた。
動くな!その声は響いた。ときに言葉は強い抑止力となる。驚きと困惑で動けなくなったフィヨドル人たちの前に現れたのは黒獅子軍だった。
入江に向かうにはルートがふたつあり、ココレットたちは兼ねてから潜んでいた森を抜けた。そのほうが発見される可能性が低かったからだ。黒獅子軍は街道をやってきたのだろう。その背後には森では木々が邪魔して乗ることができない何台もの軍用車が見えた。
フィヨドルの人々に向かって銃を構える兵士たちの中からひとり、白衣を着た男が姿を見せる。ココレットが小さく息を呑んだ。
それはヴィルヒムだった。彼は水神の一件以来姿をくらませていた。フィヨドルに戻っていたのなら、マーテルでいくら探しても見つからないわけだ。ヴィルヒムはコホンと咳払いをして、身を寄せ合う人々を見回した。
「正直、ここまでたくさんの人々がまだ隠れているとは思っていませんでした。それはともかく、ごきげんよう、フィヨドルの皆様。私はスタフィルス研究機関代表、ヴィルヒム・ステファンブルグです」
ラウルは全身の血が凍りつくのを感じ、ロクサネを抱きしめる。ロクサネはそれを嫌がったが、ラウルはそれどころではなかった。
ヴィルヒムは身を寄せ合う人々を見回した。
「フィヨドルの姫君、ロクサネ様はいらっしゃいますか?」
ラウルに強く抱きしめられたロクサネが痛いと文句を言う。
「静かにしろ……っ」
人々は自然に、ラウルとロクサネへ顔を向ける。だいたいの目星をつけたヴィルヒムがロクサネを特定しようとしたそのとき、ココレットが勢いよく立ち上がった。
ヴィルヒムたちの目と銃口はいっせいにココレットへ向く。
「これはこれは……、ココレット様ではありませんか」
「……っ」
「こんなところでお会いできるとは思っていませんでした」
「わ、私も……です……!」
ココレットが何者なのかは知らないが、彼女がヴィルヒムの気を逸らすために立ち上がったのだと言うことはラウルにもわかった。
「ところで、ロクサネ様がどちらにいらっしゃるかをご存知ですか?」
「いいえ……!そんな人は知りません……!」
「それはおかしいですね。確かにこちらにフィヨドルの姫君がいらっしゃるはずなんですよ。ねえ?スパイさん」
ヴィルヒムに話を振られたのは、ラウルの隣で震えていた男だった。さっきまで震えていたその男は、何事もなかったかのように立ち上がり、ラウルの手からロクサネを奪おうと手を伸ばす。その喉をラウルのナイフが切り裂いた。
悲鳴の中、噴き出した血が、ラウルとロクサネを含む周りの人々を真っ赤に染める。
「彼女がロクサネ様ですね」
ラウルの腕に抱かれた少女を確認し、ヴィルヒムは兵に指示を出す。
ラウルはようやく泣き出したロクサネを抱え直し、近づいてくるスタフィルス兵相手にナイフを構えた。この命尽きるまで王のために戦う、それが騎士道だ。
「フィヨドルの騎士ですか」
ヴィルヒムは珍しいものを発見したように手を叩いた。
「まだ生き残りがいたとは……。なかなかしぶとい」
ロクサネを奪おうとする兵士たちを近づけないよう、ラウルはナイフを振り回す。だが、ずっとその体力が続くわけではない。弱るのを待てばいいとだれもが思っていたが、ラウルの虚勢は時間をかけることなく、1発の銃声によって簡単に終わりを迎えた。
「あ……」
胸に空いた穴から血が流れ出す。ヴィルヒムの手にした銃から、白い硝煙が立ち昇るのを視界に入れながら、ラウルは膝をついた。
(……だれか)
ラウルは怯えるだけの人々を見回す。
(だれかロクサネを連れて、走ってくれ……)
黒獅子軍の手が届かない所へ。そうラウルが願っても、だれもその手を伸ばそうとはしない。ロクサネを庇えばラウルのように撃たれることがわかっているからだ。
(どいつもこいつも……)
ラウルは自分にすがりつくロクサネの首に、腰の短剣を押し当てた。
(逃げられないのなら、いっそ……)
小さな身体が震える。やめて欲しいとその目が訴える。
ヴィルヒムの目的はわかりきっていた。彼はフィヨドル王家唯一の生き残りであるロクサネを実験体にするつもりだ。砂の侵略者の玩具にされて、苦しめて死なせるくらいなら、この手で殺してやったほうがいい。
「だめッ!」
飛び込んできたココレットがロクサネを抱きしめ、ラウルの手はびくりと止まる。
「だめ……!」
「ゴボッ!」
大量の血を吐き出したラウルが崩れ落ちた。
彼女に手を伸ばす兵士をココレットがキッと睨む。そんな彼女からフィヨドル人たちは距離を取った。
「ココレット様は、なにか勘違いをなさっておいでのようだ。まさか、ご自分にまだリュケイオンの権威があるとでも?」
「………」
「スタフィルスの内乱に巻き込まれたのか、どうしても行方のつかめないあなたを諦めた将軍は、死体のない葬儀を執り行いました。あなたはもうこの世にない存在なのです。いま頃になって亡霊がノコノコ出てきてはいけません」
―――父親に愛されていないことくらい知っていた。彼とは生まれてから数えるほどの会話もなく、ココレットは将軍としてのゴッドバウムしか見たことがなかった。黒い獅子の旗を背負う男は、父であって父ではなかった。
彼に愛してもらいたいと思ったことはある。気を引こうと着飾ってみたり、気に入られようと頑張ったこともあった。だが、そんなココレットに、父からかけられた言葉は残酷なものだった。
―――おまえもマリアベルにはなれない。
ヴィルヒムは構えた銃でココレットの眉間を狙う。
「では、亡霊は亡霊らしく、在るべき場所に帰っていただこう」
そのとき、入り江で爆発音が響いた。
ヴィルヒムも、ココレットも、獅子軍も、フィヨドルの避難民も、全員の目が燃え上がる入り江から姿を見せたひとりの男に釘付けになる。
「……お兄様」
たったひとりの男の登場でその場は静まり返った。ルシウスはスタフィルスの軍服を着ているが、彼がもう軍人ではないことは、フィヨドル基地に所属する黒獅子の兵士なら誰もが知っていた。その恐ろしさも。
自然に兵士は動揺し、戦う前から足を退く。ルシウスが炎神の力に適合した際、その力でフィヨドルの研究施設を滅茶苦茶に破壊した事実はまだ記憶に新しかった。
「……ようやく見つけた」
フィヨドルでもマーテルでも逃げられ、やっと再びこの地で見つけることができた。ルシウスの身体は歓喜に打ち震えていた。握り締めたその拳に炎が宿る。その熱気はかなり離れているココレットにも伝わった。
「やっと殺せる……」
ルシウスはそう言うと、ヴィルヒムへ向かって砂浜を走る。彼を止めようと何発もの銃弾が放たれるが、どれも彼に当たることはなかった。彼が身体にまとっている炎がすべての弾丸を溶かしてしまうからだ。
ヴィルヒムの護衛兵はまばたきの間に黒焦げにされる。適合者には並の武器は通じない。兵士たちは恐れをなして逃走し始める。
守る盾のなくなったヴィルヒムをルシウスの炎が襲う。彼はそれを突き出した手から放出した風でルシウスへ押し返した。
「適合者……!?」
ココレットは知らなかったが、ルシウスはすでにヴィルヒムの風の力をマーテルで目にしている。そして、ヴィルヒムに押し返された炎はルシウス自身が生み出したもので、彼の炎が彼自身を焼くことはない。
炎を突き抜けたルシウスの手に顔を掴まれかけたヴィルヒムは、風に乗って彼から距離を取った。
スタフィルス研究機関のトップであるヴィルヒムは、軍にとってゴッドバウムの次に重要な人物だ。だが、守るべき存在である彼を守ろうとする兵はいなかった。適合者同士の戦いに手を出せば死ぬ。それはもはや周知の事実だった。
「安心しろ。じわじわ焼き殺してやる。意識は残したままがいいな。己の身が焼かれていく恐怖をたっぷりと味わうがいいッ!」
両手にためた炎を、ルシウスはヴィルヒムに放った。灼熱の炎が彼を包むかと思った瞬間、ルシウスの炎は大爆発を起こす。
「!?」
殺気を感じたルシウスはその場を飛び退いた。だが、一瞬遅れた彼の腹は大きく切り裂かれる。
(なんだ……!)
だが、ヴィルヒムのものとは質が違う気がした。腹を押さえたルシウスの指の間からボタボタと血が滴り落ちる。
「ちっ……」
トドメを刺すつもりだったため、さっきの炎に力を使いすぎた。ゼエゼエと息を切らす兄の背中を、呼吸をすることさえ忘れたにココレットが見つめていた。
(クサナギか……?いや、違う……)
なかなか土煙の晴れない場所をルシウスは睨み付ける。
(奴がステファンブルグを庇うわけはないし、いまのは奴の風ではない……)
目や鼻の数は同じでも、人の顔や体がそれぞれ違うように、同じ能力であっても、適合者によって適合率も攻撃方法も違う。ルシウスとミュウの炎も、炎の大きさ、熱などはかなり違っていた。それはそれぞれの個性のようなものだった。
ルシウスも、適合前ならアキの風とヴィルヒムの風を違うとは思わなかっただろう。それは適合したからこそわかることだった。立ち込めていた煙が晴れた。
そこにはヴィルヒムともうひとり、彼を庇うように立っている黒髪の少女がいた。10代後半に見える少女は初めて見る顔だったが、適合者で間違いないことは明らかだった。
「お父様。大丈夫?」
「ああ、すまないな」
(お父様……。父親?)
少しも似ていないふたりの会話に、ルシウスはくっと笑いをこぼした。それに少女は視線を向ける。
「大佐は私が」
そう言って、少女はその細い腕をルシウスに向ける。放たれた瞬間はわからなかったが、寸前で風刃を見切ったルシウスはそれを炎の熱で叩き落とした。
少女は華奢な身体を宙に浮かせると、ルシウスに向かって複数の風刃を投げつけた。それらをルシウスは炎で撃ち落としていく。あちこちに火の粉が散らばり、避難民たちが悲鳴を上げて森へと逃げ出した。
手数はあるが、少女の風にはアキほどの重みがなかった。それでもいつまでも攻撃は続く。止まない風にイラついたルシウスが雑に風を振り払った直後、爆炎の中から少女が飛び出してくる。
(速い……!)
少女の風がルシウスの肩を切り裂き、血飛沫は数メートル先まで風に運ばれた。よろめいたルシウスの腹めがけて、少女は両手を突き出す。1秒後には、ルシウスの身体は大きく吹っ飛んでいた。
「ぐ……!」
地上に叩きつけられて脳震盪を起こしたルシウスは、揺れる視界の中で立ち上がる。そのときにはヴィルヒムと少女は森の中へと姿を消す。置き去りを食らった黒獅子の兵士たちも、慌てて軍用車に乗り込んでその後を追った。
「邪魔だ!」
ルシウスは、軍用車に乗り込もうとした兵士の襟首を掴むと、腕の一本で彼を車外へ放り出す。地上へ叩きつける前に兵士の身体は骨まで燃え尽きていた。
軍用車を奪ったルシウスはヴィルヒムの後を追っていった。炎神そのものになったような兄の姿に呆然としていたココレットは、むせ込む声にハッと我に返った。
「ラウルさん……ッ」
「船、は……?」
ココレットは入江に顔を向けるが、ルシウスの炎で燃え上がったそこからは、ベキベキと木材が倒れていく音が聞こえていた。
悲痛な顔で首を振るココレットに、ラウルは彼女の首にかかっているキュラトスの指輪に手を伸ばした。
「頼む。……ロクサネを、マーテルへ……。黒獅子の……あいつらにだけは渡さないでくれ……」
ゲホゲホッとむせ込み、ラウルは苦しそうに呻く。
とにかく血を止めなくてはいけない。メアリーに教えてもらった応急処置の方法を思い出し、ココレットは着ていた上着を脱いで止血に使おうとしてその動きを止めた。彼女の膝の上でラウルは既に事切れていた。
「ラウル、寝ちゃったの?ねえ、ラウル」
ロクサネが呼びかけるが、彼はもう応えない。だが、ロクサネにはまだその死が理解できない。
(死んでしまう……)
誰よりも優しかったセバスチャンも、ずっとメアリーのそばにいてほしかったハインリヒも、ロクサネを守らなければならないラウルも、みんな死んでしまう。
(お兄様も……)
ラウルの身体を岩の上に横たえると、ココレットは首から下げていたキュラトスの指輪をロクサネの首にかけた。
「ど、どこへ行くの……?」
立ち上がったココレットに、フィヨドル人が聞いた。
入江の船はまだ燃えている。脱出するための船はもう一隻も残っていない。なら他の手段を考えなければならない。そのことをハルヒに伝えなければならない。
「いまから友人を追います。必ずマーテルへの脱出手段を手に入れて戻るので、あなた方は黒獅子軍に見つからないように森に隠れていてください」
そう言うと、ココレットは一台だけ、見捨てられたようにそこに残っていた軍用車へ顔を向けた。
□◼︎□◼︎□◼︎
ココレットたちと別れて数時間後、ハルヒはクロノスの案内でフィヨドルの軍施設を見下ろす場所に到着した。眼下に聳える巨大な施設を確認したハルヒは、気合を入れるためにバンダナを巻き直す。
「その色、きみによく似合っているね」
ハルヒが巻いているバンダナは、アキに贈られたものだった。もう捨てるべきなのかもしれないが、代用品がないという理由でハルヒはずっとこれを巻き続けていた。
「……あんたもフィヨドルの軍服が似合ってる」
ハルヒの皮肉めいた返しを受けたクロノスは、自分が地雷を踏んだことを察した。
(難しいな……)
ハルヒとは年齢が離れているせいか、ハルヒとの接し方をクロノスは困難に感じていた。
カゲトラとナツキの姿はまだ見えない。出発から数時間も歩けばハルヒやカゲトラの予想通りナツキの足は重くなり、これ以上無理をすれば発作が起こる危険性を考慮して、休憩しつつ先に進むことになった。
カゲトラは後から追いかけると言って、ナツキに付き添っている。先に施設へは侵入しないと約束し、ハルヒとクロノスは先にこの場へやってきていた。
「ふたりはまだ見えないな」
「だから連れてきたくなかったんだ」
ナツキの気持ちはわかるが、身体がそれに追いついていない。なるだけ危険から遠ざけたいのに、弟は最近言うことを聞かないことが多くなった。
「彼はまだ自分の限界を決める年齢じゃないだろう」
「あんた、言うことがジジ臭えな」
ハルヒに一蹴されたクロノスは肩をすくめた。
ハルヒの頭に巻いたバンダナが、スタフィルスからの砂を運ぶ生ぬるい風に吹かれて揺れる。足元の枯れた葉がカサカサと音を鳴らした。
「お父さんは―――」
「え?」
「きみのお父さんはどんな人なんだ?」
クロノスに聞かれて、ハルヒは胸ポケットにしまっていた写真を取り出した。いつだったか、ココレットがシノノメ家から無断で持ち出してきたものだ。家族4人が写っている最後の写真だった。
「物静かで、優しい人だ。つってもガキの頃の記憶だから」
クロノスは写真を受け取り、そこに映る家族の顔を順番に見る。まだ幼いハルヒ、ナツキ、ふたりの母親、そして父親を。
「クロノス?」
シノノメ家の家族写真を見ていたクロノスは、呼びかけられて我に帰る。
「……お父さんの名前は?」
「アキラだ。アキラ・シノノメ」
クロノスの顔つきが変わる。だが、先を急ぐハルヒにはそれが見えない。写真を返すふりをして、クロノスはもう一度アキラの顔を確認した。
「ナツキのやつ遅ぇなぁ……。なぁ、俺ちょっと中見てくるから、おまえはここでふたりを、」
「ハルヒ」
早々に痺れを切らしたハルヒだったが、クロノスの真剣な顔に続く言葉を止めた。
「……なんだよ」
「きみのお父さんは、……おそらくもう軍施設にはいない」
ハルヒは眉をしかめ、クロノスを見上げる。彼の背後では夕日が沈もうとしていた。黄昏色がフィヨドルの大地を染める。
「なんでそんなこと……」
「俺は以前に一度だけ、きみのお父さんに会っている」
「……どこで?」
ハルヒはクロノスに聞き返す。それは初めて聞いたアキラの目撃情報だった。軍の研究機関の人間でバルテゴにいた父が、どうやってフィヨドルの騎士と出会ったのか。ハルヒの胸の鼓動は速くなっていく。
「8年か、9年くらい前だったと思う。いまはもう滅びたフィヨドルの、ゴザという港町で会った」
「………」
「彼は……ナツキくんくらい、いやもっと幼い少年と一緒だった」
どくんと、ハルヒの胸が鼓動する。
「少、年?」
「確か道を……道を聞かれたんだ。陸路ではなく海路でスタフィルスへ行きたい。港で船に乗るには、どちらへ行けばいいのか。道を教えると、彼は丁寧に礼を述べて去って行った。去り際に、連れの少年がこちらを振り返った。黒髪の少年だった。紫色の瞳が、珍しいものを見るように私を見ていた。ここに……泣きボクロがあったのが印象的だった」
ハルヒは棒立ちになっていた。海から強い風が吹き、その頭で空色のバンダナが風に揺れる。森から飛ばされたカラカラの葉が軍施設へ飛ばされていく。
「彼らに教えた港町は俺の故郷だった。途中で用事があった俺は、彼らに数時間遅れて久しぶりの故郷へ帰還した……」
クロノスの表情は沈痛なものへと変わっていく。
「潮の香りが濃い故郷の空気を胸いっぱいに吸うはずだった俺の鼻をついたのは、吐き気がするほどの血の匂いだった」
「………」
「町にはたくさんの死体が転がっていた。それはまるで虐殺があったような風景だった。俺の目に映ったすべてがその命を失った抜け殻で―――。その中で、たったひとりだけ動く存在があった」
いったい、懐かしい故郷になにがあったのか、転がる死体の中に両親の姿はあるのか。そんなことをぐるぐるとまとまらない頭で考えながら、クロノスはゆっくりと立ち上がる人影を食い入るように見つめた。
「黄昏色の空の下にいたのは間違いなくあの少年だった」
フラついたハルヒは一歩下がり、その背中が木の幹にぶつかる。
「次の瞬間、鋭い痛みを感じて意識はそこで途切れた。再び目覚めたのは別の町にある病院のベッドの上だった」
言いながら、クロノスは「失礼」と軍服をめくる。彼の脇腹には、爪痕のような古傷が残っていた。ハルヒは自分でも気付かないうちに、アキにつけられた腹の傷の上に手をやっていた。大きさは違えど、それは同じ傷痕だった。
「そこに生き残った者はいなかった」
もう昔の話だった。クロノスの胸に残るのは虚無感だけで、すでに胸を引き裂くほどの悲しみは通り過ぎてしまっている。そもそも、見せ付けられたいきなりの惨劇に、涙が出たのかどうかも覚えてはいなかった。ただ強烈に覚えているのは、街を染めていた血のような夕焼け色だけだった。
「!?」
突然、爆発音が響いてハルヒは我に返る。見下ろす軍施設からは黒煙が噴き出していた。
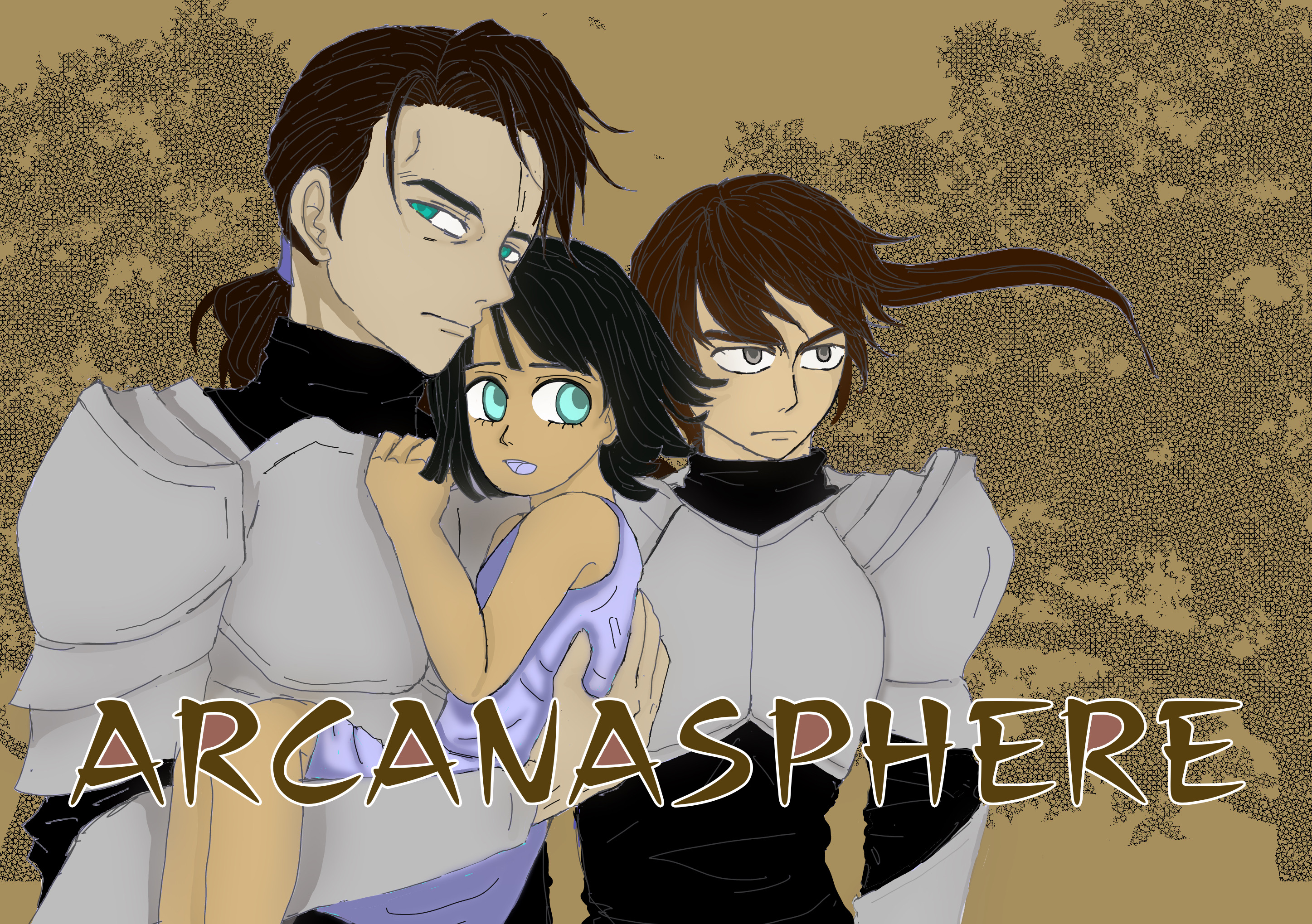
 にぃなん
Link
Message
Mute
にぃなん
Link
Message
Mute

 にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん