ARCANASPHERE5 夜通し続いた砂嵐が去った翌日の昼になり、リュケイオン家に保護されたハルヒは目を覚ました。
「………」
最近は、目が覚めたとき見知らぬ部屋にいることが多い。毎日見ていた薄汚れた自宅の天井が懐かしいと思いながら、寝返りを打とうとして脇腹に差し込んだ痛みに、ハルヒは声も出せず悶絶する。
「だ、大丈夫ですかッ」
その声は、どこかで聞いたことのあるものだった。それでもそれがだれの声かはわからず、傷の痛みを堪えながら顔を上げたハルヒは、そこにいたココレットの姿に目を丸くする。
「なんでおまえが……」
ココレットはゴッドバウムの娘で、ルシウスの妹だ。まだ自分は軍の手の中にいる。そんな絶望的な気分になったハルヒは、ノックもせずに部屋に入ってきたカゲトラにますます混乱する。
「ハルヒッ」
「トラ……」
やっと目を覚ましたハルヒに駆け寄り、カゲトラは大丈夫かと声をかけた。
「ここはどこだ……!」
「彼女の屋敷だ。彼女は心配ない。敵じゃない」
カゲトラがそう言うが、ハルヒは納得できずにココレットを睨む。その黄金の髪は否応なしにルシウスの姿を思い出させ、ハルヒに不快感を与えた。
「……あいつは?」
ハルヒが聞いた。
ハルヒがだれのことを尋ねているのかはわかっていたが、カゲトラはすぐには答えなかった。目覚めてすぐにハルヒが思い出すことはアキのことだ。それが憎しみゆえであればと思うのに、ハルヒはその目に不安の色を載せている。アキが心配でたまらないという、そんな顔をしている。
「トラ。クサナギはどこだ?」
「無事だ。この屋敷内にいる。まずは落ち着け」
「会いに行く」
「待て。先にその傷について聞かせろ」
カゲトラはベッドから降りようとするハルヒを引き止める。
「何にやられた?いや、だれにやられた?」
「………」
「答えられないのなら当ててやる」
「こんなのなんでもない」
「クサナギだな」
「なんでもないって!」
「あの男がやったんだな!」
もとからアキがハルヒを傷つけたことはわかりきっていた。ハルヒが答えることを渋ったことでさらにそれが決定的になり、カゲトラは怒りに燃えて部屋を出て行く。
「おい、カゲトラ!……イッテェ!」
カゲトラとは長年の付き合いだ。彼がいまから何をするのかわからないハルヒではなかった。だが、傷の痛みで身体が思うように動かず、ベッドから転がり落ちかけたハルヒを、慌ててココレットが受け止める。
「俺に触るな……!」
せっかく助けてくれたココレットを睨みつけ、ハルヒはベッドから降りると床を這い、扉まで来ると壁に掴まってようやく立ち上がる。
「カゲトラ……!」
大股で歩くカゲトラの姿は、すでに長い廊下の端まで遠ざかっていた。
「おいおいおいおい!」
部屋に踏み込んできたカゲトラの剣幕に、ソファーでうたた寝していたハインリヒは飛び上がって、ベッドで寝ているアキを庇うため立ち上がった。
「あんたもしつこいな!アキじゃねえって言ってんだろ!」
身体を張って止めなければ、カゲトラは昏睡状態のアキを殺しかねない雰囲気だ。
「こいつに間違いない!」
「このわからず屋の大男……!」
アキを守らなければならないが、腕力ではとても敵いそうにない相手だ。何か武器になるものを探したハインリヒは、やっとの思いでカゲトラに追いついたハルヒの姿に気づいた。
「嬢ちゃん。目が覚めたのか!」
カゲトラが振り返ると、無理をして歩いてきたハルヒの脇腹には血が滲んでいた。
「ハルヒ……!」
たった20メートルほど歩いただけでゼエゼエと息を切らすハルヒを支え、カゲトラはハインリヒと睨み合う。部屋の外では、ハラハラとした様子でココレットがその様子を見ていた。
「クサナギは……?」
カゲトラでは話にならないと判断し、ハルヒはハインリヒにアキの様子を聞いた。
「ああ、アキならずっと眠ってる。心配ないとは医者に聞いてるよ」
「そうか……」
「ハルヒ。その傷はクサナギにやられたんだろう」
「トラ……。何があったか説明するから、ちょっと待ってくれ」
せめて息が整うまで待ってほしい。ハルヒはそう願うが、カゲトラは納得しない。
「こいつの仕業に決まってる!」
「ああ、そうだよ!クサナギにやられた!だけどな!俺はこいつに対して怒ってないし、恨んでないし、憎んでもない!」
むしろカゲトラに対してハルヒは怒りをあらわにする。アキに傷つけられたけれど、アキを許す。そう言ったハルヒに、カゲトラはその顔を苦しそうに歪ませ、勝手にしろと言い残して部屋を出て行った。
ようやく静けさが戻った室内で、ハインリヒはやれやれとタバコに火をつけようとしたが、騒ぎを聞きつけてやってきたメアリーにそれを取り上げられる。
「屋敷内は禁煙よ」
「……すいません」
ハインリヒは出番がこなかったライターをポケットに戻してため息をついた。
「ばかね。起きてすぐ動き回るからよ」
顔色を失ったハルヒに呆れ、メアリーはソファーに座りなさいと命令した。
「あんただれだ……」
「メアリー・シュベルツ。あんたとそこの彼を手当てした医者よ」
「……クサナギはいつ起きる?」
手当ての件で礼のひとつでも言われるのかと思ったが、ハルヒの口から出た言葉はアキを心配するものだった。
「体力を回復するために眠っているんだとは思うけど、その……神様の力って言うのは私の専門外だから、なんとも言えない」
でも、血圧も脈拍も正常の範囲内ではある。メアリーからそう説明を受け、ハルヒは静かな寝息を立てているアキを見つめる。
軍施設からどうやって脱出したのかハルヒには記憶がない。おそらく、アキが連れ出してくれたのだろうが、それがかなりの負担になったのかもしれない。
(……起きたら、)
ハルヒはアキに聞きたいことがあった。それはヴィルヒムがアキに聞けと言った、父親のことだった。
(クサナギは父さんを知ってるのか……?)
軍施設で、アキは確かにアキラの名を口にした。眠り続ける彼に心の中で聞いても、当然ながら答えが返ってくるはずもないし、いまのカゲトラには相談できない。あの様子では、アキラの名前なんて出せば最後、本当にアキを殺しかねない。
「あ、あの……」
考え込むハルヒにココレットが声をかける。カゲトラはココレットが敵ではないと言っていたが、ハルヒはまだ納得していなかった。
「これをお返ししたくて……」
視線だけを向けると、ココレットは手に持っていたものを差し出した。それはハルヒたち家族4人が写った写真だった。カッとなったハルヒが写真を引ったくると、当たった爪がココレットの白い手を意図せず傷つけた。
「お嬢さま!」
ココレットの手の甲に滲んだ血に過剰反応をしたのは、本人ではなくメアリーだ。父親が長年執事として仕えているココレットは、彼女にとって大事な妹のような存在だった。
「何するのよ!」
「こっちのセリフだ!ひとの家のもの勝手に盗みやがって!」
「……ココレット様?」
ハルヒの言葉をすぐには信じず、メアリーはココレットに確認する。
「……本当よ。盗むつもりはなかったけれど、承諾を得ず勝手に持ち出しました」
ココレットは怒られた子犬のように肩を落とす。ココレットが自らそんなことをするなんて信じられず、メアリーはハインリヒをジロリと睨んだ。誘拐はされていなかったが、ココレットを連れ回していたのが彼だということを聞いたからだ。
「なんだよ」
「お嬢様を唆したわね!」
「はぁあああ?」
「あんたみたいなのに唆されないと、純真無垢なお嬢様が盗みなんてするわけないのよ!」
「とんでもねえ思想の女だな……」
ハインリヒはこれまでたくさんの女性と関係を持ってきた。女性ならばすべてを愛せると自他共に認めるような彼だが、メアリーは一番苦手とするタイプだった。
「メアリーっ、私はハインリヒ様に唆されたりしてないわっ」
「でもお嬢様ッ」
「話したでしょう。ハインリヒ様にはたくさん助けていただいたの」
メアリーは忌々しそうに顔を歪める。
「ハルヒ様。大切なものを勝手に持ち出して、本当に申し訳ありませんでした」
ココレットはハルヒに対し、深々と頭を下げた。リュケイオン家の令嬢が、F地区に住むハルヒに頭を下げるだけでもあり得ないことなのに、その上彼女はテロリストだ。メアリーは現実を受け止めきれず目を回しそうになっていた。
「理由を説明させていただいてもよろしいでしょうか」
「………」
ハルヒは黙ったまま何も言わない。
「まず、お家にお邪魔したのは、ハルヒ様がご帰宅されてないか確かめたかったからです。そのときに写真を持ち出したのは、ハルヒ様をお見かけしていないかひとに聞くためでした」
「お嬢ちゃんはテロリストだから、それはやめろって言ったんだよ」
ハインリヒが口を挟む。それを聞いたメアリーは、ゾッとしたと同時にホッと胸をなで下ろす。ハインリヒは気に入らないが、この件に関しては彼がそばにいてよかったと思ったからだ。
「……なんで俺を探してた?」
「ナツキ様の居場所をお伝えしようと思ったんです」
ブロッケンビルで、ココレットがナツキのことを伝えようとしていたことを覚えているハルヒは、対して驚きもせずに頷いた。
「それで、弟はどこだ?」
「ごめんなさい……。いまは、コウヅキ様のそばを離れたようで、どこにいるのかわからないんです……」
「……あのとき、ナツキはブロッケンビルにいたのか?」
ココレットを人質にしたあの場所にはレイジの姿もあった。ナツキの誘拐にはレイジが関わっていることは間違いない。ハルヒの質問に、ココレットはコクリと頷いた。
「……クソッ」
ハルヒは拳を壁に叩きつける。
もう少し探していれば。全部の部屋を見ていれば。ナツキとあのとき会えていたかもしれない。見つけていたかもしれない。そう思うとたまらなく悔しかった。
宛てもなくナツキを探すのは無理であることは、もうハルヒにも理解できた。いまはレイジの手中にはない弟の無事を祈り、ここに留まるべきだと判断し、ハルヒはアキが眠るベッドの足元へ腰掛けた。
「……あんた」
ハルヒは部屋を出ようとしていたハインリヒを呼び止めた。それは、眠っているアキには聞けないことを聞くためだった。
「こいつの育ての親なんだろ?」
「アキがそう言ったのか?」
ハインリヒは質問に質問を返す。ハルヒは頷いた。
「おまえに拾われたって聞いた」
「まあ……そうだな。間違ってねえな」
ハインリヒは答えに困ったようにボサボサ頭をボリボリと掻いた。
「あー……」
「なんだよ。違うのか?」
「まあ、拾ったって言うか買ったっつーか……」
「買った?」
ハルヒは首を傾げるが、ハインリヒは明けた口を自分の手で物理的に塞いだ。
「まあ、詳しく知りたいならそれはこいつに聞いてくれ」
俺の口からは言うことじゃねえと、ハインリヒはその話を終わらせた。
「あんたはこいつの力のこと知ってたのか?」
「……お嬢ちゃんもマジで言ってんのか」
「そっか……。あんたは見たことないんだな……」
ハルヒも自分の目で見なければ信じられなかったし、最初に助けられたときは何が起こったのかもわからなかった。それに、日常生活でアキは力を使う必要がなかった。それがハルヒと出会うことで危険に巻き込まれ、結果いまこんな状態になっている。
ハルヒの顔を見れば、ハインリヒはカゲトラの言っていたことをすべて否定する気持ちにはなれなかった。あり得ないと思いつつも、実際ハルヒの傷はどんな薄く鋭利な刃物で切られたのかと思えるもので、アキは外傷もないのに原因不明の昏睡状態だ。
「アキは……ただの優秀なやつだよ」
ハインリヒは自分が知らないアキの力のことではなく、よく知っている彼のことを話し出す。
「頼んだことはそつなくこなすし、人当たりもいい。相手が何を欲しがってるのか少し話すだけで理解する。大学も首席で卒業して、どんな一流企業にだって入れたってのに、わざわざ俺の会社を選んだ。ばかだったのはそこだけだな」
ふたりの出会いはどうあれ、アキがハインリヒを信頼していることは、話の節々でハルヒにも十分伝わっていた。
「アキをちょっと頼めるか」
「え?」
「一服させてくれ」
ハルヒが目覚めるまでアキにつきっきりだったハインリヒは、あくびをかみ殺しながら部屋を出て行った。ふうっとメアリーが息を吐く。
「彼のことだけど」
ハインリヒには伝えたことを、メアリーはハルヒにも伝えるべきだと判断し、アキのいるベッドに近づく。そして、アキが着ているシャツを左右に開いた。ココレットが慌てて目を逸らす。
「わかる?ここ、血管が異常に盛り上がってるでしょ」
「ああ……」
アキの胸にある手術痕、その心臓あたりの血管は、メアリーが言う通り皮膚の上に盛り上がっていた。
「ここへ運び込まれたときはもっと酷かったから、マシにはなってるわ。だから回復しているんだとは思うけど、こんな症例はいままで見たことないから、やっぱりなんとも言えない」
神の力なんてものは一般の医者であるメアリーの手に余る。アキを診せるなら研究機関なのだろうが、黒と白の獅子、どちらの研究機関にも彼を渡せるわけがなかった。
□◼︎□◼︎□◼︎
真っ赤なバラが飾られた病室で、ルシウスは報告書と睨み合っていた。
それは毎月上がってくる取るに足らない報告書であり、通常であれば中身を吟味するまでもない。渡されたらその場でサインをすれば事足りるものだ。そんな、急ぎでも重要でもない書類仕事など病室に持ち込むものではなかったが、いまはそれしかすることがない。なぜなら、仕事の合間を縫って会いにきた人物はベッドでよく眠っているからだ。
エルザの怪我はすべて、あのとき彼女の言葉を聞いて退避しなかった自分のせいだと考えるルシウスは、時間に余裕ができると病室へと足を運んだ。
報告書を机の上に置き、ルシウスはふうっとため息をつく。どこへ逃げたのか、ハルヒとアキの目撃情報はいまだ何もない。仲間に匿われているとしても、【トライデント】の動きも掴めず、レーベル社の少ない社員は全員行方不明だ。
(どこに隠れた……)
一度ならず二度までも煮え湯を飲まされた形となったルシウスは、まさかココレットの屋敷にふたりが匿われているとは知らず、躍起になって捜索命令を出していた。
コンコンっと病室の扉がノックされた。看護士だろうか。返事をしたルシウスが顔を上げると、予想に反してスーツ姿の男が病室へ入ってくる。
「クリム」
「やあ、ルシウス。ここに来てるって聞いたんや」
男の名はクリム・グレイスター。軍事兵器開発会社グレイスター社の社長の息子でで、ルシウスの古くからの友人でもあった。
「どうした」
「ちょっと話せるやろか?」
「ああ。構わない」
軍施設内にあるルシウスの執務室ならまだしも、こんなところまで来るなんで、よほどの急用がなのだろう。ルシウスは立ち上がり、廊下に出た。
「少尉は大丈夫なん?」
「ああ。命に別状はない」
「聞いたで。きみを庇っての負傷やて。部下に恵まれとるなあ」
クリムは独特な口調で冗談にも聞こえることを口にした。
ふたりはエルザの病室から、病院内にある休憩フロアへと移動する。幸運なことにそこにはだれの姿もなかった。
「それはそうと久しぶりだな」
「僕は結構テレビとかで見るけど」
母親に似て容姿端麗なルシウスは広報に立つことも多かった。軍に入りたての頃のルシウスを、当時中佐だったヘリオスは嫌味を込めて黒獅子のアイドルと呼んでいた。だが、10年も経たないうちにルシウスは、そのヘリオスと並ぶ士官に昇進した。
「実際に会うのは久しぶりだろう」
「そやね。僕、数ヶ月フィヨドルに行ってたし」
隣国であるフィヨドルは、先日スタフィルス軍が落としたばかりだ。
「戦場にいたのか?」
「社会勉強と、兵器の実験のためにね」
なるほど。戦場ほど兵器実験に適した場所はない。ルシウスは納得する。
「まあ、王城での戦闘は連れてってもらえへんかったけどね」
フィヨドルの戦場には砂が舞っていたと言う話を聞いた。ルシウスは出征していなかったが、フィヨドルに現れたバケモノの映像は見た。そして、映像が一度切れ、再開されたときそこには砂しか残っていなかった。
頭の悪い兵士たちは砂の神が守ってくれたと口にしているらしいが、ルシウスにはそうは思えなかった。あれはアキと同じく、このスタフィルスの砂神の力を持つ適合者の仕業ではないのか。それはスタフィルス王家を滅ぼしたゴッドバウムではないのか、そう考えていた。
ルシウスに、父親であるゴッドバウムと家族らしい会話をした記憶はない。家族と呼べるのは母親だけだった。ココレットが生まれて、彼女が自殺するまでは。父親という名前だけの男には、おそらくアキと同じような力がある。それについて聞きたいと思ってはいたが、ルシウスがゴッドバウムと会う機会はなかなか訪れなかった。
「今日はこれを見せようと思って」
クリムはそう言って、考え事をしていたルシウスの膝の上にファイルを置いた。確認しろと言うことだろうと理解し、ルシウスはそれを手に取る。表紙を捲ると、1枚目にグンニグルと書かれていた。
「パパにさ、将軍に渡すように頼まれて持ってきてん」
「では渡す相手を間違えているな」
「きみに先に見てもらいたかったんやって」
ルシウスは無言のままページを捲り、ファイルに目を通す。グンニグルと名付けられたそれは巨大な爆弾だった。積まれている火薬の量は、スタフィルス市街ひとつ簡単に吹き飛ぶサイズだ。
「きみのパパ。次はどこの国を手に入れるつもりなんかな?」
フィヨドルを滅ぼしてまだ日が浅いにも関わらず、ゴッドバウムはもう次の戦争の準備を始めている。クリムはそれをルシウスに伝えに来たらしかった。
「私に取り入っても無駄だぞ。時期将軍はヘリオスとの噂もある」
「そんなのただの噂やん。この時代に年功序列とかアホらしい。僕はきみに期待してんねん」
クリムは指で銃の形をつくり、ルシウスの胸に向けて引き金を引く真似をする。
「僕は、きみに次の将軍になって欲しい」
「将軍ね……」
「そんな気のない返事をせんとって、少しは考えてや。きみが将軍、僕がグレイスターの社長。軍事政権のトップと、軍事産業会社のトップ。僕ら、生涯に渡っていい関係を築いていけると思わへん?」
つまりクリムは、ルシウスとの友情を基盤に、社会の中でも揺るぎない地位を手に入れたいと言うことだ。今回、軍はグンニグルの発注をグレイスター社に一任したようだが、以前は違う大手軍事産業の民間会社と契約していた。
「テロリストと遊ぶんも楽しいみたいやけど、きみがもう少し野心を持ってくれることを祈っとるよ」
そう言って、クリムは花瓶に飾られていた花を1本手に取ると、ルシウスが着ている軍服の胸に差す。そして交換するようにファイルを取り戻すと、鼻歌を歌いながら休憩室を出て行った。
□◼︎□◼︎□◼︎
咲き誇る季節の花々と、風を受けて回る大風車。高台にある神殿がいつもの冒険コースだった。家庭教師が来る前にこっそりと部屋を抜け出して、妹の手を引いて走った。
待って、おにいさま。あどけない声でセルフィが自分を呼ぶ。今度はなにを見つけたんだろう。小さな花?それとも、指先に乗る羽根だろうか。だけどセルフィはそんなものを見ていたわけじゃなかった。小さな指を遥か丘の下に向けて、セルフィが見ていたのは城から馬に乗って駆け出していく兵士だった。
「見て―――。あんなにたくさんのひとが―――」
セルフィの言葉の途中で、城下町で赤い光が爆発した。そこからかなり離れている神殿にも、その轟音が聞こえてくる。一瞬にして戦場と化した町の中ではためく黒獅子の旗が映っていた。
悲鳴と炎と爆音の中、妹を抱いた母と逃げた。風の嘆く音が聞こえていた。ラティ。セルフィ。もう逃げきれない。絶望した母は、子守唄を歌いながら、眠っている妹の首に手をかけた。どうせ死ぬのなら、眠ったまま安らかに。それが母の願いだった。
荒れ狂う竜巻。国土を蹂躙され、怒りに燃える風の守護神。あの日見たものがなんだったのかは、何年もたった後に知った。風神が巻き起こしたのは、後に死の風と呼ばれた。
「………」
目覚ましをかけ忘れた。
朝にしては明るすぎる日差しに、アキはそう思った。すでに昼に差し掛かっているであろう日差しに、眩しくてまともに目が開けられない。完全に遅刻だ。アキはとりあえず時間を確かめようと手を伸ばす。
いつも同じ位置に置いておけばいいのだが、どうもその時の気分次第であちこちに置いてしまうので、いつもこうして苦労する。仕事に遅刻した理由を、ハインリヒにどう言い訳しようか―――。
目覚ましを探して虚空を彷徨う手がパシッと受け止められる。それは目覚ましではなく、柔らかい手だった。その感触が、長い夢の記憶を払拭し、アキの意識も記憶も完全に覚醒させる。
「ハル……ッ」
飛び起きようとしたアキは胸を押されて止められる。アキは半身を起こしかけたまま、そこにいるハルヒの姿を見つめた。
頬と、首と、肩と――――ハルヒには傷の手当てをされた形跡が見えた。
「ごっ……」
ごめん。そんな簡単な言葉も言えないくらい、アキは動揺していた。手当てされたハルヒの頬に触れようと腕を持ち上げるが、どうしても触れることができない。触れたらまた傷つけてしまうかもしれない。その恐れがアキの身体を硬直させた。
「……いた、い?」
そんなわかりきったことを聞いてしまう。痛くないわけがない。自分の放った風がどんな結果を生むかくらい、アキが一番よくわかっていた。
「平気だ。こんなのなんでもない。最初からたいしたことないけどな」
強がりなのか、優しさなのか、ハルヒはぶっきらぼうに答えた。怖くなかったはずがないのに。
「お腹……深く……」
「ああ、腹はこんな感じ」
ハルヒは縫合された脇腹の傷痕をアキに見せる。メアリーの縫合は丁寧だったが、それは一生消えない傷跡になっていた。
「クサナギ?」
「………」
「おい」
「………」
「おい、こら」
反応を見せないアキの胸倉を掴み、ハルヒは強い力でベッドへ突き飛ばした。アキは、目を丸くして自分の上に圧し掛かってきたハルヒを見上げた。
「勝手に落ち込む前に、俺に感謝しろ」
「………」」
「俺はおまえを助けてやったんだぞ」
いつも助けられている身でなにを言ってるんだろう―――。ハルヒはそう自分につっこむ。だが、自己嫌悪に落ち込むアキを見て、ハルヒはあえて悪役を演じ切るつもりだった。
「俺はひとりでも逃げ出せたけど、わざわざおまえを迎えに行ってやったんだ。ほら、感謝しろ」
ハルヒは胸を張ってそう言う。アキの記憶では、ハルヒを抱えて研究施設を脱出したのは自分だ。だが、ハルヒがそう言うのならそうなのだろう。自分はハルヒに助けられてここにいる。
「ありがとう……」
アキがようやくそう言うと、ハルヒはその顔に笑みを浮かべ、彼から手を離したが、今度はその手をアキが掴む。
以前のハルヒならすぐさま振りほどいていただろうが、それはなく、彼女はじっとアキを見つめていた。
「クサナギ?」
「僕は……みっともないところ見せちゃったよね……」
アキが、研究施設でのことを言っていることはすぐにわかった。ハルヒは首を振る。あれをみっともないことだとは本当に思っていなかったからだ。逆にハルヒは、取り乱すアキの姿に人間性を感じた。無敵に見えたアキにも、人間らしい弱い部分があることに気づいたからだ。
「おまえ、これからはもっと俺を頼れよな」
「え?」
「俺を頼れって言ってんだよ。わかったか?」
「……うん。わかった」
アキは頷き、ぎゅっとハルヒの手を握った。
「あのとき……僕のこと名前で呼んでくれたよね?」
「あれは……」
あれはアキを正気に戻そうと思って、咄嗟に出たものだった。ハルヒにしてみても、ほぼ無意識の結果だ。
「もう一回呼んで欲しいな」
「……嫌だ」
「どうして?」
意識化で呼ぶのはなんだか気恥ずかしい。その理由は伝えず、ハルヒはただ嫌だと言い張った。
「じゃあ……キスしていい?」
「ばっ……、ふざけんな!」
ハルヒはアキの手を振り払い、安全な位置まで飛び退いた。だが、その顔に最初に会ったときようなアキに対する嫌悪感や否定的なものは見えなかった。顔を赤らめているハルヒの反応に、アキは苦笑しながらごめんと謝った。
「ここはどこ?」
王宮だろうか。アキが覚えているのは、ハインリヒの姿を見たところまでだった。
「ココレット・リュケイオンの家だ」
「え?」
「ココレット・リュケイオン。あのクソ野郎の妹の家だよ。とりあえずはここに来るしかなかったんだと」
不貞腐れた顔のハルヒを見る限り、ここに留まることを決定したのは別の人物だと思われた。それは、アキはその人物を頭に思い浮かべた。
「ここに社長もいるの?」
「なんであいつがいるの知ってんだ?」
「意識を失う前に最後に見たの、社長だったから」
「そうなのか。呼んでくる」
「あっ、いいよ。自分で……っ」
自分で会いに行ける。そう行ってアキは立ち上がりかけ、締め付けられる胸の痛みに息を詰まらせた。思わず押さえた胸に視線をやると、そこには少し浮き上がった血管が見えた。
(リバウンドしなかったのは奇跡だな……)
アキがもたもたしている間に、ハルヒは部屋から出て行ってしまっていた。
□◼︎□◼︎□◼︎
「―――適合率62%です」
機械的な調子で今日の結果が伝えられる。
脳波や心音のメーターグラフを真剣な顔で見つめていたチグサがOKのサインを出すと、それに従って研究員が手元の青いボタンを押す。すると、プシュッと音がして奥にある扉が開いた。
「今日は終わりにしましょう。F−241」
暗い扉の向こうから、ナンバーで呼ばれた人物がゆっくりと姿を見せた。研究員がゴクリと喉を鳴らすが、チグサは微笑を浮かべたまま彼を出迎えた。F-241―――イスズ・バレシアを。
「なかなかの調子よ。初日と比べたら、10%以上も適合率があがっているわ」
喜ぶチグサにイスズは辛辣な視線を向ける。
「……やつの適合率は瞬間的にでも80%を越えるんでしょう?」
「B-101のこと?」
イスズは鼻で笑う。
「ナンバーで言われるとややこしいな。クサナギ先輩ですよ」
「そうね。でも、一瞬のものよ」
「それでも僕より高い!」
激昂したイスズの腕の血管が膨張し、研究員は悲鳴を上げて椅子から転がり落ちる。いまこの瞬間にも一突きで殺されるかもしれない。イスズにはその力がある。なぜチグサが恐怖を感じないのか、研究員は理解できなかった。
先ほど受けたヴィルヒムからの連絡では、アキが強化ガラスを突き破ったときの適合率は90%を超えていたそうだが、その情報をイスズに開示する必要はなかった。
「焦ってはだめよ」
そう言って、チグサはイスズの頬にかかる髪に指を絡めた。
「あなたはこれからまだまだ強くなるわ。そう―――アキ・クサナギなんか足元にも及ばないくらい。あなたは選ばれたのだから―――」
まるで呪いのような言葉を振り払うかのごとく、イスズはチグサの手をはね退けた。そして、血管の浮き出た腕を撫でながら、その場を後にする。研究員は腹の底から息を吐いた。生き返ったと言う心境だろう。
「ドクター・ワダツグ。あのように解放しては―――」
自分たちに危害が及ぶのではないか、研究員の当然たる危惧に、チグサは首を振る。
「機嫌を損ねなければ平気よ。ボウヤの扱い方くらい学びなさい」
チグサは煙草をくわえ、ライターに火をつける。
ボウヤ―――、確かに今年36になる研究員から見てもイスズは若かった。しかし、だからこそ恐ろしいと感じた。
若さは戻らない眩しさであり、未熟さの象徴だ。たった一言を間違えれば、簡単に感情が爆発して、どうなるかわからない。それが、普通の人間なら青春の一環としてとらえることもできようが、相手は適合者だ。下手なことを言えば、自分の命に関わる。適合者を前にしたとき自分は、チグサが吐き出す煙のように頼りない命でしかなかった。
□◼︎□◼︎□◼︎
その日の朝、リュケイオン家の食堂は不協和音に溢れていた。
マナーもなにもお構いなく出された皿にがっつくハルヒに、新聞を読みながら肩肘をついてパンを頬張るカゲトラ。ハインリヒの姿は見えない。唯一、まともなテーブルマナーを知っているのはアキだけだ。
全員で食事をするのは今日が初めてだった。だが、それを企画したココレットでさえ、ハルヒの食事姿に目を丸くしている。このままではこちらまで品性を欠いたウイルスに汚染されそうだ。メアリーは隠すつもりのないため息を吐き、それに気付いたアキが顔を上げる。
「クサナギくん。具合はどう?」
「おかげさまで。先生の手当てのおかげです」
汚れてもいない口元をナプキンで拭き取り、アキはメアリーに笑顔を見せた。メアリーの目にアキは普通の青年に見えたが、その胸には手術痕があり、不思議な力があると言う。それをまだ実際に見たことはなかったが、ハルヒの傷を見た彼女に真っ向から否定する気はなかった。
「それで、あなたの上司はどこへ行ったの?」
「さあ、詳しくは僕も聞いてないです。たぶん、恋人のところだと思います」
「追われてるのに呑気な男ね。その恋人の家に軍が張り込んでるとは考えないのかしら」
捕まったらリュケイオン家に迷惑がかかると思わないのだろうか。嫌味さを隠すことないメアリーの言葉に、アキは同意して頷いた。
「でも、全員を見張るのは無理でしょうね」
「全員?」
「社長の恋人はひとりじゃないので」
「……最ッ低」
メアリーは低い声でそう言い、サラダにフォークを突き刺した。
「はれはほひふ」
口いっぱいにパンを頬張ったハルヒが、カゲトラの読んでいる新聞を指差す。そこにはハルヒやココレットと変わらない年恰好の少女の写真が掲載されていた。
「リジカ・エド・アメンタリ。アメンタリの王女ね」
ハルヒの質問にはメアリーが答える。カゲトラもハルヒが見ている面に目を向けた。そして呟く。
「アメンタリからの花嫁か……」
アメンタリは西にある火の国と呼ばれる国だ。まともな教育を受けていないハルヒでも、それくらいは知っていた。
「花嫁って……だれかと結婚すんのか?」
他国の王女との婚姻相手として相応しいのは王子と言うことになるが、この国の王族はもはやアメストリアしか残っていない。そしてその存在は一般には伏せられている上に、彼女は女性だ。
まさかゴッドバウムかと考えたのはココレットも同じようで、まだ幼いとも言える年齢とリジカに自分を重ね合わせてしまったのか、その顔色は青ざめていた。しかし、こんなものどう見たって政略結婚だ。あり得ないとは言い切れない。
「相手はルシウス・リュケイオンだ」
だが、適任はほかにもいる。最初からわかっていたのか、アキは納得したように目を伏せ、ココレットはひとまずホッとして胸を撫で下ろす。だが、ハルヒだけは目を丸くした。
「ルシウスって、あのルシウスか?」
「ほかには思い当たらないな」
「なんであいつなんだよ」
「将軍の息子だからな。軍事政権も世襲制なんだろ」
カゲトラは半ば投げやりにそう言った。ハルヒがアキを庇った一件で、少しは落ち着いたものの、彼の機嫌はまだ悪かった。
「知ってたのか?」
ハルヒはココレットに聞いた。
「いえ……。お兄様とは、ブロッケンビルのパーティー以来お会いしていないので……」
ココレットは膝の上でその手をぎゅっと握りしめた。ブロッケンビルでのことを思い出すとまだ泣き出しそうになる。兄に嫌われているのを知っていても、大勢の人々が集まっているあの場で見捨てられるとは思っていなかったからだ。あのとき、結果的にココレットを守ってくれたのは、彼女を人質にしたハルヒだけだった。
「人質だろうな」
新聞を机の上に投げ出してカゲトラが言った。
「人質?」
「自国を守るためにアメンタリも必死なんだ。王女を人質としてスタフィルスに送りつけ、フィヨドルの二の舞になることを避けようとしてる」
ハルヒはルシウスが嫌いだった。数々の出来事から好きになるほうが難しい。そのため、祖国のためとはいえ、あんな男に嫁がなければならないリジカに心から同情した。
「婚姻ごときで黒獅子が止まるならいいが……」
フィヨドルを攻め落としたとはいえ、まだアメンタリ侵攻が正式に発表されたわけではない。バルテゴ侵略から月日は経ったがゴッドバウムはこれで二国を侵略し、自国を含めれば三国を滅ぼしたことになる。
そして、戦争はもちろん負けることもある。万に一つでも劣勢になれば国内だって戦場になる。
「トラ?」
立ち上がったカゲトラは、日没には戻ると言って食堂から出て行った。どこへ行くんだと聞く暇もなく出て行ったカゲトラに、ハルヒはため息をついた。いつになったら機嫌が直るのか、いい加減にしつこい。
「ご馳走さまでした」
食事の終了を知らせたアキの落ち着いた声は、そんな空気の中、違和感しかなかった。
□◼︎□◼︎□◼︎
「もう限界だと思う」
食事を終えて部屋へ戻ったアキはハルヒにそう言った。
「ここから出て行かなきゃ、これ以上はココレットちゃんたちに迷惑をかけるどころか、危険に巻き込むことになりかねない」
アキの言うことはもっともだ。リュケイオン家に保護されてもう数日が経つ。確かにここは安全な場所だが、王宮のようにはいかない。あの場所は軍に黙認はされているが、ここは違う。
だが、ここを出るとしてそのあとはどうすればいい。ナツキを探すにしても、自分たちが落ち着く場所を見つけなければ、ハルヒたちは指名手配犯だ。ココレットという箱庭を一歩出れば発見され、軍に連行される可能性もある。
ハルヒの危惧することはまだあった。それはイスズだ。アキに対して明らかな殺意を抱いていたあの男は、あの後どこへ行ったのか。のこのこ出て行けば、またアキに危険が及ぶかも知れない。
「ハルヒ」
「おまえさ……軍に捕まってたときのことって、覚えてるか?」
「……全部じゃないけど、部分的には」
「アキラって……言ったことは?」
「……え?」
「アキラって奴のこと、知ってるか……?」
ハルヒは縋るような気持ちでアキを見つめた。
父のアキラは国外で仕事をしていた。父からくる手紙を、母に読んでもらうのが好きだったハルヒは、手紙が途絶えたことで、幼心にも父に何かあったのだと察した。その父のことをアキが知っているかも知れない。手がかりさえ掴めなかった父の行方がわかるかも知れない。
「……ごめん。知らないかな」
だが、アキの返答はハルヒの希望していたものではなかった。
「……えっ、……あ、いや、気にすんな。別に。大したことじゃねえし……。そ、そうだ!早くこっから出てかないとな!」
思っていたこととは違ったアキの返答に、ハルヒの口調はどんどん早くなる。
「ト、トラの奴が戻ってきたら話すよ。お、おお、おまえもハインリヒに言っとけよな!」
アキを指差してそう言うと、ハルヒはアキの前から走り去っていった。
(アキラ……?)
覚えているのは燃えるような赤い夕焼け。その中で立ち尽くす自分。周りにあるのは大勢の死体。
「……っ」
アキは針が差し込むような頭痛に顔をしかめた。記憶の断片をつなぎ合わせようとすると、いつも痛みに邪魔された。ジクジクと古傷のように痛む頭を壁に預け、アキはもう一度謝罪の言葉を口にした。
□◼︎□◼︎□◼︎
ルシウスがアメンタリの王女との結婚を知ったのは、エルザが入院している病室でのことだった。
しかも、それもその報せは父である将軍からではなく、テレビ報道だ。アナウンサーが笑顔で読み上げた原稿に言葉をなくしたルシウスは、おめでとうございますと言う、どこか呆然としたエルザからの言葉で、ようやく我に返った。
冗談ではない。
ルシウスの気持ちを表すのなら、その言葉以上に適したものはなかった。この結婚が平和のためだと言うのなら、余計に冗談ではなかった。しかも、相手はまだ年端もいかない少女だ。あり得ない。
納得のいかない現実は覆すべきだ。父である将軍に抗議するべく立ち上がったルシウスの手をエルザが掴んだ。だが、ハッとなった彼女はすぐにその手を離す。
「も、申し訳ありません」
エルザがここまで狼狽えることは滅多にない。まだ現実が消化し切れていないことが、彼女の顔にありありと出ていた。
ともすれば、エルザは知らない間に結婚を決められたルシウスよりも動揺している。ルシウスは一旦息を吐き、エルザの肩に手を置くと彼女の瞳を真っ直ぐに見つめた。
「アメンタリの王女とは結婚しない」
「しかし、大佐。それは……」
ルシウスとリジカの結婚は、すでに大々的に発表されてしまっている。本人の了承はないにしろ、これはすでに決まったことでしかない。
「少尉。もう一度言う。彼女と結婚はしない」
「し、しかし……っ」
エルザの心の中はぐちゃぐちゃになっていた。自分は部下として、軍人として、ルシウスを支えなくてはならない立場にいる。アメンタリ王女との結婚で、彼は次期将軍としての後ろ盾を他国にも持てることになる。それは非常で喜ばしいことであるはずなのに、上っ面の言葉でしか目出度いと思えない。相反する感情に脳が混乱し、エルザの目に涙が浮かんだ。
「……エルザ」
こぼれ落ちそうになった涙に気づき、慌ててそれを拭おうとしたエルザは、当然ルシウスに抱きしめられて息を呑んだ。
「た……大佐」
「結婚はしない。信じてくれ」
「……しか、」
しかし、それはルシウスのためにならない。そう言いかけたエルザの唇は、ルシウスによって塞がれていた。
ルシウス直属の部下になる前から、エルザは彼の遊び癖を噂で聞いて知っていた。ルシウスはその容姿から、一度パーティーに出席すれば、その場限りの適当な女性と一夜を共にすることは定番だった。
彼は女性選びが上手く、決して家柄のいい令嬢には手を出さない。どうやっても自分とは不釣り合いな相手を選んで一夜限りの愛を囁く。彼はこれまで女性に本気になったことはなく、これからもないだろうと思えた。それが自ら命を絶った母親の死に関係あるかどうかはわからなかったが、エルザに詮索する気はなかった。大佐としてのルシウスの働きは申し分なかったためだ。部下である自分はプライベートにまで干渉するべきではない。公私を混同すると碌なことにはならない。
ルシウスは相手を選ぶ。だから彼はこれまでエルザにも触れたことすらなかった。仕事柄ふたりきりになることは何度もあったが、男と女の関係にはならなかった。自分がルシウスの興味の範疇にいるとは思っていないエルザは、自分がいつしか彼を愛していたことにも気づいていなかった。
「……ん」
唇が離れると、エルザは小さく吐息を漏らす。まるで精巧な人形のように美しいルシウスの顔は、鼻先がか擦れるほど近くにあった。
「すぐに戻る」
「……はい」
夢心地のエルザにもう一度軽く口付け、ルシウスは病室を後にした。
昼過ぎになり、ルシウスはようやくゴッドバウムとの面会が許された。
実の息子が父親と会うだけにいつまで待たされるのだ。毎度のことながら手続きをしなければ会うこともできない父にイラついたルシウスは、部屋の前にいる秘書を押し退けるように執務室へと入った。
秘書からは将軍は忙しいと聞いていたが、窓際に立って外を見ているゴッドバウムはとてもそうは見えず、ルシウスが室内に入っても彼を見ようともしなかった。
一歩進むと、ジャリっと砂を踏み、ルシウスはその端正な顔を歪める。いくら掃除をさせても砂が部屋に落ちている。以前、廊下ですれ違った清掃会社の従業員がボヤいていたのを思い出す。
「何の用だ」
靴裏にこびりつく砂を床に擦り付けて取ろうとするルシウスに、ゴットバウムが話しかけた。息子から話しかけることはあっても、父から言葉をかけたことは母の葬儀以来かもしれない。お世辞にも安らかとは言えない母の死に顔を見て、ゴットバウムはルシウスに言った。おまえは間違えるなと。
「私はアメンタリ王女との結婚を望んでいません」
ルシウスはキッパリとそう言った。
「……娘とおまえの結婚をと望んだのはアメンタリ王だ」
「どちらからだって同じことです。結婚はしません。しかも彼女はまだ子供でしょう」
正式な年齢はルシウスの知るところではなかったが、テレビ画面に映し出された顔写真を見る限り、リジカの年齢は妹のココレットとさほど差があるようには思えなかった。
「年齢は関係ない。たとえ、赤子であってもアメンタリは王女を差し出しただろうな」
「アメンタリと和平を結ぶつもりなどないのでしょう」
アメンタリから差し出されたリジカは人質だ。リジカをルシウスの妻にすることで、スタフィルス軍の侵攻をアメンタリは食い止めたい。だが、それが不可能であることをルシウスは知っていた。
「グンニグル」
その兵器の名前を聞き、ゴッドバウムはようやくルシウスを見た。隻眼である彼に目はひとつだけしかないのに、大半の者はその視線に萎縮する。得体の知れない恐怖ゆえにだ。
「グレイスター社の大型爆弾だ。知らないとは言わせない」
「………」
「和平を願うなら不要な代物ではないのですか」
「私が願うのは和平ではない。支配からの解放だ」
ゴッドバウムはゴキリと首の骨を鳴らした。
「解放……?」
ゴッドバウムの言っていることの意味がわからず、ルシウスはただその言葉を繰り返す。解放とは、どんな意味で言っているのか。父が宗教に傾倒していると言う話は聞いていない。しかし、自分が父を完全に理解しているとは言えない。理解できない彼の言葉はルシウスにそんな不安を抱かせた。
歴史は繰り返す。狂人がトップになった国は長くは続かない。狂人の欲望は果てしなく、そして大きくなりすぎた国家はやがて内側から腐って崩れていく。
「解放とは……」
「失礼しますぞ。将軍閣下」
ノックもなく、そう言って入ってきたのはヘリオスだった。振り返ったルシウスの目に、気まずそうな秘書の顔と、もうひとり。報道でその顔を見たばかりの少女の姿があった。
「これはこれは、ルシウス殿。ちょうど良かった。あなたの花嫁をお連れしましたぞ」
ルシウスが先客であることはわかっていただろうに、わざとらしく鉢合わせしたような態度で、ヘリオスはルシウスの肩を強い力で叩くと、自分の後ろにいる少女、リジカ王女を紹介する。
「いやあ羨ましい」
私も20年若ければと、ヘリオスは場違いな大声を上げて笑った。
何をばかなことをと、ルシウスは心中で毒づく。ヘリオスの年齢はルシウスよりもゴッドバウムに近い。20年若くとも、まだ10代のリジカとは不釣り合いでしかなかった。ルシウスでさえリジカとは倍の年齢差がある。
「あ、あの……」
浅黒い肌に真紅のワンピースを着た少女は、怯えた様子で視線を彷徨わせて、やがてルシウスと視線が交わる。
「り……、リジカ・エド・アメンタリ、です……」
「………」
ルシウスは何も言えなかった。リジカは報道された写真で見るよりまだ幼く見えたからだ。そして、その怯えた様子は妹のココレットを彼に連想させた。
「る、ルシウス様におかれましては、ご、ご機嫌うるわしく……っ」
リジカはワンピースの裾をわずかに持ち上げ、震えながら必死に言葉を探している。自分の一言で母国がどうなるかわからない。もしゴッドバウムの息子の不興を買えば、アメンタリもバルテゴやフィヨドルの二の舞になるかもしれない。ひとりの少女が受け止めるにはその責任は重過ぎるものだった。
「リュケイオン大佐。姫君は長旅でお疲れだ。屋敷へお連れして差し上げるのがよろしいのでは?」
「まだ話が───」
「ルシウス。話は終わりだ」
ゴッドバウムはすでに窓の外を向いている。母と話をしているときもそうだった。母が一生懸命に話しかけているのに、ゴットバウムは窓の外を眺め、心ここに在らず状態で相槌だけを降っていた。幼心にも、自分と母親が愛されていない事実をルシウスは感じていた。母が死んだそのときから、ルシウスにとってゴッドバウムは他人よりも遠い存在になった。
「あの……」
リジカがルシウスを呼ぶ。ゴッドバウムの部屋を追い出され、その前で立ち尽くしていたルシウスは、ようやく彼女の存在を思い出した。
廊下には彼女付きの使用人だろう女性も数人いて、ルシウスと目が合うと顔を赤らめる。母国がこれからどうなるかもわからないと言うのに、女というものは呑気なものだと思いながら、ルシウスはリジカの前へ跪いた。
「お待たせして申し訳ありません」
「い、いえ……そんな……」
もはや、幼い王女に国に帰れとは言えない。敵地の中心で怯えきっている彼女も、彼女の意志でここへきているわけではないのだから。
(お互い……似たもの同士か)
「お疲れでしょう。今日はひとまず屋敷へお連れ致しましょう」
「はい……」
ルシウスが手を差し出すと、リジカは恐る恐るそれに掴まった。
□◼︎□◼︎□◼︎
―――グレイスター本社。
ナツキは自分の頭ひとつ分よりも背の高い男2人に両脇を固められ、その高層ビルの通路を歩いていた。
その顔は暗く沈んでいる。レイジのところを抜け出したのは、たぶん3日ほど前のことになる。実際の経過日数は不確かだが、窓の外の景色を見つめ、ナツキは意識を取り戻してからの日数を数えていた。
ナツキはF地区の自宅で発作を起こし、その意識は暗転した。次に目覚めた時には、すでにこの高層ビル一室に連れてこられていた。扉に鍵がかけられているわけではなかったが、その入り口に四六時中恰幅のいい男たちが見張りにつけば、まだ施錠されているほうがマシだ。
レイジの時も外出は禁じられていたが、それはナツキを想うが故の言いつけだと納得できた。呼吸器官が弱いナツキは、いつどこで発作に襲われるかわからない。案の定、抜け出した先で発作を起こしていまこうなっている。
(レイジさん……心配してるだろうな……)
何も言わずに抜け出したりするんじゃなかった。そんな後悔をしても、レイジに連絡する方法さえない。ナツキがため息をつくと、両脇を歩いていた男たちの足が止まる。
「お入りください」
「あの……やっぱり人違いじゃ……」
自分はこんなビルに呼ばれるような生まれじゃない。身体が弱く、家からほとんど出られなかったナツキでも、自分が最下層の家に生まれたことはわかっていた。
だが、男たちは無言のまま、早く入れとナツキを威圧する。ほかの選択肢はなさそうだ。仕方なくナツキは扉を開けようとするが、それは手を触れる前に勝手に開いた。
レイジに連れられていった軍の施設内で初めて、ナツキは初めて自動扉を見た。そのため、ここも軍の施設なんだろうかと思いながら中に入る。
ハルヒと会えなくなって何日経っただろう。レイジはずっと姉を探してくれていたが、一向に手がかりは掴めなかった。最悪の事態が何度もナツキの頭をよぎったが、ナツキはその度その思考を振り払った。ハルヒまで自分を置いていくわけない。そう自分に言い聞かせた。
室内は想像よりもずっと広く、大きな窓からはスタフィルスの街並みが小さく見えた。自分がそれだけ高い場所にいることを再認識したナツキは、どんどんハルヒから遠ざかっているような気になり、ますます心細くなる。そのときだった。
「みゃおん」
「え……?」
その声に顔を向けると、そこには猫がいた。これまで、腹をすかせてガリガリに痩せた野良猫なら見たことがあったが、ナツキの足に擦り寄るのは長い毛並みの美しい、スタフィルスには生息しない種類の長毛猫だった。
人懐っこい猫はなおもナツキの足に自分の身体を擦り付けている。ナツキは手を伸ばし、その猫を抱き上げた。温かな体温と柔らかい毛並みが頬に触れ、ずっと緊張しっぱなしだった心がいくらか解れていく。
「その子、マリアンっていうねん」
ナツキがそうしているとその声はかかった。そこには男がひとり立っていて、ナツキはビクッと肩を震わせる。
「何年か前に、フィヨドルからわざわざ取り寄せたんよ。可愛いやろ?」
「は、はい……」
ナツキは男の顔を知らない。だが、相手は自分のことを知っているように話しかけてきて、ナツキは軽く混乱しながらも返事をした。
「いややわ。そんな緊張せんとって。ナツキ・シノノメくん」
男がそう言うと、ナツキの腕にいたマリアンが飛び降りた。タタタッと身軽に走るマリアンから抜けた毛がふわふわと漂う。
「僕はクリム・グレイスター」
「ナツキ……シノノメ、です」
相手は自分のことを知っているようだったが、とりあえずナツキは自己紹介をした。
「あれ?」
「え?」
「僕のこと知らへん?結構有名人やと思うんやけど」
「ご、ごめんなさい……っ」
ナツキは首を振る。
「あ、あのっ……」
「ああ。ええよええよ。気にせんとって」
けほっとナツキはむせる。
「まあ、座ってや」
クリムはそう言って大きなソファーを勧めた。クリムが自分をここへ連れてきたのなら、聞きたいことは山ほどあった。質問をするためには、まずは言うことを聞くべきかと、ナツキはソファーに腰掛けた。
「まずは、手荒な真似したみたいでごめんな」
グラスにワインとジュースを注ぎ、クリムはそれをソファーの前にあるテーブルの上に置いた。
「穏便にって頼んだのに、荒っぽいひとたちが多くて困るわぁ」
「……ケホッ」
「でも、きみにもいい経験になったんとちゃう?きみみたいな子があんな無法地帯にひとりウロウロするんは危険やで」
危険も何も、ナツキがいたのは自分の家だ。だが、クリムから見れば貧困地区にあるあの家は危険な場所でしかない。
「あの……ケホッ、どうして僕をここに……ケホケホッ」
「……ええと、大丈夫?」
ヒューヒューと、ナツキの喉は風穴のような音を鳴らし始めた。それに気づいたクリムが眉をしかめる。
「だ、大丈、夫……っ、ケホケホッ、ヒッ、ゥッ、ケホッ」
「ちょ、ちょ、ちょっと?」
ナツキの様子は明らかにおかしい。急激に青ざめていったナツキは、やがて喉を押さえてソファーに倒れた。
クリムはすぐさま医者を呼び、ナツキのシャツの胸元を緩める。
(何かのアレルギー?報告書にはなかった。何も口にしてへんから、発作的なものか)
苦しそうに呼吸を繰り返すナツキに、クリムは水を入れたグラスを差し出した。
「ちょっとだけ飲み」
言われた通り、ナツキはグラスの水を少し飲む。それを繰り返した。そうしていると、だんだんと呼吸が穏やかになっていく。やがて医者が来る頃には、ナツキは正常な呼吸に戻っていた。
原因は猫の毛でしょうと医者に言われ、すぐさまクリムはマリアンを別室へ連れていくように指示を出した。
「迷惑かけてごめんなさい……」
ようやく話せるようになったナツキはしょんぼりと肩を落とした。
「ええよ。気にせんとって」
クリムはナツキが虚弱体質であることを知らなかった。だが、偶然のこととはいえ、これを利用しない手はない。だから嘘をつくことにした。
「僕も子供の頃は砂嵐のたびに発作起こしてたから、なんか懐かしいわ」
「ほんとですか?」
これは商談の際に培ったことだ。相手の警戒心を削ぐために一番手っ取り早いのは、共感を持たせることだ。実際のところはクリムはナツキと違い、喘息の発作には縁がなかった。
ほら見ろ。クリムは内心ほくそ笑む。クリムが自分と同じ体質だったと言うだけで、ナツキの目の色はさっきまでとまるで違う。
「昔のことやけどね。それはそうと、ナツキくんはあんまりお姉さんと似てへんねんな」
「……姉ちゃんを知ってるんですか?」
「あれ、聞いてない?友達やねん」
「友達……」
ナツキはクリムの顔をまじまじと見て、ハルヒとした会話を思い出す。
「あの……間違ってたらごめんなさい。クリムさんって、その……姉ちゃんの恋人ですか?」
あの日、デートだったのかと聞くとハルヒは違うと言った。だけど意を決してナツキはそう聞いてみる。すると、クリムはにっこりと笑顔を見せた。
「内緒にしとってんけど、そうなんよ」
まるで住む世界が違うハルヒとクリムがどうやって知り合ったのかは謎だ。だが、ナツキはそれよりも聞きたいことがあった。
「姉ちゃんはどこにいるんですか?」
レイジでも見つけられなかったハルヒの居場所を、クリムなら知っているかもしれない。その期待で胸が膨らむ。
「残念やけど―――」
だが、クリムの言葉はナツキの期待を打ち砕くものだった。急速にしぼんでいくナツキの笑顔に、クリムは満足そうだった。ほんの数分の会話で、ナツキと言う人間の内面を深く見ることができた。
ナツキを揺り動かすもの、それはハルヒだ。そして、ナツキの中で、最愛の姉の恋人として自分は君臨した。目で見てわかるナツキの気持ちの浮き沈みに、クリムはその肩を撫でた。
「ナツキ君。―――僕ら、力を合わせられへんかな」
「え……?」
「ハルヒは僕にとっても大事な人や。それが、どうやら悪い奴に騙されとるみたいで―――僕は彼女を助けたいねん」
ルシウスがテロリストの、それも小娘に夢中になっている。その話を人づてに聞いたときは、つまらない話だと思った。だが、ふいに興味が湧いた。あのルシウスの興味を惹くテロリストとは、どんな女なのだろうと。
ルシウスとクリムは友人であり、学生時代からライバルでもあった。だが、貴族階級であるルシウスの家柄には、商人としてのし上がってきたグレイスター家には太刀打ちできないものがあり、クリムはそれに何度も歯がゆい思いをしてきた。
生まれという、自分ではどうにもできないことで、ルシウスと差をつけられるのが悔しくも憎らしくもあった。そして、クリムはいつしかルシウスが興味を抱くものを欲しがるようになった。
「クリムさん……」
捩れを、歪みを、闇を知らない真っ直ぐな瞳。ハルヒとナツキで共通するのはそれくらいだろうか。クリムは手帳に挟んでいる新聞記事の切抜きを思い出す。
ルシウスが失態を犯し、クリムがそれに腹を抱えて笑ったあの裁判の日、各新聞社がこぞって一面に押し出した記事と写真。そこには両親を爆破テロで殺されたという悲劇の少女の写真が掲載されている。
のちに、テロリストの一味であることが判明したその少女が真っ直ぐにカメラを睨み付ける視線と、疑うことを知らないナツキの視線は、込められた意味は違っても、そこには確固たる意志が存在していた。
□◼︎□◼︎□◼︎
朝から姿がなかったハインリヒが戻ったのは、翌日の昼だった。いまのいままで何をしていたかわかるような香水の匂いを纏ったハインリヒが、リュケイオン家に足を踏み入れることすら嫌で仕方ないメアリーは、嫌悪感をその顔に浮かべて食堂から出て行ってしまう。
「だれのところに行ってたんですか?」
アキが聞くと、アマンダちゃんと答えが返ってくる。新しい恋人なのか、それはアキも知らない名前だった。
ハインリヒの交友関係は深いようで浅く、狭いようで手広い。人物像と同じで掴みどころがないのだ。そんな彼に記者と言う仕事はまさに天職だった。
「熱烈な女性なんですね」
「わかるか?」
「シャツが口紅だらけなんだよ」
そうハルヒに指摘される。いくら目ざといハインリヒでも、背中についた口紅までは発見できなかったようだ。
「すぐに替えをお持ちしましょう」
やり取りを聞いていたセバスチャンがそう言い、サッと部屋を出ていった。
「なにか収穫はありました?」
ハインリヒはここではない逃げ場所を探しにいっていたはずだ。ハインリヒの考えそうなことは、長年の付き合いである程度わかる。だからアキもハインリヒが戻るまではリュケイオン邸で待っていた。
すべてお見通しのアキに、降参とでも言うようにハインリヒは両手をあげる。その右手にはアキの写真付きの身分証明書があった。
「それ……」
身分証明書は肌身離さず持っていたが、軍の施設に捕まったときに奪われた。ハインリヒがそれを奪い返したとは思えない。案の定、差し出されたそれは偽造された身分証明書で、氏名も年齢もまったくのデタラメだった。そして、それはハルヒの分もあった。
「これでお嬢ちゃんと出国しろ」
「は……?」
聞き返したのはハルヒだった。
「スタフィルスじゃなけりゃどこでもいい。ここより安全な国へ逃げろ」
「………」
アキは偽造された身分証明書を無言で見つめる。ハインリヒはこれを作るために姿を消していたのだ。だが、さすがに国外まではアキの予想外だった。
「勝手なこと言ってんじゃねえぞ!」
ナツキを置いて逃げることなんかできない。ハルヒはふたり分の身分証明書を掴むと、ハインリヒに向かって思い切り投げつけた。そこへカゲトラが戻ってくる。
怒りをあらわにしたハルヒと、考え込むアキ。そしてそれをハラハラと見ているココレットという、食堂に漂う嫌な雰囲気にまずため息をつく。カゲトラはいま戻ったばかりではあったが、床に落ちたハルヒの写真付きの偽造身分証明書を見れば、大体の話は理解できた。
「おまえと同じ考えだったとはな……」
そう言って、カゲトラは胸ポケットからやはり偽造した、アキとハルヒふたり分の身分証明書を取り出した。
「トラ……!」
「ハルヒ。この国じゃもう逃げ場がない」
王宮に助けを求める以外には。カゲトラはそれを言葉にはしなかった。
「ナツキは俺が必ず連れていく。だから先に逃げろ」
「嫌だ!」
ハルヒは絶対に譲らない。心の中ではまだ迷いながらも、カゲトラはアキにハルヒを託そうとしていた。
「どこに逃がすつもりだ」
ハインリヒがカゲトラに聞いた。
「アメンタリを考えている」
「だめだ。あそこが一番危険だ」
「王女を差し出してきたばかりだぞ」
カゲトラの反論にもハインリヒは首を振る。
「グレイスターが動いてるって話だ。すぐにでも戦争になる」
「冗談だろ」
「カゲトラさんよ。俺は腐っても記者だぞ。情報掴むのはあんたより得意なんだ」
「人質がいるのにか?」
「あんな娘っ子ひとりでゴッドバウムが止まるとは思えない。俺らの業界じゃあの男は砂の悪魔だってもっぱらの噂だ。なあ、アキ」
同意を求められたアキはとりあえず頷いた。実際、ゴッドバウムは得体が知れない。バルテゴを滅ぼした後、何年も姿を見せなかったこともあり、一時は死亡説も流れていた。随分あとになり、スタフィルスで刊行された過去の記事を読んでアキはそれを知った。
「我らが将軍閣下は明日にはリジカさまの首を突き刺した槍持って、アメンタリの戦場に立っててもおかしくねえ男だぞ」
「で、でも」
ココレットが口を挟み、全員の視線が彼女へ向いた。
「あの……リジカさまは、お兄様と結婚される方ですし……お父様もまさかそんなこと……」
ただの人質じゃない。ココレットはそう言いたいのだろうが、ハインリヒは頷かなかった。
「娘であるお嬢ちゃんには悪いが、俺たちの国のトップはそんな人間だ。この国はそんな国なんだ。あのバルテゴにだって、スタフィルスは和平条約を結ぶと言いながら攻め込んだ」
ココレットの顔は蒼白になっていた。自分の父と兄が、他国に嫁いできた王女を殺してアメンタリに戦争を仕掛ける。そんなことを信じたくはない気持ちはわかるが、これが現実だ。
「ならどこに逃がすんだ」
「アメンタリ以外なら、マーテルはどうだ」
アキが小さく息を詰めたが、それに気づくものはだれもいなかった。
「あそこなら海の向こうだ。進軍しようったってそう簡単にはできねえし、マーテル海軍は世界屈指の軍団だ。……アキ?」
「あぁ……。そう、ですね……」
アキは取り繕うように頷く。様子がおかしいことはわかったが、いまはそれを問い詰めている時間もハインリヒには惜しかった。
「俺はナツキを見つけるまで絶対にこの国から出ねえぞ!」
「お嬢ちゃん。そんなこと言ってる場合じゃねえんだ」
「てめえに命令される筋合いはねえ!」
「アキを殺すのか!」
ハインリヒが声を荒げる。直接的なその言葉にハルヒは言葉を失った。
「わかってくれよ……!このままこの国にいたらふたりとも殺されるんだぞ」
「社長、待って」
アキが止めようとするがハインリヒは止まらない。
「だいたい、お嬢ちゃんの弟はまだ生きてんのか。いなくなってもう何日経って……」
ゴッという、骨と骨がぶつかる音が鳴り、ココレットが悲鳴をあげる。ハルヒに顔を殴られたハインリヒは、椅子を巻き添えにして床に尻餅をついた。はぁはぁと息を切らすハルヒは、拳を握り締めたまま部屋を出て行った。
「……強烈だな」
まともに殴られた頬をさすり、ハインリヒは口の中に滲んだ血をぺッと床へ吐き出した。それは手加減したほうだと、カゲトラが鼻で笑った。
□◼︎□◼︎□◼︎
ルシウスに対し、アメンタリ侵攻への徴収命令が降ったのは、エルザが退院したその日だった。
それにより、復帰したエルザの初仕事は、ルシウスの荷物をスーツケースへ詰め込みになった。エルザは自分も同行することを願い出たが、復帰したばかりで戦地に連れて行くわけにはいかないと、ルシウスはそれを許さなかった。代わりに彼は、屋敷に残していくことになるリジカの護衛をエルザに命じた。
国民のほぼ大半の予想通り、アメンタリとの戦争は避けられなかった。その事実をルシウスはまだリジカには知らせることができずにいた。どう伝えてもその事実は残酷だ。いまからあなたの国を、家族を焼きにいく。それが政略結婚であろうと、夫となる男に言われることなら尚更に。
「大佐。リジカ様はいま……」
「私の屋敷に置いている」
「……大佐」
「先日言った通り、私は彼女と結婚する気はない。だが、こうなってしまった以上放り出すわけにもいかない」
「それは重々承知しています。大佐の心遣いに姫君も感謝しておられるでしょう」
「……国を焼かれるまではそうかも知れんな」
自分が将軍になれば、こんな無意味な戦争を止めることができるのだろうか。だが、そのためにはゴッドバウムには死んでもらわなければならない。あの男が生きている以上、将軍の椅子がルシウスに回ってくることはない。
「大佐。お時間です」
時計を確認し、エルザがルシウスに刻限であることを告げると、彼はため息をついて立ち上がる。自分の前までやってきたルシウスに、エルザは準備が整ったスーツケースを差し出した。
「エルザ。……これをきみに」
ルシウスはそう言って、胸ポケットから銀色の懐中時計を取り出した。
「私が戻るまできみが持っていてくれ。母の形見だ」
「そのような大切なものをお預かりすることは……」
「頼む。戦場には持って行きたくない」
「……了解しました」
エルザはルシウスの手から懐中時計を受け取ると、まるでガラス細工に触れるようにそっと手のひらで包み込んだ。
□◼︎□◼︎□◼︎
ナツキが見つかるまではスタフィルスから動かない。それがハルヒの確固たる意志だった。
それでも力ずくで無理やり船に乗せることはできる。どんなに強がってもハルヒは17歳の少女でしかないからだ。だが、その方法をとりたくないのはだれだって同じだった。それにできることなら、ナツキを探し出したいのはカゲトラも同じ気持ちだった。
カゲトラはハインリヒに半日の猶予を頼み、王宮へ向かった。もちろんアメストリアの手を借りるためだ。彼女が手を貸すかどうかは自信がなかったが、ほかに頼れる存在はいなかった。アメストリアに頼ることはハルヒに伏せておいてくれと言い残し、カゲトラが姿を消して数時間後、まったく別のところからナツキの情報はハルヒの耳に届いた。
「グレイスター社のビル……?」
ハルヒは情報を提示したセバスチャンに聞き返す。
「はい。B地区にある、クリム・グレイスターさまのご自宅を兼ねたビルでございます」
「そこにナツキがいるのか?」
ナツキを探していろんな場所へ行った。だが、ブロッケンビルに入っていく車で一瞬見たきり、その姿を見ることはなかった。ナツキはまだ生きているのか。ハインリヒの疑問は、信じたくはないがハルヒだって考えなかったわけじゃなかった。身体の弱い弟が、レイジの庇護を受けずに生き延びている可能性は低かったからだ。
「知人から、それらしき人物がクリム様の部屋へ連れられていくのを見たと聞いております」
今朝、スタフィルス軍はアメンタリへ向かって進軍を開始した。グレイスター社はこの戦争に兵器を提供しているらしいが、その本社にナツキがいるのかハルヒには見当もつかなかった。
「……ここに銃、あるか?」
「ございますが、危険な代物でございます。免許はお持ちですか?」
「あるわけねえだろ」
「でしたらお渡しすることは出来かねます」
「……このこと知ってんのは?」
「お嬢様と私だけでございます」
「……カゲトラが戻ったら、俺がグレイスターに行ったって伝えてくれ。そんで、このことほかのやつには言うなよ」
「おひとりで行かれるつもりですか?」
「ああ」
ハルヒもカゲトラも戻らなければ、ハインリヒは見切りをつけてアキを国外へ逃がす判断をするだろう。ハインリヒにとって重要なのはハルヒではなくアキだからだ。いつまでもナツキを探すことを諦めないハルヒは、ハインリヒにとって邪魔な存在でしかない。
「世話になった。感謝してる。あいつにも……お嬢様にも言っといてくれ」
「お嬢様は、……あなたに憧れておられます」
それにハルヒは吹き出した。育ちのいいココレットに憧れを抱かれるものなんて、自分は何ひとつ持ってはいない。最後に、それは勘違いだとセバスチャンにそう言って、ハルヒはアキとハインリヒがいる中庭を避け、屋敷の裏口から敷地外へ出た。そこで眉をひそめる。
「……そこで何してんだよ」
ハルヒにそんな顔をさせた原因は、そこに立っていたココレットだった。彼女の背後には小型バイクが見えた。セバスチャンから聞いたグレイスター社のビルまでは少し距離がある。ハルヒにとってバイクがあるのはありがたいが、ココレットは不要だった。
「グレイスター社に行くんですよね。私も行きます」
ココレットはハルヒに憧れている。その話をさっきセバスチャンに聞いたばかりだが、お嬢様の冒険につき合う時間はなかった。
「バイクだけありがたくもらっとく」
ハルヒはココレットを押しのけ、バイクのエンジンをかけようとしたが、鍵がついていなかった。チャリンという音に顔を向けると、小さな鍵を手にしたココレットが挑むようにハルヒを見ていた。
「よこせよ」
「私もナツキを助けに行きます」
「おまえには関係ねーだろ」
ハルヒに鍵を奪われそうになったココレットは、慌ててそれを自分の背中に隠した。いつもはヒラヒラとしたワンピースを着ているのに、今日のココレットは動きやすいパンツスタイルであるため、ハルヒの手はココレットを掴めず空振りする。
「さっさと鍵渡して屋敷に戻れ。じいさんの血圧が上がる前にな」
「銃も持ってます!」
そう言って、ココレットは肩から下げたカバンの中から、ガンホルダーと銃を取り出した。
「……弾は?」
入ってないだろと決めつけて聞いたが、ココレットはたどたどしい手つきで弾倉をハルヒに見せる。弾倉は全装填されていた。
「私も行きます」
「……俺はお嬢様の面倒なんか見れねえぞ」
「大丈夫です。自分の身は自分で守ります」
ハルヒはどうしようかと悩む。ここで騒がれたら、アキやハインリヒにバレないようにこっそり出てきた意味がなくなる。
「……わかった」
ここは一旦承諾して、屋敷から離れたところでココレットは捨てればいいと結論づけた。そこで銃も奪ってしまおう。
いまは元気そうにはしているが、あの神様の力を使うたびアキは酷く疲弊する。あのとき、アキの胸の周りの血管は、いまにも破れそうなくらい盛り上がっていた。二度と、アキをあんな目に合わせたくはなかった。
「早く乗れよ。行くぞ」
突っ立ったままのココレットを急かす。
「は、はいっ。運転は私がしますね」
ココレットはそう言ってハンドルを握る。ハルヒは渋々シートの後ろにまたがった。ヘルメットをかぶってくださいねと渡され、恐ろしい低速で走行するココレットからハルヒがハンドルを取り上げるまで、そう時間はかからなかった。
□◼︎□◼︎□◼︎
夕焼けも落ち、薄暗くなってきた中庭で、ハインリヒは白い煙を吐いた。向かい合っているアキの顔には影が落ちていて、その表情はよく見えない。
「―――そうか」
ハインリヒが口にしたそれは、アキの話に対する感想―――返事だった。ふたりは、まだ夕焼けに程遠い時間帯から中庭にいた。
話しておきたいことがあると、ハインリヒはアキに呼び出された。ハルヒのそばにいなくていいのかとからかったが、大事な話だと言われた。アキのいう大事な話とは、レーベル社で一緒に働いていたふたりのことだった。
ブロッケンビルのパーティーに参加して、ハルヒを助けたことでレイシャとはぐれたこと。【トライデント】であるハルヒを庇ったアキのせいで、レイシャはテロリストの疑いをかけられ軍に取り調べられたこと。そのときはカゲトラに救われたが、その後、アキと同じ適合者が放った風によって殺されたこと。
カゲトラから、レイシャはアキが殺したのだと聞いていたハインリヒは、それが彼の早合点とわかり息を吐いたが、レイシャが死んだことに変わりはなかった。
「僕が―――」
「おまえが」
アキの言いかけた台詞を遮り、ハインリヒは吸った煙を吐く。
「おまえが自分のせいだって言うのなら、おまえらをブロッケンビルにやったせいだと、俺も責められるべきだな」
「………」
「物事ってのは、色んな偶然が重なって、必然と化していく。どっかの偉い奴の言葉だ」
たぶんそれはハインリヒがいま作った言葉だ。彼は時々、自分が考えた格言をだれかの言葉にしたがる。
「もう過ぎたことで自分を責めるのはやめとけ。虚しいだけだ」
「……社長」
「あん?」
「ここまで巻き込んでおいて今更だけど、もうこの一件から手を引いて欲しい」
「……本当に今更だな」
アキは長くなった自分の影が、暗闇の中に消えていくのを見つめた。
「バレシアくんはもう戻れない」
イスズは闇の中に取り込まれてしまったから。
「社長はここでリタイアして欲しいんです」
「―――おまえは?」
ハインリヒの問い掛けにアキは首を振る。
「僕もとっくに戻れない」
自然にあげた手が心臓の上で止まる。そこにもう痛みはない。だが、そこには得体の知れない異物が埋め込まれている。
「さぁ、そろそろハルヒの所に戻ろうかな」
「飯の時間だな」
「また先生怒るんだろうなあ、ハルヒの食べ方見て」
「テーブルマナーで人のことは言えないが、あれは論外だぞ」
「あはは」
屋敷に入る扉を開け、アキは笑う。
「おまえ、あのじゃじゃ馬のどこがいい……」
「ちょっとあんたたち!」
屋敷に入るなり、アキとハインリヒの姿を見つけたメアリーが廊下の端からものすごい勢いで走ってくる。
何事だと顔を見合わせるふたりの前まで早足で詰め寄ると、メアリーは持ってるのか持ってないのかと聞いた。
「持ってるって言ってよ!あんたが持ち出してるのよね!?」
「ちょっと先生落ち着けよ。なんの話だよ」
「ああ、やっぱりお嬢様……っ」
メアリーは腰が抜けたようにその場に座り込む。娘のあとを追いかけてきたセバスチャンも姿を見せた。説明はこっちにしてもらうほうが早そうだと、ハインリヒはすぐに話し相手を切り替えた。
「何があったんだ」
「どうやら、お嬢様が金庫を開けられて、中から拳銃を持ち出されたようなのです」
「そりゃ……物騒な話だな。で?」
そんなことをしたココレットの目的はと考えて、アキはハッとする。
「いないのよ。お嬢様も!あのじゃじゃ馬娘も!」
「秘密にしているように申しつかりましたが、ハルヒ様はナツキ様にお会いするため、グレイスター社へ向かわれました」
セバスチャンがそう言った。
「私がその情報をお伝えしたのです」
ココレットもそれについて行った可能性が高い。そうでなければ銃の使い道なんてないと思うが、ハルヒが足手まといでしかないココレットを連れて行ったとは思えなかった。
「僕が追いかけます。ふたりを連れ戻す」
「俺も行く」
4人は急ぎ足で屋敷の玄関へ向かい、セバスチャンが両開きの扉を開けた瞬間、眩しいライトが屋敷内を照らした。
「隠れてッ!」
咄嗟に叫んだアキに従い、ハインリヒは柱の後ろへ逃げ込んだ。アキはすぐ後ろにいたメアリーを抱き抱え、倒れこむように床に伏せる。鼓膜を破るような銃声が鳴り響いたのはその直後だった。
浴びせかけられた何十発もの銃弾は、あっという間に屋敷の玄関ホールにあるありとあらゆるものを破壊していく。悲鳴をあげるメアリーを強く抱きしめ、アキはギリッと奥歯を噛みしめる。
(遅かった……!)
もう猶予は半日もなかった。あたりには、銃弾により破壊されたコンクリートの破片と、真っ赤な血が飛び散っていた。
(間に合わなかった……!)
風で防壁を作る時間もなかった。アキたちより前にいたセバスチャンの悲鳴は聞こえない。その呻き声さえも。
「アキッ!」
いつまでもやまない銃弾の雨に、ハインリヒも身動きが取れない。
「援護しますから先生と奥へ下がってください!」
「援護っておまえ武器もないのにどうやって!」
「行って!」
アキは一瞬の弾を装填するタイミングで身を起こし、メアリーをハインリヒに突き飛ばした。起き上がったときに父親の無残な姿をその目にしたメアリーは、声にならない悲鳴を上げる。その身体を半ば抱えるようにして、ハインリヒはアキに言われたように奥へと走り出す。
「ちくしょおおおおッ!」
また銃声が鳴り出し、ハインリヒは思わず首をすくめたが、弾が飛んでくる気配はなかった。それどころか、あたりはピタッと静かになる。怖くなったハインリヒが背後を振り返ると、玄関ホールにいたアキは文字通り飛ぶように彼に追いついた。
「!?」
ハインリヒは二度見するが、玄関ホールにはだれの姿も見えない上に、扉もなくなっていた。
「その部屋へ!」
アキの指示に従い、ハインリヒは部屋に飛び込んだ。ゼエゼエと息を吐くハインリヒの頬には、最初の銃撃での流れ弾が当たったらしく血がにじんでいた。メアリーは目を見開いたまま瞬きもしない。その顔色は真っ白になっていた。
「おい先生、怪我は?」
「………」
「先生!怪我はないのか!」
「……お父様が、……助けないと」
フラフラした足取りで部屋を出ようとしたメアリーをハインリヒが無言で止めた。どうやってももう助けられない。メアリーは音もなく涙を流し、ハインリヒの胸に頭を押し付けた。
「いったいナニモンだよ……っ」
軍か、研究機関か、まさか白獅子の騎士たちか。ハインリヒの問いかけの答えを探しながら、本当にこの国には敵しかいなくなってしまったことをアキは痛感していた。
「何者かはわからないけど、僕がやつらを引きつけます。その間に逃げてください」
アキはハインリヒにそう言う。狙いはおそらく自分だが、セバスチャンは撃ち殺されている。逃さなければハインリヒやメアリーも危険だ。
「だけどおまえは……」
「僕は大丈夫です」
「……わかったよ」
ここに残ればアキの足手まといになるのだろう。まるでハルヒにとってのココレットだ。自分がそんな立場になるとは思っていなかったハインリヒは苦笑し、アキの頭をガシガシと撫でた。
「C地区の教会は覚えてるか?そこで待ってるぞ」
「はい」
アキと約束したハインリヒは、そっと窓を押し開けて外の様子を確かめる。静か過ぎるのが気持ち悪いが、裏口でも扉を開けるのはもうごめんだった。
「先生。行くぞ。ほら、しっかりしてくれ」
ショック状態ながらも、メアリーはハインリヒの手に掴まろうと手を伸ばしたが、ふたりの手が触れるその前に、ハインリヒは緑色の触手に肩を貫かれ、その勢いのまま天井に叩きつけられた。
メアリーの悲鳴が響き渡る中、アキが放った風が触手を切り裂くと、支えを失ったハインリヒは床に落下する。
「イッテェ……ッ!」
肩に残っている触手をハインリヒ自身が引き抜くと、そこから勢いよく血が吹き出した。天井近くの壁まで飛んだ血飛沫にアキは言葉を失ったが、逆に医者として冷静さを取り戻したメアリーが、上着を脱いでハインリヒの傷口に押し付けた。淡い色をしていた彼女の服は見る間に赤く染まっていく。
「やっと見つけた……」
窓の外から聞こえたその声にアキが息を呑む。そこにはイスズの姿があったが、彼の姿は異形と化していた。その5本の指は失われ、代わりにそこから触手が伸びている。その一本は途中で切り裂かれていて、これがハインリヒを貫いたものだと推測できた。
「バレシア……っ」
ハインリヒが呟くように彼の名を口にした。アキの話では聞いていた。だが、聞いた話と実際に見るのとではわけが違う。アキの言った、戻れないと言う言葉の意味をハインリヒは痛みとともに噛み締めていた。
「こんばんは。社長」
イスズは笑顔で挨拶をする。それはまるで毎日出社していたときのように、それよりも和やかな口調だった。
「社長もグルだったんですか。そうですよね。クサナギ先輩は社長のお気に入りですものね」
「……バレシアくん」
何も言い返せないハインリヒに代わり、アキがイスズを呼んだ。
「お願いだ。ふたりは……傷つけないでほしい」
イスズが出てきたということは、ヴィルヒムたちがここを嗅ぎつけたということだろう。やはり長い時間ここへとどまるべきじゃなかった。後悔しても遅いとは思っても、せずにはいられなかった。
「きみが憎いのは僕だろ……?だったら僕だけを―――」
どんっと、イスズの触手が壁を砕く。メアリーの頭上にパラパラとコンクリートのカケラが降り注いだ。
「関係ないことはないでしょう?先輩とテロリストを匿っていたんだから、裁判やってもどうせ死刑ですよ。だったらいま死んでも一緒だ」
そう思いませんかと言うイスズの問いかけに答える声はなかった。
「そう言えば、あのテロリストはどこですか?僕、先輩の目の前であのクソ女の首を吹っ飛ばしたいんですよ。こんなふうに!」
メアリーの首を刎ねようとしたイスズの右腕を、アキの放った風刃が切断した。肩から切断された異形の腕は、イスズの背後にドシャッと落ちる。
何が起こったのかハインリヒにはわからなかった。だが、アキが何かをしたのだと言うことはわかった。カゲトラが言っていたのはこのことだったのだと、ようやく彼は理解し始めていた。
「……痛いなあ」
ぼそり、とイスズは呟いた。切断部分から出血していないのはどんな手品なのか、ハインリヒが目を疑う中、その切断部からはまるで生き物のような動きで新たな緑の触手が生え出してくる。
うねりながら伸びた触手は、だんだんとその色と形を変えて、イスズの右腕を形作っていく。見る間にイスズの腕は再生してしまった。
「先輩の力じゃこんなことはできないんでしょう?」
アキは黙ったままイスズを見ていた。
「先輩にできるのは、ミナシロさんにしたように、切り刻むだけですもんね!」
イスズの右腕が勢いよく伸びた。ドリルのように回転しながら伸びてくる腕を、アキは風刃で弾く。だが、触手のドリルは切り刻まれる側から再生され、襲いかかってくる。
「ぐっ……!」
アキの手数が落ちればイスズの攻撃を捌き切れなくなる。いつまでもこの状態が続かないことはわかりきっていた。
「アキ……!」
自分とメアリーがここにいることで、アキは防戦一方を強いられている。どうすればいい。それを探ろうとしたハインリヒは、イスズの頭上、天井にひびが入っていることに気づく。
「アキ!上だ!」
ハインリヒに言われたアキは天井を視界に入れると、身体をひねって触手のドリルを避け、そこに風をぶつけた。
「!?」
崩れ落ちてくる天井にイスズも気づいたが、わずかに遅く、その崩落に巻き込まれてその姿は瓦礫の下に見えなくなる。アキは走りながら身を起こし、メアリーごとハインリヒを抱えると、風に乗って屋敷を飛び出した。
□◼︎□◼︎□◼︎
ハルヒとココレットはグレイスター社の非常口からビル内へ入り込み、まずはココレットが扉の前に立っている兵士を監視カメラが届かない位置まで引き寄せた。
まだ幼さは残るが、容姿端麗なココレットに目を奪われた好色な中年兵士は、足音をたてずに近づいたハルヒに後ろから首を絞められて昏倒した。あっけなく倒れた兵士の腰から銃を抜き取り、ハルヒは武器を手に入れる。
グレイスター社に来るまでの間に、頼んでもいないのにペラペラ喋ってくれたココレットからの情報で、クリム・グレイスターがルシウスの友人であることが判明していた。
目指す副社長室はこのグレイスター社ビルの最上階にある。以前、このビルの完成披露パーティーに招待されたことのあるココレットは、おぼろげながらビルの内部を記憶していた。
万が一の時に早急な対応ができるように、社長室は最上階まで上った後、非常口を出て真っ直ぐ突き当たりにある。50階まで続くこの階段さえ上りきればゴールは見えていた。
「はあ、はあ……」
20階を越えた辺りで、ココレットは息を切らして手すりに体を預けた。すでに鉛のように重くなった足は、気力だけでは持ち上がらなくなっている。数段上にいるハルヒが振り返った。
「す、すみません……っ」
ココレットは慌てて足を上げようとするが、疲弊しきった身体は思うように動かなかった。躓いて、顔から階段に倒れそうになったココレットを、素早く降りてきたハルヒが受け止める。
「ご、ごめんなさい……っ」
ふうっとハルヒはため息をつく。
ハルヒに呆れられてしまった。ココレットは泣きそうになるのをぐっと堪えた。
「飲め」
「えっ?」
ハルヒは腰にぶら下げていた水筒をココレットに押し付けた。
ビルの中は空調や温度設備も整っているのだろうが、普段は使われない非常階段にまでは配慮されていないようだ。いまはもう日も落ちているが、昼間のむせ返るような熱気が密閉された空間に満ちていた。
普段、空調のきいた部屋で過ごすことの多いココレットは大量の汗をかいているが、この暑さに慣れているハルヒはそうでもない。そもそも、ふたりは基礎体力から違っていた。
「でもこれはハルヒ様の……」
「俺はおまえほどバテてない」
ハルヒの言葉通り、彼女は汗ばんでいるがココレットほどではない。ココレットは小さな喉を鳴らして水を飲み、口を離すとまた謝る。
「おまえなんでそんな謝るわけ?」
「えっ?」
「さっきから、何回謝んだよ。しつこいな」
「ご、ごめんなさ―――」
「ほらまた」
ハルヒに指摘され、ココレットは顔を赤くした。これだけ何度も謝られたら、誠意がないと思われても仕方ない。ますます沈み込んだココレットに、ハルヒはため息をついた。
「顔上げろ」
「………」
「それにおまえ、なんですぐに下向くんだよ」
それは相手の冷たい視線に耐えられなくなるからだ。本当はいじけたくないのに。前を向いていたいのに。ハルヒみたいに強くなりたいのに。
泣きそうな顔でなんとか笑おうとするココレットを見たハルヒは、その両頬を挟み込むようにパチンと叩いた。
「笑いたいなら笑って、泣くなら泣けよ」
「ハルヒ様……」
「様をつけんな」
「えっ、と……」
「呼び方、おまえはココでいいな。全部呼ぶの長いから」
そんなに長くはないと思いながらも、ココレットは頷いた。ハルヒは自分に助け舟を出してくれたのだ、そう理解して。
「ハ、……っ、ハル!待ってくださいっ」
同じく呼び名を二文字に省略したハルヒの後を追い、ココレットはなぜだか軽くなった足で彼女を追いかけた。
ハルヒとココレットはどうにか50階まで階段をのぼりきり、ゆっくりと非常扉を開く。視界内にだれもいないことを確かめ、ハルヒはビル内へと足を踏み入れた。夜明け前という時間であるため、ビル内にひとの気配はない。逆に怖いくらい静まり返っていた。
ハルヒに続き、ココレットも非常灯のみがついた廊下に出ると、副社長室が肉眼で確認できた。クリムの部屋だ。
社員が出社してくる出勤時間までは、後3時間ほどある。それまでにやることはひとつだ。足音を立てないように進みつつ、ハルヒは腰から銃を引き抜いた。室内からは明かりが漏れている。
「おまえはここで待て」
一緒に行こうとしたココレットにハルヒは言った。
「えっ」
「脱出ルートの確保を頼む」
反論は許さないと言うように畳み掛けられて、ココレットはその場で立ち止まるしかなかった。
ハルヒは足音を立てないようにクリムの部屋へ近づく。すると自動扉は歓迎するように勝手に開いた。慌てて壁際に張り付いて息を整え、慎重に室内を確認する。
(だれもいない……)
視界が届く範囲に人影はない。だが、室内は広そうだ。ここからでは部屋全体を見るのは難しいだろう。そう判断し、ハルヒは室内へと足を踏み入れた。
10人は座ることができそうな大きなソファーの前には、ワイングラスがふたつ置かれていた。中身はまだ残っている。大きな窓からはスタフィルスの夜景が遠くに見えて、のぼって来た高さを思わせた。
執務室にはクリム・グレイスターの名が書かれたプレートが置かれていて、ここが目的の場所で間違いないことをハルヒに教える。
「にゃおん」
「!」
反射的に銃に手をハルヒは、そこにいた猫に息を吐いた。
「猫かよ……」
いままで見たことのない種類ではあるが、猫に間違いはない。金持ちが住む地区の猫は毛並みがいい。おそらくこの猫は毎日、F地区の人間よりもずっといいものを食べているんだろう。それも腹一杯に。
人は平等ではない。その運命は生まれた場所でほぼ決まる。F地区生まれのハルヒやナツキが知らない幸せを、目の前の猫は苦労もなく享受している。
「可愛いやろ」
「!?」
今度こそハルヒは確実に銃口を向けた。そこにはバスローブ姿のクリムが立っていた。シャワーを浴びていたらしく、その髪はまだ濡れている。
「マリアンって言うねん」
銃口を向けられていると言うのに、クリムは少しも動じた様子も見せず、濡れた髪を後ろへ撫で付けた。
「……クリム・グレイスターか」
クリムの年恰好はルシウスと同じくらいに見えた。ココレットからの前情報から、おそらく間違いないと思いながら、ハルヒは本人であることを確認する。
「僕のこと知ってるん?嬉しいわ。ハルヒ・シノノメ」
「……!」
「なんで僕がきみを知ってるか?知らんかもしれんけど、きみはテロリストとしてかなり有名やで。もしかしたら彼女より有名かもしれへん。なあ、ココレットちゃん」
ハルヒが振り向くと、そこには室内を覗き込んでいたココレットの姿があった。
「クリムさん……」
「久しぶりやね。こんな時間にどうしたん?」
「お、お願いが……あるんです……っ」
「なんやろか。僕にできることやったらなんでもしてあげる」
緊張感もなくそう言ったクリムの足にマリアンが擦り寄る。
「な、ナツキを返してください……っ」
ココレットは勇気を振り絞るが、声はどうしても上擦った。
「ナツキはここにいるんでしょうッ?」
「お願いってそれなん?」
クリムはクッと笑う。ハルヒはトリガーに手をかけているのに、クリムには余裕さえ感じられる。一発撃って、ナツキの居場所を吐かせるか。だが、銃声が鳴れば警備がやってくる。そうなれば今度は脱出が難しくなる。
「良かったわ」
目論見通りに動いてくれて。クリムがそう言うと、部屋の明かりが消えた。一瞬で真っ暗になった室内で、ココレットの悲鳴が聞こえたのはすぐだった。再び明かりがついた室内でハルヒが見たものは、警備に銃を奪われ、それを頭に突きつけられたココレットの姿だった。
「……やめとけよ。てめえのお友達の妹だぞ」
その情報があるから、ハルヒはココレットをここまで連れてきた。いざとなればココレットを人質にクリムト交渉するか、別の案としてはクリムを引き受けている間に、ナツキだけでも連れ出してもらおうと思っていた。
「そうやなあ。きっとルシウスが悲しむなあ」
カタカタと震えるココレットを、クリムは笑顔で見つめる。
「でも、それもええかも知れへん。実は僕、ずうっとあいつのこと憎たらしいと思てたし、ルシウスにとってココレットちゃんが人質にはならへんことは、きみもブロッケンビルで学んだんちゃうの?」
「………」
「でもやっぱりお友達やから、妹がテロリストになったやなんて、僕はよう言わんわ。そうや。こう言うとこか?ココレットちゃんは僕を庇って、テロリストに撃たれて死んだって―――」
クリムはニヤリと笑う。ハルヒは無言のまま手に持った銃を投げ捨てた。床を滑った銃はクリムの足元で止まる。
「あははぁ。アホみたいに情に脆いテロリストやな。でもまあ、弟のほうも簡単にひと信じるアホやから、似たもん同士か」
「ッ、ナツキはどこ……!」
パンッ!と軽い音がなり、ハルヒの身体はソファーまで吹っ飛んだ。
「えっ」
ココレットはそんな声を上げる。すぐにはハルヒが撃たれたことを理解できなかったからだ。
クリムが引き金を引いた銃から発射された弾丸がハルヒを吹っ飛ばした。時間をかけてその事実を認識すると、ココレットの意識は急激に薄らいでいった。
クリムは呻き声にソファーへ顔を向けた。
「クソ……!」
ソファーの上で、ハルヒは撃ち抜かれた腕を押さえ、脂汗を滲ませてクリムを睨み付ける。
「ごめんごめん。いきなり大きな声出すから、びっくりして撃ってしもたわ」
「ナツキは……、どこだ……ッ」
「教えたとして、その状態でどうやって助けるん?いままでみたいに王子様の助けは期待でけへんで」
王子様とはおそらくアキのことだ。ルシウスもそう言っていたなと思いながら、出血と痛みでクラクラする意識の中、ハルヒはリュケイオン邸に残してきたアキの顔を思い浮かべる。アキのことだ。今頃はもうハルヒがいないことに気づいているだろう。アキなら、自分がどこにいたって……。
「ココレットちゃんの屋敷は今頃、軍の襲撃におうとるはずや」
「……は?」
ハルヒの頭にアキや、いま屋敷にいるはずのメアリーやハインリヒの顔が浮かぶ。
「ステファンブルグはおっとろしい実験する男やから、クサナギくん以外は皆殺しやろなあ」
ゼエゼエとハルヒは荒い息を吐く。ソファーに染み込む量は、とっくに意識を保っていられる許容量を越えていた。
ハルヒがリュケイオン邸を出るとき、アキは回復していた。だからそう簡単にやられるわけがない。きっとみんなを守ってくれる。そう自分に言い聞かせながら、ハルヒは意識を失わないように唇を噛む。
ハルヒの前までやってきたクリムはそのバンダナをつかんだ。結びが緩んでいたために、それはするりと外れ、隠れていた長い黒髪が溢れる。
「あらら。こうして見たらちゃんと女に見えるわ」
その声はもうハルヒには届いていなかった。
□◼︎□◼︎□◼︎
夜が明けて、朝日が昇る。それは母国であるアメンタリも、スタフィルスも変わらない。
しばらく屋敷には戻れない。そう言い残して夫になるルシウスが屋敷を出て、一夜が経過した。眠れずにその夜を過ごしたリジカは、朝の7時を回ってノックされた扉に消え入るような返事を返した。
「おはようございます」
扉を開けて敬礼を見せたのは、ルシウスの命令でリジカの身の回りの警護任務についたエルザだった。
「朝食をお運びいたしました」
エルザがそう言うと、使用人が朝食を部屋へ運んでくる。
「大佐はいつ頃戻られますか?」
「申し訳ありませんが、存知上げません」
扉の前に立ったエルザは簡潔に答える。軍人であるエルザはおしゃべりな使用人とは違い、聞かれたこと以外に無駄なことは口にしない。
「アスタエル少尉」
テーブルに並べられた食事を見つめたまま、リジカは再びエルザを呼んだ。
「大佐はどちらにいらっしゃるのでしょうか」
ルシウスの行き先は聞いていない。軍務に就いている。リジカが夫について知っていることはそれだけだ。
リジカはアメンタリの第5王女だ。彼女には4人の姉がいたが、彼女たちはすでに国内で結婚していたため、ルシウスの花嫁にはまだ子供のリジカが選ばれることになった。
リジカはルシウスと愛し合って結婚するわけではない。だから夫が冷たくても、国のために耐えなさい。母親はそう言ってリジカを送り出した。アメンタリの王族としてリジカはこの国にやってきた。祖国を守るために。
「お戻りになるのを共に待ちましょう」
エルザはリジカを嗜めるように言った。
ルシウスはアメンタリ攻略に参加している。だが、そのことはリジカに伝えるわけにはいかなかった。リジカを心身ともに警護するのがルシウスからの命令だからだ。だが、いまこのとき隠したところで───。
リジカ様と、使用人が悲鳴を上げた。ベッドから起き上がった彼女が、窓枠へ腰をかけたからだ。ここは3階だ。落ちでもしたら怪我ではすまないかも知れない。
「リジカ様。危険ですのでこちらへお戻りください」
どうせ飛び降りる気なんかない。ただの脅しだ。使用人とは違い、そう思っているエルザは慌てず、冷静に対処しようとする。
「私は本当のことが知りたいのです」
手を差し伸べるエルザに、リジカは凛とした表情で言い返す。
「将軍閣下と大佐はどちらにいらっしゃるのですか?教えてください」
さあっ、と外からの風が部屋の白いカーテンを揺らした。エルザは表情一つ変えずにリジカを見つめていた。
「……それを知ってどうなさいます?」
「知りたいのです!」
「答えならすでにリジカ様はご存知なのでは?」
エルザの言い方にリジカの顔色が変わった。
「……ります」
震えているせいでリジカの言葉は聞き取りにくい。アメンタリ訛りは嫁いで数日で消えるものではない。
「リジカ様」
「いますぐ祖国への侵攻をやめなければ、私はここから飛び降りますッ!」
可哀想な異国の姫君。ルシウスの妻になる彼女は、彼を想うエルザにとって決して喜ばしい存在ではないが、その境遇を考えれば十分に同情できた。
「……あなたが自害なされても母国の運命は変わりませんよ」
「……やめて」
すがるような声に、エルザは首を振る。将軍の決定には誰も逆らえない。大佐であり、息子であるルシウスでさえ変えられないものを、エルザにはどうすることもできない。
「お願い、やめさせてっ!」
窓枠から離れ、リジカはエルザにしがみ付いた。
「みんなを助けてっ!」
悲痛な叫びは部屋に響くが、地続きであっても、ここから遠いアメンタリまでは届かない。
「アメンタリを焼かないで……!」
ドズン……!遠くで地響きが鳴った。
エルザは自分にすがりつくリジカの腕を引き離し、部屋にあるテレビのスイッチを入れる。そして、砂嵐のチャンネルを回し、やがてひとつだけまともに映る放送局を見つけた。
テレビの中ではリポーターが興奮した中継をしている。カメラに映るのは、大きく上がるキノコ雲だ。リジカが大きく目を見開いた。
ごらんください。アメンタリ上空は大きな煙に巻かれています。スタフィルスの勝利を確信し、リポーターの歓喜した言葉が飛ぶ。
「いや……」
晴れることのないような巨大なキノコ雲を見つめ、リジカはそう呟いた。その瞳から涙がこぼれ落ちる。
「嫌よ、いや……嫌……!嫌ぁ―――ッ!」
部屋に響き渡るリジカの絶叫と共に、キノコ雲を突き抜けた炎の塊がテレビ画面を横切った。
「アメンタリの神か……!」
エルザが息を呑む。フィヨドルのときに聞いてはいたが、その存在をテレビ画面の中と言えど、目にするのは初めてだった。
バルテゴで、風をまとった神と呼ばれるそれは死の風を巻き起こし、大勢の命を奪った。同じく、フィヨドルで恐ろしいほど巨大な花が毒を撒き散らした記憶は新しい。ヴィルヒム率いる研究機関は、あれらを使って適合者を作り出している。
テレビ画面には、アメンタリ城よりも巨大な二本の角を頭につけた炎の巨人が咆哮を上げ、その身体から火球を撒き散らした城下町はあっという間に炎の海に包まれた。
「……殺して」
あの場にルシウスがいないことを祈るエルザは、確かにそう言ったリジカを振り返った。彼女はテレビ画面を睨みつけ、炎の巨人に向かって命令する。
「あなたがアメンタリの神なら、スタフィルス人を皆殺しにしてッ!」
ごおおおおっ!
炎の巨人が炎を撒き散らす。グンニグルの爆風に巻き込まれないため、降下場所よりずっと離れていたはずの中継ヘリの映像が途絶えた。砂嵐になったテレビにリジカは狂ったように笑い出す。
「大佐……っ」
焦ったエルザは他の放送局へチャンネルを回す。すると、さっきまでは砂嵐だったチャンネルが回復し、また巨人の姿を映した。その身体を形成する炎で、スタフィルスの軍旗が燃え上がっている。
「きゃはははははっ!!」
小さな子供のようなリジカの笑い声の中、エルザは戦場にルシウスの姿を探し、胸ポケットに入れた懐中時計を軍服の上から押さえた。
「―――将軍、ここは危険です!」
エルザとリジカは聞こえてきたその言葉に同時に反応した。テレビに小さく映ったのはゴッドバウムの姿だった。
「閣下!」
ひとり佇んで炎の神を見ている将軍へ、見知った人物が駆け寄る。それはルシウスだった。そこへ向かって炎の巨人が突進していく。ルシウスとゴッドバウムに火炎の雨が降り注ぐ。
まるでリジカの願いを聞き入れたように、炎神がゴッドバウムに突っ込んでいく。自分たちを飲み込もうとする巨大な炎のうねりに肌が焼かれる。もう逃げることはできないとわかりきっていたが、ルシウスはそれでも身構えた。
そのとき、ぶあっと砂嵐が吹き荒れた。舞い上がる砂の粒は、吠え掛かる炎の巨人をあっという間に包み込む。炎神の周りを吹き荒れていた砂により、その炎が消化され小さくなっていく。炎神は砂を振り払おうと激しく暴れるが、無限とも思える数の砂はまとわりつき、離れない。あっという間に燃えたぎる赤い色から砂色に変化した炎神は、やがて力なく地上へ倒れ、動かなくなった。それはあっと言う間の決着だった。
焦土と化したアメンタリの大地に落ちた炎神から抜け出た砂が、地を這いゴッドバウムのもとへ戻っていく。足元から吸い込まれるように姿を消した砂に、ゾッとしたルシウスは、自分の父親から一歩離れた。
(砂の……適合者……)
パチパチパチ、背後で拍手が響く。ルシウスが顔を向けると、そこにはヴィルヒムの姿があった。
「お見事です」
「あとは任せるぞ」
一言だけを残し、ゴッドバウムは軍服のマントを翻してその場を立ち去った。
「これは大佐。先日はどうも」
立ち尽くすルシウスにヴィルヒムが声をかける。
「少尉の具合はいかがです?」
それは、まったくこの場に似合わない社交辞令だった。
放心したようにリジカはその場に座り込んだ。テレビ画面に映ったのは、砂に侵食されていく炎神の姿が最後だった。そこで途切れた映像は、その後の成り行きを伝えてはくれない。だが、勢いをなくして炎を散らしていく炎神の姿は、その後の顛末を容易に想像させた。
「……殺してやる」
フラリと立ち上がったリジカの言葉に、エルザもハッと我に返る。駆け出したリジカは、用意された食事の中からナイフを掴むと、部屋を飛び出そうとしてエルザに腕を掴まれ、引き止められる。
「触るな、無礼者!」
リジカはもっていたナイフを振り回した。食事用だが、特注品のナイフの切っ先が勢いをつけてエルザの腕を切り裂く。思わず顔をしかめたエルザは、ナイフを持つリジカの腕をねじ上げた。
「離せッ」
噛み付きそうな勢いのリジカの頬を、エルザは構わずに引っ叩いた。
「ナイフ一本でなにができるのです!」
エルザはリジカを怒鳴りつけた。
「アメンタリ王家の血族を繋げるのは、もはやあなただけかも知れないのです!自分の両親やきょうだいが、最後にあなたに何を願ったか、頭を冷やしてよくお考えください!」
エルザ自身、勝手な言い分だとはわかっていた。アメンタリを焼いたのは他でもないスタフィルスなのに、これが祖国の仇である国に囚われた王女の嘆きに、追い討ちをかけるものだとわかっていた。だが、リジカを生かすためにはエルザはそう言うしかなかった。
「うっ……ううっ……」
リジカの頬に涙が伝う。もう何もない。和平という名の従属の証として、自分をスタフィルスへ渡すことを決心した父王。人質同然の婚姻を結ばなければならない娘の不幸にむせび泣いた母親。自分を心配してくれた優しい兄弟、姉妹。幼い妹に貰った耳飾りが、リジカの耳で揺れる。大切なものはすべて砂に飲み込まれた。
「うああああああ――――ッ!」
エルザの胸に抱き締められ、リジカは声が枯れるほど泣き叫んだ。
(……大佐)
これからこの王女はどうなるのだろう。自分の胸でむせび泣くリジカの行く末を思うエルザのもとへ、血相を変えた兵士が駆け込んできた。その口から知らされた報告に、エルザは自分の耳を疑った。
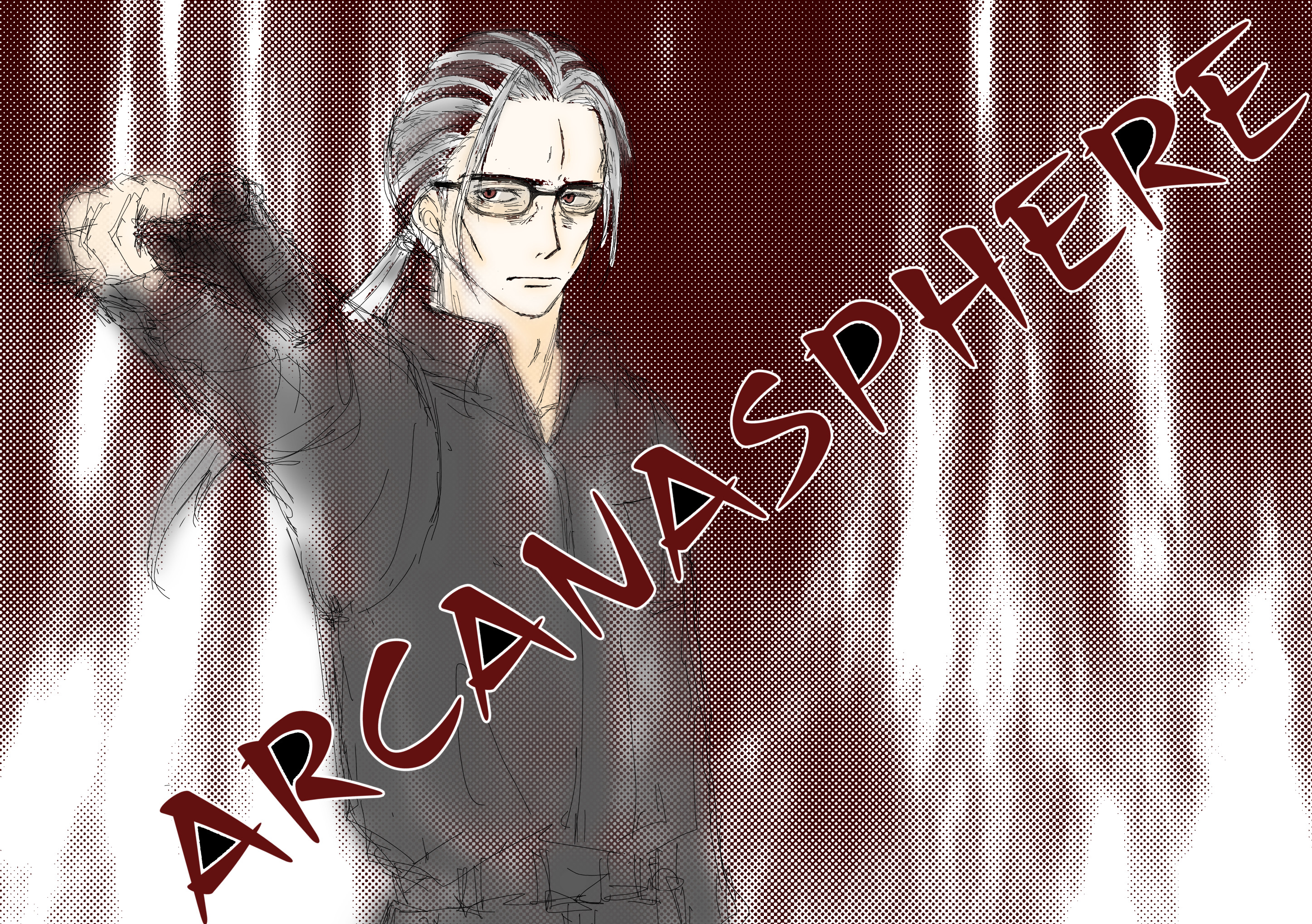
 にぃなん
Link
Message
Mute
にぃなん
Link
Message
Mute

 にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん