ARCANASPHERE14 フィヨドルがアメストリアの軍に制圧されたと言う情報が全世界に知れ渡ったのは、ハルヒたちがマーテルへと帰国してすぐのことだった。
ルシウスの強襲がかなりの打撃になり、あれほど長引いていた両軍の睨み合いは、それこそあっと言う間にその軍配をアメストリアにくだした。
アイシスはフィヨドルからの避難民に城のホールを解放し、彼らを受け入れた。そして、時間はかかるかもしれないが、順を追って住む場所を用意すると約束した。
一方、ルシウスは手錠をかけられて城内の一室に監禁された。罪状は先王であるジグロードの殺害容疑だった。暴れてどうにもならないかと思ったが、ルシウスは黙ってそれに従った。
死刑は免れまい。それが元老院の判断だった。いくらヴィルヒムを狙ったものであっても、実際に死んだのはマーテルの先王だ。それにより水神が出現し、イニスの町は壊滅的打撃を受けた。町は復興しつつあるが、元老院は世論を操るためにも、全ての責任を押し付けられる人物を必要としていた。
だが、それにアイシスは反対した。そして、彼女はルシウスの処遇を元老院に提案した。
「……マーテル王のロイヤルガードだと?」
ルシウスはキュラトスにそう聞き返した。ちょうどそこにいたココレットは、機嫌がいいとは言えない兄の声を感じ取っていた。
「そうだ。アイシスの護衛につけば、おまえは死罪を免れる」
「……ひとつ聞きたいが、おまえたちのだれが私を殺せるんだ?」
じわっとルシウスの身体が熱気を纏う。炎こそ見えないが、彼がその気になればキュラトスなど一瞬で燃え上がる。
「話をすり替えんなよ」
「ただの質問だ」
「受けるのか、受けないのか。質問してんのは俺だ」
「……即決できる話ではないな」
ルシウスはため息をついた。その態度は、自分のことであるのにどこか他人事に対峙しているように見えた。
ココレットに根負けして、マーテルに戻る船に乗ったときからこうなることはわかっていた。わかっていなかったのはおそらくココレットだけだ。下船したルシウスがマーテル兵に取り囲まれたとき、ココレットは見るからに動転していた。
「即決できないのなら明日には首が飛ぶぞ。ジジイどもはゴッドバウムの息子であるてめえの首飛ばしたくて仕方ねえんだからな」
キュラトスとしては、ルシウスのような危険要素を姉のそばになど置きたくない。だが、アイシスがそう望むものを、自分が嫌だからという理由で排除することもできなかった。
「お兄様……」
ココレットが不安そうな声を漏らす。それにまたルシウスはため息をつく。
適合者として目覚めてから、ヴィルヒムを殺すことばかりを考えて生きてきた。それ以外のものは本当に目に入らなかった。
(この命は……あの男を殺して終わるものだと思っていた)
目的を果たしてなお生き延びてしまったいまは、ルシウスにとっては予定していなかった時間だった。
「おまえはどう思う?」
「えっ」
突然、話を振られてココレットはそんな声を上げた。同じ部屋にいて、さっきからずっと話を聞いていたのだから、問われたことはわかっているはずだ。
「おまえの意見を聞きたい」
「わ、私の、ですか?」
「俺はてめえに聞いてんだぞ。ルシウス・リュケイオン」
「少し黙っていられないのか。小僧」
「こっ……」
キュラトスに対して暴言を吐ける人間はそうそういない。ルシウスは指をさしてキュラトスを黙らせると、ソファーを立ち上がってココレットのそばへ向かった。
「おまえは私に死ぬなと言っただろう」
「は、はい……」
「では、私はこれからどう生きればいいと思う?」
「そ、それは……」
目の前までやってきたルシウスは、ココレットの頭の上に腕をつき、彼女を見下ろした。ルシウスの圧でココレットは完全にすくみ上がってしまっている。自分の生死に関わりがある問題だと言うのに、ルシウスの顔はどこかこの状況を楽しんでいるようにも見えた。
「趣味悪ィ」
自分は何を見せられているんだと、キュラトスはそう吐き捨てた。それに対しルシウスは、おまえたちの女の趣味よりはマシだと、ここにはいないアキを含めてキュラトスを皮肉った。
□◼︎□◼︎□◼︎
「隣、いいかな?」
そう声をかけられて、ブロックに身体をもたれかけ、水平線を眺めていたハルヒは顔を上げた。そこにはクロノスが立っていた。
「フリースペースだよ」
ブロックはずっと向こうまで続いている。ハルヒに断らなくてもクロノスが使うことは自由だった。
ハルヒにそう言われて、クロノスはハルヒの隣のブロックに手を置いた。マーテルへ戻るときは酷く荒れたが、いまの海は穏やかなものだった。
「何が見える?」
クロノスがハルヒに聞いた。
「海以外何も見えねえよ」
ハルヒはそう言うが、空にはカモメが飛んでいるし、遠くには帆船も浮かんでいる。だが、ハルヒの目には本当に海しか見えていないのだろう。いや、海さえ見えているのかどうか定かではない。彼女の意識はすでに肉眼では見ることのできない大地へ向いていることに、クロノスは気づいていた。
「……マーテル王から、彼女のロイヤルガードにならないかという申し出があった」
「フィヨドル人たちの安全を保障するためにか?」
「そんな交換条件はなかったな」
「だろうな」
ハルヒはブロックに背を向け、それにもたれかかった。アイシスはそんな打算的な考えでは動かない。たとえ、元老院がそれを持ち出したとしても、アイシスはそれを許しはしないだろう。
「で、なるのか?」
「マーテルへの恩を考えれば、王の申し出は受けるべきだということはわかっているが、俺はロクサネの騎士だ」
「だったら断れよ」
ハルヒはきっぱりとそう言った。
「マーテルが欲しいのは、命をかけてアイシスを守る騎士だろ。ロクサネとアイシスが同時にやばいとき、アイシスを守れないなら受けるべきじゃねえよ」
「もっともな意見だ」
ハルヒの意見に頷き、クロノスは心を決めたようだった。
さあっと海からの潮風がハルヒの髪とバンダナをなびかせた。
「静かだな……」
フィヨドルでの出来事が嘘のようだと、クロノスはそう言った。
「いまだけだ」
ゴッドバウムも、アメストリアも、まだ生きている。白獅子はフィヨドルを手に入れ、黒獅子もグリダリアまで後退はしたが、壊滅したわけではない。両方が潰し合いをしてくれるのが、マーテルとコシュナンにとっては一番のシナリオだ。だが、そう上手くはいかないだろうことは、ハルヒにだってわかっていた。
□◼︎□◼︎□◼︎
アイシスは執務机上の地図を見つめていた。いまの情勢を確認するための会議が終わったのが、午前一時のことだった。
ゴッドバウムはグリダリアを滅ぼすというあの会見以来、その姿を見せない。まことしやかな死亡説も囁かれていた。
スタフィルスを手中に収めたアメストリアと手を組もうと言った元老院に反対したのは、アイシスのロイヤルガードを引き受けたルシウスだった。
父親を庇うつもりかと元老院はルシウスを責めたが、彼にはもちろんそんなつもりは毛頭なかった。
下手をすればアメストリアはゴッドバウムよりも残虐だ。クーデターが起こったダフネは酷い惨状だった。同盟を結ぶことは可能かも知れないが、背中を向けたが最後、撃たれることは間違いない。それがルシウスの意見だった。
「……ふう」
アイシスは小さく息を吐く。
疲れた。夜明けまで少し眠らなければ、政務に差し支える。部屋を出ると護衛の兵が慌てて姿勢を正す。
部屋へ戻るだけだからと、アイシスは護衛を断ったが、それはできないと兵士は首を振った。ロイヤルガードにはルシウスが着任したが、彼だって24時間動けるわけではない。彼にも休息を取る時間は必要だ。
アイシスは、アメストリアという人物のことをもっと知りたかった。ルシウスのほかに、アメストリアを知る人物と話がしたい。明日、ハルヒやカゲトラと話せる時間は取れるだろうか。
アイシスがそう思い立ったとき、前を歩いていた兵士が足を止めた。どうしたのかと聞く前に、その首はずれ、床に落ちた。
声も出ないアイシスの目に、その向こうに立っていた男の姿が映る。
「ヴィ、ヴィルヒム・ステファンブルグ……?」
アイシスがその名を口にすると、それを認めるように彼はニコリと微笑んだ。
(そんな……)
ヴィルヒム・ステファンブルグは死んだ。ルシウスが焼き殺したと、フィヨドルから戻ったココレットから、アイシスは報告を受けていた。
ココレットが嘘をつくとは思えない。だが、ヴィルヒムはいま、火傷ひとつ負った様子もなくアイシスの目の前にいた。
「マーテル王。いくら城内と言っても、おひとりで歩かれるのは危険では?」
ヴィルヒムがそう言うと、アイシスの背後にいた兵士が倒れた。振り返ったアイシスは左右で真っ二つになった兵士の姿に小さな悲鳴を上げる。信じられない量の血が溢れ、それはアイシスの足元まで広がってくる。
「どうしました?お見かけしたところ、とても驚いておられるようだ。私が死んだという報告でも受けましたか?」
「……ッ」
時間が時間だけに、辺りに人影は見当たらない。助けを呼ぼうにも、アイシスの喉は恐怖で引き攣り、声が出なかった。
(キュラ……!)
ヴィルヒムの手が伸びてくる。自分が殺されたら、水神はキュラトスに宿る可能性が高い。だから死ぬわけにはいかない。
「弟君のことならご心配は要りませんよ」
まるでアイシスの心を読んだかのように、ヴィルヒムがそう言った。
「水神の力に必ず適合しますから」
「え……」
シュンッ!
風が空気を裂く。身を退くのが一瞬遅れたヴィルヒムの腕が切断され、彼の足元へ落ちた。肉の断面から吹き出す血に足を退いたヴィルヒムの背後に、黒い影が飛び降りる。
黒い影───アキは、ヴィルヒムが振り向く前にその首を風刃で刎ねていた。
「ラ……ティ……?」
アキの名を呼びながら、アイシスの意識は遠ざかっていった。倒れ込むその身体を抱きとめ、アキは窓から見える塔の鐘めがけて風を放った。衝撃を受けた鐘は揺れ、深夜のマーテル城に警鐘を鳴らす。
静まり返っていた城内が騒がしくなり、足音が向かってきていることを確かめたアキは、アイシスを死体から離れた場所へ下ろし、窓から飛び降りた。
その直後、仮眠をとっていたルシウスが現場へ駆けつける。彼は倒れているアイシスを確認し、すぐさまそばへ駆け寄った。ロイヤルガードはもうクビかと思ったが、アイシスに怪我はなく、彼女の衣服を汚しているのは返り血だけだった。
廊下には少なくとも3体の死体が転がっている。むせ返るような血の匂いに顔をしかめたルシウスは、ようやく駆けつけたキュラトスにアイシスを任せ、死体の側へと近づく。
「なんだよこれ……」
姉は完全に意識を失っている。凄惨な現場にキュラトスは顔を歪め、死体を確かめたルシウスもまた息を詰める。
「ヴィルヒム・ステファンブルグ……」
その死体は彼にしか見えなかった。骨で止まることもなく、首をきれいに切断された顔は、驚いた表情のまま時間を停めている。自分が死んだことにすら気づいていない。そんな印象さえ受けた。
「ばかな……」
ルシウスは握り締めた拳を震わせる。
殺したはずだった。この手で殺したはずだった男が、ここでまた死んでいる。しかも、どう見てもこの切り口は風神適合者の仕業だった。
□◼︎□◼︎□◼︎
ヴィルヒムによる深夜の強襲をハルヒが聞いたのは、翌日になってからだった。その知らせを聞いて駆けつけたハルヒは、アイシスの部屋の前で待ち構えていたルシウスに足を止められる。
「アイシスは?」
「怪我はない」
「へえ、噂のロイヤルガード様が守ったからか?」
ルシウスがロイヤルガードになったことを、ハルヒはココレットから聞いていた。あんな男をアイシスの護衛につけるなんて正気とは思えない。ハルヒはそう思ったが、反対するにもすでに決まったあとではどうしようもない。
「おまえの嫌味に付き合う気はない」
「だったらどけよ」
「ヴィルヒム・ステファンブルグが生きていて、昨夜また死んだ」
ハルヒはルシウスを見上げたまま、だんだんと眉間のシワを濃くしていく。
「……あいつはてめえが殺したんじゃなかったか?」
「ああ。確かに焼き殺した。だが、昨夜また首を刎ねられて死んでいた。間違いなくバルテゴの力でやられた傷だ」
(クサナギがマーテルに……戻ってる?)
バルテゴの適合者は他にいるかもしれないが、ハルヒの頭にまず浮かぶのはアキの顔だ。
「同じ人間がなぜ二度死ぬか、それはやつから聞き出すのが早そうだ。クサナギはどこにいる」
それを聞くためにルシウスはハルヒを呼び止めた。アイシスの危機に現れ、すぐに姿を消したアキは何か知っている可能性が高い。そして、アキの居場所を知るには、ハルヒに問いただすのが手っ取り早い。ルシウスはそう考えた。
「俺が知るかよ」
「知らないのなら呼べ。おまえがちょっと叫べば来るだろう」
「来るわけねえだろ」
フィヨドルで、アキはミュウと行ってしまった。ハルヒの声は届かなかった。それに、ルシウスはそうだと決めつけているようだが、バルテゴの風使いはアキだけではないかもしれない。新たな適合者がいるのかもしれない。
「クサナギを呼べ!」
「しつこいんだよ!」
ボウッとルシウスの手に炎が宿った。赤い炎はハルヒの顔を明るく照らす。
「……いいぜ。やってみろよ」
「言っておくが、骨も残らんぞ」
「上等だよ!」
そう叫んだハルヒの腕は、後ろから掴まれて身体ごと引き戻される。背中にぶつかったのはクロノスの胸で、文句を言おうと口を開きかけたハルヒだったが、ルシウスを睨む彼の視線に何も言えなくなる。
「どうか落ち着いてください。リュケイオン、大佐」
スタフィルス軍から抜け、その軍施設を何度も破壊したルシウスはもう砂の国の大佐とは言えないが、クロノスはルシウスの呼び方をそれしか知らなかった。
「これは何事ですか」
「小娘がクサナギの居場所を隠すから、それを吐かせようとしているだけだ」
「クサナギ?」
クロノスがハルヒに視線を向けると、彼女はギリッと奥歯を鳴らした。
「アキ・クサナギ。ラティクス・フォン・バルテゴ。B-101。やつの呼び名は多いが、その小娘の恋人だ」
「違う!」
ハルヒは叫んだ。それにルシウスはクッと笑った。
「なんだ。ついに捨てられたのか?」
ここで怒ればもっとルシウスを楽しませるだけだ。ハルヒはすうっと息を吸い、クロノスの手も払いのけた。
「てめえがハインリヒを焼き殺したあと、あいつはどっかに消えた。最後に見たのはフィヨドルでだ。あいつがマーテルに戻ってんなら、お得意の共鳴で探してみたらどうだ?」
「何?」
「ミュウって赤い髪の女がいただろ。クサナギは……あいつと一緒にいた」
ルシウスは2秒ほど考えた後、両手に灯した炎を消してその場を立ち去った。襲われたばかりのアイシスのそばを離れ、ルシウスはアキを追うつもりだ。ロイヤルガードが聞いて呆れる。ルシウスの足音が聞こえなくなると、ハルヒは深いため息をついた。
□◼︎□◼︎□◼︎
シャワーの音が止まると、シャワーカーテンの向こうから伸びてきた手が、洗面台の上にあるタオルを掴み、またカーテンの向こうへ消える。
ふうっとミュウは息を吐いた。
つい10分前、アキは血塗れになってこの部屋に戻って来た。アキが出て行ったことには気付かず、ミュウは戻った音で目を覚ました。おそらく、アキは共鳴に誘われたのだろう。風の適合者の共鳴はミュウには聞こえないものだった。
最近のアキはほとんど口を聞かなくなった。表情もまったくなくなり、食べることも寝ることもただ生きるためだけの行為で、彼は共鳴を聞くためだけに生きているように見えた。
「アキ」
ミュウはシャワーカーテンの向こうにいるアキに声を掛ける。
「何か食べるもの買ってくるね」
返事はなかったが、聞こえてはいるはずだ。アキからの返事を期待したわけではなかったミュウは、そのまま部屋を出た。
数日前、アキとミュウはフィヨドルからマーテルへ戻って来た。理由は、ヴィルヒム・ステファンブルグがマーテルへ戻ったという情報を掴んだからだった。いまのアキの目的は、彼のオリジナルを殺すことだ。
安いモーテルを出たそこはイニスの裏通りだ。水神がもたらした被害など遠い昔のことのように活気付く表通りと違い、日の差さないここらは人通りもあまりない。だから、あまり表立ってはできない商売などが当たり前に横行する、法の目の届かない場所でもあった。
イニスの表通りに出れば、知っている顔に会うかもしれない。アキはマーテルと同盟関係にあったバルテゴの王子だ。彼の顔は知らなくても、キュラトスの顔を知る者なら、アキをそのまま見過ごすはずはない。だからこうして人目につかないモーテルを選んだ。
マーテルへ戻ってきて、アキは今日を含めてヴィルヒムを13人殺している。正しくはヴィルヒムのクローンを。
ヴィルヒムが複数体いることに気づいたのは、フィヨドルでのことだった。アキと一緒に見つけたクローンの製造工場に、ミュウは自分が立っていた世界が足元から崩れ落ちていくような感覚を味わった。果たして、これまで自分がパパと呼んで慕ってきたあの男は、本物のヴィルヒムだったのだろうか。培養液の中に浮かんだヴィルヒムは、ミュウの目に本物しか見えなかった。
ヴィルヒムの複製体は、ここ数日の間に何度もマーテル城へと侵入しようとした。そして、そのすべてをアキは仕留めてきた。だが、情報は偽物で、オリジナルのヴィルヒムはグリダリアにいるらしいことがわかった。
オリジナルを潰さなければクローンはいくらでも増殖する。そう考えたアキは即座にマーテルからグリダリアへ向かおうとしたが、海域にまで張り巡らされた強烈な共鳴が邪魔をして、国内に入ることさえできなかった。
本物のヴィルヒムの居場所がわかっていても、近づくことさえできない。仕方なく、アキはマーテルへ戻り、執拗にアイシスを狙ってくるクローンを処分していくしかなかった。
一度、ミュウはアキが切り裂いたヴィルヒムを見たことがあった。本物ではない。クローンだとわかっていても、心が重い。アキにとっては憎い相手でも、実の親の顔を知らないミュウにとっては、ヴィルヒムはたったひとりの父親だった。
だが、ミュウはアキのそばにいる。ヴィルヒムを殺そうとしているアキのそばにいる。アキと、本物のヴィルヒムがぶつかる時、果たしてミュウはどちらの側につくのだろう。それは本人にもまだわからなかった。
「!」
考え込んでいたせいか、ずっと続いていた微弱な共鳴のせいか、ミュウはそれに気付くのに遅れた。まずいと思ったときには、ルシウスはすでに彼女の目の前に立っていた
「クサナギはどこだ?」
開口一番、ルシウスはミュウにそう問いかけた。
「あんたに答える義務はないね」
場所は表通りと裏通りの境目だ。そこそこだが人通りもある。炎こそ見せないが、険悪な様子で睨み合う男と少女に、見物人は否応なしに数を増した。適合者同士の戦いに巻き込まれたら、一般人は怪我では済まない。
だが、そんなことはルシウスもミュウもなんとも思っていなかった。ここで巻き込まれて死んだとしても、群がってきたほうが悪いのだ。その点において、彼らの考えは一致していた。
「いいだろう。おまえを焼き殺してから、探してやる!」
「やれるもんならやってみればぁ!?」
ほぼ同時に2人の手に炎が宿った。兄妹ケンカか何かかと思っていた人々は、彼らが適合者だと知ると悲鳴を上げて逃げ出した。
ふたりの炎はぶつかり合い、激しい火炎を撒き散らした。
□◼︎□◼︎□◼︎
なんだか外が騒がしい。ナツキが窓から外を見ると、仕事を放り出した人々が、裏通りのほうへと流れていくのが見えた。
フィヨドルからマーテルへ戻ってからも、ナツキの気分は晴れなかった。普段ならハルヒが気に掛けてやるのだが、当のハルヒもアキのことで頭がいっぱいのようで、弟のことにまで気を回せない状況が続き、それを見かねたカゲトラが、ココレットの協力もありナツキを外へと引っ張り出していた。
「何かあったのかしら?」
伸びっぱなしのルシウスの髪を切るための理容ハサミを選んでいたココレットも、髭剃りを吟味していたカゲトラも、騒ぎに気づいて顔を上げた。その瞬間。窓の外で巨大な火柱が上がった。
「……!」
炎の勢いで周辺の屋根が吹き飛び、店のガラスがガタガタと揺れる。
「伏せろ!」
カゲトラがふたりを床に押し倒すと、耐えきれなかったガラスが店内へ飛散した。
「あの男……ッ」
炎の原因はわかりきっていた。
アイシスのロイヤルガードに任命されて、少しは落ち着いたかと思えばこのザマだ。やはりあのまま置き去りにすればよかったと、ふたりを庇ってガラスを浴びたカゲトラが口汚くルシウスを罵ると、ココレットがその下から這い出した。
「ココレット!」
ナツキがだめだと言うが彼女は止まらず、割れた窓ガラスを飛び越えて外へと出て行った。
「ナツキ、おまえはここでいろ!」
カゲトラは一緒に追いかけようとしたナツキを指差し、自分はココレットを追って店を出ていく。取り残されたナツキは店内を見回すと、カウンターの奥で震えている店員を見つけて、大丈夫かと声をかけた。その瞬間、店員の首は胴から離れて床に転がる。
吹き出した血はナツキの顔にまで飛び、栗色の髪からは粘着質な血液が垂れ落ちた。それを見た他の客が悲鳴を上げて逃げ出そうとするが、その身体も真っ二つにされて床を滑り、陳列棚でやっと止まる。
「おやおや。これは大変だ」
言葉もなく立ち尽くすナツキの背後で、この状況にはとてもそぐわない、落ち着いた男の声がした。ナツキはゆっくりと振り返る。
「怪我はないかな?ナツキ・シノノメくん」
ナツキにそう聞いたのは、ヴィルヒム・ステファンブルグだった。
「……な」
アイシスがヴィルヒムに襲われた。そのことはナツキも聞いていた。ヴィルヒム・ステファンブルグはフィヨドルでルシウスが殺したとココレットから聞いていたので、ハルヒとふたりで何かの間違いではないのかと顔を見合わせた。とにかくアイシスに会いにいくという姉を見送り、自分はカゲトラに連れられてここへやってきた。まさか、またヴィルヒムが現れるとは夢にも思わずに。
「……っ」
ナツキはヴィルヒムに直接会ったことはないが、スタフィルス研究機関の顔である彼の姿は知っていた。
「外は酷い騒ぎだね」
「………」
炎神の力は見た目に派手だから仕方がないか。そう言ってヴィルヒムはナツキに微笑みかえる。ヴィルヒムは店員と客を迷うことなく殺した。ナツキを殺すのだって1秒あれば済む。それが適合者の力だ。
ナツキの背中を冷たい汗が流れ落ちていった。自分たちに向いて牙を向かなかっただけで、アキの力が恐ろしいものであったことを、ナツキはいま初めて思い知っていた。
「そう怖がらないで。今日はきみにプレゼントがあって来たんだ」
「え……」
掠れてしまった声を漏らすナツキに、ヴィルヒムは胸ポケットから一本の注射器を取り出した。
「なに……?」
自分に向けて差し出されたそれにナツキは眉をひそめる。ヴィルヒムが自分にプレゼントをする意味も、その注射器も、何もかも意味がわからなかった。
「アキ・クサナギが憎いだろう?」
「!?」
ナツキが思わず足を退く。陳列棚に足が当たったことで、その上にあった理容ハサミに気づいたナツキはそれを掴んで、ヴィルヒムに向けた。こんなもの、投げつける前に風で切り裂かれる。わかってはいても、それはナツキにとって唯一の武器だった。
「父親を殺した彼を憎むのは、至極当然の感情だと私は思うがね」
「僕は……」
「だが、いまのきみでは彼には勝てない。彼はバルテゴの適合者で、適合率もトップクラスだ。だからこれをきみに」
ヴィルヒムは手のひらの上で注射器を転がした。
「それは、なに……?」
「魔法の薬だよ。これを使えば、きみは適合者になれる」
「……!」
ナツキは目を剥いてまた一歩下がった。ゴクリとその喉が鳴る。
「ナツキ・シノノメくん。きみは彼を憎む権利、そして復讐する権利がある」
大切なお姉さんのためにもねと、ヴィルヒムは一歩ナツキに近づいた。
□◼︎□◼︎□◼︎
ルシウスの炎を受け止めきれず、ミュウは家の壁に背中から激突した。その衝撃で内臓が跳ね上がって息が詰まる。まるで相手にならないミュウを、ルシウスは冷淡な目で見下ろした。そして、二度目になる言葉を口にする。
「クサナギはどこだ?」
もう立ち上がる力も残っていないミュウは、へらっと口の端に笑みを浮かべた。それが答えだった。ルシウスは両手で炎のアーチを作り出す。
まるで適合率が違う。ミュウではルシウスの相手にもならない。もしルシウスが脳手術を受けていたなら、彼はヴィルヒムのお気に入りになっていただろう。そんなことを考えながら、ミュウは申し訳程度の炎を手に灯し、それを投げつけた。
「悪あがきを―――」
避けるまでもないとルシウスが過信したミュウの炎は、彼の目前で風に煽られて燃え上がった。
「お兄様!」
ミュウの炎がルシウスを包んだ瞬間、そこへ駆けつけたココレットが叫ぶ。
「クサナギィッ!」
炎を振り払ったルシウスは、ミュウを抱き起こしたアキに炎を投げつけた。アキは自分の前に真空を作り出し、それを無効化する。
「アキ……」
アキが助けに来てくれた。ミュウは鼻水をすすってアキに抱きついた。アキは無言のまま彼女の身体を抱き上げる。
「黙って行かせるわけがないだろうッ!」
ルシウスは拳に炎を宿し、そのままアキに向かって殴りかかった。アキはミュウを抱えたまま片腕を突き出し、風でそれを受け止める。周囲に散らばる炎に集まった野次馬が悲鳴を上げた。
「知っていることをすべて話てもらおうか!」
アキは無言のまま、退くことを知らないルシウスの力を利用し、ミュウを抱えたまま飛び上がると、フワリと屋根の上に飛び乗った。そこへ向かって炎を放とうとしたルシウスは、突風に吹き飛ばされて建物の壁に叩きつけられた。
昨日降った雨のため、そこに残っていた水たまりが彼の服を泥まみれにする。
「……殺す」
衆人環視のもとに受けた屈辱に、ルシウスの目の前は真っ赤に染まり、その身体を炎が包んだ。
「お兄様!」
兄に駆け寄ろうとするココレットをカゲトラが止める。いまのでルシウスは完全にキレた。下手をすればココレットだって無事では済まない。
全身を炎神のごとく燃やすルシウスは、弾丸のように走り、アキが乗っている家の壁を殴りつける。炎が壁を突き破り、屋根が積み木のように崩れ落ちていく。
足場を失ったが、それは風使いにはたいした問題ではなかった。アキは次の屋根へと飛び移り、ルシウスはその家も破壊する。早くここから離れろとカゲトラが叫び、見る間にそこらは瓦礫の山と化していく。
「やばいよ、あいつ!」
我を忘れて暴れるルシウスは手がつけられない怪物だ。
「早く殺しちゃわなきゃやばいって!」
ミュウの言う通りかも知れない。とにかく、ルシウスに止まってもらわないことには市街の被害は広がるばかりだ。どこか広い場所へ誘い出して、落ち着かせることはできないか。建物の屋根から大きく飛び上がったアキは、その場所を探して周囲を見回し、そこにいる男に気づいた。キィィッと微弱だがずっと続いていた共鳴が強くなる。
「パパ……!」
ミュウが息を呑み、アキはその瞬間に風刃を放つ。人体を真っ二つにする風が届くまでは3秒と必要ない。もちろん、共鳴に気づいていたヴィルヒムが顔を上げると、その前にいただれかも振り返る。アキの目に映ったそれはナツキだった。
「ッ!?」
風刃の軌道にナツキがいる。だが、もう放ってしまった風は止めるすべがない。風刃は屋根を突き破り、ナツキを庇ったヴィルヒムの右半身を刎ね上げ、それは家の外まで飛ばされた。
ガクガクと足を震わせたナツキはその場に座り込んだ。その足元にヴィルヒムの血が流れてくる。
「きみには、彼を憎む権利が、ある……」
そう言うとヴィルヒムは事切れた。ナツキは破れた屋根の向こうにいるアキを見上げる。その瞳は激しく動揺していた。
「……!」
ナツキは無事だ。だが、その視線に耐えることができなかったアキは、ミュウを抱えてその場から飛び去った。
「クサナギィッ!」
いくら炎を投げつけても空を自在に舞うアキには当たらない。憤慨したルシウスはなおも追撃しようとしたが、頭から水を浴びせかけられて足を止める。そこにはバケツを手にしたココレットの姿があった。
「やめてください、お兄様……!」
ボロボロと涙をこぼすココレットの姿に、ルシウスはようやく周囲に目をやる。ルシウスが暴れた一角は、水神が暴れたのかと思うほどめちゃくちゃに破壊されていた。
□◼︎□◼︎□◼︎
「クビにしろ」
城下での騒ぎを聞いたキュラトスは、ルシウスからロイヤルガードの権限を剥奪しろとアイシスに要求した。ロイヤルガードが城下で暴れて、合わせて3棟の建物を全壊、6棟を半壊させるなんてマーテルの歴史上聞いたこともない失態だ。
ようやく意識を取り戻したところでその報告を聞いたアイシスは、被害報告を受けて機嫌の悪い弟に対し、苦笑いを浮かべた。
「あなたの言いたいことはわかるけれど、彼をクビにしてどうするの」
「地下牢にでも閉じ込めちまえよ。あのコードとかいうガキが言うには、共鳴装置使えば弱らせることもできんだろ」
「それではマーテルもスタフィルス研究機関と変わらないわ」
ぐっとキュラトスは言葉を詰まらせた。アイシスの言うことは正論だが、理想論でもある。適合者のすべてが味方ではない。実際、いまのマーテルにとっては敵のほうが多かった。こうしている間にも、スタフィルスでは新たな適合者が作り出されているかも知れないのだ。
「ラティが戻ったのね……」
「……みたいだな」
城下の目撃証言から、アキが戻ったことは知れた。だが、彼はアイシスやキュラトスに会いには来なかった。城下でルシウスと派手に戦った後、また姿を消したアキの行方は知れない。
「最初の話に戻るけれど、彼をクビにはしないわ」
「アイシス……」
「彼はマーテル側についてくれる唯一の適合者よ。彼に守ることができないのなら、だれにも私は守れない」
そうでしょう?と聞かれて、キュラトスは黙り込んだ。確かにアイシスの言う通りだ。だが、ルシウスが盾になるのかと言われたらそれはそれでキュラトスには疑問だった。
キュラトスは立ち上がった。
「キュラ」
「ちょっと出てくる」
「もうラティを探さないで」
「……アイシス」
アイシスを守ることができるのはルシウスでも適合者でもない。それはアキだ。適合者であるアキさえ戻れば、ルシウスなんて必要ない。キュラトスのそんな考えなどアイシスは見抜いていた。
「だけど……」
「彼には彼の考えがあるわ。どうか自由にさせてあげて」
「……わかったよ」
マーテルにいるとわかっているだけマシなほうか。いまは来たる戦争を警戒して港を閉鎖していて、どんな船でもマーテルを出ることは許していない。そのため、海を泳ぐか、飛ぶことでしか大陸間を行き来することは不可能になっていた。
まさか、アキでも外海を飛び続けることはしないだろう。アキがどこまで風の力が使えるのかキュラトスにはわからなかったが、無茶だけはしてくれるなと願い、アイシスの部屋を後にした。
□◼︎□◼︎□◼︎
悪夢はいつだって同じ色をしている。
黄昏色に染まる世界の中、自分は立ち尽くしている。辺りには切り刻まれてバラバラに散らばる多くの死体があった。
なぜこんなことになったのかわからない。わからないけど、こんな状況を作り出すことができるのが、風の適合者だけだと言うことはわかりきった事実だった。
海からの風がアキの髪をなびかせる。初めて訪れた墓地には、夕刻ということもあり人の姿はまばらだった。葬列に参加していないため、ハインリヒの墓を見つけるのにアキは苦労した。
ようやく見つけた墓石にはまだ新しい花が飾られていて、少し前にだれかが来たのだとわかった。
「………」
ハインリヒは大丈夫だ。きっと大丈夫だ。何を根拠に、そんなありえないことを信じていたのだろう。育ての親の変化にも気付かずに、自分のことだけで手一杯になって、彼は自分が殺したようなものなのに、葬列にさえ出席しなかった。
「怒ってるよね……」
あんなに世話してやったのに、恩を仇で返すようなやつだって。背後から文句が聞こえてきそうだが、実際はそんな声は聞こえない。聞こえるのは岸壁に吹き付ける海風の音だけで、ハインリヒの声はアキの記憶の中で再生されるだけだ。だが、その声もいずれは忘れてしまう。泣きじゃくるセルフィの声を、もうハッキリとは思い出せないように。
「……どうするのが正しいのか、わからないんだ」
これで大丈夫だと背中を押して欲しいし、間違っているなら、進むべき道を示して欲しい。自分はもう大人だと思っていたのに、どれだけハインリヒという存在に甘えていたかを、アキは彼の喪失で思い知っていた。
「僕はどうしたらいい……」
このままマーテルでヴィルヒムを殺し続けたところで、それはイタチごっこに過ぎない。グリダリアにある黒獅子軍の本拠地を潰さなければ、適合者もクローンもどんどん送り込まれてくる。だが、共鳴に阻まれて、アキはグリダリアの海域に近づくことさえもできなかった。
バサッと背後で音がする。アキが振り返ったそこには、持ってきた花束を取り落としたメアリーの姿があった。
「……クサナギくん」
「………」
アキは軽く頭を下げ、そのまま立ち去ろうとしてメアリーに腕を掴まれる。ハインリヒが最後に愛した彼女は妊娠している。振り解くわけにもいかず、アキはそのまま立ち止まった。
「酷い顔してる」
「……え?」
「ちゃんと寝てるの?それに食べてるの?」
「……すいません」
自分は、メアリーからも、彼女のお腹にいる赤ん坊からもハインリヒを奪った人間だ。アキはメアリーの手をやんわり剥がそうとするが、その手も掴まれて止められる。両腕を拘束されたアキは困り果ててその眉を下げた。
「ちょっとこっちに来なさい」
「僕は、」
「いいから、いらっしゃい!」
メアリーは強い口調でそう言うと、アキを引きずるように墓地の端にあるベンチに座らせた。
「昼間のことは聞いてるわ」
ルシウスとぶつかったことか、それともナツキを殺しかけたことか。アキにはどちらかわからなかったが、派手にやったわねとメアリーはそう言った。
「すいません……」
「私は何の被害も受けていないわ。それに正直、私もリュケイオン大佐は苦手よ」
彼は、メアリーにとっては妹のようなココレットの毒でしかなかった。フィヨドルで何があったのかすべてのことは知らないが、なぜココレットがルシウスを連れて戻ったのか、メアリーには理解できなかった。
アキは黙ったまま彼女の言葉を聞いている。
「……ハインリヒのことで自分を責めているなら、もうやめなさい」
「………」
「時間を巻き戻したとしても、彼はきっと同じ選択をするわ。あれは彼の意志よ。だれにも止めることはできなかった」
「……すいません」
「謝ってばかりね」
メアリーの言う通りだ。だが、謝ることしかできない。そして、謝って許されることでもない。
「……ハルヒのところに戻る気はないの?」
アキは首を振った。
「放っておいたらあの白の王子に取られちゃうわよ」
メアリーは冗談めかして言ったが、アキは寂しそうな笑みをその口元に浮かべ、頷いた。
キュラトスとハルヒが惹かれ合うのなら、それを止める権利はない。そもそも、ハルヒのそばにいる資格もない。アキはそのすべての言葉を飲み込み、立ち上がった。
「……クサナギくん」
「アイシスを襲ったヴィルヒム・ステファンブルグはクローンです」
「……え?」
「だから何体殺しても代わりがやってくると伝えてください。キュラに、コシュナンに援軍を要請して、国境の軍の配備も強化するように言ってください」
ヴィルヒムのクローンの適合率はそれほど高くはないが、普通の人間にとっては脅威だ。ヴィルヒムほどの適合率であっても、その気になれば、いま国境に敷いているマーテルの配備は総崩れになる。
「ヴィルヒムが単身でマーテルに乗り込んでくるのは、おそらく水神を手に入れた後の実験体を多く確保したいからだ。だけど、ヴィルヒムひとりでアイシスを手に入れられないとわかれば、黒獅子軍は軍事力で叩き潰しにくる」
お願いします。そう言うと、アキはベンチを立ち上がり、夕闇の中を去っていった。
□◼︎□◼︎□◼︎
ナツキがヴィルヒムと接触したらしい。
その話をカゲトラから聞いたときは肝が冷えたが、夜にもなるとナツキの様子は安定した。ぐっすりと眠っている弟を見つめ、ハルヒは息を吐いた。
ナツキには怪我はなかった。だが、それはギリギリと言ったほうが正しい。一歩でもナツキが前に出ていたら、彼はアキの風に引き裂かれていた。
アキがヴィルヒムを狙ったのだということはわかりきっている。それでもナツキが死にかけたのも事実だった。
「………」
ハルヒはため息をつき、立ち上がった。このままでは眠れそうもないので、少し夜風に当たろうと思ったからだ。
音を立てないように彼女が部屋を出ると、ちょうどキュラトスがそこに通りかかる。
「よう」
「あぁ」
軽い挨拶を交わしたあと、なんだか気まずい沈黙になってしまう。マーテルへ帰ってからも、ゴタゴタしてしばらく会ってなかったせいだろうかとハルヒは考えた。
「ちょっといいか?」
キュラトスはハルヒにそう言って、外を指差した。ハルヒはそれに頷き、ふたりは庭園に出た。夜の庭園にはだれの姿もなく、ただ白いリリーの花だけが揺れていた。
リリーを見ると、アキはアイシスを思い浮かべるが、ハルヒは違っていた。この花を見てハルヒが思い出すのはアキだ。アキに出会ってからいろんなことがあった。ほんの数カ月間の間の出来事とは思えないほどに。あの砂の大地を脱出できるなんて夢にも思っていなかったのに、自分はここにいる。
「弟の具合は?」
キュラトスが声をかけた。
「心配ない」
ショックで少し熱が出たが、それも明日には下がるだろうとハルヒは答えた。
「ルシウス・リュケイオンって男はとんでもねえやつだな」
「言えてる。アイシスはマジであんな男をロイヤルガードにして大丈夫なのか?」
「俺は反対したんだよ」
ルシウスの存在は、ここ最近のキュラトスの頭痛のタネだった。
「で、おまえの話って?」
「ああ……。俺さ、コシュナンと同盟結んだだろ?」
「援軍はまだ来てないみたいだけだけどな」
「それを言うなよ」
天候不良まで思い通りになるかと、コシュナンの救援が遅れていることにキュラトスは苦い顔をした。それにハルヒは、ふふっと笑う。初めて会ったとき、キュラトスのことをアキに似ていると思ったが、いまはそうは思えなかった。
確かにアキとキュラトスは似ているが、中身は全然違う。それがわかってしまえば、ふたりはハルヒにとってまったくの別人だった。いまキュラトスが見せているような表情は、アキの顔に見たことはない。
「で、コシュナンとの同盟がどうした?まだ褒めてなかったっけ?」
意地悪い言い方をしたハルヒは、キュラトスに頭を小突かれる。
「同盟ってのは王族の婚姻で結ぶもんなんだけどな」
「ああ」
「俺はおまえのことが好きだから、コシュナンの王女との結婚は断ってきた」
ハルヒの目がぱっちりと開いた。何度もまばたきを繰り返すその顔に、キュラトスは苦笑する。
「なんだよ。その全然気づいてなかったって顔」
「……なんで、俺?」
「人の趣味にケチつけるなよ」
「別にケチは……つけてねえけど」
キュトスは上着のポケットに手を入れて、その中から小さな箱を取り出した。ハルヒの目の前で開けられた小箱の中には指輪が入っていた。
それはハルヒ、ココレット、ロクサネ、クロノスと、周り回ってようやく返却されたキュラトスの王位継承権を示す指輪ではなく、ハルヒの指のサイズの指輪だった。
キュラトスはハルヒの前に跪いた。
「おまえが好きだ。俺と結婚してほしい」
「………」
ハルヒは絶句した。予想もしていなかった事態に、なんと答えればいいのか本当にわからずに、空いた口が塞がらない。キュラトスはマーテルの王子で、ハルヒは貧民地区生まれの元テロリストだ。釣り合わないにも程がある。
だが、キュラトスはそんなことを気にしてはいない。それはハルヒにもわかっていた。キュラトスが気にしているとすれば、それはハルヒの心から消えないアキの存在だった。
「……ラティが好きか?」
いつまでも何も言わないハルヒに、キュラトスはフッと寂しげに笑った。その問いにもハルヒは答えることができなかった。
「……わかった」
「キュラ……」
「いいって。気にすんなよ。じゃ……、俺の話はこれで終わりだ」
キュラトスはそう言うと、指輪を上着のポケットに入れる。そしておやすみと言うとハルヒに背中を向けた。
「あ……」
去っていくその後ろ姿がアキと重なり、ハルヒは気づけばキュラトスの腕を掴んでいた。
キュラトスは振り返らない。振り返ったら最後、未練がましい行動をとってしまう。それを恐れた。
「……クサナギのことを、どうすればいいのかわからないんだ」
ハルヒは言った。珍しく震えるハルヒの声に気づいたキュラトスが肩越しに彼女を視界に入れる。ハルヒの目には涙が滲んでいた。
「……ハルヒ?」
「あいつを憎むことが正しいのか、わからなくて……っ」
アキがアキラを殺した。クロノスの話からその可能性は高い。だが、ハルヒはそれをどうしても認めたくはなかった。アキではないと思いたかった。アキを憎むには、すでにハルヒの心は彼に寄り添いすぎていた。
「どうしたらいいのか、わからなくて……っ」
フィヨドルで、アキはハルヒの銃口を前に目を閉じた。その命を投げ出した。まるでその罪を認めるように。
「……おまえはラティを殺したいか?」
キュラトスの静かな問いかけに、ハルヒは首を振る。殺したくなんかない。本当は憎みたくなんかない。たとえ、アキがアキラを殺していたとしても。アキを失いたくない。
殺したくないと、嗚咽混じりにそう言ったハルヒを、キュラトスはそっと抱きしめた。
□◼︎□◼︎□◼︎
黒獅子軍が動き出したという情報が、国境からマーテルへ入ったのは明朝のことだった。
コシュナンからの援軍は天候不良により、開戦には間に合いそうもない。アイシスはその報告を受け、マーテル全土に獅子軍との戦争へ突入することを伝えた。
だれもが数の上で勝る黒獅子軍との戦争に覚悟を決めたその日の朝、ハルヒはキュラトスの腕の中で目を覚ました。
「………」
まばたきをすると、目尻がジンジンと痛んだ。泣きすぎたせいだと思い出したハルヒは、間近で寝息を立てるキュラトスの顔を見つめた。
スタフィルスで暮らしていた頃は、男に抱かれて眠ることなんて一生ないと思っていた。母親を殺した軍人が憎かった。自分のことを男だと言い張ったのは、女であることを認めたくなかったのは、力で敵わない男に負けたくて、虚勢を張っていただけだ。自分の身さえ守ることができない。あの頃は、それを認めることもできない子供だった。
「……キュラ。キュラ、起きろよ」
声をかけると、うーんと唸ってからキュラトスは眠そうに目を開け、まだ寝ぼけた様子でハルヒの頭をポンポンと撫でた。連日の疲れもあっただろうが、ハルヒの体温が心地よく、昨日はいつ眠ったかも覚えていなかった。
「おはよ……」
大きな口を開けてあくびをするキュラトスの顎には、うっすらとヒゲが生えていた。眠る前にはなかったはずのそれを、ハルヒは不思議そうに見た。
「おまえもヒゲ生えるんだな」
「……そりゃ、生えるだろ」
当たり前のことを指摘されたキュラトスは、自分のヒゲを指で擦った。
「……昨夜は悪かった」
ハルヒは、あれだけ泣きじゃくっていたことが嘘のようにスッキリとした顔をしていた。
「貸しひとつな」
キュラトスはハルヒの額を指で押すと、ソファーにかけていた上着を手に取る。そこでドンドンと扉が叩かれた。ノックの仕方からカゲトラだとわかっていたハルヒが返事をすると、すぐに扉が開く。
「ハルヒ!国境に……!」
ベッドの上にいたふたりに、カゲトラは言葉を失い、開いた扉を閉めようとしてハルヒに止められた。
「国境がどうした?」
「いや……、ええと、だな……」
「早く言えよ」
男と一夜を共にしたにしては、ハルヒの態度はいつも通りすぎる。確認するように視線を合わせたキュラトスが首を振ったことで安堵したカゲトラは、自分を落ち着かせるためにゴホンと咳払いをしてから口を開いた。
それを聞いたキュラトスは顔色を変え、立ち上がるとハルヒの部屋から飛び出した。
(まずい、まずい、まずい!)
いまごろ城では自分を探し回っているだろう。一刻も早くアイシスのそばへ戻らなければならない。キュラトスは城へ向かって全速力で走った。
□◼︎□◼︎□◼︎
黒獅子軍がマーテルの国境となる海域に近づいている。宣戦布告もなく攻め込む姿勢を見せた黒獅子軍の動きを知ったアイシスは、兼ねてから決めていたことを開始させた。それは、マーテル国民のコシュナンへの避難だった。
「おまえは先に避難しろ」
ハルヒはナツキにそう言った。一緒に避難するつもりでいたナツキは驚いてカゲトラを見るが、彼も同じ気持ちを顔に出していた。
「姉ちゃんは……?」
フィヨドルで敗退したといっても、黒獅子軍はその戦力を削がれたわけではない。ルシウスの炎に巻かれたあの基地には、ほとんど研究員しか残っていなかった。
いかにマーテル海軍が世界最強と謳われようと、正規軍と真っ正面からぶつかれば、イニス市街地の被害は避けられない。ジグロードはマーテルという国を存続させようとしていたが、アイシスは違った。彼女が守りたいものは国民であり、国土ではない。軍船、商船、個人船。種類を問わず、アイシスは国民をコシュナンへ逃がすために、城の裏手にある入り江に船を集めていた。
「クサナギを見つける」
ハルヒはその顔はどこか吹っ切れたようにナツキに見えた。アキはきっと国境に現れる。マーテルとアイシスを守るために。
「姉ちゃん……」
「あとから必ず行く」
マーテルはこれから戦場になる。ハルヒの言葉を素直に信じられる状況じゃなくなることは、フィヨドルで体験していた。
「もし国境が破られて2時間経っても俺が戻らなかったら……」
「僕も……っ」
「そのときは俺を探しに来い」
自分も一緒に行くと口にしようとしたナツキは、予想外だったハルヒの言葉に目を丸くする。
「まあ、その前に俺は戻るけどな」
そう言って、ハルヒはナツキの頭を撫でた。
「子供扱いしないでよ……」
「子供だろ。まだ15だ」
「ふたつしか違わない。僕が子供なら、姉ちゃんも子供だ」
ハルヒは困ったように眉を下げる。
「姉ちゃんも一緒に逃げようっ」
適合者同士の戦いも、軍同士のぶつかり合いも、ハルヒに出る幕はない。一般人に分類されるハルヒは、アイシスが用意した船で同盟国へ逃げるべきだ。ナツキはハルヒの腕を掴んで、懇願する。
(クサナギさんが……)
ハルヒはアキを引っ張ってくるつもりだ。だが、ナツキは違う意味でハルヒの言葉を解釈した。
(クサナギさんが、姉ちゃんを連れていく……)
自然にナツキの力が強まり、その指はハルヒの腕に食い込んでいく。
(あのことを伝えれば、姉ちゃんは僕の側でいてくれる?)
心の中ではナツキは何度も叫んでいた。アキがアキラを殺したのだとハルヒに訴えていた。それは声にならないだけで、何千回も、何万回も繰り返されていた。
「ナツキ。コシュナンへ逃げる時は一緒だ。約束する」
なにも言えなくなったナツキを離し、ハルヒはカゲトラを見上げる。
「おまえはどうする?」
ハルヒと一緒に国境へ行くか、ナツキを守って安全圏で留まるか。カゲトラはそのふたつのうちどちらかを選べと迫られていた。
「……おまえを抱えてでも国境へは行かせない」
「………」
「と、言ってもだめなんだろう?」
カゲトラはため息をつき、壁に預けていた背中を伸ばす。
「おまえと行く。ナツキ。ハルヒは俺が必ず連れて戻る」
カゲトラの言葉にも、ナツキは顔を上げなかった。うな垂れたその顔をついに見る事ができないまま、ハルヒとカゲトラはその部屋を後にした。
□◼︎□◼︎□◼︎
国境が破られた知らせがアイシスの耳に入ったのは、それから数時間後のことだった。
船の速度と潮の流れを考慮した結果、黒獅子軍は夕刻近くにはマーテルの港へやってくる。アイシスは軍船を含めたすべての船を、マーテルを脱出するための船とした。そのため、この戦いに海戦はない。黒獅子軍と、キュラトスが率いるマーテル軍がぶつかるのは、マーテルの海岸線だった。
長い年月、ジグロードの政治的手腕もあり、世界中から裏切り者と罵られようがマーテルは戦争を知らずに穏やかな時を過ごしてきた。だから、グリダリアが滅んだと言う時も、なにかそれが別の世界の出来事のように、遠い現実として人々は事実を受け流した。自分たちの身に降りかかる現実とは夢にも思わずに。
だが、戦争は足音を鳴らしてこのマーテルへ近づいてこようとしている。戦えない人々は、同盟を結んだコシュナンへ逃げ延びようと反対側の港へと殺到した。アイシスは早めの避難を呼びかけていたが、イニスは大丈夫だという根拠のない自信が、彼らに生まれ育った家を離れることを躊躇させ、結果として市街に大混乱を招いた。
そんな中、ハルヒとカゲトラは逃げ出す人々とは逆方向へと向かっていた。目的地は、グリダリア側に開いた港だ。そこではすでに黒獅子軍を迎え撃つべく、キュラトスを総大将としたマーテル軍が陣を組んで集結している。
市街戦に持ち込まれる前に、相手がまだ船の上にいる間に勝負を決めたい。それがマーテルの思惑だった。そのため、国境には正規軍が集められた。
出し惜しみをしてずるずると後退するようでは話にならない。議会の討論は最後の最後までふたつに分かれていた。ひとつは挙兵し、獅子軍を正面から迎え撃つ案。もうひとつは、国を捨てて全員でコシュナンへと逃げる案。
ふたつ目の案を取れば、大地と誇りは失っても、命は助かる。マーテルの王族の血さえ絶やさなければ、水神は守られ、いつの日かこの地に戻る事が叶った時は国を立て直せる。
アイシスとキュラトスは国民を避難させ、自分は国に残ることを決意した。黒獅子軍をマーテルという水際で食い込めることを決断した。マーテルがここで逃げ出せば、同盟国であるコシュナンの指揮も下がる。マーテルは抑止力にならなくてはならない。ゴッドバウムがすべてを砂と変えていくこの世界で、ほんのわずかでも抑止力にならなくてはならない。マーテルがいま取る態度が、アルカナの未来を決めると、アイシスは考えた。
バルテゴやフィヨドルはあっと言う間に滅ぼされた。アメンタリは同盟を結んだのに焼き払われた。グリダリアは一方的な宣戦布告の後、命乞いも虚しく内側から崩壊した。
いまだかつて、ゴッドバウムに一丸となって立ち向かった国はない。それをマーテルがやらなければならない。それがどんな結果をもたらすことになろうと、アイシスとキュラトスの決心は固かった。
□◼︎□◼︎□◼︎
水平線に見えていた黒い点は、やがてはっきりと船体の形をとってマーテルへ近づいてくる。黒獅子の旗が海風になびいていた。
双眼鏡を顔から話、キュラトスは目を細めた。
あの船の中のどれかにいるのだろうゴッドバウムさえ潰せば、マーテルの勝ちだ。頭さえ潰せば終わる。戦争というものはそういうものだ。黒獅子軍自体も脅威ではあるが、本当の脅威は砂の悪魔に他ならない。
ゴッドバウム・リュケイオン。あの男さえいなければ、こんなにバタバタと国が滅ぶなんてことはなかったはずだった。
(ここで食い止める……!)
市街はもちろん、港になど入れないし、アイシスがいる城に近づけさせはしない。
(必ずここで食い止める……!)
あと数メートルで船が射程に入る。それを確認したキュラトスが大砲の撃ち手に合図を出したそのとき、先頭の船が真っ二つに裂けた。
マーテル軍がどよめき、海風に乗って悲鳴が聞こえてくる。あれを見ろとだれかが叫んだ先には、沈んでいく船の帆先から、別の船の帆先へ飛び移る黒い影の姿があった。
「ラティ……!」
キュラトスが双眼鏡でアキの姿を確認すると、2隻目の船が1隻目と同じ運命をたどる。マーテル軍から歓声が上がった。この調子でいけばアキひとりで黒獅子軍の船体はすべて海に沈む。
黒獅子軍は混乱状態だ。兵士たちがまともな判断が取れないなか、船が跳ね上げた海水を浴びたアキが3隻目に飛び移ったそのとき、彼はゾクリとした悪寒を感じてそのから飛び上がった。
「!?」
その直後、アキが一瞬だけ足場にした帆先がサラサラッと崩れ落ちた。風をまとったアキが見たものは、船上から自分を見上げるゴッドバウムの姿だった。初めて肉眼で見る砂の侵略者の姿に、アキがゾクリとしたものを感じた直後、アキに向けられたゴッドバウムの手のひらがググッと力を込めて握られる。
「う……!?」
アキは全身が乾いていく感覚を覚え、放ちかけていた風刃が霧散する。海水で濡れていたはずの身体が、砂漠に立ったときのように水分を失っていく。アキの周囲にはいつの間にか砂が浮いていた。
「く……!」
完全に砂に捕まれば乾き死ぬ。それがアキの判断だったのか、風神の声だったのかは不明だが、アキはゴッドバウムの力を振り切るために海の中へ飛び込んだ。
「ラティッ!」
遠目には、アキは海に落下したように見えた。真っ青になったキュラトスに、兵士長が砲撃の許可を求める。だが、下手に撃てばアキにトドメを刺すことになりかねない。
キュラトスが躊躇っている間に、海の青が黄色い砂に埋め尽くされていく。空気中に散った細かい砂が砲手からサラサラとこぼれ落ちた。異様な光景にマーテル軍が息を呑む中、兵士の足元に押し寄せてきたのは、波ではなく大量の砂だった。
「な……」
海水だったものが砂に変わり、それに押された黒獅子軍の船がものすごい勢いで海岸線へ押し寄せてくる。
「た、退避しろ!逃げろ───ッ!」
キュラトスの命令でマーテル軍は下がり始めるが、とても間に合わない。ものすごい音を立て、マーテル軍が敷いた前線に黒獅子軍の船が激突した。
「ブハッ!」
砂の中に埋まっていたキュラトスは、窒息する寸前で顔を上げた。その顔からバラバラと砂が落ちる。それは、マーテルの海岸にある砂とは明らかに異質な、キュラトスが触れたこともない砂漠の砂だった。
顔を上げたキュラトスが見たのは、砂と敵軍の船に蹂躙された海岸線だった。準備していた砲台も兵士も、砂にまみれて見る影もない。
ドン!と砲撃音が響いた。黒獅子軍の船から放たれた砲弾が市街へとび、イニスの一角を破壊する。
「クソ……!」
海岸に近づけさせず、射程圏内ギリギリで仕留める作戦は失敗だ。第一次防衛線は突破された。台座から軒並み吹き飛ばされている砲台の中、キュラトスは比較的無事な姿のまま残っているものを見つけ、そこへ走った。
(やられっぱなしでたまるか!)
崩れた木箱から一抱えもある砲弾を持ち上げると、キュラトスはそれを砲手に詰めて、市街を撃ち続ける船を下から狙う。
ドン!と砲手が震え、その砲弾は黒獅子軍の船体の真ん中を吹き飛ばした。船の上にいた兵士が木屑と一緒に砂の上へと落下する。
マーテルの海岸だった場所へ乗り上げた獅子軍の船は船首を斜め上に向けている。その砲弾は、腹の下にいるキュラトスを狙えない。砲弾がある限り撃ち放題だ。
「動けるやつは使える砲手を探して砲弾かき集めてこい!」
ようやく砂の中から起き上がった兵士達に命令を飛ばし、キュラトスは次の砲弾を砲手へ装填し、放つ。とにかく船を全て吹き飛ばす。それがキュラトスの考えだった。
「王子!」
兵士が砲弾を抱えて走ってくる姿が見えた。あれを装填してから二発続けて撃ち込んでやる。そう考えたキュラトスの目の前で、その兵士は船の上から飛び降りてきた男に潰され、砂に血と肉片を撒き散らした。
「……!」
キュラトスはすぐさま砲手をその男に向ける。
「あははぁ!やめとけって、王子様。そんなの俺には効かねえから」
「食らってから同じことほざいてみろッ!」
砲手から砲弾が飛び出し、男に命中する。だが、木っ端微塵に砕け散るはずの男は、その言葉通り微動だにせずにそこに立っていた。
「あーあ」
身体には傷ひとつないが、ボロボロになった服に男は舌打ちする。
「この服気に入ってたんだぜぇ。でもあんたの着てるその鎧もいいなぁ。俺にくれよ」
船体さえ吹き飛ばす砲撃を、この距離で食らって生きている人間なんていない。キュラトスは、いまはもう埋まってしまった城の地下水路で戦った男を思い出す。目の前にいるのは、あのときよりもずっと若い男の適合者だった。
「……グリダリアの、」
「ご名答」
ゴキッと男は首の骨を鳴らす。
「あんたマーテルの王子様だろ?そうだよな?」
「………」
「俺の任務はさぁ、あんたを五体満足でヴィルヒムの野郎のとこまでエスコートすることなんだって。来てくれるよな?」
「おととい来やがれ……!」
「ざぁんねん。じゃあ、同意を得られなかったってことで、腕の一本くらいなくなっても仕方ねぇか」
男はそう言うと、キュラトスに向かってゆっくりと歩いてくる。
キュラトスはゴクリと生唾を飲み込んだ。グリダリアの適合者で攻撃が通じるのはその眼球だけだ。引き付けて、眼球を潰すことでしかキュラトスに勝ち目はない。腰からナイフを抜いてキュラトスは身構えた。
「怪我するだけだからやめとけぇ!」
男はキュラトスに向かって砂を蹴り上げた。男が猛進してくるものだと思っていたキュラトスは、視界を覆う砂を浴びて動揺する。男はその隙に間合いへ飛び込もうとしたが、殺気を感じて逆に飛んだ。直後、鋭い風を受けた砂浜が抉れる。
男はその顔に笑みを浮かべ、風が放たれた背後を振り返った。そこには海水に濡れたアキが立っていた。
「ラティ……!」
「……まぁ、あの程度でくたばりはしないわな。なんたってあんたはヴィルヒムのお気に入りだ。B-101」
グリダリアの適合者の皮膚は硬い。アキの風でも瞬間適合率が高くなければ切り裂くことは不可能だ。それはバロックやチグサで経験済みだった。
能力には相性というものがあるが、バルテゴの能力はグリダリアに対して有利とは言えなかった。
「まずは自己紹介。俺はカイル。話は聞いてるよ。B-986と、G-36を殺ったんだろ?」
アキは反応を見せなかった。
「あぁ、ナンバーじゃわかんねえか。B-986はラッシュっていう、あんたと同じ風神の適合者のガキだよ。もう忘れた?」
忘れるわけがない。ラッシュが放った風は、レーベル社の同僚だったレイシャの首を跳ね飛ばし、結果イスズはフィヨドルの適合者になってアキを憎んだ。
「G-36はバロックってゆうガタイのいいグリダリアの適合者。喋れない奴、覚えてないかぁ?おまえが細切りにしてくれたんだってな。ヴィルヒムが言ってたよ」
あのとき、水の中に落ちてきた肉片を思い出し、キュラトスは顔をしかめた。肉片が浮か水の中を泳ぐなんて真似は二度と体験したくはなかった。
「それにしても、この硬い身体を細切りにしたって、すげえ適合率だよな。まあ、バルテゴの王子様ならその適合率も頷けるかぁ」
黒獅子軍の大群も放ってはおけないが、適合者はもっと面倒だ。早めに潰しておくに限るし、さっき何をされたのかはわからないが、ゴッドバウムはアキにとっていま最大の脅威と言えた。カイルの言う適合率でいうのなら、おそらくゴッドバウムはアキよりずっと上だ。
アキはカイルに向かって風刃を飛ばす。カイルは後ろに飛んでそれをかわし、二発目を腕で跳ね飛ばした。跳ね飛ばされた風刃はキュラトスのギリギリを飛び、彼の金髪が数本砂の上に舞った。
「城へ!」
キュラトスがいたら全力で戦えない。ハインリヒやレイシャのようにキュラトスを巻き込むことを恐れ、アキはそう叫んだ。
「人の心配とは余裕だなぁ。それにこっちは生きるか死ぬかってのに、王族ってだけで簡単にカミサマの細胞に適合しちまうんだから、たまんねぇよ」
「え……?」
アキの表情が変わった。カイルはそれを見て、嬉しそうに目を細める。彼は、完璧そうに見える人間が見せるこんな顔がたまらなく好きだった。勲章をつけた軍人でも、生まれながらに高貴な血筋の王族でも、弱点を的確につけばそのプライドはひび割れ、権威は崩れ落ちていく。元はただの実験体にしかすぎなかった自分よりも低い場所まで落ちていったところを見下ろす瞬間が、たまらなく彼を愉悦に浸らせた。
「そのツラってことはぁ、知らねえんだろうな。アルカナのカミサマが、自分たちの血を引くとされる王族だけは贔屓して、必ず適合者にするってこと」
「!?」
王族のみを差し出せば、国を滅ぼしはしない。いつかのゴッドバウムの言葉がアキとキュラトスの耳によみがえる。王族の血筋の中に神が眠っているから、砂の侵略者はそれを望んだ。神話だと思っていたものは真実だった。だが、その力を研究機関により与えられた王族が必ず適合者になることを、アキとキュラトスは知らなかった。
アキは自分の両手を見下ろす。確かに、どの適合者よりもアキの適合率は高かった。だが、それは偶然なのだと思っていた。適合するのも、適合しないのも、その適合率の高低差も。そう思っていたものを、カイルが否定する。
(じゃあ……)
イスズに刺され、スタフィルスの研究施設に収容されたとき、ヴィルヒムはアキに言った。
(あれは……?)
ヴィルヒムはあのときアキに言った。彼女は不適合者になったと。確かに言った。
「いま気づいたけどあんたさ、」
カイルは自分の目の下を指で指す。
「あいつと同じ場所にホクロがあるんだな」
ゾワッとアキの背筋に寒気が走った。
「……いもうとは、……どこ?」
「泣きボクロっての?俺さぁ、あいつに突っ込んでるときに、あれ舐めんのが好きなんだよね」
カイルは唇の周りをペロリと舐めた。
「セルフィはどこだッ!」
アキは叫び、その身体から竜巻が巻き起こる。砂を巻き込んで荒れ狂う風に、カイルは声を上げて笑った。
ビンゴだ。ヴィルヒムにはまだ秘密にしていろと言われたが、何も知らないアキを目の前にして言わずにはいられなかった。こんなにも面白いことはなかなかない。
「効果覿面ってかぁ!」
竜巻の中から飛び込んできたアキをカイルは素手で受け止め、背を仰け反らせると思い切り頭突きを返す。グリダリアの適合者の渾身の一撃にアキの頭からダラッと血が溢れた。
「ラティ!」
「おっと、やべえ。頭割れちまったかな」
喉に詰まるような声を漏らし、アキは砂の上に倒れた。
「嘘だろ!ラティ!」
駆け寄ろうとしたキュラトスの目の前に、カイルが片手で投げ捨てた砲手が落ちてくる。砂に埋まったそれは、総重量200キロは超える鉄の塊だ。キュラトスはゾッとしてその場から動けなくなる。
「てめえは後で特別なおもてなしをしてやるから、そこで大人しくしてろ。姉ちゃんから引きずり出した水神を仕留めた後でな」
カイルはアキの髪を掴む。顔を血で赤く染めたアキは、目だけを動かしてカイルを見たが、脳が揺さぶられたせいで指一本動かなかった。
「風は怖ぇけど、本体は壊れもんだな。そうだ。頭割ったお詫びに、いいこと教えてやろうか。ラティクスお兄様」
そう言って、カイルは目を細めた。
「セルフィの具合は最高だ。締め付けがたまんねえ。あんたにも味合わせてやりてえけど、兄妹じゃやべえか」
「……ッ」
カイルの言うことが本当かどうかはわからない。セルフィが生きているなんて証拠はない。ヴィルヒムは狡猾な男だ。適合者たちを使って、アキを動揺させるためならどんな手だって打ってくる。だが、もう生きてはいないと諦めていた妹が、もしかしたら生きているかもしれない。その可能性にアキは動揺を隠せない。
「あんたも会いたいだろぉ?だったら俺と行こうぜ。あんたが戻ればみんな大喜び。それに俺も褒められる。良いことづくしだ。そう思うだろぉ?」
戦局はマーテルとって不利になっている。アキが戦線を離脱すれば、キュラトスは捕らわれて、イニス市街地は砂に呑み込まれ、間違いなくアイシスは殺される。
「どうする?」
カイルはアキに決断を迫る。銃声が鳴ったのはそのときだった。撃ち抜かれたカイルの右目からダラッと血が溢れ出す。
アキとキュラトスが振り返ると、そこには銃を構えたハルヒの姿があった。撃ち抜かれた右目を押さえ、カイルは腹の底から叫び声を上げる。
残る左目に狙いを定めていたハルヒは、暴れ出した標的にチッと舌打ちした。狙いたいのは眼球だ。それは、止まっていても当てことが難しい小さな的だった。
「立て!逃げるぞ!」
早々に見切りをつけ、ハルヒはアキとキュラトスに叫んだ。
「こっの、クソアマァァッ!」
カイルはハルヒの姿を見つけると、怒りに我を忘れて突っ込んでくる。真っ直ぐに来るならばと、逃げずに狙いを定めようとしたハルヒをカゲトラが横から掻っ攫い、なんとかカイルの拳をかわした。
「ラティッ!」
キュラトスがアキに駆け寄り、その腕を掴んで身体を引き起こした。アキの頭から流れる血はまだ止まっておらず、意識も朦朧としている。本当なら動かしたくはないが、戦場でそんなことを言っていられない。キュラトスはアキの腕を肩にかけ、砂に埋もれた海岸に向かって声を張り上げた。
「第一次防衛線は放棄する!マーテル軍は市街地まで下がれッ!」
「逃げんのかァ!」
叫んだカイルの顔に弾丸が当たって弾ける。外したが、ハルヒは冷静に次の弾を装填する。怒りに顔を歪めたカイルを、アキの風が吹き飛ばした。砂の上を転がったカイルは凶悪なものへと変化した顔を上げ、アキを睨み付ける。
「わかったよぉ!お兄様!あいつにはそう伝えるさ!」
「……!」
「喜べよ、アキ・クサナギ!セルフィはヴィルヒムのためにおまえを殺しに来るぞ!あいつにズッタズタにされちまえッ!」
逃げる背中にかけられたカイルの言葉に、車へ飛び込んだハルヒの目がアキに向いた。
「……セルフィ?」
ハルヒがそう口にしたとき、城にある鐘のはるか上空に炎が上がった。ハッと顔を上げたアキは、ミュウの合図を確認する。何度も打ち上げられる炎は、アイシスに危険が迫っていると伝えるためのものだった。
「アイシス……!」
アキはそう口にして、風をまうと車から飛び上がる。
「ラティ!」
キュラトスの呼び声には答えず、アキはそのまま物凄いスピードで城へと飛び去っていった。
ハルヒも車のアクセルを踏んだが、横から強い突風を受けた車体は吹き飛ばされた。咄嗟にハンドルにしがみついたハルヒと、助手席にいたキュラトスの上からカゲトラが覆いかぶさるが、3人は横転した車から投げ出されて砂の上に落下する。
「うえ……っ」
これで砂に埋まるのは今日2度目だ。口の中に入った砂を唾と一緒に吐き出したキュラトスは、すぐ側で倒れていたハルヒに気づき、彼女に駆け寄ろうとして我が目を疑う。
「なんだよこれ……」
さっきまで、海岸を埋め尽くしていた黒獅子軍の船が粉々に砕けて散らばっていた。その骨組みさえ残っているものは一隻もない。何がどうなればあの大型船をここまで破壊できるのかわからず、呆然と立ち尽くすキュラトスは、ハルヒの呻き声に我に返った。
「ハルヒ、大丈夫か?立てるか?」
「なんなんだよ……いまの……」
風なんか吹いていなかったのに、突然車が吹き飛ばされた。風神の適合者としか思えないが、アキはマーテル城へ行ってしまった。ならばヴィルヒムか。そう思って起き上がったハルヒは、粉々になった黒獅子軍の船体の向こう、沖合にボンヤリと見えるものを確かめようと眉間にしわを寄せた。
「嘘だろ……」
見間違いだと思いたいが、そこには海を覆うほどの白獅子軍の旗を掲げた船体が見えた。マーテルにとっては最悪のタイミングだ。
ハルヒは微かな声に反応して背後を振り返る。そして、車体の下から見える太い腕に気づいた。
「カゲトラッ!」
ハルヒは上下逆さまになった車体に駆け寄り、その下にいるカゲトラを引っ張る。キュラトスもそれを手伝うと、車体の下が砂であったことが幸いし、ふたり掛かりでどうにかカゲトラの巨体を車の下から引き出すことができた。
「カゲトラ!おい!しっかりしろ!」
カゲトラの脚を見てキュラトスは絶句する。彼の脚には車の部品だろう鋭利な破片が突き刺さっていた。ハルヒもそれに気づく。どこまで深く刺さっているのかは、破片の全体像を見ていないためわからないが、動脈を傷つけている可能性はある。その場合、抜けば大量出血だ。
キュラトスは辺りを見回し、砂の中に埋まっている軍用車を見つけた。砂を払いのけてエンジンをかけると、勢いよくその回転が始まる。
「ハルヒ!」
車から飛び降りたキュラトスはハルヒを助け、ふたりがかりでカゲトラを車へ乗せる。
「マーテル兵は聞け!第一防衛線は破棄!全員城まで退避しろ!」
キュラトスは再び叫んだ。海岸で動く影はまばらだ。もうどれだけの兵がこの声を聞いているのかはわからない。ゴッドバウムはアメストリアにくれてやればいい。キュラトスはそう叫ぶ。黒獅子に蹂躙されるにしろ、白獅子に呑み込まれるにしろ、マーテルは確実に落ちる。いまできることは、アイシスの望み通り、ひとりでも多くのマーテル人をコシュナンへと避難させることだった。
「キュラ!乗れ!」
ハルヒの声に、キュラトスは車へ向かおうとして、自分の足元で跳ね上がった砂にビクリと足を止めた。
「うわッ!」
ハルヒとカゲトラが乗る車の周りも、まるでかまいたちのように風が吹き荒れ、砂や建物を切り刻んでいく。風の適合者がいるのだと気付いたキュラトスは、ゾクリとした悪寒に顔を上げた。
自分の頭上空高く、そこにはズラリと並んで浮かんでいるアキがいた。
「……なん、」
キュラトスは言葉を失う。それはハルヒも同じだった。端から端まで、一列に並んでいるのは、アキと同じ顔をした適合者だった。これはなんの悪夢だ。ハルヒの額から一筋の汗が流れ落ちる。
「おや、まだ生き残りがいたのか?」
もはや破壊された船の上から、やはりアキと同じ顔をした適合者に抱かれて姿を見せたのは、アメストリアだった。
黄金色の髪を砂の海になびかせた毒蛇が、いまマーテルの大地へ降り立った。
□◼︎□◼︎□◼︎
キュラトスが戻るまでは絶対にこのマーテルの大地から離れない。
いまだコシュナンの援軍は到着する兆しを見せないと言うのに、その一点張りのアイシスに困り果てた元老院は、妥協案を打ち出した。それは、せめていつでも逃げ出せるように、脱出船のそばで待つと言うことだった。王を置いて自分たちだけが逃げるわけにはいかない元老院は必死だった。
アイシスはそばで控えるクロノスと、その腕で震えているロクサネに目をやる。ロクサネは一言も話さず、クロノスの腕の中から動かない。フィヨドルを失った時と同じ空気をロクサネは感じ取っていた。
クロノスはアイシスのロイヤルガードを断ったが、亡命したロクサネを受け入れてくれたマーテル王を残してコシュナンへ向かうことは、フィヨドル王家の名を汚すことになるため自分も残ることを選んだ。彼はロクサネだけはコシュナン行きの船に乗せようとしたが、ラウルの死でショックを受けた彼女はクロノスのそばから離れることを泣いて嫌がった。
自分が動かなければ、クロノスもロクサネもマーテルの道連れにしてしまう。幼い王女を想い、アイシスはようやく首を縦に振った。
元老院は胸を撫で下ろす。とりあえず船まで行けば、いよいよとなってもすぐに逃げ出せる。イニスへ大軍が押し寄せても、彼らが反対側の隠し港までやってくる前に、自分たちはマーテルを後にし、コシュナンへ望みを繋げることができる。
「マーテル王……」
アイシスの決断がロクサネのためだと言うことはわかっていた。クロノスは拳を握りしめた。
本来であれば騎士である自分はマーテルの王子と前線で敵を迎え撃つべきだった。それが数日間とはいえ、マーテルに保護してもらったことに対する恩義だとクロノスは考えていた。だが、まだ幼いロクサネは戦争の気配に敏感に反応して、クロノスから離れてはくれなかった。
(俺だけ安全な場所で……)
騎士としての不甲斐なさを感じながら、クロノスはマーテル城を照らす夕焼けへ向けられた。どこかもの悲しい光が照らす光を、クロノスは我を忘れたように見つめる。
「……クロノス?」
何度かかけられたロクサネの呼び声で我に帰ったクロノスは、不安そうな彼女に大丈夫だと首を振る。
アイシスが隠し港へ向かうことが決まると、ロイヤルガードであるルシウスも壁に預けていた身体を起こした。
前後を兵士と議員、そしてロクサネを抱いたクロノスとルシウスに守られながら、アイシスは入り江を目指すことになった。王宮関係者のみが乗船を許された船は、一般のマーテル人が乗り込む手筈となっている隠し港とは少し離れた場所にある小さな入り江に停泊していた。
城を下っていくアイシスの目に、砲撃によって崩された街並みが映る。あんなに活気付いていた街並みには砂が降り積もっていて、すでにマーテルが滅亡したような光景だった。城の中にも自分たち以外の人間はだれもいない。
「ど、どうした!なぜ止まる!」
元老院のひとりが声を上げる。兵士の前には不自然に砂が散らばっていた。アイシスの後ろに続いていたルシウスがピクリと反応した。
「早く行け!」
一刻も早く入り江に避難したい。元老院のひとりは立ち止まった兵士を後ろから小突く。すると、グラリと兵士は倒れ、身につけていた鎧が床に当たってバラバラになる。そのパーツの間からこぼれた砂が床に撒き散らされた。
クロノスがロクサネの目を覆い、腰の剣に手をかける。元老院は悲鳴を上げて座り込んだ。ルシウスがアイシスを自分の背後へ引き戻すと、元老院ふたりも砂となって崩れ落ちた。サラサラと流れ落ちる砂の道を踏み締め、その男は暗闇から姿を現す。
「ゴッドバウム……!」
クロノスがゴクリと喉を鳴らした。自然と力が入ったクロノスに抱きしめられたロクサネが恐怖に震え出した。
「行け」
ルシウスが手に炎を灯す。
「でも……!」
「全員邪魔だ!さっさと行け!」
ルシウスの怒鳴り声に、クロノスがアイシスの肩を押した。ゴッドバウムは祖国の仇だ。だが、ここにいてはロクサネに危険が及ぶ。
「すまない……!」
入り江へ続く道は塞がれた。別のルートで向かうしかない。その場から離れていくアイシスたちを視界の端で見送り、ルシウスはフィヨドル基地の惨劇以来の再会となる父親を、炎の揺らめきの向こうに映した。
□◼︎□◼︎□◼︎
アイシスは半ば兵士に引き摺られるように走っていた。途中何度も振り返るが、ゴッドバウムが追ってくることも、ルシウスが追いついてくることもなかった。
やっとの思いで兵士がアイシスを連れて行ったのは王座の間だった。気が動転しているのだろう。向かっていた入り江からはかなり遠ざかってしまった。それでも、涙を浮かべて息を切らす若い兵士を責めることはできず、アイシスは再び戻って来た王座を見上げた。
長年、あの席に座っていたジグロードの姿は、まさに王そのものであったと思う。政略を巡らして戦争を避け、マーテルを栄光へと導いた王。
自分はそんな彼とは大違いだ。そのやり方がどんなに非人道的なものだったとしても、彼はマーテルを戦火には巻き込まなかった。王と民、どちらが欠けても国は成り立たない。いま、この瞬間にも、多くの民が兵士として戦い、命を落としているのかも知れないのに、自分は―――。王と言う名の非力な自分をアイシスは痛感していた。
「陛下!」
王座の扉を開け放ち、砂にまみれた兵士が飛び込んでくる。キュラトスが戻ったのか、その知らせを望んだアイシスは兵を振り返る。
「コシュナンの船です!」
「え……」
「コシュナンの船が沖合いに見えたと報告が!100を越える軍船です!」
それはマーテルへ射した光だった。
「や、やりましたぞ、陛下!」
元老院たちが手に手を取り合う。キュラトスが命がけで結んだ同盟が、いま海を越えてやってくる。これで多くの国民を救うことができる。すぐにロクサネを連れて港へ行くようにクロノスに命じようとしたアイシスの視界で、手を取り合って喜んでいた元老院たちの首が身体から離れ、床に落ちた。
首を失った身体は折り重なるように血だまりの中へ倒れ込み、ロクサネが悲鳴を上げる。
「陛下!」
クロノスが立ち尽くしているアイシスを床に押し倒す。その上を通り過ぎた風の刃が、王座の周りにいた兵士をバラバラに切り刻む。
王座の間へ入る扉から、深くローブを被った小柄な人物が姿を見せた。扉の横で震え上がっている兵士が逃げようとした瞬間、その首は天井にまで飛ばされた。
玉座の間にいた護衛の兵士が、元老院の面々が、たったの数秒でひとり残らず殺された。適合者の力を改めて思い知らされたクロノスは、アイシスとロクサネをどうにか守ろうと、剣を構えた。
「無駄ですよ。フィヨドルの騎士候よ」
ローブの人物の背後からそう言って現れたのは、ヴィルヒムだった。
「もう逃げられた後かと思っていましたが―――ロクサネ様も、まだここにいらしたとは、私も幸運だ」
「ヴィルヒム・ステファンブルグ……!」
フィヨドルを滅ぼした黒獅子軍研究機関の代表。この男の研究のためにロクサネたったひとりを残してフィヨドル王家は滅んだ。クロノスが剣の柄を握りしめると、ローブの人物が胸の前で手を構えた。
あの手が振られたら首が飛ぶ。その前にこの剣で、一撃のもとに息の根を止めなければ勝機はない。自分が殺されてしまえばアイシスとロクサネを待っているのは地獄でしかない。
ロクサネを突き飛ばしたクロノスの足が床を蹴る。わずか二歩でローブの人物の間合いに入る。長剣がローブを切り裂く。その瞬間、風が放たれた。
脇腹に浅い痛みを感じ、クロノスは身を翻す。痛みからして傷の程度は浅い。もう一撃―――、クロノスはローブが剥がれ落ちた風使いに向かって剣を振り下ろす。
「―――やめてっ!」
それをアイシスの悲鳴が制した。クロノスも剣を振り上げたまま、その適合者を凝視した。それはまだ少女だった。
「……!?」
ズキンっと、差し込むような頭痛を感じたクロノスの目の前で、部屋に差し込む夕焼けの光が少女を照らす。ゴザの惨劇の記憶と、目の前のその映像が揺れながら重なっていく。
「セルフィ……っ」
アイシスがその名を口にした。セルフィと言うその名が、黄昏の中に消えたクロノスの記憶を揺り動かす。
(その実験体を―――殺してはいけないよ)
「うッ!」
激痛に膝が折れた。セルフィが突き刺した風の刃が、クロノスの右腿を貫通する。
「クロノス!」
ロクサネがクロノスの背中にしがみ付く。セルフィは表情のないその顔をアイシスへ向けた。
「マーテル王。あなたはどうして私を知ってるの?」
その唇がアイシスに問いかける。細い首が不思議そうに傾げられる。
ドン!天井を突き抜けた炎が、空高く放たれた。
ドン!ドン!続けて何発も、マーテルの空に炎があがる。見覚えのあるその芸当に、ヴィルヒムとセルフィは背後を振り返った。
「これは驚いたな」
そこに立っていたのはミュウだった。炎を放った手を震わせ、怯えるようにその目はヴィルヒムを見ている。
「無事だったのだね―――ミュウ。もう生きてはいないものと覚悟していたのに」
ヴィルヒムは笑顔で両手を広げた。
「探していたんだよ」
それは追い求めた父親の胸だった。吸い寄せられるようにミュウは足を進ませる。
「本当に無事でよかった。私の大事な娘―――」
まるで呪いのようだ。ヴィルヒムの声には、ミュウが逆らえないなにかがある。見捨てられたことを知りながら、ミュウはヴィルヒムの胸に抱きついた。
ヴィルヒムの大きな手がミュウの後ろ頭を撫でた。それは彼女にとって安心できる父親の手だった。数秒間それを堪能したミュウは、やがて自分から父親の胸を押し返す。その顔に子供染みた表情は残っていなかった。
「アキが来るよ」
「……ミュウ?」
「いまここに呼んだ。アキはパパを殺しに来るから」
「そうか……」
それがどうしたとでも言うように、ヴィルヒムはミュウを再度抱き締めようと手を伸ばす。それに対してミュウは炎で応えた。父親に刃を剥いたミュウに、セルフィが父親を庇って身構える。
「なんのつもり?」
「どうもこうも……」
ミュウは皮肉を込めた微笑をその顔に浮かべた。
「そろそろ、あたしたちも父親離れする時期じゃない?」
「お父様を傷つけるのは許さないわ」
「本当の父親じゃないでしょ」
セルフィは眉間にしわを寄せる。確かにヴィルヒムと血の繋がりはない。だが、いまさらそれがなんだと言うのか。セルフィはミュウの意見に賛同できない。
「お父様はお父様よ」
「……あたしもそう思ってたかったよ」
向かい合ったふたりの手に風と炎が生まれる。適合した神の力は違うが、ふたりはヴィルヒムのもとで共に育ってきた姉妹だった。
「撤回して!」
セルフィが風刃を飛ばすが、そのすべてはミュウにかすりもせずに通り過ぎる。それは所詮威嚇にしか過ぎなかった。適合者同士の姉妹喧嘩なんて冗談でも居合わせたくない現場だ。だが、いまなら逃げられるかもしれない。
クロノスは痛む頭と足を引き摺ってアイシスのもとへ向かう。どうにかふたりだけでも無事に逃がそうとするクロノスの背後から、ヴィルヒムが風の刃を振り上げた。
「させない!」
ミュウの放った渾身の炎がヴィルヒムを包んだ。
「ミュウッ!」
激怒したセルフィがミュウの肩を風の刃で切り裂く。だが、すでにヴィルヒムは炎に包まれ、真っ黒に炭化していく。どうせクローンだ。そう思っても、黒焦げになった父親の死体にセルフィは苦々しく顔を歪めた。
(アキ……!)
肩を切り裂かれたミュウはヨロヨロと後退しながら、傷口に手の平を当てる。肉の焼け焦げる匂いが辺りに漂った。
風神の力は鋭利な刃物だ。掠っただけなら大したことがないと思っても、そこから流れ出る血で徐々に体力が奪われていく。
「ミュウ……!」
セルフィの目にはミュウに対する殺意が宿っていた。裏切り者!そう叫んだセルフィが、ミュウに風刃を飛ばそうとしたそのとき、キイイイイイイイッ、と耳を裂くような共鳴が彼女を襲った。
いまだかつて感じたことのない強烈な共鳴にセルフィは悲鳴を上げて頭を抱える。それはミュウにとって絶好の好機だった。ミュウは握りしめた炎の拳でセルフィの心臓を狙う。
「だめ!」
その前にアイシスが身を投げ出し、ミュウは息を詰まらせて、握りしめた右手の拳を止めるため、自分の左手で右腕を掴む。それでもアイシスの髪は熱で焼け焦げた。ふわり、とアイシスの金の髪がセルフィの頬を撫でる。
(アイシスお姉様―――)
断片的に甦る幼い記憶が痛みとなってセルフィを襲った。
「う、ああああ――――――っ!!」
共鳴の痛みと、記憶の渦に襲われ、セルフィは頭を抱えて絶叫する。暴風が王座の間に吹き荒れる。
その風はロクサネを庇ったクロノスの背を大きく切り裂き、オートで適合者を守ろうとした炎の盾をぶち抜いてミュウを切り裂いた。
「はぁっ、はぁっ……!」
暴走する風神の力をなんとか収めようと、セルフィは自分自身を強く抱きしめる。その彼女の足元で、真っ赤に染まった長い金色の髪がバラバラに散らばった。視線をずらしたセルフィの視界の中で、ズタズタに切り裂かれたアイシスが、その震える手をセルフィに手を伸ばす。
「セル――フィ……―――」
真っ赤に染まった白い手に恐怖を覚え、セルフィは悲鳴を上げて窓から飛び出した。
それと入れ違いに、ようやく共鳴から解放されたアキが反対側の窓から飛び込んでくる。それは遅すぎた到着だった。
これまでになく酷い共鳴が遠ざかっていくことを感じながら、アキはこの場にいるはずのアイシスとミュウの姿を探した。王座の前には何人もの人間が倒れている。首のない死体、血塗れの死体。ドクドクと激しく鼓動する心音が頭にまで響く。絶望的な予感を味わいながら、アキは彷徨わせていた視線を、床に広がった長い髪で止めた。
「……アイシス」
血だまりの中を歩いたアキは、床に倒れているアイシスを抱き起こす。血にまみれた顔を服の袖で拭ってやると、アイシスはわずかに目を開けて、瞳に映ったアキの姿に微笑んだ。
「ラティ―――」
アイシスから流れ出る血は止まらない。おそらく、全身の動脈が切り裂かれている。どんなに優秀な医者がここにいても手の施しようがない。このまま死ぬのを見ているしかない。
「キュラに、伝えて―――」
アイシスは力の抜けていく腕を持ち上げ、アキの頬に触れた。
「ありがとうって……」
アキはだめだと首を振るが、アイシスの身体からは急激に力が失われていった。その命が燃え尽きていく。
「……ラティ。―――もう一度あなたに、会えて……よかった……」
もう、アイシスの目にはアキの顔がはっきりとは見えなかった。その身体が青白い光に包まれていく。
「……セルフィ」
アイシスの唇を震わせた妹の名に、アキは息を呑む。再会してから、アイシスは一度だってセルフィの名を口にすることはなかった。それはキュラトスも同じだった。アキの態度から、セルフィはもうこの世に生きていはいないものと知り、ふたりはセルフィの名を口には出さなかった。
(いまの……共鳴はまさか……)
「ごめん……ね……」
「アイシスッ!」
カッと眩い光が迸り、その光の中でアイシスの身体は輪郭を失っていく。数秒も立たずに、アキは握っていたはずのアイシスの手の感触を失った。
□◼︎□◼︎□◼︎
黒獅子軍に比べ、白獅子軍は数の上で不利だった。だが、彼らはスタフィルスでのクーデターを成功させ、フィヨドルをゴッドバウムから奪い取り、そしてこのマーテルまでやってきた。
軍と呼ぶにはあまりに人数が乏しい。それはだれもが思っていたことだったのに、何度もよみがえる白獅子軍を、フィヨドルの避難民は不死軍と呼んでいた。それをハルヒは思い出していた。
次々に、砂浜へとアキと同じ姿をした適合者が降り立つ。さっき、マーテル城の方角へ飛び去ったアキがいなければ、ハルヒもキュラトスもこの中に本物がいるのではないかと探したかもしれない。それほどその適合者たちはアキそっくりだった。
―――クローン。ハルヒはアイシスがアキから聞いたという言葉を思い出していた。何度殺してもよみがえって姿を見せるヴィルヒムの謎はそれで解けた。
「誰かと思えば―――」
カゲトラを庇うように身を低くし、自分に銃口を向けるハルヒの姿に、アメストリアは口の端に笑みを浮かべた。
「小娘。まだ生きていたのか」
ハルヒは返事の代わりに引き金を引いた。狙いを定めた銃弾は、アメストリアの眉間を捕えて発射され、直前でクローンのどれかが腕の一振りで弾き飛ばした。アキのクローンたちはハルヒを敵と認識する。
「殺すな」
アメストリアがそれを止めた。
「この娘は丁重にもてなさねばならん。死なぬ程度に、少しずつ―――少しずつ切り裂いてやれ」
ハルヒの前にキュラトス自分の身体をねじ込んだ。悪夢続きで頭がどうにかなりそうだと思いながら、彼はどうにか立っていた。
「マーテルの王子か」
キュラトスの顔でそう判断し、アメストリアはクローンたちを下げた。
「……ハルヒとバンダを見逃すと約束するなら、マーテルの王子が捕虜になってやる」
「キュラ!」
「どうなんだ!」
この状況でハルヒの意見を聞いている余裕はない。キュラトスはハルヒを無視してアメストリアの返事を促す。
「―――いいだろう」
アメストリアはキュラトスの提案を了承した。
「ハルヒ。行け」
「できるわけ……!」
「頼むから行ってくれ!このままじゃバンダが死ぬぞ!」
カゲトラには一刻も早い手当が必要だ。キュラトスの背中と、意識のないカゲトラへ交互に視線をやったハルヒは、ギリっと奥歯を噛み締めると車に乗り込みアクセルを踏み込んだ。遠ざかっていくエンジン音を聞きながら、キュラトスはホッと息をつく。
車が巻き起こす砂煙を眺めながら、アメストリアはキュラトスの前まで歩いてくる。
「つくづく―――わからんな」
ささくれひとつないアメストリアの手が、砂と埃で黒く汚れたキュラトスの頬を撫でた。
「………」
「クサナギといい、そなたといい、あんな小娘のなにがおまえたちを惹き付ける?」
「……さあな」
チクリとした痛みにキュラトスは眉をしかめる。アメストリアの爪はキュラトスの頬に食い込み、そこからジワリと血があふれた。
「……もういいだろう。追って殺せ」
クローンに向けて命令が下される。
「おい!約束しただろ!」
「すでに小娘は視界から消えた。私はそなたの言う通りに見逃した。なんの不服がある?」
キュラトスは言葉遊びを始めたアメストリアの手を振り払う。振り返ったその目がマーテル城に満ちた青い光を映した。見覚えのある光景にキュラトスは言葉を失う。
マーテルの大地が轟音を響かせて揺れ動く。嘘だと呟いたキュラトスの声は、マーテル城を突き破って出現した水神の咆哮にかき消された。
□◼︎□◼︎□◼︎
地鳴りで隠し港の天井になっている岩盤がパラパラと崩れてくる。何事かと船の上の人々が顔を見合わせた。
コードは険しい顔時計に目をやった。キュラトス率いる正規軍が国境へ向かってから、すでに半日が経過している。戦況はどうなっているのか。海岸線で黒獅子軍を食い止めたのか、それとも市街戦になっているのか。数時間前から詳細を知らせる連絡は途切れていた。
「………」
最悪の事態が考えられる。海岸線が破られたのなら、アキを探しに行ったハルヒの無事も絶望的だった。
「大丈夫?」
ココレットの声に、コードは彼女へ目を向ける。
「ああ……」
「ねえ、ナツキを見た?」
「いないのか?」
「ええ。この船に乗ってるはずなの。カゲトラさんに、自分が戻るまでついていてやって欲しいって言われてたのに……」
コードが甲板を見回した直後、港が縦に揺られる。海面大きく波打つ。天井から落ちてきた岩盤を見た乗組員たちが、慌てて船を出港させる準備に入った。
「待ってください!」
ナツキが船に乗っていないかも知れない。ココレットは慌てて乗組員を止めた。
「もう待てない!」
この揺れも黒獅子軍の仕業かも知れない。いまにも岩盤が崩れしてくるかもしれない恐怖が船乗りたちを駆り立てていた。船がゆっくりと港を離れていく。
「おい!」
コードがそれに気付いた時にはもう遅く、ココレットは甲板から桟橋へと降り、港を走り出していた。
「お嬢様!」
メアリーが手すりにしがみ付く。
「船を戻して!」
「違う船で行くわ!」
船員の胸倉を掴むメアリーに、ココレットは手を振った。
「コード!メアリーをお願い!」
そう言うと、ココレットは王城へと引き返す。城内が激しく揺れる中、壁や柱に掴まりながら進んだココレットは、通路に響く兄の声に気づいた。
(お兄様……!?)
兄であるルシウスは、ロイヤルガードとしてアイシスと行動を共にしているはずだった。ココレットは反響する声を頼りに通路を進む。
「いい加減、燃えろッ!」
ルシウスの炎を渇いた砂の壁が防ぐ。一度も当たらない攻撃にルシウスはイラついていた。
ルシウスは本気だった。父親といえど、本気で殺すつもりだった。だが、彼は防ぐばかりで攻撃ひとつしてこない。まるで立っているステージが違うとでも言うように、ルシウスは完全にゴッドバウムの手のひらの上で遊ばれていた。
「この……!」
さらに炎を投げつけようとしたルシウスは、足下の揺れで壁に手をついた。上で何が起こっているのか、この地鳴りは異常だ。それには気づいていたが、ゴッドバウムから目を離すわけにはいかない。
「……出たな」
ゴッドバウムがそう口にした。久しぶりに聞いた父親の肉声は酷く掠れていた。まるで何かと重なるようなその声に、ルシウスは違和感を抱く。
「何が出たと……!」
そう言いかけたルシウスは、崩れ落ちてきた天井に気づいて床を転がると、次々と落ちてくる瓦礫から身を守ることを優先する。
やがて静かになった周囲に顔を上げたルシウスは、ぱっくりと穴が開いた頭の上を通り過ぎていく巨大な何かを見た。
「水神……!?」
マーテルの守護神を見るのは二度目だった。ルシウスは我が目を疑うが、マーテル全土に響き渡るような水神の鳴き声に、アイシスがもう生きてはいないことを確信する。
「水神マーテル……」
ゴッドバウムの声にルシウスはハッと我に返った。同じものを見ていた彼の父親は、崩れた瓦礫の上を砂が砂の山を滑るように進んでいく。
「逃がすと思っ……!」
再び炎を生み出そうとしたルシウスの首に、人間の手を模したような砂が絡みついた。砂の一粒一粒が、生きているようにルシウスの気道を締め上げる。声も出せないルシウスは必死に砂を掻き毟るが、つかみ所のない砂を引き剥がすことはできない。
「……っぐ」
砂に持ち上げられ、ルシウスの足が宙に浮く。絞め殺されると思ったそのとき、二発の銃声が響いた。
「ゲホッ!ゲホゲホッ!」
首を絞めていた砂が散らばり、ルシウスは喉を押さえてむせ込む。急激に取り込んだ酸素のせいで歪む視界を凝らすと、そこにはゴッドバウムに銃を向けるココレットの姿があった。
「お兄様、逃げてください!」
ゴッドバウムがゆっくりと手をあげる。その手の先に、砂で形作られた槍が姿を現した。
「───やめろッ!」
ルシウスは転がるように走るが、その前にゴッドバウムの砂の槍はココレットの胸に突き刺さり、目的を果たして飛び散った。
「――――――き、さまアアッ!!」
渾身の炎を手にしたルシウスの背後を、水神の青い光が貫いた。衝撃と爆風に吹き飛ばされ、ルシウスは倒れたココレットのそばに転がる。
倒れた子供たちには目もくれず、ゴッドバウムはマーテルの空を飛び回る青い光を見上げると、どこからか集まってきた砂の中に姿を消した。
「……ッ」
脳震盪を起こして朦朧としていた意識を、首を振ることで取り戻したルシウスは、そばで倒れているココレットに気付く。妹の白い顔には砂の粒子が散らばっていた。
(また守れなかった―――)
込み上げる後悔に震える手を伸ばし、恐る恐る触れた妹の頬はまだ温かかった。
「う……ん」
ココレットの唇から小さな声が漏れた。ルシウスは自分の耳を疑ったが、彼の腕の中でココレットの閉じられていた瞼はピクピクと震え、ゆっくりと開いていく。
「お、兄様……?」
「……ココレット」
砂の槍に貫かれたはずだ。どうして生きているのかと、ルシウスは貫かれたココレットの胸に手を触れた。そこからルシウスの母の形見である懐中時計が転がり落ちた。
ルシウスはロイヤルガードとしてアイシスを守らなければならず、ココレットとコシュナンへ向かうことはできなかった。そのため、別れる前に彼は懐中時計をココレットに持たせていた。
「………」
懐中時計にはぽっかりと穴が開いていたが、裏面は衝撃に耐えていた。それは、まさに皮一枚でココレットを砂の槍から守っていた。
(皮肉だな……)
ココレットが生まれたことで命を絶った母親の形見が、他でもない彼女を救うことになるなんて、だれが予想できただろう。
「お兄様……」
「喋るな」
懐中時計が守ったと言っても、脂肪が乏しいココレットの胸は圧迫されてダメージを受けている。
アイシスが死んだとわかった以上、これ以上マーテルに留まる意味はない。ルシウスはココレットを抱き上げると隠し港へと向かった。だがそこに船は一隻も残っていなかった。
「ごめんなさい。行ってしまったの……」
ココレットがそう言った。
「もう待てないって……。メアリーと赤ちゃんが、コードも乗ってて……」
少し混乱しているのか、ココレットの話はあちこちに飛んでいる。息が途切れがちになるココレットにもう話すなと言って、ルシウスは船のない隠し港に背を向けた。
□◼︎□◼︎□◼︎
(―――他に、どんな未来があったんだろう?)
青い光に跳ね飛ばされ、砕けた王座の上に倒れこんだアキは、猛り狂う水神を見上げて、来なかった未来を考えた。
バルテゴが滅びずに、アキとアイシスが結婚して、両国が平和のもとに結ばれていたなら、どんな未来があったのかと考えた。
こんな未来ではなく、リリーの中で幸せそうに微笑む彼女の姿を、穏やかな時の流れの中で見つめることもできたんだろうか。そんな夢のような未来も、確かにあったはずなのに。
「アイシス……」
あの日、恥ずかしげに俯く彼女に、母に託されたリリーを贈った。その頃はまだ国同士の関係なんてそれほど深くは考えてもいなくて、ただアイシスとずっと一緒にいられるのだと言う事が単純に嬉しかった。リリーの花のような彼女を、この手で幸せにできるものだと、信じて疑わなかった。―――そう、信じて疑わなかった。
もう手の届かない水神にアキは手を伸ばす。その想いに呼応するかのように、水神はその長い蛇のような身体をくねらせて向きを変えると、王座の間に突っ込んでくる。
アキはそれを迎え入れるために両手を広げた。バルテゴの血を引くアキに水神を封じることはできない。それでも、アキはその場を動かなかった。
「アキッ!」
ミュウがアキを突き飛ばして、水神の直撃から彼を守る。水神は物凄い勢いで王座にぶつかると、そのまま床を突き抜けていく。マーテル城はまるで積み木のように崩れていった。地下まで城を突き抜けた水神は、また空へと舞い上がった。
「アキ!」
ミュウに呼ばれて、アキはようやく彼女に視線を向けた。アイシスの危機を知らせてくれた彼女もまた、切り裂かれて無数の傷を負っていた。
「神様になんか勝てないよ!マーテルはもうだめだ!逃げなきゃ死んじゃうよ!逃げなきゃみんな死んじゃうッ!」
「……そうだね」
わかったと、アキは頷いた。
「……アキ」
「歩ける?」
「う、うん……」
ミュウが頷くと、アキはクロノスのそばで泣きじゃくっているロクサネに近づく。膝を折ったアキが手を差し伸べると、ロクサネは錯乱状態になって叫んだ。
「大丈夫。ここから一緒に逃げよう。彼も一緒だ」
アキは声を大きくすることはせず、静かにロクサネに言い聞かす。
「ミュウ。手を引いてあげて」
アキに言われ、ミュウはロクサネと手をつなぐ。アキは意識のないクロノスの腕を肩にかけ、ずっしりと重みのある彼の身体を引き上げた。
「城の裏手の入り江に王族専用の脱出船があるはずだよ。行こう」
まさかアイシスを残して船は出港していないはずだ。アキはそう考え、4人は崩れ落ちる城の中、慎重に足場を選んで階下へと下りていく。
「う……っ」
アキの肩で揺られたクロノスが目を開けた。
「……?」
自分の身を支えているアキの横顔がクロノスの目に映る。8年の年月はアキを確かに成長させたが、彼が故郷に死体の山を築いた少年だとクロノスが理解するのに、そう時間はかからなかった。
アキを目の前にすれば怒りや憎しみが溢れ出すものと思っていたが、それはなかった。クロノスは、自分を必死に支えてここから脱出しようとするアキに対し、すでに自分の中に恨みや復讐心が残っていないことに気付く。流れた年月がそうさせたのか、ただ、なにかが違うと思った。
アキの予想に反して、たどり着いた入り江に船は残っていなかった。絶望的な状況にミュウから手を離したロクサネは、クロノスの足にしがみ付く。
「……コシュ、ナンの」
クロノスが意識を取り戻したことに気づき、アキは彼を壁際へ座らせた。
「コシュナン?」
「援軍……。軍船が、そこまで来てると……。ロ、ロクサネさまを……」
息も絶え絶えにそこまで言うと、クロノスはゲホゲホとむせ込んだ。
(援軍が近隣海域まで来てる……)
キイイッ!
「ギャッ!」
ミュウの耳を共鳴が襲った。そのすぐ目の前に、ココレットを抱えたルシウスが飛び降りてくる。
「クサナギさん……?」
「ココレットちゃん……と、大佐……」
「ここにも船はないのか」
同じ目的でここへ来たらしいルシウスに、アキは頷いた。ここにもということは、隠し港にも残っていないのだろう。
ルシウスは舌打ちし、ココレットを下ろすと瓦礫の中に埋まっている扉を引き抜いて戻ってくる。そして、それが波の上に浮かぶことを確認すると、ロクサネ王女と騎士を乗せろと言って、ほかに使えそうな板がないか探しにいく。
「こ、こんな板で海に出るつもり!?」
ミュウが悲鳴のような声を上げた。
「泳ぎたければ泳ぐがいい」
止めはしないと、ルシウスはミュウを見もせずに返した。
もたもたしていればここで生き埋めだ。船がなければこんなものでも駆使して海へ出るしかない。運が良ければコシュナンの船に拾われる。
アキはクロノスに手を貸し、彼を頼りない扉の板に乗せた。続けてロクサネを乗せると、ルシウスが2枚目の扉を持って戻ってくる。アキはミュウに、ココレットと乗るように言った。
海はオレンジ色に染まっていた。クロノスは朦朧とする意識の中、揺れる海面を見つめる。
―――そこまでだ。
8年前の黄昏に染まるゴザの街で、そう言ったのはヴィルヒム・ステファンブルグだった。返り血まみれになった、まだ子供のアキはその場に立ち尽くしていた。
全身を切り裂かれて倒れた目の前の男の姿を映したまま、アキの目は焦点を失ってしまっていた。
その実験体を―――殺してはいけないよ。
ヴィルヒムの言葉に従い、傍らにいた風使いが手を下げた。
―――鬼ごっこはおしまいだ。さあ、おいで―――アキラはもう死ぬ。
瞬間、物凄い共鳴が港街を走り抜けた。風神の力が暴走し、アキを取り囲む黒獅子の兵や、ヴィルヒムや、彼の傍らにいた風使いを切り裂いた。その場で無事だったのは風の壁に守られたアキだけだった。
鋭い風の刃はクロノスの脇腹を切り裂いた。薄れゆく意識の中、クロノスはアキラの名を呼んで泣きじゃくるアキの姿を見ていた。アキはとっくに事切れたアキラの亡骸を抱きしめて泣き叫んでいた。
「………」
さっきまで虚ろだった意識が冴え渡っていく。クロノスが、自分とロクサネを海へ逃がそうとするアキの胸ぐらを掴むと、彼はその目を丸くした。
「……きみじゃない」
「……え?」
セルフィにやられた傷が浅くはないことを、クロノスは理解していた。逃がされたところで自分は助からないかもしれない。だが、これだけは伝えなくてはならない。騎士の誇りをかけて。
「あの日、ゴザの街を切り裂いたのは、きみじゃない……!」
アキの顔に動揺が走る。アキはクロノスを覚えてはいなかった。血塗れになったアキラを目にし、ショックで呆然となっていたアキの目に、クロノスの姿は映らなかった。
ゴザは、アキラに連れられてやってきたフィヨドルの港街だ。そこでヴィルヒムに追い詰められ、アキラは死んだ。ヴィルヒムはアキが殺したんだと言った。アキもそれを否定できなかった。
「きみはだれも殺してなんかない……っ」
アキの胸ぐらを掴むクロノスの手を解いたのは、ルシウスだった。いまは悠長に話しているときじゃない。彼はふたりを乗せた扉を蹴り、崩れゆく入り江から海へと送り出す。波に揺られながら遠ざかっていくクロノスを、アキは呆然と見送った。
(きみはだれも殺してなんかない……)
アキの背後に瓦礫が落下する。砕けた小石が海へ飛び散った。
(じゃあ、誰がアキラを殺したの……?)
アキは覚えていなかった。ヴィルヒムたちにゴザで追い詰められ、初めて体感した酷い共鳴の後、アキが目にしたものは、切り裂かれて倒れゆくアキラの姿だった。
それを見た直後に、アキの頭も、目の前も真っ白になった。我に返ったときには、ゴザは死体が散らばる地獄と化していた。
まだかすかに息があったアキラを助けようとした。だが、手の施しようもなかった。アキラは首を振って遠くの空を指差した。
嫌だと泣きすがった。助けるからと、そんな力もないくせに彼に言った。母は口癖のように言っていた。罪もない人に罰は訪れない。自分を救ってくれたアキラがこんな所で死ぬはずはない。そう信じていた。アキラはアキの手を取って、自分の胸に押し当てると、生きろと言った。
アキラが息を引き取って、どこをどう歩いたのかは覚えていない。その数ヶ月後、アキはスタフィルスで客引きをしていた所を、ハインリヒに拾われた。
(僕じゃないなら、だれが……アキラを……)
霧がかる記憶―――断片的に甦る映像は、自分を庇うアキラの背中と、ヴィルヒムの笑み。そしてその隣には―――。
(誰、が……)
ルシウスがココレットとミュウを乗せた扉を蹴ると、それは不安定ながらもプカプカと浮きながら遠ざかっていく。あとは自分たちだけだ。そう思って振り返ったルシウスは、水神の声にハッと顔を上げる。
「クサナギ!」
ルシウスの声に気づいたアキは、上空から突っ込んでくる水神に気づく。まだ4人を乗せた扉はそれほど離れていない。ここに突っ込まれたら波で転覆してしまう。アキとルシウスはほぼ同時にそれぞれの力を周囲に張り巡らせた。風と炎の結界に水神が激突する。
「お兄様!」
ココレットが身を乗り出すと、バランスが崩れた板の上でミュウが悲鳴を上げた。海水を被ったココレットも慌ててドアノブにしがみ付く。
「あ、ああああんた!ばかじゃないの!」
「ご、ごめんなさい!」
「漕いで!」
ミュウは板に張り付き、腕で必死に海水をかき始めた。
「でもお兄様が!」
「あんた如きになにができんのよ!」
「……!」
「あんたが戻るくらいならあたしが戻ったほうがマシなのよ!あたしらがさっさとコシュナンの船まで行ったら、アキもあんたの兄貴も、クソみたいな神様相手に、あんな命削るような真似しなくて済むんだよ!わかったか!?」
ミュウの言うことは正論だ。ココレットは泣きそうになるのを堪え、ミュウと同じように海面を漕いだ。
「ぐ……!」
ルシウスは胸の痛みに顔をしかめながら、隣のアキに目をやった。どうやら消耗しているのはお互い様のようだ。アキの首もとには、盛り上がった血管が見えた。
ずっと全力を振り絞っていると言うのに、防ぐことしかできない。水神の勢いは衰えない。所詮、自分たちは大地の力のひとかけらを分け与えられただけなのだと、ルシウスが痛感したそのとき、アキの頬までの血管が膨張する。風神の力が膨れ上がり、それは水神の身体を突き破った。
グラリと傾いたアキの身体を受け止め、肩に担ぎ上げると、ルシウスは降りかかってくる水飛沫の中を走り抜けた。この場を切り抜けるためだとしても、自分で動けないほど消耗しては次に続かない。適合率が高かろうと、所詮アキは王族だ。訓練を積んだ軍人とは違う。それに水神は何度砕いたとしても甦る。まともにやりあったとしても勝ち目はない。だが、アキのおかげでココレットたち、入り江を脱出していた。
城を出ると、ルシウスはアキを瓦礫のそばへと降ろした。
「ど、こへ……?」
背中を向けたルシウスにアキが聞く。
「貴様に教える義理はない」
殺されないだけマシだと思え。そう言い残して、ルシウスはその場を後にした。
ルシウスとココレットに起こったことを知らないアキには、なぜ彼がマーテルへ留まって、アイシスのロイヤルガードにまでなっていたのかがわからなかった。
アキは回復すれば船までくらい飛んでいける。だが、アメンタリの能力でそれは難しいはずだ。それでも自分にルシウスを止めることなど不可能だろう。彼の背中はすでに遠ざかり、アキが次に目を開けたときには見えなくなっていた。
「………」
ひとのことに構っている場合じゃない。アキは自分の心臓を落ち着けようと、深く息を吸う。次第に血管の膨張は収まり、呼吸も楽になってきた。水神は一度形をなくしたようだが、まだ消えたわけではない。神はマーテル王家の人間に封印するか、殺すしかない。だが、あんなものをどうやって殺せるのか、アキには見当もつかなかった。この世界で神を殺した男はゴッドバウムだけだ。
(砂の力があれば殺せるのか……?)
フィヨドルもアメンタリもグリダリアも、これまで滅ぼされてきた国の神は砂の力の前に葬られてきた。
(それとも、ゴッドバウムの適合率が、僕らとは桁違いなのか……)
アキはぐっと胸を押さえ、立ち上がった。そこへ鋭い車のブレーキ音が鳴る。アキが顔を上げたそこには、運転席から立ち上がったハルヒの姿があった。
カゲトラの傷は楽観視できるような状態ではなかったが、ハルヒは少し待っててくれと言い残し、壊れた車の窓から外へと出た。
(―――やっと会えた)
胸を押さえ、血管の膨張が首を伝った状態のアキは、言葉もなくハルヒを見ていた。
「クサナギ」
「……ハルヒ」
きみはだれも殺してなんかない。クロノスはそう言った。だが、それを信じる根拠はどこにもない。我を見失っていたあの状況で、アキが力を暴走させなかった保障はどこにもない。
ハルヒは自分の胸の前で拳を握り締めた。
「ずっと……考えてたんだ」
ハルヒが話し出す。
「本当におまえが父さんを殺したのかって……、本当にそうだとしても、本当におまえがやったんだとしても、俺は、おまえがやったなんて思いたくなくて……!」
自分勝手な言い分にしか過ぎない。現場にいたアキすらあやふやな記憶しか持っていないのに、クロノスに話を聞かされるまで、ハルヒは起こった惨劇のことさえ知らなかった。だが、それは彼女の切望であり、正直な気持ちだった。
「……覚えて、ないんだ」
アキの言葉に、ハルヒはハッと目を見張る。
「あのとき、何があったのか……っ、どうしても思い出せないんだ……っ」
アキはワナワナと身体を震わせる。感情が高ぶった瞳から涙が零れ落ちた。ハインリヒが死んでも、アイシスが死んでも泣けなかったアキの、堪えきれなくなった感情が爆発する。
「わからない……、わからないんだ。僕が、殺したの……?僕がっ……だけど、あのひとは違うって……!違うって!じゃあいったいだれがアキラを殺したの!?」
その声はカゲトラにも届いた。もう生きてはいないと覚悟はしていたものの、親友の死をアキの口から知らされ、彼はぐっと拳を握り締める。
「あんなっ、あんな、ズ、ズタズタに、切り裂いてっ……、あんなに血が出て……っ、なんで、アキラが……!」
―――おいで。
差し伸べられた手を、光を失った目で見上げた。そこには白衣の研究者の男がいた。それは、風神のカケラに適合した日の夜だった。月明かりの差し込むベッドの上で寝かされていたアキにその手は差し伸べられた。
「なんでアキラが死ななくちゃ……ならなかっ……――――!」
言葉に詰まるアキをハルヒは抱き締めた。
根拠なんて何もない。それを裏付ける証拠もない。だけど違う―――。
「おまえじゃない……!」
アキを見つめればわかる。真実が見える。絶対に違うと言い切れる。
「おまえがやったんじゃない……!アキ……!」
ナツキは無人になったイニスの町を走っていた。海岸線での戦闘が始まってから、二時間はとうに過ぎていた。姉に言われた通り、ナツキは彼女を捜すために市街地を駆け抜けていた。
息が切れ、肺が痛み、心臓が弾けそうになる。とうとうスタミナが切れて、ナツキは建物の壁に寄りかかって足を止めた。
周りには誰の姿もない。こんなところで発作を起こせば助けてくれるひとはいない。ナツキはだれにも言わずに船を抜け出していた。
(姉ちゃん……!)
再び走り出そうと辺りを見回したナツキは、風に乗って運ばれてきた話し声に気付いた。ハルヒの声だと言うことはすぐにわかった。少し先の建物の向こうに、風に吹かれた黒髪が見えた。
疲弊し切っていた顔に笑顔を取り戻したナツキは、すぐに駆け寄ろうとして足を止めた。その目に、ハルヒに抱きしめられているアキの姿が映った。
「………」
ナツキは声をかけることができなかった。ハルヒに抱きしめられていたアキは、父親を殺したその腕で、強くハルヒを抱き締め返した。その映像を瞼の奥に焼き付けるように、ナツキはまばたきもできなかった。
(姉ちゃん……)
声にならないナツキの声がハルヒに呼びかける。
(姉ちゃん……)
知らず知らずのうちに、ナツキは強く拳を握り締めていた。
(その男がお父さんを殺したんだよ?)
ふいにハルヒは振り返った。突き刺すような視線を感じたからだ。アメストリアがやって来たのかと思い、その手は銃を握り締めていた。
「……ナツキ?」
ハルヒは視界に映ったくせっ毛に気づき、弟の名を呼んだ。すると、家の影からナツキが姿を見せる。
「おまえ、なんで……」
「姉ちゃんを探しに来たんだ」
ナツキは笑顔でそう言った。
「2時間したら探しに来いって言ったでしょ」
それは紛れもない自分の言葉だ。時計を持っていないハルヒには、2時間たったかどうかまではわからなかったが、この戦場でナツキとすれ違わなかったのは奇跡に近かった。
「悪かった……」
「いいよ。ちゃんと会えたんだし」
ナツキはアキを見上げる。
「クサナギさんも、会えてよかった」
「ああ……。うん。そうだね。……よかった」
「と、とにかく乗れ。港へ行くぞ。船がなくても車ごと海に飛び込んで、それからコシュナンの船まで泳ぐ」
助かるかどうかは望み薄だが、ここで立ち止まっているよりはマシだ。ハルヒはナツキの手を引き、車に乗るようにアキの背中を押した。
助手席に乗ったアキの顔から、血管の膨張はほぼ消えていた。とりあえずハルヒがホッとすると、キュラはどうしたのかとアキに聞かれる。ハルヒは顔をしかめた。
「……俺とカゲトラを逃がすために、アメストリアに捕まった」
キュラトスは命をかけてハルヒを守った。なのに、自分はアイシスを救えなかった。キュラトスはきっと絶望しているだろう。
ハルヒとナツキとカゲトラ。3人を無事にコシュナンの船に乗せたら、キュラトスをアメストリアから取り戻す。アキは口には出さずに決意した。
ハルヒだって、いますぐキュラトスを助けに戻りたい。だが、カゲトラとナツキをコシュナンの船に乗せることが先決と判断した。
カゲトラが裁判にかけられると聞いたときは、後先考えずに飛び出していた少女と同一人物だとは思えない。ハルヒの成長を感じていたアキは、マーテル城の上空を震わせた咆哮に顔を向ける。そこには再びその形を取り戻しつつある水神の姿があった。
(やっぱり……)
仕留めきれていなかった。車の中から水神を見つめるアキの視界の中で、一際大きく鳴いた水神は、苦しむようにその長い身体をくねらせた。ナツキとカゲトラも目を見張る。
「ゴッドバウム……!」
ハルヒが呟く。水神の周りには無数の砂が舞っていた。
 おまえがやったんじゃないにぃなん
おまえがやったんじゃないにぃなん 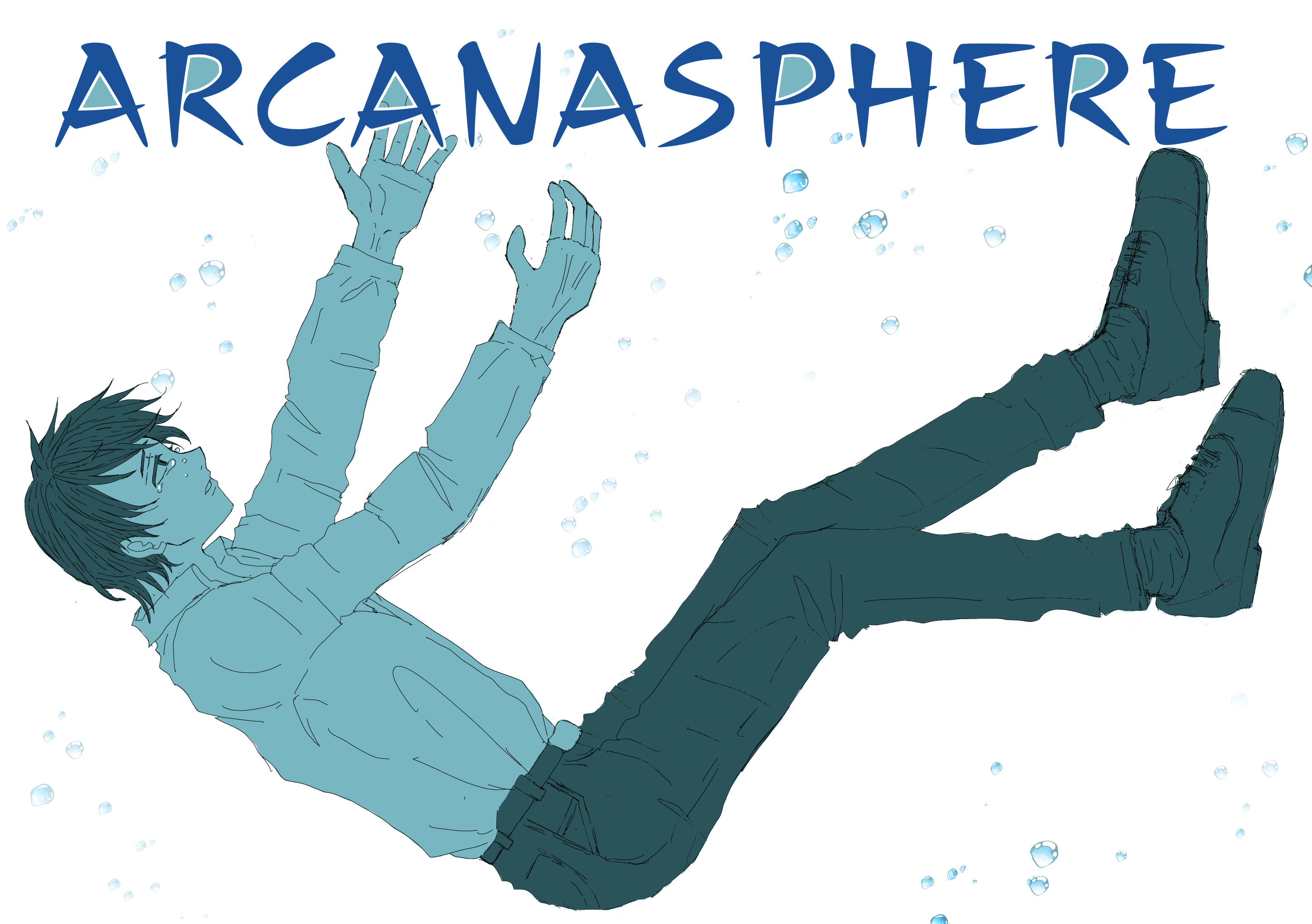
 おまえがやったんじゃないにぃなん
おまえがやったんじゃないにぃなん にぃなん
Link
Message
Mute
にぃなん
Link
Message
Mute

 にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん