ARCANASPHERE6 白獅子軍がスタフィルス軍本部を制圧したのは、黒獅子軍がアメンタリを陥落させる数時間前、朝日が昇る直前だった。
アメストリアの騎士、ヨウヘイ・カガリヤの指揮のもと、細かく割り振られた各々の役目をきっちりとこなした騎士たちによって、わずか数時間というスピードで、彼らは黒獅子軍の本部を掌握した。
アメンタリ攻略のため、軍本部の兵士は8割方出払っていたのが白獅子軍にとって功を制した。
守りを任された兵士たちは、外部からの―――つまり他国からの強襲には備えていたが、まさか自国内からの襲撃は予想できず、抵抗と言う抵抗をする暇もなく、アメストリアに将軍の椅子を奪われた。
アメストリアに協力を申し出に行ったカゲトラが軍本部に到着したのは、そのすべてが終わったあとだった。
□◼︎□◼︎□◼︎
軍本部に王座と言うものはない。20年間王宮から出たことのなかったアメストリアは珍しそうにゴッドバウムの執務室を見て回る。執務机に、書棚、そして豪華とは言えないソファ。F地区までとは言わないが、部屋の調度品には豪華なあつらえが見られなかった。ゴッドバウムは国土を広げることについて最近はご執心のようだが、身の回りについては倹約家でもあるらしい。
カゲトラも同じことを感じた。アメストリアの居城になっていた王宮や、リュケイオン邸を見ているからだろうか。どうもこの質素な部屋が国を牛耳る将軍の部屋とは信じがたかった。
「……ゴッドバウムとはどんな男だ?」
黒皮の椅子に深く腰掛け、アメストリアはカガリヤに聞いた。
「実際に言葉を交わしたことはありませんので、望まれる回答を用意できかねます」
この男らしい返答だ。カゲトラはそう思った。
「そなたはどうだ?」
アメストリアはカゲトラに振る。クーデターで国内が混乱する中、カゲトラは運よくアメストリアに会うことを許された。
「ゴッドバウムをどう思う?」
「……王殺しの大罪人」
「違いない」
カゲトラの答えにアメストリアは満足そうに笑い、廊下を走ってくる足音に耳をやった。カガリヤが扉を開けると、顔色を失った騎士がそこに立っていた。
「陛下!け、研究施設で……!」
「―――出たか」
ニヤリと確かに口角を笑みの形に変え、アメストリアは椅子から立ち上がった。
軍本部前の広場は騒然としていた。スタフィルスで一番大きな研究施設は、軍本部のすぐ横に隣接する建物だ。外部に公表されていないこの施設を、アメストリアはじっくりと攻略するつもりだった。どうせ中にいるのはモヤシのような研究員ばかりで、彼女にとって脅威ではないからだ。
だが、軍の敗北を阻止しようとした研究員たちは、最後の手段とばかりに実験体であるナンバーズを解放した。それが血相を変えた騎士からの報告だった。
「アメリアっ」
アメストリアの姿を見つけたコードが駆け寄ってくる。
「適合者か?」
「違うよ。不適合者だ」
コードは不機嫌な顔をしていた。頭は切れるが、感情を隠さないコードはまだまだ子供だと言えた。
適合者ではない。コードの言葉に、アメストリアはユラリユラリと蠢くそれを見下ろした。広間の中央には、もはや人間の形もしていないそれは数体いて、方向性も定まらないまま、ただ蠢いているとしか言いようがない。
「適合しなければ待つのは死だけではなかったのか」
「あの胸のリミッタ―で、拒否反応を途中で止められてるみたいだよ。なんのためかはわからないけど」
コードは植物の根が絡みつくその物体の胸を指差す。そこには、胸当てのようなものが取り付けられていた。
「ふははははっ」
不適合者を解放した研究員が笑い声を上げる。
「皆殺しにしてしまえ!」
高々と命令をあげるその研究員の顔面に触手が突き刺さった。目玉から後頭部へ突き抜けた触手により、研究員は一瞬で命を奪われてその場に崩れ落ちる。
不適合者たちは敵も味方もわかっていない。取り囲んでいた騎士たちは、だれからともなく包囲の輪を広げた。コードは身を守るために手近にいたカゲトラにしがみつくが、アメストリアは表情ひとつ変えずにその光景を見つめた。
「まさに怪物か。どうやって止めるのだ」
「リリリ……リミッタ―を壊せば拒否反応が進んで自滅するはずだよっ!」
アメストリアはカガリヤの手から狙撃銃を受け取り、狙いを定めるとその引き金を引いた。放たれた弾丸は不適合者のリミッターに直撃し、砕け散る。お見事ですと言うカガリヤの賞賛は、不適合者の絶叫にかき消された。
不適合者は自らの身体から伸び出た触手に埋め尽くされ、やがて急激に枯れ始める。そこからボロボロと崩れていくまでは瞬きの間だった。
「リミッタ―を狙え!」
アメストリアの声が広場に響く。
「リミッターを破壊すればこやつらは自滅する!」
白獅子軍を率いる女帝のカリスマ性に、怖気づいていた空気が一掃される。戦場は再びアメストリアの手の平へ戻った。
□◼︎□◼︎□◼︎
軍本部が敵の手に落ちた。その一報を聞いたとき、敵は【トライデント】だとエルザは直感したが、そうではなかった。黒獅子の代わりに軍本部に上がった旗には白獅子の姿が描かれていた。
白獅子を掲げる存在とは何者なのか。軍本部を占拠した反乱分子からの声明はまだないが、白獅子が王政であった頃のスタフィルスの紋章だと言うことはだれもが知っていた。
(何がどうなっている……!)
目的地までの通路を早足で進みながら、エルザはギリリと奥歯を噛みしめる。将軍とルシウスの留守を狙って起こされた、これはクーデターだ。
まさかこんなことになるなんて。敵が内側にもいることは知っていたが、まさか【トライデント】以外の勢力に、軍本部を乗っ取られるなんて、留守を任された身として、エルザは己の不甲斐なさを痛感していた。とにかく、ゴッドバウム及び正規軍が戻る前にこの事態をなんとかしなければならない。
「エルザ・アスタエル少尉、入ります!」
ノックする間も惜しい扉をノックし、入れという許しと共に開くとエルザはその場で敬礼する。
室内で彼女を待っていたのはヘリオスだった。前回のフィヨドル戦で将軍と遠征したヘリオスは、今回は国内の治安維持に当たるためスタフィルスに残っていた。兵士の話では、彼は軍本部にいたはずだが、クーデターが起こったときには外出していたため、事なきを得たと言うことだった。
ゴッドバウムもルシウスも不在であるいま、スタフィルス軍の最高責任者は仮といえどヘリオスになる。エルザはヘリオスの人間性が好きではなかったが、いまはそんなつまらない内輪揉めをしている場合ではない。
「あぁ、アスタエル少尉。まずはお互いに無事でなによりと言うところか」
この緊迫した状況下であるにも関わらず、腑抜けたことしか言えないヘリオスに、エルザはますます苛立った。
「お言葉ですが、それには同意しかねます」
軍本部にいた兵士はほとんどが捕らえられた。残されたのはほかの地区の施設にいた者、エルザのように別任務についていた者や、ヘリオスのように運がいい者たち少数だ。
「一刻も早く軍本部を奪還しなければなりません。部隊編成のご命令を」
そのためにエルザはわざわざヘリオスのもとへ来た。どんなに気に入らない男でも上官であり、いまのスタフィルスに彼以上の権威を持つ男はいない。ルシウスさえいれば、今頃すでに部隊は編成され、軍本部に攻め入っていただろうに。初動の遅れにエルザはさらに苛立ちを感じた。
「噂通りきみは真面目な女性のようだ」
「……?」
「ルシウスから、きみは生真面目ないい部下だと聞いていたものでね」
同じ階級であっても、実力も家柄もルシウスがヘリオスを圧倒する。ヘリオスがルシウスに勝るのは年齢と腹回りの脂肪くらいだったが、先任士官のプライドか、年長者の驕りか、ヘリオスはルシウスを格下に見たがる。本人のいないところで呼び捨てにすることも、いまに始まったことではなかった。
「大佐。部隊の編成命令を───」
「アスタエル少尉。すでに本部は陥落した。手遅れだ」
「取り戻さねばなりません!大佐は本部を逆賊に奪われたまま将軍閣下に凱旋いただくおつもりか!」
「少しは落ち着いて肩の力を抜きたまえ」
ヘリオスはエルザの肩に手を置く。すぐにでも振り払いたい衝動に駆られたが、エルザは拳を握り締めて気色悪さに堪えた。
「残された兵士の数では、どんなに甘く考えても太刀打ちできるものではないし、むざむざ殺されに行くことはない。それに、もしきみに万が一のことがあれば、あのボウヤも悲しむのではないか?」
「……それは、だれのことをおっしゃっているのですか」
「ああ、これは失礼。そういえば、ボウヤにはアメンタリから幼妻が押しかけてきたんだったな。きみとの関係は終わりか。それとも器用に続けるのか?」
これはルシウスに対する最悪の侮辱だ。エルザの頭はすうっと冷えていく。ヘリオスに部隊を編成するつもりがないことに気づいたからだ。
「……大佐。あなたは、この母国転覆の危機を、ただ指をくわえて見ているだけのおつもりか」
「私は転覆した母国を掬い上げようとしているのだよ。スタフィルス王たるアメストリア様とともに」
ヘリオスがそう言うと、エルザの背後で扉が開いた。そこには白い獅子の旗を掲げた騎士の姿があった。
なぜ軍本部がこれほど短時間で落とされたのか、エルザはいまやっと理解した。そして、それを理解するのが遅かったことを痛感していた。
□◼︎□◼︎□◼︎
とうの昔に帰る家などなく、この街に逃げ場はない。無理矢理にでも国外へ出そうとしたハインリヒやカゲトラの気持ちはわかっていたのに、アキはハルヒを説得することができなかった。
軍とイスズの襲撃から逃げ出し、やっとの思いで廃墟になっている教会へたどり着くと、アキはその場にハインリヒとメアリーを下ろした。
「はぁ、はぁ……っ」
長時間の空中移動は、アキが思ったよりも体力を奪い去っていった。ほぼ回復したと思っていたが、自分が思っている以上にまだ身体は本調子ではなかったようだ。
「アキ、大丈夫か……?」
そう言うハインリヒの顔色も血の気を失って真っ白になっていた。イスズの触手には種類があるのか、ハインリヒは毒に侵されている様子はなかったものの、出血が酷い。気を失っていないことが奇跡だと言えた。
「僕は、大丈夫……」
メアリーが微かな声をあげた。気がついたようだ。彼女はかすり傷程度のようだった。だが、ハインリヒは重症だ。早く病院に連れていかなければと思うが、指名手配犯である彼を連れて行ける病院をアキは知らなかった。
「ここはどこ……?」
まだ夢うつつの状態のメアリーは、教会跡だと聞くと、まるでひとごとのようにそうなのと頷いた。
「先生……ごめんなさい」
セバスチャンを救えなかったことをアキは悔いていた。あの状況で、彼を救えたとすればそれはアキだけだった。アキはメアリーに謝る。
「……あなたが父を殺したんじゃないわ」
セバスチャンを一瞬で殺したのは、軍服の兵士が放った弾丸だ。メアリーはアキにそう言うと、ハインリヒに顔を向ける。
「出血ほど傷は深くなかったみたいね……」
メアリーは四つん這いでハインリヒに近づき、彼の傷口を近くで確認する。
「出血も止まってるし、これならいますぐ死にはしないわ。でも、どこかでちゃんと手当てはしないと、感染症が心配ね」
「そりゃ怖ぇな……」
一応、予防注射はしてるんだがと、ハインリヒは冗談めかしてそう口にした。
「先生……。社長をお願いできますか」
いまここで自分にできることは何もない。それに、ここも完全に安全な場所とは言えない。この場所を安全にするには、自分がいなくなることが一番だ。それは間違いない。
「アキ……」
「……行きます。バレシアくんを放っておけない」
それがいま、自分がやらなければならないことだ。アキはそう決心して重い身体を起こした。
□◼︎□◼︎□◼︎
アメストリアの命令で、強い日差しが照りつける中、黒獅子軍の残党は広場に集められた。
白獅子軍に軍本部の情報を漏らしたのは、ヘリオスのその腹心の部下たちの仕業だった。彼らは警備が手薄な場所の情報を流し、白獅子の騎士たちを軍本部に招き入れた。
敵は国の内外だけではなく、味方の中にもいたと言うことだ。黒獅子の残党として広場に連行されたエルザは、組織というものは一部でも腐ると、そこから腐敗が広がっていくのだということを嫌というほど実感していた。
「アメストリア陛下!」
「陛下万歳!」
白獅子の騎士たちの歓声のもと、エルザにとってはクーデターの首謀者がようやく姿を見せた。
「……え?」
現れたアメストリアの姿を見たエルザは惚けた声を漏らした。アメストリアの顔を、古い肖像画で見たことがあったからだ。
その肖像画は、いまはもう飾ることを禁じられたものだが、エルザはその絵が好きで、どうしても燃やしてしまうことができず、いまも実家の屋根裏に隠し持っていた。それは、最後のスタフィルス王妃マリアベルの肖像画だった。
「陛下」
ヘリオスがアメストリアの前に膝をつく。それに倣って彼の部下たちも同じように膝をつく。裏切り者どもめと、エルザの横にいる兵士が吐き捨てた。
「やつらが黒獅子の残党か。少ないな」
「ほとんどの者は黒獅子の鎧を脱ぎ捨て、陛下に忠誠を誓いました」
「忠誠か……」
アメストリアは何が面白いのか、愉快そうに目を細めた。
「そこの女兵士。そなた、何か言いたそうだな」
エルザの突き刺すような視線に気づき、アメストリアが何か言いたいことがあるなら話してみろと許可を出す。
「……おまえは何者だ」
エルザたち、黒獅子の残党と呼ばれた兵士たちは両手を後ろで縛られ、武器を持つこともできない。
「なぜ白獅子を掲げている!」
「私の家の旗だからだ」
「……!?」
「これは私の父が、祖父が、そのまた祖父が掲げた旗だ。だから私も白獅子の旗を掲げている」
「……おまえはだれだ」
エルザは絶望的な思いを抱きながら、その質問をした。その視界には、勝ち誇った顔のヘリオスが映っていた。
アメストリア・ルイ・スタフィルス。彼女はそう名乗った。スタフィルス王家の生き残り。正当な王位継承者。そんなものが生きているはずはない。だが、実際に目の前にいる女はマリアベルの肖像画に生き写しだ。それは否定できない。
「私に忠誠を誓った戦士たちに礼を言いたい」
アメストリアはそう言った。ヘリオスは気を良くして裏切り者たちを集める。ズラリと並んだ兵士たちの中には、エルザのよく知る顔もあり、彼らの中にはエルザと視線が合うことを避けるものもいたが、逆に勝ち誇ったような顔を見せる者もいた。
「戦士たち。此度はご苦労だった。そなたたちの働きにより、私は王座を奪還するという長年の夢を叶えることができた」
アメストリアの演説を、カゲトラは少し離れた場所から見ていた。アメストリアにナツキの情報がないか聞いたが、この混乱した状況が落ち着くまでは待てと返されたからだ。カゲトラは広間に集められた兵士たちを確認したが、そこにはレイジの姿もナツキの姿もなかった。この国をアメストリアが掌握したら、きっとナツキの居場所もわかる。それを信じて、カゲトラはこの成り行きをじっと見守っていた。
「これは私からの礼だ」
アメストリアは微笑み、カガリヤから受け取った銃を、隣にいたヘリオスの胸に撃ち込んだ。
カゲトラも、エルザも、兵士たちも、その場にいた白獅子軍以外の全員の目が、広場に響いた銃声と共に倒れゆくヘリオスに向けられる。
「……へ、陛下」
胸を撃たれた。それでも、ヘリオスはそれでもその顔に媚びへつらった笑みを浮かべてアメストリアを見上げる。だが、その直後ゴフッと血を吐き出した。
「な、なぜ……」
「……ヘリオス大佐。20年前の忌まわしき事件を覚えているか?」
ヘリオスの身体の下の白い砂は、彼の血でどんどん赤く染まっていく。
「我が父が、信頼していたゴッドバウムという騎士に裏切られ、殺された事件だ」
アメストリアが片手を挙げると、カガリヤを始めとした白獅子の騎士たちがヘリオスの配下たちに銃口を向ける。
「私は裏切りを断じて許さない。それが、私ではない別にだれかを裏切る行為でもだ」
銃口はいっせいに火を吹き、裏切り者たちを撃ち殺していく。広場は瞬く間に悲鳴と銃声が響く地獄と化した。
「やめろ!」
逃げ出した黒獅子の兵士の足を撃って動きを止め、トドメを刺そうとする白獅子の騎士をカゲトラが止めた。だが、その兵士は別の騎士が撃ち殺してしまう。カゲトラはアメストリアを振り返ってやめさせろと叫んだ。
「なぜだ」
「何をしているのかわかっているのか……!」
「もちろんだ。これは裏切り者に対する制裁だ」
「違う!これは虐殺だ!」
阿鼻叫喚の地獄の中で、カゲトラの悲痛な声はすぐにかき消された。
□◼︎□◼︎□◼︎
全てが悪い夢だったのだとでも言うように、長い間忘れていた朝が訪れた。カーテンの隙間から差し込む光が眩しくて、ココレットはそれから逃れるためにベッドの上で寝返りを打つ。
屋敷の中でこの部屋の日当たりが一番いいからと、どうしてもここにベッドを置くと聞かなかったのは、当のココレットではなく執事のセバスチャンだった。いつも優しく微笑んで、ココレットの心配ばかりする彼は、家族の愛情を知らないココレットの親代わりでもあった。
(喉、渇いた……)
水が欲しい。ココレットはセバスチャンを呼ぼうとしたが、なぜか声が出なかった。
(水が欲しい……)
ココレットは身を起こす。そして、そこで初めてそこが自分の部屋でないことに気づいた。それと同時に自分の身に起こった出来事を思い出し、ハル!と叫ぼうとしてココレットは喉を押さえた。
「……!」
声が出ない。掠れた声さえ出ない状態に、ココレットは青ざめる。
「う〜ん」
なんとか声を出そうとしていたココレットは、すぐ隣から聞こえてきた声に驚いて飛び上がる。咄嗟にベッドから逃げようとしたが、そこに見えた顔に彼女はピタリと動きを止めた。
ベッドの中で一度伸びてから、彼は眠そうな目を開ける。その大きな目がココレットを見つけるのはすぐだった。
「あれえ、ココレットだ。なんでここにいるの?」
それはナツキだった。彼は人懐っこい笑顔を浮かべ、ココレットを見つめる。
「久しぶりだね。僕のこと覚えてる?」
声が出ないココレットは必死に頷いた。ハルヒがあんなに探していたナツキが目の前にいる。早く知らせなければと思ったココレットは、ようやくハルヒがクリムに撃たれたことを思い出し、息を詰める。部屋を見回してもハルヒの姿はどこにもない。
最悪の予感が胸を渦巻いた。もしかしたら、彼女はもう生きてはいないかもしれない。ナツキはここにいるのに。あんなに会いたがっていたのに。それが自分のことのように悔しくて悲しくて、ココレットの目から涙が溢れた。
「わ、わわっ、どうしたの?どこか痛いの?」
「……っ」
「ど、どうしたら……」
突然泣き出してしまったココレットに対し、ナツキはどうすることもできずに困り果てる。
「ま、待ってて」
自分でどうにかできないのなら、助けを呼ばないといけないと思い、ナツキは立ち上がった。ナツキはベッドから飛び降りて扉へ向かったが、彼が扉を開ける前に、それは外からの訪問者に開いた。
「あら、おはよ」
ナツキに対してそんな挨拶をしたのはクリムだった。声が出たのなら悲鳴をあげただろうが、ココレットはビクリと肩を震わせただけだった。
「クリムさん。おはようございますっ」
ナツキは、ココレットがどこか痛いみたいなんだとクリムに教えた。
「そうなん?ココレットちゃん、どこが痛いん?」
ハルヒはクリムに撃たれた。声が出なくても、ココレットはそれを忘れたわけじゃない。
「あらァ、ココレットちゃんのそないな怖い顔初めてみたわ」
よっぽど痛いんやねと、クリムは心配そうな顔をナツキに見せ、ココレットを見てニヤッと笑った。
「可哀想に。疲れが出たんかもしれんね」
そう言って、クリムはココレットの額に手を当て、その耳元に囁いた。それはナツキには聞こえない小さな声だった。
「しばらくは余計なこと喋れへんと思うから、まぁ無理せんときな」
ゾッとして、ココレットはクリムの胸を全力で突き飛ばした。少しよろけたクリムは、驚いた顔をしているナツキに首を振る。
「あんなに怖い思いしたのに、僕が軽率やったわ」
近寄りすぎてごめんなとクリムはココレットに謝った。
「ココレットちゃんはずっとテロリストに連れ回されてたんや」
「えっ」
ココレットは首を振るが、ナツキはそれを否定とは取らなかった。
「昨日やっと保護することができたんよ。声が出なくなるやなんて、ものすごく怖い思いしたんやと思う」
「ココレット……」
ナツキは泣きそうな顔になるも、もう大丈夫だよとココレットの手をぎゅっと握った。
「ここにいれば安全だからね。そうですよね。クリムさん」
「それが……そうでもないねん」
クリムは決まり悪そうにナツキから目を逸らした。
「どうもテロリストがココレットちゃん取り返そうとしてるみたいで、すぐに避難して欲しいんや」
「テロリストって、……【トライデント】ですか?」
「そうやけど、……それがどないかした?」
「―――嫌いなんです」
ナツキの一言でココレットは呆然となる。まさかと言う思いが全身を駆け巡った。クリムもココレットと同じことに気づく。ナツキはハルヒが【トライデント】であることを知らないのだ。
「テロリストって、関係ない一般の人まで巻き込むし……」
「……へえ」
青ざめていくココレットの表情を楽しみながら、クリムはナツキの話に相槌を打った。
「あんなやり方でしか自分の理想を表現できないのは……良くないと思ってて……」
「僕も同意見やわ。それやったら尚更、ここにおったらあかん。きみみたいな意見を持つ子は、テロの犠牲になるべきやない。それにココレットちゃんも守らないとあかんしな。屋上にヘリポートがあるから、そこから逃げよ」
「逃げるん、ですか……?」
ナツキの表情が曇る。
「大丈夫。これで終わるわけやあらへん。きみの力はこの先必要になる。僕たち逃げるんやない。戦うために、一度退くだけや。な、ココレットちゃんのためにも」
「……はい」
ナツキは納得しきれていないようだが、ココレットを守らなければという思いから、しぶしぶクリムに同意した。
□◼︎□◼︎□◼︎
黒獅子を掲げるスタフィルス軍は混迷していた。軍本部との通信が途切れて、1時間後にその通信室は白獅子軍と呼ばれる者に占拠されたからだ。軍本部を乗っ取った組織は白獅子アメストリアの名の下の聖戦と、王政の復活を高らかに宣言した。
それを聞いたルシウスはすぐに、数名の部下を連れてヘリポートへ向かった。向かっている最中に、部下が手配したヘリが着陸し、ルシウスは一度も止まることなく座席に乗り込んだ。
「離陸しろ!」
部下が乗り切れていないうちに、ヘッドセットをつけながらルシウスは操縦席にいる兵士に命令する。もちろん、目的地はスタフィルスだ。
スタフィルスは捨てる。黒獅子軍は、これよりフィヨドルを拠点する。ゴッドバウムの出した決定は、ルシウスが自分の耳を疑うものだった。
スタフィルスには少数と言ってもまだ兵が残っている。その中にはエルザも、そして屋敷には形ばかりの妻であるリジカもいた。ゴッドバウムがなんと言おうと、ルシウスには彼女たちを見捨てることはできなかった。
□◼︎□◼︎□◼︎
息が切れる。胸が痛い。ああ―――死神がすぐそばまで迫っている。だが、まだだめだ。死神が伸ばした手を払い除ける。死神―――彼女は寂しそうに目を細め、小さな子供を抱いて消えていく。その姿が完全に見えなくなると、レイジは白昼夢から覚めた。
「………」
こんな幻覚を見るようになったのは今日が初めてじゃなかった。これも病状の一種なんだろうか。全員に転移した悪性の腫瘍が、幻覚を見せているのかもしれない。悲しくも愛しい幻覚を。
バルテゴに吹き荒れる死の風。あっという間に愛する家族はバラバラに引き裂かれた。小さな息子が肉片へと変わるまでには、まばたきの時間さえ必要なかった。妻と息子はアルカナの神に殺された。
「………」
レイジはグレイスター本社ビルの前に立っていた。すでにそこにはたくさんの人々が集まって、口々に罵声を飛ばし、ビルへ向かって石や物を投げつけていた。
入口の回転扉は無残に破壊され、破片がビルの中に飛び散っている。正面の受付カウンターや、1階にひとの姿は見られなかった。
「軍の手先め!」
「出て来い!金の亡者ども!」
石を投げる人々は、ほとんどが下級市民層の人々だ。軍の圧政に虐げられていた彼らは、白獅子軍の蜂起と共に自分たちも立ち上がり、上位地区の貴族の屋敷や軍の関連施設、そして軍と契約を結んで甘い蜜を吸っていたグレイスターなどの民間企業を標的に、自発的な暴力行為に走っていた。
暴動はひとたび火がつけば鎮圧は難しい上に、すでに制圧された黒獅子の残存軍は機能せず、白獅子軍は市民を煽るばかりで抑えることをしない。暴徒と化した人々は上位地区に火まで放つ始末だった。
「まるで獣だな……」
いなくなったナツキの行方をあちこちで探し、レイジはやっとここへたどり着いた。普段は蟻の子一匹通さない警備がしかれているだろうが、この混乱状況のいまならば中に入り込むのも容易い。それに、すでに何人かの男たちがビルへ乗り込んでいた。
割れた回転扉をくぐりぬけ、暴徒を装ったレイジは、グレイスタービルに足を踏み入れた。
□◼︎□◼︎□◼︎
裏切り者の死体は積み上げられ、それには燃料が撒かれて火がつけられた。瞬く間に燃え広がる火は、広場を夕焼けのように染め上げた。アメストリアは満足そうにその炎を見つめていた。
魔女だ。
そう思ったのはエルザだけではなかっただろう。彼女と同じように拘束された兵士たちも、同じようにアメストリアが邪悪な存在に見えたはずだった。エルザは、最後の王妃であるマリアベルと、アメストリアが似ていると思った自分を殴りたい気持ちだった。
「―――なにか言いたそうだな」
エルザの視線に気づいたアメストリアが首を傾げた。そして、言いたいことを言ってみろと催促する。
「……魔女め」
アメストリアではなく、主人に対する暴言にカガリヤが反応し、エルザに銃口を向けた。
「やめろ」
アメストリアはカガリヤを止める。彼女は不快な顔を見せるどころか、むしろ上機嫌でエルザの前へ進み出た。
「そなた、名は?」
「魔女に教える名などない」
「どうか名乗ってくれないか。彼のためにも」
アメストリアはエルザの隣の兵士の眉間に銃口を突きつけた。配属されたばかりのそばかす顔の少年兵は、ガチガチと震えながらエルザに助けを求める。
「……エルザ・アスタエル……少尉だ」
「アスタエル少尉か。私はアメストリア・ルイ・スタフィルスだ」
「スタフィルスの王族は途絶えた!王家の名を汚す魔女め!」
ぱん!銃声が鳴り、エルザの頬に血が飛んだ。至近距離での発砲に、キーンと耳鳴りがする。少年兵の震えは止まり、その身体は力なく倒れた。
「私を傷つけないでくれ。心無い言葉を聞くと、悲しくて手元が狂う」
「……!」
「エルザ―――、私の騎士にならないか?」
「なにを、ばかなことを……!」
怒りに震えるエルザがそう返すと、アメストリアは別の兵士に銃口を向けた。
「た、助けてくれっ、騎士になるッ!騎士になるから!」
銃口を向けられた兵士は首を振ってアメストリアに命乞いをした。
「黙れ。そなたには頼んでいない」
アメストリアはエルザに微笑んだ。
「もう一度言おう。私の騎士にならないか?」
騎士になると叫ぶのは銃口を向けられた兵士ばかりで、エルザは唇を噛んだままアメストリアを睨みつけていた。
「……残念だ」
「―――陛下!」
この状況にたまりかねたカゲトラが叫ぶのと、銃声が鳴り響くのはほぼ同時だった。泣き喚いていた兵士はエルザの前に倒れ、開いたままの目は徐々に光を失っていった。
「驚かせるな、バンダ。撃ってしまったではないか」
「……敵の兵など騎士にしてどうするのですか。裏切りを許さないといましがた処刑を行ったのはあなただ」
「口が過ぎるぞ」
カガリヤの制止もカゲトラは聞かない。
「本気になるな。こんなものただの座興だ」
「……座興?」
「そうだ。この女を騎士にするつもりなどない。ただ遊んでいるだけだと言っている」
まるで地を這う芋虫をゆっくりと踏み潰すように。蝶の羽根を一枚ずつむしり取るように。アメストリアの言葉にカゲトラは言葉を失った。それに反して、エルザはクッと笑いを漏らした。
「見ろ、バンダ。この状況で笑うとは。この兵士、すぐに殺すには惜しいと思わぬか?」
「カゲトラ・バンダ」
エルザに名指しされ、カゲトラは顔を向ける。
「確か【トライデント】の理念は、弱き者を助けるだったか。テロリストがご大層なものだと、大佐は一笑されたよ。だかな―――いまは貴様らのほうがよっぽどマシだったと思う」
言葉は毒であり、鋭いナイフだ。エルザの吐き出したものは、カゲトラの深い場所に食い込み、じわじわと全身に広がっていく。
良かったな、バンダ。アメストリアはどこか的の外れたことを口にし、今度こそエルザに銃口を向ける。
「どこがいい?どこを撃って欲しい?わずかでも生き延びたいのなら、少しずつ失血して死ねるようにしてやろ――――」
ズズズン……!静まり返ったその場に地響きが鳴った。カガリヤがアメストリアを守るように周囲を警戒する。だが、それは地上にはいなかった。
「下だ!」
カゲトラが叫ぶ。その瞬間、広間の噴水が粉砕し、緑の触手が地下から地上へと飛び出した。
噴水から溢れた水であっという間に広場は水浸しになる。突然の出来事にほとんどの者が対処できず、ただ呆然と水の代わりに天高く伸び上がった触手を見上げていた。
カゲトラは、砕かれた噴水のコンクリートから上がる煙の中に、だれかが立っていることに気づいた。ジャリジャリと、コンクリートの破片を踏みしめる音が、白い煙の中から聞こえてくる。その男を知っているのは、広場に集まったたくさんの人間の中で、カゲトラひとりだった。
「……誰か、クサナギ先輩を知りませんか?」
周囲に集まった数百人にも及ぶ人間に対し、イスズはそう聞いた。その右腕は彼の身体よりも太く膨張していて、その色は植物のような緑色をしている。その先には何本もの触手がユラユラと揺らめいていた。
それは異形に似合わない、とても落ち着いた口調だった。クサナギの名に反応したのはわずかな者だったが、イスズはそれを見逃さなかった。アメストリア、カガリヤ、カゲトラ、エルザの中で、イスズは1番動揺を見せたカゲトラに視線を向ける。
「クサナギ先輩はどこですか?」
覚えている。目の前にいるのは、あの日レイシャの死体の前で叫んでいた青年だ。その変わり果てた姿にカゲトラは言葉を失っていた。
「先輩はどこにいるんですか?」
「………」
「答えてくださいよ!」
イスズの腕から触手が伸びる。紙一重でそれをかわしたカゲトラは、直後に発砲音を聞いた。
だれかが撃った銃弾がイスズの脚に命中し、ジワリと血が滲む。
「いま撃ったのだれだよ」
自分の脚を見下ろしたイスズは言った。誰もが口にするわけではないが、視線はイスズを撃った騎士へと否応なく向けられる。
「痛いだろ」
目にも止まらぬ速さで突き出た触手が騎士の喉を貫いた。鎧と兜のわずかな隙間から見える生身を貫かれ、騎士は血の泡を吹き出して絶命する。
そこから恐怖が伝染病のように広がった。白獅子騎士たちの武器を持つ手は震え、拘束されている黒獅子の兵士たちは真っ青になって身を寄せ合った。そんな空気の中、また発砲音が響く。確実に心臓を狙った銃弾を、イスズは触手で受け止めた。そして、発砲したアメストリアを見る。
「どうした。撃ったのは私だぞ?」
何を考えているのか、アメストリアはさらにイスズを挑発する。
イスズの顔が狂気に歪んだ。だが、アメストリアは動じず、余裕の表情を崩さない。そこに恐れなどと言うものは微塵も感じさせなかった。その真っ直ぐに向けられた視界の先、イスズの背後にいる男の姿を、アメストリアだけが見ていた。
「陛下!」
カガリヤが叫んだその瞬間、イスズの放った触手は風刃によって切断された。触手はドシャッと音を立ててアメストリアの目の前に落ちる。見開いたイスズの目が、アメストリアが見ている先を振り返った。そこに立っていたのはアキだった。
「クゥサァナァギィイイイイイッ!」
イスズの両腕から触手が飛び出し、それは一直線にアキへと向かっていく。
迫り来る狂気を真正面から受け止める気はサラサラない。アキは風をまとって高く飛んだ。翼のある鳥よりも自由な空中での動きに、だれもが目を奪われる。
ズドドドッ!イスズのツルはアキが立っていた場所にすべて突き刺さる。砂まみれになった触手を引き抜くと、両腕をひとまとめにして、イスズは身体を回転させる。
「伏せて!」
アキが叫ぶと、カガリヤがアメストリアを抱えて伏せた。その頭の上を太い柱のようになった触手が通り過ぎていった。避けきれなかった兵士や騎士は玩具のように吹き飛ばされていく。
「……!」
自分に向かってくる触手に息を呑んだエルザを、カゲトラが抱えて転がる。その真上を兵士や騎士を巻き込んだ触手が通り過ぎていく。
「逃げろ!ここから離れろ!」
でなければ、適合者同士の戦いに巻き込まれる。もうすでに巻き込まれているようなものだが、これ以上の被害を出さないためにも一刻も早く避難するべきだ。こんな戦いに、普通の人間が手出しすることはできない。カゲトラはエルザの身体を肩に担ぎ上げた。
「貴様!テロリストの分際で私に触るな!」
カゲトラに担がれたエルザは暴れる。
「巻き込まれて死にたいのか!」
「うるさい!私は軍人だ!戦場における自分の……!」
「いいから大人しくしてしろ!」
エルザの腰をしっかり掴み、カゲトラは戦闘区域に背を向け、走り出した。
「センパァァァァイ……」
長く伸びた両腕の触手を揺らし、イスズは地上へ降り立ったアキに身体を向ける。あのとき天井の下敷きになったはずなのに、イスズに傷を負った様子は見えなかった。
ぐらりと傾いたイスズは地上に両腕を突き刺した。身体と変わらない太さがある腕のせいで、ただ立つことですらバランスが取りづらいためだ。
「逃げるなんて酷いですよ……。いつも、いっつも、そうなんだから……。ミナシロさんの誘いを断ってばかりで、少しも彼女に優しくしてあげない……」
「……バレシアくん」
「あなたに笑いかけられるだけで、彼女は幸せだったのに……、あんなに想われていたのに……どうしてですか?」
ボコッとアキの足下の砂が沈んだ。
「!?」
沈んだ砂の中から触手が飛び出し、アキの足首に巻きついた。切断する間もなく、アキの身体は上空へ持ち上げられ、そのまま建物へと叩きつけられた。
「クサナギッ!」
カゲトラが叫ぶ。アキの姿は崩れ落ちた建物の瓦礫の下に埋まり、あっという間に見えなくなった。最後にカランと小石が瓦礫の山を転がり落ち、建物の崩壊は止まった。
「呆気ないな……」
イスズはそう言って伸ばした触手を引き戻す。そして周囲を見回した。目当てのハルヒの姿は見えない。イスズは落胆してため息をついた。アキの目の前でハルヒを殺してやりたかったのに、順番も方法も滅茶苦茶になってしまった。計画は、立てたときは完璧だと思っても、いざ実行に移すとうまくいかないものが多い。自信を持って提出した記事を、やり直しと言われたときのように、うまくいかないとストレスがたまるものだ。
「……殺したりないなあ」
ボソリと呟いたイスズの一言に、兵士や騎士たちが後退する。その中のひとりの胸に触手が突き刺さった。心臓を貫かれた兵士は一瞬で絶命する。イスズは無造作に死体から触手を引き抜くと、ぐるりと自分の周囲を見回す。その口元が笑みの形に変わった。
シュンッと風が鳴る。避けるよりも、音に反応して攻撃に転じたイスズの腕は、肘あたりから回転刃のような風に切り裂かれた。
半分を失った両腕はブラリと垂れ下がる。だが、それはわずかな間のことで、切り口から触手は再生し、元の形を取り戻した。
「……!」
瓦礫の山からやっとのことで這い出したアキは顔をしかめた。イスズの触手は何度切っても再生する。あとどれくらいこの力が使えるか、状況はいいとは言えない。屋敷から逃げ出す際にかなりの力を消耗している。胸の痛みから考えても、限界が近いことはアキ自身が一番よくわかっていた。
見た目での判断だが、イスズは触手を操るだけでは消耗しない。あれだけの質量の巨腕を振り回し、形を変化させてもリバウンドの兆候は見られない。イスズの適合率がどのくらいなのかアキは知らない。知らないが、バルテゴとフィヨドルで力の種類は違ったとしても、あれだけのことをすればリバウンドが起こってもおかしくないはずだ。だが、イスズの身体に異変は生じない。そしてその武器はいくらでも再生する。フィヨドル神の力。それはきっと―――。
(……異常なまでの再生力)
自分の勘を信じ、アキは再び風刃を作り出す。いつかラッシュが見せた円盤状の風の刃を手の平に乗せ、腕を振り上げたイスズに狙いをつける。残る力は多くはない。一撃たりとも外せない。
襲いかかってきた触手を風に乗って紙一重で避けながら、アキはイスズに向かって走る。腕や脚をいくら切っても無駄だ。なら、急所を狙って一気にカタをつけるしかない。アキの狙いはイスズの心臓だった。
一点をめがけて距離を詰めてくるアキの狙いに気づいたイスズは、その顔に狂気じみた笑みを浮かべ大きく口を開ける。そこから触手が溢れ出た。
「ッ!?」
一瞬それに度肝を抜かれたアキだが、それを温めていた風刃で刎ねると、イスズの胸に両手を押し当てた。
アキから放たれた風は、イスズの肉体を真っ二つに切り裂く。鮮やかな断面を見せながら、イスズの身体上下に分かれては砂の上に落下した。力を使い果たしたアキはその場にガクリと膝を折る。大量の冷や汗が流れ、心臓がバクバクと鳴っていた。
「やった……」
「やったぞッ!」
適合者同士の戦いを見ていた両軍から歓声が上がる。黒と白、どちらの獅子軍にとっても、イスズの存在は脅威であったため、共通の敵が倒れたことでその場は妙な連帯感に包まれた。興奮した騎士がイスズの上半身へと近づいていく。
(……おかしい)
イスズの頭を蹴ってその死を確かめる騎士を見て、カゲトラはぬぐいきれない違和感を覚えた。
(……切断面から一滴も出血していない!)
カゲトラがそれに気づいた瞬間、ゾクッとアキの背筋に寒気が走る。
「そこから離れてッ!」
アキが叫ぶと同時に、切り裂かれたイスズの断面から触手が噴き出した。上半身から噴出した触手は下半身を探し当てるとその断面に貼り付き、分かれた身体を繋ぎ合わせてイスズを再構築していく。
触手は腰を抜かした騎士を絡め取り、強い力で締め付ける。まるで果物が絞られたように、脱力した騎士から溢れた大量の血液が砂を濡らした。
風刃を放とうとしたアキは、引き攣るような痛みを覚えて胸を押さえる。どんなに振り絞ってももう限界だ。それを越えれば心臓が破裂するか、皮膚に劣化反応が起こる。神の力に耐えきれず、アキは死ぬ。
「無駄ですよ、センパァイ」
膨張したイスズの腕がアキを軽く殴り飛ばす。再生を繰り返す触手の増殖により、通常の三倍もの大きさになっている彼の一撃は、アキの身体を簡単に吹っ飛ばした。
脳震盪を起こしたアキは砂の上に倒れ込み、起き上がることもできない。アキではイスズに勝てない。それを悟り始めた兵士や騎士たちは、お互いに顔を見合わせ始める。アキが殺されたら、次は自分たちの番であることは明白だからだ。
「どんなに切ったってェ、無駄ですよ……。僕の適合率はあなたに及ばないけれど、この力とは相性がいいんだ」
(相性……。それなら僕は、……悪いはずはない……)
ぼやける視界の中に、アキはますます肥大していくイスズを映す。彼の全身はそのほとんどを触手に覆われてしまい、もはや以前の面影は微塵も残っていなかった。
(僕が巻き込んだ……)
アキはどうにか身を起こすと、右足を引きずって歩き出す。
(関係ない、ミナシロさんを……バレシアくんを……)
ごめんねと、アキの口から出た謝罪の言葉に、イスズは首を振る。
「あなたの謝罪なんかいらない」
イスズは触手を集めて激しく回転させた。
「僕の望みは、あなたが苦しみ抜いて死ぬことだッ!」
ドリルのようになった触手がアキに向かっていく。「クサナギ───ッ!」
カゲトラが走るが、とても間に合わない。
迫り来る攻撃を前にしても、アキにはもう防壁となる風を作り出す力は残っていなかった。
ぱあんッ!
アキの目の前でイスズの触手が弾け飛んだ。
「な……」
何が起こった?だれも、イスズ本人でさえそれを説明できなかった。アキ以外は。
パラパラと体表面の組織が剥がれ落ちていく。腕だけではない。肥大化した身体の表面から、次々と組織が剥がれ落ちていき、パキパキとイスズの首には亀裂が入り出す。
「痛く……なかった……?」
アキが掠れた声で問いかけた。
「……なんだって?」
「心臓は、痛まなかった……?」
「………」
「フィヨドルの力は……リバウンドを、警告する痛みまで……治癒再生するの……かも、しれな……」
吊り下げられていた人形の糸が切れたように、アキはその場に崩れ落ちた。
パキパキとひび割れてはこぼれ落ちていく。崩壊はとどまることを知らず、イスズの身体はだんだんと小さくなっていき、本来の大きさまで削られていくが、それでも人間だった頃の姿は見えてこなかった。
イスズに埋め込まれたフィヨドル神の力も、アキと同じく使えば使うほどに身体に負担をかけるものだった。だが、その再生能力はその痛みさえうやむやにして、限界を彼に教えはしなかった。
崩れながら、イスズは残っている触手でそこに落ちていた騎士の剣を手に取ると、倒れているアキに向かって歩き出す。ギョッとしたカゲトラが再び砂を蹴ったが、逃げ出した人だかりが邪魔をする。
「待て!よせ、やめろッ!」
カゲトラの制止は届かず、イスズはアキの胸を狙って剣を持ち上げる。
「……ごめ、ん」
意識を失ったかと思っていたアキが、うわごとのように口にしたのは、イスズに対する謝罪だった。
「……巻き、込んで……ごめ、ん。ミナシロさ……バレシ、ア……く……」
「………」
あんなにアキを憎んでいたのに、不思議とイスズには、それが命乞いには聞こえなかった。
―――軍の研究施設でフィヨドルの力が適合し、目を覚ましたイスズは、それに気付かないチグサとタオの会話を聞いた。
アキが何年も前に風神のカケラを埋め込まれていたこと。それが、自分のように志願してのことではなかったこと。B-986と言うナンバーの、アキと同じ風使いがいたこと。その男がレイシャの命を奪ったこと。チグサとタオは、イスズにアキに対する憎しみを植え付けるために、わざとその事実を伏せた。
すべてイスズは知っていた。だが、誰かを憎まずにはいられなかった。すでにラッシュが死んでいるなら、逆恨みでもアキを憎むしかなかった。それでもしなければ、レイシャがあまりに報われなくて。
「……あなたがずっと羨ましかったんです」
やっとのことでカゲトラが人混みを掻き分けると、イスズは騎士の剣を足元へ落としていた。
「ミナシロさんと同じで、僕も先輩に憧れてた……。仕事ができて、誰からも慕われて、社長の信頼する片腕で……」
ザーッと緑の触手が茶色く変色していく。急激に枯れていく。
「先輩……僕は、あなたのよう、に……なり……」
パンッとイスズだったものは破裂し、砂の上に散らばった。だれもが言葉を失う中、枯れた触手は風に吹かれて飛んでいく。
彼の最期を目にしても、その場にいる兵士も騎士も一歩も動けなかった。目の前で繰り広げられた常軌を逸した戦いに、だれしもの心も疲弊しきっていた。そんな中、アメストリアがパチンと指を鳴らした音は、酷く鮮明にその場に響いた。
「アメストリア・ルイ・スタフィルスの名において命じる。我が同胞の白獅子たちよ。黒獅子どもをひとり残らず……殺せ」
「逃げろッ!」
また殺戮が始まる。それを阻止しようと叫んだカゲトラは、カガリヤの持つ銃身で後ろ首を殴られて倒れた。
自らの手にとって作り出した地獄の中で、アメストリアは倒れているアキの身体を仰向けに転がし、その口元を笑わせた。
□◼︎□◼︎□◼︎
チッチッチッチッチッ。耳障りな音を刻みながら、時計は確実に刻を進めていく。少しも休むことを知らない針を睨みながら、ハルヒは腕に巻きついているロープを捻った。
「クッソ……」
だが、どれだけ念入りに縛っているのか、多少の縄抜けならば朝飯前のハルヒだが、その結び目は緩めることすらできないでいた。その間も時計は止まらず、刻を刻み続ける。起爆時間へと向かって。
ハルヒの目の前には小型爆弾が置かれていた。小型といっても、ビルのワンフロアくらいは吹っ飛ばす威力はあるプラスチック爆弾だ。クリム自身がそう言っていた。時限式で、設定した時間になると爆発するらしい。
朝日が顔を出した頃、ハルヒが目覚めてしばらくするとクリムが現れて、それをハルヒの目の前に置いて去っていった。距離にしてわずか2メートルだが、縛られているハルヒの手はそこまで届かない。
せめて脚の長さが2メートルあれば届くのだが、身長が160cmほどしかないハルヒには無理な相談だった。起爆まであと1時間しかない。
「ちくしょう……!」
撃たれた傷はなぜか手当てされてた。その際に痛み止めも与えられたのか、アドレナリンのせいなのか、貫通したはずの銃の傷なのに、ハルヒは不思議と痛みは感じなかった。
だが、銃もナイフも武器はすべて取り上げられてしまっている。ついでに上着も奪われ、ハルヒは肌にピッタリとフィットする薄手のシャツしか着ていない。爆発まであと52分。時間がない。
「……!?」
タイムリミットに焦るハルヒの耳に、近づいてくる大勢の足音が聞こえた。もうなりふり構っていられない。
「だれか来てくれ!」
自分だけではどうにもならない。なんの足しにもならない自尊心をかなぐり捨ててハルヒは叫んだ。
「ここに爆弾があるんだ!このままじゃビルが吹っ飛ぶ!頼む助けてくれ!」
喚くような声は聞こえるが、ハルヒの声は聞こえていないらしく、足音はそのまま通り過ぎていった。
「気づけよ!ちくしょう!」
椅子をガタガタと揺らしてハルヒは暴れる。そのとき、ふいに目の前の扉が開いた。諦めかけていた助けが来た。そう思って顔を上げたハルヒは、そこに立っていたレイジの姿を目にして言葉を失った。
「……ハルヒ」
レイジの顔を見るのはブロッケンビル以来か。そして、彼こそが弟のナツキを誘拐した犯人でもあり、F地区の【トライデント】を壊滅に追い込んだ男でもあった。
「……レイジ、さん」
いまもまだ、敬称をつけてレイジを呼んだ自分に気づき、ハルヒはそれに口元を引きつらせた。この男がしたことを許せるわけがないのに、昔からの癖は抜けない。それだけ長い間、レイジはハルヒやナツキのそばでふたりを守ってきた。
「あ、あと、あと48分でこのビルは爆破される!」
レイジの目がハルヒの前にある爆弾へ向けられる。
「ナツキとココを助けてくれ!」
3秒間の間、じっくりと爆弾を見つめたレイジは、ハルヒの言葉に彼女へ視線を戻した。
「ナツキがここにいるんだ!頼む!爆弾を解除して、ナツキとココを助けてくれ!」
リュケイオン家は仲間だろうと、ハルヒはココレットがゴッドバウムの娘であることをレイジに確認させる。
「あいつらは【トライデント】でもなんでもないんだ!頼む!」
意地を張ったところでいまの自分にはなにもできない。それならば、奇跡のようにこの場に現れたレイジにすがるしかない。それをハルヒは理解していたし、レイジはナツキを誘拐したが、小さな頃から弟を可愛がってくれた父親の親友が、弟だけは傷つけないと信じたかった。
「……そう都合よくいくかな。それに、私に爆弾処理の経験はない」
そう言って、レイジは折り畳みナイフの刃を出した。ハルヒはゴクリと生唾を呑み込む。
「……ナツキを、助けてくれ」
自分に向けられた刃に、ハルヒはレイジに再度そう頼むと目を瞑った。レイジは【トライデント】の裏切り者だ。レイジの行動はなんらおかしいことではない。
覚悟を決めたようでいて、ハルヒはガチガチに緊張している。その姿にレイジはため息をつくと、ハルヒを縛っているロープをナイフで切り裂く。不意に身体が自由になったハルヒは、不思議そうな顔でレイジを見上げた。
「武器は?」
「全部、取られて……」
「下着の中にも隠して置くように教えただろう」
「だって、それしたら前にケツにぶっ刺さって……」
不貞腐れたように言い訳するハルヒに、レイジは持っていたナイフを折り畳んで投げ渡すと、そのまま部屋を出ていった。
「おい!爆弾……!」
「私は解除できない。現在ある選択肢は、ナツキを探すか、諦めてこのビルから脱出するかの二択だ。おまえはどちらを選ぶ」
ハルヒの答えは決まっていた。まとわりつくロープを払い除けると、ハルヒはレイジに置いていかれないように駆け足でそのあとをついていく。
バリバリバリバリ!窓ガラスがその振動で震える。顔を向けると、屋上で回るプロペラが見えた。走り出したハルヒのあとにレイジが続く。
階段を3段飛ばしで駆け上がったハルヒは、最上階への扉の前で数人の男たちが押し合っているのが見えた。
「ああクソ、開かねえ!グレイスターのクソ野郎、ヘリで逃げるつもりだ!」
扉はギイギイと動いてわずかに開くが、外側で持ち手に鎖がかけられていてそれ以上は開かない。鎖は南京錠で固定されているのが見えた。
「子供を見たか!?俺の弟なんだ!」
「ああ、確かガキをふたり連れてたぜ!」
男たちはハルヒに口々にそう言った。この扉の向こうにナツキとココレットがいる。ハルヒは男たちを押しのけ、鉄の扉に肩からぶつかる。だが、男たち数人で開かない扉が、ハルヒひとりで開くはずもなかった。
「どきなさい。ハルヒ」
レイジが腰から銃を抜く。射撃の名手であるレイジが構えるのを見て、ハルヒは群がる男たちを左右に分けて階段の手すりに押し付けた。レイジの撃った弾丸は扉の隙間から外側に見えていた南京錠を撃ち抜く。
「グレイスター!」
ハルヒを押しのけた男が扉を開ける。それに続こうとしたハルヒをレイジが引き留めた。どうしてと聞く前に、ガガガガ!と銃声が鳴り、目の前にいた男が踊る。穴だらけにされたその身体は、あっという間に階段の下へ転げ落ちていった。
驚いて声も出ないハルヒを抱え、レイジは素早く扉の陰に身を隠す。逃げ遅れた男たちが同じように蜂の巣にされ、バタバタと倒れていった。
「隠れてへんで出ておいでよ」
扉の向こうからはクリムの声がするが、不用意に出て行けば同じ目にあうことはわかりきっていた。
「まだそこにおるんやろ?」
「ナツキを返せッ!」
レイジの腕の中でハルヒは叫ぶ。それにクリムはアハッと笑った。
「その声はハルヒちゃん?すごい。なあ、だれに助けてもろたん?」
我慢できず、ハルヒはナイフを手にレイジの腕の中から飛び出す。クリムは銃を構えた数人の私兵に待ったをかけ、ヘリに手を伸ばすとそこからぽかんとしているナツキを引きずり下ろし、その後頭部に銃口を突きつけた。
「感動の再会やね」
「やめろ……っ」
グレイスターの私兵に囲まれたハルヒは真っ青になって首を振る。ナツキはまだこの状況を理解していないが、自分の頭に突きつけられているものがなんなのかくらいはわかっている。
「……ねえ、ちゃん……?」
「―――やめてください、やろ?」
ナツキは自分に銃口を突きつける男を横目が確認し、ようやく理解する。この男は姉の恋人ではないのだと。
「あと、30分ってとこやな」
自分の腕時計に目を落とし、クリムは爆破までの残り時間を口にする。
「安心しい、ナツキくんは僕が連れてくから。そんで、用がなくなったらステファンブルグにでもあげとくわ」
クリムはナツキに向けていた銃をハルヒに向けた。
「やめてッ!」
ナツキがクリムの腕に飛びつく。だが、クリムはそれを振り払い、ハルヒに狙いをつけた。
パンッ!と銃声が鳴った。ハルヒは思わず肩を震わせたが、それに悲鳴をあげたのはクリムだった。
クリムの手は血に濡れていて、握っていた銃はヘリの中に飛ばされ、転がっていた。
撃ったのはレイジだ。ハルヒだけがそれに気づいていた。
「う、撃ち殺せっ!」
どこから狙われているかわからない。自分が的になっていることを知ったクリムは、ヘリに乗り込もうとして硬直した。そして、両手を上げて一歩、二歩と下がっていく。
「……ちょっと、待ちや」
上擦った声で懇願するクリムの言葉は、自分が落とした銃を拾い上げ、銃口を向けるココレットに向けられていた。薬を使われて喋れないココレットは、ただパクパクと口を動かす。
「な、なんや?」
聞き返しても、ココレットは口を動かすだけだ。
「そんなもん持ってるの危ないから、こっちに……」
パン!前触れなく、ココレットは引き金をひいた。それはクリムの耳を貫通した。痛みに激昂したクリムがココレットに掴みかかろうとしたが、その背中にナツキが飛びついた。
ナツキに銃を向けた私兵たちは、利き腕を撃たれて叫び声をあげる。その隙にハルヒはナツキを振り落としたクリムに向かって、握り締めた拳を振り下ろした。
渾身の一発が右頬に当たり、よろけたクリムにさらにハルヒは体当たりする。ハルヒの体重さえ受け止めきれずにクリムは転倒した。彼に馬乗りになると、ハルヒはさらに腕を振り上げる。
一発、二発と、ハルヒは続けざまにクリムの顔を殴りつけた。三発目でクリムに撃たれた傷が開き、腕に巻かれていた包帯に血が滲む。
「ハルヒ!」
それでもまだクリムを殴ることを止めようとしないハルヒの腕をレイジの腕が掴んだ。ハルヒは血走った目でその腕を振りほどき、レイジの胸ぐらを掴んだ。
「姉ちゃん!」
フーッフーッと鼻息荒く興奮したハルヒを、背中からナツキが抱きしめた。
「……なんの目的でここまで来たか思い出せ」
レイジにそう言われ、ハルヒはようやく両腕を下ろす。そしてナツキを振り返った。本当に久しぶりに再会した弟の目には涙が浮かんでいた。
「ナツキ……」
「姉ちゃん……!」
ナツキは両手を血塗れにしたハルヒを強く抱きしめた。
「爆破まで時間がない」
レイジが時計を確認する。もうグレイスタービルを降りている時間はない。これで脱出すると、レイジはヘリを顎で差した。
「いてて……」
夢中になっているときは気づかないが、いまになって傷が痛んできたハルヒは、ナツキに助けられながらヘリに乗り込んだ。
抱きついてきたココレットの頭を撫でるハルヒから、ナツキはレイジを振り返った。
「レイジさん……。あの、勝手にいなくなってごめんなさい……」
レイジは首を振り、肩を落として謝るナツキの頭を優しく撫でた。
「おまえは悪くない。私のほうこそ、不安にさせて悪かった」
「レイジさん……僕、」
「話は後だ。乗りなさい。脱出しよう」
レイジに急かされ、ナツキはヘリに乗り込む。銃声が鳴ったのはそのときだった。振り返ったナツキは、ヘリに倒れ込むレイジの姿を見る。その右脚の太ももには血が滲んでいた。
「レイジさんッ!」
「来るんじゃない!」
レイジはナツキに怒鳴り、自分を撃ったグレイスターの私兵の眉間を撃ち抜く。もう動く気配がないことを確認し、脚を引きずりながらレイジはヘリに這いのぼった。
「ナツキ。操縦席に座りなさい」
「ぼ、僕……?で、できないよ。ヘリなんか……」
車にさえ乗ったことがない。15歳のナツキは首を振る。
「では、ハルヒにやらせるのか」
ナツキはハルヒを振り返る。姉は腕から血を流し、それにココレットが髪にまいていたリボンをきつく縛り付けていた。
「私が言う通りに操作すればいい。そんなに難しいものじゃない。おまえならできる」
ハルヒに殴られ、意識を失っていたクリムが目を覚ますと、浮上していくヘリが見えた。呆然としながら腕時計を見ると、爆破まであと2分を切っている。すでに手の届かない空にいるヘリに、クリムは獣のように吠えた。
「……おまえ、喋れないのか?」
ココレットが何も喋らないことにハルヒはやっと気づいた。ココレットは泣きそうな顔で頷く。ハルヒはこれまで声が出なくなった子供を見たことがあった。彼は親を目の前で殺された子供だった。いまはこのヘリの操縦桿を握っている。
ショック状態から抜けたあとは徐々に喋ることができるようになったが、それには時間がかかった。
大きな怪我はないようだが、ココレットも酷い目にあったのだろう。
「……大丈夫だ」
ハルヒはそう言って、ココレットの身体を抱き寄せると、その背中をさすった。もう大丈夫だと繰り返すハルヒのほうが重症なのに、安心させようと抱きしめてくれる彼女にココレットはしがみつく。
「上手だ。ナツキ。そのままの位置で飛ぶんだ」
「は、はい」
緊張した面持ちのナツキに微笑み、レイジは脚に自分のベルトをきつく巻きつける。視線が合うと、ハルヒは複雑な顔を見せた。
「……助かった」
ハルヒから出たのは、レイジの予想していなかった言葉だった。
「あんたがいなきゃ……どうにもならなかった。だから……」
「しばらく見ない間に、随分と素直になったものだ」
レイジはそう言って笑う。
「それから女の顔をするようになったな」
「はぁ!?」
「あの男の影響か?」
「違う!」
ハルヒはすぐさま否定するが、振り返ったナツキと目が合ってしまう。
「男ってだれ?」
「だれでもない!操縦に集中しろ!」
ドォン!と西の空で轟音が鳴った。グレイスタービルが爆発したのだろう。ヘリは少し揺れたが、ナツキは落ち着いて高度を保ち続けた。
「ナツキ。フィヨドルとの国境まで飛ぶんだ。大丈夫だ。燃料はもつ」
おそらく、クリムが考えていた逃亡先もその辺りだったのだろう。ヘリには十分な燃料が積まれていた。暴動が起きているいまのスタフィルスはどこも危険だ。その判断は正しい。
だが、ハルヒはリュケイオン家に置いてきたアキたちのことが気がかりだった。クリムは、リュケイオン家が襲撃されたと言っていた。
(クサナギがいる……)
アキがいればきっと大丈夫だ。ハルヒは自分に言い聞かせた。
(まずはナツキとココを安全な場所に避難させてから……)
ピピッとレーダーに反応が出た。レイジがすぐに反応して確認する。中央に向かって赤い点がどんどん近づいてくる。かなりスピードが速い。あっという間に追いつかれたが、そのヘリはそのまま真横を通り過ぎていった。
「軍用ヘリ……!」
黒獅子が描かれたヘリは、ハルヒたちが乗るヘリとは逆方向へ向かって飛んでいく。そのヘリにはルシウスが乗っていたが、ハルヒたちはだれもそれに気づくことはなかった。
「妙だな……」
アメンタリの凱旋というわけではなさそうだ。それに、暴動鎮圧のためのヘリならば、一機だけなのはおかしい。
「何が起こってるんだ……」
ヘリから見下ろした景色はいつもの街並みとは違っていた。建物のあちこちから炎と煙が上がり、大勢の人々が大きな屋敷になだれ込んでいるのが見える。自分がグレイスタービルにいる間に何が起こったのか、ハルヒにはわからなかった。
「アメストリア・ルイ。スタフィルスと名乗る女が、自分こそが正当な王位継承者だと宣言した。つまりはクーデターだな」
ココレットが青くなって口元を押さえた。
「将軍率いる本隊はアメンタリへ遠征中。勝算を見込んでのクーデターだ」
ハルヒの知らない間に、スタフィルスはアメストリアの手中に落ちた。だったらもうテロリストとして追われることはなくなるのか。いや、楽観視はできない。黒獅子の本隊はまだ残っている。ハルヒはココレットの手から銃を奪い取って、それをレイジに向けた。
「姉ちゃん!」
「あんたは、【トライデント】から軍に寝返った裏切り者だろ。味方の心配をしなくていいのか」
「えっ?」
ナツキが振り返る。フッとレイジは笑った。
「ここでバラすとは、酷いな。ハルヒ」
「あんたがやったことを忘れたわけじゃねえ。あんたは仲間を罠に嵌めて殺し、トラまで殺そうとした。今回は助けられたけど、それで全部チャラになるわけじゃねえからな」
「さすが【トライデント】だな」
ナツキがさらに息を呑んだ。操縦桿を握ったまま振り返るが、ふたりはナツキを見ない。ふうっとレイジは息を吐いた。
「……レイジさん」
「ナツキ。ハルヒの言う通り私は悪い人間なんだよ。裁判でカゲトラを処刑しようとした所をハルヒに邪魔されてね。だから私はおまえを誘拐することにした。ハルヒとカゲトラを始末するための道具に使おうと思ってね」
いつでも優しかったレイジの口から語られるのは、ナツキには信じられない言葉ばかりだった。
「でも、あんたはそうはしなかった」
銃口を向けたままハルヒが言う。その通りだ。いつだってそうできた。ナツキを人質に、ハルヒとカゲトラをおびき出し、始末することはできた。だがレイジはそうはしなかった。それはなぜなのか。本人もその理由を探す。
「……ごほっ、ごほごほっ」
むせ込んだレイジは自分の口元を押さえ、ハルヒたちに背中を向ける。聞いたことのある咳にナツキが気づいた。
「レイジさ―――」
「ごほっ!」
激しく咳き込んだレイジは手のひらに吐血した。ハルヒが顔色を変える。
「……あんた」
さっきまで憎まれ口を叩いていたレイジの予想していなかった姿に、ハルヒはその場に立ち尽くした。レイジの顔色は真っ白で、口の周りについた赤い血と対象的な色が死を連想させる。そのコントラストにナツキはゾッとしたものを覚えた。
冷や汗の滲む額を手の甲で拭い、レイジは呆然としているハルヒに苦笑した。
「なんだ……。おまえらしくもない顔をしているな」
「………」
「おまえは昔から負けん気が強くて、頑固で、アキラもフユカも手を焼いた……。だからナツキは、おまえに比べて育てやすかったよ。素直で、優しく、穏やかな子だから……きっとあの子が、シュンが生きていたら……そんなふうに……」
レイジはナツキに、幼くして亡くなってしまった自分の息子を重ねていた。愛情を注げば、注いだ以上に笑顔を返してくれるナツキが愛しくて―――。息子が生き返って、側にいるような気がして―――。
「私は末期の癌だ。撃つのは自由だが、弾の無駄だと思うぞ」
明日には死んでいるかもしれないからなと、レイジは付け加えた。
「―――レ、」
ガガガガガ!いきなりの銃撃にヘリは傾き、その衝撃で扉が開いた。ハルヒは外へ吹き飛ばされかけたココレットの腕を捕まえる。ナツキもレイジに手を伸ばすが間に合わず、レイジの体はヘリから投げ出された。
「レイジさんッ!」
「操縦桿を放すな!」
ナツキに怒鳴り、ハルヒはココレットを奥の座席へ突き飛ばした反動を使って、ヘリの扉にかろうじてぶら下がっているレイジの手を掴んだ。
「うぐ……!」
レイジを引き上げようとしたハルヒの腕の包帯に血が滲む。
「姉ちゃんッ!」
「ナツキ!どっかに着陸させろ!」
レイジは細身だが、怪我をしているハルヒひとりで引き上げることは不可能だった。このままでは振り落とされる。プロペラの回転音に負けない声でハルヒは叫んだ。
どこか安全にヘリを降ろせる場所を探そうとしたナツキは、再び襲いかかった銃撃に悲鳴をあげた。気づかないうちに、一機のヘリがすぐ後ろまで迫っていた。レーダーに映った赤い点の正体を、ハルヒは肉眼で確認する。
「グレイスター社……!」
グレイスター社のロゴがペイントされたヘリから、三度の銃撃がハルヒたちの乗るヘリのボディに穴を開ける。クリムだ!その姿が見えなくてもハルヒにはわかった。
「ナツキ!ヘリをおろせ!」
「待って……!まず真っ直ぐにならないと!」
「とにかくおろせ!また撃ってくる!」
機銃はずっとこっちを向いている。すぐにまた撃たれる。燃料タンクを撃たれてもしたら空中で爆発炎上する。
「ハルヒ!手を離せ!」
ヘリの平衡感覚が戻らないのは、レイジがぶら下がっているからに他ならない。ハルヒが手を離しさえすれば少しは事態も好転する。だが、ここはまだ地上はるか上空だ。手を離せばレイジは死ぬ。
「ハルヒ!」
「黙ってろ!!」
離すどころか、ハルヒはレイジの手を握る腕に力を込める。
「あんたはナツキを殺さなかったッ!だからあんたのことは許せねえけど、俺はあんたを見捨てない!絶対に離さねえぞッ!」
ナツキはどうにか平衡を保ってヘリを着陸させようとしている。あと地上まで少しという所で、これ以上ないくらいグレイスターのヘリが迫る。操縦席で、目を見開いて笑うクリムの姿が見えた。今度こそ撃ち落とされる。
思わずハルヒが顔を背け、ココレットが耳を塞ぎ、ナツキが絶望に振り返る。そして、レイジはハルヒの手を振り払った。
「レ……!」
ゆっくりと落下しながら銃を構えるレイジの狙いは、1秒足らずで定まった。小さな口径から弾丸が放たれヘリの燃料タンクに当たるのと、レイジの身体が機銃に撃ち抜かれるのはほぼ同時だった。
体中に穴を空けられて落下していくレイジの姿に、ナツキは叫び声を上げてヘリを旋回させ、グレイスターのヘリに体当たりする。遠心力でハルヒはヘリの中へ放り込まれ、扉が勢いよく閉まった。
ドオオオオンッ!レイジの弾丸で燃料が燃え上がり、クリムを乗せたヘリが大爆発を起こす。ハルヒたちのヘリは爆風に吹き飛ばされたが、扉が閉まっていたために、その炎をまともに受けることはなかった。
ヘリはコントロールが効かないまま地上に落下し、砂の上を何メートルも滑ってようやくその機体は停止する。衝撃に嫌と言うほど身体をぶつけたが、その痛みでまだ自分が生きていることを実感する。
「ナツキ……!ココッ!」
どうにか身を起こしたハルヒは、まずココレットの無事を確かめる。操縦席を見ると、ナツキがヨロヨロと身を起こしていた。
ヘリは横倒しになっていて、ハルヒは真上にある扉をスライドさせて開く。外へ顔を出すと、熱気に顔を焼かれ、思わず息を詰める。少し離れた場所に墜落したグレイスターのヘリが激しく炎上していた。燃料タンクからエンジンに燃え移った炎は、瞬く間にヘリの操縦席まで達し、そこには黒焦げになっている人間らしき塊が見えた。
「レイジさん!」
「待て、ナツキ!」
ハルヒが止める間もなく、ナツキはヘリから飛び降りて走り出す。ハルヒは慌ててヘリの中に残っているココレットに手を貸し、彼女を外へと引っ張り出した。
ナツキはレイジの名を呼んで辺りを探す。そして、ヘリが衝突して崩れた建物の陰に、銃を持った腕だけが見えているのに気付き、急いで駆け寄った。
「……!」
だが、そこにあったのはレイジの腕だけだった。その先に目をやると、身体の一部らしきものが点々と転がっているのが見えた。頭、肩、頭―――対人用ではない兵器に撃ち抜かれた身体は、無残にあちこちに散らばっていた。
「ナツ―――」
ナツキを追ってきたハルヒが、ナツキが目にしているものに気付き、その足を止めるとココレットの行く手を遮った。
「……ナツキ」
ハルヒはナツキをそこから離そうとしたが、その前にナツキはレイジの手から銃を取ると、燃えているヘリに向かって走った。
「ナツキ!」
ナツキは操縦席に向けて引き金を引く。発砲音は何度も鳴ったが、まともに銃を握ったことのないナツキの腕では、大きな的であるはずのヘリのどこにもかすらない。もちろん狙っている黒焦げの死体にも。
「やめろ、ナツキ!」
数発も撃つと弾丸は切れたが、ナツキの気は収まらない。なおもガチガチと引き金を引くナツキの肩を掴んだハルヒが、その手から銃を取り上げる。
「やめろってッ!」
「でも……っ、だって……!」
ハルヒから見れば、レイジは許せない裏切り者だったけれど、ナツキにとってはずっと信頼できる父の親友だった。ウララが死んで、ハルヒと引き離されて、たったひとり頼れる大人だった。
「だってぇっ……!」
ナツキはボロボロと涙をこぼす。
弟を引き離されて何日も経った。その間、ハルヒにはいろいろなことがあった。それと同じで、ナツキにもハルヒの知らないたくさんのことがあったはずだった。ハルヒはナツキをそっと抱き締めた。
□◼︎□◼︎□◼︎
白獅子軍が起こしたクーデターによって混乱する街並みを見ながら、ルシウスの乗る軍用ヘリは彼の自宅である屋敷のヘリポートへ着陸した。
「大佐!危険です!」
屋敷周りに暴徒の姿はなかったものの、すぐにヘリから飛び降りたルシウスを操縦士が止めたが、彼は止まらなかった。
屋敷の中に入ったルシウスは絶句する。屋敷内は見るも無残に荒らされていた。アメンタリへの出撃前の屋敷の姿はそこにはなく、あるのは無数の足跡に蹂躙され、砂に塗れた廊下だった。
調度品はあるものは倒され、あるものは割られて床に散らばり、生前の母を描いた彼女の肖像画はナイフでめちゃくちゃに切り裂かれている。それに怒りを覚えたルシウスだったが、もっと大切なものの存在が彼に冷静さを取り戻させる。
そこから脇目も振らずに目的の部屋へ向かったルシウスは、勢いよくその扉を開けた。だが、そこにはだれの姿もなかった。
「クソ……!」
そこはリジカのために用意した客室だった。室内が荒らされた形跡はなかった。ルシウスは、そこに手のつけられていない朝食が残っていることに気づく。
「………」
ルシウスは部屋の奥へと進み、本棚の前に立つと、赤い背表紙の本を引いた。するとガコンっと音がなり、本棚が横へスライドしていく。
屋敷には有事のために、いくつもの隠し扉が作られていた。これはそのひとつだった。中には膝を抱えたリジカがいて、彼女は扉が開いた音に気づいてゆっくり顔を上げた。
「……姫」
リジカは無事だ。きっと暴徒が乗り込んできた際、エルザがここへ隠したのだろうと推測できた。慌てて隠れたのか、リジカは薄い寝巻きのままだった。
「姫。無事で良かった」
ルシウスは軍服のジャケットを脱いでリジカの肩にかけようとしたが、リジカはそれをはねのけ、隠し持っていた食事用のナイフを突き出してくる。
「ゴッドバウムはどこです……!」
アメンタリのことをすでに知っている。リジカの様子からそれが予想できた。知らせないようにとエルザには念を押したが、伝わらないほうがおかしいというものだ。そして、隠し通せるものでもない。
「よくも我が祖国を……!砂の蛮族め!」
リジカの手は震えていた。
本来なら、こんなことができる性格ではないのだろう。これは、初対面のときに見た弱々しい少女が虚勢を張っているだけに過ぎない。
「姫……」
同情してもアメンタリは戻らない。ルシウスがリジカにできることはひとつしかなかった。
自分に手を伸ばすルシウスにリジカはナイフを振る。その切っ先がルシウスの手の平を薄く切り裂いたが、動じることなくルシウスはリジカの身体を抱きしめた。
止められなかった。自分ではゴッドバウムを止める術がなかった。
「離せ!離せぇッ!」
リジカはルシウスから逃れようとめちゃくちゃに暴れるが、まだ子供の彼女に逃れる力はない。
「申し訳ありません。姫。私の力ではアメンタリを救うことができなかった」
リジカはルシウスの首に噛み付く。痛みにルシウスは顔をしかめたが、リジカを離しはしなかった。
「どうかあなたに償わせてほしい」
異国にたったひとり残された少女を守り抜かなければならない。ルシウスはそう決意した。
□◼︎□◼︎□◼︎
ヘリの墜落現場から歩き続けたハルヒたちは、リュケイオン家を目指すことにした。
リュケイオン家は襲撃された。クリムの言ったことが本当か嘘かは定かではなかったが、ハルヒはまだココレットにそのことを言えないでいた。
クリムが嘘をつく意味があったのかと考えると、可能性は半々だ。あれはハルヒの気力を削ぐための嘘だったのかもしれない。それもこれも、屋敷に戻ればすべてわかることだった。できるなら、カゲトラも戻っていることを祈りながら、ハルヒはふたりを連れて砂の道を歩いた。
しばらく歩くと、ようやく見覚えのある街並みが広がる場所へ戻ってきた。どうやらヘリが墜落したのはF地区の外れだったようで、そこはハルヒが毎日のように目にしていたF地区の大通りだった。だが、その様子はいつもとは違っていた。
いつもならたくさんの人々で賑わっている大通りにはだれの姿もなく、代わりに家財道具や商品などあらゆるものが散乱していた。
アメストリアがクーデターを起こした。レイジの言っていたことを思い出し、ハルヒは周囲に注意しながら進む。その後ろを、ココレットの手を引いたナツキが続いた。
あちこちの商店に略奪された痕跡があった。クーデターにより、日頃軍に抑圧されていた人々の鬱憤も爆発したのだろう。
ハルヒは店先に落ちている日除けのキャップを拾い上げる。多少踏まれて汚れていたが、十分に使える。ハルヒはキャップの砂を払うと、それをココレットの頭に被せた。ココレットはキョトンと目を丸くする。
「おまえの顔はそこそこ売れてるんだろ」
暴徒の怒りの矛先は、自分よりも恵まれた生活を送っていた人々だ。下位地区の商店がこの有様では、上位地区の貴族の屋敷はもっと酷いことになっているだろう。この状況で、リュケイオン家のココレットが大手を振って歩くのは自殺行為でしかない。
ハルヒの言いたいことを理解して、ココレットは深く帽子を被りなおした。ナツキは無言のまま、どこか遠くを見ている。まだ現実に頭が追いついていない。そんな様子だった。
あの後、バラバラになったレイジのパーツをできるだけかき集め、3人で掘った砂の中に埋めた。ヘリの残骸くらいしか墓標にできるものはなかった。ナツキは拾った破片で墓標にレイジの名を刻んだ。
こう言ったことは、嫌でも流れる時間が解決してくれることをハルヒは知っていた。記憶と言うものは喜怒哀楽のどの種類であれ、日々薄れていく。母親のことを思い出しても、彼女が死んだときと同じだけの悲しみは、もうハルヒの胸には残っていなかった。
「ナツ……」
ナツキにも何か被せよう。直射日光から弟を守るため、別の帽子を探そうとしたハルヒは、人々の声にハッと顔を上げた。
「……ここでいろ」
近くに大勢の人間がいるが、そこは安全ではないかもしれない。大通りの惨状を見れば、大勢と合流するのが安全であるとは言い切れなかった。
「姉ちゃん……」
「だれか来たら隠れろ。だめなら逃げろ。おまえがココを守れ。いいな」
ハルヒはナツキにそう言って、ひとり様子を確かめに行こうとしたが、ココレットに引き止められた。まだ声が出ないココレットは必死に首を振る。
やっとナツキに会えたのだから、ふたりは離れるべきじゃない。その目はそうハルヒに訴えていた。
「……わかった。離れるなよ」
危険だとわかっているところにふたりを連れて行きたくはなかったが、いまとなってはどこも安全だとは言えない。ハルヒはふたりを連れて銃声の鳴ったほうへと歩き出した。
騒ぎが起こっているのは街の外へ出るためのゲート前だった。いつもは開かれているゲートは閉じていて、その前は集まった人々でごった返している。大きな荷車を引いている男、小さな子供を抱えた女、若者から老人まで、その数はFとE地区の人間がすべて集まったのではないかと思うほど大勢だった。
以前ならゲートを管理しているのは黒獅子軍だったが、いまゲート前で銃を手にしているのは白い鎧を着た騎士たちだ。アメストリアの顔を思い出し、ハルヒは小さく舌打ちした。
人々はゲートを開けてくれと口々に言っていた。クーデターが起こった国内にいるのは危険だ。フィヨドルに行けば黒獅子軍がいる。きっと保護してもらえるだろう。白獅子の騎士に向かって口にしはしないが、人々はそんな思いでゲートに集まっていた。
アメストリアは人々を国外に出すつもりはないらしい。この分では、他の地区の門も閉じられているのだろう。
「サーマに病気の妻がいるんだ!」
子供を抱えた男がそう叫ぶ。は、サーマはスタフィルス内の都市で、砂漠のオアシスのそばにある、この首都ダフネから一番近い街だった。
「私はここへ薬を買いに来ていただけなんだ!ここに通行証もある!頼むから通してくれ!」
「私の娘がプランマリンにいるの!」
「両親と連絡がつかないわ!」
その男を皮切りに、あちこちで声があがる。騎士たちは顔を見合わせ、最初に声を上げた男を手招きした。
男は子供を抱き直し、人込みを掻き分けて騎士のもとへと進んでいく。あいつだけ通すのか。俺たちはどうなるんだ。非難の声が漏れる中、ゲートの前までやってきた男に騎士は銃口を突きつけた。ハルヒが息を呑むのと、男の頭が撃ち抜かれるのはほぼ同時だった。
悲鳴が上がり、ゲートに詰め掛けていた人々がワッと散る。
「いいか!アメストリア陛下の命に逆らう者は反逆者とみなし、この場で処刑する!」
騎士はそう言うと、父親を撃ち殺された子供に銃を向けた。子供は泣くこともできずに自分に向けられた銃口を見ている。
「やめろッ!」
思わず声を上げたハルヒに気づいた騎士は、すぐさま彼女へ銃口を向けた。撃たれる。ナツキがハルヒを守ろうと前へ飛び出そうとしたそのとき、黒い車がその間に滑り込んできて、ハルヒに当たるはずだった弾丸を受け止める。
「撃つな、僕だ!このばかども!」
車の窓が開き、そこから顔を出して怒鳴ったのはコードだった。彼は憤慨したあとに車の扉を開けると、早く乗れとハルヒに言った。
「なんで俺がおまえと……!」
コードはアメストリアの仲間だ。ハルヒたちが目指すのはリュケイオン邸であって、王宮ではない。ハルヒは拒否の姿勢を見せる。
「このばか女!クサナギを取り戻したいなら早く乗れって!」
どういうことなのかまったく意味がわからない。困惑するハルヒの腕を掴み、コードは強引に車の中へと引っ張る。
「姉ちゃん!」
「ああもう!全員乗って!早く出して!」
ナツキとココレットも車に押し入れ、コードは運転手に出発するよう命令する。車はすぐに走り出した。
□◼︎□◼︎□◼︎
―――おいで。ここから逃がしてあげる。大丈夫だよ。怖がらないで。
―――僕を見て。
―――僕はアキラ。
手を伸ばす彼の顔は影になっていてよく見えない。8年前の記憶はいつも断片的で曖昧だ。
「……アキラ」
アキはそう口にすると、重い頭と体を起こした。まだ生きていると言うことは、イスズは死んだのだろう。見届けてはいないが、その予想はついた。
最近、目が覚めるたびに違うベッドに寝ているせいか、自宅のベッドを恋しく感じることがある。だが、二度とあの部屋に戻ることはない。アキはそれを理解していた。
「目が覚めたか」
その声に、アキは顔を向ける。そこにある大きなソファーに深く腰掛けていたのはアメストリアだった。
彼女の存在にアキは驚かなかった。イスズの行方を探してたどり着いた広場には、彼女の姿もあったからだ。
「気分はどうだ?」
イスズに刺されることなった出来事の前に、アキはアメストリアの王宮から逃げ出している。そのことを責められるかと思ったが、彼女はご機嫌に微笑んでいた。
「先の戦闘では大儀であった」
アキがアメストリアの言葉の意味を理解するのには数秒が必要だった。
「……あなたのために戦ったんじゃない」
アキはなんとしてもイスズを止めなければならなかった。イスズの憎しみは自分の蒔いた種だったのだから。
「随分と謙遜するのだな。褒美として、私のもとから逃げ出したことは許そう」
「どうも」
忘れていてくれて良かったのに。アキは苦笑する。
「では、これで貸し借りなしと言うことですね」
「私は王だ。貸し借りなど初めからない。私のために働くことは、そなたの生きる意味そのものだ」
アキは、今度は頷こうとしなかった。そろそろこの場から立ち去りたいが、アメストリアが邪魔だ。彼女は王ではあるが、適合者ではない。力を使えばここから脱出することは簡単だが、イスズとの戦闘で力を使いすぎている。服の上からでも心臓の周りの血管が膨張しているのがわかった。
「あの娘が気になるのだろう」
「………」
「ハルヒ・シノノメ。そなたは、あの野良犬のような娘がいまどこにいるのか知りたい。違うか?」
「グレイスタービルでしょう」
「ああ。そうだ。そこにいた。そして吹き飛んだ」
「……え?」
「あのビルは爆破されたんだ。そのとき、ハルヒ・シノノメはそこにいた。その弟もな」
アキは黙ったままアメストリアを見つめる。そして首を振った。
「……信じない」
「嘘ではない。グレイスタービルは瓦礫の山と化した」
「この目で見るまでは信じない」
アキはグレイスタービルへ向かうために立ち上がる。強烈な共鳴音が鳴り響いたのはそのときだった。
「うぁ……ッ!」
アキは膝から崩れ落ち、耳を押さえたが共鳴音はそれくらいでは防げない。鼓膜を震わせる音は、脳へ刺すような痛みを与える。
アメストリアは手に持った端末を持ち上げ、一瞬で顔色を失ったアキに見せ、フッと笑う。
「コードに聞いたときは半信半疑だったが、これほど効き目があるとはな」
端末は、黒獅子軍の研究施設にあったものだった。アメストリアには聞こえないが、適合者だけが聞こえる共鳴音が出せる端末だとコードは言っていた。
「アキ・クサナギ。私の騎士になれ」
「……ッ!」
「私の騎士になると誓えばその苦しみから救ってやる」
「う……!」
アメストリアは適合者じゃない。彼女を風で吹き飛ばして端末を奪おうとしたアキは、頭が砕けるような痛みに襲われ悲鳴を上げる。
脳神経に直接電流を流すようなものだから、乱用すれば廃人になりかねない。コードはそれを危惧していたが、アメストリアは構わず共鳴レベルを上げていく。
「ぐぁ……!うぅ……ッ!」
研究施設に捕まったときは、共鳴の中でも力を使うことができた。無我夢中ではあったものの、あのときアキの適合率はヴィルヒムの予想を超えていた。
「なんでも、報告書によれば、そなたに一度打ち破られたことで、この装置は強化したらしいぞ」
ボタボタッとアキの鼻から血が垂れる。
「私の騎士になると誓え」
「い、や……だ……!」
アキはゼェゼェと息を吐き、首を振る。目の前のアメストリアが邪魔だ。自分は早くグレイスタービルに行かなくてはならない。ハルヒの無事を確かめなければならない。もし、助けが必要なのであれば、彼女を救わなければならない。それにはアメストリアが邪魔だ。
アキの髪が風に揺れ、アメストリアの手の端末が真っ二つになって床に落ちていく。それが落下する前に、アキは部屋の窓から外へ文字通り飛び出そうとしたが、開け放った窓には鉄格子がはめられていた。
(切り裂く……!)
アキの適合率であれば、鉄の棒を切り裂くことくらいわけはなかった。実際あと1秒、部屋の四隅に設置されたスピーカーから共鳴音が鳴り響かなければ、アキは逃げ出していただろう。
スピーカーからの強烈な共鳴はアキの脳を焼き、その意識さえも奪った。アメストリアは床に倒れたアキのそばへと近づき、その腕を掴んで彼の身体を仰向けに転がした。
「陛下」
ずっと部屋の外で待機していたカガリヤが中へ入ってくる。そして、床に転がっているアキを汚いものを見るような目で一瞥した。
「この男をおそばに置くのは危険です」
「私に意見するのか」
「……いいえ。そうではありませんが、」
「問題ない。すぐに騎士になりたいと懇願してくるさ。そうなるよう調教してやる」
ハルヒと、うわ言をアキが口にする。それを聞いたアメストリアはニィッと目を細めた。
「それで、この男の本当の素性はわかったか?」
「……はい」
アキの素性については、前々からアメストリアに調べておけと言われていた。アメストリアが知りたがったのは、だれもが知ることのできるアキの個人情報ではなく、彼がスタフィルスへ来る以前のものだった。
カガリヤはアメストリアに報告書を綴じたファイルを差し出す。その1枚目には、アキの顔写真とともに、ラティクス・フォン・バルテゴの名が書かれていた。
□◼︎□◼︎□◼︎
ハルヒたちを乗せた車は夕方軍本部へと到着した。降りてとコードに言われて、ハルヒは車から出た。ナツキとココレットもそれに続く。軍本部には白獅子の旗が掲げられていて、それはここがココレットにとって安全な場所ではないことを示していた。
「クサナギはどこだ?」
「焦らないでよ」
そう言うが、急かして連れてきたのはコードだ。軍本部前の広場には真新しい血痕があって、ここで起こった出来事をそれぞれに想像させた。
「まず僕のプランを聞け」
コードがそう言うと、車を運転していた男が地図を広げた。それは軍本部の見取り図だった。
「クサナギはここにいる」
コードは少し前まではゴッドバウムの部屋だった場所を指差す。ココレットの父である彼は、ほとんどの日々をここで生活していた。
「待てって!この単細胞生物!」
またもやすぐに軍本部へ乗り込もうとしたハルヒに対し、コードが暴言を吐く。
「クサナギはここにいるけど、アメリアもここにいるんだよ!彼女がいるってことは、ここが!一番!警備が!厳重なんだ!わかるか!」
「どうにか忍び込む」
「どうにかってどうやって!網の目状の包囲網だぞ!行き当たりばったりの成功率ゼロプランなんかごめんだ!いいか。まず警備システムを切る。この警備室へ行くぞ」
コードは地図上の警備室を指差し、ハルヒたちの返事を待たずに歩き出す。コードはヴィルヒムの息子だ。そのためイマイチ信用できないハルヒの手を、ナツキが後ろから繋いだ。
ひとりなら突っ走るハルヒも、いまはナツキとココレットを連れている。その手の温もりを感じたハルヒは、コードの言う通り行き当たりばったりで行動すれば、このふたりも巻き添えを食うことを再認識する。
ハルヒはナツキに頷き、ココレットの頭を帽子の上からポンと叩くと、その背中を押してコードの後へ続いた。
□◼︎□◼︎□◼︎
騒がしかった外が静かになった。あれだけ聞こえてきていたひとの悲鳴も、爆音も、動物の鳴き声も聞こえなくなったことに気づいたハインリヒは、隣で目を閉じているメアリーに目をやる。
「……先生。起きてるか?」
「……ええ」
「……暴動は収まったと思うか?」
ふたりはクーデターが起こったことをまだ知らなかった。だが、外で何かとんでもないことが起こったのだろうことは、聞こえてくる悲鳴や爆音で察するに十分だった。
「……どうかしら」
少しだけ目を開けたメアリーは、確認しないとわからないと言った。外に出れば武器を構えた兵士に取り囲まれるなんてこともありえない話じゃない。命はひとつ。冒険はできない。
「アキは……どうしたかな」
アキの力をその目で見た。力を持たない身からすればアキの力は最強に見えるものだが、ハインリヒにはそうは見えなかった。神の力は人間には扱えない。風を放つたびに疲弊するアキの姿が、ハインリヒにそう思わせた。
「わからない」
メアリーは正直に答えた。アキはイスズとの決着をつけにいった。その決着がついたのかどうかすら、ハインリヒとメアリーには知る由もなかった。
「アキは……俺が買ったんだ」
「前に言ってたわね」
ココレットもいたから詳しく聞きはしなかったが、ハインリヒはアキを拾ったではなく、買ったと言った。つまりアキは自身を売っていたと言うことだ。
「あいつは街娼の中でも一番痩せこけたガキでさ……、なんか知らねえけど腹が立ってよ……。軍に媚びへつらうことでしか生きてけない人生が嫌になってたのかも知れねえな……、それとも気まぐれか……あの夜買って、育てた……」
「………」
「あいつは―――やらせれば大概のことはうまくこなしたし、対人関係も踏み込みすぎない一定距離を知っている。買った当時は表情なんかなかったあいつにたったひとつだけ教えた、人当たりのいい笑顔で、だれからも好かれるのに、なぜか関わりを嫌う。いままで恋人みたいなもんも何人か見てきたけど、心を許せてるって感じはしなかったな……」
ハルヒを見つめるアキは、ハインリヒが初めて見るアキだった。なんのことはない。心を許されていなかったのは、自分も同じだったというわけだ。
「あいつがだれかのために必死になるとこなんて初めて見たよ」
いつも持てる力の半分も出さないで、フワフワと風に飛ばされるまま、ただ生きているように見えた。その姿はすべてを失った死人のようにも見えた。それが変わったのは、紛れもなくハルヒの影響だ。
買って育てて教育して、大学まで出して世話をして、それなのに酷いものだ。ハインリヒは苦笑する。親子と言うには歳が近すぎる、不思議な関係だった。それでもアキの変化に、ハインリヒの胸には父親が感じるような満足感が広がっていた。
「そろそろ行くか」
ここでじっとしているわけにもいかない。この国がどうなったか、何が起こったのか確かめる必要があった。立ち上がろうとするハインリヒをメアリーが支えた。
□◼︎□◼︎□◼︎
警備室に到着したコードはカードキーを使って中に入る。その直後、中にいた男に首根っこを掴まれてモニターに押し付けられた。
驚いたハルヒは、反射的にコードを助けようとして繰り出した蹴りを、男は片腕で受け止める。そこでやっとふたりは互いの顔を確認した。
「トラ!」
「ハルヒ……!」
思わぬ場所での再会に、ハルヒは身体の力が抜けるのを感じた。これまでは、ナツキとココレットを自分が守らなければならないと思う重圧があったが、カゲトラがいればその負担を半分にできるからだ。
「カゲトラ!」
ナツキが叫んでカゲトラに飛びついた。一瞬、自分が幻を見ているのかもしれないと思ったカゲトラだったが、ナツキの柔らかな髪を撫でると、これが現実だと知ってその目に涙が滲んだ。モニタールームの端には、カゲトラが沈黙させた警備兵が数人伸びていた。
「トラ。そいつをおろしてやってくれ」
ハルヒがコードを解放するように頼む。
「アメストリアの仲間だぞ」
「わかってる。だけど、俺たちはクサナギがここにいるって聞いて来たんだ。見つけるのにこいつの助けがいる」
カゲトラが合流しても、彼も軍本部の内部をよく知るわけじゃない。コードの助けは必要だとハルヒは判断した。
カゲトラは渋々コードから手を離す。やっと解放されたコードは、文句を言いながら襟元を直した。
「無事だったんだな」
「まあ、色々あったがこの通りまだ生きてる。おまえたちも無事で良かった」
アメストリアに逆らったカゲトラは一時拘束されたが、自力で脱出してモニタールームを制圧した。ハルヒたちとの再会はその矢先だった。
「クサナギはアメストリアのところだと思うが……」
「いた」
モニターを操作していたコードが指をさし、そこへハルヒは目を向けてギョッとする。そこには裸の男女が映っていた。ナツキはぽかんと口を開け、ココレットは真っ赤になって目を逸らす。
監視カメラーに映る映像は鮮明ではなかったが、それがだれかくらいは判別できる。裸で抱き合っているのはアキとアメストリアだった。
「この映像は本物だけど、ショックを受ける必要はないよ。共鳴装置を使われたんだろうと思うから」
やめとけと言ったんだけどねと、コードはため息をついた。
「共鳴装置?」
「適合者にしか聞こえない種類の音波を出す装置だよ。研究施設にあったものを僕が見つけた。強い共鳴に脳がやられると、正確な判断ができなくなる。個人差があるけど、大体はあるはずのものが見えず、あるはずのないものが見えたりする。薬物中毒に似た症状だって、ヴィルヒムの研究資料には書いてあったよ」
ハルヒは、アキと一緒に捕まった研究施設でのことを思い出す。あのとき、アキはハルヒを見ているのに、別の何かに見えていた。だから、いまのアキがどんな状態になっているかは予想がつくのに、ハルヒは声が出なかった。
「ハルヒ。聞いてるか?」
「……ああ。聞いてる」
アキが別の女と抱き合っている姿にショックを受けていることに、彼女自身が気づいていない。カゲトラは小さく息をつく。
「おまえはなぜ俺たちに手を貸す?」
ハルヒはコードに質問した。それは当然の疑問だった。アメストリアのもと、コードは研究機関の代表として特に不自由のない生活をしているように見えた。
「僕にあって、アメストリアやヴィルヒムにないものはなんだと思う?」
「さあな」
「人間としての良心だよ。それに、僕はやつらにはない、一般的な倫理観ってやつも持ってる」
「……おまえを信じるぞ」
コードは無言のままハルヒに頷いた。
「クサナギを取り戻したあとのプランは?」
白獅子に制圧されたこの国に留まることはできない。そして、ナツキを取り戻したいま、国外に出ることをハルヒが拒否する理由もなかった。
コードは警備室の壁にある地図を指差し、集合地点をハルヒに伝えた。
「船でマーテルへ亡命する。船はフィヨドルの隠し港にある。そこまでは車で移動する。僕もおまえを信じる。30分以内にクサナギを連れてここへ戻ってこい」
ハルヒが振り返ると、ナツキとカゲトラが頷く。
「クサナギのところには俺ひとりで行く。ナツキ。おまえはココとここにいろ。時間内に俺が戻らなければ先に行け」
ナツキは頷かない。ハルヒを置いていくことも、離れ離れになることも納得できなかった。
「俺はどんな手を使っても追いつく。クサナギもいるから大丈夫だ。だから行け」
「姉ちゃん……」
クサナギもいる。ハルヒはそういうが、ナツキはアキについて何も知らない。
「カゲトラ。おまえはココレットの屋敷に戻ってくれ」
「なぜだ?」
いまさらあの屋敷になんの用があるのかと、カゲトラは聞き返した。
「……屋敷が襲撃されたって、クリム・グレイスターが言ってたんだ」
ココレットが息を呑んだ。屋敷にはセバスチャンたちが残っている。リュケイオン家を襲撃したのは白獅子軍なのか、それともクーデターに乗じた暴徒なのか。それはわからないが、重要なことは屋敷に残してきた彼らの安否だった。
「ほんとか嘘かはわからない」
だが、嘘だとも決めつけられない。動揺してフラついたココレットをナツキが支えた。
「マーテルへ行くならあのじいさんと、その娘の医者の女と、それとハインリヒの野郎も一緒だ」
「わかったよ」
これを渡しておくと、コードはカゲトラに通信機を投げる。アキは確実にここにいるが、屋敷が襲撃されたのなら、ハインリヒとメアリーがその場にとどまっているとは考えにくい。
コードにアメストリアの部屋までの最短ルートを聞くと、ハルヒは頼んだぞとカゲトラの胸を拳で押し、自分も目的の場所へ走り出した。
□◼︎□◼︎□◼︎
ふたりの荒い息遣いと、アメストリアの嬌声。扉の隙間から漏れ出してくるそれを、カガリヤは扉の前で聞いていた。その表情は穏やかではなかった。
20年、アメストリアを守ってきたカガリヤにとって、それは衝撃的なことだった。いままで、アメストリアがその行為を許したのは、自分しかいなかったからだ。
胸を渦巻く感情が嫉妬かと問われれば、カガリヤは否と首を振るだろう。アメストリアに性交渉の手ほどきを行ったのは、あくまで役目としてだ。嫉妬の感情を抱くような、そんな浮ついた感情は初めからなかった。彼にとって彼女は女ではなく、王なのだから。彼はそう自分に言い聞かせていた。
カガリヤの胸を不安が渦巻く。アキは指先1本使わずに、いつでもアメストリアを殺すことができる。共鳴装置を鳴らすのが少しでも遅れたら、アメストリアの首は次の瞬間飛んでいるかもしれない。アキはバケモノなのだ。
それなのになぜ、わざわざそんな危険なバケモノをベッドに引き入れるのか、文句は腐るほどあったが、アメストリアの騎士として、それを彼女にぶつけることはできなかった。
一際高いアメストリアの声があがる。カガリヤは拳を握り締め、自分の足元を射抜くように見つめた。
□◼︎□◼︎□◼︎
忍び込むなら通風ダクトが手っ取り早い。大きな建物であれば、ハルヒが通り抜けるくらいのダクトは必ず常備されていた。ハルヒは埃だらけのダクトを這い進み、目的の部屋の上までやってきた。
ダクトの中から室内を見下ろす。将軍の私室はオフィスとプライベートに分かれていて、アキがいるのはプライベートのほうだ。ダクトから、監視カメラの映像で見たベッドにアキが横たわっていることを確かめる。アメストリアの姿はないが、シャワーの音が聞こえた。アメストリアに見つかるのは面倒なので都合がいい。ハルヒはダクトにぶら下がってから音を立てずに床へ降りた。
侵入がバレる前にアキを連れて脱出する。ハルヒは足音を立てないようにベッドへと近づいた。
「………」
本当はあの映像を否定しかったのかもしれない。服も着ず、ベッドで眠っているアキを見て、ハルヒは初めて自分がそう思っていたことに気づいた。
コードから共鳴の説明はされた。共鳴でアキがどうなるかも見たことがある。だからこれは事故のようなものだ。アキが望んだことじゃない。そうわかっていても、ハルヒは胸にズキリとした痛みを覚えた。
「……しっかりしろ」
ハルヒは自分にそう言って、両手で頬を叩いた。まずはアキを起こさないといけない。アキは細身ではあるが、自分が彼を支えきれないのは経験からわかっていた。
「クサナギ。クサナギ、起きろ」
ハルヒが二、三度揺り動かすと、アキは薄く目を開ける。トロンとした、寝ぼけたような目がハルヒを映した。
「俺がわかるか?」
「……ハルヒ」
「よし」
アキはちゃんとハルヒを認識した。ホッとしたハルヒは床に落ちていたアキの服を彼に押し付けた。とりあえず、服を着せないことには連れ出せない。
「早く着ろ」
いつアメストリアがシャワーから戻るかわからない。このあと、まだマーテルへ亡命するという大仕事が残っている。できれば騒ぎを起こすことなく脱出したい。
ハルヒに言われるまま、アキは渡された自分の服を身につけ、周りを確認する。自分はなぜ裸だったのか、頭の芯が痺れているようで、記憶もはっきりしない。ずっと耳鳴りがしている気がして、アキはそれを振り払おうと首を振る。
───いい子だ。ラティクス。
「!」
断片的な記憶がふわりとアキの脳裏を掠めた。バスルームの扉が開いたのはそのときだった。そこから姿を見せたアメストリアに、ハルヒはアキを守るように前に出る。
「アメストリア……!」
「確か……ハルヒ・シノノメだったな」
濡れた髪を拭きながら、アメストリアはバスタオル一枚だけを巻いた姿で、ベッドへと近づいてくる。ペタペタと裸足が床を踏む音に、アキの耳鳴りは酷くなっていった。ピースの足りないパズルのように、所々抜け落ちた記憶の中で、アメストリアの唇が笑みの形を作り、アキを呼ぶ。───ラティクスと。
「その様子では、まったく覚えていないわけではなさそうだな」
アキは動揺に見開いた目でアメストリアを見た。
「そんな目で見られるとは心外だな。あんなに求め合った仲ではないか」
アキの顔はますます苦いものになる。アメストリアの言う通り、すべてを覚えていないわけじゃない。唇にはまだアメストリアの唇の感触が残っていた。
「そなたも楽しんだだろう。その証拠に───」
アメストリアはそう言って下腹部を押さえた。
「さて……、小娘。残念だがその男は私のものだ。返してもらおうか」
「こいつはだれのものでもねえ」
「そうであれば、そなたのものでもないと言うことだ」
「そうだな。だけど悪いが、こいつが命かけて守ろうとするのは俺なんだよ」
アメストリアの口元に歪んだ笑みが浮かぶ。
「てめえみてえなクソ女じゃなくな」
「小娘。言葉選びを誤ったことを後悔するがいい」
アメストリアはクッと笑い、指を弾いた。するとそれだけの合図で、カガリヤとはじめとした騎士が数名部屋へ入ってくる。彼らが持つそれぞれの武器はすべてハルヒに向けられた。
「やめ……ッ、ぐ……!」
ハルヒを守ろうとしたアキは、鼓膜を震わせた共鳴音に耳を塞いだ。アメストリアの手には共鳴装置が握られていた。
「小娘を殺せ」
アメストリアの命令に従い、騎士が槍を突き出すが、アキの風がそれを跳ね飛ばす。アメストリアが共鳴レベルを上げた。
「うぁあッ!」
「やめろ!」
ハルヒは共鳴装置を持っているアメストリアに飛びかかろうとするが、主君を守るためにカガリヤがその行く手を遮り、ハルヒの横腹を蹴り飛ばした。加減のない力にハルヒの身体は壁際まで吹っ飛ぶ。
「ハルヒッ!」
ハルヒは蹴られた脇腹を押さえて悶絶する。立ち上がろうとしたアキは、さらに強くなった共鳴に悲鳴を上げた。ハルヒにとどめを刺そうとしたカガリヤをアメストリアが止める。
「ラティクス」
アメストリアはアキをそう呼んだ。
「最後のチャンスをやろう。私の騎士になると誓うなら、小娘は助けてやってもいい」
「……!」
「よく考えて返答しろ」
共鳴の中では立ち上がることもできない。返答を間違えればハルヒはカガリヤに殺される。ゴクリとアキは生唾を飲み込んだ。
「……僕は」
ふいに共鳴音が消えたのはそのときだった。アキの身体は嘘のように軽くなる。それに気づいたのもアキだけで、もとから聞こえない音が消えたことにだれも気づいていない。
「僕は……あなたの騎士にはならない」
アキの答えを聞いたアメストリアは共鳴レベルを最大まで引き上げ、ハルヒを殺せとカガリヤに命じたが、その命令は遂行されることはなかった。なぜなら、次の瞬間にはカガリヤを含む騎士全員が、アキの風で壁に叩きつけられていたからだ。
アメストリアは共鳴装置のレベルを確かめるが、それは最大になっている。アキは自分で起き上がろうとするハルヒを止め、軽くその腕に抱き上げた。
アメストリアはすぐに引き出しにある銃に手を伸ばすが、銃身に指が触れる前に彼女の身体は天井に叩きつけられ、床に落下した。
「し、死んだ……?」
アキの腕の中でハルヒが珍しく声を震わせた。
「大丈夫」
たぶんねと、アキは心の中で補足して、抱き上げたままのハルヒをぎゅっと抱きしめた。
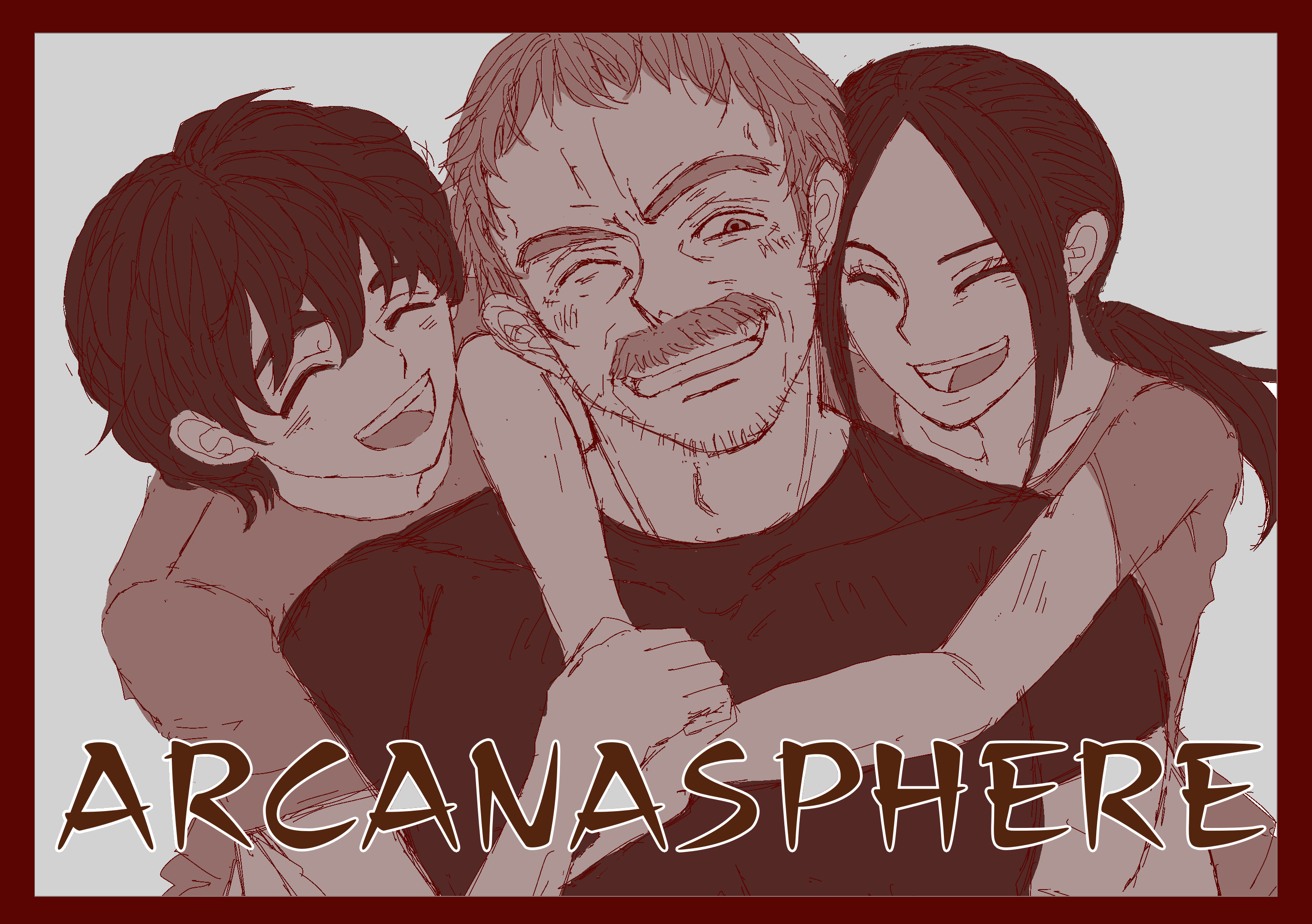
 にぃなん
Link
Message
Mute
にぃなん
Link
Message
Mute

 にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん