ARCANASPHERE4 手術中の赤いランプが点灯してから2時間が経過した。手術室が見下ろせる2階席から、ルシウスとエルザは手術の様子を見下ろしていた。
胸を開かれた実験体は、その体内に異物を埋め込まれると同時に、目を見開いて暴れ出した。拘束具を引き千切るような力に、手術に立ち会っていた医師や研究員がその場から離れる。
首輪にF-207と記された実験体は、白目を剥いて口から大量の泡を噴出すとあっという間に事切れた。その後、その身体は見る見る水分を失って枯れていく。それは何度も見た光景だったが、どうしても慣れないエルザはグッと口元を押さえた。
干乾びたミイラのようになった死体は、すぐさま処理班によって手術室から運び出されていった。
「本日の適合者は0です」
そんな嬉しくもない報告を受けたチグサは無反応だった。タオもつまらなそうに鼻の下にペンを挟み、天井を見上げて口を尖らせている。退屈極まりないと言いたそうな態度だった。
そんなふたりの姿にエルザは怒りを覚えた。今日だけで14人の実験体が死んだ。エルザとルシウスがこの実験に立ち会うようになってからでも、もう200人以上の人間が死んでいた。
「なぜ適合しない?」
ルシウスが資料を机の上に投げ捨てる。重ねられているだけだったそれは机の上で無造作に散らばった。
「適合するのは稀でスヨ」
タオが答えた。
「長いこと、この研究に携わっていまスガ、適合者は1000人にひとり、いるかいないかデス」
「1000人だと……!?」
「進歩には犠牲がつきものですわ。少尉」
思わず声を上げたエルザに微笑み、チグサはタバコに火をつけた。
「それに、苦労して得られるものだからこそ価値があるのです」
「だが、そろそろ結果を出してもらわねば困る。今まで適合した実験体で共通するものはないのか?」
チグサはそうですねと言って足を組み替え、ルシウスを見つめる。
「関係ないとは思いますが、強いて言えば……若い男かしら」
大佐のような。そう付け加えたチグサに、エルザが腰の銃に手をやったのを、ルシウスが手で制した。
「若く、健康な男―――これまでの適合傾向を見ればそうなります」
「エルザ。明日までにF地区あたりから若い男を集めておけ」
「大佐……!」
「命令だ」
ルシウスの低い声に、エルザは不本意ながら敬礼を残して部屋をあとにした。室内にチグサの吐き出した白い煙が漂う。
「大佐にご協力いただけて、機関としてはとても助かっておりますわ。代表であるステファンブルグの代わりにお礼を申し上げます」
「知っていれば、もっと早くにバックアップできたんだがな」
嫌味とも取れるルシウスの言葉に、チグサはニッコリと微笑む。そこへ研究員がひとりやってきて、チグサに耳打ちする。それは、フィヨドルから大勢の捕虜が送られてくるという報せだった。
□◼︎□◼︎□◼︎
ありがとうございましたと感謝の言葉を述べ、深々と頭を下げると、ココレットはその店をあとにした。店の外に出るとすぐ、焼け付く太陽が肌より先に視界を焼く。今日の空は、先日の砂嵐が嘘のような快晴だった。
住まいがあるC地区から、ここF地区まで、ココレットはひとりでやって来ていた。正確には執事の目を盗んで屋敷を抜け出した。そんなココレットの目的は、ナツキの家を探すことだった。
店主に聞いた話によれば、ナツキの家はこのあたりにあるはずだ。その情報だけを頼りに、ココレットは生まれてから一度も歩いたことのない、舗装もされていない道を歩く。
ココレットの出で立ちは動きやすい軽装だが、それでもF地区を歩くには場違いな素材で作られた服だということは一目瞭然だった。路地で座り込む物乞いの人々にとって、ココレットは格好の獲物でしかないが、本人はそんな視線にも気付かずに、ハルヒも入り込まないような町の奥深くへと踏み込んでいく。
「えっと、ここを曲がって……あれ?」
店主に聞いた話では、この先にナツキの家があるはずだが、ココレットの目の前には高い塀がそびえ立つ行き止まりになっていた。周囲にはゴミ袋が積み上がっているだけで、家らしきものは見当たらない。道を間違えたのだと判断したココレットは引き返そうとして、ビクリと肩を震わせる。振り返ったそこには、数人の物乞いたちの姿があった。
「な、なんですか……?」
ココレットの問いかけには答えず、物乞いたちはじりじりと近づいてくる。怖くなったココレットは一歩下がる。その足が触れたゴミ袋がガサリと音を鳴らす。本当の恐怖を感じたときは悲鳴も上げることができない。ココレットはいつか読んだ本の、そんな一文を思い出していた。
パシャ!その音と同時に、暗い路地裏が光に照らされる。カメラのフラッシュだ。物乞いたちは驚いてその場から逃げ出していった。ココレットはホッと胸を撫で下ろす。
(でも、いまのフラッシュ……どこから……?)
「お嬢さん。踏んでるんですけどね」
「キャーッ!」
声はココレットの足元からした。口から心臓が飛び出るほど驚いたココレットは悲鳴をあげて腰を抜かす。その視線の先、ゴミ袋の山がひとりでに動き出し、そこに埋まっていた男が姿を見せた。ゴミの山から生まれた男を、ココレットは真っ青になって見ていた。
「あー、痛かった」
ココレットに踏まれた脛を撫で、男―――ハインリヒは頭をボリボリと掻く。そこから飛び散るフケに、ココレットは目を丸くした。彼女の15年の人生の中でこれほど不潔な人間を見るのは初めてのことだった。
「あんたみたいないいとこのお嬢さんがこんなとこ来ちゃだめだろ」
見るからに何不自由なく育てられた上流階級のココレットは、飢えた人間の格好の餌食にしかならない。ハインリヒはそう言って立ち上がった。
「あ、あの、あ、危ないところを、ありがとうございました」
「いえいえ。じゃあ、俺はこれで」
「あのっ」
シャツの胸ポケットから、ヨレヨレになった煙草を取り出したハインリヒを、ココレットが呼び止める。
「少しお尋ねしたいのですが―――」
店主に教えられた場所とはまったく違う場所に、ココレットが探していたナツキの家はあった。
ハインリヒに案内されてやってきた家の前で、まずココレットの目に入ったのは壁にあるこの家の住人に向けた中傷や落書きだ。窓ガラスは割られて、室内にはゴミが散乱していた。
お邪魔しますと言って、屋内に入ったココレットは、埃と砂を被った家具類を見回す。ひとの気配は感じられない。やっと探し当てた家の中は、何年も使われていないかのように寂れていた。
(いない……)
ここに来ればハルヒに会えるかもしれないと思っていた。それは安易な考えだったとココレットは意気消沈した。
「なんの用事か知らないけど、早めに終わらせて出たほうがいい」
落ち込むココレットにハインリヒが言った。
「ひとが死んだ場所になんて、記者でもあんまり長居したくねえもんなんだよ」
ここではウララ・シノノメという女性が死んでいる。彼女は【トライデント】の関係者だったという、軍が流した嘘か本当なのかわからないような情報は、ハインリヒの耳にも入ってきていた。
そのあと、アキが死にそうになって戻ってきたと思ったら、レーベル社まで【トライデント】の協力者という汚名を着せられて、ハインリヒはいまもこうして逃げ隠れる毎日を送っている。
(いったい何がどうなってんのやら……)
「それに、こんなとこでウロウロしてたら、お嬢さんも【トライデント】だって疑われるぞ」
「私が?」
ココレットは大きな目を丸くして、その顔に笑みを浮かべた。
「いいですね。【トライデント】」
「はぁ?」
「私もあんなふうに強くなりたいです」
「……あんたなに言ってんだ。もう出るぞ」
ハインリヒに急かされたココレットは、机の上に伏せられた写真立てを起こす。そこには、家族4人で撮った写真が飾られていた。その中に幼いナツキの姿とハルヒの姿を確認し、ココレットは写真立てごと鞄に入れると、ハインリヒに続いて家を出た。
□◼︎□◼︎□◼︎
フィヨドル陥落。
連日、テレビもラジオも新聞も、そのニュースを報道し続けた。新聞の一面にはフィヨドル城に咲いた毒々しいまでの花の写真が形成され、見出しには神殺しと大きく書かれていた。
白く清潔なカバーが掛けられたテーブルに新聞を置いたアキは、すでに冷め始めたコーヒーを一口飲む。馴染みの店が使う豆より幾分か苦い味が口いっぱいに広がり、その刺激で頭はスッキリとした気がした。
早朝のラウンジには、まだだれの姿もない。と言っても、ここを使用できるのはアキたちとコードくらいのようで、ほかの研究員や兵士がここで食事をしているところは見たことがなかった。
スタフィルス軍に追われているアキたちは実質、白獅子のアメストリアに保護された形になった。アメストリアはナツキを捜索する代わりにアキの協力を望んで、彼はそれを承諾した。
アメストリアはアキたち3人の部屋を、研究施設がある離宮に用意した。ナツキの情報が入ればすぐに報せる。そう言った彼女からは一週間音沙汰がない。
「早いな」
そう言って姿を見せたのはカゲトラだった。彼がアキの向かいに腰掛けると、すぐにウェイターがやってくる。カゲトラは水だけを頼み、アキが置いた新聞に視線を落とした。
「まさか、こんな短期間で国が落ちるとはな……」
アキは無言で頷くが、スタフィルス軍がそうしようと思えば、不可能でないことは知っていた。バルテゴ国軍の総力を振り絞っても、黒獅子にはかすり傷ひとつつけられなかった。そして───、
「ハルヒは?」
水を飲みながらカゲトラが聞くと、朝まで胸に抱いていたら教えてあげられるんだけどと、アキはそう答えた。
「……おまえのそれは本気なのか?」
「もちろん」
「なぜハルヒなんだ」
アキの容姿はスタフィルス人にはない涼しげな魅力があり、カゲトラの目からも女性に困っているようには見えなかった。現に、レイシャはアキに惚れていたのだろう。そうでなければ、軍に捕まるかもしれない身でありながら、アキを探しになんて行くわけがない。恋愛感情なんてと鼻で笑うやつに言いたいのは、恋愛感情が時に命取りになることもあるということだ。
「一目惚れ」
「俺は真面目に聞いてるんだ。あれはF地区生まれの薄汚い小娘だぞ」
「ハルヒを守ろうとしてるのはわかるけど、その言い方は酷いよ」
「……あれはおまえの思い通りにはならんぞ」
「人聞きが悪いな。思い通りにしようなんて思ってないよ」
そう言ったアキが冷たくなったコーヒーを飲もうとすると、バンッとテーブルが震えた。カゲトラが両手で叩いたからだ。もう少しカップの中身が残っていたなら、きっと白いテーブルクロスはシミになってしまっていただろう。
「びっくりした」
「あれを女として見るな」
「僕には女の子にしか見えないよ」
「ハルヒの───!」
カゲトラはそこで言葉を止めた。理由はハルヒがあくびをしながらラウンジへ入ってきたからだ。
「おはよ。ハルヒ」
「はよ……」
掠れた声で応えたハルヒに覇気はなく、寝不足らしい目は赤い。それも無理はなく、ナツキが姿を消してもう二週間近くが経っていた。
レイジのそばにいることはわかっているものの、そのレイジの消息がブロッケンビル以来まったくわからない。せめて無事であることがわかればいいが、協力すると言ったアメストリアからもなんの音沙汰もない。いまはまだ我慢しているハルヒが爆発するのも時間の問題に思えた。
食事は何にするかと聞きにきたウェイターに首を振り、ハルヒは窓の外に視線をやってため息をつく。
「ハルヒ。何か食べろ」
「いらねえ」
一日中この離宮から出ることもないため、ハルヒには食欲がなかった。もとから余分な肉のないハルヒは、少し痩せてげっそりして見えた。
「昨日の夜も食べなかっただろう」
「欲しくねえんだよ」
ハルヒはそう言うとより深いため息をついて、ラウンジにあるテレビの電源を入れた。数秒間の砂嵐のあと、映像は徐々に鮮明になっていく。それはフィヨドル国内を映した映像だった。
おそらく戦闘があった城下町だろう。そこを歩くスタフィルス兵の姿が見える。あちこちには枯葉が散らばって、少しの風に吹かれてカサカサと音を立てて飛んでいく。道端に積まれているものが死体の山だとハルヒが気づいたとき、映像は急遽切り替わった。
速報ですと、スタジオに切り替わった映像の中で、何事もなかったかのようにアナウンサーが言った。パッと、アナウンサーの横にココレットの顔写真が映し出されて、ハルヒは電源を切ろうとした手を止めた。
『行方がわからなくなっているココレット様について、軍ではその安否と共に、行方を捜索していましたところ―――』
ハルヒは眉をしかめた。ココレットの顔は忘れていない。ブロッケンビルで人質にした彼女の肩の震えは、同じように緊張していたハルヒに直に伝わった。あのとき、ココレットはナツキのことを知っている様子だった。
『レーベル社の代表取締役であるハインリヒ・ベルモンドに誘拐されたことが判明しました』
ゴブッと、ハルヒの背後でアキがコーヒーの最後の一口を吹きかける。ハルヒも目を丸くしていた。
『レーベル社はテロ組織【トライデント】との繋がりも囁かれており、軍ではハインリヒ・ベルモンドを未成年者誘拐の容疑者として捜索しています』
ココレット隣に映し出されたハインリヒの顔写真で、アキとハルヒはそれが本人だと確認する。
「なんであの男がお嬢様を誘拐なんてするんだよ……」
「さあ……」
アキも首をひねった。ハインリヒとココレットに繋がりはないはずだった。いや、あったのか。ハインリヒも記者として将軍の娘にインタビューしたことくらいあったのかもしれないが、それはアキの知らないことだった。
「だれだ?」
ハインリヒが何者か知らないカゲトラが首をひねる。
「リュケイオン将軍の妹と、こいつの上司だよ。ブロッケンビルでおまえとはぐれたあと世話になった」
「そうか……」
ハルヒの行動範囲は知っていたつもりだったが、ここ最近で彼女の世界は知らぬ間に広がりを見せていた。そのことでカゲトラは胸に複雑なものを感じた。
「どうすんだよ」
「どうするって?」
「放っとくのか?」
「あのひとは大丈夫だよ」
このニュースが真実であれ、虚実であれ。アキの知っているハインリヒは、どんな状況下に置いてもうまく立ち回る男だった。現にテロリストとの関係を疑われてもいままで逃げおおせている。
「薄情なやつだな」
ハルヒはそう返した。ハインリヒを信用してのアキの言葉は、逆にハルヒに軽薄感を与えたようだった。
「けしかけるな。ハルヒ」
「だけど、こいつ前にも……」
「ナツキはどうする」
カゲトラに言われ、ハルヒは何も言えなくなる。
物事には優先順位がある。いまのハルヒにとって、それはナツキの救出に他ならない。ナツキを探すためには広い情報網を持ったアメストリアの協力が必要で、アキはそのために欠かせない存在だ。彼をけしかけてこの場から出て行かせようとするのは矛盾でしかなかった。
□◼︎□◼︎□◼︎
ハルヒとカゲトラがアメストリアに呼ばれたのは、それから数時間後だった。期待通り、ナツキの居場所がわかったと言われたハルヒは、まだ弟を助けたわけではないのに、数日ぶりの笑顔をカゲトラに見せた。
ナツキはB地区の軍施設内に入っていく姿を目撃されたらしい。詳しい場所を聞いたハルヒは、もう一分一秒が惜しいという様子だ。
「クサナギを呼んでくる」
「待て。アキ・クサナギがここを離れることは許さん」
すぐにアキがいる研究施設へ向かおうとしたハルヒは、アメストリアの言葉に足を止めた。
「……なんだと?」
「陛下のお言葉の通りだ。やつはここに残る。弟の救出にはおまえたちだけで行け」
アメストリアに聞き返したハルヒに対し、代わりに答えたのはカガリヤだった。納得いかない顔をしているハルヒに、アメストリアはフッと笑う。
「弟の居場所がわかれば、やつを手放すと約束した覚えはないがな」
確かにそんな約束はしていない。だが、これではナツキを助けるために、アキを生贄にしたようなものだ。連日、検査と言う名のもとに研究施設に呼ばれているアキの腕が注射針の痕だらけになっていることを知らないハルヒではなかった。
「……もう十分調べただろ」
「十分かどうかはそなたが決めることではない」
自分から納得した上でのことだからか、アキは文句ひとつ言わず平気そうにしているが、ハルヒは違っていた。何をそんなに調べることがあるのか、アキの検査はいつまでたっても終わる気配がない。ナツキが見つかればそこで終わると思っていたが、そうでもない。ハルヒの性格上、アキを置き去りにはできなかった。
「あいつは連れていく」
「それもそなたが決めることではない」
「ンだと……!?」
アメストリアに対して明らかな暴言を吐こうとしたハルヒに気づき、カゲトラがその肩を押さえた。堪えろとその顔が言っていた。
「クサナギとナツキと、選べるのはどちらかだ」
「……!」
「おまえにとって本当に大事なのは会ったばかりの男か、それとも血の繋がった弟か」
ここでアメストリアに殴りかかればどちらも失うことになる。少し前なら、ハルヒが選ぶほうは決まっていたはずだったが、彼女は迷うそぶりを見せる。まさかアキを選ぶつもりかと、カゲトラはジワリとした焦りを覚えた。
ハルヒを女として見るアキは、遅かれ早かれ必ず、カゲトラが娘のように思っている大切な彼女を傷つける。あの適合者と引き離せるのはいましかない。ハルヒを守ることができるのなら、その手段が姑息だと言われてもなんでも構わなかった。
「いいか、ハルヒ。ナツキは強くない」
ナツキは生まれつき病弱で、少しの刺激で喘息の発作を起こす。成長するにつれてマシになってきたとはいえ、油断はできない。
「………」
「レイジに連れ去られて、考えたくはないが、どんな扱いを受けているかわからん。早く助けてやらなければ。そうだろう?」
「……わかった。でも、あいつにいまから行ってくるって、声をかけるくらいはいいだろ?」
アメストリアは了承した。だが、投与された薬で眠っていたアキに、ハルヒが別れを告げることはできなかった。
□◼︎□◼︎□◼︎
アメストリアの計らいで、ハルヒとカゲトラには民間業者の配送車にカモフラージュした車が与えられ、偽造通行証も渡された。通行証があればゲートを超えることは容易い。たいしたチェックもなく目的の軍施設近くまでやってくると、ハルヒは助手席でため息をついた。
「どうした」
「いや……、別に」
なんでもないとハルヒは言うが、まだアキのことが気になっていることは一目瞭然だ。結局、ハルヒはナツキを選びきれていない状態で、ここまでやってきた。
それでも切り替えなければならないということはわかっている。これから乗り込むのは敵の本拠地だ。喝を入れるため、ハルヒは自分の両頬をパンッと叩いた。
与えられたこの配送車は、この施設のクリーニングを主に扱っている業者のものだ。荷台にはクリーニング業車の制服までちゃんと用意されている。業者を装えば内部に入り込むのは簡単だ。あとはナツキを見つけて脱出する。
「おそらくこの辺りが怪しい」
カゲトラは広げた地図をハルヒに見せる。アメストリアは軍施設内の地図まで用意していた。機密事項である施設内の情報をこうも簡単に手に入れているところから考えても、レイジが言っていた、黒獅子軍の中には白獅子に加担する存在があるという情報はおそらく正しいと言えた。
「そろそろ着替えるか」
カゲトラに言われ、そうだなとハルヒは荷台に移動しようとして、車のサイドミラーにチラリと映った金髪に勢いよく振り返った。
「どうした?」
「……いまあいつが、」
「まさかクサナギか?」
ハルヒを追いかけてきたのかとカゲトラは顔をしかめた。
「違う。クサナギじゃなくて、あいつだ。クサナギの上司に誘拐された……」
「ココレット・リュケイオンか?」
どこにいると、カゲトラは周囲を見回すが、それらしき姿はどこにも見当たらない。見間違えたか、他人の空似か。だが、このスタフィルスにはあれほど見事な金髪は少ない。ハルヒの知っている限りでは、ココレットとその兄であるルシウス。そしてアメストリアだけだ。
「確か後ろを通ったはず……、ッぎゃあッ!」
ハルヒはそう言って、荷台から車外に出ようとして悲鳴をあげる。すぐさまカゲトラがその身体を運転席へ引き戻し、自分が荷台に乗り込んだ。
「どうも」
そこには両手を挙げたアキがいた。
「……な、」
なんでここにいると言いたかったが、それ以上は声にならなかった。また荷台にやってきたハルヒが代わりにそれを聞く。
「ナツキくんの居場所がわかったって聞いたから」
「でもあの女は……」
アメストリアにはアキを手放すつもりがなかった。彼女が承諾したのでないことはわかりきっていた。
「ナツキくんの居場所がわかったなら、僕の協力も終わりだよ。ずっと協力するなんて約束した覚えはないしね」
果たして、その言い分がアメストリアに通じるかどうかは別として、ハルヒの横顔に確かな喜びを見たカゲトラの心中は複雑だった。ふたりを引き離すことはもう無理なのかもしれないとさえ思えた。
「それで作戦は?」
「クリーニング業車に変装して施設内に入る」
「いいね。強行突破じゃないところに成長を感じるよ」
「遊びじゃないんだぞ」
軽い調子でハルヒに親指を立てるアキに、カゲトラが苦言を漏らす。
「忘れているなら思い出させてやるが、俺たちは【トライデント】だ」
「僕は適合者」
テロリストなんだと繰り返しても、アキは動じない。確かに、適合者であるアキにはテロリスト数人分、下手すれば数十人いても勝ち目がない。それも武器を持っていての話だった。
「おまえに変装用の服はないぞ」
荷台にはカゲトラとハルヒのサイズの服しか用意されていない。アキが施設内に正面から入るのは不可能だった。
「じゃあ別行動で行こう。集合場所はそうだな……ここはどう?」
アキは広げっぱなしの地図を指差す。そこは施設内の3階にある更衣室だった。どうやってそこへ入り込むのか、それはアキに聞くまでもないことだということを、もうハルヒもカゲトラも理解していた。
□◼︎□◼︎□◼︎
クリーニング業者に化ければ、施設内に入るのは嘘のように簡単だった。
わかったことは、服をひとつ変えただけで簡単にひとは騙せると言うことだ。裁判所へカゲトラを助けに行ったときに、アキが用意したワンピースの意味もいまならわかる。あのときは嫌でしょうがなかったが、身に付けるものは時に自分と味方を守る盾になる。
洗濯カゴをエレベーターまで押し、中に入るとカゲトラが扉を閉める。気合いを入れるためにハルヒは目深に帽子をかぶり直した。
『ハルヒは本当に手に負えない』
ハルヒには伝えなかったが、レイジがそんな苦言を漏らしたことがある。いつだったか、カゲトラの店から武器を盗み出して、単身軍施設に乗り込もうとしたときだったと思う。
あの頃のハルヒを一言で表すなら、爆弾だった。ボタンひとつでいつ爆発するかわからない。それがどのボタンなのかもわからない。頭で考えるよりも先に手が出る。母親が死んでからと言うもの、その性格は輪をかけて凶暴になった。
ハルヒの父親も母親も温厚な性格だった。ナツキは彼らに似て穏やかに成長した。本当に血の繋がった姉弟なのかと疑ったこともあるほど、ふたりの性格は違っていた。
カゲトラが、ハルヒに変化を感じたのは最近だ。カゲトラが、死んだウララが、ナツキがどんなに言っても危険を顧みなかったハルヒが変わったのは、ひとの言葉に耳を貸すようになったのは、アキが現れてからだ。
エレベーターが上昇していく。ハルヒは黙ったまま、階層を移動するたびに点滅箇所が変わる階層の数字を見つめていた。
「……クサナギが好きか?」
ブッとハルヒは吹き出した。そして怪訝な顔をカゲトラに向ける。
「なに言ってんだよ」
「聞いておきたくてな」
「……別に、嫌いじゃねえけど」
「そういう意味で聞いてるんじゃない」
エレベーターが3階に到着し、ポンっと軽い音が鳴ると扉が開いていく。
「……そんなこといまはどうでもいいだろ」
ナツキを助け出すのが先だと、ハルヒはそう言ってエレベーターを出ていく。カゲトラはそうだなと消えるような声で同意し、そのあとに続いた。
ふたりが3階の更衣室に入るとそこには兵士の姿があり、ハルヒはギョッとして足を止めた。その背中が後ろにいたカゲトラとぶつかる。
「問題はなかったようだな」
カゲトラが兵士にそう言って、ハルヒは初めてその兵士がアキだと気付いた。
「ど、どうしたんだよその服……」
「サイズの合うものがあったから着てみたんだ。これなら施設内を自由に歩けるでしょ」
アキはそう言ってくるりと回ってみせる。ハルヒはそれに対し、敵かと思って殴りかかりそうだと苦笑した。ハルヒの表情の中に恐怖はない。母親を強姦し、殺害した兵士と同じ服を着た男がそこにいても、それがアキだとわかっているからだ。
「手分けしようか。ここ広いし」
この施設は5階建ての大きな建物だが、1階と2階は駐車場だったため、スタートはこの3階からとなる。
「わかった。俺とハルヒはこの階から探す」
「なら僕は最上階から探すよ。集合場所は車でいい?」
「ああ。そうだな」
「OK。じゃあ気をつけてって言いたいんだけど、ナツキくんの特徴を教えてもらえるかな。ハルヒと似てる?」
「似てない。ナツキは父親似で、栗色の巻き毛が特徴だ。15歳で瞳の色だけはハルヒと同じだ」
アキはわかったと言って窓から外へ出て行った。勢いよく屋上まで飛び上がったアキを見送り、ハルヒは行こうとカゲトラに声をかけた。
□◼︎□◼︎□◼︎
洗濯カゴを押しながら施設内を歩き回ったが、3階ではナツキの姿を見つけることはできなかった。せめて、レイジが何をしているのかがわかればその行動にも予想がつくのだろうが、そう簡単に尻尾は掴ませてくれない。
「上に行くか」
3階にはナツキはいない。ハルヒがエレベーターへ顔を向けると、白衣の男が前から歩いてくるのが見えた。それがドクター・タオだと気付いたカゲトラは、ハルヒの腕を掴んで手近な部屋に身を隠した。
「なんだよっ」
「静かに」
カゲトラとハルヒが息を潜めていると、タオは通路に残された洗濯カゴに気づく。
「ヨカッタ〜。汚れちゃったカラこれを洗濯しといてもらオウ」
タオはカゴの中に脱ぎ捨てた白衣を入れると、鼻歌を歌いながらその場を立ち去った。カゲトラはホッと胸をなでおろす。いくら変装していると言っても、知り合いの目までは誤魔化せない。それにタオは昔の同僚でもあった。
タオがいなくなるとカゲトラとハルヒは部屋を出た。見ると、カゴの中にはどす黒い汚れが染み付いたタオの白衣が入っていた。これが何の汚れなのか詳しくは話し合いたくない気持ちは同じで、カゲトラはほかの洗濯物の下に白衣を押し込む。
「ちょっとあなたたち」
聞き覚えのある声がかかったのはそのときだった。カゲトラは顔を上げることができなかったが、チグサは構わずヒールを響かせて一歩一歩近づいてくる。
「ドクター・タオを知らない?似合わない髭を生やした小太りの男なんだけど」
ハルヒは無言のまま首を振る。チグサは舌打ちをして、ずっと洗濯カゴの中を掻き回しているカゲトラに目をやった。
「あなた、いい体格をしているのね」
「………」
「あなたなら実験も成功しそう」
その仕事に飽きたら研究機関に遊びにきてねとカゲトラに言い残し、チグサはタバコに火をつけるとその場を立ち去った。
「……あいつら、知ってるやつか?」
「ああ……昔、少しな」
タオとチグサがいると言うことは、ここには実験施設がある。そんな場所でナツキの姿は目撃された。レイジがそこまで冷徹だとは考えたくないが、あの男のせいで何人もの仲間が死んだことも事実だ。頭をよぎった最悪の予感にカゲトラは青ざめていた。
「トラ?」
「いや……、なんでもない。ナツキを探そう」
カゲトラはハルヒの背中を押してエレベーター内へ入った。上昇する箱に乗って上階へ行くと、そこにはアキが立っていた。すんっとハルヒが鼻を鳴らす。フロアに独特な臭いが漂っていたからだ。
「ナツキくんはいなかったよ」
「え?」
「ここにも5階にもいなかった。目撃情報が間違っていたのか、すでに別の場所へ移動したのかのどちらかだと思う」
「でも……」
まだ自分の目で確かめたわけじゃない。すぐ先に見えている白い扉の向こうへ行こうとするハルヒをアキは身体で止めた。
「行っちゃだめ」
「……なんでだよ。どけよ」
アキは首を振ってカゲトラを見た。何も言わなくてもアキの目はハルヒを止めろと言っていた。
「ハルヒ。脱出するぞ」
そう判断したのは、アキのことは信用できないとしても、カゲトラ自身がその先に嫌な予感を覚えたからだ。
「トラ……!」
「ナツキくんはいなかったよ」
「なんでわかるんだよ!おまえはナツキに会ったこともねえだろ!」
ハルヒはアキの身体を押しのけて扉の先へ入る。そして、アキが見せることを拒んでいた理由のものを目にして、ヒュッと喉を鳴らした。
扉の向こうにはガラス張りの部屋がいくつかあり、そこにはF地区の実験施設で見たものと似通った異形の死体が積み上げられていた。
「ナツ、キ……」
「ハルヒ」
思わずよろめいたハルヒの肩をアキが受け止める。
ガラス張りの部屋の中には胸が異様に膨れ上がったもの。肩から何かが飛び出しているもの。頭の半分が見当たらないものもいた。たとえここにナツキがいたってわからない。判別できない。ハルヒにそう思わせるほどその光景は悲惨だった。
「ナツキくんはここにはいないから、外に出よう」
ハルヒを落ち着かせようと、アキの声色はいつも以上に静かだった
「行こう」
アキに促されると、ハルヒはようやく頷いた。
アキはハルヒの肩を押してエレベーターへ戻る前に、一度だけガラス張りの部屋を振り返る。死体の中で何かが動いた気がしたが、きっと気のせいだろうと自分自身に言い聞かせた。
□◼︎□◼︎□◼︎
3人はそれぞれが侵入したルートで軍施設から脱出した。
車へたどり着く前にハルヒがふらつきだしたので、公園にあるベンチで少し休むことにした。ちょうど木陰になっているベンチにハルヒを座らせて、アキはその前に膝を折る。
「大丈夫?」
「……あぁ」
そうは言うものの、ハルヒの顔色は青白い。
「車を回してくるから、おまえはここで待ってろ」
カゲトラはそう言って、ハルヒの帽子をポンと叩くと、少し先に停めてある車へ向かった。
「ハルヒ。あそこで水を買ってくるよ」
アキはそこに見えている自販機を指差した。
「すぐ戻るから。いい?」
ハルヒが頷くと、アキは立ち上がって自販機へ歩いていく。その後ろ姿を見ながらハルヒはため息をついた。
ナツキは大丈夫だ。ナツキはあんなところにいなかった。レイジはナツキを自分の息子のように可愛がっていた。あんな目に遭わせるはずがない。
ハルヒは自分に言い聞かせるように繰り返す。だが不安は拭えなかった。だって、レイジはハルヒのことも本当の娘のように可愛がってくれた。たくさんのことを教えてくれたのに、カゲトラを、ハルヒを裏切った。
「………」
ハルヒは自販機にコインを入れるアキを見る。なんでアキは自分を助けてくれるんだろう。アキがそばにいることはこの上なく心強かったが、ハルヒはその理由がわからなかった。ハルヒについてくることでアキはその生活も仕事も失ったのに、少しもそれを惜しむ顔を見せない。
水を購入したアキはそれを手に取り、ハルヒに手を振ってから、自分に近づくひとりの男に気づいた。
「クサナギ先輩」
久しぶりにそう呼ばれて、アキはそこに立っている男が、レーベル社で同僚だったイスズであることに気づいた。
「バレシア君……?」
「ふふ。どうしたんですか?そんな格好をして」
軍服を着ているアキの姿を見たイスズは可笑しそうに笑う。その目の下は黒く、体調が悪そうなのが印象的だった。
「……無事、だったんだね」
生きている可能性が高いとは思っていたが、またこうして会うことになるとは予想外で、アキは珍しく動揺していた。
「ええ。僕は」
そのあとにレイシャの話が続くであろうことを覚悟したが、イスズはそこで言葉を切って、チラリとハルヒを見る。
「さっき、あのひとと話してましたよね?」
「………」
アキは無言になる。少し前から見られていたことに気付いたからだ。イスズはすぐに声をかけてこなかった。自分とハルヒはイスズに観察されていた。
「恋人ですか?」
「……まだ違うかな」
「じゃあ、いずれはそうなるってことですね。先輩にそんなひとがいるなんて知らなかったですよ」
イスズはレイシャが好きだった。それはだれの目にも明らかで、アキもそれを知っていた。
「……バレシアくん。ミナシ───、」
「ミナシロさんのことなんですが、報告してもいいですか?」
イスズのそれは、まるで仕事をしているかのような口調だった。
「彼女、ご家族がいらっしゃらなかったので、遺体は教会のほうへ引き取ってもらいました」
「……そう。色々、悪い、ね」
「え?」
「色々と、大変だったでしょ……」
「ええ。でも、同僚ですから」
どこか台詞めいたイスズの言葉にアキは言いようのない気持ち悪さを感じた。何かがおかしいことはわかるのに、それがなんなのかわからない。とにかくイスズから離れたい。ハルヒを連れていますぐにここを離れるべきだ。本能が警告音を鳴らす。
「あんなひとが先輩の好みだったんですね」
アキの視線を追ったイスズがハルヒを見てそう言った。
「ミナシロさんとは全然違う。これじゃ、彼女が相手にもされないわけですよね」
アキはハルヒのもとへ走るために左足を退いた。頭に危険を警告するアラームが鳴り響く。目の前にいるのはイスズで間違いがないはずなのに、毎日のように顔を合わせていた後輩とは違う。まるで別人だ。なぜなら、レイシャのことが好きだったイスズは、アキに対して笑顔なんて見せたことなんかなかったのだから。
「ハル―――!」
「―――あなたがミナシロさんを殺したんだ」
イスズがそう言うと、彼の手首から飛び出したものがアキの腹に突き刺さった。
「えっ……」
アキがガクリと膝を折り、ハルヒが声を上げる。
アキの手から落ちたペットボトルが砂の上に転がる。自販機の中では冷えていたペットボトルには、握っていたアキの体温と外気温で水滴がついていて、渇いた砂はそれに吸い寄せられて付着する。濡れて色濃くなった砂は、まるで餌に群がる蟻のように見えた。そして、そのペットボトルの周りにさらにポタポタと雫のように落ちてくるそれは、赤い色をしていた。
「クサナギッ!」
ベンチから立ち上がったハルヒはアキのもとへ走るが、その前にイスズが手を振ると、アキの身体がハルヒめがけて飛んでくる。
「!?」
アキの身体を受け止めきれず、激突の衝撃でハルヒは彼共々倒れ込んだ。
「って……!クソ!クサナギ!」
自分の上にのしかかっていたアキの身体をハルヒが押しのけた瞬間、ガフッとアキは血を吐き出した。目の前に飛び散る鮮血にハルヒは言葉を失った。
(刺された……!?)
アキの軍服にはどんどん血が滲んでいく。アキの傷口を確かめようとして、ハルヒは砂を踏みしめる音に顔を向ける。そして、そこに立っていたイスズの姿に目を見開いた。
イスズの手首からは植物の蔓のようなものが生えていて、それは意志を持っているように蠢いていた。ハルヒの脳裏に、テレビ中継で見たフィヨドル城下町の映像がよみがえる。
イスズの手首の血管は膨張していて、ドクドクと脈打つ。その先で緑色の触手が揺らめく。
「オェ……ッ!」
ビシャビシャと嘔吐したアキを見て、イスズはクスクスと笑う。その顔は愉悦に歪んでいた。
「苦しいですか?苦しいですよね?この触手には毒があるんですよ。でもおかしいな。練習で刺したやつらはすぐ死んだのに、先輩はなかなか死なないんですね」
どうしてかなと、イスズはあどけない表情で首をひねる。その様子を視界に入れたまま、アキは震える手でハルヒの手を掴む。
「逃げ、て……!」
「……!」
たぶん、すぐに死なないのは自分が適合者だからだ。アキにはそれがわかっていた。だが、ハルヒはそうじゃない。ここから逃がさないとイスズに殺される。
「はや……く……!」
目の前が霞んで、見えなくなっていく。だんだんとアキの表情は虚ろになっていく。
「先輩、まだ起きててくださいよ。いまからミナシロさんみたいに、その女の首を刎ねとばして見せますから!」
イスズの触手がハルヒに襲いかかり、アキから放たれた風がそれを切り裂いた。あっとイスズは声を上げた。そして、切断面からボタボタと流れ出る緑色の体液に汚いと顔を歪めた。
「うぐ……ッ」
刺されたような胸の痛みにアキは息を詰め、首を振る。
「バレ、シアく……!ハルヒは、きみを……助け……っ」
あのとき、ハルヒがトラックで突っ込んで来なければ、イスズはラッシュの風に殺されていた。それを伝えてイスズを止めたいアキだが、毒が心臓の鼓動の分だけ身体を駆け巡り、舌まで痺れ出してどうにもならない。そうこうしているうちに、イスズの反対の手首から新たな触手が生えた。もう力を使う余力がないアキはハルヒを抱き締め、自分の肩で触手を受け止めた。
突き刺さった触手は脈動したのを目にしたハルヒは、それを掴むと力任せにアキの肩から引き抜いた。紫色の液体が飛び散り、それは砂の上でジュウジュウと音を立てた。
「邪魔を───」
「そこまでよ」
イスズを止めたその声に、ハルヒはギュッとアキを抱き締める。
「殺さないと約束したでしょう」
そう言って、イスズの肩に手を置いた白衣の人物は、さっき軍施設内ですれ違った女性だった。
「悪い子ね」
霞んだ視界の中でなんとかチグサの姿を認識したあと、アキはガクリと意識を失う。アキの全体重を受け止めたハルヒは、彼を強く抱き締めてチグサを睨み付けた。
□◼︎□◼︎□◼︎
一方、車を取りに停車した場所へ戻ろうとしたカゲトラは、そこに軍の姿があることに気づいて慌てて身を隠した。停車した車の周りには数台の軍用車が停まっていて、数人の兵士がトラックを調べている。
(戻れないか……)
あの様子ではしばらく離れてくれそうもない。車は諦めてハルヒのところに戻るべきだ・そう判断したカゲトラは来た道を戻ったが、公園にハルヒたちの姿はなかった。
代わりに軍が厳重な包囲網を敷いていて、ブルーシートをかけられた公園内を見ることもできなかった。自分が離れている間に何かが起こったことは間違いないが、何が起こったのかカゲトラにはわからない。
(ハルヒ……)
ハルヒにはアキがついている。カゲトラにとってアキはなるだけハルヒに近づけたくはない男ではあるが、彼は必ずハルヒを守ろうとするはずだった。
ブルーシートに近づこうとしたカゲトラは、そこにタオの姿があることに気づいて慌てて身を隠した。裁判所から逃亡したカゲトラは指名手配されている。街を歩くのも気をつけなければならない上に、チグサとタオはかつての同僚だ。さっきは運が良かったが、変装していても見破られる可能性が高かった。
「クソ……」
ここに長居するのは危険だ。そう判断したカゲトラは裏通りへ入った。もしかしたら、ハルヒたちは軍から逃げたのかもしれない。それなら隠れる場所はハルヒの家か、もしくはカゲトラの自宅兼店、それからアキの自宅アパートだと考えられるが、どれも【トライデント】のアジトとして目をつけられているはずだ。だったらどこへ逃げるか。考えられる場所はアメストリアがいる王宮だ。あそこなら軍の手は及ばない。
「……戻るしかないか」
裏道ばかりを通って王宮まで帰るのは骨が折れそうだが、いまのところそれしか思い当たる場所がない。決心したカゲトラは踵を返した。そして暗闇の中に気配を感じて立ち止まる。
「……出てこい」
カゲトラがそう言うと、ゴミ箱の裏から男が姿を見せる。暗すぎて顔は見えないが、それはヒョロリとした体格の男だった。
「そこで何をしている」
カゲトラの声には凄みがあった。
「待ってくれよ。隠れていたのはこっちが先だぜ?あんたが後から来たんだ」
「隠れていただと?」
「そうだよ。俺は軍に追われてるからな。隠れなきゃやばい」
この男は仲間だろうか?カゲトラはそう推測した。【トライデント】なら軍から逃げている理由は頷ける。
「【トライデント】か?」
「はあ?勘弁してくれよ。テロリストに疑われんのはもう腹一杯なんだ。俺はただの優良な一般市民だってのに」
そう言って、男は一歩前に踏み出す。ようやく肉眼で捉えることのできた男の顔を見たカゲトラは、それがだれなのかを知った。
「おまえ、ハインリヒ・ベルモンドか?」
ニュースで見たばかりの顔だ。忘れるには早すぎる。カゲトラは、ハインリヒに隠れて金髪の少女がいることにも気づく。少女は誘拐されたと報道されていたココレットに間違いなかった。
「うわー。ココレットお嬢様やばいって。やっぱり有名人になってるって……ん?んんん?おい、あんた!見たことあんぞ、その顔!あんた【トライデント】のカゲトラ・バンダだろ!」
ハインリヒはカゲトラを指差して声を上げる。その声の大きさに、カゲトラは兵士たちを振り返ったが、こちらに気づいた様子はなくホッと胸を撫で下ろした。
「あんたのとこのお嬢ちゃん。なんてったかな。ほら、頭にバンダナ巻いた」
「ハルヒを知ってるのか!」
「そうそう!ハルヒ!」
確かアキがそう言ってたと言うハインリヒの胸ぐらを掴み、カゲトラは唾が飛ぶ距離まで顔を近づけた。
「ハルヒはどこだ!」
「いや、こっちが聞きてえよ!アキはどこだよ!」
「あの、おふたりとも……」
睨み合う男ふたりを見かねたココレットが口を挟んだ。
「少しお声が大きいようです……」
ココレットの言う通りだ。このまま言い合いをしていては軍に気づかれる。
カゲトラは一先ずハインリヒから手を離した。アキの居場所がわからないと言うことは、ハインリヒはハルヒの居所も知らないだろう。
「ハルヒとクサナギの行方なら俺も探しているところだ」
「はー、まじか……」
ハインリヒはボリボリと頭を掻きむしった。
「それでは、……ハルヒ・シノノメ様は、いまどこにいらっしゃるかわからないのですね」
ココレットはしょんぼりと肩を落とす。カゲトラはその様子に怪訝な顔をした。ハインリヒが部下であるアキを探す理由はわかる。だが、ココレットがハルヒを探す理由はカゲトラにはわからなかった。
「ハルヒに何の用だ?」
こんなか細い少女がハルヒに何かできるとは思えなかったが、ココレットはリュケイオン家の人間で、ゴッドバウムの娘であり、あのルシウスの妹でもある。油断はできなかった。
「その……ナツキ様のことでお伝えすることがあって」
ココレットの言葉にカゲトラは息を詰めた。脳裏にさっき軍施設内で見たものがよみがえる。あそこにナツキがいたなんてことは信じたくはなかったが、完全に否定することもできなかった。
「ナツキは生きているのか」
カゲトラが聞くと、ココレットはキョトンとした顔をしたあと、もちろんですと微笑んだ。
□◼︎□◼︎□◼︎
まるで悲鳴のように風が泣いていた。
スタフィルス軍がバルテゴの城壁を崩して国内へなだれ込んできた。これまで一度も止まることのなかった神殿の大風車が砂の重みで動かなくなり、城下町は逃げ惑う人々で溢れた。
アキは母親に連れられて地下道を走った。国を捨てて逃げるためだった。何度も振り返って父親の姿を探したけれど、そこには闇が広がるだけだった。母親の腕の中で小さな妹は怯えて泣いていた。地下道に響き渡る妹の泣き声は不安を増幅させて、永遠にこの道が続くんじゃないかと錯覚させたけれど、地下道にもちゃんと果てはあった。
ようやく地上に出ると同時に、強い風が吹いた。それは後にバルテゴの死の風と呼ばれることになる、風神がその死と共に巻き起こしたものだった。大風車よりも巨大な竜巻は、スタフィルス兵もバルテゴ国民も分け隔てせずに巻き上げた。
それを見ていた母親は、マティウスと、なぜか父親の名を口にした。その頬を流れていった涙がどんな意味を持っていたのかは、いまもわからないままだ。
□◼︎□◼︎□◼︎
「………」
昔の夢を見たのは久しぶりだ。夢自体見るのが久しぶりのように思えた。特にあの日の夢は、心が思い出すことを拒否しているようだった。
匂いのしないシーツの上、アキは寝返りを打とうとして痛みに呻いた。反射的に腹を押さえると包帯の手触りがあり、イスズに刺されたことを思い出してヒュッと喉を鳴らす。
「ハルヒ!」
その瞬間だけは痛みを忘れて身を起こす。ハルヒの姿はどこにもない。その代わりに、嫌という程見覚えのある室内を目にして、アキは言葉を失った。
強化素材で覆われた白い壁、何重にも重ねられた分厚い鉄でできた扉。天井は首が痛くなるほど高く、そこも強化素材で覆われている。
そして部屋に唯一ある鏡は異様に大きく、いつも見えないだれかの視線を感じていた。その鏡に映る自分の姿を確認したアキは、震える手で首に触れる。悪い予感通り、そこには首輪がはめられていた。
「ぁ……」
スタフィルスに来る以前の記憶は曖昧だ。そうカゲトラに話したのは本当のことだった。だが、その記憶は目に映る室内の様子に急速にフラッシュバックしていく。暑くもないのに手のひらがジワリと汗ばむ。
「……っ」
ハルヒを探さなければ。自分にしかできない目的を持つことで、どうにか落ち着こうとしたアキは、鏡がすうっと透明になっていくのに気づいた。アキの姿を映さなくなった鏡は、代わりに部屋の向こう側にいる白衣を着た男の姿を見せる。汗ばんでいたことが嘘のように、全身に襲いかかる悪寒によりアキの身体は震え出していた。
「やあ」
男───ヴィルヒム・ステファンブルグは街中で偶然会った相手にそう言うように、アキに声をかけた。
「随分と久しぶりだ。また会えて嬉しいよ」
「………」
「どうしたんだい?私を探していると、ドクター・ワダツグから聞いていたんだが、違っていたかな?」
言葉を失ったアキに対し、ヴィルヒムは困ったように白髪が混じり始めた眉を下げる。
「それはともかく、すっかり大人になっていて見違えたな。ラティ───、いや、いまはアキ・クサナギと名乗っているんだったね。私もアキと呼んでも?」
目に見えて震えているアキにヴィルヒムは話し続けるが、その内容なんて少しもアキの頭には入ってこなかった。
ヴィルヒム・ステファンブルグ。この男を見つけたら、考えうる限りの残酷な方法で殺す。アキはそう心に決めていた。なのに、実際目の前にしてみたら情けなくも身体は震えるばかりで、身動きひとつできないでいた。
「そうだ。君の妹のことなんだが」
いま思い出したことのようにヴィルヒムはそう言った。そして、アキの反応を楽しむように数秒間待ったあと、首を振った。
「手術後に拒絶反応を起こして、不適合者になってしまってね」
軍の研究施設、ガラス張りの向こうに見た無残な実験体の姿がアキの脳裏によみがえる。
「適合したきみの妹だから私としても期待していたんだが、残念だよ」
バン!と鏡が、正確には強化ガラスが震えた。アキが渾身の力で飛ばした風刃が激突したからだ。だがそこには傷ひとつついてはいなかった。そんなはずはない。全力で狙えば、建物の壁さえ数枚切り刻むことができる。その自信がアキにはあった。
殺すつもりでもう一度ヴィルヒムを狙おうとしたが、腹がズキリと痛んで風は霧散する。腹部に巻かれた包帯には血が滲んでいた。
「ああ、無理をしないほうがいい。フィヨドル神の毒は強力だからね。適合者でなければ5分と保たないんだ。そうだ。フィヨドルでのニュースは見たかい?酷いものだったろう。バルテゴ神の断末魔は死の風と呼ばれたが、フィヨドルのあれは後世になんと呼ばれるようになるんだろうね」
「殺して……やる……!」
ようやく口を開いたアキに、ヴィルヒムは頷いた。そして、やってみろと言わんばかりに両手を広げる。アキの髪が風に吹かれて揺れる。
「セルフィアナは最期まできみを呼んでいたよ」
お兄様と、まだ小さな妹の泣き叫ぶ声がいまも鼓膜に響く。耳を塞いでも頭の中で鳴り響く。痛みさえ感じる妹の泣き声を思い出し、アキの目に溜まった涙がボロボロとこぼれ落ちる。
「そう───バラバラに飛び散るその瞬間までね」
見開いたアキの目がヴィルヒムを捉え、室内に暴風が吹き荒れた。
□◼︎□◼︎□◼︎
嗅いだことのない甘い花の香りでハルヒは目を覚ました。
そこは見知らぬ部屋だった。そこはハルヒの家の4倍はある広さの部屋で、赤と白で統一された室内は豪華な内装だ。眠っていたベッドも柔らかく清潔なシーツが引かれていた。
(ここ、どこだ……)
王宮に帰ってきたのだろうか。内装の様子にそう思いはしたものの、戻った記憶がない。香りの正体はベッド脇に飾られている数少ない砂漠に咲く赤い花だった。
(俺、寝てたのか……?何があったんだっけ……)
とりあえず身体を起こしたハルヒは、そこでようやく自分が何も着ていないことに気づき、ずれ落ちたブランケットで慌てて身体を隠す。
「隠すほどのものか?」
その声にまたハルヒはギョッとなる。だれもいないと思っていたのに、少し離れた場所にあるソファーには、優雅にティーカップを傾けるルシウスの姿があった。
「おまえのような貧弱な身体に興奮するあの男の気がしれんな」
「な、ん……っ」
ハルヒがルシウスの姿を見るのはブロッケンビル以来だが、死んだとは思っていなかった。ここ最近のハルヒはよくテレビを見ていたが、そんな報道はなかったからだ。
ルシウスがなぜここにいるのか。その理由を考えようとしたハルヒは、アキがイスズに刺されたあと、軍に取り囲まれたことを思い出す。車に乗せられるところで抵抗したが、そこでハルヒの記憶は途切れていた。
「クサナギはどこだ!」
ハルヒは引き剥がしたシーツを身体に巻きつけ、何か武器になるものがないか室内を見回す。そして、扉のすぐ横の壁に立てかけられているルシウスの剣に目を留めた。
剣は軍服の一部として形式上携帯が義務付けられているものだが、銃が出回った現在で使う機会は滅多にない。ルシウスにとってはただの飾りだが、ハルヒにとっては唯一見つけた武器だった。
「クサナギはどこだ……」
ルシウスを視界から外さずに移動し、ハルヒは剣へと近づく。
「おまえでは持ち上げることすらできんと思うがな」
ハルヒの狙いなど見ていればわかるが、それを阻止するわけでもなく、ルシウスは可笑しそうに笑った。その態度はハルヒの負けん気を刺激し、何がなんでも剣を奪おうと裸足で走る。
パン!と銃声が鳴り、ハルヒの足元から煙が上がった。もう一歩踏み出していれば脚を貫通しただろう銃弾に、自ずとその足は止まった。
「エルザ」
ルシウスは手に持った銃をくるくると回してから、部屋のすぐ外で待機させていたエルザを呼んだ。
命令に従って室内に入ってきたエルザは、床にある銃弾の痕を一度見たあと、姿勢を正してルシウスに敬礼した。
「着替えさせろ」
そう言うとルシウスは立ち上がり、ソファーの上に置いてあった白い検査服をハルヒに投げつける。
「だれがこんな服着るか!俺の服を返せ!」
「あんなものは捨てた。ここは軍の研究施設だぞ。雑菌に塗れた服のまま立ち入れる場所ではない」
「……!」
「いいか。小娘。足りない頭で考えて正しい判断をしろ。大人しくそれに着替えれば、会いたい男に会わせてやってもいい」
「……クサナギはどこだ」
「すべてはおまえ次第だ」
ルシウスはそう言うと部屋を出て行った。残されたハルヒは床に落ちている検査服を見下ろし、ぐっと拳を握り締めた。白一色のその服にハルヒは見覚えがあった。それは、忍び込んだ研究施設で、異形と成り果てて死んでいた実験体。ナンバーズと呼ばれる彼らが着ていた服だった。
(クソ……!)
エルザが見ている中、ハルヒは袖さえついていない検査着を頭から被った。裸よりはマシだが、空調の効いた室内では何も履いていない下半身が肌寒いし、靴もない。
ハルヒが着替えを終えると、エルザはついてこいとだけ口にして彼女に背中を向けた。
□◼︎□◼︎□◼︎
「素晴らしい」
感嘆の言葉と共に、ヴィルヒムの孤独な拍手が鳴り響く。その目の前にある強化ガラスには、大きな裂傷が刻み込まれていた。いまにも砕けそうだが、あと一押しが足りない。アキが渾身の力を振り絞って放った風だったが、あと一歩ヴィルヒムまでは届かなかった。
アキはゼェゼェと肩で息をして、指が肉に食い込むほど左胸を押さえる。爆発しそうな心臓の鼓動に合わせて、血管が千切れそうなほど脈打っていた。まるでオーバーヒット直前のエンジンのように。
(リバウンドする……!)
ハルヒを抱えてビルから飛び降りたときですら、こんなに胸は痛まなかった。身体が限界を超えたことを感じ、アキはすぐそこに見えている死に気づいたが、それよりもヴィルヒムへの殺意が上回った。
「う、ぐ……ッ」
鉛のような腕を上げ、ガラスの向こうにいるヴィルヒムを狙う。この男を道連れにできるのなら死んでもいいと思った。
「そういえば、一緒にいた女の子。あの子は生きていればきみの妹と同じ年頃だね」
「……!」
「これは私の勝手な予想なんだが、彼女は守れなかった妹の身代わりかな?」
殺さないでと、そう母親に頼んだ。妹は自分が守るから、殺さないでと。せめて苦しむ前に死なせてやろうと、眠っている妹の首を絞めようとする母親に、自分が絶対に守るから殺さないでと懇願した。なのにひとりだけ逃げ出した。あんなに小さな妹を残して。約束を破って。ひとりだけ。
「違う……」
スタフィルスにやってきて、昔のことを思い出すこともなくなった頃、ハルヒと出会った。ハルヒは命を燃やして生きている炎のような少女だった。妹が生きていれば、ハルヒのように育ったかもしれない。そう考えたことがないとは言わない。だが、身代わりにしたかったわけじゃなかった。
「ハル、ヒは……ちが……、」
ガクリと膝を折り、アキはその場に倒れ込んだ。意識を失いましたと、アキをモニターしていた研究員がヴィルヒムに報告する。おそらく、リバウンドを阻止するために身体が意識を奪ったのだろうとヴィルヒムは推測した
「クサナギッ!」
頭上から聞こえた声にヴィルヒムは顔を上げる。そこにはハルヒの姿があり、彼女はひとつ上の階から倒れたアキを目撃して叫んでいた。その後ろにはルシウスとエルザの姿もある。
死んだのかと、モニター室にルシウスから通信が入った。
「いいえ、大佐。かなり疲弊していますが、生きています」
「クソジジイ!てめえクサナギに何しやがった!」
ルシウスの手から通信機を奪い取り、ハルヒはヴィルヒムに怒鳴る。
「ははは。威勢のいいお嬢さんだ」
目を覚ましたハルヒを初めて見たヴィルヒムはその威勢の良さに笑った。
「単に力を使い果たしてしまっただけで、リバウンドも起こっていないから彼は大丈夫だよ」
ハルヒは目の前のガラスを殴りつけるがそれはビクともしない。倒れたアキはそこに見えているのに、ハルヒには近づくこともできなかった。
「クサナギ!おい!クサナギ!起きろ!」
「残念だが、おまえの声は届かない」
諦めることを知らないハルヒにルシウスが言った。カッとなったハルヒはルシウスに向かって通信機を投げつけようとしたが、エルザによって腕を取られ、壁に押さえつけられる。
肩の関節が外れそうになり、その痛みでハルヒは声にならない悲鳴を上げた。
「もう少し丁寧に扱ってやれ。たかが小娘だぞ」
「お言葉ですが、小娘であろうとテロリストです」
エルザが反論するのは珍しい。ルシウスは片眉を上げて好きにしろという意思表示をする。
「クサナギ……っ」
ルシウスの言うとおり、ハルヒの声はアキには届かない。届いていても、意識のないアキは返事をしない。アキの首にはめられた首輪に気づいたハルヒは、ギリッと奥歯を噛み締めた。
□◼︎□◼︎□◼︎
チチチ、と小鳥のさえずりが耳に届く。同じ砂漠の町とは思えないほど澄んだ空気の中、ナツキは目を覚ました。
昨夜は一度も苦しくなることがなかったので、朝までぐっすり眠った。砂が舞い込むF地区の家では、夜中に何度も目を覚まして喘息に苦しんでいたのが嘘のように、レイジに保護されてからはナツキの、少なくとも体調については安息の日々が続いていた。
「おはよう」
外の木の枝に止まる鳥に声をかけ、ナツキはベッドから降りた。外はよく晴れていて、風はない。枝葉の動きでナツキはそれを確かめた。今日は少しくらいなら外を歩いても大丈夫かもしれない。レイジに聞いて、許可が出たらハルヒを探そうと決めてナツキは部屋を出た。
レイジに保護されてから、ナツキはあちこちを転々と移動した。それは全部ハルヒの情報が手に入ったから、出来るだけ近くで待つためというのが理由だった。それでもなかなかハルヒとは会えなかった。体調が悪いときは大人しく待っていたナツキだが、喘息の発作の回数が減ってくると、自分からハルヒを探しに行きたいとレイジに頼むようになった。
レイジはまだ早いと言っていたが、これだけ元気になれば問題ないだろうと自分で判断し、ナツキは顔を洗ってからレイジの部屋をノックする。砂が飛ばない今日ならきっとレイジも外出を許してくれると期待して。
ガターン!と室内で大きな音が鳴った。ノックの返事にしては大きな音にナツキは驚いて飛び上がったが、すぐに扉を開ける。
「レイジさん!」
部屋の中では、倒れた執務用の椅子の横でレイジが激しくむせ込んでいた。椅子で身体を支えようとしたが、支えきれなかったのだろう。ナツキは部屋の中へ駆け込み、レイジの背中をさする。しばらくすると、レイジの咳は止まり、彼は落ち着きを取り戻した。
「レイジさん……」
咳き込むことの苦しさを誰よりも知っているナツキは、軽はずみに大丈夫とも聞けずにレイジの顔を覗き込んだ。そして、息を詰まらせる。
「ナツキ……」
一瞬で顔色を失ったナツキに気付き、レイジは口を押さえていた自分の右手が血で汚れていることに気づいた。
「ぼ、ぼく、お医者さんを……!」
動揺しながらも助けを呼ぼうとしたナツキを引き止め、レイジは首を振る。
「大丈夫だ」
「でも……っ」
血が出るなんて普通じゃない。レイジが死んでしまうと怯えるナツキの頭を撫で、レイジは微笑む。
「本当に大丈夫だから。ほら、もうおさまったろう?」
「レイジさん。死んじゃやだ……っ」
ナツキの目に涙が滲んだ。無垢な子供から零れ落ちる涙を見たレイジは、ズキリと胸が痛むのを感じた。痛んだのは、すでに失ったと思っていた良心だ。自分はナツキを騙して利用している。ナツキを人質としてハルヒをおびき出し、カゲトラ共々始末しようとしている。そして、そのあとはナツキも―――。
「部屋に戻りなさい……」
「レイジさん。でも……っ」
「私は大丈夫だから、部屋に戻りなさい」
強い調子でそう言われ、ナツキはしょんぼりと肩を落としてレイジの部屋を出て行った。ナツキの部屋の扉の開閉音が聞こえると、レイジは手元の壁を殴りつけた。
部屋へと戻ったナツキは涙を拭う。そして、そっと窓を開くと、そこから身を乗り出した。
□◼︎□◼︎□◼︎
目覚めた部屋に連れ戻されたハルヒは、ソファーに座ることを強要された。エルザが運んできたコーヒーがテーブルの上に置かれると、向かい側に座っているルシウスがそれを手に取り、口に運ぶ。
「そう睨み付けるな。せっかくの味が悪くなりそうだ」
ハルヒは拘束されていない。手足は自由に動いた。それでもソファーの上から動けなかったのは、逃げようとすれば間違いなく撃たれるからだ。一発で死なないとしても、脚を撃たれでもしたらアキを助けることが難しくなる。
「そうだな。まずはカゲトラ・バンダの居場所でも聞こうか」
「………」
「話すわけがないという顔だな」
「拷問してはいかがですか?」
エルザが言った。彼女はハルヒを殺したくてたまらない。ルシウスを傷つけたテロリストが許せなかった。
「小娘を痛めつける趣味はない」
「実の妹を撃ち殺しかけといてよく言えたな」
あいつも小娘だろと、ブロッケンビルでのことをハルヒが鼻で笑い、ルシウスは目を細めた。
「エルザ。ふたりにしてくれ」
「しかし大佐」
「ふたりで話したいんだ」
「……部屋の外で待機します」
エルザはギロリとハルヒを睨み付け、部屋を出て行った。扉が閉まると、ルシウスはソファーに深く腰掛け、長い脚を組んだ。
敵はひとり減ったわけだが、ルシウスに力で敵わないのはもうわかっている。間合いを詰めるのは失策だ。どうにか距離を保ったままこの場を乗り切れないか、ハルヒは必死になって考える。
「わかっていると思うが、おまえの運命は私の気分次第だ。今回はクサナギ王子も助けにはこない」
「………」
「おまえの使い道はまあまあある。ひとつは、おまえを餌にカゲトラ・バンダを含めた【トライデント】のメンバーをおびき寄せて根絶やしにすること。または、レイジ・コウヅキに引き渡すのもいい。【トライデント】の件に関しては、あいつのほうが適任だろうからな」
ルシウスはレイジと繋がっている。こんな状況でもなければレイジの居場所について問い詰めたかったが、いまはナツキよりもアキが優先だ。
「他は……そうだな。ナンバー付きの首輪をつけて、ステファンブルグにやってもいい。生きのいい実験体としてな」
「クサナギと会わせろ」
「B−101か?彼とはさっき会ったばかり───」
「アキ・クサナギだ!」
アキをナンバーで呼ばれたことが、自分がそうされたように腹が立ち、ハルヒは声を荒げた。
「心配しなくても、彼はドクター・ステファンブルグのお気に入りの玩具だ。そう簡単に殺されはしない」
「玩具だと……!」
アキを侮辱されることにいちいち怒りを露わにするハルヒに対し、ルシウスはフッと笑った。
「なにを今更。やつが適合者だと知らないわけじゃないだろう」
その力で何度も守ってもらったじゃないかと、ルシウスは続けた。
「やつは人間じゃない。バケモノだ。やつの身体にはバルテゴ神のカケラが埋め込まれて―――」
「クサナギは人間だ!」
ハルヒは叫んだ。ルシウスは笑顔のまま話すのをやめ、部屋に静寂が訪れる。
「なるほど。そんなに彼が好きなのか」
ルシウスの言葉に、ハルヒは顔をしかめた。
「……なんだと?」
「ああ、これは失礼。自覚していなかったのか。しかし、悲劇ならぬ喜劇だな。実験体とテロリスト―――はははっ」
ブッと、ハルヒが吐いた唾が、ルシウスの膝に飛んだ。その瞬間、ルシウスはハルヒの胸ぐらを掴むと、布地の薄い検査服を引きちぎり、ハルヒを強い力で突き飛ばした。
「しばらく考える時間をやろう」
立ち上がったルシウスの足音が遠ざかっていく。ハルヒはそれすら見る事ができず、唇を噛んで床を睨み付けた。ルシウスとエルザ、ふたりの足音が聞こえなくなると、やっと、ハルヒの目に滲んでいた涙がこぼれ落ちた。
□◼︎□◼︎□◼︎
脳波、脈拍、心音。取り付けた様々な機械がアキのデータを数字へ変える。溢れ出すデータ用紙を目で追いながら、ヴィルヒムは満足そうな笑みを浮かべた。
「ああ、もう手当てはいい」
そして、アキの傷の手当てにあたっていた研究員に声をかけた。研究員は取り替えようとしていたガーゼを持ったまま、目を丸くした。
「傷は時期に癒える」
「いや、しかし……」
イスズの触手は直径3センチほどある。それに刺されたアキの傷は小さくはない。いくら適合者でもと言いかけた研究員は、アキの傷口がもう塞がりかけていることに気づいた。確かに、これならヴィルヒムの言う通り手当ての必要はなさそうだった。
仕事を失った研究員が退室すると、部屋にはヴィルヒムはアキだけになった。一定の間隔で落ちていく点滴は、ゆっくりとアキの体内に入っていく。
「さあ、目を覚ます時間だ。B−101」
ヴィルヒムが呼びかけると、アキの双眸がゆっくりと開いていく。その虚ろな視線がヴィルヒムを映した。
□◼︎□◼︎□◼︎
夜半過ぎ、ココレットの案内で、カゲトラとハインリヒは軍が管理する集合住宅街に来ていた。C地区にあるこの住宅街は、軍が兵士とその家族を住まわせるために建設したもので、窓にはたくさんの明かりが見えた。
ココレットたち3人は、夜の闇に紛れて住宅街を目的の家まで進んだ。長年ココレットの世話をしている執事、セバスチャンの情報では、ここでナツキの目撃情報があったと言うことだった。
「なあ、お嬢様」
「ココレットです」
「いや、それは知ってますけど」
ココレットは、ハインリヒがいままで相手にしたことのないタイプの女性だった。あらゆるジャンルの女性と関係を持ってきたつもりのハインリヒが、ココレットについては予測できない答えばかりが返ってきて、どうもリズムを狂わされている。
「本当に間違いないのか?」
「はい」
セバスチャンを信頼し、キッパリと言い切るココレットだが、ハインリヒは一抹の不安を拭えなかった。カゲトラも眉根を寄せる。そして、ハルヒのそばを離れたことを深く後悔した。あのとき別行動をしなければ、ハルヒはもうすぐでナツキに会えたかもしれない。
(ハルヒ。無事なのか……)
ハルヒにはアキがついている。多少の心配はあっても、万が一のことはないと思いたい。これまで、アキはハルヒの危機を何度も救ってきた。
「おいっ」
ハインリヒが小声でココレットを引き寄せる。男に抱き締められたことのないココレットが、反射的に悲鳴をあげそうになったのを、カゲトラが大きな手で押さえた。否応にも3人の鼓動は高まる。
物影に隠れた3人の目の前を、バタバタと兵士が通り過ぎていった。そして、目指す家の前で立ち止まって扉をノックする。
少し間を置いて中から扉は開けられた。カゲトラの体が強張る。そこから姿を現したのはナツキではなく、どこか痩せ衰えたように見えるレイジの姿だった。
冷える砂漠の夜にガウンを着込んだレイジは、兵士の報告を受けて頭を押さえる。
「私が聞きたいのはそんな報告じゃない!いないのなら見つかるまで探せ!15歳の子供であの子は身体も弱いんだ!そう遠くへは行けない!」
「りょ、了解!」
烈火のごとき怒りを見せたレイジの命令を受け、兵士たちは砂を蹴散らしながらその場を立ち去った。兵士たちがいなくなると、レイジはガウンの前を合わせてゴホゴホとむせ込む。
カゲトラはその姿をじっと見つめた。一際大きくむせ込んで咳を止めたレイジは、口元を押さえていた自分の手に視線を落とす。カゲトラたちのいる暗がりの中からでは、レイジの手についた血液までもは見えなかったが、その後口元を拭うレイジの仕草で、カゲトラとハインリヒは何かを察した。
忌々しそうに舌打ちしたあと、レイジは荒々しく扉を閉めて家の中へ姿を消した。すぐにそのあとを追いかけようとしたカゲトラを、慌ててハインリヒが引き止める。
「あんたの優先順位を聞いておこう」
「………」
「俺たちは、ナツキと言う小僧を誘拐しにここに来たんだよな?」
「誘拐したのは軍ですッ」
ココレットが訂正するが、ハインリヒは首を振る。
「世間はそうは思わない。シノノメ家の発砲現場で、少年は軍に保護されたことになっている。それを連れ出せば誘拐だ。真実がなんだろうと民衆が信じるのはテロリストじゃない。軍とそれにコントロールされた報道だ」
ココレットを論破してから、ハインリヒは改めてカゲトラに向き直った。
「いまのやり取りでわかったはずだ。探してる小僧はもうここにはいない。逃げたんだよ」
カゲトラは強く口元を結んだ。ナツキが軍の手に落ちた時、最悪実験体にされる未来もあったが、レイジはそうはしなかったようだ。考え込むカゲトラにハインリヒは首を振る。
「優先順位を教えろ。あんたの目的は小僧を見つけることか、それともあのいまにも死にそうな男を殴り殺すことか、どっちなんだ」
カゲトラの拳はずっと握られたままだった。ナツキはここにはいない。だが、仲間を売ったレイジが、目と鼻の先にいる。
「乗りかかった船だ。俺は自分の責任として、このお嬢ちゃんを守る。だが、あんたは別だ。あの男の部屋に突っ込むのなら、それは俺たちがここから離れたあとにしてくれ」
カゲトラは何も言わないが、その頭の中で相反するふたつの選択肢がせめぎあっているのは明らかだった。こんな状況なければ煙草に火をつけたいところだが、それをなんとか堪えるハインリヒの視界に、そっとカゲトラの手を握るココレットの姿が映る。
「……ナツキを探しましょう」
カゲトラを見上げ、ココレットはしっかりとした口調でそう言った。夕闇が濃くなってきていた。
□◼︎□◼︎□◼︎
かなり長い時間、床を見て俯いていた。考え込んでいた訳ではなく、絶望がハルヒの思考回路を闇に染めていた。
あれからルシウスは現れなかった。そして、アキも姿を見せない。ハルヒが窮地に立たされた時は、必ず風のように駆けつけたアキは、いつまで待ってもやってこなかった。
「………」
ここへ来るアキの姿を想像し、それを願っている自分に気づき、ハルヒはパンッと自分の両頬を叩いた。
「……しっかりしろ」
それは自分に向けて言った言葉だった。
いったいいつから、こうやって助けを待つだけになったんだ。いったいいつから、ひとりでは立ち上がれないようになったんだ。いったいいつから、アキがいなければなにもできないような、腑抜けた人間になったんだ。
(俺は神様の力なんかないけど、腕がある。足がある。心臓も動いてる)
ハルヒは顔を上げ、ソファーから立ち上った。目的は、この敵地のど真ん中から、アキを探し出して脱出すること。それだけだ。
今度は自分の番だ。今度は、自分がアキを助ける番だ。強い意志を瞳に乗せ、ハルヒは施錠もされていない部屋の扉を開けた。
薄暗い部屋のモニターに、慎重に廊下の状況を確認しながら部屋を出て行くハルヒの姿が映った。その様子を観察していたルシウスに、よろしいのですかとエルザが尋ねる。質問したものの答えは聞くまでもないとわかっていた。だが、部下として一言は必要だと考えた。
「構わん。ステファンブルグに餌を用意したと伝えろ」
ルシウスはエルザが予想した通りの答えを口にすると、アキまでのゲートを全て解放しろと命令を出した。
部屋の外にはだれの姿もなかった。ハルヒは拍子抜けしながらも通路を慎重に進んでいく。建物内の構造はわからない。知っているのは、さっきルシウスに連れられて歩いた道だけだ。
さっきと同じ場所にアキがいるとは限らないが、ハルヒはそこへ向かうしかなかった。監視カメラが左右に首を振っている姿に不気味なものを感じながらハルヒは進んだ。
「開いてる……」
エルザがカードをかざさなければ開かなかったはずのゲートは、なぜか開きっぱなしになっていた。まるでハルヒを招き入れるように開いている扉を潜り、もう一度監視カメラを見上げる。
(誘導されてる……)
おそらくカメラを通してルシウスに見られていて、彼は自分をこの先へ行かせたいのだろう。間違いなく罠であるこの状況に、ハルヒは拳を握り締めて次の一歩を踏み出した。罠であろうが、ここで足を止めて部屋に逃げ帰る気はなかった。
空いているゲートを通り抜け続けると、前方にエレベーターが見えてきた。ルシウスに連れて行かれたときは、このエレベーターに乗って上に行ったが、たどり着いたのはアキを見下ろす場所だった。
どうしようかと考えていると、いきなり右手側の扉が開き、ハルヒは驚いて肩を震わせた。無言で目的の前に誘う監視カメラに中指を立て、ハルヒはその扉の中に入った。その先には一本道の通路が続いていて、さらに奥には一枚の扉があった。初めて見る閉じた扉に向かってハルヒは歩いていく。おそらくこの先が目的の場所だ。ハルヒが近づくと、扉は触れる前に横にスライドした。
「ッ、クサナギ!」
扉が開くと、そこはさっき見下ろしていた部屋だった。ガラス以外は白一色で統一されたその部屋の中では、アキがひとりバッドの上に座っていた。すぐさまハルヒは彼に駆け寄る。
「クサナギ!大丈夫か!?」
ハルヒが声をかけるがアキは返事をしなかった。虚ろなアキの目は、開いていてもハルヒを認識してはいない。強めに頬を叩いてもアキはまったく反応しなかった。
「こんなもん……!」
ハルヒはアキの首にはめられた首輪を引っ張ったが外れない。つるりとした形状のそれの留め具がどこにあるのかもわからなかった。
「なあ、これどうやって外すんだ?」
「………」
「クサナギ。返事しろよ!」
「………」
「いったいどうしたんだよ……」
こんな状態になったアキは見たことがなかった。意識はあるのにハルヒの声が聞こえていない。人形のように生気のない顔つきのアキの手を掴んで引っ張ると、アキはされるがままに立ち上がった。
とにかくここを脱出しよう。外に出て時間が経てばアキももとに戻るかもしれない。ハルヒはそう考え、入ってきた扉を振り返った。
「!?」
その瞬間、扉がピシャリと閉じた。ハルヒが引っ張るがピクリとも動かない。ハルヒとアキは室内に完全に閉じ込められてしまう。罠だと言うことはわかっていたのに、油断した。ハルヒは扉を蹴りつけ、ちくしょう!と吐き捨てる。
『どうも。お嬢さん』
その声は室内に響き渡った。肩を震わせたハルヒが振り返ると、鏡だと思っていたガラスの向こうにヴィルヒムの姿が映っていた。
『さきほどは挨拶もせずに失礼したね。私はスタフィルス研究機関代表、ヴィルヒム・ステファンブルグ』
ハルヒはヴィルヒムを睨み付けた。
「クサナギに何しやがった……!」
『かなり興奮していたから、大人しくしてもらうために薬を投与しただけだよ』
身体に害はないとヴィルヒムは言うが、ハルヒにはそうは思えなかった。
『ハルヒ・シノノメ』
レイジが軍側についた以上、名を知られていたことについて驚きはしない。ハルヒの個人情報など知られていて当然とも言えた。
『アキラからきみは母親似だと聞いていたけれど、目元は彼にそっくりだね』
「……!?」
アキラ・シノノメ。それは8年も前に連絡がつかなくなった父親の名だった。アキとハルヒの父親は名前が似ていた。子供じみた理由だとはハルヒも思ったが、これまでアキを名前で呼ばなかったのはそれが理由だった。予期せぬところで出た父親の情報にハルヒはゴクリと喉を鳴らした。
「父さんを知っているのか」
『もちろん。知っているさ』
ヴィルヒムはすぐにそれを認めた。
「父さんはどこだ」
『おや、家に戻っていないのかい?』
「ふざけんな!父さんはどこだ!?」
『私に聞くよりも―――彼に聞くことをお勧めするよ』
「え?」
この部屋にいるのはハルヒとアキだけだ。思わず振り返ったハルヒは、虚ろな表情のまま立っているアキを見つめる。
「なんでこいつに……」
『さて、なぜだろうね』
ヴィルヒムはその理由を言うつもりがないようだった。口を開いたとしても、真実を語る保証はない。ヴィルヒム・ステファンブルグという人物をよく知っているわけではないハルヒだが、人間に首輪をはめるような男を信用できるわけがなかった。
「ここから出せ」
『焦らないで。遅かれ早かれきみはここを出て行くことになる』
ヴィルヒムはそう言うと、わざわざ持ち上げた小さな端末をハルヒに見せる。そこにはいくつかのスイッチがついているのが見えた。
『死体となったあとでね』
ヴィルヒムがスイッチを押すと、ビクッとアキは身体を震わせた。そして、声にならない悲鳴をあげて耳を押さえ、その場にうずくまる。
「クサナギ!」
ハルヒには聞こえない共鳴音に苦しむアキは、駆け寄るハルヒを視界に入れる。だが、それはハルヒの姿から徐々にヴィルヒムの姿へと変化していく。自分に向かって手を伸ばすヴィルヒムの幻に、恐怖を覚えたアキは無意識に風を放っていた。
「!?」
目には見えない風刃は真っ直ぐに飛び、ハルヒの横腹を切り裂いて入り口の扉に衝突し、そこにわずかな爪痕を残した。
「………」
一瞬、何が起こったのかわからなかった。腕を突き出したままのアキから、自分の脇腹へと視線を落としたハルヒは、白い検査服を赤く染め上げていく自分の血を見て、ようやくアキに攻撃されたのだと理解する。それでも、それがなぜなのかは理解できなかった。
「クサナギ……」
アキの力は何度も見た。だからそれがどれほどの力なのか、ハルヒは知らないわけではなかった。もう少し深く食い込んでいたら内臓を傷つけられていただろうし、もう一歩踏み出していたら真っ二つにされていただろう。
『首が飛ぶのかと思っていたが、この程度か』
ルシウスの声がした。ハルヒが目線だけを動かすと、ヴィルヒムの隣にはルシウスとエルザの姿があった。
「一応、リミッターをつけていますので。そこまでの威力は出せないかと」
「リミッターとはあの首輪か?」
「はい。あれが暴走を抑えるリミッターになっております。これほどの適合者はなかなか手に入らないので、ひとつの保険です」
「だが、切り刻むことくらいは可能なんだろう?」
ハルヒの脇腹は酷く出血している。あれくらいの威力は出せると言うことだ。自分をばかにしたテロリストが苦しんで死ぬ様が見たいルシウスに頷き、ヴィルヒムは手に持った端末の音波レベルをゆっくりとあげていく。
「うぅ……!うぁあ……っ」
強すぎる共鳴音に頭に激痛が走る。痛みに頭を抱えたアキは苦しさを紛らわせようとでも言うように風を纏い、周りのすべてを拒絶する。
「クサナギ……!」
「セルフィ……っ、セルフィ……!守るって言ったのに……!約束したのに……ッ」
うわ言のようにアキは同じ言葉を繰り返す。
アキは正気じゃない。ハルヒはどうにかアキに近づこうとするが、アキの周りには強烈な風が吹き荒れ、離れていても踏ん張らなければ吹き飛ばされてしまいそうになる。
「クサナギッ!」
血が止まらない脇腹を押さえながら、やっとのことでハルヒが一歩を踏み出すと、飛んできた風刃がむき出しの腕を切り裂いた。
「いっ……!」
痛みにハルヒは顔をしかめるが、次の一歩を踏み出す。近づくほどに、アキの風はハルヒの全身を切り刻んだが、ハルヒは止まらない。
「クサナギ……ッ」
嵐の中心でアキは自分の身体を抱きしめ、ずっとセルフィに謝り続けていた。守れなかった妹に許しを求めている彼は、一度もハルヒを見ようともしない。
「こっち見ろ!クサナギ!」
ついにハルヒの手がアキの肩を掴む。その腕が刎ね飛ぶさまを予想したルシウスだったが、アキの風はハルヒをかすらず、周囲の壁を切り刻むばかりだった。
肩を掴まれたアキはようやく顔を上げる。だが、ハルヒの顔を見るとすぐに逸らそうとした。
「ふざけんな、この……!目ェ逸らしてんじゃねえ!」
涙でぐしゃぐしゃになったアキの顔を掴んだハルヒは、アキの額に自分の額をぶつけた。ゴッと音が鳴り、アキの視界のすべてをハルヒが占拠する。
「……!」
「俺を見ろ!アキッ!」
―――おいで。ここから逃がしてあげる。大丈夫だよ。怖がらないで。
―――僕を見て。
真っ赤に染まる黄昏の空。あたり一面に転がる、ズタズタに引き裂かれた死体。記憶の奥にしまい込んだ映像が、弾けたようにアキの目の前に広がる。
「―――アキラ……!」
確かに父親の名を口にしたアキを、ハルヒが力一杯抱きしめると、室内に吹き荒れていた風がやんだ。嵐が収まった部屋の中で、アキはようやく我に返った。
「ハル、ヒ……?」
恐る恐る呼んだハルヒは反応しない。力を失ったその身体はアキの腕からズルズルと滑り落ちていく。ハルヒを抱き上げようとしたアキは、ぬるりとした感触を覚えた。持ち上げた手には真っ赤な血が付着していた。
「小娘は死んだのか?」
一部始終を見ていたルシウスがそう聞いた。だが、ヴィルヒムにとってそれは重要ではなかった。彼にとって重要なのは、共鳴音を止めていないのにアキがハルヒへの攻撃をやめたことだった。
ルシウスの質問に答えないヴィルヒムに視線をやったエルザは、彼と同じことに気づいた。その瞬間、アキの風が強化ガラスに激突する。バンッという衝撃音のあと、ガラスにペキペキとヒビが入っていく。
「大佐!退避してください!」
「破れるものか……!」
アキの適合率では破れない強化ガラスだ。そう報告されているルシウスは動かない。だが、ヴィルヒムはすでに踵を返していた。
「大佐!」
エルザが叫んだ瞬間、アキの風が強化ガラスを突き破った。
「大佐!」
ルシウスを庇ったエルザの背中は、ガラスを突き抜けても勢いのやまなかった風に切り裂かれ、その上に無数のガラス片が降りかかった。
まさか強化ガラスを突き破るとは思っていなかった。完全に測定ミスだ。アキの高い適合率を目の当たりにしたヴィルヒムは、すぐさまモニタールームを出た。
アキはヴィルヒムを追うことはせず、ハルヒを抱き上げて真上に向かって風を放った。いとも簡単に天井が吹き飛び、風をまとったアキはそこから飛び出した。
軍施設から脱出したアキは、数ブロック離れたところで胸に痛みを感じ、降りる間もなく地上へ落下した。
「うッ!」
ハルヒをかばって背中から落下したが、ちょうど積み上がった砂の上だったのが幸いして、少しむせ込むだけで済んだ。イスズに刺されてからどれくらい時間が経ったのかはわからないが、辺りは暗くなっていた。
「はぁ……はぁ……っ」
心臓の音がうるさいくらい頭に響く。アキは共鳴の置き土産とも言える頭痛に耐えながら、着ていたシャツを脱いでハルヒの脇腹にきつく巻きつけた。白いシャツはすぐに赤く色づいていく。
「ハルヒ……っ」
腕に抱えたハルヒは完全に血の気を失っていて、固く閉じられた目は呼びかけても開かない。その脇腹から溢れる血で、検査服はびしょ濡れになっていた。
これは間違いなく自分がやったことだ。覚えてないけれど、こんな傷をつけられるのは自分しかいない。
「お願い、死なないで……!」
休んでいる暇はない。早くハルヒを医者に連れていかなければならない。胸を押さえて、アキはもう一度飛ぼうと風を纏う。たとえこの心臓が破れて全身が砕け散っても、ハルヒだけは───。
「―――アキ!」
ふいに名前を呼ばれたアキは、肩を震わせて振り返った。そして、そこに立っているハインリヒの姿を認識すると、敵ではないことに安堵して持ち上がっていた肩を落とした。
ハインリヒの隣にはカゲトラの姿もある。なぜふたりが一緒にいるのか、アキにはそんなことどうでもよかった。駆けつけて来るハインリヒの姿が幻でないことを祈りつつ、アキはその場に膝を折った。
「おいおいおいおい!冗談だろ!」
アキの腕に抱かれているのがハルヒだと気づいたカゲトラも、ココレットを残して走った。
「ハルヒ!」
駆け込んだカゲトラは裂傷まみれのハルヒの姿に言葉を失った。特に脇腹の傷は深いのか、恐ろしいほど出血しているのがわかる。
「アキ!アキ、しっかりしろ!クッソ……!」
いくら呼びかけても反応しないアキの腕を肩にかけて持ち上げると、病院に行くぞとハインリヒが言った。
「病院はだめだ!軍の手が回る!」
そうしたくなくて突き放したこともあったが、もはやハルヒも【トライデント】の一員だ。そして、ハルヒを助けたアキだって同じようなものだった。
「だったらどうすんだよ!」
「静かにしろ!いま考えてる!」
「考えてる時間なんてあんのかよ!」
「少しくらい黙っていられないのか!」
「やめてください!」
怒鳴り合うハインリヒとカゲトラをココレットが止める。
「私の屋敷がすぐそこにあります!そこに手当てができる者がいますから、行きましょう!」
カゲトラとハインリヒは顔を見合わせる。ココレットこそ間違いなく軍関係者だ。だが、ナツキとハルヒを再会させるためにF地区までやってきたココレットが病院よりもまだ信用できると判断したのは、ふたりほぼ同時だった。
屋敷に到着すると、ココレットが先に中へと入った。ほどなくして屋敷の中からセバスチャンがひとりでてくる。
「初めまして。私はセバスチャン・シュベルツ。この屋敷の執事として、ココレットお嬢さまのお世話をさせていただいております。このたびはお嬢様を無事に送り届けていただき、本当にありがとうございました」
カゲトラとハインリヒは顔を見合わせて、ココレットがこの執事にどんな話をしたのかをおおよそで想像する。
「ベルモンドさまにおかれましては、多大なる誤解があったようでございまして、ここにお詫び申し上げます」
「ああ、ああ、それはいいんだ!いいんだけど!」
「怪我人がいると聞いております。どうぞお屋敷の中へ」
長い前置きだったが、とりあえず匿ってはもらえるようだ。ハインリヒとカゲトラはセバスチャンについていき、ロビーに入った。そこにはすでにココレットの手配でストレッチャーが二台用意されていて、ふたりはアキとハルヒをそこへ寝かせた。
「恥ずかしながら、少し手当ての真似事ができますので、医者が来るまで応急処置などをさせていただいてもよろしいですか?」
ハルヒの傷を見たセバスチャンがカゲトラにそう言った。カゲトラが了承すると、真似事と言った割には迷いのない手つきで、執事はハルヒの脇腹に巻かれたシャツを外すと、周囲にこびり付いている血を拭き取っていく。
「どうなんだ」
「傷口が深い。縫合が必要でしょう」
「あんたは縫えるのか?」
「経験はありますが、もう歳ですので。若いお嬢さんの身体に縫合痕が残らないように縫えるかと聞かれれば───」
「縫えるのか、縫えないのかを聞いてるんだ!」
思わずカゲトラが声を荒げたと同時に、屋敷の玄関が開いた。反射的にカゲトラはハルヒを、ハインリヒはアキを庇う姿勢を取る。中に入ってきたのは若い女性だった。
「……何なの」
どう見ても寝巻きの上にコートだけを羽織った女性は、ロビーに集まった面々を見回し、最後にハインリヒの顔を見てギャーッと叫んだ。
「ちょっと!こいつ誘拐犯よ!」
「違うの、メアリー!」
慌ててココレットが否定する。メアリーと呼ばれた女性は、ココレットの無事な姿を見てホッと胸を撫で下ろした。
「お嬢様!ご無事でしたか!」
「心配かけてごめんなさい。メアリー。来てくれたばかりなんだけど、お願いがあるの」
ハルヒとアキを助けてほしい。ココレットの願いに、メアリーはストレッチャーの上のふたりに目をやった。
彼女は私の娘で、現役の医者です。呆気にとられているハインリヒとカゲトラに、そうセバスチャンが説明した。
□◼︎□◼︎□◼︎
出血のせいで見かけはハルヒのほうが重症に見えたが、実際はアキのほうが危険な状態だった。力を使いすぎたために血圧が急激に下がって、脈も心臓の鼓動もかなり弱っていたが、メアリーの手当てでなんとか持ち直した。
「もうだめかと思ったんだけど、しぶといわね」
点滴を調節しながらそう言ったメアリーに、カゲトラは顔をしかめた。
「何よその顔。嬉しくないの?」
「ああ、嬉しい嬉しい。助かったよ」
カゲトラの態度を怪訝に思うメアリーの前にハインリヒが入る。メアリーは見るからに不潔なハインリヒが近づくと、鼻をつまんで一歩下がった。
「女の子のほうはだいぶ出血したから、もしかしたら輸血が必要かもしれない。血液型は?」
「……Bだったと思う」
「血液型くらい覚えてないの?」
父親でしょうと言われたカゲトラは首を振った。
「これは友人の娘だ」
「そうなの……。そちらは?」
どういう関係なのか聞かれたハインリヒは、アキは仕事上の部下だと話した。
「それじゃ、どういう経緯でこんな怪我を……」
「ハルヒを傷つけたのがその男なら許さない」
メアリーの言葉を遮ってカゲトラがハインリヒに言った。ずっと、アキを睨みつけていたカゲトラは、いつ襲いかかってきてもおかしくない雰囲気を見せていた。それはないと、ハインリヒはアキの関与を否定する。
「こいつは女を襲うようなやつじゃねえ」
「おまえはこの男の何を知ってる」
「は?」
「この男の何を知ってて、そう言えるんだ」
「何って……」
ハインリヒは眠り続けるアキの顔に目をやる。アキのことは数年間見てきた。彼の人となりは十分に知っているつもりだった。
「あんたよりはずっと知ってるよ」
「じゃあ、この男がひとの皮を被ったバケモノだと言うことも知っているのか」
カゲトラの言葉にさすがのハインリヒも眉間にシワを寄せた。
「そりゃあ……いくらなんでもあんまりな言いかただろ……」
アキが気に入らないとしても、そこまで言われる筋合いはない。ハインリヒもアキに対しては親心がある。ここで黙っているわけにはいかなかった。
「そもそも、あんたら【トライデント】がアキを危険なことに巻き込んだんだろうが。テロリストなんかに、なんでバケモノだなんて言われて責められなきゃならねえんだよ」
「その男は適合者だ!」
「……は?」
「その力でハルヒを傷つけたに決まってる!」
「あんた、何言ってんだよ……」
カゲトラの言っていることが理解できないのはハインリヒだけではなく、その場にいるメアリーも同じだった。
「あんたはその男について何も知らない。そいつはバルテゴの適合者で、人間を簡単に切り裂く力を持ってる」
カゲトラは大股でアキに近づくと、それを阻止しようとするハインリヒを押しのけ、アキの胸元のシャツを引きちぎる。とめてあったボタンが弾け飛び、コロコロと床を転がった。
「見ろ」
カゲトラはそう言って、アキの胸にある手術痕を指差す。
「風神のカケラを埋め込んだ手術痕だ」
アキの胸に手術痕があるのはハインリヒも知っていた。まだ一緒に住んでいた頃指摘すると、アキは心臓の手術をしたんだと言っていた。
「なんだよその話……冗談だろ」
「ならハルヒの傷はどう説明する!」
ダンッ!とカゲトラが壁を殴りつける。アキを殴らなかっただけまだマシだが、大きな拳に殴られた壁を伝わり、屋敷全体が震えた気がした。
「ハルヒだけじゃない。こいつは、あんたの部下を殺したかも知れないんだ」
「……殺した?」
「違うと思っていた。違うと思いたかった!だが、俺が駆けつけた時には彼女の首はすでに転がっていた!」
ラッシュとアキが対峙したあの晩、カゲトラは遅れてやってきた。アメストリアにそそのかされたレイシャを追って。だが、その到着はあまりに遅く、そこにはレイシャの死体の前で半狂乱になり叫ぶイスズと、アキと、ハルヒがいた。ラッシュはすでにいなかった。
ハルヒとアキが目覚めてからも、カゲトラはなにも聞かなかった。アキじゃないと思っていた。そんなことがあるはずはないと信じ込んでいた。アキがいればハルヒは安全だと思っていた。だが―――ハルヒはズタズタに切り裂かれて戻ってきた。
「レイシャ・ミナシロを知っているだろう」
「……部下だ」
「彼女は死んだ。刃物のような風に首を刎ねられてな」
レーベル者が【トライデント】の協力者として軍に目をつけられて以来、レイシャには会っていない。そんなことになっていたなんて、ハインリヒは全然知らなかった。
「彼女は……ブロッケンビルで助けることになって、成り行き上仕方なく行動を共にした。だが、俺の知らないうちに出ていって―――殺された」
「……アキじゃない」
呆然とした様子で、ハインリヒは力なく否定した。もはやアキを信じる根拠はなく、信じたいからと言う気持ちだけが頼りだった。
「2時間前までは俺もそうだと信じてた」
吐き捨てるようにそう言って、カゲトラは部屋を後にした。
□◼︎□◼︎□◼︎
ナツキがF地区の家に戻るには勇気が必要だった。それでもなけなしの勇気を振り絞って戻ってきたナツキは、ウララが殺害された現場へと足を踏み入れる。しばらくぶりに戻る家の中は静まり返っていて、まるで何年も人の出入りがなかったように思えた。
ナツキが一歩踏み出すと、ギシッと床が鳴る。この音が怖いと夜中ハルヒを起こしたこともあったと思いながら進んだ。
ハルヒが戻っていればと思ったが、姉の姿はなかった。だが、その代わりとでも言うように、リビングにあったはずの写真がなくなっていた。
「……姉ちゃん」
ハルヒは一度ここへ戻ったのだろうか。それで写真を持って行ったのだろうか。ここで待っていれば、ハルヒはまた戻ってくるだろうか。どうしようか迷っているナツキを、窓から差し込んだ月明かりが照らす。
「レイジさん……」
レイジに甘えてばかりではいけない。自分でハルヒを探そうと思ってここまで来た。だけど、本当に来て良かったのかという気持ちが大きくなっていく。
レイジは血を吐いていた。自分は彼のそばにいるべきなんじゃなかったのか。抜け出したことでいま頃レイジは心配しているかもしれない。
「戻らなきゃ……」
レイジのもとへ戻ろうと決めたナツキは振り返り、そこでギクリと足を止めた。
「だ、だれ……?」
月明かりの向こうに立っている男の姿が見えた。暗くて顔まではよく見えないが、確かにだれかいる。知らないシルエットに、ナツキの心臓はドキドキと鼓動する。自然に息が荒くなっていき、それにヒューヒューと言う音が混じり出す。
「はぁ、ハッ……はぁ、はぁ……っ」
男が一歩家の中に踏み込んできた。ナツキはそれに合わせて後退しようとしたが、足がもつれてその場に倒れこんだ。
男の手が伸びてくる。苦しい息の合間に見たそれが、ナツキが覚えている最後の映像だった。
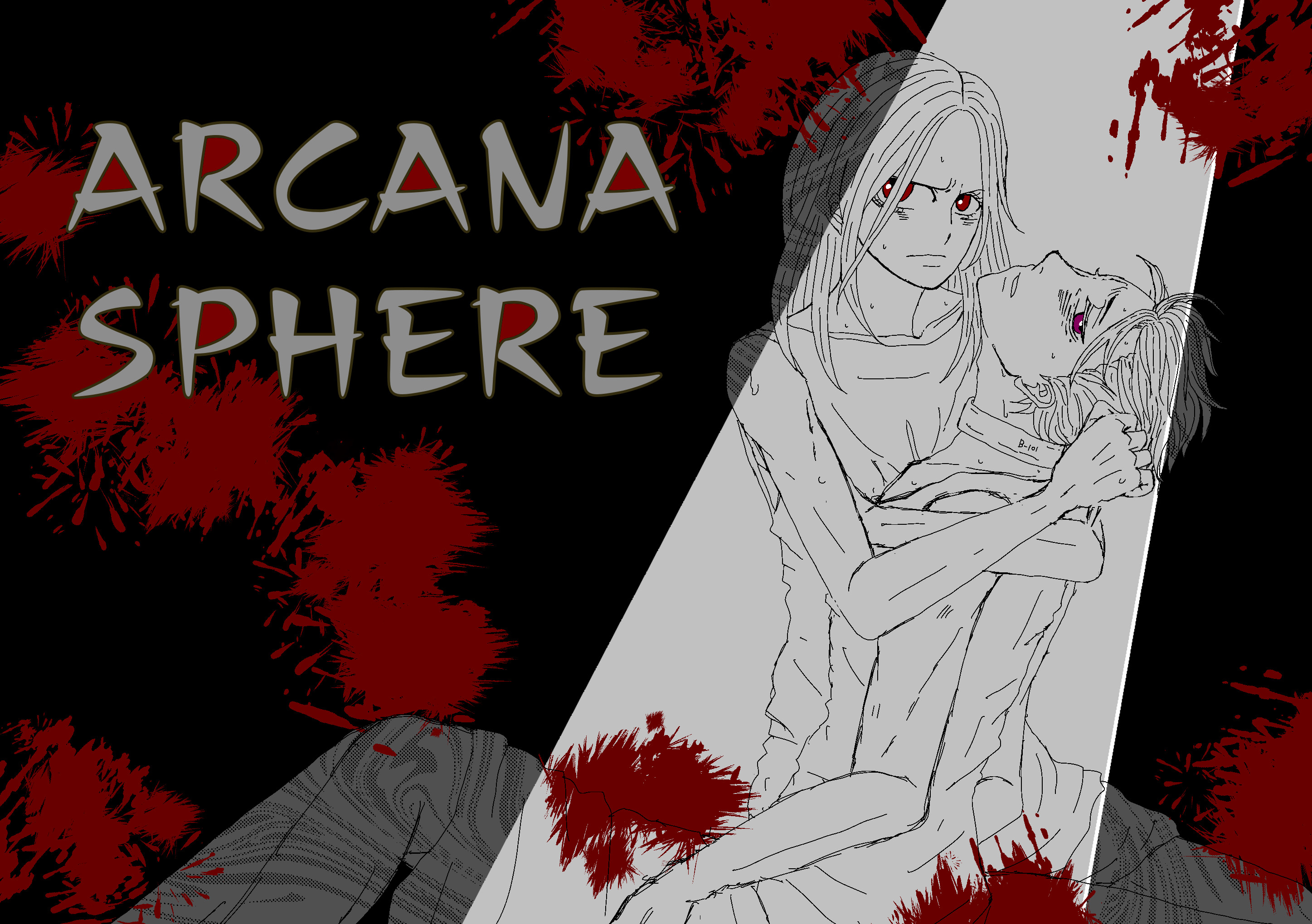
 にぃなん
Link
Message
Mute
にぃなん
Link
Message
Mute

 にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん にぃなん
にぃなん