カフェのドアを開けば軽快にベルが鳴り、そこにいたメンバーが一斉に『いらっしゃいませー!』と声を揃えた。
今日の当番はホールにミミ、リエとスギ、レオ。
確か厨房にはサナエにMr.KK、リュウタ…だっただろうか。
「あ!紫姐さん!」
そんな事を考えているとリエに声をかけられ、顔を向け返事の代わりに左手を軽く振った。
「こちらへどうぞ!」
手際よくカウンター席に促されて腰掛けるや否やミミとリエが迫る。
「「…で、どうだった!?」」
二人のそんな様子に軽く溜息を零して紫は先ず珈琲をオーダーする。
「…あんた達、カフェに来た客にオーダーも取らないってのかい。
そりゃ職務怠慢ってもんじゃないのかい?」
「「…ご、ごめんなさい〜…」」
ど正論の小言に詫びを入れつつも二人は彼女の返事が気になって仕方がない様子だ。
先日収録現場で倒れたもえはその後主治医監視の元、静養を言い渡されている様だ。
収録の翌日ニャミとポエットが見舞いに出向いたが主治医だけでなく彼女の恋人や兄達からも阻まれ彼女に面会する事は叶わなかったと言う。
また彼女の携帯電話も電源が落とされたままの様でこの数日は彼女と連絡の一切が途絶えていた。
Deuilの面々も表に出てくる事はなく…
唯一神だけはマメに様子を見に行っているが今は何も話せないとミミやニャミ、そしてポエットに語っているようで完全に情報がない。
そこで動いたのが彼女、紫である。
先日の収録現場でリーダー直々に『いつでも来い』と声がかかっていることもあり…また、もえを心配する仲間達の声が予想よりも多く上がったこともあり。
そして何より紫自身がもえを心配していた為、この程妖怪屋敷へ赴いた訳である。
カウンター席で頬杖をついた彼女はもう一度溜息を零すと静かに語り出した。
「もえ本人には会っては来なかったよ。」
「「「…ええ!?」」」
予想外の声が混じっていた。
カウンターの内側にいたスギだ
どうやらしっかり聞き耳を立てていたらしい。
「…あ、すみません…」
ミミとリエの視線に加え紫の視線も浴びることとなり何やら気まずそうである。
「……あの日以降殆ど自室で休んでるってさ。
何より主治医の締めつけも強い様だよ。」
「……ロティ、さぞ怒ったろうしなぁ…」
紫の言葉にミミが手にした盆を胸に抱え込んで零した。
「ロティ、怒ると大変そうだもんね…」
「…うん、大っ変なんだ…。
こわいこわいこわい…。」
「もえちゃん怒られてないといいけど…」
「あ!それはないと思う。」
「え?そうなの?」
「うん。
ロティもルークもマイスイートには激甘だから。」
「え…じゃあ、誰が怒られるの?」
「そりゃー…アッシュとスマイルだよ。
……流石に…同情しちゃうねー…
八つ当たりにも近いだろうから…」
「そ、そんなに…?」
リエの問いかけに黙って頷くばかりのミミにリエは少々青ざめている。
しかしミミの推測は的確だ。
今日赴いて見た様子を窺う限りではあの二人はロティに頭が上がらない様子で傍目には大変面白い光景だった。
城のリビングに通されソファーに腰掛けると直ぐにお茶やお茶請けを出された。
『あの子に連絡がつかないってんで騒いでたよ、子供達がね。』
『携帯の電源落としてるからでしょ。
アッシュやスマイルの方は鳴りっぱなしよ。』
『…だけど、二人もまともに答えないらしいじゃないか。』
『そんなの、当たり前ダヨ。
情報なんてどこからどう漏れるか分かったもんじゃナイんだ。
…警戒もするデショ。』
『…そりゃまた…
随分と慎重なもんさねぇ?』
振る舞われた緑茶を啜ってそう零した。
『…それで?
アンタら今後はどうするつもりなんだい?
いつまでもあの子を閉じ込めておく訳にゃいかないだろう?』
『『……そ、それは……』』
揃って言い淀む二人を一瞥した後、辺りを見渡した。
『……ユーリはどうした。
あの子に付き添ってるのかい?』
『ええ。…うちの兄と一緒にね。
ついさっき神も来て
今大事な話をしているらしいわ。』
『…そうかい。
こりゃタイミング悪かったんだねぇ。』
『す、少しくらいなら会えますよ!
会われますか?』
『ちょっとアッシュ!
勝手に決めるんじゃないわよ!』
『い、いやでも…っ
折角わざわざいらしたんですし…
何より姫だって会いたいんじゃないっスか?』
『そっ…そりゃ…そうかもだけど…』
そんなアッシュとロティのやり取りに思わず感心して言葉が漏れた。
『……アンタ達仲良いねぇ…。
アタシゃロティとロストが付き合ってんのかと思ってたけど。』
『…つ…つつ、付き合ってないわよっ!』
『おや、そうなのかい。
…で、ロティ。
アンタの本命、どっちなんだい?』
サラリとストレートな問いかけにスマイルとアッシュは揃って吹き出した。
『『ぶは…っ』』
紫は相変わらず静かに飄々としてロティはあからさまに狼狽えている。
『なっ……ななな、なんで…っ
んな事答えなきゃなんないのよぉぉぉーーーーっ!!!』
面白い程に顔を赤くしたロティがそう喚く。
『おやまぁ。面白い反応だこと。
…しかしいいさ…
アンタ達は寿命も長いんだから
駆け引きも火遊びも存分に楽しめば良いだろう?
……【命短し恋せよ乙女】なんてのは人間に限りだろうさ。』
ふっと妖艶に微笑んでまた茶を啜る。
『…そいじゃ…
それならこれでお暇しようかねぇ。
主治医の締めつけも随分と厳しい様だし。』
『え…ムラサキさん、帰っちゃうんスか!?
姫には…!?』
『…宜しく伝えておいておくれよ。
また顔を見に来るからってさ。』
そう言って立ち上がり颯爽と歩き出した。
玄関まで見送りに来てくれたアッシュが申し訳無さそうに零す。
『折角いらして下さったのに…
ホントすみません…』
『良いんだよ、気にしないで。
それより、あの子……もえを頼むよ。』
『はい。』
重たい前髪の隙間から真っ直ぐに自分を見つめ返して来るアッシュをまじまじと眺めて紫はふと押し黙った。
『………。』
『……あの…ムラサキさん?』
怪訝そうに首を傾げたその姿は幼い子供のようにも見えてくる。
彼はDeuil最年少とは言え自分よりも長生きのはずだが、どこか頼りなささえも感じる。
『…アッシュ。』
『はい?』
『あの子がここへ来てもう二年余りだ。
…それでも…あの子は相変わらずなのかい?』
『…いいえ。
来たばかりの頃に比べたら比較にならないくらい甘えてくれてますよ。
それでもまだまだ足りないですけれど。』
そう零した彼の表情は緩みきって…
如何に彼女を溺愛しているのかが分かる。
それは微笑ましいと思わせた。
『……そうかい。
どうか、あの子を見放さないでやっておくれね。』
『え?み、見放すなんて…!』
予想もしなかった一言にアッシュが言い募ろうと声を上げた。
しかし紫は静かに右手を上げて制する。
『アンタ達を信用していないから言うんじゃないんだ。
寧ろ信用したいんだよ。
…あの子はね…
ずっと、『隠して』きたんだ。
辛いこと
弱いこと
泣きたいこと
苦しいこと…
どんなに言いたくても言えずに。
周りの大人たちがそうさせてきたせいで
自分為に、弟の為に…
慣れるより道が無かったんだろうさ。
其れを自身に強く課してきた。
……それでもね。
あの子は…まだ子供さ。
恐ろしい程に
【大人】が板についてしまった【子供】
……可哀想に…他人に甘えたくても
簡単に甘えられないのさ。』
『…それは分かります。』
アッシュの相槌に微笑んで紫は続けた。
『あたしは過去
【何故言わないのか】とあの子を責めた事がある。
倒れるまで無理を重ねたあの子に…
何も知らない癖に冷たい言葉を投げた。』
『……姫は……何て…?』
『何て言ったと思う?』
『……【ありがとうございます。】
…かな。』
『おや、つまらないねぇ。』
『違ったっスか?』
『正解だよ。
だからつまらないんじゃないかい。』
その一言に彼は苦笑してすみませんと零した。
『…【アイドルじゃないわたしは
透明人間みたいなものだから】…
まだ14だったあの子はそう言ったのさ。
…あたしゃその時の表情がずっと忘れられなくてね。
それ以来何だか放っておけなくて…
ついついお節介しちまうんだよ。』
だから…くれぐれもあの子を頼むよ?ともう一度告げると、口元に優しい笑みを浮かべたアッシュははい。としっかり返事をした。
目の前に置かれた珈琲に視線を落として紫は息を吐く。
彼らが付いていれば大丈夫。
……そんな風に思えた。
「あのちゃらんぽらんも…
随分粋なことをするもんさね。」
「「え?なに??」」
すっかり話し込んでいたミミとリエが零した独り言を拾ったようだ。
「『神サマ』を少しだけ見直したって話さ。」
「え?少しだけ?」
「そうさ。ほんの、少しだけね。」
「紫姐さんってばめっちゃ厳しい〜。」
楽しそうに笑う年頃の少女達。
彼女達を見ていると
あの子も何の懸念もなく無邪気に笑えるようにしてやりたいと願ってしまう。
そしてそう考えてふと思う。
もしかしたら神もそんな風に思ったのだろうか…と。
「だとしたら…
最初から心配なんてする必要無かったかねぇ…。」
もう一度小さく呟いて
紫は賑やかな珈琲タイムを楽しむのだった。
Side-Lavender
先日収録現場で倒れてから数日間、毎日ルークとロティがやってきて診察をしてくれた。
その結果、自覚は無かっだが余程体力に無理が来ていた様だ。
確かに熱は引かない上高熱に転じることも多く
正直しんどいと思う事もあった。
それでも心に刺さる不安に比べればそんなことは取るに足らない。
しかし主治医の二人はこの数日特に厳しく、極力部屋から…と言うよりはベッドから出ないようにと口を揃えていた。
昨日の診察で漸く城内に限り自由にしても良いとの許可を得た所であるが…
そんなもえは今、丘の上の大樹の前で静かに佇んでいる。
ユーリ城はこの国の人々が『[[rb:血染めの丘> (ブラッディ・ヒル)]]』と呼ぶ小高い丘の上にある。
丘の頂上に立てばポップンシティの一部や王城も視界に捉えることが出来る程見晴らしが良い。
丘の上には欅の大樹が一本根付いており
宝物庫の横にある桜の大木よりも遥かに大きい。
庭で洗濯物を干しながらいつもこの大樹を気にかけていた。
子供の頃の事だが弟や翔、そしてリュウタと共に
外で駆け回り何度も木登りをしたことがある。
当時は今と比べ物にならないほど身体も丈夫だった、ような気がする。
そして久方ぶりに木登りでもしてみれば
あの頃のようにまた元気に走り出せるようになるかもしれない。
…勿論頭から信じている訳でも無いが…
今の彼女を駆り立てるには充分だった。
昼食と片付けが済み、Deuil面々は久方ぶりの会議中。
ダイニングキッチンの勝手口からそっと抜け出し大樹の元へやってきて
それを見上げたもえはよしっ!と気合いを入れた。
一番低い場所にある枝に手を伸ばして足の置き場を決める。
そうしてゆっくり、ゆっくり
その大樹に登って行った。
「…わぁ…」
眼下に広がる景色は冬の色。
所々に多くの雪が残っている。
今年は雪が少なめだと言うが
雪を見慣れないもえにとっては新鮮そのものである。
大昔、この丘で大量殺戮があったらしい。
幾千幾万もの人間の軍勢が『吸血鬼』の討伐に向かったのだと言う。
昼夜問わず大挙して押し寄せては例外なく返り討ちにされた様だ。
数日に及んだ人間たちによる一方的な宣戦布告は
たった一人の吸血鬼による圧勝で幕を閉じた。
言い伝えによれば
それは酷く静かな血を吸ったように赤い満月の夜の事だったという。
押し寄せた人間達の殆どがこの地に散ることとなったが…命からがら逃げ延びた者達は後にこう伝えている。
『[[rb:血染めの丘> (ブラッディ・ヒル)]]の吸血鬼だけは
決して近づくな、関わるな。
あれは正真正銘の【化物】だ。』
……と。
数百年の時が流れ、それは人々の記憶から薄れた。
当時大量の鮮血に染められたと言われるこの丘も
今ではそんな事が想像も出来ないほどに緑に溢れ穏やかで美しい。
『[[rb:血染めの丘> (ブラッディ・ヒル)]]』
その名だけが今も過去を表している。
「…すごい……綺麗な景色……」
穏やかに吹く冷たい風が頬を撫でて通り過ぎる。
枝に腰を据えて街を見下ろした。
当時の人々は何故この丘へ…この城へ攻め入ったのか。
『彼』が人間に対して一体何をしたのか。
この昔話を聞いた時
メルヘン王国国立大図書館で色々と調べてみた。
しかし人間達が攻め入った『事実』の記録はあれど…吸血鬼側のアクションに関しての記録はどの歴史書を観ても記載がなく。
何より普段の彼を見ていれば理由もなく人間を襲うようにも思えない。
例え何か仕掛けられたとしても余程でない限り相手をする事さえ面倒に思ようなタイプだ。
故に…人間側の一方的な宣戦布告であったと理解した。
人間は酷く愚かだ。
彼が、そして彼らが『人間』というちっぽけなものを厭い、憎み…そして距離を置いた理由もよく分かる。
同じ人間であるはずの自分でさえ何度『人間』というものを憎み、嫌ったことか。
…自分とて人間であるのに。
今でこそこの様に穏やかな時を過ごせているが
彼らは過去に何度『人間』によって迷惑を被ってきたのだろう。
それなのに彼らは今、自分を受け入れ
こんなにも甘やかし、守ってくれる。
城主であるユーリと恋人関係となり
そうなったことで周囲に様々な変化が生まれた。
勿論、良い変化だけでは無く悪い変化もある。
そしてこれからも…
彼と恋人関係である限り
それは決して切り離せなくなるだろう。
時に危険も降りかかることとなるのだろう。
…けれど…
「…わたしは『家族』でいたい。
……守りたい。」
己の体調でさえまともにコントロール出来ていない癖によく言ったものだ。
そんな風に思う。
それでも決して譲れない想いを得てしまった。
今は弟を失いここへ来た直後のように虚無に満ちた心では無い。
勿論恐怖は大きい。
大切な人々が巻き込まれやしないか、という恐怖は何よりも。
自分独りで済むのならそれに越したことはないのに。
「…わたしに、何が出来るんだろうな…」
無力な自分が憎らしい。
無意識に右手で左腕を掴み爪を立てる。
「…何も思い浮かばない…
………悔しいな…」
哀しく揺れるその視界に広がった美しい景色が徐々に霞んで行く。
また泣いてるなんて。
泣くだけで何も出来ないなんて。
ああ、なんて情けない。
泣いたって何も変えられやしないのに。
胸に詰まる鉛のような『先の見えない不安』が自分を蝕んでいることは確かだ。
それでも『きっと大丈夫、何とかなる!』と楽観視出来るほど生易しい状況でもない。
彼らの手前、なるべくそんな風に見せないようにはしているが…
どうしても耐えきれないこともある。
…そんな時彼らは決まって甘やかしてくれるものだから…尚更不甲斐ない。
「………ダメだよ。
…強くならないと……。」
涙を拭って前を向く。
「何度だって…
起き上がれるように…ならなくちゃ。」
穏やかな冷たい風がまた頬を撫でた。
それはまるで『頑張れ』と言ってくれているような。…そんな気がする。
「姫ーーーーーっ!?」
「ひーーーっめーーーっ!!
ドコーーー!?」
城の勝手口の方から兄達の大きな声がした。
姿が見えない事に心配になったのだろう。
とは言えまだ30分も経っていないのだが…。
「…一体何処へ…」
「また熱、ぶり返しちまうっスよ…」
「も、もしかして
どっかで倒れてるんじゃナイ…!?」
「こっ…怖いこと言わないで貰えますっ!?」
「だってだってぇぇぇ〜!」
「…残念ながらその可能性は
完全に否定は出来ぬな…」
「「……ひぇっ……。」」
「ひっ……ひめーーーーっ!!
ねぇ、ドコーー!?
聴こえてたら返事してぇぇぇぇ…!!!」
聞こえてきた会話にもえは思い切り苦笑してしまった。
流石に心配症と過保護が過ぎる気がするのだが…
それでも『嬉しい』と思ってしまう辺り
すっかり毒されてしまっただろうか。
「ひーーッッーーめぇぇぇ……ッッ!!!」
スマイルの悲痛な呼び掛けに
もえはなんだか申し訳なく思えてきた。
「皆さん!
あの、どうしたんですか?」
「「「…!!!」」」
そう声をかけると彼らは動きを止め辺りをキョロキョロと見回していた。
「こちらです。上ですよ。」
「「「…………上?」」」
ゆっくりと視線を上げた彼らは自分の姿を捉えた様で
もえは軽く手を振ったが…
彼らは面白い程に狼狽えていた。
「ひっ…姫っ!?
な、ななな、何してるんスか!
ンなトコでっっ!!!」
「たっ…高ぁぁっ!!!
ああああ、あぶっあぶあぶっ
アブナイデショーーー!!!」
「……まさかその様な所に…。」
「風が気持ちいいですよ?
…少し、冷たい……ですけど。」
「ったり前っス!!!
今、真冬っスよ!!
風邪引くじゃねぇっスか!!」
「「降りて!!今、直ぐにっ!!」」
二人の様子にしょうがないなぁと苦笑して
もえは分かりました、今降りますね。と答え立ち上がろうとした。
「モエっ!」
「…はい?」
「動くでない!!」
「……えと…?」
「動いてはならぬ。
登るより降りる方が危険故。」
「あ…は…はい。」
彼の言わんとするを事を汲み取ったもえは動くのを止める。
それを見てユーリはその背の翼を広げ、もえの目の前までやってくると手を差し出した。
「さぁ、お手を。」
「…はい、ありがとうございます。」
差し出されたユーリの手に自分の手を重ねるとユーリはその手を握り軽く引き寄せる。
引き寄せた手を自分の胸元に誘導して身を預けさせるとその身体を抱き上げた。
「一体いつからここに?」
「ま、まだ30分と経っていませんよ。」
「しかしこんなにも身体が冷えているではないか。
手も頬も氷のようだぞ。」
「…そ、そうですか…?
そんな事も…ないと思うのですが…」
「………モエ…?」
「…う……ご、ごめんなさい…。」
「よろしい。」
ゆっくりと地上へ降りるとすぐさま二人が駆け寄った。
「怪我は!?
怪我してないですか!?」
「…あ……登る時に膝を擦りむいたくらいで…」
「怪我してるんじゃんっ!!」
「直ぐに手当しましょう!
オレ、救急箱用意しときますっ!」
「ユーリ、ホラ早く早く!
リビング戻るよッ!」
「「…………。」」
いそいそと戻っていく二人の背中を見遣って
二人は同時にふっと笑った。
「全く…騒々しい奴らだ。
モエの姿が見当たらないと騒ぎ出してな。」
「…あはは…すみませんでした。
会議してらしたので、いいかなぁって…」
「彼奴らは過保護の度が格段に増しているな。」
「…それは…
ユーリさんも…だと思いますけれど…」
「そんな事もあるまい。」
「…あります。
それじゃあ、もう降ろして貰えますか?」
「………それは了承致し兼ねる。」
「ほらぁ…」
「……では参ろうか。
二人にどんな文句を言われることか
知れているからな。
…歩き出す故、舌を噛まないようにするのだぞ。」
「むぅ…誤魔化しましたねっ。」
リビングに戻ると先に戻っていた二人は準備万端整えユーリともえを迎えた。
ユーリの定位置であるロングソファーに降ろされ
毛布で包まれた後アッシュによる手当を受ける。
軽度の擦り傷だと言うのに大袈裟に包帯まで巻かれてしまった。
それには文句の一つ二つ零したが
兄達はそれでいいのだと譲ることは無く
結局自分が折れる羽目になったのだった。
「まったく、姫はしっかり捕まえてないと
すーぐどっか行っちまうんスから…」
「ダメ!なんて言わないケド…
せめて一言教えてヨ。
それにあんな高さじゃ…
落ちたら一溜りもナイデショ?
もし大怪我でもしたらどうするのサ〜。」
「それ以前にッ!
姫はまだまだ本調子じゃないんスよ!
確かに安定しつつありますけど
つい昨日許可が出たばっかだってのに…
あんな無謀な事して…!」
「ソウダヨ!ソウダヨ!!
辛くなるのは姫自身なんダカラネ!」
兄達のくどくどしいお説教にもえはただただ苦笑する。
どうやら本当に相当な心配をしてくれていた様子ではあるが。
「姫、聞いてますか!?」
「聞いてるの、姫っ!?」
「き…聞いてます!
聞いてます、ちゃんと!」
二人に詰め寄られてもえは慌てる。
そこへ助け舟を出したのはユーリだ。
「…その辺にせぬか。
モエとて悪気があった訳ではない。
それにお前達…そこまでモエの自由を奪ってどうするのだ?
その様に束縛するのではそのうち愛想をつかされ嫌われてしまうぞ。」
「「ゔ…っ…」」
「だっ…だけどサ!
アレはダメデショ!?
落ちたらどーすんの!!」
「そうですよ!あの高さですよ!?」
「…ふむ。
確かにあれは少々危険だったな。
モエ、次からは一言声をかけてくれまいか?
私がエスコートしよう。」
「え!?
い、いえ、そんな、そこまでは…!
それに、もう木登りはしませんから
…大丈夫です。」
スマイルはもえの頬に両手で包むようにして触れる。
「姫?
ボクらは絶対ダメなんて言ってるんじゃナイんダヨ。」
「…解っています。
でも、もういいんです。
……満足、したから……」
満足したと言う割にどこか悲しげなその瞳を見て三人は口を閉ざした。
「……まぁ……姫がそう言うナラ…。
でも気が変わったらちゃんと教えてネ。」
「はい。その時はちゃんと…
お兄ちゃんにお伝えします。」
「…ウン、約束だからネ。」
スマイルはもえをぎゅうっと抱き竦めて
いつもの様に頭や背中を撫でるのだった。
夕方、アッシュはエプロンを纏いキッチンに立つ。
「さて。夕飯は何がいいですか?」
「何でもイイヨー」
「最近カレーとは言わぬな?」
「…まぁネ。
ボクもオトナになったってコトさ。
ヒッヒッヒッ。」
「200年以上かかってやっとっスかー。」
「…なーんかトゲがあるねェ…
わんちゃん?」
「わんちゃん言うなッ!
…全く…それのどこが
『大人になった』だか…」
やれやれと呆れてダイニングの席に座った二人に茶菓子を差し出した。
「姫は何が食べたいです?」
アッシュがコンロの前に立つもえに声をかける。
しかし彼女からの返答はない。
彼女は一点を見つめてぼんやりとしていた。
「……姫、もしや具合悪いんスか?」
その声にはっと我に返ったもえが慌てている。
「え!?な、なんですか!?」
真面目な表情でアッシュはもえの前に立ち、額に手を当てたが幸い熱は無い。
「熱はないですけど…疲れたんじゃ…」
「あ、いえ。
ちょっと、考え事を……」
そこまで言って失言だったと思い直す。
何故ならアッシュの様子が途端に不安げに変わったからだ。
「……してました。
………えと……ごめんなさい……。」
あの一件以降、彼らは特に神経質で。
心配を寄せていてくれる事が解るだけに酷く申し訳無くなる。
「謝ることなんてないっス!
……でも無理しちゃ、ダメですよ。」
「…はい。」
彼の暖かく大きな手が頭を撫でてくれる。
不安で詰まる胸のつかえが僅かに溶けていくように感じた。
「ところで姫。夕飯何がいいですか?」
「え?えっと…」
「二人とも特に無いみたいで。決まらねぇんスよ。」
「あ、それじゃあ…
オムライスがいいです。
それからツナサラダとかぼちゃのポタージュかな。」
「いいっスね、そうしましょう!
…あ〜でも…かぼちゃあったかな?
確かこの間煮付けにしちまって…」
がさごそと冷凍庫を漁る。
「あ。」
「ありました?」
「………煮付けの方なら…」
そう言いながら煮付けの入ったタッパーを手にする。
「…この煮付け、確か薄味にし過ぎたって仰ってましたよね?」
「…そうっスね…。
おかげで二人の口には合わなかったみたいっスよ。」
そう言いながら二人を見るアッシュだが
当の二人は素知らぬ顔をしている。
「…それなら…
このままポタージュにしちゃいません?」
「え…でもこれ煮付け…ですよ??」
「案外大丈夫かもしれませんよ。
お出汁で味は付いてますからあとは少し整えるだけですし
煮てあるから裏ごしもしやすいですよね。」
「……それは…確かに。」
「それに、失敗してもいいじゃないですか。
失敗は成功のもとと言いますし、次に繋がる知識が得られるかも。」
にこにこと笑みを湛えて
そう前向きな言葉を口にしたもえに
アッシュは思わず言葉を失った。
自分とて今までは料理に対しては貪欲に何でも挑戦してきたはずだった。
勿論失敗だって数知れない。
予想が外れて食べられたものでは無いものもあったし、逆に案外いけたものもあった。
そんな風に挑戦と失敗と成功を重ねて知識を得てきたはずだ。
それなのに、いつからこんなにも保守的になったのだろう。
まして彼女は今、自分には推し量れない程の不安を抱えている最中であると言うのに
こんなにも自分や同居人の二人を始め
ルークやロティ、ロストに加え仲間達のことに至るまで気遣いや心配をしている。
「………。」
「あの…アッシュさん?」
「あ…いえ!
…姫の言う通りだなって思って。」
自分を取り巻く状況や彼女を守りたいと言う強い想いが…無意識にそうさせて居たのだと気付く。
しかし彼女を守りたい想いと料理に対する想いは違うのだから。
「…そうですよね。
やってみなきゃわかんねっスよね!」
「そうです!
なので試してみましょう♪
それに…アッシュさんだったら
きっと美味しくアレンジ出来ちゃうと思いますよ?
『魔法の手』があるんだもの。」
そんな彼女だからこそ彼女を知り愛する誰もがこの笑顔を『守りたい』と願うのだろう。
それは自分や二人も例に漏れず…だ。
「…姫に美味しいって言って貰えるように頑張るっス…ッ!!!」
片手をもえの肩に置いてもう片手はぐっと拳を握り締めて。
力強くそう宣言するアッシュを見てもえは穏やかに微笑んでいた。
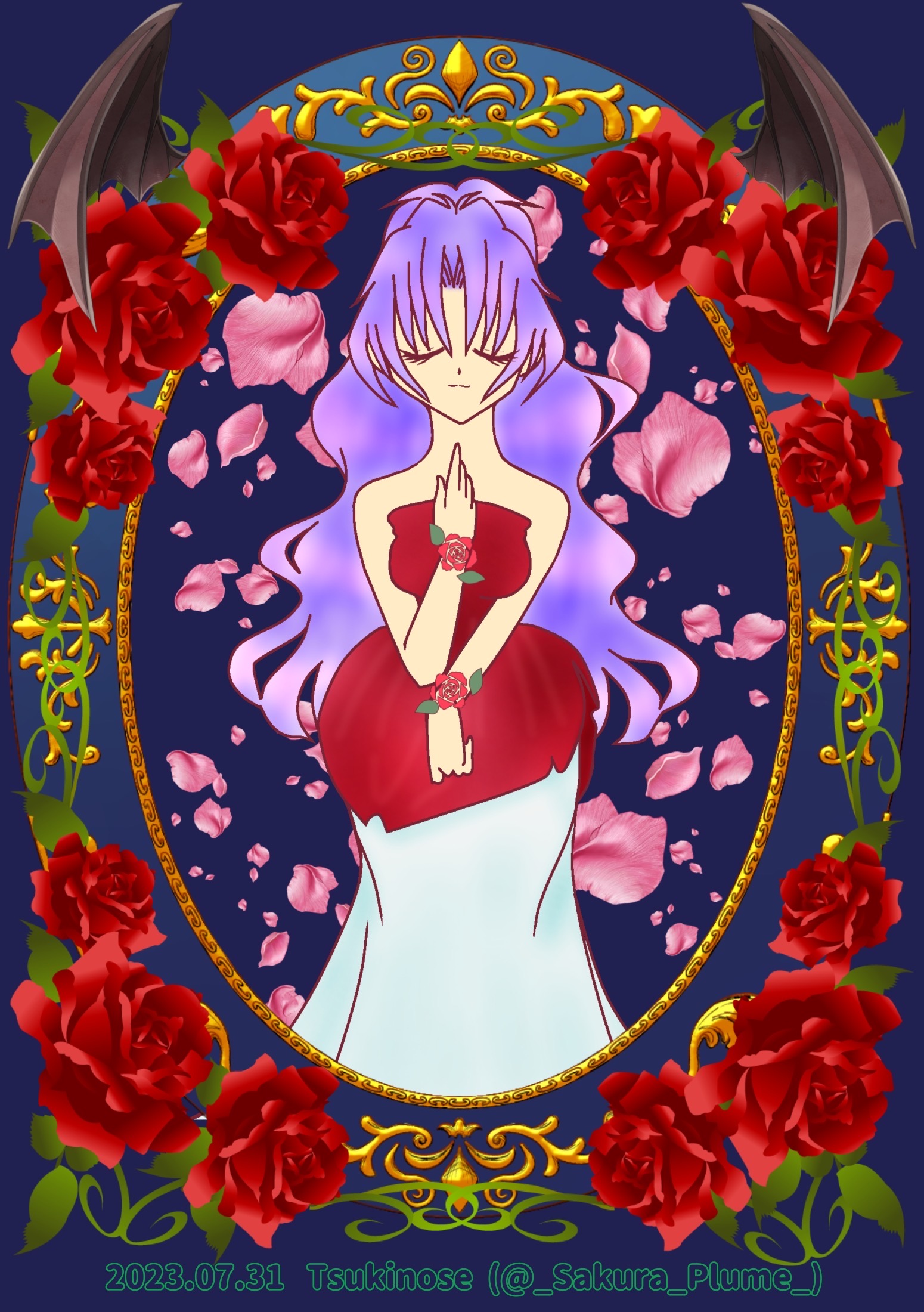
 月瀬 櫻姫
Link
Message
Mute
月瀬 櫻姫
Link
Message
Mute
 ステキと思ったらハートを送ろう!ログイン不要です。ログインするとハートをカスタマイズできます。
ステキと思ったらハートを送ろう!ログイン不要です。ログインするとハートをカスタマイズできます。

 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫