茨路〜守護〜
もえの復帰初日に際してどちらが彼女を送り届けるかを決める白熱のジャンケン合戦は五本勝負三勝二敗でスマイルが制した。
しかし、翌朝実際に彼女を送り届けたのはユーリであったという。
『…昨夜のあれはそう言う事だったのか。』
『ソウダヨ!!』
『そうかそれは済まないな。』
『…思ってないデショ。』
『ないっスね。』
『モエ、支度は良いか?』
『え、はい…』
『では、参ろう。』
『え、と…あの
ひとりで行けます、ので!』
『駄目だ。』
『ダメっス!』
『ダメダヨ!!』
『でもそれじゃ、意味がな…』
『いいですか、姫!
まだ完全に落ち着いたワケじゃないんですよ!』
『そうっ!
途中で倒れたらどうするノ!?』
『一人では急な体調の変化に対処しきれまい?』
『仕事行きたかったら
この条件は絶対に呑んで貰いますよ!!』
『わ、分かり…ました。』
『そうだ。それで良い。
…ではな、二人共。』
『はい、行ってらっしゃい。』
『イッテラッシャーイ。』
『…行ってまいります。』
玄関まで見送りに出ながら
スマイルは肩を落としていた。
『………さて、アッシュ…。
ボクらも仲良く買い出しという名のデートしてこよっかー…』
『そーっスねー。』
やや不貞腐れた様子のスマイルは半ばヤケになっていた様だ。
しかしながらアッシュもアッシュでノリが良い。
…台詞は全てまるで棒読みだったが。
そんな二人のやり取りを思い出すと何だかとても微笑ましく思えるもえだった。
ホールは動きが多く病み上がりの身体には負担が大きいから、と…厨房側に入るように言われたもえは慣れた手つきで注文の品を用意している。
厨房入口の両サイドには小窓があり
片方は丁度カフェ入口が視界に入る。
ドアベルの音が響く度、そこに視線を向けて誰が来たかをチェックし注文の予測を立てているようだ。
決まったメニューをオーダーするメンバーも割と多いため彼女は先手取って準備をしている。
そして彼女の予想は大概が当たっていてKKは感心したように呟いた。
「……すげぇな、嬢ちゃん。」
「何が、ですか?」
「注文予測だよ。
殆ど外さねぇじゃんか。」
「カフェにいらっしゃる皆さんはメニュー決まってらっしゃる方が多いですからね。」
「いや、だけどよ?
いつもと違うのも当ててんじゃんか。」
「ああ、それはいくつかパターンがあるんですよ。
今日のお天気、気温とか…
あとは噂として聞こえて来るお仕事の状況とか
そういうのも踏まえてみると結構分かりますよ。」
「いやまず、それ把握してんのがすげぇ。」
「そんなことないですよ。
ほら、女の子は大概お喋り好きですからね。
はい、KKさん。これお願いします。」
にっこりと笑顔を添えて手渡された注文の品を手にKKはおう。と答えてホールのメンバーの元へ持っていく。
またドアベルの音が響いて誰かがやって来たようだ。
やって来たのはピエールとジルの二人。
二人は紅茶やココア、ホットミルクのオーダーが多い。そしてこの時間ならば少し早めの昼食も兼ねていると思われる。
以上を踏まえるとオーダーはサンドイッチセット、若しくはホットサンドセット辺りか…。
そんな風に考えながら一先ずカップと、ティーポット、ココアの缶、紅茶のティーパック、砂糖のケースを目の前に並べた。
さりげなく食パンも戸棚から出しておき、更にホットサンドメーカーも温めておく。
「嬢ちゃん、オーダーだ。」
「はい!」
「サンド1、ホットサンド1、紅茶2だ。」
「お席はどちらですか?」
「2階。」
「分かりました。」
そんな問いかけをしながら既に紅茶の用意をしている。
予め盆に乗せていたティーポットに茶葉と熱湯を差してティーポットカバーをかけた後、ソーサーに伏せたティーカップとティースプーン、シュガーポットとミルクピッチャーを添えて盆に乗せ、KKに手渡した。
「先にお飲み物を。
熱くて危ないので階段はゆっくり上がってください。
あと、なるべく揺らさないでくださいね。
零れちゃいますから。
お渡しする頃には丁度美味しく飲めると思います。」
「…りょーかい。」
手渡したあと既に次の行動に移っているのを見てやっぱすげぇな…と感心するKKだった。
程々に客入りがあり、程々に忙しそうなカフェのカウンター席の隅でユーリはカフェの中を見渡していた。
ここはいつも通り変わらず賑やかで、なんだかほっとした。
そんな風に思うのはここのところ張り詰めていたからか…と溜息を零す。
抱える問題は解決した訳ではなく常に傍らにある。
それ即ち、いつでも危険と隣り合わせであると言うこと。
彼女が無茶を重ね、精神や肉体に影響を及ぼしやすいということ…だ。
それでも彼女は前を向いている。
自分たちの方が余程尻込みしている様だ。
「…おい、おじいちゃん。」
「KKか。何用だ?」
カウンターの内側からKKは手招きをする。
「?」
ユーリは立ち上がりカウンターの内側へと入る。
そしてKKは覗いてみろと言わんばかりに小窓を指さした。
促されるままにユーリがそこを覗くと、中ではもえが右往左往していた。
城でもあの様にアッシュと共に右往左往している事が多いため、まず見慣れた光景ではある。
「…すげぇな、嬢ちゃん。」
「…何がだ?」
「一人であんだけ出来るんだぜ?
俺がいる方が足引っ張っちまう。」
「ほう、それで貴殿はサボっているのだな。」
「いや、サボってねぇよ。」
「左様か。」
「…ありゃいい嫁さんになるなぁ…。
しっかり捕まえとけ?」
「元よりそのつもりだが?」
「愛想、尽かされないようにな。」
「……貴殿は嫌な物言いをするな。」
「ユーリタイプの奴は大体愛想尽かされるもんなんだよ。
傲慢だからな。気遣いとか優しさを履き違え易い。」
「…私に説教とは…。
そして言ってくれるな。」
「説教じゃねぇよ。アドバイスだ。」
「…心得ておく…」
「おう。…でもまぁ、大丈夫だろ。
嬢ちゃんの方もゾッコンみたいだからな。」
「…貴殿にはそう見えているのか…」
「俺だけじゃねぇと思うけどなぁ。
アンタらお似合いだぜ?」
「……左様か。ならば…良かった。」
ユーリはふと微笑んで再び小窓を覗いた。
「……KK。」
「ん?」
「済まないが…モエを止めてきてくれぬか。」
鋭い視線でそう言ったユーリを見てKKに緊張が走る。
「は?」
「少し無理をしているようだ。
倒れる前に休ませたい。」
「…分かった、連れてくる。」
「奥のボックス席に移動しておく故。」
「了解。」
カフェシフトの復帰は入ってみればいつもと何ら変わりなかった。
仲間たちが快く受け入れてくれた上、何かと気遣いもしてくれた。
特に女性陣からは無理をしない様にと厳しく言い含められてしまい、思わず苦笑した。
…おそらく神やDeuil面々に加えミミやニャミが根回ししているものと思われる。
改まってKKに呼ばれやって来た席にはユーリがおり、座るように促された。
「ユーリさん。
ずっといらしたんですか?
お帰りになったのかと…。」
促されるまま腰を下ろして向かい合う。
彼はテーブルに肘をつき微笑んでいる。
「初日だからな。
終了時間まで居るつもりだったのだ。」
「……それだと退屈しませんか?」
「皆、何かと親切に声を掛けてくれる故
退屈などしておらぬよ。
色々な話を聞かせてくれる。
…特に、今までモエが重ねてきた無茶の数々など…
大変興味深いぞ。」
「そ…それ、誇張されてませんか…」
「さぁ、果たしてどうであろうな?
私が聞いた話は実に『モエらしい』話ばかりであったが。」
「…………。」
「答え合わせでもしてみようか?」
やや意地悪にそう告げて愉しげに微笑む彼から視線を外し気まずそうにするもえが口を開く。
「……い、いえ……結構です。
…御遠慮します。」
そんな様子も新鮮で愛らしい。などと思いつつも少し虐めすぎたかと省みてユーリは話題を変えた。
「ふっ…左様か。
ところで、姫君。甘い物でも如何かな?」
「い、いえ。まだ勤務中ですし…」
「その話だが…
今日はここまでにしておいてはどうか?」
視線を落としたもえを見据えたユーリが静かにしかし厳しい声色で告げた。
「既に随分無理をしているのだろう?」
「…でも、流石にそれは…」
否定をしない。と、言うことは指摘は正しいと見える。
ユーリは静かに次の言葉を紡いだ。
「問題ない。
……Mr.KK。」
静かに名を呼べばいつの間にやらユーリの横にいたKKが返事をした。
「あいよ。」
「問題ないのであろう?」
「おう。元々俺もキッチンだからな。
嬢ちゃんには及ばんが引き継ぐぜ、任せな!」
彼はにっと笑って力強く頷いた。
確かに彼も手先が器用で何も心配もないが…少しばかり寂しい気持ちもあり、もえの心中は複雑だ。
「今日頑張り過ぎたら明日来られなくなるだろ?
そしたら明日出の奴らが寂しがるぜ。
楽しみにしてる奴多かったからな。
だから今日の所は帰って休め。」
そう言って笑ったKKがぽんと頭に手を置いてその無骨な手には似合わない優しい手つきで撫で回した。
「「…………。」」
「…何だよ、ユーリ。
いいじゃねぇの、ちょっとくらい。」
「何も言っておらぬであろう?」
「よく言う。
その目がありありと語ってるだろうが。」
「……あと10秒だけ待ってやろう。」
「ケチケチすんなよぉ、おじいちゃん。」
「7……6……5……」
「わーったよ!!
…ったく…おっかねぇなァ…」
大袈裟に両手を上げて溜息を吐いた。
「…ってなワケだ。
また明日な、嬢ちゃん。」
ひらひらと手を振ってKKは厨房へと戻って行った。
「………。」
あからさまに沈んだ様子の彼女を見てユーリはどう言葉をかけようかと迷う。
周囲の仲間達は敢えてそっとしていてくれている空気を感じている。
「…城に帰る前に寄りたい所があるのだが、寄っても構わぬか?」
ユーリは冷めきった珈琲を飲み干して静かにカップを置くとそう問うた。
特に断る理由もないもえはそれに小さく頷いて答える。
それを見たユーリが席を立ち『立てるか?』と手を差し伸べれば、彼女は疲労が滲み出た表情に無理な笑顔を貼り付けて『大丈夫です』と答えるのだった。
ユーリが立ち寄りたいと言っていたのは
クリスマスに訪れた城下町にある王室、貴族御用達商店街の宝飾店だった。
どうやら事前に来店予約をしていた様子で、特別室に通された二人はスタッフに促されるままソファーに腰を降ろした。
程なく店のオーナーがやってきて恭しく頭を下げると向かい側に座る。
「この度は当店への御来店ありがとうございます。
お問い合わせの件で御座いますが『アミュレット』に加工するための宝石は種類とサイズに制限が御座います。」
「ああ、承知している。
候補はルビー、サファイア、ダイヤモンド、エメラルド、アクアマリンだ。」
「畏まりました。御用意致します。」
オーナーは控えていた店員に合図を送り、店員は直ぐに部屋を出て行った。
「付与される効果は決めておられますか?」
「物理防御と魔法防御だ。」
「でしたら一つの宝石に二つの付与を施されるのでは無く物理防御で一つ、魔法防御で一つの方が効果的です。」
「それも承知している。
確か物理防御はサファイアかエメラルドが
魔法防御はルビーかアクアマリンが
ダイヤモンドはどちらにも適していたと記憶しているのだが間違いないか?」
「はい。流石で御座いますね。
しかし、吸血鬼族の皆様は
わざわざこう言った品をお求めになる事は少ないかと思うのですが…」
「うむ。
確かに我々の種族は必要にはならぬな。
此度も私自身の物では無い故。」
オーナーは穏やかに微笑んで『なるほど、そうでしたか。』と納得した様に告げた。
そこへ店員がいくつかの黒い小箱を載せたワゴンを押してやって来る。
それらを丁寧にずらりとテーブルに並べた。
「ダイヤモンド以外は原石を御用意しております。
全てこれから加工を行いますので三月程お時間を頂くのですが…」
「三月で仕上がるのか?」
「お得意様ですので、三月で仕上げさせて頂きます。
少しでも早く対策を…とお考えでしょうから。」
「それは頼もしいな。宜しく頼む。」
「はい。それでは…」
宝飾店のオーナーとユーリの会話を黙して聞いていた。
オーナーは人間の様に見えるがスタッフの中には明らかな非人間族も居るようだ。
宝飾店ということもありセキュリティ強化を兼ねているのであろうか…。
「モエ。」
「は、はい…!」
そんな事を考えていた矢先に名を呼ばれて驚く。
「何でしょうか?」
「好きな石を選ぶと良い。」
ずらりと並べられた原石とカタログを指さしてユーリは告げた。
「……え、と…?」
「遠慮などするな。
これはモエの身を守る為の道具だ。」
「………わたし…?
わたしの買い物だったんですか??」
「ああ、言っていなかったか?」
「聞いていません。」
ユーリのそらとぼけた白々しいその表情に、もえはややむっとした様子を見せる。
事前に言ってしまえば突っぱねられる事を知っていたからこそ彼はわざと何も言わずにここへ連れて来たのだろう。
目の前に並ぶ未来の宝石達は一体いかほどの金額なのか…聞くのが恐ろしい。
「ユーリさん、あの…」
「『不要』とは言わせぬぞ。
不要であるならば元より来てはおらん。」
「…でも…」
「茨の道を往くと決めたのであろう?
…ならば是が非でも。」
「………。」
「お嬢様。大変差し出がましいのですが
宜しいでしょうか?」
「は、はい…」
「『アミュレット』とは『御守り』の意です。
魔力と共に術式を素材の石に刻み、封じる事で『人工魔石』となり…また、それらを加工する事で『アミュレット』となります。
地球で言う所の『御守り』とは異なり
身を守る為の実用的な『魔具』なのです。
お嬢様は人間でいらっしゃる。
ユーリ様が仰った様に『耐物理』『耐魔法』の二種はお持ちになった方がよろしいかと。」
「ですが、そんなに高価な物は…」
「確かに高価ではあります。
しかしながら素材の石は何でも良いと言う訳ではなく良質な素材でなければ高度な術式や強い魔力には耐えられないのです。
ですが、それらは強く高度である程『アミュレット』として長持ちしますし、何よりユーリ様程の魔力に耐えうる素材は少ない。
…術式はご自分で刻まれるのですよね?」
「無論。」
「でしたら、ここにお出しした物でもやや厳しいかもしれません。」
素材となる石はただ単に硬度が高ければ良いという訳でもないらしい。
込める術式の種類によって石との相性がある様で、相性が合わなければその負荷に耐えきれず術式や石そのものが破壊されてしまいアミュレットとして精製出来ないのだ…とオーナーは語る。
「宝石は持ち主を『呼ぶ』と言う。
俗信的な話ではあるがあながち間違ってはいない。」
「はい。宝石のみならずパワーストーンが人気であるのもそれを裏付けていると考えます。」
どうやらユーリとオーナーはとても気が合う様子だ。
城にいる時のように穏やかにリラックスしているその様子からもそれがよく伺える。
「さて、蘊蓄はこの辺りにして…」
「ええ、左様で御座いますね。
ではお選び頂けますか、お嬢様?」
「あ、はい…。」
「「……………。」」
帰宅したユーリともえは黙りを決め込んだままリビングのソファーに座っていた。
二人のただならぬ様子にアッシュとスマイルの二人は
『…ナニ?ドシタノ?』
『知らねぇっスよ。』
…と視線で会話する。
アッシュは静かに紅茶を差し出して成り行きを見守った。
「…怒っているのか?」
先に口を開いたのはユーリだ。
「…怒っています。」
「何故?」
「…お分かりなのでは?」
「さて…皆目見当もつかないな。
教えて頂けまいか?」
そのすまし顔は実に白々しい。
分かっているくせに…と思わず口にしてしまいそうになるのを何とか抑えてもえは言葉を紡ぐ。
「…なんで、何も言ってくれなかったんですか。」
「ふむ。
言ってしまえばモエは反対するであろう?」
「当たり前です!」
「故に言わなかった。」
悪びれもせずに、淡々と告げるユーリに
もえは深い溜息を零す。
「…あんなに高価な物を
幾つもぽんぽん買うなんて…」
「私の財産だ。構わぬだろう?」
「そう言う問題じゃありません!
勿体無いって言ってるんです!」
「何故、勿体無いと?」
「あんな高価な宝石たちに見合う価値がわたしにあるとは到底思えないから…。
だから、勿体無いんです。
完全に宝の持ち腐れです!」
「何故その様な事を言う。」
「事実でしょう!」
「そんな事はない。決して。
寧ろ随分控えめ過ぎたのではと省みているところだ。」
「…ゆ…っ……ユーリさんは…っ…
今、ある意味盲目状態…だからっ
そんなことが言えちゃうんですよぉっ!」
「「「………。」」」
もぉぉっ!と怒りを全身で表しながらもえは勢いよく立ち上がるとダイニングへ引っ込んだ。
「……私は、盲目…か?」
「デショ。」
「ですね。」
「……………そうか。」
彼女の顔が赤かったのは怒りによるものか
はたまた別の理由か…。
何れにせよ新鮮で愛らしい。
等とユーリは呑気な事を考えていた。
アミュレットの引渡しは三ヶ月後である。
しかしその三ヶ月間を凌ぐ目的として
ユーリは帰り際にペンダントを一つ購入しもえに預けた。
それは薔薇の花とリボンの模様があしらわれた月長石のカメオでそれなりに高価なひと品だ。
彼はその場でペンダントに簡易的な術式を刻み自分の首にかけた。
『極力身に付けているように。』と
強く念を押して…
散々高価な宝石を取っかえ引っ変えし
結局全種類の原石を一つずつ購入した挙句のその行動にもえはふつふつと湧き上がる怒りを覚えてしまった次第である。
ダイニングテーブルに突っ伏したもえは深い溜息を吐いた。
微かに響く物音がダイニングに誰かが入ってきた事を報せる。足音が二種類。
そのうちの一人が自分の頭をくしゃりと無言で撫でた。
「…何かご用ですか…」
「疲れてるデショ。
こんな冷えたトコにいたらまた熱が出るヨ。」
「お茶入れ直しますね。」
「………。」
かたん。と音がしてスマイルが席に着いた様だ。
キッチンの方から音がしてアッシュがお茶を入れる準備をしているのが分かった。
「…まァ、ユーリはサ。
群を抜いて金銭感覚オカシイカラ。
怒ったって仕方ナイヨ。」
「…………。」
「……姫は、嬉しくなかったっスか?
ユーリからのプレゼント。」
「………。」
「「………姫?」」
「………ない…」
彼女のくぐもった小さな声に二人は耳をそばだてる。
「……嬉しくない……」
「「…え…?」」
「わけ……ないじゃないですか…」
その言葉に二人は思わず安堵して顔を見合った。
「…どれだけ大切にしてくれているのか
どれだけ心配くれているのか…
今は…よく、 わかるから…」
「だったらサ。受け取ったげてヨ。」
ネッ?とスマイルがひと押しをする。
子供のように無邪気なその笑みは微笑ましいと思いつつやはりどこか釈然としないもえなのだった。
乱雑に資料や筆記用具が散らばるリビングテーブルの上…ちらりと視界に入った資料を見る限り、どうやら新曲お披露目の際の衣装デザイン案のようだ。
衣装デザインを任せたデザイナーから送られてきたものだろう。
そのデザイナーはDeuilのファンとして知られている上、Deuilの女性ファンである【乙女達】から支持の厚いデザイナーであると共にひょんなことからユーリ直々に衣装デザインを依頼する運びとなった強運の持ち主でもある。
「皆さんお疲れ様です。
お茶は如何ですか?」
真剣な面持ちで各々が作業に打ち込んでいる。
余りに真剣でどこか声をかけにくい空気ではあるのだが午後三時を過ぎ…詰めすぎるのも良くないだろうともえは意を決して声をかけた。
三人は同時に顔を上げ、そしてこちらを向くと一様に柔らかく笑みを浮かべた。
「あ、ありがとうございます。姫!」
「さっすが姫〜!
丁度欲しいと思ってたんダ〜♪」
「気遣いありがとう、モエ。」
各々そう口にして一斉にテーブルを片付け始め、あっという間に綺麗になった。
仕上げにアッシュが布巾でテーブルの上を拭きあげると待ってました!とばかりに再びこちらを見て笑った。
その表情はまるで無邪気な少年のようで思わずふふっと零れてしまう。
もえは各々の前にティーカップを置いて
中央には大きなティーポットを置いた。
「あと少し蒸らしてくださいね。」
「了解っス!」
「それからクッキーを焼いてみたんですがお召し上がりになりま…」
「食べるッ!!」
言い終わる前に身を乗り出してスマイルが声を上げた。
それも微笑ましくてまた笑ってしまう。
「わかりました。お持ちしますね。
お茶は先にどうぞ。」
そう言って立ち上がるとヤッターと子供のようにスマイルがはしゃいでいた。
「モエも同席してくれるのであろう?」
「え、でも…お仕事中ですし…」
「……して…くれぬのか……」
あからさまにしょんぼりとした城主にもえは慌てる。
「で、では、あの…少しだけ…」
そう答えると彼は大層嬉しそうにそうか。と笑う。
それには…ああ、またのせられた…と苦笑するもえだった。
ユーリの隣に腰を据え、お茶をしながらの会議に耳を傾ける。
…しっかりと腰に腕を回されていて身動きが出来ない。
「この衣装より、こっちがよくないっスか?このモチーフとか。」
「だったらサァ、コッチの衣装にアッチの衣装のエンブレム持ってきたらどう?」
「…ふむ。悪くないな。
アッシュ、どうだ?」
「…うん、それならいいと思います。
色もまとまってるし、目も引くし。」
「そしたらユーリの衣装のこの部分の色、もう少し淡くてもいいカモネ!」
「そっスね。ユーリの衣装はどちらかと言うと貴族寄りですし。」
「そーそー。フリルとかばしばしだもんネ!」
「ユーリのネイルはどうします?合わせますか?それともいつもの黒か赤か…」
「……面倒だ。
ネイルはせずとも良いだろう。」
「「えーーーー!!」」
「ボーカルがマイクを持つ手は目立つっスよ!」
「そうそう!一番見える所、勿体ナイ!」
「姫もそう思うっスよね!?」
「姫もそう思う、デショ!?」
「え…!?」
「「ねっ!?!?!?」」
「え……ええ。」
唐突に話を振られてもえは苦笑する。
「お前達、モエを困らせるでない。」
「だってェ…
すーぐめんどーってゆーからァ…」
「そっスよ!
それに姫の意見は貴重でしょう?」
「……それは間違いないが……」
二人の熱量にユーリはやれやれと溜息を零した。
「お二人ともユーリさんのこと、大好きなんですよ。
だから最高にかっこよくきめて欲しいんです。
…もちろん、わたしもそう思っています。」
素直なその言葉にユーリはやや赤くなって視線を泳がせた。
「……ぜ、善処する…。」
「ふふ、はい。是非お願いします♡」
帰宅した時の二人はやや険悪で心配もしたが、すっかりいつも通りな今のそんな様子を見て杞憂であったと安堵する。
そして微笑ましそうに見守るアッシュとスマイルにユーリは『何か言いたいことでもあるのか!?』と詰め寄るが、二人は何やらニヤニヤとしながら『『別にー?』』とはぐらかして相変わらず息がぴったりであった。
夕飯を済ませた後、リビングで寛ぐユーリとスマイルが雑談を交わしている。
そこへ片付けを済ませてやってきたアッシュともえが合流した。
「お疲れ様、二人共。
今日もありがとう。」
「オツカレサマ!アリガトネッ!」
最近の二人は良くこうして感謝の言葉を口にする様になった。
それは間違いなく彼女の影響である。
「どういたしまして…っス。
ユーリもスマもお疲れ様です。
それから姫も。」
「いえ…わたし大したことは…」
「んな事ねぇっスよ。
いつも言ってるけどオレすんごく助かってるんですよ。」
「そ、そうですか…?」
「ええ!」
「だったら嬉しいです。」
そう言って笑ったもえにユーリは『こちらへ』と手を差し出した。
その手は白く綺麗でしなやかだ。
もえがきゅっと握り返すと彼はその手を引いて手の甲に口付けを落とす。
一連の動作は大変美しくいつも見惚れてしまうもえだった。
「あ〜…!!そだ!アッ君アッ君!
そーいえばサ!
例のハナシ…なんだけど、サ?」
「え?…あ…!
ああ、アレ、っスね!!
えと…じゃあ、ダイニングでしますか。」
「オッケ!オッケ!
じゃーボクら、ちょと行ってくるネ!」
そそくさと立ち上がってダイニングへ引っ込む二人をもえがきょとんとして見送る。
ユーリは…気を遣ってくれるのは有り難いがもう少し自然に出来ぬのか…とやや苦々しい表情だ。
「…もしかしてわたし、お邪魔でした…?」
ぽそりとそう零したもえをユーリは横抱きに抱え上げる。
「否。…不自然が過ぎたがあれは口実だ。」
「口実…?」
「そう。私に気を回したのだろう。」
「……あ…」
ユーリの言葉の意味を解したもえはその顔を真っ赤に染めて俯く。
力強い腕に抱き竦められながら。
「折角二人が気を回してくれたのだから堪能させておくれ。」
そっと頬に手を添えて導くように上を向かせられる。
綺麗な紅玉の瞳が柔らかく微笑んで、目を奪われるほどに美しかった。
視線を落とすと自分の手に添えられた彼の手がよく見えた。
細く長い指はビスクドールのそれのように整っており、爪も艶やかで綺麗な形だ。
「…ユーリさん、ハンドケアはどうしてるんですか?」
「ハンドケア?
…特に何もしてはおらんが…」
「ハンドクリームとか、ネイルオイルとかも?」
「そうだな。自身でしたことは無い。
ネイルを頼んだ際に施術してもらったことならあるが…。
ああ、確かマコト…兄君だったな。」
彼の技術は実に素晴らしいな。と彼が呟くのを耳にして自分のことでは無いというのにどこか誇らしくもあり、くすぐったい。
「ネイルはいつもどうしているんですか?」
「専属で任せている故マコトが施してくれることが多いが…時折スマイルがするな。
なかなかに手先が器用故上手くして退けるぞ。」
「あ、わたしもスマイルお兄ちゃんにトップコート塗って貰ったことあります。
確かにとってもお上手ですよね。」
「うむ。
だが余りに嬉々としてやって退けるのでな…まるでヤツのプラモデルにでもなった気分になるのが少々解せぬ。」
ユーリの言葉にふふふっともえが笑う。
「それはきっと…本当に嬉しいんですよ。」
「嬉しい?」
「ええ。
だって沢山の視線を浴びる方の一番目立つところを自分が手がけられるんですもの。
しかもそれが大好きな人だったら…
そんなに幸せな事ってないじゃないですか。」
「…その着眼点はモエならではの様な気がするな。」
「そうですか?」
「彼奴はそこまで深く考えておらぬだろう。何せ気まぐれだ。」
「ふふふ…」
「…何だ?」
「そんな事言ってても嬉しそうじゃないですか、ふふっ」
「………。」
「ふふふふっ。
恥ずかしがらなくていいと思いますよ?
むしろ素直に嬉しいって伝えてあげてください。」
その言葉にやや赤らむ顔で『別段嬉しいという訳では…』と告げるユーリを前にもえは更に楽しげに笑う。
ユーリはひとつ咳払いをして続けた。
「モエ…?
大人を揶揄うものでは無いぞ?」
「あら。大人が子供をからかって楽しむのだって十分に悪趣味だと思いますけれど。」
「…言ってくれるな…。」
「お互い様です。
それに、偶にはわたしも反撃しないと
フェアじゃないでしょう?」
「何を言う。元々モエに分があるのだからフェアになどならないだろう。」
「いつわたしに分があったんですか?」
「……いつも、だろう?
我々は姫君に頭が上がらぬからな。」
「それは大袈裟な物言いではないですか?」
「何が大袈裟なものか。
我々は姫君に絶対服従さ。」
「…相変わらず嘘がお上手ですねぇ。」
「嘘などではないぞ。」
改まってユーリが向かい合うように体を向けると右手の指を絡め組むようにする恋人繋ぎをして、左手はそっと取る。
「モエの方こそハンドケアをせねばなるまい。水仕事で少々荒れている様だぞ。
そもそも、その様なことはアッシュに任せるが良かろうに…。」
絡められたユーリの手指をしっかり握り返してもえは笑う。
「わたしがしたいんですよ。
それにアッシュお兄ちゃんばかりに家事が寄ってしまうのは負担が大きすぎますから。」
「しかしモエはアイドルなのだぞ。
近く女優業に転身する予定になっているだろう?
手元はしっかりとケアしておかねば。
二人とてそう言うに違いない。」
「…もう…本当に甘いんだから…」
「それはそうだ。
それこそが我々の役目なのだから。」
そう言って顔を近付けるユーリは額にちゅっと唇を落とす。
「…先程の様子では外してしまうのではと心配していたが…ちゃんと身につけてくれているようだな。」
彼の探るような視線にもえは頬を赤らめる。
「…はい…。」
「あくまでも仮故、大した効果は期待出来ぬが…ないよりはマシのはずだ。
何時いかなる時も身に付けておるのだぞ。」
「…はい、分かりました。」
素直なその返事に満足そうな様子で『今度はペアリングを新調しようか。』と微笑むユーリにもえは『これ以上の散財はいけませんっ!』と跳ね除けたのだった。
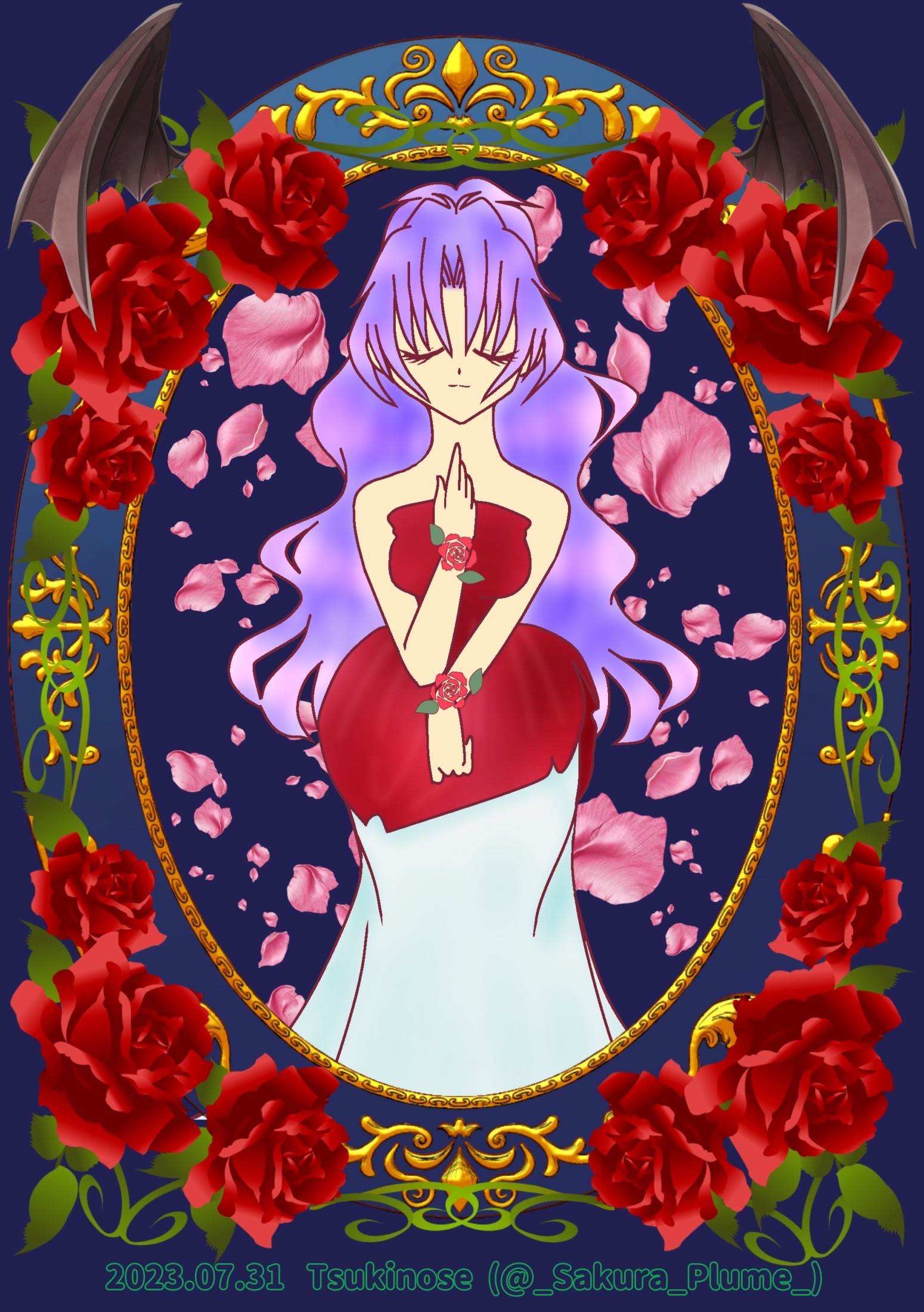
 月瀬 櫻姫
Link
Message
Mute
月瀬 櫻姫
Link
Message
Mute


 ステキと思ったらハートを送ろう!ログイン不要です。ログインするとハートをカスタマイズできます。
ステキと思ったらハートを送ろう!ログイン不要です。ログインするとハートをカスタマイズできます。

 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫 月瀬 櫻姫
月瀬 櫻姫