すばる・すば右ついった小ネタログ■七番目の男(蒼星+響也+昴)
「どう思う?」
閑散とした事務所の窓からは、やわらかな午後の日差しが注いでいる。静寂のなかに降り積もり続けるタイプ音をふいに崩して投げられた声に、橘蒼星はパソコンのディスプレイに向けていた顔を上げて背後を振り返った。
「どうって、……ああ、『彼』のこと?」
「そう」
確かめるように返した視線の先では、ソファに腰掛けた響也が遅い昼食を摂っている。公演期間のあいまにぽつりと落ちた休演日であっても、山積した書類仕事を片付けるために出勤しているふたりだったが――今日はこの三十分ほどあとから、書類仕事以外の予定がひとつだけ入っている。
「まあ……いまのうちの状態で新しい団員を加えるっていうのは、正直、厳しいよ。いくら未経験だからって、決まってる分より給料を下げるわけにはいかないし」
「うーん……そう、だよなあ」
予定というのは入団希望者の面接であり、ことの発端は昨晩、公演終了後に遡る。
ロビーで終演後のアンケート回収をしていたはずの受付スタッフのひとりが、困惑顔で響也と蒼星を呼びに来たのである。
曰く随分と熱烈な入団希望の青年がいる、どうしたものか、とのこと。
むろん、基本的にはまず名前と連絡先だけを預かって詳しいことは後日とするよう、カンパニー内での対応は決めてある。それでも、『待ってますから、少しでいいので担当の人と話をさせてください、お願いします』と頭を下げられ続けてついぞ返答に窮し、ふたりのもとへやって来たらしい。どうしましょう、と答えを求めるスタッフに、響也は目瞬きひとつでこう尋ねた。
『それってもしかして、最後まで席に残ってたお客さんじゃないか?』
ことミュージカルにおける彼の観察力と直感力については長年の付き合いのなかで何度も驚かされてきた蒼星だったけれども、この件についても例に漏れず――結果からいえば、しばらくしてスタッフと共に事務所へやってきたのは響也の言った通りの青年だった。
「あのさ、蒼星」
響也が、ぽつりと蒼星を呼びながらタマゴサンドを齧り取る。それから、氷の泳ぐレモンティーのグラスをほんのすこし傾けて、言った。
「俺、昨日、『見つけた』って思ったんだ」
「え?」
「あのホンの、最後のひとり。――ずっと埋まらなかった、『フェルナンド』」
「……響也、それって」
ぽかんと口を開けて、思わず蒼星は幼馴染の端正な顔を凝視するように見つめ返した。
他界してなお日本のミュージカル界に名を響かせ続ける朝日奈真が遺した、未完の脚本。遺稿を見つけてからというもの響也はほうぼう手を尽くして物語を完成させられる脚本家を探しながら、並行してキャスティングを行なっており、そちらは最後のひとりを残すのみとなっていた。
クライマックスを前に絶筆となった物語には、七人の主役がいる。 最後の空席が、彼の言う『フェルナンド』だった。得体の知れない高揚にさざめく感情を深呼吸で宥めつけて、蒼星は彼を呼ぶ。「響也」
「さっきも言ったけど、これ以上メンバーを増やすのは難しいよ。スポンサーが降りるかもしれない状況で、まったくの未経験者をいきなり入団させるのは、あまり現実的とは言えない」
「……蒼星、」
「でも、響也が『どうしても』って思うなら、俺はとめない」
だって、お前の力になるために俺はここにいるんだから。
幼馴染への親愛と自負と意地を込めてそう続ければ、響也は目を丸くして目瞬きを数回繰り返したあと、ありがとうと言って笑う。
事務所に威勢のいいノックの音が響いたのは、それからおよそ二十分後のことだった。
***
20170508Mon.
■フロム、地球のかたすみから(まどかと昴)
「オレ、子どものときさ、いま立ってる道をずうっとまっすぐ走っていったら、地球をぐるっと回って同じところに帰ってこれるって思ってたんだ」
ロードワークのコースの途中にある運動公園のベンチに並んで腰掛けて、ささやかな休息にゆっくりと息を吐く。スポーツドリンクで喉を潤した彼が、幼さの残る横顔でふいにそう言って笑った。男の子らしいかたちの指先がひとつ持ち上がって、目の前に広がった道をまっすぐに指し示す。
「ふふ、昴くんならなんだかできちゃいそう」
「えっ、ホント?」
「うん」
その指先の向こうにある道はきっと、どこまでも続いている。
失くした夢の傷痕を残しながら、それでも伸びやかに力強く舞台へ立つその足が駆けていく先に、一緒にいられたら良い。碧い芝生と、青い空と、風に揺れる明るいひとみと髪がなぜだかとても眩しく見えて、目を細めながら頷いた。
***
(ふたりへのお題ったーhttps://shindanmaker.com/122300/『まあるい地球の片隅で』)
20170830Wed.
■ミラージュお稽古
ダガーナイフを両手に携えた男が、美しい調度品で飾られた屋敷の廊下を息を潜めて進む。獣のように足音と気配を殺し、壁と遮幕伝いに忍び込む先は、屋敷の主である富豪の私室だった。
屋敷の中心部に位置するその部屋の周囲は人払いがされているのか閑散としており、敷地への侵入時にほとんど騒ぎにさえならないごく少数の傭兵を始末する程度の手間で済んだのは幸運と言って良いだろう。
身を隠していた遮幕から抜け出して、富豪の男の首筋を掻き切るために走らせたダガーナイフの切っ先は、しかしその直前で空を切る。
すらりと、弦月を思わせる湾曲したシルエットの細身の片刃刀――シャムシールを構えた男の視線が、暗殺者を捉えた。
「ここまで来たのだ。今宵は存分に楽しませてくれるのであろうな?」
国王と繋がりを持つほどの莫大な富を持つ男は、他者から命を狙われることに慣れていた。傭兵を呼びつける悲鳴を上げるでもなく、余裕さえ湛えた低い声で楽しげに投げられた問いに、暗殺者である男は応えなかった。ぐ、とその長躯を撓め、床を蹴りつけてひといきに距離を詰める。
翻って自身を迎える長刀を、上段に大きく振りかぶっての左の一太刀目で力強くはじき返す。右手に構えた二太刀目を懐へ捩じ込みかけたところで、富豪の男の長い脚がしなやかに振られて暗殺者の体側を蹴り飛ばした。暗殺者は獣の動きで受け身を取りながら間合いを整え、低い姿勢のまま俊敏に立ち回って富豪の手首を捩じり上げる。床に落ちたシャムシールを遠くへ蹴り、ダガーの切っ先が喉元へ躊躇いなく突きつけられた。
静寂。あとほんの十数秒のうちに、暗殺者は自らに課した役目を果たし遂せる、はずだった。
富豪と暗殺者の対面を、ピンスポットライトが不意に射貫く。同時に鳴り響くピアノとヴァイオリンの高い音色が、偶然主人に呼びつけられていた奉公人の少女を場に登場させた。
「逃げろ、サニヤ!」
富豪の男、ファルークが、暗殺者と対峙した瞬間浮かべていた冷笑めいた余裕を捨て去って少女の名を呼ぶ。刃物を突きつけられていることにも構わず少女を逃がそうと叫ぶ富豪の喉に、暗殺者が振りかざしたダガーの切っ先が迫るのと同時に、少女の大きな悲鳴が響く。
目的は富豪の命だけだったが、目撃者は始末しなければならない。暗殺者が目瞬きの間に富豪から少女へと刃の標的を変える。彼女に悲鳴を上げる暇も与えず、男は少女の首にダガーを押しあてた。
「……女。お前には悪いが、この場で死んでもらう」
鋭く磨かれた刃が細い首筋を引き切る寸前、駆けつけた護衛たちが、富豪を守るように取り囲む。完全に目的の遂行を阻まれたことを悟った暗殺者が、舌打ちをひとつ。
「舌を噛みたくなければおとなしくしていろ」
少女を救うよう叫ぶファルークの声と、鍵盤と弦の高音が絡み合い、少女を人質に退却する暗殺者の姿とともに尾を曳いて袖へと消える。
暗転。
場面転換。
「――そこまで!」
パン、と、手を打つ音が舞台に響いた。
「本当はこのまま続いていくところだけど、いまは一旦ここで切るよ。仁兄、昴、どうだった?」
客席から一連の流れを眺めていた響也の声に、舞台上に立つファルーク――仁と、下手側の袖から戻って来た昴がちらとお互いの顔を見合わせて、どちらが先に答えるかを視線だけでやり取りする。まず口を開いたのは仁だった。
「アクションの流れ自体は、演じる側としては舞台上で動いてみても特に違和感はなかったかな。動きのテンポが速めだから、客席から見てわかりづらくなければいいけどね」
「うーん……そうだな、もう少し動きを大きくしてもいいけど、間延びして緊迫感がなくなるといけないし。昴、そのあたりの調整できそうか?」
先ほどまでの立ち回りを振り返った仁の応えを受けた響也が、その隣の昴へと水を向ける。響也の問いに思案を巡らせつつ頷いた。
「はいっ。衣装もできてきてるし、それ着て動きやすいかどうかも含めて考えてみます」
「ああ。頼むな」
次回公演『ゴールデン・ミラージュ』で、昴は中核人物のひとりである大富豪ファルークの命を奪おうと暗躍する暗殺者・ターヒルを演じる。願いを叶える魔法のランプを軸に登場人物たちのさまざまな思惑が錯綜する本編の中でも、ファルークとターヒルが対峙するシーンはとりわけ緊張感のある場面だ。
***
(没原稿ぶったぎり供養)
■ブラバンお稽古(まどか+陽向+昴)
劇場内のひと気も徐々に減り始めた、午後八時過ぎ。機材の確認のために立ち寄った舞台袖に見慣れた小柄な背中を見つけ、声を掛ける。
「陽向くん?」
「わっ……、ああ、おねーさんか。びっくりした~」
驚かせないようなるべく抑えた声で話しかけたつもりだったけれども、どうやら随分と集中していたらしい。彼はびくりと肩を竦ませてこちらを振り返ったあと、小さな息を吐きつつ相好を崩した。
「こんなところでどうしたの?」
「んー?衣装のチェック、かな」
「え?」
今日は午後の最初に衣装合わせがあり、夕方まで衣装を身につけての通し稽古が行われた。衣装デザインを担当している彼が、居残って衣装チェックをしている、という答えは合点がいったが、いまの彼の周りに衣装はひとつもないように見える。首を傾げてみせると、数歩先から指先でちょいちょい、と手招かれた。呼ばれるままに隣に並ぶと、明るいステージライトの向こうから足音と小さな声が聞こえてくる。
「ホントは客席から見たいんだけどさ。すっごい集中してるから、なーんかジャマできなくて」
呆れたような、けれどもどこか楽しげな声とひかりの先へ目を向ける。白と金、空色と赤を基調にデザインされた爽やかなマーチングバンドのユニフォームの長い裾が、日差しのように降り注ぐ照明の下でばさりと大きく翻った。
「!」
力強く溌剌とした靴音に紛れて聞こえるのは、ステージにひとり立つ彼が口ずさむカウントの声だと気付く。それと同時に、高く頭上に投げられた赤いドラムメジャーが最高点に達し美しい円を描きながら落下を始める。
あざやかな赤が重力に従って床へ落ちきるまでのほんの数秒の間に、しなやかな長躯がステージを蹴り、ま白い尾の影を観客の瞼の裏に残しながら側転、バック転と続けていく。円の落下点に体を滑り込ませ――背面に回った白手袋が、ドラムメジャーをしかと捉えた。
「アクション中のシルエットは裾の動きが映えていい感じだけど、……気になるのは帽子かな。動いてるときにズレたら大変だし、留め具が緩んだりしてないか毎回よく気を付けるように言わなくちゃ」
「うん」
舞台上の彼は、難易度の高いアクションを成功させたあとも集中を切らすことなく演技を続けている。このままシーンの区切りになるところまで演じるつもりなのだろう。
「あれだけ動いてまわるんだから、衣装もしっかり丈夫にしといてあげないとね。それで、バシッと決めてもらわなきゃ」
「ふふっ、……そうだね、本番が楽しみ!」
いましがた目にしたのが、この演目のレッスンが始まったときから毎日欠かすことなく練習を重ねていた大技だと、カンパニーのメンバーであれば皆が知っている。ステージの上で白くはためく伸びやかな青春の旗印に目を細め、隣に立つ彼と小さく笑みを交わした。
***
夢キャスワンライ『Wind-Wind Symphony!』/20190119Sat.
■140字
【元チームメイトの彼×昴くん】
『今度のバーベキュー、友達連れてっていい?』そんなメールに軽く了承を返したのは数日前。当日彼が連れてきたのは所属している劇団の同僚で、細身で黒髪の大層な美男子だった。不慣れそうな友人の皿に肉や野菜を次々入れて世話を焼く彼がしきりに友人の名を呼ぶ明るい声が、いやに耳に残っていた。
【仁すば】
「お前は、俺が帰ってもいいんだね?」少しばかり、意地の悪い問い方をした自覚はあった。痛いところを突かれたからだろうか。明るい茶色の双眸が、弱く揺れながら歪む。「……あっちで、おれのすきな、かっこいい仁さんでいてくれるなら。……おれは、それでいい、です」震えた応えに、息を呑んだ。
【ひなすば/フォロワさんよりお題:興奮】
「待って陽向マジで死ぬ!」「待つわけないよね~」「あー!!」気紛れにダウンロードした数百円の落ち物ゲー厶、五戦中三本先取で勝利。ストレート負けを喫し再戦をせがむ彼へ切るのは予定通りの手札。「いいけど、負けたらキスしてよ?」あどけない興奮を載せた頬が朱に染まりきるまで、あと数瞬。
【いおすば】
逆袈裟の軌跡を描く銀光を、鋭く尖った拳鍔が獣の速度で弾き返して剣の峰をわずかに焦がす。背広の下のしなやかな脚部が大地を蹴って跳ねる。目瞬きの間に詰まった間合いを、即座に翻した刃で遮りそのまま首筋を狙う。男の体軸の移動は数ミリ。薄皮を裂かれながらの拳の向こうに、猟犬の瞳が見えた。
(BULLETお稽古)
---
至近距離でじっと顔を眺めると、時折目を逸らされることがある。思わず眉根を寄せて真意を問えば「いや、その、嬉しいんだけど」と慌てたような弁解が続く。「なんか、かっこよくて照れるっていうか……」これ以上無自覚に豪速球を繰り出される前に、恥じらいがちに呻く唇は口付けで塞ぐことにした。
(フォロワさんよりお題/恥じらい)
---
さっきのプレーはここが凄くて、あっでもいまのも――クッションを抱えながら、隣に座る男がしきりに画面内の解説を寄越してくる。実際は男の言う内容の半分ほども理解できていないのだけれども、短い相槌と首肯を返すだけで男がそれは嬉しそうに笑うものだから、今夜もそうして数時間を過ごすのだ。
■07:00(いおすば)
朝の布団は魔境だ。どれほど就寝前に早起きを誓いながら床につき、むろん念入りにアラームをかけておいても、ほんのわずかな油断が二度寝という結果を招く。そして今朝もまた、藤村伊織はあたたかな湯のなかをたゆたうように、心地好いまどろみに身を任せかけていた。
「……り、いおり!」
「……む……?」
沈みかけたまどろみの水面を、聞き慣れた声がふいに波立たせた。声だけでなく、ちいさな子どもがするような遠慮のなさで肩を揺さぶられて、顔をしかめる。
「いーおーり!起きろってば、朝メシだぞ!」
なんだ、と問いを発したはずだったが、起き抜けの喉からはなにごとか呻くような音が出ただけだった。
朝飯。朝食。……そういえば、米の炊けるにおいがしているような。頭上から降ってきた言葉の意味を低回転の思考で理解して、ようやくのろのろと瞼を押し上げる。
「あっ、起きた!」
眩しい朝日よりも先に、弾むような声と笑顔が視界に飛び込んでくる。開け放した窓から射す陽光を背にした昴が、伊織の枕元に腰を下ろして嬉しげに笑っていた。
「今日は早起き成功だな、伊織」
「ああ……」
衣服こそまだ部屋着代わりのジャージ姿だったが、その溌剌とした様子からはすでにまどろみの気配さえ感じられない。今日はこれから支度をして、ふたりで釣具屋に買い物へ行くことになっている。いつまでも惰眠を貪っているわけにはいかないのだ。すぐそばにあった男の手にふれると、体格に見合った大きさの手のひらが伊織の手を掴んで体を軽く引き起こした。
表情を綻ばせる昴の赤茶色の癖毛が朝日に透けて滲むのが間近に見えて、知らずのうちに目を細めた。伊織の手首を捕まえたままの手は、相変わらずあたたかい。ねむい。
「……おはよう、」
「へへ、おはよ……って、あれ、伊織?」
どうにか押し出した言葉とは裏腹に、あたたかな温度に誘われて、広い肩に頭を載せていた。特別な相手の体温というもうひとつの罠の存在を、伊織が頭の隅に思い出したときにはすでに遅く。
「…………、うーん、やっぱりダメだったかー……」
布団よりも幾らかあまいまどろみに沈む間際に、微笑を含んだやわらかな声を聞いた気がした。
***
20171226Tue.(きれはし供養)
■あすについて(ゆうすば)
「湧太郎さん、明日はどうしましょうか」
うつらうつら。子どものように舟を漕ぎながら、それでもまだ眠りたくないと言いたげに目を擦って、彼が問いを投げてくる。枕にうずめられた彼の頬の、あどけなさが残る輪郭にそっとふれて、そのぬくもりにちいさく笑った。
「そうだな、もし晴れてたら、洗車を手伝ってくれないか」
「洗車?」
「ああ」
いつもより少し遅く起きて、朝食を済ませて、ランニングから帰ってきたら。言葉を続けながらやわらかな癖毛に指先を通せば、彼もくすぐったげに目を細めて吐息だけで笑う。ふとしたしぐさがこのごろどこか大人びてきているように思えて、少しだけ落ち着かない心地がすることがあるのは、まだ自分だけの秘密だ。
「暑くなってきたから、きっと、気持ちいいですね」
カラメル色のひとみが、穏やかなまどろみに溶けてゆく。それを目を眇めて眺めながら、そうだね、と、呟いた。
***
20180703Tue.
■春ゆきこんこ、海こえて(ゆうすばゆう)
こちらでも桜が咲いたよ。この前の昴くんからのお裾分けの、お返しです。
ぽこ、と胸ポケットのなかで響いたいつもの通知音さえも、そのメッセージと、添えられていた写真を目にした途端になぜだかとても愛らしくかろやかなもののように聞こえる。
昴が暮らすこの街では夜風も春のにおいを帯びて、日増しに空気がやわらかくなってきたところだ。歩き慣れた閑静な住宅街、道ばたにひっそりと佇む自動販売機のそばで足を止める。
まじまじと見つめたディスプレイには、画面と同じ形に切り取られたニューヨークの朝の空と桜、それから端々になにげない景色が映し出されている。もちろんここで顔を上げても彼と同じ色を見ることはできないと知っていたけれども、――それもいまの昴にとってはさしたる問題ではなかった。
写真に映っていたのは彼が休日によく利用しているというサイクリングコースだ。
……だから、それは、つまり。
「もしもし、湧太郎さんですか?」
昴です!
続けて名乗った声を、穏やかな夜風がさらって通り過ぎていく。遠い場所でも同じ色をしている春の雪を、よく似た風が揺らしているのかを、ただ彼のあたたかな声に確かめられればそれだけでよかった。
***
20210306Sat.
■いつかの少年(ひなすば)
ラッシュを終えた平日の午前十時すぎ、ふたりで乗り込んだ市バスは人影もまばらな閑散とした空間だった。
降りる停留所はわからない。――というより、決めていないのだ。「久しぶりにバスに乗って遠出がしたい」という、起き抜けの彼の言葉に誘われるまま、昴は彼とふたり、バスに揺られていた。
遮りきれない夏の温度が、バスのガラス窓越しにじわりと滲んで頬を撫でる。しばらく連なっていた高いビルの蔭から出た途端に視界を包んだ強い日差しに思わずぎゅっと目を瞑ると、隣の席からくすくすと小さな笑い声がした。
「……なんだよー陽向」
「んーん、なんでも」
二人がけのシート席、その通路側に座った彼に、どうやら見られていたらしい。悪戯めかした笑みの気配を含んだ応えに気恥ずかしさを覚えてじとりと目を向けてみたけれども、見慣れた笑顔にさらりと躱されただけだった。
「っていうかすばるん、さっきから外見すぎ。なんかあった?」
「えっ、いや、別になんか変わったものがあったわけじゃないけど」
「けど?」
とはいえそれもふたりにとってはすっかり慣れた調子の流れであったので、どちらともなくあっさりと間を取り直して会話が続く。混み合う時間帯と比べればおそらくずいぶんと数の少ない乗客はそれぞれ離れた席に点々と座っているものの、彼らに配慮してか少し抑えぎみのトーンの声がなぜだかすこしくすぐったい。鼓膜にやわらかくふれられているような心地がして、心地良さにころんと口から本音が零れ出る。
「すげーいい天気だなー、今日も空が青いなーって思って。あと雲がうまそーだなーとか」
「…………、すばるんって、本当にさぁ……」
「?」
「っふ、あは、もー!なんでもない!――ほら、降りるよ!」
「あっ、おい、陽向!」
ほんの今しがたまでまるでそんなそぶりもなかったくせに、肩を揺らして笑った彼がふいに腰を浮かせて降車ボタンを押す。タイミングよく停留所が近づいていたようで、停車のアナウンスとともにバスの速度が落ちはじめた。
「陽向、この近くになんかあるのか?」
ぷしゅう、がこん。ドアの開閉音に送り出されて歩道を踏みしめた途端、夏が全身をつつむ。温度の高い風。アスファルトの照り返し。蝉の大合唱。
「んー?わかんない」
「へ、」
蝉の声に負けないように投げた問いに、思わぬ答えが返ってくる。降り注ぐはずの日差しだけが、道沿いに植えられた街路樹の緑にやわらかく遮られてゆらゆらときらめいていた。
「窓の外じゃなくて、こっち見ててよ」
木漏れ日のなか、そう言って冗談めかして笑う彼のひとみの奥にみつけた夏が、ただ、まぶしい。
***20190117Thu.
Special thanks/Le☆S☆Ca「ひまわりのストーリー」
■彼と星の話(1)
※元チームメイトの彼とすばるくん※捏造注意
ここにいるはずのない彼の姿をフェンスの向こうに見つけたのは秋の暮れ、日が落ちたころだった。
「……昴?」
その日は週に一度の早上がりの日で、ナイター照明が点灯する時間になったところで練習を切り上げることになっていた。ダウンを済ませ、チームメイトたちがばらばらと帰り始めているのをぐるりと見渡したそのとき、照明の明かりの届くか届かないかの境界めいた場所に、ふたつの人影を見つけた。
ひとつは、リュックを背負った小柄な少年だった。チームに在籍している女性スタッフの息子で、やはりサッカーをしているらしい。早上がりになっている日はクラブチームの練習のあとと思しきユニフォーム姿のままここへ寄って母とともに帰路につく。大抵がひとりきりだったが、それでも目を輝かせながら練習風景を眺めているのをフェンス越しに何度も見たことがある。視線を奪われたのは、あざやかなリフティングを少年に見せているもうひとつの人影のほうだった。
小柄な少年と比べて頭数個ぶんほども上背のある、すらりとした長身。明るい茶色のくせ毛が、冷えた風にふわふわと揺れていた。
用具を片付けるために動かしていた足が止まる。突然立ち止まった自分に、そばを歩いていた仲間が訝しげに声をかけてくる。形ばかりの謝罪とともに用具を押し付け、思わず駆けだしていた。
「昴!」
そこにいたのはかつてのチームメイトだった。そばまで駆け寄って名前を呼ぶと、彼がぱっとこちらを振り向いた。視線を逸らしたために彼が蹴り上げていたボールの軌道が一瞬乱れたが、すぐに持ち直す。
「にーちゃん、ここのチームの人なの?」
やわらかな弧を描いて少年へとボールを返した彼に、少年が問う。彼は朗らかに笑って、首を横に振った。
「ううん、チームの人の、友達。にーちゃんはね、役者やってんだ」
「役者?」
「そう。夢色カンパニーってミュージカル劇団」
「こんなに上手いのに、サッカー選手じゃないんだ?」
「あはは、前は選手やってたけど。いまは引退して、役者やってる」
「へー……?」
「――さ、そろそろキミのお母さんも仕事終わる時間だろ?迎えに行ってあげなくちゃ」
「あっ、ほんとだ!にーちゃん、また遊んでよ!」
「おー!」
ほんの少しのあいだにすっかり仲良くなったらしく、そんなやり取りのあと少年は元気に手を振って背を向けた。ボールを抱え、リュックを揺らして走り去っていく後姿を懐かしそうに見送ったあと、ゆるく息を吐いた彼がようやくもう一度こちらに向き直る。髪色によく似た明るい茶色の瞳と視線がぶつかる。
「お疲れ。あと、久しぶり」
「ああ、うん、久しぶりだな……って、どうしたんだよ、急に」
「あはは、たまたま近くに用があってさ」
ナイターついてるのが見えたから、あ、やってんなーと思って来てみたんだけど、見つかっちゃったなー。
そう言って悪戯っぽく肩を竦めてみせた彼の幼い顔立ちには、少年に向けていた笑みの余韻が残っている。
「みんな元気にしてる?」
「おー、相変わらずだよ」
「そっか。よかった」
フェンス越しにグラウンドを見遣った彼の問いに答えれば、噛み締めるように嬉しげな声が返ってくる。彼のことを知っているチームメイトもまだグラウンドにいくらか残っていたけれども、なぜだか彼らを呼びつける気にはなれなかった。その代わりに、彼に問いを投げ返す。
「お前は?……まだ、あの……前言ってた、劇団にいるんだろ?」
「ああ。いまは次の公演の稽古中なんだ」
「へー……」
そっか、と下手すぎる相槌を打ってしまい、そこで会話が途切れる。チームメイトだったころは、こんなぎこちなさなど感じなかったというのに。ちくりと胸が痛んだ。一瞬落ちた空白を取り繕うように、慌てて言葉を継ぎ足す。「あのさ、」
「十五分。十五分で終わるから。……そこで待っててくれねえ?」
「へ?」
「――あ、いや、このあと特に予定がなければなんだけどさ!せっかくだから、メシくらいどうかなって」
一年ほど前にはわざわざ待たせてまで誘うようなこともなかった。同期の仲間として一緒に過ごしていたのだから、当たり前だ。彼はそのまるい瞳を二、三、ぱちぱちと目瞬かせたあと、明るく笑って頷いてみせた。
「じゃあ、支度してくるわ」
「おう!待ってる!」
目の前にいる彼が、どうしてかすっかり別人のように思えて仕方がない。妙に落ち着かない心地がするのは、はじめて見るライムグリーンのつなぎのせいか、先ほど少年に向けていたあざやかな笑顔のせいかわからなかった。
***
20161110Thu.
■彼と星の話(2)
※元チームメイトの彼×すばるくん※捏造注意
彼と連れだって訪れた、行きつけ――というには少々気恥ずかしい、けれども馴染みで世話になっている牛丼屋は、聞き慣れた喧騒に満ちている。
肩を並べて座るカウンター席、自分と彼の前には大盛の牛丼がひとつずつ。いただきます、と手を合わせ、追加でつけた卵を肉の上につるりと落とす。箸の先で黄身をつぶして、白身と肉と米に絡めてひとまとめに口へ運んだ。美味い。
「やっぱ練習上がりには肉だよなー!」
「そうだな」
小さな子どものように牛丼を頬張る姿は相変わらずだ。嬉しげな表情につられて笑みを零しつつ相槌を打ってから、彼の手元に視線を移す。
「大盛でよかったのか?昴、いつも特盛だったろ」
「ん?ああ、今日はこれくらいで大丈夫。帰ったらランニング行くし」
「へー……どれくらい走ってんの」
「大体毎朝一時間と、夜二時間……?早めに上がった日は三時間くらいは外にいるかな」
「……結構走るんだな」
「んー……。……ホントは、もっと走り込んで体力つけときたい」
「お前が?」
苦笑交じりの彼の答えに、思わず目を丸くして問い返す。同期のチームメイトのなかでも彼の選手としての素質は頭ひとつ抜けていて、それは持久力という意味でも同じだった。ミュージカルというのは、彼がそんな意識を抱くほどの体力勝負の世界なのか。彼は口に含んでいた米をごくんと飲み込んで、ひどく真剣な面持ちで頷いた。
「オレもびっくりしたんだけどさ、演技と歌とダンスを同時に全部やるのって、すっげー体力いるんだ。オレ、役者としてまだまだなとこばっかりだから、体力つけてそのぶんもフォローしてかないと」
――まあ、いちばんはお客さんと仲間の前でカッコ悪いとこ見せたくないからなんだけどさ。
そう言って笑う彼は、自分の知らない景色を見ている。その事実にどうしてかかすかに感情を波立てられていることに気がついて、理由は探さないまま食事を口に運んで蓋をした。続けられる言葉が見つけられず短い相槌を返したきり黙り込んでしまった自分を、彼はほんの少しだけ不思議そうに見遣ってから、もう一度口を開く。
「なあ、来月の真ん中からあとで空いてる日、ある?」
「……おう。いまんとこいくつか空いてるけど」
その答えを聞いた彼は「よかった」と小さく呟いてから、つなぎのポケットから携帯を取り出してなにごとか操作を始めた。少しの間のあと目当てのものを探し出したらしい彼が、端末をこちらに差し出してくる。
「今度の公演、オレが主演なんだ。チケット取っとくから、よかったら観に来てほしい」
そんな言葉とともに手元に置かれた端末の画面を、まじまじと覗き込む。劇団の公式サイトらしいページの上部に、タイトルロゴとバナー画像が表示されていた。
公演期間は来月中旬から。演目名は、「四神闘龍」。
***
20170202Thu.
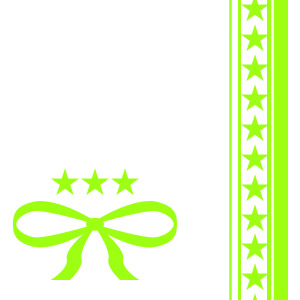
 なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
Link
Message
Mute
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
Link
Message
Mute


 ステキと思ったらハートを送ろう!ログイン不要です。ログインするとハートをカスタマイズできます。
ステキと思ったらハートを送ろう!ログイン不要です。ログインするとハートをカスタマイズできます。

 なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH