はなのあるまちリリィ・リリィ
不動行光の主からは、いつも花の匂いがする。
「ゆきちゃん、ごめんね、そこのバケツとってもらえる?」
「なんで俺が……」
「だって、ゆきちゃんももううちの子でしょ? 働かざる者食うべからずって昔の人も言ったじゃない?」
不動とそれほど背丈の変わらない女は、エプロンの紐を手早く結びながらそう笑った。
確かに働かざる者食うべからず、という言葉はあるけれど、それは本業に関していうことであって、少なくとも刀である己の本業は、水がなみなみ入ったバケツを運ぶことではないはずだ。そう言ってやりたいのは山々だったが、この女に何を言っても無駄だということはこの一週間で骨身にしみてよく分かっている。
不動は大きく息を吐いて、座り込んでいた店の片隅から腰を上げた。
「えっ、もうこんな時間!? 大変、急がなきゃ」
女はそう叫んでバタバタと奥へと走っていく。不動の持っているバケツで、水がたぷんと揺れた。
「おい、バケツ──」
「お店の真ん中の机においておいてくれる? それが終わったら、お店の奥に朝ご飯があるから、ゆきちゃんも食べちゃいなさいね」
「俺は、別に──」
「ああそれから、もう営業中に甘酒飲んじゃだめよ? カルピスなら冷蔵庫にあるから、ほしくなったら言いなさいね」
「ガキ扱いすんな!」
一を尋ねたら百くらいで返してくる女だ。いいからさっさと支度しろ、と叫べば、嬉しそうに軽やかな笑い声が聞こえてきて調子が狂う。
壁に掛けられている鳩時計が八回鳴くと、勝手口の方から人間の声が聞こえてくる。女と同じエプロンをつけた人間たちは、相変わらず店の隅に座り込んでいる不動にも、性懲りもなく明るい声をかけてきた。
やがて女が店の奥から出てくると、バイトさんとか、店員さんとか呼ばれている人間たちは、両腕に大きな花を抱えて、ハサミを水の中につっこんだり、葉っぱをむしったり、大きな鉢植えを外に持って行ったりする。
「じゃあ、今日もよろしくお願いしますね」
九回鳩が鳴くと、決まって女はそう頭を下げた。人間たちの「よろしくお願いします」の唱和を、不動は今日も店の片隅で聞いている。
*
城下町の一角にあるキニアン生花店に、刀剣男士である不動が配属されたのは、今からちょうど一週間ほど前の三月九日のことだった。
なんでも、城下を遡行軍に襲撃されて、職員が何人か犠牲になったことを受け、政府が試験的に城下の店に護衛として刀剣男士を配属することにしたらしい。
その試験対象に選ばれたのが、大和国城下で唯一の花屋であるここと、政府預かりになっていた短刀不動行光だった、ということなのだった。
「ダメ刀だからって花切バサミ扱いかよ……」
思わず出てしまったそんなぼやきに、実際に花を切っていた男の店員はカラリと笑った。
「いやあ、ゆきくんじゃ花は怖くて切れないよ。水の中につっこむわけだしね」
「前から思ってたけど、その呼び方何なんだ」
「店長が、こうやって呼んだ方が親しみがこもってて良いって」
あのアマ、と内心毒づいたのに気づいたのか、店員は苦笑する。曲がっていた腰を伸ばして、萎れていた一輪をバケツから抜き取った。
「まあそう邪険にしないであげてよ。俺たちにとっては、刀剣男士様は神様で、今まで崇める対象だったから、いきなり身内になって戸惑ってるのさ」
「全然そうは見えねぇんだけど」
「そう見せないようにしてるだけ。……これはもうダメかな」
そう言って翳した花は、不動の目にも明らかに萎れていた。だが、それは店で売るにしては、であり、どこかに飾ってあっても気にならないくらいだ。
思わずじいっと見つめていた不動に気づいたのか、店員は再度腰を屈め、水の中に手を突っ込んだ。パチンと心地の良い音がする。
「あげる」
「は?」
「物欲しそうに見てたから」
「別に……」
ふいっと視線を背けると、店員は不動の代わりに、その隣に置かれていた甘酒の瓶を持ち上げた。手持ちぶさたに握っては、中身がないのについ傾けてしまうその瓶に、水を張って花を生ける。
「おい、俺は別にいらないって」
「まあそう言うなって。俺からの就任祝い的なあれだよ」
「就任祝い……」
「そ。うちへようこそ、ゆきくん」
不動にとっては不本意きわまりない就任なのに、何が祝いだ、と言いたくなったが、言い返す相手は店先に現れたお客の方に行ってしまって、開いた口を渋々閉ざす。
何でこんな店なんかに、と今では一輪挿しになってしまった瓶を弾けば、澄んだ音とともに指先が鈍く痛んだ。
そもそも、自分が花屋だなんてガラじゃない。かつて同じ主に仕えた短刀が「雅なことなんぞ分からん」とのたまっていたが、不動もどちらかというと雅なんて終ぞ解せないタイプだった。
もしも、彼がきちんと本丸に顕現されていて、影響を受けるに足る主を持っていたのなら話は別だったかもしれない。だが、今の不動の主は審神者の能力もないただの花屋の店長である。
「花の名前すら満足に言えないのに」
なんでこんなことになっちまったんだか、とぼやけば、近くで聞いていた別の店員がカラカラ笑った。
「そんなの気にすることないって、ゆきくん」
「あ?」
「売れ筋ベストスリーの見分けがついたら、うちで働く分にはぜんぜん問題ないから!」
そういう彼女の手には、その売れ筋ベストスリーのうちの一つが小さなブーケになって束ねられている。
「菊、百合、ひなげし。それだけ覚えてたら大丈夫。っていうか、基本それしか売れない」
「それはそれでどうなんだよ……」
というか、と不動はぐるりと店内を見回した。
売れるものが分かってるなら、それしか仕入れなければいいものを、この花屋には酔狂なことにチューリップもあればパンジーもスイートピーもある。この一週間で、だいたい売れるのが切り花だというのも分かっているのに、しつこく鉢植えも種もおいてあった。
経営に明るくない不動にだって分かる非効率っぷり。ある意味、この店らしいといえばらしいのかもしれない。
独り言にすら相槌を打たなきゃ気がすまないような人間ばかりなのだから。
「流石にゆきくんだって見分け付くでしょ? 菊と百合とひなげし」
「バカにしてんのか?」
「ほら大丈夫。ゆきくんもうちで働けるよ」
「俺はここで働くなんてひとことも言ってない!」
ええ、と不満げな声を漏らした店員に、不動はふんと鼻を鳴らして立ち上がる。そうだ。自分は刀。使命は敵を斬ること。断じて花を切ることなんかじゃない。いかにダメ刀だと卑下しようとも、本質は譲れないのだ。
そう思いつつ握りしめた甘酒の瓶には香り高い白百合が生けられていたから、周りの視線は生温かくて、不動の苛立ちはさらに募る。
もういい、外に出よう。護衛の任務が全うできるように、店先に座ってりゃ問題ないだろう。
不動が立ち上がって外に出ると、背中に「お昼ご飯までには帰ってきてね」なんてふざけた店主の声が被さってきた。
くそう、バカにしやがって。歯噛みしながら座り込んだ店先では、刀剣男士が主を伴わずにいるのが相当珍しいらしく、不躾な視線が突き刺さる。中には迷子を心配して声をかけてくる審神者までいた。そのたびに店員が「うちの神様です」なんて説明するから、座敷わらしにでもなった気分だった。
こんな時こそ飲んで忘れたいのに、甘酒の瓶の中には百合の花。何から何まで最悪だとうなだれたときに、本日何度目かになる陰が差す。なんだよ、迷子じゃねぇぞ、とへの字に曲がった唇からとげとげしく吐き出そうとした不動の視界に入ったのは、ある意味因縁といってもいい短刀の姿だった。
「何フテてんだ?」
「……何しに来たんだよ」
菫色の瞳を宿した端正な顔立ちに似合わぬ笑い声をひっさげて、薬研藤四郎は立っていた。日差しを遮るような風貌に、不動は目をうっすら細める。
「様子を見てこいって大将に頼まれてな。楽しくやってそうで何よりだ」
「どこを見たらそんな判断になるんだよ」
「全体的に」
ざっくりにもほどがある回答に不動はがっくりと肩を落とした。元凶は笑いながら店の中を見渡し、店長の女に軽く手を挙げて挨拶している。暢気なもんだと刀剣男士の顔を見上げた。こっちがどんな思いでここにいるかも知らないで。
「おまえんとこの審神者に言っとけ。おまえのせいで散々だ、ってなぁ」
「おう。散々楽しそうにしてるって言っとくわ」
「薬研!」
なんだよ、と薬研は悪びれない。それがしゃくに障ってギロリとねめつける不動に、おお怖い怖いと彼はわざとらしく身震いした。
「なんだかんだ仲良くやってるじゃねぇか。その花なんか」
「これは……」
たいしたもんじゃない。売れ残りだ、と言い掛けて、のどの奥にひりついた。この一週間一緒に過ごして、店の連中がどれだけ花に時間と力をかけているかは知っている。いくら気に入らないヤツだからと言って、そんな風に言うのははばかられて、不動はうろうろと視線をさまよわせた。
「……就任祝いって」
「へえ、就任祝いなぁ」
薬研は甘酒の瓶に入っている百合の花をじいっと見つめ、にやっと意味ありげに笑う。それから思い立ったように店の中に入っていき、十分も待たずに帰ってきた。
「ほら」
ずいっと目の前に差し出されたのは、赤いリボンで結わえられた茶色いクラフト紙の袋。茶色いスタンプには自分が座っている店の名前が書いてある。
「……なんだよ」
「就任祝い」
「は?」
いいからいいからと押しつけるだけ押しつけて、薬研は不動に背を向けた。
全く意味が分からん。何がしたいんだあいつは。ぼやきながらリボンをほどくと、中から拳よりも二回りほど小さい固まりが転がり出てくる。
「……球根?」
なんで花屋に球根なんか。前々から分かんねぇヤツだと思ってたけれどとうとうどこかおかしくなったんだろうか。つまみ上げた茶色い固まりを日にすかせながら、不動はこてんと首を傾げた。
*
流石花屋というべきか、球根片手に戻ってきた不動に店主はすぐに小さな鉢を出した。店の奥からふかふかの腐葉土を引っ張ってきて、小さなスコップで優しく球根にかぶせると、ふわふわと笑って首を傾げる。
「ゆきちゃんが花を育てたいなんて」
「誰もそんなこと言ってねぇし」
口ではそう言いつつも、不動は水で満たした瓶を傾けて水やりをしていた。閉店後には解禁される酒で赤らんだ顔に、手つきはややおぼつかないが、土は黒く湿っていく。
「あら、ダメよゆきちゃん。水をあげすぎると腐っちゃうから」
「腐るぅ?」
「そう。ゆきちゃんもお酒飲みすぎると腐っちゃうでしょ? それと一緒」
思わず瓶を握る手に力が入ったが、すんでのところで瓶は砕けずに不動の手の中に収まっている。嫌味か、と見上げた顔は相変わらず暢気な顔色で、どうやらジョークのつもりもなんでもなく、単に考えなしで発した言葉らしい。
どうもこの女といると調子が狂う。それとも、不動が知らないだけで人間は皆こんなもんなんだろうか。
「それにしても嬉しいわぁ。ゆきちゃんが花に興味持ってくれたなんて」
「持ってない」
「いよいようちの子になってくれたって感じで」
「なってない!」
人の話を全く聞かない。よくこれで店主なんて務まるものだとねめつけても、女は嬉しそうに花の手入れをするだけだった。時刻は午後の八時を回り、店員は皆それぞれの住居に帰ったというのに、店主は未だ花の世話を続けている。
白い百合に、菊に、真っ赤なひなげし。大部分を占めるのはその花だが、それ以外の花も決して少なくない数が仕入れられている。
しおれかけた花は水切りをして、それでも回復が見込めない花は部屋に飾って。間違いなく赤字になる商売だろうに、と不動は目を細めた。
「なんで花なんか売るんだよ」
今は戦時。ここは前線の重要な補給拠点。ならば花を売る前に、もっと儲かるものを売ればいいのだ。他の店と同じように。そうぼやいた不動に、あら、と女は目を丸め、想像よりもずっと強かに笑った。
「ゆきちゃんは誤解してるわ」
「あ?」
「今だから花を売るのよ」
ぱちん、と音高くはさみを鳴らしながら、店主は黄色い菊の茎を切る。
「きれいな花が咲くと良いわねぇ」
それ以上は続ける気がないと言うように、店主はうっとりと目を細める。言われてちらりと不動は植木鉢に視線を移した。
「……そういやこれ、なんの花なんだ?」
「ゆきちゃん、それを聞くのは野暮ってものよ?」
いい、と店主は腰に手を当て、はさみを芝居がかった動作で振りながら諭す。
「そりゃあね、私だってお花屋さんだもの。球根を見ただけでどんな花が咲くなんて分かっちゃうけれど、答えを知っていて育てるなんてつまらないでしょう?」
「そうかぁ?」
「そうよ。どんな花が咲くのか、わくわくしながら育ててちょうだい。そして、ちゃあんとその両目で、あなたが育てた花を見てあげてね」
そこまで言うと、店主はその場にしゃがんで、机の下にあった段ボールを探る。しばらくごそごそしてから、はい、と笑って差し出したのは、ひょろっこい紫の水差しだった。
「あげるわ。就任祝い。ゆきちゃんのその水差しも素敵だけど、それだとお水をあげすぎちゃうから」
大事にしてね、と店主は言い含め、再び花の方へと体を向ける。鉢一つにしては大きすぎるプラスチックの水差しをもてあそびながら、不動はちみりと甘酒を口に含んだ。
結局働かせる気まんまんなんじゃないか、この女。
ハッピー・ライラック1
城下町にある花屋は、このご時世、流行っていないのかと思いきやそれなりに繁盛しているようだった。
やはりよく売れるのは菊、ついで百合、ひなげしだったが、それ以外のものも少しずつだが売れている。生け花の花材を探している歌仙兼定や三条派の太刀なんかに始まり、食卓に花を飾りたいのだという燭台切光忠。変わり種だと、食べられる花があると聞きつけてやってくる鶴丸国永(食用花の取り扱いはないと店員が丁重に送り返していたが)など。
そして、時々いるのがこの手の話だった。
「ですから、今日という今日こそは、刀剣男士が喜ぶ花を教えてほしいのです!」
「……なんで俺に聞くの……?」
「それはもちろん、あなたが刀剣男士だからですわ、不動行光様」
両の手をぎゅっと拳にしたかと思えば、何を当たり前のことを聞くのかときょとんとしてみせる人間に、不動は痛む頭を押さえた。それだと、「あの審神者の好きな食べ物何?」「どうして私に聞くの?」「だってあんた同じ人間だろ」が罷り通ってしまうのだが、その辺り理解してるのだろうか、この娘は。
年端もいかない少女の威勢のいい声に、なんだなんだとこちらに顔を向けた店員たちも、様子をうかがってああなんだいつものことかとそれぞれの持ち場に戻っていく。薄情ものめ。ちょっとくらい助けてくれたっていいじゃないか。内心で文句を垂れつつ、不動は店先にしゃがんだまま、女審神者を見上げる。年の頃はおよそ十にも届かない、緋色の袴を穿いた、若いというより幼い娘だった。
「たんぽぽでも摘んで渡せばいいんじゃねえの」
「まあ、なんて暴論! 私がいくら子どもだからって馬鹿にしすぎではなくって!?」
子どもだっていうことは自覚しているのか。ぷりぷり怒る審神者の前で、不動はうんざりとため息をつく。自分の業務は花屋の護衛であって、店員でもないしお悩み相談でもない。花の名前も分からないし、増してどの花が想い人にふさわしいのかなんて尚更だ。
素直に店に入って店員に聞けばいいのに。頬を膨らませる彼女に、不動は甘酒の瓶に入った花を指でくるくると回した。今日はマリーゴールドだと、店員が得意気に言っていたっけ。
「じゃ、薔薇とか」
「き、気合いが入りすぎでは?」
「んじゃあ菊」
「菊は少し……」
じゃあ何ならいいんだよ。いい加減面倒になってきた不動が、もう店の奥にひっこんでしまおうかと思ったとき、「ありがとうございましたぁ」と気の抜けた挨拶と共に外に出てきた男の店員が、おや、とこちらに目を向けた。
「ようこそいらっしゃいませ、審神者様。お求めの花は見つかりましたか?」
「それが全然ですの。聞いてくださる? この不動行光様、全く相談に乗ってくださらなくって。それどころか、たんぽぽを摘んで渡せばいい、なんておっしゃいますのよ!」
だから、俺の仕事じゃないんだよ。この少女に対して何度も言ったそれを、不動は諦めと共に飲み込んだ。何を言っても無駄だと最近理解したのだ。
それに、若干苦笑した店員は、「でも、案外名案かもしれませんよ、審神者様」ととりなす。
「同じ花でも、ご自身で摘まれる方が、より意味をもつものです。審神者様も、想い刀様がわざわざ摘んできてくださったお花をいただくほうが嬉しいでしょう?」
「それは……そうかもしれませんわ」
でしょう? と店員は得意気に鼻の下を擦る。そして、「あ、でも」と付け足した。
「たんぽぽは、ちょっとやめといた方がいいかもですね」
「あら、どうして?」
「たんぽぽには、『別離』って花言葉があるんです。綿毛が飛んでいってしまうから」
それに、彼女は分かりやすく顔を青くした。それにさすがにしまったと思ったのか「勿論、たくさんある花言葉のひとつですけどね!」と店員がとりなす。
「『愛の信託』とか『真心』とか……決して悪い花ではないんですよ、本当に」
「ええ、ええ。……でも、今回は別のお花にしておくわ。何がいいか相談に乗ってくださる?」
そうですねえ、と男は懐から端末を出して、いくつか野の花を示して見せる。「ハハコグサなんていいんじゃないでしょうか」とすぐさま提案して見せる姿に、少女の関心が逸れたことに内心ほっとしつつ、不動はそろそろとそのふたりから距離をとった。
店の中に逃げ込むと、大きなブーケを作っていた店主がこちらに笑顔を向ける。
「あら、ゆきちゃん。接客お疲れ様」
「したくてしたわけじゃねえよ。あれ、どうにかしてくれ」
「難しい話ねえ。お客様はどなたでも歓迎がうちのスタンスだし……」
だったらせめて俺に客を回すなと主張したが、店主はにこにこするだけだ。ちくしょう、また暖簾に腕押しかよ。小さく毒づいて、不動は店の隅にある本棚に身を預けて座り込んだ。
「……ああいうの、いつもやってるわけ」
「ああいうのって?」
「だから、どの花を贈るといいか、とか」
「そうよ。それが私たちのお仕事だもの」
淡い色合いのふわふわした花をひとつひとつ、丁寧に挿し込みながら店主は頷いた。
「どの贈り物もそうだけれど、お花は、お花そのものを贈るのではなくて心を贈るものだわ。どのお花が一番お客様の心を託すのに相応しいのか、まあ、お見合いをするわけね」
「花言葉ってやつ?」
「そうね。それもひとつだし……色や形、本数も。求婚するには、やっぱり赤い薔薇でしょうし、萎れていてはみっともないわ。リボンの色も一緒に考えなくてはいけないし」
ふーん、と、不動は気のない声で相槌を打つ。
「大変だな」
「楽しいでしょ?」
ぴったりと重なった感想は、タイミングこそ揃えど意味は正反対のもの。あらあらと苦笑する店主に、不動は微かに鼻を鳴らしてそっぽを向いた。やっぱり、この女とは考え方が合いそうにもない。
「もしも花言葉が気になったなら、ゆきちゃんの後ろにある本棚にたくさん事典はあるからね」
「気になってねえし」
「勿論、聞いてくれてもいいわよ?」
「聞かねえ!」
前門の狼、後門の虎ならぬ、店前の女審神者、店内の店主だ。もう店から出ていってやりたいが、仕事上そうもいかない。不動はむっすりとしたまま、置き所のない身をひとまずその場に寄せ続けた。店の外からは相変わらず、明るく呑気な人間たちの声が聞こえる。
*
三日ほど経ったころ、いつも通り店先で暇をもてあましていた不動が、花を選んで欲しいのです、と、再び声をかけられたとき、内心、またか、と思っていた。
しかし、見上げた顔に不動の口は止まる。そこに立っていたのは、いつものあの少女ではなく、ましてニヤニヤと笑うあの性悪の短刀でもなく──その兄だ。穏やかな春の日差しを背負って、鮮やかな色の髪を風にそよがせ、一期一振が立っている。
「申し訳ありません、出し抜けに」
そう丁寧に頭を下げられ、不動はいよいよ戸惑った。一期一振自体は、頻繁にではないにせよ時々見える刀だ。だからこの刀がここにいることは、そう珍しくもないのだが、『この』一期一振が来るのは恐らく初めてだろう。纏う霊力に見覚えはない。
そして、あの女審神者や薬研以外から、こうして店のものとして声をかけられるのは、初めてのことだった。
「……花?」
「はい。花を……贈るつもりで」
「それは」
俺ではなくて、店員に聞いた方がいいだろう。不動は店内に視線を滑らせ、口をつぐんだ。生憎と全員が接客中だ。
もう少ししたら、誰か店のものを呼んでくると言った不動に、一期一振は金色の両目でじっとこちらを見つめた。
「貴方では駄目なのですか」
何を言っているのだろう。不動はぼんやりとその目を見上げる。
「俺じゃ駄目だよ。花のこともよく分からないし、第一、本業じゃねえんだ」
「そう、なのですか。失礼いたしました」
別に失礼はしていないのに。不動はそろそろと一期一振の様子を窺う。丁寧な口調に、礼儀正しい振る舞いは彼の刀らしいが、しかしところどころにぎこちなさが滲んでいる。
緊張しているのだろうか、と分析したちょうどそのときに、「ありがとうございました」という穏やかな挨拶と共に、店主が店の外へと躍り出てきた。
「あら? ゆきちゃん、お客様ね?」
いつもは憎らしさも感じる、垂れがちな瞳がちょっぴりだけ頼もしい。首肯した不動に、一期一振も会釈をする。それに彼女は嬉しそうに微笑み、片足を引いてお辞儀をした。
「ようこそいらっしゃいませ、一期一振様。本日は何をお探しでしょう」
歌うように出迎えた店主に、一期一振は言葉に迷う素振りを見せ、やがておずおずと顔を上げた。
「花を、贈りたいのです」
先程と同じ言葉に、不動はちらりと店主の方を見た。
あまりにも情報の少ないオーダーだ。誰に、も、何の目的で、も不鮮明。それでも彼女は、桜色の唇を持ち上げたまま、はっきりとした声でこう言った。
「分かりました。お手伝いいたします」
そう、何も尋ねないで。にも関わらず、自信にあふれた声で。
「ひとまず中にご案内しますね」彼女は一期をそう招いて、こちらにちらりと一瞥をくれた。
「ゆきちゃんもいらっしゃい」
なんで俺が、と言い返すのはやっぱり心の中でだった。彼女には何を言っても無駄なのだ。そして、無駄なことに力は使わない方がいい。
店主は、店の中にある小さな接客スペースに一期一振を通した。普段はブーケのオーダーをとったり、店員とちょっとした話をしたりする、背もたれのついた木製の椅子とテーブルがあるばかりの質素な空間だ。
そこに、店員がシンプルなティーセットを持って現れる。一期一振と不動の前に気取った仕草で置いて、「どうぞごゆっくり」なんて一人前なことを言った。
「貴女は?」
「お構い無く。そういう規則なんです」
政府に所属する普通の人間は、政府所属の刀剣男士以外とみだりに飲食を共にしてはならない。初めの頃に教わった就業規則を思い出しながら、不動はティーカップの中の水面を眺める。ただの茶ではなく、透き通った黄色い液体は、ここに来てから何度か飲んだ、カミツレの花を使った茶だ。
「もしかしてお急ぎだったかしら?」
「いえ、そういうわけでは。良い香りですね。美味しいです」
「お口にあったなら良かった」
言いつつ、店主は手元の帳面をパラパラと捲る。今日店にある花、取り寄せることの出来る花が纏められたものだった。
やがて、いくつかのページにあたりをつけてから、彼女は一期一振の方に向き直る。「お答えしづらいことがあったら、無理をなさらなくて結構ですけれど」と前置いてから、静かにこう尋ねた。
「あなたが花を贈られるのは、想いを告げられるためかしら。それとも、お別れをなさるためかしら」
カミツレの茶によく似た色の瞳が、大きく見開かれてひどく揺れた。
はく、と唇が震える。目を見開いたのは不動も同じだった。いきなり何を言っているのか。それでも、彼女は凪いだ表情のまま、じっと一期一振の言葉を待っている。
しばらくして、一期一振は力なく笑った。これまで強ばった顔をしていた彼の、初めての変化だった。
「それほど、分かりやすかったでしょうか、私は」
「いいえ。とてもよく隠されていらっしゃったわ。ただ、ここにはそういう方がいらっしゃることもあるから。それだけです」
一期一振の目はもう揺らがったし、ぎこちない素振りも見せなかった。力の抜けた所作でティーカップに口をつける。
「他言無用で願いたいのですが」
「勿論。誓って、秘密はお守りいたします」
「……両方なのです」
両方。不動は恐る恐る復唱する。一期一振ははい、と囁いた。
「想いを告げるために、そして、別れを告げるために、花を贈りたいのです」
分かっていた、というように、店主は無言のまま頷いた。
2
一期一振の仕える主は、齢七つほどの姫君を連れて審神者となった。
もう、十年以上昔のことになる。
奥方に先立たれ、現世に幼い娘ひとり残すのはどうにも憚られて、一緒に連れてくることにしたのだと打ち明けられたのは、一期が顕現したその日だった。勉学は通信制授業に、年にいくつかの登校日で済ませているとはいえ、心配なのは社会性。特に友達とのつきあい方だと。
お前はたくさん弟がいるし、うちの娘のこともひとつよろしく頼むと言われ、やや戸惑いつつも拝命したことは、昨日のことのように思い出される。もっとも、主の心配をよそに、姫君はとても逞しく、健やかにお育ちになったのだが。
短刀たちとの喧嘩はしょっちゅう。腕力で勝てないと悟ると次は口が達者になった。誰に影響されたのかとんでもない悪戯をしでかし、最初は主鍾愛の姫君だからと遠慮をしていた一期も二年目には遠慮なく雷を落とすようになった。そのたび、彼女は叱られているくせに嬉しそうにして「一期が怒った!」ときゃらきゃら笑っていた。
初等教育を終える頃、ずっと男所帯はあんまりだと乱が進言し、中等部から姫君は現世の学校に通うこととなった。現世と本丸の往復には危険が伴う。送り迎えは必ずするようにと政府から厳命を受け、交代で刀剣男士が迎えに上がるようになった。
制服に身を包んだ姫君は、いつの間にか鯰尾と並ぶほどの背丈になっていた。一期が校門で待っていると、決まってむっすりと仏頂面になって「過保護なんだから」と固い言葉を吐いた。それに、過保護などであるものか、と一期が丁寧に説明をしては、そっぽを向かれるのが常だった。主に相談すると「反抗期だねえ」と笑われるばかりだった。
それも、いつしか鳴りを潜めた。あの事を謝罪されたことはないが、高等部に入学したその日、迎えに行った一期に、一度だけ「ありがとう」と姫君が言ったことがある。それが、冷戦終結の合図だったように思う。
姫君は伸びやかに育った。いつの間にか幼子から娘になり、可愛らしいと形容するよりも美しいと称する方が相応しくなった。大学になると独り暮らしを始め、刀剣男士は遠くからその暮らしを守るようになった。
元より、姫君の霊力は、審神者になるには乏しすぎた。職員として残る道もあったが、主は、姫君にこの世界に留まらせる気はないのだと言った。本人にその気があるのならともかく、親の戦争に子どもを巻き込む必要はない、と。
だから、いつか別れが来るのだということは、ずっと頭の片隅にあったのだ。
主が、姫君が婚約をしたということ、結婚を機にこの世界から離れるということを告げたときも、一期はちっとも騒がなかった。ただ、そうですか、と答え、その時からずっと、どう別れを告げるか、考えている。
*
簡単に身の上の話を終えると、一期一振はその娘がここをたつ日は一週間後だと告げた。その日に、花を渡したいということも。
「花の種類も、私にはよく分かりません。ですので、全てお任せするつもりなのですが……」
ひとつだけ、と、彼は微風のような囁き声で注文をつけた。
「出来る限り、ささやかなものでお願いしたいのです。大輪の花束ではなく、片手に収まってしまうほどのものを」
不動は僅かに首をかしげた。どうせ贈るならば大きいものの方がいいのではないか。だが、口を開く前に店主が頷く。
「その方が良いですね。送り主の名前は、添えられますか?」
「いいえ。私が贈ったものと、分からないようにしていただきたいのです」
その言葉に、やはり不動だけがいぶかしんだ。店主は「そうですね」と微笑して、手元の注文表にそう書き付ける。
「どうして?」
「機密保持のために、本丸から離れることになった人間の記憶は操作されるの。程度は人により調整されるけれど、そのご令嬢の場合だと、審神者様の記憶と、どこか遠くて不思議な環境で過ごしたということくらいしか残らないのではないかしら」
「仰る通りです」
残らない。不動は小さく繰り返す。本丸で過ごしたことも、その側に誰があったかも、一期のことも、忘れてしまうということか。
「それなのに、もしも姫君が私の名前を見つけてしまったら、きっとお困りになるでしょう? 下手をしたら、外部に情報を洩らすものとして、花ごと政府に没収されるかもしれない」
「……でも、それでいいのか?」
「元より、ただの自己満足なのです」
何をどうしたって、彼女はここを出て行って、一期一振のことを忘れて生きていく。それならば、伝えたところで何の意味もない、無駄なことなのだ。
それでも、一期一振は花を贈ろうとしている。
理解できずに固まる不動の隣で、店主は頷いて注文表を閉じた。
彼女が告げたのは、姫君が出発する前日にこの店に再び来てくれということ、それまでに花を用意しておくが、もし気に入らなかったら納得するまで花選びに付き合うということのふたつ。一期一振は神妙な顔で「よろしくお願い申し上げる」と深々と頭を下げた。
一期一振が去ってから、店主はバケツに生けられていた数々の花の見分を始める。一方、不動は椅子に座ったまま、まだどこかで納得できないままでいる。
どうせ届いたところで、何の意味も、持たないものだ。
「ゆきちゃん。ゆきちゃんは何のお花がいいと思う?」
「……俺に聞くなよ。つうか、もうどうせあたりはつけてるんだろ」
「あら、たくさんの意見を聞くことは大事だわ。でないと独りよがりになってしまうもの」
独りよがりねえ。口内でイガイガした響きの言葉を転がし、不動は立てた膝に顔を埋める。
独りよがりだっていうなら、花を贈ることだってそうじゃないか。何の意味もありやしないのに。
「そう?」
「そうだよ。あんな顔すんなら、あのお姫様が現世に行かないように根回しすりゃ良かったんだ」
「そうねえ。それもひとつの解決かもしれないわね」
店主は否定することなく、一輪の花をバケツから抜き出す。手元に何かを書き付けて、次は別のバケツへと。
「でも、きっとそれは望まれてないんだわ」
「どうして」
「一期一振様は、ご令嬢の自由と幸せを願われたのよ」
「綺麗事だ」
「綺麗事なら、花なんて贈らないわ」
普段の彼女からは想像のつかない、鋭く尖った声音に、不動ははっと顔をあげた。
だが、彼女はいつも通り、穏やかに花を切っている。不動の視線に気づき、へにゃりと力なく眉を下げた。
「少し疲れちゃったわね。ゆきちゃん、おやつにしましょうか」
そう言って彼女はバケツから手を引き上げる。まだ春も中頃を過ぎない時期の水は冷たそうで、白いはずの彼女の手は真っ赤に染まって、ところどころにひびが入っていた。
*
──綺麗事なら、花なんて贈らないわ。
彼女の張りつめた声が頭に残っていた。普段の、気の抜けるようなへにゃへにゃしたものとは違って、触れれば斬れてしまいそうなほど鋭くて、凍てついてしまったように冷ややかで。それがどうにも頭から離れてくれない。
いつものように店先に座り込みながらも、花を選びに来た刀剣男士や審神者たちの様子をまじまじと観察し続けている自分がいる。柄でないことをしていると自嘲して首を振った。傍らに置いた鉢植えは、育て方が悪いのか、それともそういう品種なのか、植えてそろそろ一月になるのに芽を吹く気配はまったくない。
「ありがとうございましたー!」
花束を抱えて満足そうに店を出る審神者に、店員が上機嫌で頭を下げていた。そのまま店の中へと戻ろうとして、不動の視線に気づき目を丸める。その様子に若干嫌な予感がしてすぐに顔を背けたが、店員は気にせずニコニコしながら不動の前にしゃがみこんだ。
「なんだよ」
「ゆきくんもとうとう花屋稼業に興味をもってくれたのかなと思って!」
「もってねえ。もつつもりも予定もない」
「またまたあ、さっきから花を選ぶ審神者様や刀剣男士様に熱ぅい視線を送ってたでしょ?」
ニコニコをニマニマに変えて詰め寄ってくる男に、不動はじりじりと後退る。が、背後は壁だ。「近い!」と手のひらを押し付けると、ようやく彼は近寄るのをやめた。
「別に、花屋に興味があるわけじゃない」
「ん? ならどうして?」
「……どうして、花なんか贈るんだよ」
店員はぱちりと瞬いた。
「花なんか贈っても意味ないだろ。伝えたいことがあるなら口で伝えれば良かったんだ」
花屋に対してかける言葉ではないと分かっていたが、気がつけば不動は、ぼそぼそとした口調ながらもはっきりと尋ねていた。
そうだ。口で伝えればいいのだ。花を贈りたいのだと息巻いたあの少女審神者も、花を贈りたいのだと悩んでいたあの一期一振も、口で伝えればいいのに。
「伝わらなくていいなんて、嘘だ……」
俯きがちになって小さく絞り出した声に、ふと、温かい重みが頭の上に乗ったのを感じた。はっと顔をあげると、男が微笑を浮かべながら不動の頭を撫でている。
「……おい」
「いやあ、ようやくゆきくんの本音が聞けて嬉しくて」
「おい、ガキ扱いすんな!」
「してないよぉ。俺普通に大人相手でも頭撫でるし、店長も」
それはかなりの例外だろう! と吼えた不動に、男はおどけて手を離した。それから、ぐるりと辺りを見渡す。店の前に、中に、多くの審神者や刀剣男士が、花を選んでいた。
「俺はね、花を贈るのはけじめだと思ってるんだ」
「けじめ?」
聞き返した不動には答えず、男は内緒話をするように声を潜める。
「ゆきくん、どうしてうちの売れ筋トップスリーが菊、百合、ひなげしなのか分かるかい」
「……そんなの、」
分かるわけがない、と言おうとして、ひとつだけ、ずっと前から、もしかしたら、と思っていた可能性が頭の片隅でちかちかと閃いた。
は、と固まる不動に、男は小さな声で答え合わせをする。
「雛罌粟はイギリスでは戦没者の象徴なんだ。百合は宗派問わず死者の献花の定番。菊は……言うまでもないかな」
目を細めて菊の花束を抱き締める彼女も、たった一輪のひなげしを大事そうに受けとる彼も、店員とお喋りをして、笑って、それではと手を振ってから向かう先に何があるのか。
本当は、ずっと前から気付いていた。
「花なんて贈っても意味なんてないよ。伝えたいのなら口で言うべきだっていうのも正しい。伝わらなくてもいいなんて、嘘なんだよ、ゆきくん。君は正しいんだ」
「……」
「それでも花を贈ると、少しだけ、気が楽になるんだ」
独り善がりだ、と、不動は呻いた。そうだよ、と男はそれも肯定した。
「心って弱いからさ、独り善がりでないと生きていけないときもあるんだ」
誰かが店員を呼んだ。「答えになったかなあ」と困ったように言いながら彼は立ち上がる。影になっていた彼が歩いていったおかげで、日の光がすうっと不動のもとまで射し込み、眩しい、と目を細めた。
どれくらいそうして客たちを見送っただろう。長かった影が短くなり、また長くなった頃──
彼の刀は、やや緊張した面持ちで現れた。
3
寂しくなるね。待合室のソファでぽつんと呟いたのは、最後の見送りに来てくれた乱だった。
「そうだね」
大きな鞄と、紫色の花束を抱えた彼女もまた、ぽつんと返した。
そこは病院のような見た目の建物だった。ソファの横にはこれまた診察室の入り口のような扉があって、中で現世に馴染むための処置が行われる。具体的に言えば記憶を有耶無耶にする術式と、彼女のわずかな霊力を制御するための術式を施すのだ。
霊力に乏しい彼女の瞳でも刀剣男士はとらえることができる。ただ、あの扉を潜れば最後、もう乱の姿はこの目には映らない。
湿っぽくなりかけた空気を蹴飛ばすように「あーあ、湿っぽい話はもうやーめた!」と、乱はうんと伸びをする。
「それにしても、ボク、まさかいち兄がこんなにロマンチックなことするなんて思わなかったよ」
「この花束のこと? ……卒業式の花束贈呈みたいなノリじゃない?」
彼女はそう肩を竦める。自分の目付役として、実の兄か或いは保護者のように接してきた一期一振は、最後の日である今日も特に態度を変えなかった。
好き嫌いをしないこと。夜更かしをしすぎないこと。たまには父親である主に連絡を寄越すこと。一人暮らしを始めてから帰省で顔をあわせるたびに口を酸っぱくして言われることを今回も繰り返された。あと数時間でそんな忠告、記憶から全部消されてしまうというのに、彼は努めて、いつものように彼女を送り出した。
ただ、ひとつだけ。餞だと手渡されたのは、片手に収まってしまうほどの、小さな紫の花束だった。
いいですか、と、言った、あの穏やかな声を思い出す。
──むっと思っても口に出す前に自分の胸に手を当てて、言葉を選びなさい。
──手を出すなんてもっての他。あなたは我々が手塩にかけて育てたのですから、並みの男なんて相手になりません。力を使うときはきちんと考えること。
──もう何かあっても、主にも私にも泣きつくことは出来なくなるのですから、あなたが選ばれた方と二人で助け合って生きていきなさい。
「お兄ちゃんなんだから」
小さく囁いた恨み言ももう届くことはない。浅葱色のリボンが結わえられた花束を見つめれば、乱は寂しそうに笑った。
「ねえ、それ、何の花なの?」
「ライラックだって」
花束に添えられた、花屋のものだろう説明書きには、紫色の小花を咲かせる木の写真と共にそう名前が綴られていた。カードを読み上げると、へええ、と乱は目を丸めて、彼女が差し出した花束に顔を寄せる。
「『ヨーロッパ生まれの花木。フランス語ではリラ。花言葉は思い出。花冠の先は通常四つに割けているが、五つに割けているものは珍しく──』」
そこで彼女は一旦言葉を切った。乱の青い瞳がこちらを向く。
ふ、と、彼女の瞳が大きく揺らぎ、そして静かに凪いでいった。
「『見つけたことを誰にも知らせずにその花を飲み込めば、愛する人と永遠に幸せに過ごせる』んだって」
「……えっ」
彼女の指が摘まんだのは、ちょうどその、五つに割けたライラックの花だった。
「待って!? なんで知らせちゃうのさ!」
「さあ、なんでだろうね」
彼女はそのままぷつんとその花をちぎって口にふくんだ。効力のないおまじないの花が奥歯で擂り潰されて、こくりと飲み込まれる。
「もう叶わないからじゃないかな」
目を閉じれば鮮明に思い浮かぶ。花束を渡したときの一期一振の顔が。あと一時間も経たずに消えてしまう記憶の中で。
いつもとは違う、兄ではない表情を、初めて少しだけ覗かせて、どうかお元気でと彼は言ったのだ。
*
花屋の中はライラックの花で溢れかえっていた。いつも朗らかな店員たちも「どうするんですか、これ」と呆れている。
「だって、どうしても必要だったのよ。五弁のライラック」
「だからってありったけライラック注文しないでください!」
流石に非があることは自覚しているのか、店主は肩をすぼめて小さくなった。紫色の花は独特の匂いを振りまいていて、良い匂いなのだが流石に鬱陶しい。不動はライラックの林のふもとに座り込んで、本日何度目かになるため息をついた。
「あら? 今日は、ええと……ずいぶん良い匂いがしますわね?」
と、そこで顔を出したのは、いつぞや不動に花を選べと騒いだ少女審神者だ。「それも紫ばかりが沢山……?」と不思議がった彼女に、店員たちがひきつった表情筋をなんとか自然に動かして笑顔を向ける。
「今日も花を探しに来たのか」
「ええ! 今日こそ相談に乗ってもらいますわ、不動行光様!」
「……例のハハコグサはどうなったんだよ」
「あれも贈らせていただきました! だけどまだまだ、私の想いが届いた気がしなくって……」
だとしても、自分に聞いたところで届くようなものでもないだろうに。ふああと欠伸をすれば「真面目に取り合ってくださいまし!」とむくれた彼女が不動につかつか詰め寄った。
「じゃ、ライラック」
「ライラック? ……こちらの花ですの?」
「そうだよ。ライラック全般の……花言葉、は、思い出だけど、紫のライラックだと別の意味になる」
「……それは?」
「……あー、と、『恋の芽生え』とか、『初恋』……?」
少女の目が煌めいた。頬を掻き、目をそらしながら不動は続ける。
「あと、恋のおまじないにも使われるとかなんとか……」
「買いますわ! ありったけ包んでくださる!?」
即断即決、気持ちの良いくらいのスピードに店員たちは心からの笑顔で「かしこまりました!」と叫んだ。
両手いっぱいの花束を抱えて、少女審神者はほくほく顔で店を後にする。その様子を見たのか、ひとり、ふたりと客が入り、この花はなんだと店員に問うた。そこから彼らの切り替えは早く、やれ『思い出』を花言葉に持つ花だ、やれ『友情』を意味する花だと舌を回してはライラックを売り込んでいる。
「……なんか、悪いことした気分だ……」
大量に買い付けたライラックは全て花弁を確認しており、うち、五花弁のライラックは一期一振に卸したあれだけだ。審神者たちが買っていった花束の中に、恋が叶う花は入っていない。
だが、店主はけろりとして「こういうのは気の持ちようですもの」なんて宣った。
「ゆきちゃんはプラシーボって知ってる? お薬だと思いこんで食べれば飴玉だってお薬になるのよ」
「詐欺師じゃないか!」
「幸せになるためには多少の嘘やごまかしも必要だと思うわ」
花言葉なんて最たる例だと花売りは笑う。
「タンポポの花だって、『別離』の花言葉を持つけれど、『真心の愛』の意味だってこもってるし」
「結局気持ちってことかよ……」
「そうよ。お花はあくまで媒体であって、メッセージを込めるのはその人自身なんだもの」
そこで店主は嬉しそうに手を合わせた。
「ゆきちゃんも立派にお花屋さんになってくれて嬉しいわ」
「だから! 花屋になるつもりも! なる予定もないって言ってるだろ!」
声を荒げても店主はまるで聞いちゃいない。やってられるか、と不動は店先に出ていつもの場所に座り込んだ。紫の花束を持ったものたちは、不思議そうに、あるいは微笑ましそうにそれを見て、それぞれの道へと帰っていく。
カーネーション1
朝の八時。いつものように、住居として使っている二階から、店のある一階まで欠伸をしながら下りてきた不動は、店舗を埋め尽くす色に息を詰めた。
──赤。
──一面の赤。
ゆらゆらと記憶の中で揺れる色の中に、人間がひとり、うずくまっている。さあ、とすべての音が遠のいていく中、その人間がゆっくりと立ち上がり、こちらを振り向いた。
「あら、おはよう、ゆきちゃん」
「……っ、ああ、おはよ」
人間は、この花屋の店主で、片手に花切り鋏を持っている。「なあに、まだおねむ?」と笑う彼女に、不動はようやく、彼女をとりまく赤い色が花であることに気が付いた。
なんだ、と、拍子抜けすると同時、知らずのうちに安堵していた不動は首を後ろを掻いて「別に」とそっぽを向く。
「まだ始業まで少しあるから、顔を洗ってきたら?」
「だから別に、眠いわけじゃねえ。少しぼうっとしてただけだ」
「そう?」
「それより、なんだよこれ!」
この光景の異様さを見せつけるように、不動は大きく手を振った。赤い花があるだけならまだいい。この花屋ではヒナゲシもよく売れるから、それくらい日常茶飯事だ。だが、問題は満たされていることと、もう一つ。
「なんで同じ花ばっか仕入れてるんだよ!」
「あら、ゆきちゃんも花の種類が分かるようになったのね」
「馬鹿にしてるだろ!」
「してないわよ。成長を喜んでるだけ」
それを人は馬鹿にしていると言うんだ! 怒鳴ってやりたかったが、怒鳴ったところで暖簾に腕押しだろう。不動は開きかけた口を閉ざし、ぎりぎりと歯ぎしりをした。
襞をたくさん集めたような花は、この店で売れ筋トップスリーと呼ばれる菊・ユリ・ヒナゲシほど登場頻度は高くなくとも、たびたび花束として買われていくから知っている。かつては「あんじゃべる」と呼ばれていた、現代ではカーネーションという花だ。
だが、この入荷量は尋常ではない。選択肢は広ければ広いほどいいなんて普段は採算度外視で宣うノホホン連中の店では考えられない狂気の沙汰だ。それも、よりによって菊でもユリでもヒナゲシでもなく、カーネーションだ。
いや、一度だけこんなことがあったかと不動は思い出す。一期一振のため、どうしても五弁の花を手に入れたいとありったけ紫のライラックを注文し、店内が紫色で溢れかえったことが。あの時は店員総出で目が痛くなるくらい紫を見た。
「……今度は何弁を探すんだ?」
恐る恐る尋ねたのと同時、勝手口から「おはようございまあす」と陽気な声と共に店員たちがやってくる。そして、立ち尽くす不動と、店を埋める赤い色と、店の真ん中に佇む店主を交互に見て、ああ、と合点がいったように手を打った。
「そろそろ母の日ですね!」
「そうなの!」
ハハの日……? と固まった不動に、店員はにっこり笑って頷いた。現代の風習だよ、と。
曰く、現代の日本では、五月の第二日曜日を母親の日としているらしい。そして、その日には、日頃の母親の苦労をねぎらい、感謝を込めてカーネーションを贈るのだとか。
なあんだ、と、脱力したように不動は店の片隅にへたりこんだ。「また店長が頭おかしいことしでかしてるって思ったでしょ」と、よりにもよってその店長の目の前で言い放ったのは、不動によく絡んでくる、茶色いエプロンをした男の店員だった。
「あら、私そんなに頭のおかしいことしてるかしら?」
「ライラック事件のこと、忘れたとは言わせませんよ。ゆきくんもそれ思い出してたんでしょ」
「全部さばけたからよかったじゃない」
「じゃなくて、探したときのことですって」
仰る通りだ。珍しくうんうんと同意を示しながら、いや待てよ、と不動はさっき男や店主が言っていたことを思い出す。
母の日には、赤いカーネーションを贈ると。
「いや、需要!」
「需要?」
「大和国に本丸は確かにたくさんあるけど! その中で女審神者の割合と! 女審神者に子供がいる割合を考えろよ!」
ばん、と不動が立ち上がる。確かに、と男は頷いた。ただでさえ出会いが少ないうえ、本丸の主権の問題で審神者間の結婚は成立しづらい。言わずもがな、審神者と一般人の結婚もだ。つまり、この業界で母親の数は圧倒的に少ない。
仮に、本丸の審神者が、現世にいる母親にカーネーションを贈るとしても、城下で買った花を現世に送ることはできない。普通に業者を使うはずだ。
そして、これは至極当然のことなのだが、物である刀剣男士に母親はいない。
「需要がないだろ! どう考えても!」
「あるわよ。……たぶん?」
「言い切ってくれよ!」
「だって、洋菓子店さんはバレンタインデーやホワイトデーみたいな、現世のビジネスチャンスを上手に取り入れてるじゃない? だったら、お花屋さんだって、最大のビジネスチャンスな母の日をやるべきだと思わない?」
「方法を吟味して!」
バレンタインデーやホワイトデーは、意中の相手に贈るという、本丸の生活でも再現しやすい大義名分があるが、母の日にそれはないだろう。ああもう、と頭を掻く不動に、まあまあ落ち着いてと男は手を振る。
「たとえば、母の日のポップを審神者様や、審神者様のお子様向けに出して、刀剣男士様向けには『これを機会に審神者様への日頃の感謝を伝えませんか?』っていう風に宣伝してみたらどうかな?」
「どれを機会にだよ……」
「あら、でも、審神者は刀剣男士を顕現させるんだから、ある意味生みの親みたいなものじゃない?」
「……審神者は審神者だろ」
親とは違う。唇を尖らせる不動に、店主は眉を下げて「ゆきちゃんにとってはそうなのね」と呟く。ふたりを交互に見た男は、ううむと顎を擦った。
「なら、わざわざ明記しなくてもいいから、『日頃はなかなか伝えられない、審神者様への想いをお花で伝えてみませんか?』って感じで宣伝してみたらどうかな」
どのみち、と男は苦笑して店内をぐるりと見渡した。
「このカーネーションの山、どうにかしなきゃなんだしさ」
「……まあ、それはそうだけど」
しぶしぶと引き下がった不動に、男は店主の方を見て小さくウインクした。店主はほっとしたように笑って、「じゃあ、ポップを作らなくちゃね」と机に向かう。
「ゆきちゃん、ポップ書いてみない?」
「書かない」
どうしてこの流れで自分に書かせようと思うのか。ふい、と不動は踵を返して、甘酒の瓶を片手に店の外に向かった。
「お外に出るなら、鉢植えに光を当ててあげてね。あと、お水も」
「分かってる!」
店員の誰かが、反抗期の息子と母親みたいだなあとぼそっと零した。誰が反抗期だ。そんでもって、誰が誰の息子だって? 冗談じゃないと不動は首を振る。
自分を顕現させた主ならまだしも──と、考えて、やめた。不毛なことだと思ったからだ。
*
どうせそう売れないだろう。いそいそと広告を作り、売り込みの言葉をかける店員たちを尻目に、不動はそう決めつけていた。ただでさえ需要がないのに、母の日だなんて。第一、主への日頃の感謝、なんて、人間側から言ったって押しつけがましいだけじゃないか? とも。
だが、そんな不動の予想に反して、売れるのである、これが。
「主君、良かったですね」
「うん!」
ふくふくしい林檎ほっぺを輝かせたのは、まだ十にも届いていないだろう少年だった。その隣でニコニコしているのは秋田藤四郎で、おそらく護衛としてつけられているのだろう。
白いカーネーションの花束は、少年の小さな手にも収まりやすいよう、茎を短く切って籠に詰められていた。「きっとお母上もお喜びです」と声をかける秋田に対し、少年はこくこくと頷いて、小さな手で落とさないようにぎゅうっと籠の持ち手を掴んでいる。
その後ろで、真剣な顔で花を選んでいるのは、上品な色無地を纏った老婦人と浦島虎徹だった。
「切り花だとどこにでも飾れるけど、すぐに萎れちゃうよなあ。でも、鉢植えだと世話の手間がかかるし……」
「いいのよ、浦島。気持ちだけで」
「でも、ほら、せっかくだしさ。主さんいつも言ってるじゃん。俺たちのこと、自分の子どもみたいに想ってるって。じゃ、親孝行しないとさ!」
「まあ……」
「あ、でも、皆で一斉に同じもの贈られるとそれはそれで大変だよな。ごめん、主さん! やっぱ後で皆で相談して決めるね!」
つきあわせてごめんなさい! この通りです! と手を合わせる浦島に、店内もほっこりした空気に包まれた。それにつられて、自分も、と、店を覗く刀剣男士がつられ、そうでなくても、そういえば母親に連絡とってなかったな、と審神者が足を止める。おかげで店はいつも以上に賑やかだ。
完全に予想が外れて、唖然とした気持ちで不動はそんな店内を眺めていた。逆に店主は清々しい笑顔で、「またのご利用をお待ちしております」と、花を持った客たちを送り出している。
何故? 店の前で首をかしげる不動の耳に、「あらまあ」と、あまり聞きたくない声が入った。
「今日はいつも以上に賑やかですのね」
「げ」
「げ、とは失礼ですわね、不動行光様」
眉を寄せたのは、よく花屋に訪れては不動にちょっかいをかけてくる、やっかいな少女審神者だった。
刀剣男士が意中の相手なのか、『刀剣男士』ということしか共通項を持たない不動行光を捕まえて、どの花を贈るべきかと一方的に相談してくる相手だ。警戒心を顕わに、「……花の相談には乗らないからな」と言えば、彼女は「今日は結構ですわ」と胸を張った。
「今日はカーネーションを買うって決めてましたもの」
「めずらしいな」
「私だって、自分で考えることくらいあります。白いカーネーションは『純粋な愛』を意味する花でもあるのよ。まあ、さっき店員さんから言ってもらったことですけど」
結局受け売りじゃないか。なあんだと呆れた不動に、彼女は「受け売りでもいいんです」とぷりぷりと頬を膨らませた。
「どうせカーネーションを売る戦略だろぉ」
「それでも、白いカーネーションが『純粋な愛』を意味するのは変わりませんわ。きっかけなんて些細な問題です」
力強く言い切った彼女に、不動はようやく顔を上げる。
「きっかけが不順であれ、どうであれ、良い行動に結び付けばいいんです。それを言い出せば、母の日にカーネーションを贈ることだって、お花屋さんがお花を売る口実ですわ」
「……まあ、それはそうだけど」
「でも、それがきっかけで、日頃言えなかったことを言えたのなら、それは悪いことじゃないでしょう? 違って?」
正論に不動は言いよどむ。言い負かされたのが悔しくて、「そうだな」とぶっきらぼうに返せば、彼女はむふんと鼻息を荒くし、「ですので、不動行光様」と手を合わせた。猛烈に嫌な予感がする。
「刀剣男士様が好むリボンは何色なのでしょう?」
「相談には乗らないって言っただろぉ!」
「『花の』相談には乗らないと仰いましたわ。ラッピングの相談には乗らないとは仰ってませんもの」
「屁理屈だ!」
屁理屈結構。今日こそは逃がすかと目をきらめかせた彼女の後ろ、ぽかんと佇む刀剣男士が視界に入った。
その刀剣男士が、こちらを向く。澄んだ緑の瞳。山姥切国広だ。
「あんた、この店の──」
そう言いかけて、いや、と口を閉ざす。しかし、不動がそれを許さなかった。
基本的に、不動は店員ではない。店員の仕事はしない。だが、この状況において、この少女審神者から逃げる手っ取り早い名目は、店の仕事の一点しかなかったのだ。
「そうだ」
気付けば不動はそう言っていた。
「何か花を探しているのなら、話くらいは聞いてやる」
と。
2
『普段はなかなか言えないような、感謝の気持ちを伝えてみませんか?』
花にあまり興味のない自分が、思わず店先で立ち止まってしまったのは、その売り文句にどきりとしたからだろう。赤い色を中心に、店先から零れ出るように咲き誇っている花々の中、そのポップは決して派手ではなかったけれど、山姥切国広の意識を奪うには十分だった。
初期刀である自分が、審神者である女主人に仕えてもう十年近くになる。彼女の就任記念日は、そろそろ間近に迫っていた。
「なるほど、審神者様の就任記念日に合わせた贈り物を」
素敵、と微笑んだのは、国広に声をかけてきた不動行光ではなく、花屋の店主である妙齢の女だった。花咲くような笑顔で店内に迎えたかと思えば、あれよあれよという間に国広は来客用の椅子に座らされ、気付けば茶を飲んでいる。茉莉花を乾燥させて作った茶は、口に含めば良い匂いが鼻に抜けた。
「……自分でも、似合わないとは思っているんだが」
「そんなことはありませんよ。ねえ、ゆきちゃん?」
振られた不動行光の顔には「俺に聞くな」とでかでかと書いてある。店員じゃなかったのかと尋ねると「ただの護衛だ」ととげとげしく返された。その態度もよくあることらしく、店主は顔色一つ変えない。
「山姥切国広様は、既に極がついていらっしゃるようですけれど、審神者様との間柄はどのようなものなのですか?」
「初期刀で、審神者の就任からずっと近侍を任されている。身近にあるという意味ではそれなりだとは思う」
あと数日で、この付き合いも十年に届こうとしている。膝の上に置いた手を軽く握り、薄黄色の水面に視線を落とした。
十年だ。最初は血を見ると真っ青になり、怪我をして帰ると慌てふためいていた彼女も、ずいぶん肝が据わった。頼りなかったただの少女は、十年経って立派な主になった。
それに気が付いたのは、日課をこなすために演錬場に向かった時だった。
「国広、少し待ってくれ」
そう呼ばれて立ち止まり、審神者の視線を辿れば、困ったように立ち尽くす、真新しい緋袴を纏った少女がいた。似たような状況には何度が遭遇したことがある。初心審神者にとって、たくさんの会場がある演錬場はちょっとした迷宮だ。地図を持ったまま難しい顔をしている彼女の隣、まだ襤褸布を身に着けている頃の自分が、どう声をかけたものか惑っている。
「まだ時間はあるね?」
「ああ。あと三十分は」
「ちょっと行ってくる」
言うやいなや、彼女は少女審神者の方へとつかつか歩いていく。主を見上げた少女審神者の目には、薄く涙の膜が張っていた。
どこか既視感があるその光景に、はた、と国広は思い出す。そういえば、自分たちも似たようなことがあったはずだ。
あの、頼りない少女審神者は、十年前の主そのものだ。
あんなに頼りない少女だったのだ。それなのに、彼女が主であるということが、あまりにも当たり前になっていた。
捥げた腕を見て気を失いかけていた彼女は、今では細い肩で重傷の刀剣男士を担いで歩く。刀なんて触ったことがないと言っていた白くて細い指は、いつの間にか皮膚も厚く、節くれだっていたし、鍬すら持ったことがなかったくせに、今は田植えで腰が痛いなんてぼやいている。
今更、彼女が成長したことや、その成長を当然だと思っている自分に気が付いた。
「毎年、就任日は祝いの膳を出したり、挨拶をしたりするんだが、贈り物はしたことがなくてな」
十年の節目ということにかこつけてもいいはずだが、どうにも踏ん切りがつかなかった。
今まで何も伝えてこなかった。どころか、その成長を当然のものとして胡坐をかいてきたのだ。
そんな自分が、今更何を伝えたものだろう。
「……正直、目についたから花屋に立ち止まっただけで、花を贈られている彼奴も、花を贈っている自分も想像できないでいる」
国広は顔を上げて、花屋の中をぐるりと見渡す。
彼女は、いつの間にか、花だとか、可愛らしくて柔らかいものに興味を示さなくなっていた。そんな中、花を贈られても、興味がないと困らせるだけかもしれない。
それに、歌仙兼定、三日月宗近、小狐丸。いかにもな文化刃ならともかく、自分が花を持って、贈っている姿はあまりにも現実味がない。
そして、花を持って、自分が何を言えばいいのかも。
大ぶりな、赤い花束を持った自分が、何を言う? ありがとう? それとも立派になったな、だろうか。
そもそも、何を伝えたいのかすら、広がっていくばかりでまとまらないのに。
国広は押し黙って、しんと辺りは静まり返った。店主は何かを考えているようで、扱う花の目録を視線でなぞっている。そこから一、二、三拍。国広は小さく息をつき、「すまない」と呟いた。
「やはり、今回は──」
やめておく、と言いかけたのを制したのは、いつの間にかこちらをじっと見つめていた、紫色の瞳だった。
「やめるのか」
と、小さく尋ねる不動に、隣に座っていた店主がわずかに目を見張った。
声にしてから、不動は自分が口に出していたことに気が付いたのだろう。気まずげに目を泳がせる。
「……いや、何でもない」
「何でもないことはないだろう」
「本当に、何でもないんだ。俺はダメ刀で、あんたみたいなヤツに言えることはない」
「俺も、かつては自分のことをそう感じていた。だが、それを決めるのはあんたじゃない。俺だ」
なんでも言ってくれと促した国広に、不動は躊躇いながらも口を開く。「それであんたは、後悔することはないのか」と。
「きっと、あんたのそれは今じゃなきゃダメだ」
「不動」
「ダメなんだ。後で、とか、また今度とか、そういうのは絶対にダメなんだ。俺は、俺が言えたことじゃないけど、でも、ダメだ」
深い紫色をした瞳の中に、カーネーションの赤い色がちらちらと映り込んでいる。
「いつか、は、ずっとあることじゃないから」
国広は小さく息を詰めた。
「大袈裟で、柄じゃなくて、あんたの審神者には笑われるかもしれないし、言わなきゃよかったって思うこともあるかもしれないけど、でも、言ってりゃよかったって思うことだって、あるんだ」
だから、と言いかけて、続く言葉を選べなかった不動は唇を引き結ぶ。沈黙が再度下りかけた、その中で浮かんだのは、不動の隣に座った女のやわらかな声だった。
「山姥切国広様。私も、不動行光の言っていることに賛成です」
はっと不動が隣に顔を向ける。それに構わず、彼女は微笑んだまま手を合わせた。
「差し出がましいことを言ってしまっているかもしれませんわ。でもね、山姥切国広様が考えていることは、形にしないと一生審神者様には伝わらないと思うの」
そして、彼女は胸に手を当てる。「同じ、現代に生きる人間だから分かるのですけれどもね」と静かに続ける。
「審神者様はとても、とても大変な思いをなさって、変わられたんだわ。そして、そんな審神者様を、山姥切国広様は心から敬愛してらっしゃるんだって」
「……そう言われるとなんだか気恥ずかしいんだが」
「でも、ここで私が、審神者様のその努力は審神者として当たり前の事だって言ったらものすごくカチンとくるでしょう?」
それはそうだ。彼奴がどれだけ苦労したのか、目の前で見てからもう一度言えと詰め寄るくらいはするだろう。何も知らないくせにと怒鳴るだろう。
だったらそう伝えた方がいいわ、と、彼女は力強く言った。
「審神者様は、自分にとってはもう自慢の主なんだって。だって、そうじゃないと、相手が自分をどう考えてくれているのかなんて分かりませんもの」
ひょっとしたら、山姥切国広の中では、自分はまだただの弱々しい女の子なのかもしれない。これくらいの努力は、審神者として当たり前のことだから、大したことはしていない。むしろ、もっと頑張らないといけない。そんな風に考えているかもしれない。
大袈裟でもいいんですよ、と彼女は笑った。
「それに、山姥切国広様は、何て言えばいいのか分からないと仰ったけれど、だったら猶更お花はぴったりだと思います」
「それは、どういう意味だ?」
「お花なら、言葉なんていらないんですよ。だって、言葉の代わりにお花があるんですもの」
さあ選びましょう、と彼女は目録を開いた。
「貴方にとって、審神者様がどんな方なのか、たくさん教えてくださいな」
心を締め付けていた何かが、明るく照らされることで融けだしたような気がした。
鉢植えがいいでしょうか? 花束がいいでしょうか? ──最初だから、花束がいいと自分は答えた。中堅に数えられるようになって、日々忙しい主に、花を世話する暇はないだろうし、何よりあまり長く残ると自分が少し恥ずかしい。
大きさはどれくらいがいいでしょう? ──あまり、大きくない方がよさそうだと自分は答えた。あまりに大きすぎる花束だと、そう大柄でもない主の手には余ってしまうかもしれないから。でも、一輪だけに決め切れる自信がないから、やはり束にはしてほしい。
色はどんな色がいいでしょう? ──難しいが、赤は贈りたい。
国広は顔を上げて、店先に並んだ花を見た。この店に入ろうと思ったのも、あの赤い花がきっかけだった。
乱藤四郎がよく好むような、ふわふわした、フリルとかいうのをぎゅっと集めたような柔らかい花。彼女の手が固くなっていくにつれて失われたもの。
「あの花は、感謝を伝えるために贈る花、なんだったな」
ならばあの花はぴったりなんじゃないかと思った。
不動と店員が花の入ったポットを持ってくる。赤、白、桃色、淵だけ赤い白だったり、面白いものだと七色のものまで。束ねるとこんな形になると、いくつか花をまとめて握った店員の向こうに、別の色を見つけて国広はわずかに尻を浮かす。
「ああ、この色は……確かに。花言葉的にちょっと難しい子ではありますけど、色は山姥切国広様にぴったりだ」
「ベースは別の色にして、アクセントで入れる分には大丈夫じゃないかしら」
そうですね、と店員は頷き、その色を花束に加える。出来上がった花束を前にして、国広は目を細めた。
もう、不安はなかった。
3
最初に捨てたのはスカート。次に捨てたのはリボン。それから捨てたものは、もうあまりよく覚えていない。
とろとろとした微睡の中、就任十周年、おめでとうございますと声をかけられて、彼女はゆっくりとそちらを見た。
「もう一端どころか、熟練の審神者様でいらっしゃいますね」
「そうだろうか。まだまだ半人前のように思うよ」
「いえいえ。主様はとても立派な審神者様ですとも!」
と、審神者の私室でぴょんぴょん跳ねたのは、本丸が設立されてからの付き合いになるこんのすけで、「その証拠に、ほら」と誇らしげにディスプレイを表示して見せる。
「こんなにもすばらしい戦績が!」
「単なる年の功だよ」
「またそんな風に……審神者様がすごいのは本当に本当なのですよ? 身近で見ていたこんのすけめが証明です」
「はいはい。ありがとう、こんのすけ」
適当に頭を撫でておくと、むう、とこんのすけは押し黙り、表示させていた戦績画面を消す。しばらく審神者に恨めし気な目を向けていたが、「さ、支度なさってください」と気分を切り替えるようにひと声吠えた。
「刀剣男士の皆さまも、主様のお祝いをしたいでしょうから」
「そうかな?」
「そうに決まってます! まったくもう、どうして貴女様って方はそんなに頑ななんですか」
「そういう性分でね」
軽く手を振って身を起こす。ぼさぼさになった長い髪をかき上げて、ぼんやりと視線を巡らせた。十年間、たいして変わり映えもしない、物の少ない私の部屋。
あらかじめ水が張られた盥で顔を洗い、衣桁にかけられた、文字通り色気のない無地の小袖をまとって地味な色の袴を合わせる。髪は適当に梳かして後ろで束ねた。ふと、姿見に映った自分を見る。油っけのないぱさついた髪に、紅も差さない地味な顔。
「せっかくの記念日なのですから、多少はおめかしされてもいいのでは?」
足元のこんのすけがつんつんと袴の裾を引いてそんなことを言う。「ほら、いつぞや御母堂が贈られた紬など」と、箪笥に視線を投げるものだから、審神者は思わず笑ってしまった。華やかな桜色のあの紬。しまい込んでどれくらいになるだろう。
「いくら記念日とはいえ、戦時であるには変わりない。贅沢は敵……とまでは言わないが、通常任務に支障が出る装いは避けるべきだよ、こんのすけ」
「むう……」
「それに、今更こんなのは似合わない。お笑い草になるのは勘弁だ」
「そのようなことは、ないと思いますがあ」
ぐちぐちと言いながらも後ろに続くこんのすけを抱き上げ、審神者は「お世辞でも嬉しいよ」と額を合わせた。ふわふわでぬいぐるみのような不思議な管狐。抱きしめることはかなわなくても、肩に乗せるくらいはかまわないだろう。
廊下を歩き、大広間の戸を開けると、そこにはいつものように刀剣男士たちが並んでいる。一番前、もはや顔を隠さなくなった初期刀が前に進み出て跪坐し、「就任十年、お祝い申し上げる」と朴訥に告げた。
「有難う、国広。皆も」
「きょうは、おいわいのせきももうけますからね! 燭台切と歌仙が、いっしゅうかんもひたいをくっつけてなやんだこんだてです!」
「ちょ、今剣……!」
軽やかなやりとりにどっと笑いが起きて、厨番のふたりがやや気まずげに頬を掻く。そんな様子を微笑みと共に見渡して、審神者はここ十年で随分通るようになった声を張る。
「皆の忠心、真心、祝福に心からの感謝を。が、残念ながら戦争は現在も続いている。私が無事生きて十年を迎えられた幸運には感謝もせねばなるまいが、十年経っても戦闘が続いている現状は憂うべきことだ」
「はっ」
「羽目を外すのは夜の宴席からだ。それまでは、浮かれすぎず、騒ぎすぎず。諸君らのいっそうの奮戦を期待する」
「御意に」
一斉に頷く群れを見つめ、「それでは、解散」と手を打てば、三々五々、それぞれがそれぞれの任務へと向かっていく。こうやって主として担がれるのも、ずいぶんと慣れてしまったものだ。小さくふ、と息をついていると、目の前にゆらりと金の陰が立った。
「ああ、すまないな。行こうか、国広」
立ち上がりながらそう言えど、近侍の反応は微妙に鈍い。どうした? と首をかしげても、「いや、」と言い淀み、何も言おうとしない。
「……ひょっとしてものすごい量の仕事が届いた、とかか?」
「そんなことはない。断じてない。普通の量だ」
「そ、そうか?」
そんな力いっぱい否定するようなことだろうか。審神者はなおも訝しみつつも、ひとまず国広に合わせて頷いた。「そうだ」と念を押してから、近侍はぎくしゃく歩き出す。執務室に向かうのだろうか。
廊下ですれ違った山姥切長義は盛大にため息をついた。庭で洗濯物を干していた堀川国広はやけに生温かい視線を投げてくる。馬小屋の近くにいた山伏はいつもの如く笑うのみだ。全員、何かを察しているが、自分に教える気はないらしい。
それはそれでなんだか腹立たしい。国広の様子がおかしいまま執務室について、いつものごとく文机の前に座って端末をつけると、祝いのメールが一斉に開いた。大半が政府の役人や、社交辞令じみた同僚からの祝電だが、中には何通か、かつて面倒を見た後輩のものも混じっている。
ひとつひとつ、返事を考えながらより分けていると、ふと一通で指が止まった。
「……ああ、あの時の」
「どうした?」
「いや、前に演錬場で迷っていた女の子がいただろう。わざわざ御礼と御祝のメールをくれたんだ。律儀だなと思って」
頼りなげな体を縮めながら、おびえたようにあたりを見渡していた、緋色の袴の彼女。ちょうど、十年前の自分を見ているような気になって、思わず声をかけてしまったあの少女だ。
なんとか本丸の運営も軌道に乗り始めました、という近況報告と、あなたのようなかっこいい審神者になりたいです、という純粋な賛辞がつづられていて、彼女は小さく苦笑する。
私のようになっちゃいけないよ、と返事をしてもいいものか。キーボードに指を置きながらそう独り言ちると、隣の近侍の碧い瞳がはつりとひとつ瞬いた。
「あんたは、こうなったことを後悔しているのか?」
「いや、後悔はしてないけど……そうだなあ。捨ててきたものを、数えることはあるかな」
なんせ、昔は今よりもずっと、厳しい世界だったから。
女が刀の主だなんて、と何度言われたかわからない。所詮は顔の良い刀剣男士につられたのだろうと陰口を叩かれたこともあった。女に戦の何がわかると、人だけでなく刀剣男士にも、面と向かって言われたことすらある。
血を見るたびに恐ろしく感じた。誰かが傷つき倒れることが恐ろしくてたまらなかった。それを、自分は女々しさと呼んで呪って恨んできた。
スカートなんて穿かない。動くのに邪魔だし、戦うには非効率だ。リボンもいらない。結ぶ手間がかかりすぎる。化粧もしなくていい。そんなものにかける時間もお金もない。
弱さをなくすために、自分から「女」を削いだ。「女」である審神者を見るたびに、内心密かに見下して、削いだ。削いで、削いで、削いで──そうして。
気が付いたときには、「女」に戻れなくなっていた。
「今はとてもじゃないけど、緋袴なんて穿けないよ。恥ずかしい」
こんな男女がさ、と笑って見せたのに、国広の表情はぴくりともしなかった。どころか、じっとこちらを見つめる瞳は澄んでいて、真剣そのもので、審神者はわずかに身構える。
「恥ずかしいことだろうか」
「……や、だって、私には女の子らしすぎるというか」
「あんたが女の子らしくて何が悪いんだ」
まっすぐな、馬鹿正直な声でそんなことを言うものだから、審神者は言葉を失った。
「いや……あんたが、その、緋袴が嫌いで仕方なくて、それで穿かないというのならば、好きにすればいいと思うが、恥ずかしい、が理由ならば、恥ずかしいことではないと言いたかった」
「……いや、でも、私は主で」
「女の子らしい主の何が悪いんだ」
「悪いっていうか……悪いでしょ、色々と。だって」
国広は見てきたはずだ。たかだか軽傷で右往左往する、馬鹿みたいに情けない弱っちい自分を。
刀ひとつまともに扱えなくて、倒れた男士を介抱することさえできない、女々しくて弱い私を。それなのに、「女の子らしい主の何が悪い」だなんて。そんなの。
「悪くない」
「……悪いよ」
「悪くない」
「……悪いよぉ」
「あんたが言ったんだ。俺は俺でいいんだろう。なら、あんたはあんたでいい。女の子らしかろうが、なかろうが」
ぽん、と頭に手が置かれて、そこで初めて、自分がうつむいていることに気が付いた。目の奥が熱くて、鼻の奥がきいんと痛む。滲みかけた視界に、ふと差し込まれたのは、ふわふわとしたフリルのような束。柔らかなオレンジと、ピンクと、赤い色。
「……その、就任十年の、祝いだ」
気恥ずかしそうに言った国広に、審神者は思わず顔を上げた。机越しに差し出されたのは、間違いなく花束だ。
カーネーションを束ねた、かわいらしい、女の子らしい花束だ。
「私には、」
似合わない、と言おうとして、その先は言葉にならなかった。「似合う」と、先んじて目の前の男が断言したからだ。
「笑わない。あんたは、あんただ」
「……それ、もう十年早く言ってほしかった」
「それは……本当に申し訳なく思っている」
「今更って思わない?」
「思わない」
花束を抱いてみてもいいのだろうか。おそるおそる手を差し出してみる。柔らかな香りが鼻腔をくすぐった。きっと酷い顔だろうに、国広は何も言わない。ただ、じっとこちらを見つめるだけ。
「国広」
「なんだ」
「これに合う、花瓶を探したいんだけど、あとで城下に付き合って」
「わかった」
「顔、ひっどいから……次郎呼んで。化粧教えてもらわないと」
「ああ」
「……なるべく時間かけて探したいから午前中にこの仕事終わらせといて」
「ぜ、善処する」
そこは、わかった、じゃないのか。審神者はくすりと笑って、雨上がりのように雫の散った花束を見下ろす。ピンク色、オレンジ色、赤色。柔らかな暖色の、パニエみたいに膨らんだ花束の中央、一輪だけ、黄色のカーネーションがおずおずと顔を出していた。
*
今日もほどほどの賑わいを見せる花屋の前、何やら言い合う声で不動は目を覚ました。ほのぬるい気候の中、どうやらうとうとと微睡んでいたらしい。いけないと首を振りながら、その声の方向に顔を向けると、見覚えのある刀と、その主と思しき女がひとり、店先にたたずんでいる。
刀の方は、この間カーネーションの花束を買っていった山姥切国広だ。となると、その隣にいるのはその主か。国広の方は不動に気づくと、やや気まずげに硬直した後、かくんとこちらに会釈をした。それに付き合い会釈を返していると、女審神者は突然「きめた」という。
「やっぱこっちの花瓶にする」
「あんた、さっきまでこっちを見てたんじゃないか」
「いや、だってそれめっちゃ可愛くて……こう、私の部屋に置くのは申し訳ないというか」
「すまない店主。そっちをくれ」
「ちょ、主に逆らうのは如何なものかと思うが!」
ぎゃん、とかみつくが国広は全く聞く耳を持たない。そろりと伺うと、国広が指さしていたのは確かにかわいらしい、レースの飾りのついたガラスの花瓶だ。対して審神者が指していたのは、シンプルな白磁の花瓶。にらみつける審神者に無視を決め込む国広と、穏やかでない状況を前にしても、あの肝の太い店主は「あらあら」と笑うだけだ。
「審神者様、実はこちらの花瓶、レースの飾りが外せるようになっているんです」
「へ、へえ……」
「ね? これならインテリアに応じてかわいらしくも、シンプルにもできますし、置きやすいでしょう?」
「だ、そうだが」
「……分かった。負けました。こちらにさせていただきます」
両手を挙げた審神者が、小さく「ありがと」とつぶやいたのは、不動も、店主も聞かなかったことにした。「またごひいきに」と、明るい挨拶で送り出され、山姥切国広と彼女は笑顔で頷く。その去り際を、不動は何となく目で追った。
地味な色の小袖に、地味な色の袴を合わせた、はた目にも歴戦の審神者と分かる女審神者。薄い化粧をした横顔に、束ねられた黒髪には、颯爽と赤いリボンが靡いていた。
ベニベンケイ1
加州清光の机の上には、不思議な植物が置いてある。きゅっと身を寄せあったように咲く、鮮やかな小さな花々に分厚い葉っぱ。審神者が、父であった先代からこの本丸と同時に引き継いだ刀剣男士は、数少ない私物の中に大切そうにそれを抱えていた。
主の忠実な武器であり、同時に意志持ついきものでもある刀剣男士だ。先代から渡されたそれを愛でる様に、二心を持っているのではと、眉をひそめるものも勿論いた。──ほとんどは、加州清光の働きを見て言の刃を収めたが。
加州清光の忠誠心に疑いはなく、功績にも問題がない。主従関係としての問題はなく、となると気になるのはもっと俗っぽい好奇心で。
「それ、父さんからもらったんだよね」
審神者が尋ねると、部屋でその鉢植えに水をやっていた清光は「そーだよ」と答えた。「近くで見てもいい?」と続けて聞くと、少しいざって場所を空ける。綺麗な紅色の花は、よく手入れされているのだろう、つやつやとしていた。
意外だなあと少年審神者は目を細める。長く本丸にいて、あまり自分と過ごすことのなかった父だが、優しいが不器用な人だったと記憶している。加州清光が初期刀だったと聞いたときも驚いたが、その清光にこんな可愛らしい贈り物をしていたことにも驚いた。
「まあね。大御所様、爪紅も贈ってくれたことなかったし?」
「そーなの!?」
「そ。だから主が爪紅くれたときびっくりしちゃった。あの大御所様からこんな趣味良い子が産まれるの!? って」
「あはは。そりゃ母さんの血かも」
不器用な父を補うように、母はそういった細やかな気遣いが得意だった。よく、本丸からプレゼントの相談の電話がかかってきていたっけ、と審神者は懐かしく思い出す。あの子の顕現記念なんだ、あの子が誉を百貯めたんだ、って。審神者も知恵を貸した。おかげで、清光の趣味を知っていたのだけれど。
そういえば、この花は相談されなかったな。きゅうきゅうに植わっている鉢を見て、彼はこてんと首をかしげた。
「……鉢、そろそろキツくない? 本丸の花壇に移さなくていいの?」
「移さない方がいいよ」
伸びすぎた枝を小さな鋏で伐りながら清光が短く言う。そして、ぽかんとした審神者に気づいて苦笑し、「大御所様が望んでないし」と付け足した。
「その代わり、もうちょい大きな鉢はほしいかな。主、一緒に探してくれない?」
「俺でいいの?」
「主がいいの。言っただろ、俺、主の趣味は結構信頼してるんだよね」
これくらいかな、と清光は鋏を置いた。そして上着を手にとって、「今から行ける?」と問う。
「空いてるけど、どこ行くの?」
「城下町の」
そこで清光は穏やかに笑んだ。
「キニアン生花店」
[
]
2
城下町の花屋に、本丸への直接派遣の依頼が舞い込んだのは、母の日も終わり、町行く人々の装いも薄手になり始めた頃だった。
「護衛の任務をお願いしたいの」と、不動を珍しく刀剣男士らしく扱った店主の女は、いつもの作業着然としたエプロン姿でなく、白いワンピースを纏っている。よく見ると薄く化粧もしていた。「お客様に直接お呼ばれしたのだもの」とえへんと胸を張る姿に、不動の目は点になる。
「本丸で作業すんだよな?」
「そうよ?」
「その格好で仕事できるのかよ」
本丸への直接派遣の依頼は、大抵は庭木の剪定だったり、花の植え付けだったりだったはずだ。それがこんな、如何にも非力でございみたいな格好で行って大丈夫なのだろうか。
不動はコンマ二秒で次の返しを想像していた。あら、だからゆきちゃんがいるんじゃないとにこにこ微笑みながら手を差し出す店主。うん想像できるな。そうしたらばっくれるか。
決意新たに言葉を待つと、店主はきょとりとしてくすくす笑う。
「心配してくれたのね」
「ばっ……別に」
「大丈夫よ。この格好で剪定も出来ますけどね。今日はお花を選んでほしいってだけのお願いだから」
「……それだけ?」
「ええ、それだけ」
それくらいなら店に来てやればよさそうなものだが、彼女は店の中をぐるりと見渡して「それじゃあ皆さん、お願いしますね」と呑気に言う。
「わざわざ店主が出向くほどの上客なのか」
「いいえ? 勿論お得意様はいらっしゃるけれど、審神者様のお客様に優劣はつけないわ。みんな私が対応してます」
「社畜って言うんだろ、それ」
「仕方ないんだよ。店長しか対応できないから」
と、店員のひとりが眉を寄せる。それから、べ、と下まぶたをひっぱって、あかんべえのような顔をした。
「目がよくなくってね。俺たちが本丸に行くと、その本丸の不動行光とゆきくんの見分けがつかないんだよ」
「目の問題なのか、それ」
「目というか、まあ霊力の素質だよ」
へえ、と不動は小さく呟く。ぼんやりしているように見えていたけれど、店主を務めるだけあって、そういう面でも優秀なのか。
彼女はゆるりと微笑んで、つばの短い帽子を少し調整した。「さ、行きましょ」と不動に向かって手を差し出す。繋いでほしそうな顔をさくっと無視して、不動は無言で前を歩いた。それを、怒るでもなく、不服げにするでもなく、くすくす笑うのだからまったくこの女のことは分からない。
転移門を通り抜けると、その本丸の刀剣男士である加州清光が待っていた。彼の装いは極と呼ばれるそれで、不動は何となく居心地が悪くなる。
「あんたが花屋?」
「はい。お初にお目にかかります。大和国城下町、出店番号第十八番、キニアン生花店の店主でございます」
深く腰を折った店主を横に、不動も小さく頭を下げる。それに加州はじろりとこちらを見た。
「刀剣男士付き?」
「はい。こちらは護衛の不動行光です。本丸内で抜刀はさせませんのでご安心ください」
「まーそれは当然なんだけどさ。……主の部屋までついてくんの?」
「叶うならば」
加州は無言で、上から下までじっくりと不動を見た。なんだよ、と睨み返すと、店主が小さく「ゆきちゃん」と咎める。
「……歪なやつ。まあいいけど。俺も同席するし、変なことしたら叩き斬るからね」
「随分物騒なんだな」
「事情があんの」
剣呑な声で加州はそう刺して、「ついてきてよ」と店主を促す。頷き歩き出した彼女の隣、不動もぼんやり本丸を眺めながら続いた。
いたって普通の本丸だ。きゃらきゃらとした笑い声が響き渡り、空気は程よく澄んで、馬のいななきも聞こえる。だが、じきに言いようもない違和感が胸に落ちた。
「桜の葉があまり茂っていませんね。藤も花の付きがよろしくないよう」
「うん」
「成程。だからわざわざ私どもを召したのですね」
「……ここが主の執務室だよ」
す、と襖を開くと、そこに座していたのはひとりの、壮年の男だった。
そうして、不動の違和感の正体がようやく分かる。
「おや、いらっしゃっていたのですか。失礼をいたしました」
「いいえ。ご案内いただきましたので。初めまして。キニアン生花店の店主でございます」
「やあこれはどうもご丁寧に……僕は大和国第1265番本丸の審神者。仮名を宗哲と申します」
そう名乗った男は店主と軽く握手を交わし、して、と辺りを探るように視線をさ迷わせた。
「誰が案内を?」
不動は息を飲む。だが、加州は驚くこともなく、淡々と答えた。
「俺だよ、主」
「ああ、清光か。ありがとうな」
「いーって。それから主、花屋さん、護衛に刀剣男士連れてきてるんだけど」
「そうなのか。しまったな。座布団をもう一枚持ってこないと」
「それくらい後でやるから」
無言のままやりとりを見守る店主に気づいたのか、いやお恥ずかしい、と男審神者は頭を掻く。
「この通りです」
「視えないのですね」
「ただ今日は調子のよい方です。聞こえはしますから」
それは、日によっては声すら聞こえぬこともあると言うことで。絶句した不動の隣、店主は穏やかに微笑み「後継は」と尋ねる。
「有り難いことに、息子が継ぐと言ってくれております」
「何よりです」
「ささ、立ち話もなんですから座ってください。お茶は出さない方が良いのでしたか」
「ええ、恐縮ですが、そういう決まりですので」
そうして店主は鞄を引き寄せ、「早速で恐縮ですが、本題に入らせていただいても?」と尋ねる。そこで審神者はぐるりと辺りを見渡した。「ここだよ、主」と加州が声をかけると、ああ、と審神者は頷く。
「すまないが、加州は外してくれないか」
「……は?」
「他の刀剣男士たちにも、しばらく外すように頼みたい」
「待って、言ったよね。俺。ここに刀剣男士がいるって。何かあったらどうすんの」
「失礼だよ、清光」
だが、不動には加州の気持ちの方がよく分かった。腐っても守り刀だ。無防備な、それも刀剣男士の気配を感じ取れない審神者と、刀を携えた部外者が二人きりなんて生きた心地がしないだろう。
「俺、出てる」と腰を浮かすと、「そうね」と店主も促した。
「せっかく来てもらったけれど、ごめんなさい、ゆきちゃん」
「……別に」
これくらい当然のことだ。それに、剣呑だった加州の気配もやや和らぐ。どうにか丸く収まるかと思いきや、否と首を振ったのは審神者の方だ。
「可能ならば、そちらの刀剣男士には同席してもらいたいんだ」
「なっ」
「ッ、主!」
ならばどうして加州清光を側に控えさせない。さっきから言っていることが滅茶苦茶だ。どうにか説得してくれと無言のままに店主を見やると、彼女は何かを考え込んでいた。
そして、確かめるように審神者の方を見る。しばらく、人同士にしかわからない何かを推し量るように黙っていた彼女は、やがて背筋を伸ばして不動を招き寄せた。
「加州清光様」
「何」
「どうでしょう。不安でしたら、この不動行光、縛りますが」
縛る? と、審神者と加州だけでなく不動も首を傾げた。その瞬間、店主がぱんと拍手を打つ。
その手の間からするりと出てきた紐が、勢いよく不動の鞘と鍔に絡みついた。思わずおい! と声を荒げる。
「せめて許可とれ!」
「ごめんなさい。縛らせてもらえるかしら? いいわよね?」
「事後承諾すんな! くっそ抜けねぇ……!」
縛るなんてなまっちょろいもんじゃない。不動は尻のすわりが一気に悪くなった心地で何度か腰を浮かせては落ち着けてを繰り返す。それの気分の悪さを知っている加州は「うわ……」と声を漏らした。
刀は己そのものだ。それを意のままに操ることが出来ないように封じるなんて、例えるならものすごく痒いのを踏ん張っているとか、ものすごくトイレに行きたいのを堪えているとか、そんな感じで。
「……大丈夫なの、あんたの不動。息できてる?」
「めちゃくちゃ気分悪い」
「でもこれ以上弛めたら自力で破れちゃうでしょ? いかがかしら、加州清光様」
ことりと尋ねられ、加州はうううと唸る。駄目押しになったのは審神者の「頼む、清光」という真剣な声だった。
「何かあればすぐに呼ぶから」
「……分かった。分かったよ」
両手をあげて降参のポーズ。ようよう出ていった加州に、「ごめんなあ」と眉を寄せた審神者へ、不動は小さく唸った。
「なんで俺がこんな目に……」
「不動行光にも、申し訳ない。どうしても刀剣男士の意見が欲しかったんだ」
「ならあんたの刀を手元に置きゃよかったじゃないか」
「そうもいかないのよ、ゆきちゃん」
答えたのはやはり店主で、「そうですね?」と確かめた先、審神者は「お見通しでしたか」と苦笑する。
「先程もお話しした通り、じきに僕はこの本丸を去ります。息子が継いでくれるので、本丸自体は続きますが……節目として、こんな僕に着いてきてくれた刀剣男士たちに、何か贈り物がしたくって」
だが、自分にはとんとセンスがないのだと審神者は恥ずかしそうに項を掻いた。
「仕事一辺倒で……これまでにも、プレゼントをしたことはあったのですが全て家内や息子に選んでもらっていました。でも、今回は」
「貴方が選ばれることに意味がある」
「はい。でも、あまり派手に残るものだと、次代へのプレッシャーになるでしょう」
そこで花を、と考えたのだとぽつぽつと審神者は言った。
「花は、いつか枯れますから……」
その言葉と、いつかライラックを求めた一期一振の姿が、不動には重なって見えた。
「そうですか」
では、とカタログを取り出そうとする店主の隣、不動は膝の上で拳をきゅっと握りしめた。
花はいつか枯れる。いつか朽ちて、捨てられる。後腐れがなくて、それを潔いと思っているのだ、こいつらは。
「──身勝手だ」
ふつふつと沸き上がってきた気持ちを唇に乗せると、店主がこちらをじっと見た。審神者もきょとりと虚ろな目を向けてくる。
「ゆきちゃん?」
「……あんたたちは、ほんと、身勝手だ。いつか枯れるから花がいい? その枯れた花を捨てなきゃいけない刀の気持ちを考えたことがあるのかよ」
は、と審神者の目が丸くなった。店主が小さく息を飲む。俺は、と不動は、絞まったような心地のまま喉から声を振り絞る。
「いやだ」
大好きだった主から、形見として渡されたものを、自分で捨てるなんて。
二心を持たせたくないという気持ちも、わかる。後継のプレッシャーにならないようにという気持ちも、理解はできる。でも。
「綺麗事じゃ花は贈れないんだろ」
本当に綺麗事なら、感謝を言葉や行為にすれば良い。わざわざ物なんて贈らなくてもいいはずなのだ。
自己満足で、ただの気持ちの押し付けで、その見た目ほどには美しくあれないのが花なのだ。ならば、
「とことん綺麗事なんて捨てちゃえばいいだろ。あんた、本当はどうしたいんだよ」
「ゆきちゃん……」
「本当は、そんな綺麗な、感謝だけじゃないんだろ……!」
「ゆきちゃん!」
叱咤されて我に返った。ぽかんとした審神者の前、店主が深々と頭を下げる。
「どうか非礼を御許しください。後から言って聞かせますので」
「……」
なんで、とは口にしなかった。自分が言ったことが、間違っているとは思わなかった。だけど、建前が必要なことくらいわかる。
口をつぐんで俯く。次に来るのは叱責か、罵倒か──と身構えていると、意外にも聞こえてきたのは笑い声だった。
「……いや、失敬。やはり、刀剣男士を招いて正解だったな、と」
「……」
「そうですね。狡い。狡いんですよ。僕は」
そうして、己の目を覆い、ゆるく爪を立てて、深く、低く、吐ききるように息を吐く。
「本当は、出ていきたくなんてない……」
「ええ」
「目か、耳か、どちらかさえ動けば……一緒に畑仕事をして、馬に蹴られそうになって怒られて、晩飯を食って……今までそうしてきたみたいに、出来ないとわかっているけれど、でも、だったら」
「ええ」
「……俺が、ここにいたことを忘れてほしくない」
物の少ない執務室に、わずかに風が吹いた。
「新しい主を──たとえ我が子だったとしても、迎えたとして、これから何年と続くかわからない戦のなかで、いつ朽ちるとも知らない彼奴らの中に、俺がいてほしいんです」
忘れられたくない、と呟いた、彼の眦はうっすらと光っていて、
「俺のことなんか忘れて、新しい主と仲良くやってほしいけど、でもやっぱり」
「……」
「思い出になんか、なりたくなかったなあ……!」
振り絞るような声に、不動はかける言葉を失った。
これまでは、置いていかれるばかりで──置いていく者の葛藤と、激情を、知らないで。
沈黙が下りて、数秒。気持ちを整えるようにゆっくりと深呼吸をした審神者が「お恥ずかしいところをお見せしました」と微笑む。
「いえ。……いいえ。恥ずかしくなんてありませんよ」
「大の大人が、とも思うんですけれど」
「仕方ありませんわ。私たち、この子たちから見たら子どもみたいなものですし」
「違いない」
気恥ずかしそうに後頭部を掻いた審神者に、店主はふふ、と口許を覆って目を伏せる。
「枯れるばかりが花ではありませんね」
そうして見たのは不動の方で、なんだよ、と眉間に皺を寄せると再び微笑まれる。
「花は咲くものでした。……何度でも」
ふるり、と風に乗って、藤の花弁が迷いこむ。
ああ、と審神者の口から間抜けな声が漏れた。
「そうだなあ……そうでした」
わずかに開かれた窓越しに、審神者が庭を見やった。桜も、藤も、梅も、金木犀も椿も皆そうだった。
「店主さん、不動行光」
「なんでしょう」
「──花を、選んでいただけますか。俺らしい、花を」
それに、店主は柔らかく目を細め、頷いた。
「そのために、私どもはいるのです」
3
それで、と少年は加州の手の中にある鉢を見る。
「花壇には移さないんだ」
「そ。根付くのは、今の主には悪いだろうって大御所さまがさ」
「……気にしないのに」
「それも親心ってヤツじゃない?」
就任してから何度か訪れた城下町は相変わらず賑わっている。審神者には欠かせない資材を売る万屋は連日の大繁盛。甘味屋は初夏の新作を出したとかでいつもよりも人出があった。身なりに気を遣いたい刀剣男士や審神者は小間物屋へ。情報を仕入れに書店へ向かう者もいる。
そんな中で、ぽつんとひとつ。閑古鳥が鳴いているわけでもないが、さほど人が入っているわけでもなく。でも通りすぎ様に足を止めていく者が多い小さな店が、今回の目的地だ。
「彼奴、いるかな」
「あいつって?」
「キニアン生花店には護衛の刀剣男士がついててさ。不動行光なんだけど」
「へー……不動が花屋するんだ」
そこも意外でしょ? と加州は言う。そこも? 聞き返すと加州は頷いた。
「歪だったんだよね」
「歪?」
「外側と中側が合ってない。見たらわかると思うけど……個刃的にはもー直っててほしいかな。あれ、辛いと思うし」
ええ? と再度聞き返した矢先、濃紫の陰が店先に立った。
その姿を認めて、加州はひとつ、瞬きをして──やがて、ふ、と笑ったのだ。
日々草1
刀剣男士が見繕ってくれる花屋がある──城下町にそんな噂が流れ始めたのは、夏の気配が漂い始めた頃だった。
甚だ迷惑なことだと思う。その『花を見繕ってくれる刀剣男士』である不動行光はやはり仏頂面のまま花屋の店先に座り込んでいた。城下町に花屋なんて一軒しかない。その一軒に配属されている刀剣男士が不動であることなんて、この店を通りかかればだいたいわかることだ。そしてそれ故に物見遊山感覚の客が絶えなくなっている。
なんせ不動行光だ。甘酒かっ食らって不貞腐れている印象の強い短刀が選ぶ花とは如何に、とばかりに尋ねてくる刀、刀、時々審神者! 今のところ、ほとんどの客を店員たちが引き取っていくから大事にはなっていないが、実は、それほどお望みならばラフレシアでも勧めてやろうかと内心思っている。いや、流石に宗三にはそんなの勧められないけど。
「大人気ねえ、ゆきちゃん」
そんな心中をまったく察さずにニコニコと微笑んでいるのは店主の女で、不動は深々と溜め息をついた。
「人気なもんか。だいたいの奴が面白がってるだけだろ」
「よう不動、大人気じゃねえか」
「こいつみたいにな!」
言ってる側からこれである。不動はぎり、と声がした方を睨んだ。人の話を聞かずに呑気な感想をぶつけてきやがったそいつは、相変わらず飄々とした態度で肩を竦めている。対して店主はあらあらと微笑み、す、と居ずまいを正した。
「これは、『大和』様の薬研藤四郎様。本日はどのような御用でしょう?」
「ああ、そう畏まらんでくれや。ちょっと野暮用と、あと様子見に来ただけさ」
「どうせ酒飲みのダメ刀の、だろお?」
「それと、俺っちがやった球根がどうなったかをな」
に、と笑われて不動はふんと鼻を鳴らした。どうせダメ刀には花一つまともに育てられないとでも思ったのだろう。ご生憎様! と鉢を差し出してやる。
すっくと空を目指して延び始めた茎は、きちんと支柱で支えてやった。おかげでぐんぐんと元気よく葉を生やし、まもなく蕾をつけるだろうくらいまでの立派な成長っぷりである。どうだ、見たかと睨んでやると、薬研はおお、と素直に歓声を上げる。
「見事なもんじゃねえか。てっきりそのまま打ち捨てられるもんかと」
「……」
そうしてやればよかったと一瞬思った。だが、花に罪はないしなと思い直す。
こうなることすらこの短刀の計算通りかと思うと腹立たしいが、やりこめる術があるわけでもない。けっ、と舌を出して鉢植えを足元に置いた。
「それで、野暮用というのは?」
改まって店主が尋ねる。それに、薬研は少し黙って何かを考える素振りをしてから、にいっと唇を吊り上げた。猛烈な嫌な予感に不動は一歩後ずさる。が、それで逃がすような甘い刀でもない。
「巷で噂の刀剣男士さんに花でも選んでもらおうかと思ってな」
「まあ! ぜひ!」
「何でだよ! 絶対嫌だ!」
「どうして? 日頃お世話になってるんだもの。選んで差し上げたら?」
「勝手にお世話してるだけだろうが!」
それは親切の押し売りと言うのだ。ギャンギャン噛みつく不動に、薬研ははっはと余裕綽々で笑っている。それが腹が立つ。
第一、日頃の御礼っていうなら素人の不動よりも専門家が選んだ方がよほど御礼になるだろうに。こっちがどれだけ選ばないと主張しても、店主はにこにこ笑顔のまま不動を店の奥へと引きずっていく。薬研はしばらくぶりに入る店内を物珍しそうに眺めながら店主のあとに続いた。
「おい、俺は選ばないって」
「それで、薬研様はどのようなお花をお求めなの?」
「ああ。そうさな……でぇと用に見繕ってもらいたいんだが」
「まあまあ! 素敵!」
「俺の! 話を! 聞け!」
どいつもこいつも話を聞かない。それになんだって? デートだと? 何が悲しくて古馴染の刀が乳繰りあってる話を聞かなきゃならんのだ!
むすっとそっぽを向いている不動の前、店員がにこにことしながらいつもの茶を置く。今日はローズヒップとかいう、赤い木の実の茶だった。がぶ飲みしづらい奴だと眉間にシワを寄せて不動はカップを乱暴に取り上げる。
「薬研藤四郎様のコイバナですか! 俺も同席してもいいですか?」
「おい仕事しろ」
「構わないぜ」
「構わないのかよ」
わあ、と店員は嬉しそうに椅子に座る。そんなに珍しいことかよと眉間のシワを深くすると、「珍しくはないんですけどね」と店員はうっとりと手を合わせた。
「ネット掲示板でも薬研藤四郎様方のイケメン力はよく噂になってますから!」
「イケメンねえ……」
はん、と不動は鼻白む。
「逢引用の花選びを『野暮用』扱いする短刀がイケメンとは到底思えねえけど」
それに、薬研はぱちんと瞬いて目を丸めた。「ゆきちゃん」と店主が咎めたが、事実だろう。つんとそっぽを向いたまま茶を飲む不動だったが、意外なことに薬研が「その通りだな」と苦笑した。
「不動の言う通りだ。だから乱にも叱られてな」
「乱に?」
「毎年この時期にでぇとしてんだが、選ぶ花が通り一遍になっちまっててな。心が籠ってねえってさ」
「ええーっ、毎年お花をご用意されている時点で結構心を砕かれてると思いますけれどねえ」
それに店主の顔つきがほんの少し、変わった。つられて不動の目付きも変わる。この仕事を何度か経験して、やはり違和感には気づきやすくなった。
「で、お前の逢引相手ってのは刀剣男士か。それとも人間か」
「人間だよ」
「お前、まさか自分の審神者に懸想してんのか?」
「今の大将じゃねえよ」
ひらりと手を振ったその回答に、不動はひとつ確信を得る。同時に、何故、という疑念も腹の底に抱えた。
店主がすばやく端末を操作して、不動の方に仮想ディスプレイを送る。政府の城下町職員に開示されている、刀剣男士の情報だった。
城下町職員は専らサービス業と勘違いされがちだが、それとは別に過重労働本丸や進軍放棄本丸といった、所謂ブラック本丸の監視も本業としている。店主はその中でも最高ランクの情報請求権を保持しており、薬研藤四郎のデータは簡単に開示された。
前任審神者のステータスは『戦死』だ。
予想の範囲内だ。驚きはなかった。ただ、どうしようもなく徒労感だけが押し寄せていた。
「……なんでお前は、いつもいつも」
薬研がことりと首をかしげたが、続きは心中にとどめて口にはしなかった。ただ、目の前の男が理解できなかった。
薬研は貫けど人の腹を割かぬと称されるほどの忠義の刀であるくせ、どうしてそう、平然として別の人間の手を取れるのかが分からなかった。逢引だなんだと冗談めかして言えるほどの、想いを寄せた主君がいてもなお、この男は今、別の審神者を大将と仰ぐ。
理解が出来ない。溜め息をつくついで、「で、なんで俺なんだよ」と言ってやると、薬研は数度瞬いた。
「顔見知りがいるならそりゃ頼むだろ」
「よりによって俺に頼むかぁ? 嫌味かよ」
「特に深い意味はねえよ。不快にさせたんなら悪かったな。ただ」
「ただ?」
「お前なら俺の気持ち、ちったあ分かるんじゃないかと思ったんだ」
分かるもんかよ、と言ってやりたかった。
過去の主人の死を乗り越えて、とっくのとうに前を向いてやがるやつと、未だに主人の死をひとつとも向き合えていない自分だ。土俵が違いすぎる。
黙り込んだ不動に、薬研はふ、と苦笑した。気まずさを誤魔化すような笑い方だった。
「ま、考えといてくれや。どうしても思い付かないってんなら、店主さんに改めて頼みに来る」
言うだけ言って薬研は茶を飲み干し、とっとと立ち上がった。そのままさっさと去ろうとするのに、不動もがたんと立ち上がった。
「おい、待て」
「ん? どうした。まだ用か」
「……逢引用だって言うなら、相手の好きな色くらい知らせてから帰れ!」
それに薬研は虚をつかれたようにぽかあんとした。数秒、そのまま固まって、く、くく、と破顔してゆく。
「そうだなあ……そうだった。だから乱にどやされたんだな、俺ァ」
でもなあ、と薬研は遠い目をしていた。もうすっかりと遠退いた記憶を手繰るようにそうして、「ひとつ思い出した」とこちらを見る。
「あの人は紫が好きだったよ」
それじゃあ、と今度こそ薬研は去っていく。不動は大きく、肺の空気を全て押し出すのではないかというほど大きく溜め息をつきながら、ぺとんと椅子に座り込んだ。
とんでもなく厄介な依頼を受けてしまった、と。
*
薬研から提示された日付までは十二分に時間はあったが、花選びは難航していた。というのも、不動の気がまったく乗らなかった。
紫の花なんて候補が多すぎる。いつぞやのライラックも紫だし、カーネーションにだって紫はある。それに、一口に紫といったって濃紫から薄紫までいろいろあるだろうに、どれがいいとも言わなかった。
それに、妙にひっかかるのがあの一言だ。
──お前なら俺の気持ち、ちったあ分かるんじゃないかと思ったんだ。
時間を置けど、やはり分かりっこないと思うのだ。自分とあの刀とでは、何もかもが違いすぎるのだから。
やめだやめだ。考えるのはやめだ。不動は花のカタログを閉じて、水差しを片手に外に出た。店先にはいつも通り、たくさんの花が色とりどりに咲き誇り、道行く者たちの目を楽しませている。その端っこ、ようやく蕾を着けた鉢植えに不動はちょろちょろと水をやった。店員連中は「咲くのが楽しみだねえ」なんて言っていたが、楽しみな気分なんて欠片もない。ただ放っておけなくて育てたまでのことだ。植えられた球根に罪はない。朽ちさせるのも不憫だ。
はあ、と大きく溜め息をつきながらその場にしゃがみこむ。ちらちらと送られる視線が鬱陶しいが、カタログを前に悶々としているのに比べれば幾分かマシだった。
それでも、ぼうっとしていると浮かんでくるのは薬研の注文だった。何よりも気になるのが、「紫が好きだった」と告げた、あの男の遠く寂しそうな目だった。
そんな目をするのならば、どうして──
「今日は一段と塩垂れていらっしゃるのね」
「……嫌味を言いにきたんなら帰ってくれる?」
「ま、客に対してなんて言い種ですの」
失礼してしまいますわ、とぷりぷり怒る令嬢に、よりによって一番会いたくないやつにあってしまったと不動は頭を抱えた。この手の話題にはもっとも遠そうな相手だ。いや、逢引の花を探していると言えば目を輝かせて飛び付くのだろうが。
でも、逢引は逢引でも故人との逢引だぞ? 不動はふるふると首を振って、幾度目にもなる溜め息を大きく吐き出した。肺を削るような吐き方に、流石の少女審神者も眉を寄せる。
「……なんだか本当に元気がありませんのね。どうかなさったの?」
「別に。ただ、絶対に届かないのにわざわざ花贈る奴の気持ちについて考えてただけ」
それに、少女が分かりやすく固まった。
ぼんやりとしていた不動だったが、少女のただならぬ様子にはっと我に返る。しまった、流石に今の言い方は彼女にはキツかった。「違う、あんたじゃない」と否定すると、彼女も「ええ」と頷きにっこり笑う。
「分かっています。でも、どうなさったの? そんなことを悩むなんて」
ここで適当に濁しても、彼女は間違いなく追求してくるだろう。そういうところのしつこさは、この数ヵ月でいやと言うほど知らしめられた。
不動はまた溜め息をつく。少女はいつのまにか、着物が地面に着くのにも構わず不動の隣にちゃっかりしゃがんでいて完全に聞き出すまで梃子でも動きませんモードだ。
「……誰にも言うなよ」
「誓って。なんなら真名に誓いますわ」
「バカ、んなことに真名使うんじゃねえ」
甘酒の瓶を軽く撫でて、不動は小さく口を開く。
逢引の花を求める刀から、花を選んでほしいと頼まれたこと。
そして、その逢引の相手は既に亡くなっているということも。
「この仕事だと、そう珍しいことでもない……らしい。だから俺が選ばなくてもいいとは、店員たちに言われたけど」
「でも不動行光様がお選びになりたいのね?」
「頼まれたのが俺だってだけだよ」
そんな殊勝な理由でもない。ふいとそっぽを向くと、少女は少し考え込んだ。人間は人間なりに思うことがあるのだろうかとしばらく様子を見ていると、彼女は眉をハの字にして「ごめんなさいね」と小さく謝る。
「何が?」
「正直に言います。……素敵だなって」
「素敵ぃ?」
「だって、亡くなられた方のお参りなら、普通お墓参りとか言うはずなのに、その方はわざわざ逢引だって仰ったんでしょう?」
それに、不動ははっと目を見開いた。
「きっとその方の中では、まだ生きてらっしゃるのね。そう思うと……素敵なことだなと思うの」
──なんだ、それ。それじゃまるで、あの刀が、死んだ人間に未練があるみたいじゃないか。
まさか、と笑ってやりたかった。あいつはあの魔王の死もあっさりと乗り越えて来やがった刀だ。
でも、もしも、そうでなかったなら?
ただの墓参りではない『逢引』を、彼の刀が求めていたのならば?
口を閉ざした不動の隣、おもむろに少女は立ち上がって砂埃を払った。
「今日は私、出直しますわ。お花はまたご相談に乗ってくださる?」
「いや、だから俺は相談には乗らねえって」
「その方に何を選ばれたのか、また教えてくださいましね!」
聞いちゃいねえ。すたこらさっさと元気よく去っていった少女に不動はげんなりとした。さっきまでのあの大人びた雰囲気はなんだったのか。
まあいい。何はともあれ薬研のことだ。店内に戻って再度カタログを開く。一枚一枚、写真を見比べていると、ふ、と、もしも自分ならという思いが浮かんだ。
自分なら、何を贈るだろう。
すぐさま、ばたんとカタログを閉じた。自然、荒くなった呼吸をゆっくりと落ち着かせる。
考えるべきでないという思いが先に立った。どの面を下げてと笑う自分がいた。そんな恥知らずな真似、できるはずがなかった。
恩誼すら返せぬダメ刀。二度も間に合わなかった愚かな刀が、いったいどうして墓前に参じることができるというのか!
考えるべきでなかった、考えるべきでなかった! 自分の愚かさに頭を掻く。「ゆきちゃん?」呼ぶ声は聞こえず、ただ己を恥じていた。そのとき、
「ゆきちゃん!」
強く手を掴まれて、ばっと顔を上げた。手首をきつく握りしめる女店主は、一瞬だけひどく厳しい顔をしたが、すぐに力を緩めてにこりと微笑む。
「そんなに強く掻いたら、血が出ちゃうわ」
「……あ、ごめん……」
「悩むのもいいけれど、苦しくなるくらいなら相談してね?」
相談? おうむ返しにした不動に、店主は「そう、相談」と幼子にするように言い含めた。
「自己満足と自己完結は違うのよ」
どの花にしましょうか、といつものように店主はカタログを開く。いくつかの折れ筋を辿りながら、「ゆきちゃんはどれにしようとしたの?」と問う、その声の柔らかさに、不思議と不動は落ち着きを取り戻していた。
2
薬研藤四郎は、正直、あの花屋の不動行光が自分のために花を選ぶことはないだろうと思っていた。
例の不動の監視を命じた審神者ですら、それは時期尚早だったんじゃないのかと苦言を呈されたほどだ。彼の精神的ダメージを考えると、まだまだ復調には遠すぎる。せっかく治りかけているのに、ここでまたショックを与えたらもとも子もないのだぞ、とも。
それでも薬研が、あの不動に花を選ぶように頼んだのは、ひとつはやはり見ていられなかったからだろう。一度ならず主人を失った忠義に厚いあの短刀が、いつまでも腐っている姿を。
ただ、逸りすぎたのも事実だ。今回は無難な花を包まれて、店主か、店員が代わりに来るだろう。待ち合わせ場所に指定した政府施設の喫茶店で、雨垂れの音を聞きながらしばらく。薬研の予想に反して、その刀は現れた。
片手に、花の入った紙袋を提げて。
「……マジで来るとは」
「お前が来いって言ったんだろぉ」
来るんじゃなかった。顔をしかめた不動はポケットから納品書を取り出して薬研の前に差し出す。そこに書かれている金額を確認してさらさらと署名し、不動に返すと、彼は随分と慣れた様子でそれを確認してまた懐にしまった。
「それじゃ、用は済んだだろ。どーぞまたのご利用をお待ちしております」
つっけんどんに言い放ち、さっさと店に戻ろうとする、その手を思わず掴んでいた。
なんだよ、と睨む不動に、薬研はにやりと笑って言う。
「着いてきちゃくれねえか」
「……逢引なんじゃねえの?」
ああ、この刀はまだ優しい、自分のよく知る不動行光だ。
ほ、と内心胸を撫で下ろした。「細かいことはいいだろ。そう時間は取らねえよ」片手に傘を持って促せば、不動は心底面倒くさそうにだが、薬研の後ろに続いてくれた。
本当は怖かったのかも知れなかった。
「良い天気だな」梅雨に傘を打たせながら、政府管理の墓苑まで歩く途中、不動は当然「どこがだよ」と眉を寄せた。
「もう知ってんだろ。俺の前の主は死んでる」
「まあ……それが雨とどう関わるんだよ」
「本丸が襲撃を受けた。最後にゃ屋敷が焼け落ちた。雨が降ってりゃあな、と未だに思うんだ」
それに不動は口を閉ざした。薬研にとってはこの日の雨は慈雨だった。無言のままに歩いていると、不動がぽつりと「もしもなんて意味のないことだ」と溢した。
「その通りだよ」
頷き、墓苑の湿った石段に足をかけた。
戦死した人間の遺骨は、基本的には現世の遺族のもとへと返される。政府の墓苑に眠っている人間は、現世に寄る辺のない無縁仏ばかりだ。だが、薬研はすいすいとその墓石の群れを潜り、墓苑の頂上の大きな石碑を目指した。
「あの人が襲撃されたとき、俺は遠征に出ていた」
階段を上りながら話し出したのに、不動はじっと耳を傾けていた。
「この戦が始まってから結構早い時期の事件だった。まだ、審神者も刀も鉄砲玉みたいに扱われてた時期だ。……遠征から帰ろうとしたら本丸への転送パスが通じなかったんだよ」
馬鹿な話だと思う。襲撃を受けた本丸から、他所の本丸へと被害が拡大するのを恐れて、審神者と政府上層部は、本丸ごと遡行軍を封じ込めようとしたのだ。
「当然勝ち目もねえ。端から死ぬ気だったんだな。薄情なもんだよ。俺に届いたのは燃えた本丸の情景と、主の遺言が吹き込まれた映像記録一本っきり。本丸座標は今も行方不明で骨の回収すら出来てねえ」
墓苑の頂上にある大きな石碑は、そんな風に、遺体の回収すら出来ていない人間を追悼するための巨大な墓碑だった。
そのうちの名前ひとつを丁寧になぞって、薬研はふうと息を吐く。
「もう十年以上前の話だよ」
不動は何も言わない。己の境遇と重ね合わせているのかもしれなかった。薬研は小さく苦笑して、もらった紙袋の封を切る。
「……花を選んだときに」
「ん?」
「墓参りじゃなくて、逢引だって言うくらいだったら、まだお前が、その人が生きている風に感じてるんじゃないかって言われた」
傘越しに見えた不動の目は伏されていたが透明だった。まるで何かを見透かしたような目付きに、薬研は眉を潜める。
「生きてる風って……」
十年以上前にあの人は死んだ。毎年、こうしてこの日には墓参りをして、その事実を刻み付けた。泣いて死者が生き返るわけでもない。
首をかしげながら封を解いた。
そこから出てきた紫の色は、淡く薄いものだった。
──好きな色? 紫かなあ。
もう思い出せないものだと思っていた、朧気な声が耳元に蘇っていた。
──だって、やっくんの目の色だし。
笑うと目尻に皺が寄る人だった。いたずらが好きで、はしゃいでは良く彼の初期刀である蜂須賀と共に苦言を呈したものだった。
ああそうだ、そうだった。トピアリーのように整えられた花束を抱き締めて思った。
「毎年菊じゃあ、確かにあんた、退屈するよなあ……」
前を向くことと、忘れることは、確かに別のものであるはずなのに。これじゃ乱にどやされるわけだ。薬研はほろ苦く笑って墓碑の前に跪く。
「来たぜ、『主』──遅くなって悪かった」
御影石の台座に、ぽつりぽつりと雨粒が落ちて小さな水溜まりを作っていく。その様を、不動はじっと見つめていた。
*
花屋に戻る頃には辺りはすっかり暗く、店じまいも終わっているような時分だった。裏口の灯りは一つだけついていて、ノブを捻ると店主がちょうど玄関で靴を履いているところだった。
「おかえり、ゆきちゃん」
相変わらずのほほんとした呑気な笑顔だった。「お夕飯の支度できてるから、手を洗ってらっしゃい」と、さっさと靴を脱いで部屋へと上がる。不動は大人しくその後ろに続いた。味噌汁の芳しい匂いが廊下まで漂っていた。
花屋の二階は人が住めるように整ってはいるが、実際に住んでいるのは店主と不動だけだ。昼食はともかく、朝食と夕食は自然ふたりだった。食卓に向かい合ってつき、煮売屋から買った煮物を小皿に取り分ける。いただきますと手を合わせ、まだ温かい菜に箸をつけた。
「日々草、喜んでもらえた?」
「死人に喜ばれたかどうかなんてわかりっこないよ」
あんまりな言い草だと思いながらもそう返すと、店主は納豆をかき混ぜながら苦笑した。
「ゆきちゃんは」納豆をご飯にかけながら店主は何気なく聞く。
「お墓参り、考えたことはないの」
里芋が粘土を食んだように味がしなくなった。粘り気のあるそれを、惰性と義務感でただひたすら噛み砕く。
飲み込み、口を開いた。
「……俺にはそんな資格ない」
店主は静かに当然のこととして言った。
「資格を取り上げる人も、もうこの世にはいないのよ」
そうだ。その通りだ。不動は唇を噛んだ。資格を取り上げる人も、合わせられないと思っている顔も、もう存在しない。
どれだけ嘆いてもわめいても、起きてしまったことは変わらない。ならば事実を粛々と受け入れて、次へと向かうべきなのにその足は動かない。
結局自分はダメ刀だ。主に報いることができないばかりか、他の刀のように次へと歩みを進めることもできない。
本当に己を許していないのは、己自身だ。
「……それでも、俺にはその資格はないんだよ」
店主はもう何も言わなかった。ただ、「そう」と微笑んで、不動の小皿の上に煮物をもう少し加えた。
「疲れたでしょう。たくさん食べて、寝ちゃいなさいな。明日も朝からお仕事だしね」
「だから、俺は花屋やるつもりはねえって」
「わかってるわよ。護衛をよろしくね、ゆきちゃん」
何一つ分かっていない。眉を寄せつつ、よく煮込まれた鶏肉を口に放り込む。微かに鰹出汁の味がした。
ハハコグサ1
朝、目を覚ますと、そこは慣れ親しんだ私の部屋じゃない。お気に入りのラグを敷いた飴色のフローリングも、うさぎのぬいぐるみを置いた大きなベッドでもない。見慣れた藺草の匂いがする緑の畳と、床に敷かれた白い布団だった。
見慣れたと言っているのに、いっかな自分の物になった気はしないのは何故だろう。私は顔を覆って息を三秒止めた。強い感情は長続きしないから、怒りたくなったり、泣きたくなったらこうしなさいとは、お母様から教わったことだった。立ち上がり、布団を畳んで、寝間着を脱ぐ。衣装箪笥に入っている銘仙はどれも色とりどりで綺麗だったけれど、正直どれでもよかった。適当に目についたものを一人で着付けていく。昨日のうちに汲んでおいた水で顔を洗って、化粧水と乳液をつけてから、ニキビを隠すようにファンデーションをつけた。血色の悪さはチークとリップで。覇気のない瞳はマスカラとアイシャドウで。そうして出来上がった私の顔に、言い聞かせるように鏡に額をつけた。
「……行って参ります、お父様」
変なの。行って参りますも何も、ここが私の家なのに。
心中で圧し殺し、顔を上げてにこりと微笑んだ。どこからどう見ても明るく花のある、少女審神者がそこにいた。
*
「刀剣男士の好きな花はなんでしょう?」
明るく華やかな声に、店員たちは「ああまたか」と苦笑してそちらを見やった。見やられた側の不動は視線で助けろと訴えるが、彼らが進んで面倒を引き受けるわけがない。むしろ最近は、このご令嬢審神者の相手は不動がするものと決めたような扱いを受けている。
「もうすっかり専属ねえ、ゆきちゃん」
「誰が専属だ、誰が! あと、俺は花屋じゃねえ!」
「店長さん、こんにちは。ご機嫌よろしゅう」
「はい、こんにちは、審神者様。今日もご贔屓にありがとうございます」
少女審神者も店主も、傍目にはお淑やかそうに見えるせいで、おほほ、うふふと笑いあう様はまるで上流階級のサロンのようだ。だが、物腰柔らかな彼女らの押しの強さを知っている分、不動の目にはそれが嵐の予兆にしか映らない。今のうちに退散をとそそくさ距離をとろうとしたら、二本の腕が同時に不動の裾を掴んだ。
「まだお話は終わっていませんわ、不動様」
「そうよ、ゆきちゃん。お客様のお話の途中でこっそり離席なんてダメ」
「だからぁ! 俺は花屋じゃねえし! そいつは俺の客じゃねえの!」
「では友人として聞いてくださいます?」
面の皮が厚すぎる。不動のこめかみがひくひくと震えた。
こちとら、薬研との一件からまだ心の整理もろくについていないのだ。しばらく心静かに考えたいのに、それを許すかとばかりに彼女は不動を尋ねてくる。週に一度は必ずだ。それだけの頻度で花を贈られちゃ、受けとる側も大変だろうに、とも思うが。
「主人からの下賜だろ。何やったって喜ぶだろ」
「いいえ。現にまだ一度も受け取ってもらっていませんし……」
それに不動は眉を潜めた。それは初耳だ。「じゃしつこいんじゃねえの」とあしらえど、彼女は頑として首を横に振る。「ともかく、刀剣男士の喜ぶお花を教えてくださいな」ずい、と近寄りしがみつかんばかりの勢いに、とうとう不動の中で何かが切れた。
「……だーっ! 刀剣男士、刀剣男士ってもっと他にないのかよ! 情報少なすぎるんだよ! どの刀剣男士だよ!」
バチギレたのは堪忍袋の緒だった。がう、と噛みつくと彼女はぽかあんと目を丸くする。思えば最初からそうだ。刀剣男士の好きな花は何? 刀剣男士の好きなラッピングは何? と、このお嬢様は聞く主体がでかすぎる。どこのどいつに惚の字なのかは知らないが、歌仙兼定の好む花と同田貫正国が好きな花では百八十度どころか五百四十度は違うのだから、そろそろどこの誰に贈るのかくらいの情報は欲しいところだ。
裏手では店員たちが「うわとうとう聞いちゃったよゆきちゃん」だの「もうすこしデリカシーのある聞き出し方をしたほうが」だの言っているが知ったこっちゃない。むしろこの数ヶ月よく我慢したと称えてもらいたいくらいだった。
店主はしばらく苦笑していたが、とうとう腹を括ったようで「差し支えなければ、教えていただけませんか」と腰を低く審神者に尋ねる。
「その方が、我々としても提案しやすいもので……もしもゆきちゃんに聞かせたくないのでしたら、私が相談に乗りますわ」
「……え、ええ」
しかし彼女の歯切れは悪かった。しばらく迷うように目を泳がせ、口を軽くひき結んでからゆったりと微笑む。
「また、今度。改めて伺いますわ」
そうして少女は銘仙の袖をきっちり揃えてふわりと優雅に一礼をして、逃げるように花屋を去っていった。
なんだあいつ、と不動は呟く。「あーあ、泣かせた」と店員は茶化したが、あれで泣くようなたまだろうか。というか、不動としては至極当然の質問をしたまでだ。それなのにあの態度はなんだというのか。
もう知らん。不動は甘酒──の代わりにたっぷり注がれたカルピスに口をつけた。もう馴染んできている己の舌が憎い。
「どうせまたすぐ来るだろ。刀剣男士の好む花はなんですかーって」
それに、店員たちは「確かにね」なんて言って笑った。たった一人、店主だけは何か考え込む素振りをしていたが、店員に「店長?」と声をかけられるとすぐにまたぱっと笑顔にも度って「そうね」と頷いた。
だが、その予想を裏切って、彼女は一週間、二週間経てど、花屋に姿を見せなかった。
梅雨に濡れた店のシャッターを下ろし、「本格的に嫌われちゃったかなあ」と呟いたのは店員の男だった。あん? と目を向けると「あの審神者様だよ」と言われてすぐに、ああ、と目を細める。
「賑やかな子だったから、来なくなったら余計寂しくって」
「静かになってよかったじゃんか」
「こら、そう言うゆきくんだってちょっとは寂しいでしょ」
「誰が」
むしろ静かになってせいせいしている。そう言い切ってやると「素直じゃないなあ」と店員は苦笑する。素直も何もこれが本心だ。いなくなればどれだけ彼女に日々時間を取られていたのかということがよくわかる。まあ、時間があったとて、これとしてすることは無いのだが。
「今度はどこの店に刀剣男士様の好むものを探しに行っているんだろうね」
「さあ。知らねえし。花だって一度も受け取ってもらってねえんだろ」
「それも可哀想だよねえ。あれだけ熱心に選んでたのに」
不動はむ、と口を閉ざした。確かにそれもそうなのだ。これまで店先で色々な刀剣男士を見てきたが、程度に違いこそはあれ、主からの下賜品は皆喜んで受け取っている。それは抗いようもない、付喪神である刀剣男士の本性だ。
人から大切にされるのは嬉しい。だからこそ、不動も腹立たしいながら、店主からもらった水差しを使い続けているわけで。
「何か事情があるのかなあ」店員は首をかしげながら、商品の様子をひとつひとつ確かめていく。と、「私も思っていたのよねえ」と顔を出したのは店主だ。
「やっぱり店長も思います? 変だって」
「ええ。念のため様子を見に行こうかなって思ってるの」
「そこまでしなくたっていいだろ……」
「不審な本丸の監査も城下町職員の業務のひとつなのよ、ゆきちゃん」
それは赴任のときにも散々聞かされたことだが、大げさな、と不動は眉間にしわを寄せる。
「だいたい、監査つったって表向きは本丸訪問だろ。大義名分はあんのかよ」
「心配してくれてありがとう、ゆきちゃん。大丈夫よ。そういうの考えるの得意だから」
「それはよおく知ってっけど……」
弁でこの店主に勝てる人間など、城下町広しといえどもそういまい。店員がこそっと「洋菓子店の店主さんは同じくらい口強いよ」と耳打ってきたがそんなものは聞こえない。こんなのがもう何人もいるなんてぞっとする。
ともかく、と店主は手を叩き、にっこりと不動を覗き込んだ。
「よろしくね、ゆきちゃん」
「……は、俺!?」
「明日は私、本丸にお花を生けに行かなくちゃいけなくって」
「じゃあ監査は別日にすりゃいいだろ!」
「善は急げって言うじゃない」
「急ぎすぎだ!」
「それに」
うふ、と微笑み、店主は不動と店員に向けて端末をかざした。仮想ディスプレイにぼんやりと浮かび上がるのは、あの少女の本丸と思しき情報だ。
「引継ぎ本丸だったのか……」
店員の声に緊張がにじんだ。店主はこくりと頷く。ひとり、呑み込めていない不動に対して、店員は短く、「本丸とその刀剣男士様の所有権が、第三者に譲渡されて発足した本丸をそう呼んでるんだ」と補足した。
「親族間の譲渡でも、主従関係が上手く作れなくて破綻するケースが多いんだ」
それは、下げ渡された云々をこじらせた刀が身近にいたからよくわかるが。そういえば、花屋を訪れるとき、あの娘は一度も刀剣男士を連れていなかったなと不動は思い出す。てっきり、意中の相手を知られたくなくて意地で護衛を断っているのかと思ったが、本丸の運営が上手くいっていなかったのだとしたら納得がいく。
店員と、店主に交互に眼差しを注がれ、不動は「わかったよ」と低く唸った。
「でもね、ゆきちゃん」
なんだ、まだあるのかと不動は店主を見上げる。と、しっかりと両肩をつかまれて、思わずびくりと身をこわばらせた。
眼前には、いつにもまして真剣な顔の店主がいる。
「無理はしないでいいわ。手に負えないと思ったなら、躊躇いなく見捨てて店に戻ってきなさい」
「お、おう……」
「それじゃあ、言い訳は明日までに考えておくから、頼んだわね」
言うやいなや、いつもののほほんとした間抜け面に戻って、店主は店の奥へと引っ込んでいく。なんだったんだ、今のは。ぼやく不動の隣、店員だけは静かに溜息をついていた。
2
思っていたよりも立派な本丸だなというのが、不動がその本丸を見ての第一印象だった。門扉は立派で、外からうかがえる植木にもみずみずしさがある。以前訪れた、霊力がなかば枯渇していた審神者の本丸では、もっと緑は色褪せていた。
霊力面での問題は無いらしい。不動は小さく息を吸って、端末から本丸コードを検索し、呼鈴を一度推した。
「……はい」
掠れて聞こえるが、歌仙兼定の声だった。
「突然訪問の非礼をお詫びいたします。大和国城下町出店番号第十八番、キニアン生花店の不動行光です。此度は、当店の新商品の案内に、貴本丸の審神者様とお話をしにまいりました」
「花屋が? 不動行光が花を売っているのかい」
「ああ」
あれほど主が通い詰めていたにもかかわらず、不動の話を聞いていないのか。訝しみながらも頷けば、「どうやら身元に不審はないようだね」と歌仙が本丸の門を開く。
「ようこそ、花屋の不動行光。僕はこの本丸の歌仙兼定だ。ひとまず案内するとしよう」
「ありがとう」
姿を見せた歌仙にも特に不審な点はない。不動は短く会釈をして、本丸の門をくぐった。
いわゆるブラック本丸の話は、不動とて耳にタコができるくらいは聞いている。審神者が戦闘や刀剣男士の育成を放棄した本丸や、刀剣男士を過度に虐げる本丸は、それだけで付喪神たちの神気が濁り、本丸も自然と穢れていくものだが、この本丸の空気は澄んでいた。刀剣男士たちはのびのびと手合わせや畑仕事に勤しんでいて、一見普通の本丸に見える。
案じていたような本丸ではなかったのかもしれない。そう思いたかったが、決めつけるには引っかかる点も確かにあった。たとえばさっきから前を歩く歌仙兼定の態度だった。
どことなく緊張感を孕んでいる。あるいは怒りのようなものだろうか。その緊張感は、本丸の奥へと向かえば向かうほど強くなる。
審神者の執務室へと向かっているのだろう。それにしては、奥へ行くほどに刀剣男士の気配が薄まっていた。薄すぎると言ってもいい。
「ここだよ」
歌仙はある一室の前で足を止める。「失礼」と彼が声をかけると、中からは慌てたような応えがあった。
「な、んでしょう。歌仙兼定様」
「君に客だ」
「お客様……?」
数週間ぶりに聞いた声だが、覇気があまりに薄い気がする。不動が障子の陰から顔を出すと、少女の顔は驚きで満ちた。
「あ……不動行光様、どうして……」
「あの店主に頼まれて、セールスだよ」
「せーるす」
おうむ返しにする彼女に、歌仙はふいと視線をそらし、「それでは失礼するよ」と早々に踵を返す。その態度にはさすがの不動もむっとしたが、口には出さず「邪魔するぜ」と部屋の中へと入った。
綺麗に片付いた執務室だったが、やはり刀剣男士の姿は無い。文机の上に散乱した書類をてきぱきと集め、「今、お茶を淹れますわ」と支度をし始める彼女にも違和感が募った。いかにも良家のお嬢様然としているのに、お茶なんて淹れられるのだろうか。
「まあ、失礼な。私だってお茶くらい、淹れられるようになりました」
「ここに来てからか?」
そこで彼女は押し黙る。不動は非礼も承知て書類を一枚とりあげた。
「審神者ひとりでやる量じゃないだろ。近侍はどうした」
「……ええと、今日はお休みをあげています」
「それでも近侍の確認がないと進まない書類もあるはずだ」
「御詳しいんですね」
「俺も昔は本丸にいたから」
抽斗から覗いているのは刀剣男士の印だった。これを使って書類を偽造していたのかとすぐにわかった。それでも、遅かれ早かれ判明することだろうに。
「引継ぎ本丸だって話は聞いてる」
ダメ押しのように声をかけると、少女は背を小さくして、黙って茶を淹れていた。不動も黙って少女の様子を見守る。やがて、茶の量がばらばらの湯呑を両手に、少女は不動の正面に座った。
「どうか、通報しないでくださいますか。特に、刀剣男士は悪くないのです」
数秒、迷ってから頷いた。彼女はほっとして湯呑に口を付ける。不動も倣って一口飲んだが、やけに薄いと感じた。代わりに彼女が舌を出す。
「……湯呑が複数あるときは、濃さが均一になるように、交互に茶を注ぐんだぞ?」
「覚えておきます……淹れ直しますね」
「いや、俺がやる。貸して」
おそらく、ここに来てからひとり分しか茶を注いだことがないのだろうなと想像がついた。手早く茶を淹れてやると、彼女は一口それを啜って、ぽつりと「おいしい」と言う。
それで堰が切れたのか、両目からはぽろりと涙がこぼれた。
「あ、あら。ごめんなさい。……ごめんなさいね? こんな……ええと、すぐに止めますから」
「いいって、別に」
涙を無理矢理止めようとしているのだろう。息を止めては噎せる少女が見ていられなくて、不動はつい、ポケットからハンカチを出した。「準備がよいのですね」と、明後日の感想をこぼす彼女に、不動もまた「店主が持てってうるさいんだよ」と明後日の返事をした。
「ごめんなさい。……ごめんなさい。刀剣男士に、優しくされたこと、なかったから……」
不動は濡れて湿っていくハンカチをただ見つめ、やっぱりかと心中ひとりごちた。
彼女が泣き止んだのはそれからすぐだった。こほこほと何度か咳き込んで、大きく深呼吸してから、ひとつ決意をしたようでじっと不動をまっすぐに見る。
「引継ぎ本丸、というのは……少し正しいけれど、本当は違うのです」
「違うって、どう違うんだよ」
「正確には、乗っ取り本丸、です」
穏やかでない言葉だった。乗っ取り本丸は、引継ぎ本丸のうちでも、審神者が本丸の譲渡を承諾していないにも関わらず接収し、別の人間に権利が委譲した本丸だ。だが、ここが乗っ取り本丸なのだというのであれば、本来の所有者から本丸を取り上げたのは当然、
「私が、審神者様から本丸を奪いました」
彼女は淡々と、そう言い切った。
*
少女の親は、政府でも有力な議員だった。母親はとある会社の御曹司。その間に生まれ、何不自由なく暮らしていた少女に、審神者能力の適性があるとわかったのは、つい一年ほど前だという。
父親は、少女に良い戦績を求めた。彼女が戦果を立てれば立てるほど、父親の立場は良くなるのだから。父親は少女が、早急に功績を挙げられるように、まず地盤を固めた。
すなわち、手っ取り早く良い成果を上げることのできる、強い本丸を買収したのだ。
「私がそのことを知ったのは、本丸に着任してから、でした」
前任の審神者は審神者の資格をいわれのない罪で剥奪されて現世へと送り返された。その際に本丸の記憶は全て消去され、今はただの一般人として暮らしているという。
問題なのは残された彼女と刀剣男士たちだ。
「私は……とんでもない罪を犯しているのです。刀剣男士たちも、私にひどく敵愾心を向けました。でも、それも当然のこと、だから、私は甘んじて受け入れて……でも、武功は立てなくては、お父様に𠮟られてしまう、から」
「それで、今の状況か」
「……私が、刀剣男士の活動に干渉しないことを条件に、戦っていただいているんです。それでも、やっぱり、城下町におりるたびに、羨ましくって」
刀剣男士と仲良く歩いている審神者を見るたびに、私の何が悪かったのだろうと思ってしまうのだと彼女は泣いた。
「だから、少しでも仲良くなれたらって、お花を……お花なら、残らないから。だからね、広間に飾ってみたり、したの。でもね、そんなの一瞬だけだって、わかっちゃったの。咲いているのも一瞬だけ。ご機嫌をとれるのも一瞬だけだわ。用がなくなったら捨てて、おしまい」
ばかみたい、と彼女は笑った。それを、不動はじっと聞いていた。
不動が部屋を出たのは、日も傾いた夕方ごろだった。「また、お店にうかがいます」と微笑んで見せた少女は、元気こそは無かったが、泣いた分少しはすっきりしたような顔だった。
玄関の外へ出ると、外はぽつぽつと雨が降り始めていた。げ、と不動は顔をゆがめる。「もしかして、傘をお持ちでないの?」と首をかしげる審神者に、不動はこくりと頷いた。ここまで長居するとは想定外だったのだ。
「だったら、傘を──」
「僕が送ろう」
審神者の言を遮って言い切ったのは歌仙兼定だった。ぱ、とそちらを振り向くと、庭に歌仙が傘を片手に立っている。
困惑気味の審神者だったが、歌仙に見つめられて、小さく頭を下げた。
「それでは、お願いします」
「……不動行光、こちらに」
不動は靴を履き、歌仙が差し出した傘を受け取った。
門までは無言だった。蛇の目傘の表面が、バツバツと雨を受ける音だけを聞く。歌仙が口を開いたのは、門前だった。
「彼女は、何と」
「自分で聞けよ、それくらい」
不動はばさりと切り捨てる。く、と唇を引き結んだ打刀を前に、不動は臆することなく鼻を鳴らした。
「三十六首ィ並べた名刀のくせ、主が変わったら斬れませんってか。物のくせに」
「……」
「そんなにあいつが嫌なら、勝手に折れるなり錆びるなり朽ちるなりしろよ」
「……返す言葉もないね」
意外と素直に肯定した歌仙に、おや、と不動は眉を持ち上げる。てっきり噛みつくものと思っていたのに、嫌味でも皮肉でもなく、本当にしおらしく歌仙は同意した。
彼は自慢の衣装に泥が跳ねるのもいとわず、庭に立ちすくんで空を見上げる。
「わからないんだ」
「わからない?」
「彼女に非がないことは知っている。……最初は怒りもしたけれどね。だけど、方々に前の主の所在を尋ねて回っているのを見て、わかった。ああ、この子も、ただの被害者だと」
「だったら猶更、とっとと話せばいいじゃないか」
「その時には、僕らは彼女を傷つけすぎていた」
不動もまた、空を仰いだ。成程、本丸を訪れたときに感じた鋭い視線は、確かに付喪神のものだった。主が自分以外の刀に目をかけていることに対しての、不安と不審のそれだ。
「俺の口から、あいつの話を聞いて。それで、どうする気だよ」
「……確かに、どうもできないね」
歌仙は力なく笑う。忘れてくれと振られたその袖を、不動はしばらく迷ってからつかんだ。きょとりと目を丸める歌仙に、不動は「来い」と短く言う。
正面切って話すことができない、どうしようもなくこじれた客の扱いには、誠に不本意ながら慣れてしまっていた。
3
少女はいつも通り目を覚ました。そこはやはり慣れ親しんだ部屋ではなかった。お気に入りのラグを敷いた飴色のフローリングも、うさぎのぬいぐるみを置いた大きなベッドでもない。見慣れた藺草の匂いがする緑の畳と、床に敷かれた白い布団だった。
もぞもぞと起き上がり、少女は顔を覆って息を三秒止めた。強い感情は長続きしないから、怒りたくなったり、泣きたくなったらこうしなさいとは、彼女の母親から教わったことだった。それでも上手くいかなくて、少しだけ布団には涙がにじんだ。
立ち上がり、布団を畳んで、寝間着を脱ぐ。衣装箪笥に入っている銘仙は、やはり色とりどりで綺麗だったが、正直どれでもよかった。適当に目についたものを一人で着付けていく。昨日のうちに汲んでおいた水で顔を洗って、化粧水と乳液をつけた。昨日泣いた跡がひりひりと痛んだが、唇を噛んで耐え、ファンデーションをつけた。血色の悪さはチークとリップで。覇気のない瞳はマスカラとアイシャドウで。そうして出来上がった、いつも通りの顔に、言い聞かせるように鏡に額をつけた。
「……行って参ります、お父様」
顔を上げてにこりと微笑む。そうして出来上がった審神者の自分のまま、彼女は寝室の戸をからりと開けて、息を飲んだ。
廊下には花があふれていた。ハハコグサ、ライラック、カーネーション。これまで、彼女が選んできた花々が、丁寧に作られたブーケで山と積まれている。いったい誰が、と彼女はその場にへたり込んだ。飾った覚えのない花も置かれていた。アルストロメリア、芍薬、シンビジウム、向日葵──花屋をそのまま移してきたかのような有様だ。
でも、どうして。花の山をひとつひとつ、丁寧に部屋に運び込みながら、ふと彼女は、ハハコグサのドライブ―ケに手紙が挟まっていることに気が付いた。
紙縒りで結わえられたそれを、彼女は慎重に解く。開こうとして、一瞬息をつめた。恨み言が書かれているやもしれないと、そう思ったからだった。
だが、中から覗いたのは、柔らかな筆跡だった。
──広間の花を選んでくれてありがとう。選ぶというのは存外に難しかったよ。気づけばこの量になってしまった。
──近侍の手が必要であるならば、遠慮なく声をかけてほしい。
ぽつ、と、一筆箋に涙がこぼれて染みを作り、慌てて少女はそれを遠くへと押しやった。濡れてぐしゃぐしゃにしてしまうのはあまりにももったいなかった。
ドライブーケを抱きしめる。ハハコグサの花言葉は「無償の愛」だと、あの店員は教えてくれた。届いた気がしないとあの時は言ったが、届いていたのだ、確実に。
息を止めても涙はあふれた。とうとう情けなくしゃくりあげた。彼女はこの本丸に来て初めて、大きな声を上げてわんわんと泣いた。
それを咎める者は、どこにもいなかった。
*
あの一件から、店主と店員の機嫌はすこぶるに良かった。というのも、大口の客が入ったおかげで花が飛ぶように売れたからである。
あの夜、花屋を訪れた歌仙兼定は、あろうことか「人間の好む花はなんだろうか」と店主に聞いた。そういうところは似んでいいとすべての店員が思っただろう。「審神者様が好まれている花はなんでしょうか」と店主がそれとなく尋ねても、会話もほとんどなかったのだ。そんなの知るよしもない。
最終的に歌仙兼定が取った暴挙は、審神者が選んだ花を全て選ぶことだった。在庫があった分はそれで対応したが、その場に無いものまであったからそれはもう大変だった。最終的には店主が車を飛ばして方々まで買い付けに行って、朝に間に合うようにデリバリーをした。ハハコグサだけは時季外れもいいところで、諦められないかと店員は言ったが、歌仙兼定は頑として受け付けなかった。むしろこれが無ければだめだと言い張ったくらいだ。ドライフラワーの花材があって本当に良かった。
それほど大変なことがあったにも関わらず、店主と店員は花が売れてよかった、歌仙樣にお花をお届けできて良かったとほくほく顔なのだからつくづくお人よし集団である。花屋はそんなテンションじゃないとやっていけない決まりでもあるのだろうか。
自分はそうはならねえぞ、とひそかに誓う。と、店員の一人が「ゆきくんも、歌仙様をうちに連れてくるあたり、うちの一員になったって気がするよねえ」と恐ろしいことを言ったので「あれはたまたまだ」と即座に言い返しておいた。
「ごめんくださいな」
「うげ」
「うげ、とはなんですの、うげとは!」
やかましいのがきた、と不動は身を縮める。華やかな銘仙に身を包んだ少女審神者は、大股でのしのしと不動の近くまで寄って行って、「御礼かたがた、報告をしに来ましたのに」とわざとらしく膨れて見せた。
「これは、審神者様。いらっしゃいませ。……ええと、報告とは?」
「ええと、色々ありまして……父を通報いたしました」
「ぶっ」
不動は思わず飲んでいたカルピスを吹き出す。「ま、ばっちい」と彼女は眉をひそめたが、自分が何を言っているのかわかっているのだろうか。
「良かったのかよ」低く尋ねても、彼女はふわ、と微笑むだけ。
「良かったのです。これで」
「あっそ……で、今日は」
「はい。刀剣男士の好きな花を教えていただきたくって!」
結局か、と不動はがっくり肩を落とす。元気でないのも気持ち悪かったが、元気があったらあったで騒がしい。足して二で割ってくれないだろうかと思っていると、今日は思わぬ援護射撃があった。
「主。それでは不動殿が困るだろう」
「歌仙様。でも、これまでそうやって選んできてもらったのですよ?」
「いや、あれで対応できたのも奇跡的だから……」
それにそっちだって人の事は言えまいに。二重にやかましくなった気がしてげんなりする不動の前、少女審神者は悩んだようにううむと腕を組む。
「でしたら、たとえば不動様はどのようなお花が好きなのか伺っても?」
「ええ……好きな花なんてねえよ……」
「そこをどうにか」
そこをどうにかで思いつくものでもあるか。そして店員たちも店主もその期待のこもった目をやめろ。
ええい。不動はぼりぼりと首筋を掻いた。
「……赤くない花。菊以外」
「でしたら、赤い菊をお贈りしますね」
「話聞いてたか?」
「だって、わざわざ嫌いな花を贈る人間なんて、私くらいしかいないでしょう?」
にっこりと花のように笑顔を輝かせ、彼女は店主の元へと歩いていく。ぽかあんとする不動の隣、歌仙は小さく咳払いし、店員もくすりと吹き出した。
「なかなかやるねえ、ゆきくん」
甘酒の瓶に、赤い菊一輪が揺れるようになるのは、それから間もなくのことだった。
[
]
きみはひまわり
最近、主さんの様子がおかしい。乱藤四郎は眉間にうんと皺を寄せつつ、物陰に隠れていた。人通りの多い城下町ではあるが、そこは極短刀の隠蔽値。ほとんどの人の子は気づかずに通り過ぎていく。中には乱に気づく刀剣男士もいるが、そこはそれ、自分の主に害をなさないと判断すると放っておいてくれるのでありがたい。大きなサングラスに、長い髪を防止の中に隠して、乱なりの隠密スタイルで尾行しているのは、自身が仕える審神者その人である。
──本当は、こんなことしちゃいけないってわかってるんだけど、でも。
頭をよぎるのは、今朝。審神者の出発を確認して後を追おうとしたときに、他でもない長兄から言われたことだ。
主にも私生活というものがあるだろう。いつまでも子どもだと思っていてはいけないよ。
それはその通りだ。ちょっと前までこんなに小さくて、乱のことをみーちゃんみーちゃんと呼び慕い、戦場までついてこようとしていた『若様』だったとしても、今の彼は立派な審神者である。身長もすくすく伸びて今は鬼丸と並ぶほどには高い。体格はいささかひょろっとしているところが否めないけれど。乱が手塩にかけて育てた立派な男の子なのだ。それにしては性格が若干ひん曲がっているけれど。
そう。性格が曲がっているのが若干の問題点というか。そもそも主さん、積極的に外に出たがらないのに、最近は毎週城下町に出かけてるのはやっぱりなんだかヘンだと思う。薬研なんかは「コレでも出来たんだろ」って小指立ててたけど。その仕草めっちゃオジサンだからやめてほしいなとボクは思うのだけど! そんなの聞いてないし! 近侍のボクに一言くらいあったっていいと思わない!?
と、いけないいけない。ぶんぶんと乱は首を振った。興奮しすぎて尾行対象をロストするところだった。こんな初歩的なミスをしでかしたなんて知られたら、それこそ主さんに鼻で笑われる。
あーあ、昔は可愛かったのにな。乱はそっと息を潜めながら、前をふらふら歩く審神者を見つめた。こんなに熱心に見張っているのに、審神者は気づくそぶりすら見せない。城下町だからって油断しすぎ。そもそも護衛の刀剣男士ひとりもつれずに審神者がぶらぶら出歩いて、何かあったらどうするつもりなのさ。
まったく。ぷうっと頬を膨らませて、乱はさささと移動した。だから見張っているだけだ。ボクに他意なんて微塵もないとも。本当だよ。
*
ここ最近、とある事情で毎週花屋に通ってきている男審神者がいる。最初は、なんちゅう面倒くさい注文をつけやがるヤツだと思っていた(し、隠さずそれを表に出したつもりだったのだが、お人好し極まるここの店員たちは「素晴らしい発想ですね! ぜひお手伝いさせてください」と二つ返事で引き受けた)が、今日は余計に面倒なコブをつけてきた。花屋の店先で不動は盛大なため息をつく。何故不動がため息をついているのか全く分かっていなさそうな男は、仏頂面をことりと倒して、「何かあったか」とぼそぼそ尋ねた。
いや、何もクソも、あそこでこそこそこっち見張ってるの、お前のところの乱藤四郎だろ──と、言っても良かったが、アホくさ、と口をつぐんだ。そこまで色々首を突っ込んでやる義理もない。
と、そこで奥で作業をしていた店主がひょっこりと顔を出した。「あら、こんにちは。全手葉椎の審神者様。今週もお疲れ様です」にこにこと微笑みながら、水で濡れた両手をエプロンで拭き拭きやってくる。「どうも、お世話になります」相変わらず表情を変えないまま、こてんと会釈をした審神者に、店主は「ええ、ええ」と両手を合わせた。
「それでは、今日もご案内しますね」
「はい、よろしくお願いします」
「ゆきちゃんはお店番、よろしくね」
「だから、俺は店員じゃねえって……」
言っても聞く耳など持つわけがない。店主はにこにこ顔のまま、審神者を連れて店の奥へと引っ込んでいく。
しんと静まりかえった店の中、不動はため息をついて頭を掻く。そして、「待った」と手を差し出した。
「──ッ、ボクの隠蔽見抜くなんて、キミ、結構やる?」
「生憎と、経験だけは一丁前でなァ。悪いけど、そこは関係者以外立ち入り禁止だ」
これでも護衛だ。いかに審神者の関係者だろうが、店の最奥部に招かれざる刀剣男士を侵入させるなんて、許してはいけない。
乱藤四郎の手首をギリギリと掴む。突然現れた刀剣男士に、店内は一瞬ざわついた。だが、「ごめんなさぁい」と苦笑して両手を合わせる乱に、なんだ乱藤四郎かと場はほどけていく。
「悪いことする気はなかったんだよ? ホントっ。だから、放して?」
「妙な真似すんなよ。速さは互角。ならこの店の構造知ってる俺の方が有利だってことは分かるよな」
「わかってるよぅ。痛い、痛いってば。主さんの様子、ちょーっと見に来ただけなの! 騒ぎになるとまずいからさ、放してっ」
やれやれ。不動はそろりと手を放した。騒ぎになるとまずいというのは本当なのか、おとなしく立ったまま店の中をきょろきょろと観察している。しばらく十分に観察して気が済んだのか、あるいは情報をもっと集めるつもりなのか。じっと乱を警戒する不動に、「ね、不動行光さん」と後ろ手を組んで声をかけた。
「……何」
「主さん、毎週ここに来てるんだよね」
「そうだけど」
「何しに来てるの?」
「さあな。花でも買いに来てんじゃねえの。うち花屋だし」
ぴしゃ、と不動ははねのける。ここで働くことしばらく、この店に関わる審神者や刀剣男士には訳ありが多いことがなんとなくわかってきた。花を求める行為そのものを隠したい事情もある。守秘義務があるのだ。言う気は無いと首を振ると、「ふうん」と乱は目を細める。
「あんたんとこはずいぶん過保護なんだな」
「別に。大事な主さんのことだもん。気にするのは当たり前でしょ?」
「潜入まがいのことをしてまでか? 信頼されてねえんだな」
「そういう挑発、ボク、好きじゃないなあ。信頼してないんじゃないよ、心配なだけ」
べ、と舌を出す乱だが、過ぎた心配を寄せるというのは信頼を置いていないのとどう違うのだろうか。不動はふうとため息をつく。
「それでついてってみたら、知らない女とふたりで花屋で密会か。心配がますます高まっちまったな」
「別に。恋人が出来たっていうならそれはそれでいいんだけどさ。そうならちゃんと教えてほしかったな、ってだけ」
「……」
なんだか激しく面倒くさい行き違いが起きている気がするが、守秘義務、守秘義務と不動は己に言い聞かせてだんまりを決め込んだ。乱はしばらく店の奥をじっと見つめていたが、やがて「お花屋さんかあ」と明るく声を上げる。
「主さん、大丈夫かな。お花とか全然疎いんだもん」
「……」
「いつか、主さんに恋人が出来たら、プレゼントの選び方レクチャーしてあげるんだって思ってたんだけど、お花屋さん相手だとなかなかハードル高いよね。お花で勝負はしづらいし……アクセサリーとかなら教えられることあるかな。どう思う?」
「どうも……いや……知らねえけど……」
ようし、と乱は拳を振り上げる。「がんばるぞ」と、自分に言い聞かせるように宣言する背中を、何とも言えない気持ちで不動は見つめていた。
正直めちゃくちゃ真相を言ってやりたかった。だが、守秘義務、守秘義務なのである。そんな不動の頑張りを見つめていたのは、足下の蕾だけだった。
*
乱藤四郎にとって、審神者は可愛い弟のようなものだった。
まだ審神者が赤子のころから、その成長をずっと見守ってきた。審神者の母である先代から、直々に世話係に任命されたときは、その責任の重さと仕事の大きさに胸を震わせたものだった。
審神者は乱によく懐いた。まだ「乱」と上手く発音出来ないときから、「みーちゃん、みーちゃん」とよく乱を呼んで。そんなに甘えたでどうするんだと藤四郎の兄弟達が笑っても、乱のスカートの裾を握って放さなかったこともあった。
「しょうらいは、おれ、みーちゃんをおよめさんにする」
そんなことを言い放って、一期一振を混乱に陥れた日があったことを、乱は今も大事に心に残している。審神者と刀剣男士の結婚には大きな障害がある。生半なことで叶うことではないのだが、そんな難しいことを言ってもわからないだろうと、平野は「乱兄さんは男ですから、お嫁さんは無理ではないかと」と宥めた。そうすると幼い審神者は、ひらめいたという顔をして、大真面目にこう言った。
「それじゃあ、みーちゃんがおれをおよめさんにして」
やくそく、と立てられた小指を、あのとき乱は結べなかった。
困った顔をした先代が「結婚とはどういうことかわかっていますか」と尋ねると、審神者は得意そうに「ずっとそばにいるってこと」と答えた。それが乱にはたまらなく嬉しかった。
たとえそれが『結婚』や、『恋愛』という形でなくても。一時の気まぐれだったとしても、「ずっとそばにいる」相手として、審神者が自分を選んでくれたこと。
反抗期を迎えて、今までのように乱と接することがなくなっても。思春期を迎えて刀剣男士そのものと疎遠になっても。乱はずっとその思い出を胸の中にしまっていた。
そして、審神者が先代からその役目を継いだ、そのとき。近侍として乱藤四郎の名が読み上げられたとき。
初恋が叶ったかのような胸の高鳴りを感じたのだ。
次の週、また出かけていく審神者を見送る乱に、「今日は追いかけなくていいのか」と薬研は意地悪く尋ねた。それに乱はふるりと首を振る。「邪魔しちゃ悪いもん」と答えると、ほおう、と眼鏡越しの目が細くなった。
「つうことは、大将、当たりか。やあようやく春が来たか」
「いつか来るかもなあって思ってたけど、意外と早かったね」
「そうか? もう二十歳だぜ。適齢期だろ」
言われて初めて、乱は審神者の年齢を思った。小さな童だと馬鹿にしていたわけではないが、そういえばもうそんな年だなと。
「昔は『みーちゃんのお嫁さんになる』って言ってたのにな。寂しいか? みーちゃん」
「そりゃあ寂しいよ。寂しいけど……なんだろ、言ってくれなかったショックの方が大きいかな。これでも近侍だよ?」
「近侍だからって何でも言うわけじゃないだろ」
「そうだけどお……」
自分の知らない審神者がいたことが純粋にショックだ。そうぼそりとこぼすと、薬研は苦笑して乱の頭をぽんと叩いた。
「何」
「いや、あいも変わらず大将一筋だなと思ってな」
「……どういう意味?」
「覚えてるか? お前、大将が小さい頃、危ないからって髪切ろうとしたんだよ」
ああ、と乱は小さく頷いた。あれはまだ審神者がよちよち歩きをし始めたころ。長い髪が足や手の指に絡まってうっ血する事故が増えていると聞いたときの話だ。
それだけじゃないと薬研は指を折る。審神者が歩くようになったら、スカートだと面倒を見にくいからと衣装ごと改めようとした。どれもこれも先代が思いとどまらせたが、あれは薬研にとっては少しは衝撃だったんだと今更語る。
「だってお前、『兄弟と違う乱刃』だからこその格好だろう」
刀剣男士の姿は名前や物語そのものを表すいわばアイデンティティだ。それを改めるのに少しの躊躇いも無かった乱に、先代ともども驚いたと薬研は笑う。
「どんだけ一途なんだって」
「……」
「だからこそ、子離れは大変だろうけどな。気長にやれや」
「……子離れなんかじゃないよう」
子どもだったら手放すことに躊躇いはすれど覚悟はできただろう。だが、乱は刀剣男士で、近侍で、審神者の懐刀なのだ。
ずっと側にいられると思っていた。なんでも知っていると思っていた。その傲慢さに自分のことながらショックを受けた。その場にしおしおとうずくまる乱に、薬研が呵々と笑う。
今日から少しずつ審神者離れを始めよう。うん、とひとり決意した、その時。
「お……?」
薬研が小さく声を上げた。何だ、と乱も立ち上がる。そしてぱちりと瞬いた。
転移門の近く、審神者が立っている。その両手には大きな花束を抱えて。
「……噂の恋人にもらったのか? いや──」
それにしちゃ、と薬研が呟いた。審神者が一歩、二歩と近づいてくる。乱と薬研の目の前に来て、審神者がじっとふたりを見下ろす。
「今日は」
早かったね、と言いかけた、その時、目の前いっぱいにひまわりの花が広がった。
「…………いつも、ありがと」
ぼそぼそと声が聞こえて、乱の目はまあるく見開かれる。
「……え?」
「……ほら、今日、父の日だから」
「……え? ボク? 父?」
「みたいなものだっただろ、俺には」
ぶっ、と薬研が吹き出したのと、乱がその場に崩れ落ちたのはほぼ同時だった。
「大将、説明」
「せ、説明ってほどじゃ、ねえけど。……二十歳になったら、いつか乱にはちゃんと御礼しときたくて」
「それで、父の日?」
「就任記念日とか、いろいろ考えたけど……審神者になる前から世話になってっし……」
ん、と審神者が差し出し続けるブーケをなんとか受け取って抱きしめる。「ひまわり」呟くと、「ひまわり」と審神者も復唱した。
「いつも、俺のこと見てくれてるから、ひまわり」
「……主さん、太陽って感じじゃ無いけどね」
「うっせ」
「彼女さんに選んでもらったの?」
「は? 彼女?」
何を言っているんだと審神者が眉間に皺を寄せる。どころか「彼女いない歴イコール年齢のこと知ってるくせになんでそんな寂しいことを……」と口ごもる始末だ。
話が違うんじゃないか。はつはつと瞬いて顔を見合わせる薬研と乱だったが、そういえばあの不動行光、別にあの花屋が彼女だとは言っていないような。
「あ、あの花屋の店主さんは……」
「花、選んでもらっただけだけど」
「でも毎週花屋に行ってた!」
「知ってたのかよ! ……あー、その、花なんだけど」
ぴ、と指さすひまわりは、よく見ると花が一部欠けていたり、葉が虫に食われたりしている。売り物の花にしては不格好だが、もしかしてと審神者を見ると、こくりと彼は頷いた。
「育ててもらった御礼だろ。……俺も、育てて返したくて」
だからこっそり、花屋に場所を作ってもらって、蕾の苗を育てていたのだと審神者はぼそぼそ告げた。
乱は花束を、折れないようにぎゅっと抱きしめる。「ありがとう。嬉しいよ」心底からそう言うと、審神者は鼻の下をこすって「……ん」とだけ答えた。
「でも、次は一緒に育てたいな。約束してくれる?」
それが審神者と近侍ということだと思うから。
笑ってそう言うと、審神者は後頭部を軽く掻いて「わかったよ、約束な」といつぞやのように小指を差し出した。
それに、乱はためらいなく己の小指を絡めた。
*
ひまわりの苗、くださいな。明るい声が聞こえて表の方を見ると、乱と、乱に手を引かれるようにして男審神者が立っていた。「あら、ようこそ」と店主が審神者に明るい顔を向ける。
「不動行光さんも、こんにちは!」
「……コンニチハ、ヨーコソ……」
「もう、笑顔が暗いよ」
いやお前の笑顔が明るすぎるのだと不動は心中呟いた。審神者を尾行していたときに比べるとぴかぴかの笑顔である。「上手くいったみたいで何よりだわ」と店主は言ったが、いやマジであんな七面倒くさい依頼よく受けたものだ。
店の奥の一部、花の苗を置いておくスペースで花束に出来るくらいのひまわりを育てさせるなんて、場所がいくらあっても足りない行き過ぎたサービスだ。採算度外視なのは分かっているが、ここまでさせるともう商売としてやっていけないだろうに。
不動の呆れも気にせずに、店主は「次は大きなひまわりを試してみませんか?」なんて営業トークに花を咲かせている。次育てるなら自分の本丸でやれよと不動は心中呟いた。いや、もうそんな心配もする必要はないか。そもそも、ここで育てたいと言っていたのは審神者がサプライズを仕込みたかっただけだし。
まあ店主が相手をするだろう。自分はまた店の外で暇を潰すかと表に出ると、「不動行光さんっ」と乱藤四郎がすかさず回り込んできた。
「……何」
「御礼を言いたくて」
「礼なんて言われるようなこと何にもしてないだろ」
「ううん。あのとき、主さんがしてたこと、黙っててくれてありがとう」
へにゃとはにかんだ乱に、不動はふんと鼻を鳴らす。それこそ、礼なんて言われるようなことではない。
店の奥から、審神者が「乱、選ぶぞ」と声をかけてくる。それに「はあい」と答えて、乱は踊るように店内へと駆け入った。
店内には取り取りのひまわりの苗がある。「今回はこの小さいのにしてみよっか」と苗を持ち上げた乱に、ふと審神者が「ずいぶんあの不動行光を気にしているな」と振り返った。
「やきもち?」
「違ッ……」
「わかってるよう。ただ、やっぱり刀剣男士としては気になるよね」
刀剣男士として? 首を傾げるのに、うん、と乱は頷く。
「だって、すっごく歪だもん」
「歪……?」
「主さん、気づかない? あの不動行光」
指をさされて審神者はもう一度しげしげと不動を見るが、特に目立って気になることもない。至って普通の、特までの衣装をまとった不動行光だ。
だが、よく目をこらしてみて──いや、もしかして──
「そうだよ」
乱は静かに肯定する。
「あの不動行光、極めてるのに特の格好してるの。歪でしょ?」
と。
サンダーソニア1
梅雨の終わりの長雨が降る夜、店仕舞いのために表に出ていた店主は、あら、と目を丸くした。通りの向こう、赤い蛇の目傘を差した白い陰がこちらに向かって歩いてきたのだ。
彼の用向きはこちらにあるのだろう。店主はそう直感して、下ろしかけていたシャッターを持ち上げた。そうすると、その白い陰はちょっと傘を持ち上げて、顔に浮かんだ苦笑をよく見せた。「もう閉めちまうところだったかい」と、金糸雀色の瞳を煌めかせて。
「そのお時間を狙ったのではないですか? ようこそいらっしゃいませ、第0008本丸の鶴丸国永様」
店主が澄まして尋ねると、やあ困ったな、と鶴丸は頭を掻く。その時、鎖の佩緒につけた蓮形の飾りがチリリと鳴った。
「お見通しか。いや、花を求めるつもりもあったんだぜ?」
「そちらのお話も伺いますわ。まずは店内へ。冷えてしまいます」
「有難く。だがそこまで気を遣う必要はないんだぜ? 俺たちはきみたち人間に比べちゃ丈夫だしな」
「それでもお風邪は召されます。貴方に何かがあれば、貴方の審神者様に申し開きのしようもありませんもの」
「むしろ、静かになっていいとか言いそうだがなあ」
けらけら笑った鶴丸だったが、店主の言う通り大人しく傘をすぼめて店の中へと足を踏み入れた。相変わらず花で溢れた店内だ。所狭しと置かれた花挿と花の苗。汚れないように裾をさばいてしゃがみこみ、「おお、いいな、これ」とそのうちの一つに手を伸ばす。
「可愛らしい蕾じゃないか」
「ああ、申し訳ありません。そちら売り物じゃないんです」
「そうなのか?」
「ゆきちゃん……不動行光が育てているもので」
それに鶴丸は目を見開いた。「不動行光って、あの不動行光かい」確かめるのに、店主は「ええ」と頷く。
「審神者様が、うちにお預けになったあの不動行光ですわ」
「はは! そりゃあいい。そうか、あの不動が花を育てたか」
「ちなみに、球根をお渡しになったのはそちらの薬研藤四郎様です」
「ははあん、あいつがねえ。まあ、色々考えてたみたいだが……」
さて、と鶴丸は立ち上がり、店主の顔を見下ろした。にこにこと愛想よく微笑むが、そこにはなんの感情も乗っていない。
「どうだい。不動行光の様子は」
「……変わらず。うちのお手伝いはよくしてくれています」
「御上は、可能な限り早期の戦線復帰を要請している」
きみなら分かるだろう、と鶴丸は小首を傾げた。
「多少歪でも極の刀剣男士。政府にとっちゃ腐らせるのは勿体ない垂涎の戦力だ」
「ですが、愚管ながら今の不動行光を戦場に立たせることが、良いことには思えません」
店主は声を潜めながらも鋭く返した。無論、これは店主の独断だ。花切狭扱いに文句を垂れる不動のことだ、戦線復帰を提案されれば一も二もなく従うのだろう。だが。
「……今の、ゆきちゃんじゃ」
きっと、戦場に発たせれば帰ってこない。
ただの武器であればそれでもよかったのだろう。だが、彼は刀剣男士だ。
唇を軽く噛んだ店主を見て、鶴丸はふむ、とひとつ唸る。そして今度は心底からの柔らかな微笑みを見せた。
「わかってるさ。だから主は不動をきみに預けたわけだ」
「……私には、少し、荷が勝ちすぎているように思えます」
「そんなことはない。あんなでも、人を見る目は確かだぜ、うちの主は」
「私への信用ではなく、主様への信頼なのですね」
鶴丸は再び苦笑する。そして「変わったな、きみ」と店主を見つめた。店主は虚をつかれて黙り込み、やがて静かに絞り出す。
「……それが、私の償いです」
鶴丸はすうと目を細めて、小さく息を吐き出した。
「なあ、きみ。戦線復帰が望まれているのは何も不動だけじゃあないんだぜ」
「……」
「御上だけじゃあない。人材不足に喘いでいるのは末端も一緒だ。──帰ってこないか、『若草』」
店主は一度、口を開いて。何かを言おうとして、やめた。ふるりと首を振り、鶴丸を見据える。
「難しい状況下で、私に花屋を続けさせてくれている審神者様に御礼をお伝えください」
「……ううむ。やはり人たらしは主の領分だな。俺が勝手に動いても芳しい答えが得られたためしがない」
ま、考えといてくれやと鶴丸はひらりと手を振った。そして顎を擦り、考えてから「とびきり白い花をくれ」と言う。
「主を驚かせたいんだ。手伝ってくれるかい、『花屋』殿?」
「ふふ、ええ。そういうことでしたら喜んで」
真っ白な花をお送りしましょうね。そう言って店主はエプロンの紐をきりりと結び直した。
*
緑色のぷっくりとした蕾が、淡く色づき始めた頃。キニアン生花店にとある大口の依頼が舞い込んできた。
「オープンセレモニーに飾る花を?」
「ええ、そうなんです」
城下町の寂れた花屋に来る客にしては珍しく、スーツにネクタイを締めた男は揉み手をしながら店主を見上げた。ローズマリーのお茶を一口飲み、店主は渡された書類を眺める。不動が、その後ろから盗み見ようとすると、くるりと振り返って「ゆきちゃんも見る?」と笑顔を向けた。何でも無い風に「おう」と手を伸ばしたが、内心ではこの女の食えなさに舌を巻くばかりだ。結構本気で気配を消したんだが。
ともあれ、不動は手渡された書類にざっと目を通す。城下町に新しくできた娯楽施設の完成セレモニーだ。戦争に関係の無い花屋を置くことを許すような、このサーバーの運営方針は刀剣男士と審神者の福利厚生に力を入れることだ。新設された施設も、刀剣男士や審神者たちの慰安施設という色が強い。簡単に言えば現世でいうスーパー銭湯のようなものだろうか。
まもなく開業するというその施設の、オープンセレモニーに飾る花を頼みたいというのが男の依頼だった。
「これまでであれば、現世のフラワーショップにお願いするのが常だったのですがね。最近は城下町のような後方支援施設についても標的になるでしょう? 覚えておいでですか。政府内厨房の襲撃事件」
「ええ。部外者の入るリスクを最低限にとどめたいというお考えは理解できますわ」
「正直、警戒すべきは遡行軍のみではないと思うのですが……おっと」
口を押さえた男に、店主はにこりと微笑み首を振る。何も聞いていない、という風に。ばつの悪そうに苦笑した男は、ともあれ、と不動の持つ書類を見やった。
「お引き受けいただけませんでしょうか」
「もちろん、喜んで」
「ありがとうございます。最近、やれ襲撃だやれ派閥争いだときな臭いことこの上なかったので、久しぶりに皆様に派手に喜んでいただきたかったんですよね。あ、ポスターおいていってもいいでしょうか?」
「どうぞ」
「ありがとうございます。セレモニーは審神者様もたくさんお招きして、どーんとやりますので! あ、店主さんもぜひ、お仕事が終わられたあとも楽しんでいってくださいね」
緊張の糸が解けたのか、男は早口でそうまくし立てると踊るように立ち上がった。出て行く前にきっちりお茶を飲み干して、「では!」と頭を下げて歩いて行く。
嵐のようなやつ。呟いて不動は派手なポスターを見つめた。『大和国城下町に癒しの空間誕生! 蓬来温泉で戦士の休息を』なんて謳い文句が踊り、こんのすけが温泉につかっている写真が大きく載っていた。
「こんなの、戦争には必要ないって思う?」
「……余分を愛せって言うんだろ」
店主は笑うばかりで何も答えない。ポスターを店の表に貼り付けると、道行く審神者たちが足を止めた。しげしげと眺める者、付き添っていた刀剣男士を誘う者、様々な反応を示す彼らを眺めながら、店主はようやく口を開いた。
「私たちは戦士である前に人間だものね」
「……」
知ってる、と不動は口の中で言葉を転がした。
不動だって、本丸の刀剣男士だったのだから。
しばらく審神者たちの様子を見つめてから、不動は店内へと踵を返した。甘酒の代わりにカルピスを注ごうとして、思い出して水差しを取り上げる。
薬研が贈った球根は、すっくと伸びて。若緑色のぷっくりとした蕾をいくつもつけた。そのうちのひとつは薄く色づき始め、それが何の花であるか、もう不動には分かっていた。
サンダーソニア。
花言葉は「望郷」、「祈り」。
何を考えて薬研がこの花を不動に寄越したのかは分からない。あるいは、何も考えずに不動に贈ったのかも知れなかった。そちらの方が可能性は高いだろう。雅なことは何も分からないとのたまうような男だ。だから、何かを読み取ろうとするのが愚かなのだろうけれど。
「……」
打ち捨ててしまうには情が湧きすぎた、その花に不動は今日も水をやる。
*
オープニングセレモニーの日は快晴だった。「晴れてよかったわねえ」と店主は言ったが、この天候がすべてプログラミングで決定されていることを知っている身としてはよかったもくそもない。晴れになる日を選んで開催したのだろうと言うと、「ゆきくんは情緒ないよねえ」と運転手を買って出た店員の男は笑った。
運転席には男。助手席には店主。後部座席は花と花と花と花と不動である。時々倒れかかってくるフラワースタンドを足で支える不動に、「よっ、流石ゆきくん」と軽薄な賛辞を送ってくるのに、帰ったら二、三発殴ってやろうかと唇を引きつらせる。
「流石俺たちの守り神様」
「神様に対してずいぶんな扱いだよなあ!」
「ごめんなさいね。やっぱりトラックがよかったかしら」
「そしたら俺は荷台だよなあ!?」
まだ椅子が用意されているだけ今の方がマシなんじゃないか。ちっと音高く舌打ちをして不動は姿勢を調整した。
不動から見ればキメラもいいところの建築様式の、いちおう和風のその施設は真新しくぴかぴかと輝いていた。あのスーツの男は、「キニアン生花店」と書かれたミニバンを見つけてぱっと顔を輝かせる。「いやあ、ありがとうございます」と、癖なのか揉み手をしながら。それに店主は微笑んで、「お出迎えありがとうございます」とひらりと車から降りた。
「飾り付けの案は先日お送りした通りで構いませんか?」
「はい。正面エントランスに大きなアレンジメントと、各セクションに小ぶりな花瓶を置いてくださるんですよね。……そちらは?」
「ああ、キニアン生花店から開店祝いです。定番でしょう? フラワースタンド」
それに男は嬉しそうに眦を下げる。「今後ともうちをごひいきに」とウインクしたのは店員の男だった。『祝・御開店』と書かれたひまわりを貴重にしたフラワースタンドは、小ぶりだが玄関に彩りを添える。
さて、と店主は手を叩いた。「後から何名か応援に参ります。セレモニー開始に間に合うように、精一杯丁寧に彩らせていただきますわね」と。
各セクションごとの飾り付けは店員たちに任せ、店主と不動は正面エントランスのアレンジメントに取りかかる。トルコキキョウを中心に据えた、白とグリーンを基調にした涼やかなアレンジメントだ。だが決して質素に見えないように、高さを出して華やかに仕上げていく。
あれを取って、次はそれを取って、と指示を出してくるのに従いつつ、一時間ほどで大体の形は完成した。「やっぱりお花があると空間が一気に華やぎますねえ」と、様子を見に来た男もにこにこ顔だ。
「店長、セクションごとの飾り付けも終わりました」
「わあ、やっぱり大きいのは迫力が違いますねえ」
そうでしょう、そうでしょうと店主は嬉しそうに目を細める。不動も改めて、エントランスの全景を見渡した。確かに、花が加わったことで一気に空間が締まったように感じる。
仕上に形を整えて、片付けが終わったころにはセレモニーの開始三十分前だった。来賓たちがぼちぼちと顔を出してきたのに、男は店主たちを振り返って「よければセレモニーにも参加なさってくださいね」と頭を下げた。慌ただしく来賓達の対応に追われるその姿を見送ってから、店主もまた店員たちを見渡す。
「だ、そうだけど……、せっかくだけど、お店も開けなきゃいけないし、帰りましょうか」
「ええ、店長とゆきちゃんは参加していったらいいじゃないですか」
ぴ、と手を上げて異儀を唱えた店員を皮切りに、そうですよ、と他の店員も口を揃えた。「たまにはお休みされたらいいじゃないですか」とか「ついでに新規顧客も開拓しちゃってくださいよ」とか。なんで俺も、と言いかけたのは、店員達の笑顔で封殺された。
「わ、わかったわ……じゃあ、参加する? ゆきちゃん」
「俺に拒否権ないこと分かってて聞く?」
拒否権がなさそうなのは店主も同じだった。半ば押し切られるようにして会場に残された店主と不動は、顔を見合わせて、かたや苦笑まじりに、かたや諦めたようにため息をついた。
来賓の審神者というのは、それなりの実力者たちらしい。つれている刀剣男士たちは皆錬度が高く、極の姿の刀剣男士も多く見られた。エントランスの花に足を止め、端末で写真を撮っていく者もいる。
セレモニーはこの施設の店長からの簡単な挨拶と、施設の一日無料利用体験で構成されているようだった。「無料ドリンクです、どうぞ」と差し出されたのは白桃味のジュースで、ここでも酒はお預けかと苦い気持ちでちびちび舐める。
先ほどからちらちらと好奇の視線が鬱陶しい。そこまで不動行光が珍しいか。あるいは別の理由からか。ふう、と短く息をつく。だから参加したくなかったんだ、と。
ふらりと店主の側から離れようとすると、彼女はくるりとそちらを向いた。
「ゆきちゃん?」
「便所」
「そう。私はここにいるから、はぐれないようにね」
俺は子どもか、と思いつつも、何か言うのも面倒だ。はいはいと手をひらりと振った。
廊下に置かれた花瓶たちにも自然と目が行った。エントランスのアレンジメントと色を揃えた、シンプルな装飾は目を惹く。ふうん、と眺めていると、ふいに背後に気配を感じた。
振り返る。咄嗟に腰に手をやるが、すぐにその構えを解いた。ただの人間だ。
「何だよ」
「いや、君が噂の、花屋の不動行光かと思ってね」
審神者と思しき女は、隣に伴った長谷部をちらりと見やる。極の装いの長谷部は、不動を上から下までとっくり眺めて、もの言いたげにしつつも口をつぐんだままだった。
「噂の? ……そりゃどうも。どうせ良くない噂だろうけど」
「そんなことはない。本丸が襲撃されてなお、生き残った刀剣男士はそう多くないからね。それだけの実力者だと噂しているのさ」
「どうだか。俺の場合は運が悪かっただけだ。おめおめ逃げのびた情けない刀の間違いじゃねえの」
「おい、貴様」
「長谷部、構わないよ」
審神者は隣の長谷部を諫めて、不動を見つめ直した。そして、憂い気にため息をつく。
「……『大和』様も何を考えていらっしゃるのやら」
「あ?」
「君ほどの実力者なら、戦場に立たせるべきだろう。どうして花屋なんかさせているのかな」
それは不動こそ聞きたいことだった。戦況は逼迫しているし、戦力を遊ばせておく余裕もないはずなのに、このサーバーの代表である審神者は不動を花屋に配属させるよう進言した。
「どうかな、不動行光」女審神者は言う。「君さえ良ければ、私から御上に進言しよう」私はこれでも顔が利く方でね、と言う、その女の言葉はあまり届いていなかった。
頭の中にあるのは「何故?」だ。そして、その答えを不動はなんとなく、掴みつつある。
「……あんたは、この施設をどう思う」
「この施設? この娯楽施設のことかな」
そうだな、と女は顎を擦る。「必須ではない、かな」と言うのに、不動は目を伏せた。
「あんたらは戦士である前に人間だ。なら、刀剣男士は戦士でしかないのかな」
「……ふむ」
戦場に立つ、という選択肢を、かつての不動なら迷い無くとっていただろう。だが、今は、迷いがあった。
迷いがあるうちは答えを出さない方がいいだろう。ふるりと首を横に振ると、女は「そうか」と短く頷いた。
「言ったろ。良ければ、って。無理にとは言わないよ」
あーあ、と女は長谷部を見上げる。「フラれちゃった」と意地悪く微笑むのに、長谷部はなんとも言えない顔をする。そして不動の方に向き直った。
なんだ、文句でも言う気か。身構えた不動とは裏腹に、長谷部は数度躊躇いつつも、口を開く。
「花屋の不動行光。お前の主は──花屋の店主は息災か」
「え……? 元気だけど……」
なんでそんな事を聞くのか。ぱちりと瞬いた不動の前、長谷部はやはり何とも言いがたい顔をして、「そうか」とだけ小さく呟いた。
なんだろう。知り合いとかだろうか。なんなら今日来てるけど、と言いかけた、その時だった。
甲高い悲鳴と、爆発音が響き渡ったのは。
2
花屋の店主は、その直前まで正面エントランスのホールにいた。
大ぶりのアレンジメントの根元に立っていると、花屋を利用したことのある客なのか、何人かが店主に声をかけていった。「あのアレンジメントはキニアン生花店の手がけたものですか」「いつも素敵なお花をありがとうございます」そんな、面はゆい賛辞を微笑んで受け止め、どうかこれからもご贔屓にとエプロンの裾を摘まんでお辞儀をする。
その中に、一人、見覚えのある審神者を見つけて、店主の目はすうと細まった。
蓮の飾りを佩緒につけた鶴丸国永を従えた、少年の見目をした審神者だった。彼は覆面越しに、大きなアレンジメントをぼんやりと見上げていたが、店主が向けていた視線に気づいたのだろう。軽く手を挙げてこちらへと歩いてくる。
「……御機嫌よう、『大和』様」
「昔は花の育て方も知らなかったのに、成長したよなあ、お前」
「その節はお世話になりました」
店主はほろりと苦笑する。『大和』と呼ばれた審神者も笑って見せて、アレンジメントを振り仰いだ。
「いや、立派だよ。あの『若草』が。『多聞』が聞いたら腰抜かしそうだ」
「師匠が腰を抜かす所なんて想像できませんわ。私よりも姿勢がいいのに」
「言えてるな。ところで不動は?」
「お手洗いに」
ああ、と審神者は頷いて、「顔は見ておきたかったんだがな」と顎に手を当てる。「どんな恨み言をぶつけられるかわかったもんじゃないぜ」と鶴丸が茶化すと、「だからだよ」と審神者は答えた。
「本音を聞いておきたい」
「……それは、戦線復帰について、でしょうか」
審神者が微かに動きを止めて、鶴丸の方へ顔を向けた。鶴丸はばつの悪そうな顔でそっぽを向き、口笛を吹いて誤魔化している。が、まあそんなもので誤魔化されるわけもなく、審神者は深々とため息をついた。
「うちのが勝手して悪いな」
「いえ。鶴丸様なりに『大和』様のお立場を案じたのでしょう。お気になさらず」
「立場ねえ。どうせ頷くことしか能の無い水飲み鳥みてえな頭としか思われてねえからいいんだよ。いざとなったら全部『信貴』と『多聞』にぶん投げてトンズラこきゃいい」
「冗談でも背筋が凍りますわ。今度こそ戦線が崩壊します」
それに審神者は肩を竦める。その程度で崩壊する戦線なら崩壊すれば良いと言わんばかりの態度に、店主は苦笑を深くした。本気で思っていそうだから困る。
「それほどまでに、不動行光の戦線復帰を望む声は大きいのですか」
「鵜の目鷹の目してくるヤツの戯言だよ。いくら極つきの刀剣男士とはいえ、たかが一振戦線に戻ったくらいで何になる」
「それは理解しています。問題は声の大きさです」
審神者はじっと店主を見つめた。「おわかりでしょう」と店主もまた審神者を見つめ返す。
警戒すべきは遡行軍のみではないのだ。審神者を擁する勢力とて一枚岩ではない。
たとえば──戦争に余分は不要だと主張する勢力も。
「『若草』ならともかく、一介の花屋が気にするような事情じゃねえよ」
ふいと審神者は視線を逸らした。それに店主は言葉に詰まり、「そうですわね」と力なく笑む。
場を取りなすように鶴丸が「綺麗な花だなあ」とアレンジメントを見上げた。
「薔薇かい?」
「お前、花びらが集まってる花全部薔薇だと思ってるだろ……リシアンサスだよ」
「りし?」
「トルコキキョウです、鶴丸国永様。薔薇は暑さに弱いので。それに、長持ちするお花なんですよ」
へえ、と鶴丸は花に手を伸ばす。柔らかな花弁に細い指がそっとかかった。「良い花だな」と笑うのに、店主もまた微笑む。感謝の言葉を口にしようとした、その時だった。
「動くな!」
鋭い声がホールに響き渡ったのは。
その場にいた刀剣男士たちが素早く身構える。視線の先、立っているのは一人の男だった。片手には端末を握りしめ、側には何人か審神者が控えている。
「動かずにいれば、我々は危害を加えることはしない。城下町での抜刀には制限がかかっているだろう。刀剣男士たちは、手を頭の上で組んでその場に座れ」
「……鶴丸、従え」
ちらりと鶴丸は審神者の方を見たが、おとなしく命令に従った。随分穏やかでない要請に、審神者は軽く腕を組む。「その端末は何だ」と誰かが叫んだ。
「この施設に爆弾を仕掛けた」
高らかに男が答え、周囲からはどよめきと悲鳴が上がる。爆弾、爆弾だって。「はったりだ」と誰かが言った。「はったりではない」男は答えた。「証明してやろうか」と端末に手をかける。
「止めろ」
声を上げたのは『大和』だった。男はすぐさまこちらを向き、「おや、『大和』殿」と目を細める。
「其方においでか」
「まどろっこしいことは好かん。目的を簡潔に話せ」
「貴方はいつもそうだな。高圧的で、物事を上から話す」
「そういう性格なんだよ。うちのが短気起こす前にさっさと説明してくれるか。大量殺人がお望みではないんだろ。それならとっくに爆弾とやらを爆発させてるもんな」
どの口が、と鶴丸がぼやくが、審神者はさっぱり聞こえないふりをする。対して男はむっとしたようだったが、ふるりと首を振って『大和』を見下ろすように顎をあげた。
「では御尋しますが──この施設は何ですか」
「審神者と刀剣男士のための慰労施設だな」
「こんなものが、我々の戦争に必要だとお思いで?」
「だから簡潔に話せよ。演説の鉄則だぞ」
「──ッ、今は戦時中だ。戦に関係の無い施設に、我々の貴重な資材を注ぎ込むなと言っている!」
ぴしゃり、と空気が震えた。黙って話を聞いていた審神者たちの中にもどよめきが走る。
「戦争が始まってもう何年になる。こんな無駄なことに資材を割き、戦線を硬直させ、惰性で決着を先延ばしにして──何になる!」
「高尚なご発言だな。で? そんな演説を強制的に聞かせるために爆弾しかけて人質取ってんのか」
「審神者の代表たるべきどこぞの男が、我々の声に耳を傾けず、商業主義に唯々諾々と迎合している現状がこの悲劇を招いたとは思わないのか」
「爆破させるなら政府の会議室を狙ったらどうだ? 関係の無い審神者巻き込んでねえでよ」
「この場に集った審神者たちにも再考を促したい。己の振舞を振り返れ。今は戦時中だ。セレモニー? 慰労施設? 馬鹿馬鹿しい。そのように遊興に現を抜かしているから、犠牲は減らず、戦争が長引く」
ざわめきが少しずつ大きくなる。中には男に賛同を示す者も現われ始めた。男は満足そうにその様を見下ろし、アレンジメントのトルコキキョウを一本抜き取る。
「この花のようだ。確かに咲いていれば美しく、心も踊るだろう。だがすぐに枯れる。その後には何も残らない──無意味だ」
その花は床へと落とされ、踏み潰された。
「無意味……」
誰かが呟いた。「俺が悪かったのか」誰かが刀剣男士に声をかけた。「遊んでばかりと言われれば、」と誰かが花を見下ろした。
その様子をぐるりと見渡して、『大和』は深々とため息をつく。
「おいおいどうするんだい、主。このままだとさっき言ってた冗談がマジになるぜ?」
「そうしよっかな……正直俺好きでこの立場にいるわけじゃねえしな……」
頭を抱えた、そのとき。『大和』の隣に立っていた女が──店主が──その花を生けた人間が、一歩前に進み出た。
「可哀想な人」
短い一言に、『大和』は天を仰いで、男は眉を跳ね上げた。
「お花に感動したことがないのね」
「……なんだ、貴様は」
「貴方が踏み潰しているお花を生けた者です」
は、と男は鼻で笑う。唾棄すべき商業主義の化身が現れたとでも言わんばかりに。
「花なんぞ売って何になる。どうせ育てるならば米を育てればいいだろう」
「私は、お花を売ることでたくさんの人たちの『ありがとう』を伝えてきました」
「……」
「お米だけで、それは伝えられるかしら」
店主は一本、トルコキキョウを片手に取って、また一歩、男に向かって足を踏み出す。
「ある一期一振様の『さようなら』も、ある山姥切国広様の『お疲れ様』も──」
波が引くように、審神者達が静まりかえっていく。
「ある審神者様の『ありがとう』も、ある薬研藤四郎様の『愛している』も、ある歌仙兼定様の『ごめんなさいも』」
立ち止まり、店主は花を見下ろす。
「あるへし切長谷部の、『──』も」
きっと、すべて。
「お花じゃなきゃ、伝わらないものだわ」
は、と男は嘲笑する。
「馬鹿馬鹿しい、口で言えばいいだろう」
「言葉は万能じゃないのよ。貴方の言葉が全員に刺さらないように」
もう一度、店主は「可哀想な人」と吐き捨てた。
「戦士でありすぎて、人間であることを忘れてしまったのね」
「勝手に私を哀れむな」
「刀剣男士と一緒に暮らしていたのに、彼らと食事をして、畑を耕して、馬の世話をして……それなのに、そのすべても無駄だと思うの?」
「それは戦線の維持に必要だからだ」
「本当にそれだけ?」
また、周りの審神者たちが刀剣男士と顔を見合わせる。刀剣男士の一振が口を開いた。「貴方との暮らしは快いものです」と。「快いと思うことは罪ではないはずだ」と。
再び塗りつぶされていこうとする意見に、『大和』は頭を掻く。
「少なくとも、交渉のテーブルにつくのにも、演説のお立ち台に立つのにも、その爆弾は要らねえだろ」
「……ッ、煩い、何故分からない!」
ふらりと傾いだ男の前、『大和』が後ろ手で端末を操作する。男がぱ、と顔を上げた。
「そうだ。そもそも、こんなところに来る審神者どもが、まともな頭を持っているはずがなかった」
鶴丸が低く構える。
「この、堕落しきった馬鹿どもめ──」
「──鶴丸!」
鶴丸が低く駆けだしたのと、男が端末に指をかけたのは同時だった。『大和』が振り返って叫ぶ。
「伏せろ!」
どん、と激しく地面が揺れた。
*
不動行光の記憶は、赤で塗りつぶされている。
その赤は、本能寺で見たあの赤と、憎いくらいによく似ていた。
「……主?」
その笠は、審神者が手づから被せてくれたものだった。つっけんどんで、生意気な態度しか取っていなかった自分にも、優しい審神者だった。
不動、と呼んでくれた声が、柔らかかったことは、覚えている。
「帰りたくなったら、いつでも帰ってきなさい。俺はここで待っているから」
言いながら、審神者は笠の紐を顎の下で結ってくれた。その手の優しさが、徐々に思い出せなくなっている。
待っているはずだった。長い、長い修行の果て。今度こそ、審神者を、主を守る刀として、不動は帰ってきたはずだった。
潜った門の先は、火の海だった。
「……主、主!」
そんなはずはない。そんな、ばかなことがあっていいはずがなかった。
修行をしたのだ。今度こそ、過去ばかりに逃げずに、貴方の刀になるために。それなのに。
「誰か……誰か残っていないのか! 俺だ! 不動行光だ!」
応えはなかった。
走り出した先には、審神者の離れがあるはずだった。非常時にはシェルターにもなるのだと、かつて自慢げに言っていた、その離れは押しつぶされたようにひしゃげていた。
その、がれきの下に、あの優しい手があったとき、不動は認めざるを得なかった。
また、間に合わなかったのだと。
*
衝撃から不動が目を覚ましたとき、そこは悪夢のような光景だった。またか、と自嘲気味に笑みを漏らし、立ち上がろうとして、ふと違和感に首を傾げる。
無傷なのだ。
「──いや、マジで危なかった……」
なぜ、とぐるりと首を巡らして、その理由に気づく。あの女審神者が肩で息をしながら手を掲げているのだ。その周りには薄い膜のような結界が張られている。
「主、ご無事ですか」
「そりゃこっちの台詞。長谷部も、そっちの不動行光も怪我ない? ないね?」
「ありません」
「ない」
ぱんぱんと煤を払い、審神者はふうと息を吐く。「せっかくの新築物件が一瞬で事故物件とか、おっかない世の中」とぼやきつつ、口元を覆って煙の行く先を見た。
「エントランスのホール近くで爆発かな。こんな大騒ぎだったらすぐに救援くると思うけど」
「ですが、長居は危険でしょう。見たところ、あちらからであれば脱出が可能そうです」
「ま、全滅は避けるべきだし……ひとまず逃げようか。不動行光くん、君も」
「一緒には行けない」
不動は首を振った。エントランスのホール近くだって? だって、そこには。
「あいつが──うちの店主が、まだあそこにいる」
審神者の顔が険しくなった。
すぐさま飛び出していきそうな不動の手を長谷部が掴む。「放せ」振り返らずに短く言った不動に「その顔で行くつもりか」と長谷部は返した。
「青い顔だ」
「……青くもなるだろ。なんだこの悪夢」
「現実だ。冷静になれ、この状況で無策に突っ込んで何になる」
「ッ、俺に、また主を見捨てろって言うのか!」
また、間に合わなかったのか。不動は力なくうなだれた。
本当は分かっているのだ。このまま突っ込んでいったところで何にもならないことくらい。
だが、ここで、このまま手をこまねいて、あのときのようになるのなら、いっそ、
「いっそ一緒に折れてしまいたい、か? ……愚かな願いだな」
「愚かだよ、どうせ」
「生き残った者には、その者にしか出来ない責務がある。お前はあの花屋で何を見てきた」
不動は言葉に詰まった。
それも、薄々感づいていたこと、だった。
今更腐っていたところで無駄だということも。すべてがすべて、無駄になったわけではないということも。
サンダーソニアを打ち捨てられなかった。「望郷」「祈り」そのすべてを。
「……わかってるよ、長谷部」
俺は極の不動行光だ。
愛された分を二度も返せなくて、三度目の愛にも気づけずに、それでも今、生きている。
「不動行光くん、とりあえず朗報をお知らせするね」
先ほどから黙ってふたりのやりとりを見つめていた審神者が、端末から顔を上げる。
「ひとまず、エントランスの審神者は無事。うちの総大将がいたらしくてね。咄嗟に結界張ったから。怪我人はいるけど、死人は出てないよ」
「……そ、か」
「だけど状況は芳しくない。特に爆発を起こした犯人、何でも不動くんところの店主さんに散々煽られたらしくてお冠。うちの総大将含めてとりあえず殺してやろうって顔してるみたい」
何やってんだあの人は! 不動は一声吠えて頭を抱える。あはは、と審神者は苦笑して、「まあそう簡単に殺されるタマじゃないと思うけど」と付け足す。
「折れるために、じゃなくて、守るために行くなら、私もちょっと手伝ってあげるけど。どうする?」
それに、不動は一も二も無く頷いた。
審神者はよし、と頷いて、人差指を噛みきった。こぼれた血を使って、瓦礫の山に何か文字を書く。一言、二言、小さく何かを呟くと、ふ、と息を吐いた。
瞬間、瓦礫の山が大きく吹き飛び、一本の荒い道が出来る。
「……ひょっとしてあんた、すごい審神者?」
「そこそこ?」
「そこそこの審神者は、ここまではできないと思うけど……」
でもまあ、感謝はしておかないといけない。「ありがと」と短く言うと、「御礼はお花屋さんの優待券で」なんていたずらっ子のように審神者は笑った。
「次は間に合うよ、大丈夫」
その声に背を押されるように、不動は瓦礫の道の中へ飛び出した。
極短刀の全力だ。みるみるうちにその姿は小さな点になっていく。それを見送った審神者は、さて、と長谷部を見上げる。
「君も行く? へし切長谷部くん」
「ご冗談を。俺は、貴方の刀です」
「そう? じゃあ、行こうか。流石にこの処理、『多聞』だけには任せられないし。腰抜かしちゃいそう」
「あの御仁が腰を抜かすところなど想像できませんが……そうですね」
長谷部は一度だけ、不動の駆けていった方を見やった。そして首を振って、審神者の背を追った。
3
店主が顔を上げたとき、見えたのは瓦礫の山だった。せっかく綺麗に生けた花たちは無残にひしゃげている。思い出したのは、この施設の男の顔だった。あんなに喜んでくれたのに。
あのときも、こんな気持ちだった? 今や届くはずもない相手にそんな言葉を問いかけてみて、目を瞑る。現実逃避もここまでにしないと。
「死人出てねえか! 出てたら返事!」
「死人に口はないと思うぜ、主……」
「術使えるヤツは脱出経路の確保急げ! それ以外は怪我人の処置!」
黒い羽織を翻し、『大和』が素早く指示を飛ばす。「職員は政府機関に通報──」と言いかけたその時、鶴丸が素早くその腕を引いた。
発砲音。ギン、と白刃が何かを弾く音。
「……何故抜刀している」
「そりゃきみ、職権乱用ってやつだな。うちの主は悪いんでね。銃刀法破ってるきみも大概だが」
くそ、と男が短く悪態をつく。再び銃を向け直すのに、鶴丸もまた刀を構えた。
発砲音。鶴丸もまた素早く刀を振って弾丸を切り伏せる。真っ二つに割れた弾丸が明後日の方向に飛んでいって、誰かが悲鳴を上げた。
「どうにかしろとか言うなよ。そもそも鳥目なんだ、さしもの鶴さんも限界だぜ」
「わかってる」
「結界は」
「お前のより派手に跳弾するな」
「あっはっは、無事脱出できた暁には有給をくれ」
鶴丸が静かに息を吐く。男が引き金を引く。刀を振るい、切り落とす。
刀剣男士と人間だ。元の身体能力が違いすぎる。何度この行動を繰り返しただろう。舌打ちをした男が、周囲をさっと見渡して。もう片方の手で二挺目を抜いた。
二倍になるか。鶴丸が審神者を庇うように射線上に立つ。が、そのもう一方が向いたのは、まったく別の、店主の方だった。
「動くな」
再度の制止に鶴丸はぴくりと動きを止める。
「刀を捨てろ。その場に跪づけ」
「……嫌だと言ったら?」
「この女を撃つ」
「ふうん?」
鶴丸の目は凪いでいた。「使い古された退屈な脅しだな。きみの本丸に俺いないんじゃないか?」と呆れるその手は刀を構えたままだ。
「聞こえなかったか? 刀を捨てろ」
「何故だ?」
「この女を撃つと言っただろう」
「撃てばいいじゃないか」
あっけらかんと鶴丸は言い放った。周りが静かにざわめくのに、気にもとめずに鶴丸は小首を傾げる。
「まあ知り合いではあるが、俺にとっちゃ主の命が最優先だしな。撃てばいいんじゃないか?」
「なッ……」
「悪いな『若草』。努力はするが、まあ最悪の場合だ。死んでくれるかい」
言われた店主は苦笑する。まあ、そういう刀だということは知っていたが、ここまで当然のように頼まれるとすがすがしい。
「最大限の努力をお願いします」
「だってさ。きみも殺しなんかしたかないだろう。ここは話し合おうぜ、な?」
「なッ、なんだ貴様ら!」
「花屋です」
「刀剣男士だなあ」
飄々と言い返すふたりに、背後に庇われている『大和』は空を仰いだ。と、視界の端にちらりと光が蠢いたのを納める。
鶴丸、と審神者がささやいた。鶴丸もまた、短く頷く。
「撃つぞ!」
「だから、撃てばいいんじゃないかって言ってるじゃないか。わからんやつだな」
鶴丸は深くため息をつき、刀を構える。男の震える指が、両方の引き金にかかった。
一歩、鶴丸が足を踏み出す。
「ッ──!」
男が、声にならない悲鳴を上げながら引き金を引いた。
店主は固く目を瞑る。どうか心臓か頭以外に当たりますようにと願って。
だが、その銃弾もまた、届くことはなかった。
キィン、と、高い音を立てて弾丸が弾かれる。ぱ、と店主が目を開いた、その時には、その陰は既に男の眼前にまで迫っていた。
「──ダメ、ゆきちゃん!」
店主が叫ぶ。その鞘の先端が、男の喉仏に突き刺さる一瞬手前で、不動行光は動きを止めた。
「……お人好しだよなあ、まったく。普通銃向けた相手なら殺すでしょ」
「お、お前、は」
「キニアン生花店の、あー、護衛です」
動くな、と不動は低く男を制止する。
「三度はない。銃を置いて跪づけ。さもなくば」
「さ、もなくば?」
「どうしよう。殺しちゃダメって言われたし、骨を一本ずつ砕くくらいはしようかな」
魔王の刀、らしいし? うっそり笑った不動に、男の口端は引きつって。
かくりと頭を垂れて銃を落としたのに、ほっと皆が息を吐いた。
*
さて、これで一件落着か、と思えばそうでもなく。その後突入してきた政府所属の刀剣男士たちによって犯人たちはお縄になったが、その場にいた人間も刀剣男士も全員、医療チェックと事情聴取を受けることとなった。特に実際に銃と刃を向けあった不動や店主は拘束時間が特に長く、解放されるまでに三日はかかるありさまだった。
ようようたどり着いた店は随分久しぶりに感じられた。「皆心配したでしょうね」と困った顔で笑う店主に、もう尖った言葉を返す気はない。「そうだね」と言うと、彼女は少し驚いたように目を丸めて、やがてじんわり笑った。
「ただいま──?」
「おかえりなさい店長、ゆきちゃん!」
わ、と咄嗟に不動は手を広げた。なぜって、顔をべしょべしょにした店員たちがすっとんできたからである。
接客業にあるまじき鼻水と涙まみれのえらい顔で店員たちはふたりにしがみついた。「無事で良かったです」「心配しました」「死んでたらどうしようって」などなど、口々にそんなことを言っては不動の頭をわしわしと撫でる。「よかった」「おかえり」と連呼するのに、不動は面映ゆく唇を噛んで、小さく答えた。
「た、だいま」
「……」
「…………」
「………………」
「な、なに」
一斉に静まり返った店内で、誰ともなく口火を切った。
「ゆ、ゆきくん!!」
「わー! しがみつかないで鼻水がつくから!!」
「ゆきちゃんがやっと素直になってくれた!!」
「やめて! 恥ずかしいから!! 思うところがあったんだよ!!」
そんな様子を店主はあらあら、うふふと見守るだけ。いよいよターゲットが不動ひとりに絞られて、ぐるぐる、わしゃわしゃとかき混ぜられるのに、「あー、もう!」と吼えたが振り払おうとはしなかった。
「ほら、皆。お店を開けなくちゃいけないわ。お顔を洗ってらっしゃい」
「はい、店長」
「ゆきちゃんも。着替えてらっしゃいな。お洋服がべちゃべちゃ」
うう、と不動は立ち上がる。方方へ散っていこうとした、店員のひとりが立ち止まって、「そうだ、ゆきくん」と振り返った。
足元から取り上げた鉢植えには、サンダーソニアが植わっている。
「代わりにお世話、しておいたから。咲いた瞬間が見られなかったのは残念だけど」
ぷくりとしたオレンジの蕾が、頭を垂れて花開いていた。小さなベルのような愛らしい花が、鈴なりにいくつもついている。
手を伸ばしてそれを受け取って、不動はしばらく考えた。そして、店主を振り返る。
「あの、さ。頼みがあるんだけど……」
店主は数度瞬いて。耳打ちされた不動の「お願い」に、「ええ、もちろん」と微笑んだ。
花開いたサンダーソニアを切り落とし、簡単な花束に仕立てる。まとう戦装束は、これまでのものではなく、極のものを選んだ。ぱちぱちと瞬く店員たちに、気恥ずかしいながらも細々と「行ってきます」と口にすると、笑顔で「行ってらっしゃい」と返ってくる。
店主はシンプルなワンピース姿で不動の隣に並んだ。足の向く先は、政府の墓苑だった。
「情けない話だよね。修行で決めた覚悟を、あっさりひっくり返してまた自分の殻に籠もってた」
石段を上りながらぽつぽつと言うと、店主の声が後ろからかけられた。「そんなことないわ」と。
「それがゆきちゃんの悼み方なんだもの」
「……本当は、こうやって腐ってると、あの世のあの人に叱られるってわかってたんだけど」
「でも、そうやって昔の思い出を守ろうとしてきたんでしょう」
「物事をポジティブに考えるよね、あんた」
「悲観的に見ても仕方ないもの」
振り返ると、店主は笑顔で立っている。「そうでしょう?」首を傾げるのに、不動も力なく笑った。
不動の元主の墓は、誰かが掃除していたのか綺麗に保たれていた。「もしかして、あんた?」と尋ねると、答えはなくただ微笑まれるだけだった。
水をかけ、サンダーソニアの花束を供える。線香に火をつけ、手を合わせた。
「良い人だったんだ」
「ええ」
「こんな俺にも優しくしてくれた」
「ええ」
「……間に合わなくて、ごめん」
冷たい御影石をそっと撫でる。震える息を吐き出して、もう一度、「ごめん」と囁いた。
もう聴す相手もいない。聴しようもない。ただの自己満足だ。醜い独り善がりだ。
だけど、確かに心が楽になってしまうのだ。
「ごめんなあ、主……」
ぽつ、ぽつと、御影石に水滴が落ちていくのを、店主は黙って見つめていた。
*
茜色に染まる帰り道を並んで歩いた。あんな一件があったことが嘘のように、城下町は穏やかだった。審神者や刀剣男士たちが、仲良く道を行く姿を眺め、そういえば、と不動は店主を見上げる。
「どうして、あんたは花屋になったの?」
「ううん、そうねえ。……話すと長くなるのだけれど」
「『若草』」
不動が口にした名前に、店主がぴくりと反応する。「……まあ、聞いちゃうわよね」微苦笑して、頬に手を当てた。
「思えば変だったんだ。他の店員は普通の人間なのに、あんたは造作もなく術を使った。刀剣男士を縛るなんて、並の人間じゃできない」
「そうね」
「ねえ、あんた、元は審神者だったんじゃないか」
それに、店主は目を伏せた。数秒、沈黙したのちに、腹をくくったように頷く。
「ええ、そうよ」
「……自分の本丸は?」
「ゆきちゃんと一緒」
店主の目が、す、と遠くなる。
「ゆきちゃんが、主を見捨てておめおめ逃げのびた刀なら、私は、刀を見捨てておめおめ逃げのびた情けない主」
「でも、それは」
「ええ。判断としては正しい」
刀剣男士は替えが利くが、審神者には替えが利かないというのは、政府の教育課程でも習う鉄則だ。
だが、判断としては正しくとも、審神者が割り切れるとは限らない。
「でも、それでも。生き延びたなら本丸を再形成するか、あるいは政府所属になるか、いろいろ道はあるはずだ。それなのに、どうして?」
「それは──」
店主が答えようとした、その時だった。
店主が不自然に足を止めた。不動は瞬き、同じく立ち止まる。店はもう目と鼻の先だ。何をしているのだろう。怪訝に思って、視線の先へと目を向ける。
そこに立っていたのは、へし切長谷部だ。纏う霊力には見覚えがある。あの時、不動を手助けしてくれた審神者の刀。
うちに何か用だろうか。不動が尋ねるその前に、長谷部はふたりに、店主に向き直り、頭を下げた。
「お久しぶりです」
店主はは、と息を吐く。
「……何の、用?」
聞いたことのないような固い声に不動が店主を振り返る。いつも穏やかに微笑んでいる顔から、ごっそりと表情が抜け落ちていた。
なんだと不動は目を見張る。長谷部は憂い気に眉を下げ、「いえ」と首を振った。
「……我が主から。大和国第0437本丸、通称『信貴』より、言伝があって参りました。『若草』殿」
端的に申し上げる。長谷部は胸の前に手を当てたまま告げる。
「不動行光をつれ、審神者として戦線復帰していただきたい」
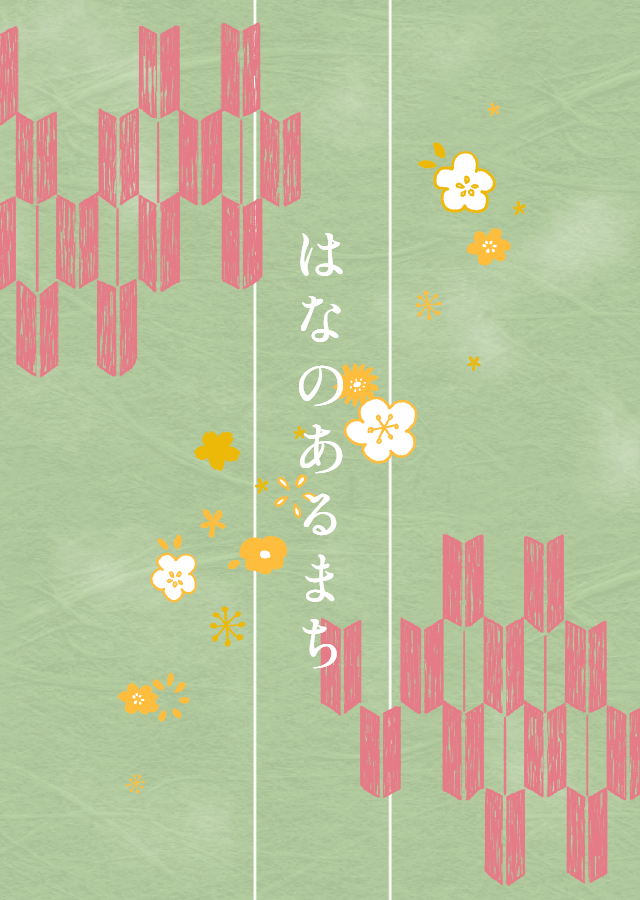
 ちびうお
Link
Message
Mute
ちびうお
Link
Message
Mute



 ステキと思ったらハートを送ろう!ログイン不要です。ログインするとハートをカスタマイズできます。
ステキと思ったらハートを送ろう!ログイン不要です。ログインするとハートをカスタマイズできます。

 ちびうお
ちびうお ちびうお
ちびうお ちびうお
ちびうお ちびうお
ちびうお ちびうお
ちびうお ちびうお
ちびうお ちびうお
ちびうお ちびうお
ちびうお ちびうお
ちびうお ちびうお
ちびうお ちびうお
ちびうお ちびうお
ちびうお ちびうお
ちびうお ちびうお
ちびうお ちびうお
ちびうお ちびうお
ちびうお ちびうお
ちびうお ちびうお
ちびうお ちびうお
ちびうお ちびうお
ちびうお ちびうお
ちびうお ちびうお
ちびうお ちびうお
ちびうお ちびうお
ちびうお ちびうお
ちびうお ちびうお
ちびうお ちびうお
ちびうお ちびうお
ちびうお ちびうお
ちびうお ちびうお
ちびうお