小さな宇宙 高校の同級生から来た葉書を何度も読みながら、ソファでだらしなく寝そべっていたら、急に世界が薄暗くなった。
「……きみなぁ、お邪魔します、とかそれくらい言えんのか」
「お邪魔します」
棒読みでそう返しながら火村はひょいと体を起す。再び視界が明るくなったことに満足しながら有栖はよ、と身を起した。
「こんな時間にどうしたん」
言いながら時計を見ると、もうすぐ十一時になろうという頃だ。
「いや、明日も大阪に用があるから」
「フィールドワークか?」
そう聞いてみると火村はネクタイを取りながら、
「いや、本業の方」
「なんだ、そうか」
「なんだよ、その残念そうな声は」
「いや、予想が外れたからそれが出とるだけやろう」
実際は残念じゃなくて安心してるのほうが割合として高いのだが。
とりあえず麦茶でもてなしてやろうと冷蔵庫を覗いた有栖は、その中身についため息をつきながら火村へとコップを渡す。
「にしても、連絡してくれれば、朝食にパンでも買ってきたのに」
「本当はもっと早く解放されるはずだったんだよ。なのに最後の最後でわけの判らねえことで時間を食われちまった」
「それは災難やな」
心から同情すると、火村は疲れを纏った息を大きく吐き出した。肩をぐりぐりと回しながら全くだ、とこぼしてくる。
「こうなると判ってるなら、レポートでも持ち歩いておきゃよかった。しかも、だ」
「しかも?」
「夕陽丘の作家先生は、いつ飢え死にしてもおかしくない食生活を送っていて、俺は自分のほかにお前の栄養状態まで心配しないといけないらしい」
「それは聞き捨てならんなあ。なんでそう言い切れる」
「余計なパンの一枚もないんだろ?」
そうさらりと指摘され、ぐ、と思わず言葉に詰った。
「さらにいうなら締め切りが近いわけでもないようだから、単に手を抜いてるだけだろ。その怠慢が大病のものだぜ」
「しがないやもめに相応しい食生活を送っとるだけや」
「偶然だな、俺もしがないやもめだがパンまで切らしたことは滅多に無い」
それは通勤のために外に出るから買い物も出来るだけだろう、と反論しようとして、その言葉のあまりの情けなさに有栖は大人しく敗北を認めた。
「いや、この暑さと梅雨のうっとうしさに食欲もこう下降気味でな、しかも昨今のコンビニの麺類がまた美味くて」
「お前そんな食生活送ってるから、ますます食欲が失せていくんだよ」
「まあそれはそうなんやけど……、ってどこにいく?」
有栖の言葉を聞かずにまた玄関に向かう火村に声をかけると、「なにやってるんだよ、お前もだ」と逆にせかされてしまった。
その言葉に意味もわからないまま反射的に後に続くと、呆れたような、それでいて仕方ねえなあ、という温かさがまぜこぜになった調子で、
「明日の朝飯もないんだろ? 仕入れだ、仕入れ」
「えっと、カップスープならあるけど、確か」
「不確かな話だな。だいたいそんなんで腹が膨れるかよ。それにお前にはまともな朝飯が必要だ。それくらいは自分で選べ」
「ああ、了解」
玄関を出てエレベーターホールに向かいながら有栖は思わず頷いた。自分だけのときは気候と昼までだらだら寝ている生活のせいで、下手すると夕方まで食欲が出ないことも多いが、火村は自分と違い真っ当な生活を送っているのだから、それに相応しいまともな朝飯が必要に違いない。しかし火村は、恐らく、なによりも自分に少しでもまともな食生活を送らせようとしているのだろう。この男は自分のこと以上に有栖のことに対して敏感だ。
「ついでに明日食べたいものも考えておけよ」
そうつらつら考えていたら、下りのボタンを何度か連打しながら火村がそう有栖に告げた。
「え」
「宿代ついでだ、二日間分の夕飯は作ってやる。一回家に帰ってからだからちょっと遅くなるかもしれないが」
明後日は休みだからのんびり出来るしな、と続けながらさっさと来たエレベーターに乗り込んだ火村に、有栖は思わず微笑んだ。
「じゃあ冷麺」
「もう少し精のつくもの食えよ。体力は大事だぜ」
「キムチなんて精のつく食べ物の筆頭やん」
「ともかく却下。昼にでも食べろよ」
「じゃあ」
「冷やし中華も却下」
「ちぇ」
コンビニで明日の朝食と共に買ってきた、晩酌用のビールを火村は一気に呷った。首筋に纏わりつく一筋の髪が目に飛び込んできて、同じくビールを飲んでいた有栖は視線のやり場を無くす。
首というのはなんともなくセクシャルな部位だ。剥き出しの急所はそのまま生命に直結するからだろうか。
ほんの少しのアルコールだが早くも回ってきたらしい。
気をそらすためにつけたテレビは、大きな笹を映し出していた。
「そういや、七夕か」
画面を見ながら火村がそう呟く。
有栖もそうやな、と返しながら、どこかぼんやりとした気分になっていった。まだ若かった時分の七夕の日、勝手に高揚した気持ちにせかされるまま走るように家路についたとき、どこかの家の軒先にあった笹飾りの短冊がなぜかはっきりと目に焼きついたことを思い出したからだ。どうも自分は日にちには敏感だ。正確に言えば、忘れ得ぬ日が人よりも多い気がする。
テレビの方を向いている火村の横顔をそっと横目で見ながら、こいつと七夕は相性がよくなさそうや、とか勝手なことをつらつらと考えていたら、思考そのままに言葉がぽろりと零れ落ちた。
「……君は昔から短冊に願いなんてかかなそうやな」
火村は心外だ、という顔を作って有栖に視線を寄せる。
「俺だって夢見がちな子供時代を一応は送ってるぜ。何を書いたかまでは覚えてないけどな」
「へぇ、君のことだから天体望遠鏡が欲しい、とかそんなんちゃうの」
「さてな。それに無条件で叶うものなんかない、って悟ったのは確かに早かったし」
どこか懐かしむような目をして、火村はまたビールを飲んだ。目の端が仄かに赤く染まっている。
「まあ、おかげで見たこと無いもんに頼ることなく、自分で掴んだ幸せを得たから、結果としてオーライだろ」
そういって急に顔を向けると、前触れもなく有栖の頬に掠めるようなキスをした。
「って、いきなりなにしとるんじゃ!」
「努力した俺にご褒美」
「お前……、酔っとるな」
「多分」
この酔っ払いが、と脇をこずくと火村は楽しそうに声をあげた。疲れているとこにアルコールを入れたから、一気に回ってしまったのだろう。
まったく、と小さくため息をつくと、火村がそっと微笑んだ。
「でも、短冊の願いが叶わなかった分の帳尻は合ってるんだぜ。寧ろ大層なお釣りがくるぐらいだ」
「火村、君なあ」
そんな殺し文句をさらりということもないだろうに。酔いも手伝って顔に血が集まるのが判る。何を言おうかしばし迷ってから、有栖は火村の方を見た。
「……今日な、高校の友人から結婚式の招待状が来て。正確には式は身内だけでやるから二次会からのみなんやけど」
「さっき見てたのが案内なわけだ」
「そ、あいつもしっかりおっさんな顔になっとったわ。そしたらなんか色々懐かしくてな」
有栖はビールを最後まで一気に流し込むと、そっと床に横たわった。仰向けになった顔の向こうに、満月から過ぎた月が見える。
「……高校に入ったときは、もう一七年も生きたって思っとったけど、それから更に十七年生きると、あんとき全てと思っとったことが実は違った、ってことも判ってくるなあ、って。なんかそう思った」
失ったものの大きさは埋められないと思っていた。いや、実際には埋められないのだが、その代わり得た大きなものがある。世界はまたバランスを取り戻し、閉じたと思っていた心の扉はまた簡単に開くようになった。
思い詰めていたあの高校生にそう告げたところで、多分判ってくれないだろう。それが年月の重みというものだ。
「……振り返ると長く思えるのに、実感としてあっという間の十七年やったなあ、ってな」
「つまり、回顧の海に沈んでいたわけか」
「詞的に表現するとそうやな」
火村はそんな有栖を見下ろすと、ふと密やかな光を宿して、そっと口を開いた。
「ところで、地球とワシ座アルタイルの距離はどれくらいか知ってるか?」
「いや」
「大体十七光年ってところなんだ。だから、今日見えてるアルタイルは十七年前の光ってことだな」
「へぇ」
十七年前、自分は星空を眺めていただろうか。火村はどうなのだろうか。お互いに、どんなことを考えて。その時発せられた光の波が旅をする間、二人は出会い、経験と体験と気持ちを重ね、いまはこうして二人でいる。
「さらに言うならアルタイルとベガの間は大体十六光年離れてる。雨が降ろうがカササギなんて当てにしないで自力で川を渡ったとしたら、今頃二人で幸せに暮らしてるだろうさ。それこそ短冊なんかに頼らなくても、な」
なんからしくねえこと話したな。そう小さく言って、火村はそっと有栖の髪を撫でた。その感触に有栖はそっと目を閉じる。手から体温とともに伝わる温かさに、どこか酔いながら。
自力で。心の中で有栖は呟いた。
あの日届かなかった、気付かれもしなかっただろうこの手は、今度は届くのだろうか。救い上げるなんて高慢なことは言わない。ただ、どんなことがあろうといざというときには躊躇い無く手を伸ばし、なにがあっても掴んだ手を離さない。そんな覚悟をしているだけだ。
有栖はそっと、天へと手を上げた。
「じゃあ、自ら幸せを得るために川を泳ぎきった織姫に乾杯」
「彦星じゃないのかよ」
「最近の女性は強いで」
それに君は泳いできてくれるんやろ、と笑いながら告げると、お前の方が泳いできやがれ、と髪の毛をぐしゃぐしゃとかき回された。恐らくは二人で同時に泳ぎ始めるだろうから、、予定の半分の時間で会えるに違いない。
そんな甘い戯言を言うくらいには、この世界はいま満ちている。いびつな凹凸を抱えながら、少しずつ球に近付いていく。
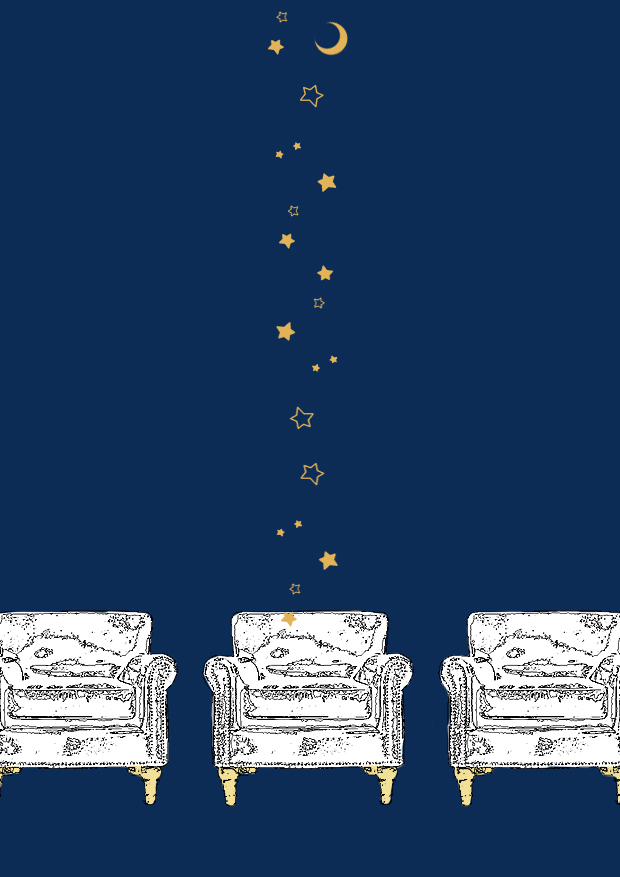
 いずみのかな
Link
Message
Mute
いずみのかな
Link
Message
Mute
 ステキと思ったらハートを送ろう!ログイン不要です。ログインするとハートをカスタマイズできます。
ステキと思ったらハートを送ろう!ログイン不要です。ログインするとハートをカスタマイズできます。

 いずみのかな
いずみのかな いずみのかな
いずみのかな いずみのかな
いずみのかな いずみのかな
いずみのかな いずみのかな
いずみのかな いずみのかな
いずみのかな いずみのかな
いずみのかな いずみのかな
いずみのかな いずみのかな
いずみのかな いずみのかな
いずみのかな いずみのかな
いずみのかな いずみのかな
いずみのかな いずみのかな
いずみのかな いずみのかな
いずみのかな いずみのかな
いずみのかな いずみのかな
いずみのかな いずみのかな
いずみのかな いずみのかな
いずみのかな いずみのかな
いずみのかな いずみのかな
いずみのかな いずみのかな
いずみのかな いずみのかな
いずみのかな いずみのかな
いずみのかな いずみのかな
いずみのかな いずみのかな
いずみのかな いずみのかな
いずみのかな いずみのかな
いずみのかな いずみのかな
いずみのかな いずみのかな
いずみのかな いずみのかな
いずみのかな