HOME4 ザップ・レンフロは刹那主義の男だ。明日の憂いより今の悦楽、過去のことは振り返らない。だからライブラからの活動費はもらったその日にすべて溶かし、日々の生活費は愛人たちに頼り切っている。時折修羅場を引き起こすことはあるが、決して超えてはならない線は敏感にかぎ取るため、いくらその背や腹を女に刺されようと愛人が途切れることはない。十六歳の少女に「天性のヒモ」と言われる始末だ。
その愛人の機嫌取りに役立っている嗅覚は、普段は温厚な後輩が不機嫌になっていることも察知した。どこかにぶつけたのか、前髪からのぞく額がやや赤い。
「まったく、酷いもんですよ」
曰く、先日ライブラに加入し(というか
師匠に置いて行かれた)最年少記録を更新した、斗流の弟弟子を連れてHLを案内していたところ、人類のチンピラに絡まれたらしい。魚臭いとか、人間様の住処に近寄るな海に帰れ、だとか。ザップも近しいことを言っている気がするが、それはさておきチンピラの言動はレオの琴線に触れたようだ。ろくに喧嘩の仕方も知らないような男が、頭突きを喰らわすぐらいには。
「レオくん、これで冷やしてください」
魚類が氷嚢を持ってきた。人とは異なる顔面を持った男が、一連のことをどう感じているのか、まだ付き合いの浅いザップには測りかねる。心を読める水希ならわかったのだろうけれど、今は不在だ。ここ最近――正確に言うと魚類が加わってから――事務所に寄り付かなくなっている。少し前までは、レオとゲームをしたり、宿題を片付けている姿を執務室で見かけたものだが。
「まあ、この街ができてから三年経っても、根強く残ってるからなあ」
コーヒーをすすりながら、デスクから愚痴を聞いていたスティーブンがやれやれと首を振る。
男の言う通り、外だけでなく霧の内側にも、そういった思想を持つ人間はわりといる。中には、集団で異界存在排除を訴える団体もあるぐらいだ。42街区のように住処を隔てているだけなら害はないが、過激な手段に出るところはライブラが潰すこともある。異界に住まう者たちを本気で怒らせ、人類と完全に敵対するような事態になれば、世界の危機につながるからだ。
「そうだ、ツェッド」
スティーブンが向き直る。
「来週の作戦だが、君は水希と――まだ会ったことがないだろうが――組んでくれ。水希のことは、今度紹介するから」
「水希と?」
背もたれから身体を浮かす。思わぬ采配だった。
「……大丈夫なんスか? だってアイツ――」
「大丈夫だろ。もう一年半もここにいるんだ。今までは君とレオとの三人で組ませてたが、それじゃバランスが悪い」
人数の偏りなら、それはそうだ。そもそも、水希は一人で行動させてもいいぐらいだとザップは思っている。大人たちが過保護だから、誰かと組まされているだけで。これが師匠だったら、容赦なく一人で死線を潜り抜ける目に遭っていた。そういう意味では、今の彼女は恵まれている。
閑話休題。聞くに、魚人の弟弟子は、師匠に拾われてからずっと秘境で修行の日々に明け暮れていたという。あのデス仙人のもとで鍛えられていたのだからヘマはしないだろうが、多人数と協力して戦う経験は乏しい。しばらくは誰かと組ませて、慣れさせるべきだ。
そうなると真っ先に候補に挙がるのは、同じ流派出身であるザップだ。しかし遺憾ながら、ザップが子守を命じられている陰毛頭もセットでついてくる。斗流二人でレオを守ってもいいが、そうすると水希が一人になる。となると、水希と魚類を組ませるのが最適だ。戦力的には申し分ない。
「……ま、番頭がそういうんなら、大丈夫なんでしょーけど」
ふと思いつく。
口角が上がりすぎないよう表情筋に力を入れながら、魚類の隣に席を移す。肩に腕を回すと、叩き落としはしなかったが、鬱陶しそうに顔を歪めた。
どこに耳があるのかいまいちわからないが、たぶん人間とそう変わらないだろうと見当をつけて、レオやスティーブンに聞こえないように声を潜める。
「お魚クンよ、アイツと組むにあたって、気をつけなきゃなんねーことがあるんだが――」
*
ザップは明日のことを考えない。昨日のことは忘れ去る。
だから数週間前に設置していた爆弾のことなど、すっかり頭から抜け落ちていた。
「わひゃひゃひゃひゃひゃ!」
弟弟子に胸倉を掴まれたことでようやく思い出したザップはひぃひぃと笑い転げる。青い肌を持つ男は、頭に血が上ってるからか、いつもより顔に赤みが増しているように見えた。
「笑い事じゃありません! 水希くんに失礼でしょうが!」
水希は男だが、自分の女顔を気にしてるから、絶対に間違えんなよ――真面目な弟弟子は、ザップの嘘をまんまと信じた。レオが妙に会話が組み合わないと指摘したことで、やっと気づいたようだ。
「っていうか水希、ツェッドさんの誤解に気づかなかったのか?」
レオの言うことはもっともだ。ザップも、水希が初日で訂正するものだと思っていた。ツェッドがわかりやすく男扱いしなくたって、心を読めばすぐにわかったはずだ。
「いつ気づくかなって……」
「うはははははは」
確信犯だった。笑いが止まらない。苦しいぐらいだ。
人里から離れた暮らしを送っていたツェッドなら、絶対引っかかると思っていたが、ここまでうまくいくとは。しばらくはいい酒のつまみになりそうだ。
「言ってくださいよ……そういうことは……」
「ツェッドさん、この人の言うことを鵜吞みにしちゃだめです。八割――いや、九割はデタラメだと思わなきゃ」
「ええ、信じた僕が愚かでした」
「ンだとコラ……ぶふっ、陰毛がえらそうに……くくっ」
「イダダダダ、笑うか絡むかどっちかにしてくださいよ!」
ヘッドロックを決めるザップを、水希はしょうもないものを見る目で眺めている。嘘に乗っかってくれたのだから一緒に笑えばいいものを、感情表現に乏しい子どもだ。しかし初めに会った頃と比べれば、幾分かマシな顔つきになった。
レオの首に回している右腕、肘のあたり。かつて水希につけられた古傷が疼く。
バカ騒ぎに付き合っている二人は、想像もしていないだろう。同僚の一人が、魚類のような存在を差別する側にいたなんて。
「まったく、しょうがない奴だな、アイツは」
どうだい、ツェッドとは。何気なしに聞いてみたら、ザップが水希まで巻き込んでろくでもない悪戯をしていたらしく、スティーブンは呆れかえった。水希もそれに付き合うとは、意外だが。
悪い友達から、悪い影響を受けてやしないだろうか。一時的保護者として、一抹の不安を覚えてしまう。スティーブンがいない場では、平気でザップと汚い言葉を使うと小耳に挟んだこともあるので、いっそう心配だ。同僚である以上、「ザップくんとは遊んではいけません」と言うわけにもいかない。
「真面目だね、あの人」
〝人〟と。水希は自然と口にした。
どこまで意識しているのかはわからないが、その一言で水希の変化が伺えて、スティーブンは微笑む。
「ザップの弟弟子なんて聞くから身構えてたが、真っ当そうな男で助かるよ」
影響を受けるのならば、ザップではなくツェッドから受けてほしい。今後も水希のことは、ザップではなくツェッドに任せよう。
水希の視線が揺れる。
細い指がスーツの裾を引いた。
「スティーブンさん。誰かつけてる」
彼女の能力は便利だ。長年裏社会を渡り歩いてきたスティーブンより、遥かに敵意に敏感だ。
「数は?」
「四人。武器も持ってる」
「よし、それじゃあ何の用事か聞いてやろうか」
ここら一帯の地図は頭の中にインプットしている。周囲を気にせず、相手を一度に制圧できる、都合のいい場所。いくつか思い当たり、その中に覚えのある路地があった。
そこにしよう。水希を連れて、路地に向かう。
つけられている、と自覚してからだとわかりやすい。どれだけ巧妙に隠れようと、どの辺りにいるのかだいたいわかった。
路地には水希から入らせた。そう簡単に背後を取られるような子どもではないが、念のためだ。
「ここ……」
ちゃんと見覚えがあるらしい。水希はきょろきょろと見まわす。
「うん、来たことがあるよ」
路地を抜けた先には、大通りがある。挟み撃ちを視野に入れていたけれど、そこまで考える連中ではないらしい。ゆっくり奥へ進んでいる間に、複数の足音が追いかけてきた。
振り返る。人類の男が四人、銃を構えていた。
「テメエに用はねえ。ガキを置いてき――」
最後まで言わせる間もなく。男たちの足先から首元まで、凍りつかせた。
「ほう。この子に、何の用が?」
首から上を残したのは、円滑に話を聞くためだ。舌まで凍らせたら、意思の疎通に苦労する。
再びスーツを引かれた。
「スティーブンさん、この人たちただの……いや、ただのって言うのもおかしいけど。子ども売り捌いてるだけだ」
「なんだ、人攫いか」
言ってから、人攫いを「なんだ」で終わらせるのも随分だなと内心で突っ込む。それだけHLに蔓延る犯罪の種類は多岐にわたり、想像もつかないほど質が悪いものまである。
それにしても、本当に便利なものだ。拷問で自ら口を割るよう誘導せずとも、頭の中にあるものを知ることができるのだから。この街には同じような技術はもちろんあるけれど、ある程度離れた位置からでも好きなように読み取れる能力は、そうそうない。
もっとも、そんな力を持った水希の存在が裏社会に知られてしまったせいで、ライブラの保護が必要な身の上になったのだが。
「それじゃ、HLPDに引き渡して、恩でも売っておこう」
ただの人類が銃を持って脅してくる程度であれば、ライブラが出る幕ではない。よほど厄介な相手だったら、警部補直々に連絡が来る。
三度、水希がスーツを引っ張ってきた。
「もう行こう。アタシ、ここ好きじゃない」
「そうかい? 僕はそんな、嫌な思い出じゃないけどな」
水希を保護して、少しばかり経った頃。スティーブンはこの場で、命を落としかけたことがある。
下手を打ったわけではない。ちゃんと敵は仕留めた。しかしスティーブンも大怪我を負い、スマホが壊れて助けを呼ぶこともできず、己が作り上げた氷に囲まれながら、流れていく血を見つめていた。世界のためとはいえ、人には言えないことにも手を染めてきたスティーブンだ。ろくな死に方をしない覚悟はしていたが、こんな狭くて、暗く、薄汚い場所で野垂れ死ぬのかと、憂鬱に思った。
――生きてる……よね?
不明瞭になっていく視界に、瞼を閉じたときだ。小さいくしゃみに驚いたら、水希が見下ろしていた。氷に覆われた路地の寒さに、顔をしかめながら。
彼女に助けを求めた覚えはない。彼女特有の第六感で、スティーブンの危機を察知し、自ら来たのだ。懐いているわけでもない、赤の他人の大人のために。
本当は、そういう子だったのだろう。
周囲の環境が、彼女を誤った方向へ進ませただけで。救える命を見て見ぬふりはできない。本当は、良い子なのだ。
「スティーブンさん?」
唇を尖らせ、水希が不満を訴える。
「そうだね、行こうか」
放置したところで、男たちに逃げるすべはない。ただの通報者とはいえ、警察とも積極的に関わる気もない。
踵を返し、路地を後にした。
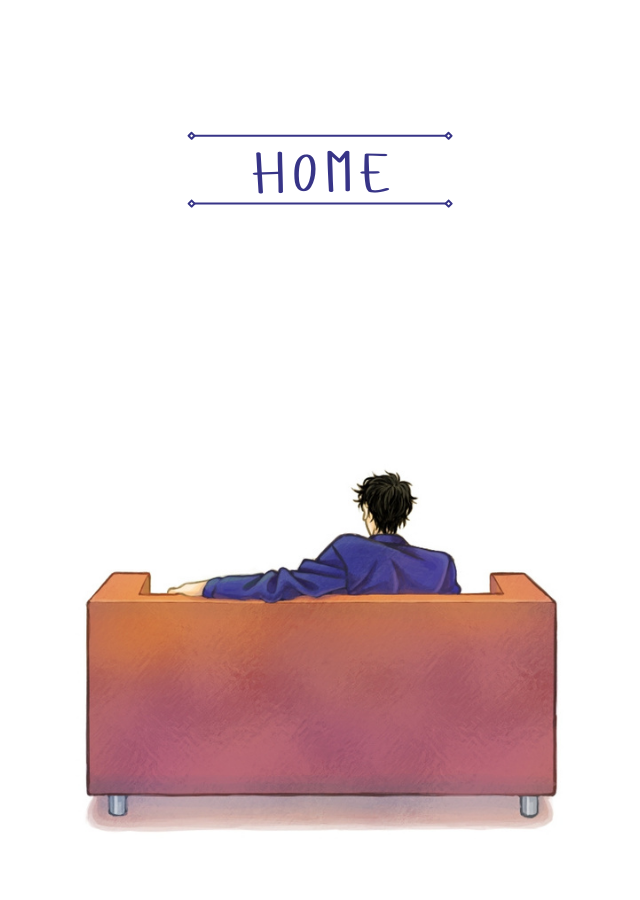
 ティウス(夢用)
Link
Message
Mute
ティウス(夢用)
Link
Message
Mute

 ティウス(夢用)
ティウス(夢用) ティウス(夢用)
ティウス(夢用) ティウス(夢用)
ティウス(夢用) ティウス(夢用)
ティウス(夢用) ティウス(夢用)
ティウス(夢用) ティウス(夢用)
ティウス(夢用) ティウス(夢用)
ティウス(夢用) ティウス(夢用)
ティウス(夢用) ティウス(夢用)
ティウス(夢用) ティウス(夢用)
ティウス(夢用) ティウス(夢用)
ティウス(夢用) ティウス(夢用)
ティウス(夢用) ティウス(夢用)
ティウス(夢用) ティウス(夢用)
ティウス(夢用) ティウス(夢用)
ティウス(夢用) ティウス(夢用)
ティウス(夢用) ティウス(夢用)
ティウス(夢用) ティウス(夢用)
ティウス(夢用) ティウス(夢用)
ティウス(夢用) ティウス(夢用)
ティウス(夢用) ティウス(夢用)
ティウス(夢用) ティウス(夢用)
ティウス(夢用) ティウス(夢用)
ティウス(夢用) ティウス(夢用)
ティウス(夢用) ティウス(夢用)
ティウス(夢用) ティウス(夢用)
ティウス(夢用) ティウス(夢用)
ティウス(夢用) ティウス(夢用)
ティウス(夢用) ティウス(夢用)
ティウス(夢用) ティウス(夢用)
ティウス(夢用)