拓崚小ネタログ8■ブーツとマフラー
澄んだ冬の空気には、彼のブーツの靴音がよく映える。
こつり。ひんやりとした外気の気配が僅かに滲む玄関先で、外出の支度を整えひとつ踵を鳴らした彼が、ふいに視線をとめてこちらを向いた。
「灰羽」
「?」
呼び声に言葉で応えるより早く、いろのしろい指先がついと伸ばされて襟元へと辿り着く。目瞬きをふたつみっつしているうちに、彼の五指は拓真の首元――普段よりも幾らか厚手のマフラーへ何度か軽くふれてから離れていった。
なにかを確かめるように小さく頷くしぐさに、彼がそれを整え直してくれたのだと気付く。面映ゆい心地で礼を述べれば、そのままの近さで彼の双眸が柔く眇まる。室内灯のひかりを汲んで、ルビーレッドがゆらりと揺らめきながらかすかに透けた。
嗚呼、これはいたく機嫌のよいときのひとみの色だ。
拓真がそう思い至るのとほぼ同時、もう一度伸ばされた彼の手のひらが緩く自身の手首にふれる。その手に引き寄せられたのか、あるいは自ら身を寄せたのかなどどちらでも構わなかった。
口付けた拍子、彼のブーツの踵がこつりと床を打つ。その靴音がひどくあざやかに鼓膜にふれたのも、――やはり、冬のせいだろうか。
***
20201210Thu.
■窓際に月明かり
それは年内最後の、業界関係者との会食を終えた夜だった。
食事を摂りながらの打ち合わせも相応に実りあるものとなり、程良い酒精も相俟って、男の自宅へ向かうタクシーの中でもぽつりぽつりと他愛ない会話を交わしていた。
きんと冷えた外気に、マンハッタンの街並みが澄んでいる。崚介の自宅の次に通い慣れたマンションの一室へ辿り着き、スリッパへ足先を滑り込ませたところで、男に名を呼ばれておもてを上げた。
「コートを脱ぐ前に、もう少しだけ、構いませんか」
まだ玄関先にしか灯らぬ明かりの下で紡がれた言葉に、けれども詮無い問いなど投げる気もなかった。眼前の男の真意は知れずとも、やわらかな中低音とまなざしの心地好さだけで答えに代わる。ただ小さく頷いて、リビングへと進む男の半歩後ろに続く。
リビングを横切り、日中日当たりのよい窓際にいくつか並べられたサボテンの鉢植えたちの傍らを過ぎて、聞こえたのはテラスへ続く硝子戸をからりと開けるかすかな音だった。
ふたりぶん並んだテラス用の外履きにそれぞれ爪先を潜り込ませ、ひそやかな夜の水底のような中庭へと足を下ろす。
はいば、と、男の名前を紡いだ唇から、白い息が零れて冬の風にさらわれる。穏やかな青がついと向けた視線の先を追えば、濃藍のとばりの降りた中天に、ひどくあかるい満月が浮いていた。
「今年最後の満月だと、聞いたものですから」
「……そうか」
「ええ」
応える男の声と輪郭が月明かりの下で淡くにじむ。コートの厚い布地越しにわずかにふれあった腕はそのまま、ただ、目を細めた。
***
20201230Wed.
■そのさきに青
あつい。繋がった場所からせり上がった熱が、背すじを抜けて全身をめぐり四肢の先にまでたどり着く。男の腰を跨いで寝台についた両膝が緩まぬよう浅い息をひとつ吐くと、節ばった長い指が崚介の様子を伺うようにそっと手の甲にふれた。
普段ならば返せるはずの肯定の言葉を、ただその手を握り返すだけのつたないしぐさに代えたのは、体に残る葡萄酒のためだろうか。あるいは酒精とともに摂り込んだ、数粒のチョコレートのかすかな残香のためだろうか。本能的な欲に揺られる回路ではどちらが正しいともつかず、またどちらが正しくとも構わなかった。いまここにある温度が、自身の五感を満たすすべてだった。
「……黒木くん?」
シーツの水面に背を預けた男の双眸が、薄明かりのなかでゆらゆらと熱を灯して揺れている。レンズ越しではない素のままの青。目を細めた。
「――……、」
いらえの代わりに、右手で掴んだ男の左手をついと持ち上げて引き寄せる。ひとみと同じように素のままの五指が、ふいの動きに半ばほどけかけるのをすくうように――その薬指の背に、唇でふれた。
ひくり。口付けた指先がかすかに跳ねる。うすい皮膚でただふれたそこが、それでも滲むような熱を帯びた気がした。口唇を寄せたまま、ようやく喉をふるわせて男を呼ぶ。はいば。
「……なん、でしょう」
ひそやかな掠れ声。男の青がこちらを見ている。情欲にけぶる理性の合間で崚介の胸裡の最奥をたどろうと、直線の眼差しを向けている。正面からその直線を受け止めて、ぞくりとした。
指の背から付け根につたい、足早に駆ける拍動のかたちを捉えるようにやわく食む。受け入れた熱と、指先から伝わる鼓動が心地好かった。
あとほんのわずかこの手を引けば、この男は自身の胸裡にふれるだろう。思うさま抱いた首筋と重ねた胸板の熱さを脳裏にえがきながら、くちづけたままの左手を引いた。
***
20210208Mon.
■融点は薔薇のいろ
しんと静まり返った寝室に微かなカーテンの音が落ちたのは、二月十四日、二十三時五十分を過ぎたころのことだった。
「黒木くん?」
ベッドサイドに灯るやわらかなひかりから、何も言わずついと離れてふいに窓辺へ向かった彼の背に、拓真はひとつちいさな声を掛ける。眠りを待つばかりの夜のとばりをいたずらに乱さぬよう投げた呼び声を視線ひとつで受け止めて、彼もやはり同じだけの声量で拓真を呼んだ。
呼ばれるまま、彼のそばまで歩み寄る。
持ち上げたカーテンの端に体を滑り込ませ、内側へ拓真を招き入れるようにもう一歩隣――あるいは、紗幕の奥と言うべきか――にずれるしぐさがどこかいとけなく目に映って、ことりと心臓の逸るのがわかる。
年甲斐にもない。胸裡をくすぐる面映ゆさはひとまず表に出さぬよう飲み込んで、そっと彼の隣に並び立った。頭半分ほど下にある彼の視線の行く先を追って、窓の外へと目を向ける。
通りによってはまだ煌々と明かりの灯り続ける、既に見慣れたマンハッタンの夜。その景色のなかにぽつりと浮いた違和感に、緩いまばたきをひとつ。
「帰りのタクシーでは見えなかったからな」
拓真がそれを見つけたことを、視線から確かめたらしい。静かな夜の海に似た彼の声がする。聳え立つビル群にあってひときわ高い摩天楼が、見慣れぬあざやかな色に染まっていた。
ひそやかな明滅を繰り返す、遠く小さなローズ・ピンク。ゆっくりとまたたくそれは、鼓動の速度だろうか。
硝子越しに、二月の夜気がじわりと滲む。彼と身を寄せあってシーツにくるまるときのように、彼の片手が持ち上げていた紗幕の端を知らずのうちにさらっていた。
夜のひかりを遮ったふたりきりの紗幕の内側で、彼の赤が澄んでいる。
長い睫がまばたくしぐさとその赤に、摩天楼のひかりがやわく溶け落ちる。唇でふれた温度の心地好さごと、あまやかな残光を飲み干した。
***
20210214Sun./HappyValentine’sDay!
■月降る海底、夏の暮
壁面沿いに並び、あるいはフロアに点在するように佇む大型の水槽から、月明かりに似た薄青い光が差している。床全体に敷かれた吸音性の高いカーペットが自身の歩みを静かに受け止める感触を靴裏で感じながら、灰羽拓真は都内某所にある都市型水族館の展示エリアをひとりゆったりと進んでいた。
時刻は二十時半をいくらか過ぎたころ。本来ならば営業時間外である現在、館内にいるのは住人である魚たちと水族館のスタッフ――それから、ジェネシスのメインキャストの面々に、必要最低限の機材を囲んだ撮影スタッフだけだ。
全体的に照明の絞られたフロアのなかで最も明るいのは機材を配置しているエントランスホールだ。順路に入り奥へ進むにつれ、海底へ潜るように周囲は薄暗くなっていく。
水族館を訪れる機会など、いつ以来だろうか。ともすれば義務教育時分にまで遡るかもわからない。思い返せば随分と遠い記憶を、歩調と同じ速度でゆるやかに辿る。ひっそりと動く人の気配が流れる空間を、濾過装置のものと思しき微かな振動音と水音が満遍なく浸している。
目の覚めるようなあざやかな尾びれを優美に揺らして泳ぐ熱帯魚が数匹、水草の影からこちらを覗いているのが見えた。
拓真たちが日本公演の合間を縫って今夜ここにいるのは、劇団のオフィシャルファンクラブ名義で発行している会報誌用のスチール撮影のためである。
むろん会報誌の発行もあくまで劇団活動の一環であり、記事の中心は直近公演に関する対談や稽古期間のオフショット等だが、有償システムの付加価値分として公演とは別ロケーションでのコンセプトフォトが数ページにわたり毎号企画掲載される。
次回の会誌発行は、現在巡業中の夏季公演終了後。日本ではまだわずかに暑気の残る初秋を予定しており、季節感に沿った誌面を構成できる現場として選ばれたのがこの水族館だった。
魚たちのストレスにならぬよう飼育スタッフの指示を仰ぎながら数班に別れての撮影となったものの、幸いどの班も滞りなく終了し――貸切契約の残り時間を、水族館側の厚意もあり束の間の自由観覧に充てていた。
主宰としてカメラマンとのデータ確認をしていた分タイミングがずれ込んだが、拓真以外のキャストの面々や手の空いたスタッフたちは順に自由行動に移っているはずだ。郊外に建つ大規模水族館とは異なり敷地面積に限りのある立地とはいえ、この人数であれば貸切観覧の贅沢さを味わうには充分な状況だった。
ついと視線を巡らせれば、れいや岳をはじめとして各々思い思いに水槽を眺める同僚の姿を点々と見つけることができる。けれども物音といえばどこかひそめたかすかな話し声が水音に紛れて時折聞こえてくる程度のもので、水族館という場所が持つ独特の静けさは保たれたままだ。
「…………、」
いつの間にか、ひとつの水槽の前で足を止めていた。熱帯魚たちの群れのなかの一点に、自然と視線が惹き寄せられる。
しなやかな動きで泳ぐ小さな体を、熱帯魚らしいビビッドな赤い鱗が覆っている。鮮烈な彩りは鰭の方向に向かうにつれ濃さを増して、長い裾のようにはためく胸びれや尾びれの端は深い夜の色をしていた。……何故その個体に目が留まったかなど、言えるはずがないけれども。
あざやかな赤と黒のシルエットが水草の向こうに消えていくのを確かめてから、そっと背後を振り返る。ゆらめく光陰と水音とひそやかな気配に満たされた夜の底で、知らず彼の姿を探していた。
エントランスホール寄りにある熱帯魚の展示エリアを進み、点在する立柱型の水槽の合間を静かに抜けてゆく。途中すれ違った湧太郎や、何人かのスタッフと軽い労いを交わしたあと、――そうして、そこへ辿り着く。
床から天井の高さまで、壁面の一角へ巨大な絵画のように嵌め込まれた水槽のなかに、無数の海月が漂っている。深い青から淡い桜色へと緩慢にうつろう照明のうっすらとしたひかりのそばで、彼はひとり静かに佇んでいた。
人の気配を察してか、ふ、と振り向いた彼がなにげない仕草で拓真を見た。撮影の首尾を尋ねる短い声に頷いて返しつつ、彼の傍らで立ち止まる。
ふたりきりで過ごす時間よりはわずかに遠く、けれども充実した日々のなかでよく知った、確かな近さ。
あわい月明かりが彼のま白いかんばせを照らしながらやわくゆらめく。うたかたの静謐に足先をひたして、目を細めた。
***
20210224Wed.
■淡雪
指先の悴むような冬を過ぎて、そそぐ日差しがかすかに和らぎだしたころ。
休日の朝、寝室のカーテンを開けかけた先の視界に広がる光景に、灰羽拓真は「おや」と小さな声をひとつ零した。
「どうした」
思わず、といった具合で零れたそれは、ほとりと落ちて背後の寝台まで届いたらしい。心地好い微睡みの気配の残るそこから静かに身を起こした彼が、よく知った端的さで問うてくる。拓真よりも彼のほうが寝覚めのよいたちなものだから、先に起き出して寝室の遮幕を開けるのもおおよそ彼なのだけれども――珍しくも今朝その役目を自身が得たことを、胸のうちで感謝する。
「黒木くん」
端を持ち上げたカーテンは開けきらぬまま、肩越しに振り返ってちいさく彼を呼ぶ。彼はといえば一、二、まばたきはしたもののそれ以上の問いを重ねることはせず、寝台の端から足を下ろした。
しなやかなつまさきをスリッパに潜り込ませ、彼はまっすぐに拓真の待つ窓辺へと歩み寄る。彼が隣へ並び立ったのを確かめてから、持ったままだった遮幕の裾の片側を彼に渡すかたちで手放した。
春の色がうすく滲み始めた朝日が視界を満たす。残る片側も自らの手で開ききってしまえば、窓の向こうには抜けるような青空と、やわらかな碧天を淡く彩る春の雪が舞うばかりだ。
「……、」
思いがけず油断していたものか、彼のルビーレッドがまばたきとともにただ青を見上げて映す。朝日のなかにあるうつくしく整った横顔とま白いかんばせのまばゆさに知らず気を取られているうちに、からりと窓の滑る音が鳴った。
日差しは和らぎつつあるといえ外気そのものはまだ冷たい。肌にふれた冷気にはたと我に返る。
不覚ながら失念していた、――こんなときばかりは彼が、気の向くままの美しい獣にどこか似ることを。
地面で重なるよりも早く陽光に溶け消えてしまうほどの淡い雪のなかを、細く開けた窓からバルコニーへと差し出された掌がわずかに游ぐ。外に出るには薄い夜着の下にある彼の素肌が冷えてしまわぬうちに硝子戸を閉めるよう促さねばならないと知りながら、あと数瞬だけやわらかな微笑を目に焼き付けていたかった。
***20210312Fri.
文字書きワードパレット 9.不治の愛(油断/掌/悴む)
■( •ᴗ• )
私用の携帯端末が、手の中で静かに震えて着信を告げている。
就寝前のベッドルーム。寝台の端に腰を下ろした黒木崚介が手元の画面を見つめたのは、話題に沿って何気なく送ったメッセージの隣に「既読」の二文字が表示されてから凡そ数十秒後のことだった。
件の文面は次の休日の外出先として候補に挙げていた美術館と、その周辺で評判のよいカフェレストラン数軒のオフィシャルページのURL、それらに対する個人的な所見を手短に書き添えたものだ。律儀な性分の男が内容を確認し、昼食を手配する店の希望を述べるために崚介の端末を鳴らすにはいささか早い。軽く首を傾げつつ、指先で画面にふれて通話を繋いだ。
「どうした」
「……いえ、すみません、つい」
「……うん?」
聞き慣れた中低音が受話口越しに耳朶を打つ。薄く滲む安堵の色に疑問符を投げればなにやらばつの悪そうな咳払いがひとつ聞こえ、ワントーンひそめられた声量のいらえが返ってきた。
「あまり見かけない表現が文章に入っていたものですから、……その、もしやアカウントのハッキングにでもあったのか、と」
「…………、」
間。
「……黒木くん?」
「……、いや、」
くつり、思わず肩を揺らしてちいさく笑う。ここしばらくのあいだ指南を受けつつ研究をしていたそれが、画面の向こうの男をいたく混乱させてしまったらしい。喉の奥に笑みの気配を残したまま、緩く首を横に振る。「すまない」
「そうすることで文面からの感情がより伝わりやすくなると聞いたものでな。このところ、個人的に用法の研究をしていた」
「研究、ですか」
「ああ」
「――……、」
「灰羽?」
「俺は別に、普段の君の言葉でも」
ぽつりと落ちた呟きに、まばたきをひとつ。数瞬のインターバルのうちに我に返った様子の男がどこか慌てて繋いだ取り消しの声を、拓真、と名を呼ぶことで柔く窘めた。
「確かにお前に対しては特段無用のものだったな」
それに、やはりこうして声を聞くほうがいい。
思ったままにそう告げて、男からのいらえにそっと耳を傾ける。
この手を直接伸ばせないのがすこし惜しい。無機質な端末ではなく男の温度を掴めたならば、それが何よりの応えだと知っていた。
***
20210403Sat.
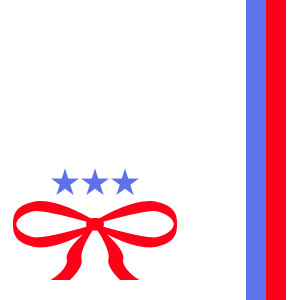
 なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
Link
Message
Mute
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
Link
Message
Mute
 ステキと思ったらハートを送ろう!ログイン不要です。ログインするとハートをカスタマイズできます。
ステキと思ったらハートを送ろう!ログイン不要です。ログインするとハートをカスタマイズできます。

 なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH
なっぱ(ふたば)▪️通販BOOTH